

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第3章 第1節 中国マクロ経済動向
第3章 中国経済動向
第1節 中国マクロ経済動向
本節では主要経済指標の動向を中心に2016年の中国経済を概観する。その上で、次節において、過剰生産能力、不良債権、不動産問題等の構造問題を見ていくこととする。
(1)GDP
2016年の実質GDP成長率は、前年より低下して6.7%となった(第Ⅰ-3-1-1図)。その寄与度を前年と比較すると、純輸出がマイナス幅を拡大させるなど内需中心の成長であり、内需の中では、投資の寄与が縮小し、消費の寄与が拡大するなど、投資から消費への転換の動きも見られる。なお、四半期ベースで推移を見ると2017年第1四半期は2四半期連続で伸びが上昇した。
第Ⅰ-3-1-1図 中国の実質GDP成長率の推移
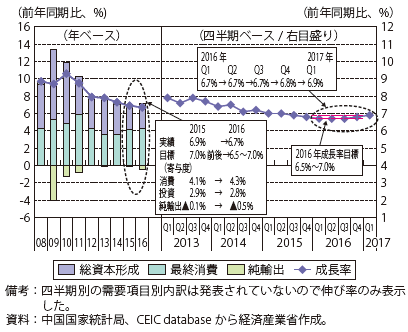
名目GDP成長率では2016年は前年より加速しており、足下の2017年第1四半期は11.8%と高い伸びとなっている(第Ⅰ-3-1-2図)。この背景には、第2節で述べるが過剰生産能力問題のため価格が低迷していた第2次産業で一定の改善が見られ、デフレーターがプラスに転じて名目成長率の上昇が続いている影響が大きい89。また、第3次産業が名目、実質ともに高い成長を続けている。
第Ⅰ-3-1-2図 中国のGDP成長率とデフレーターの推移
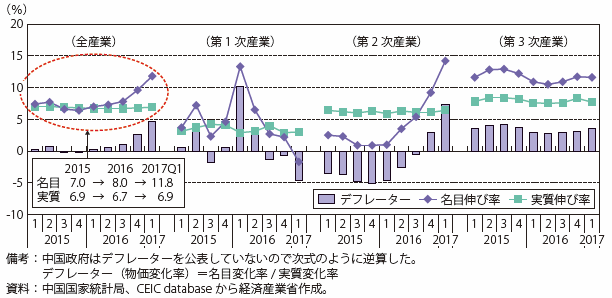
一方、地域的な跛行性が見られ、2016年がマイナス成長となった遼寧省、石炭の過剰生産能力問題の影響が出た山西省など、東北・華北地域は、低い伸びにとどまっている(第Ⅰ-3-1-3図)。
第Ⅰ-3-1-3図 中国の地域別実質GDP成長率(2016年)
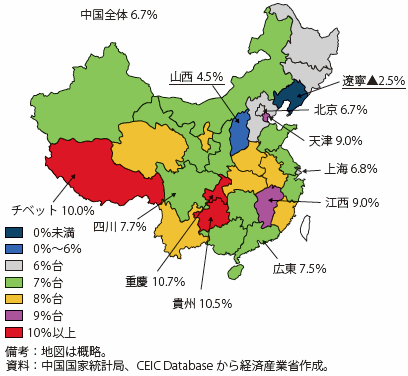
89 第1次産業も価格(デフレーター)の変動が激しいが、これは農産物の価格が天候の影響を受けやすいことが背景にあると考えられる。
(2)消費
消費の指標として社会消費品小売売上高の動きを見ると、月次の変動はあるものの、2016年全体では10.4%と比較的堅調に推移した。特に、小売の約1割を占めるネット販売が前年比26.2%の大幅な伸びを示している(第Ⅰ-3-1-4図)。
第Ⅰ-3-1-4図 中国の小売売上高の伸び率(前年同月比)の推移
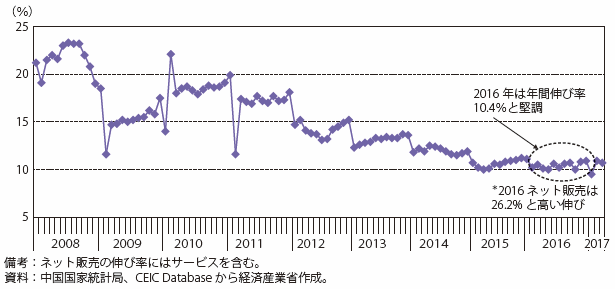
小売売上高を品目別に見ると、食料、衣類、家電など主要品目の伸びが低下する中で、小売総額の約3割を占める自動車が小型自動車の減税のため前年比10%と高い伸びを示した影響が大きい90,91(第Ⅰ-3-1-5図、第Ⅰ-3-1-6図)。なお、2017年は自動車の減税額が半減され年初の自動車販売の伸び率は2016年に比べて低下した。
第Ⅰ-3-1-5図 中国の小売売上高における主要品目別構成比(2016年)
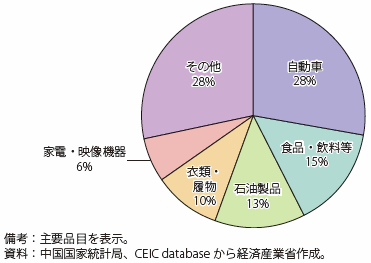
第Ⅰ-3-1-6図 中国の小売売上高の品目別伸び率
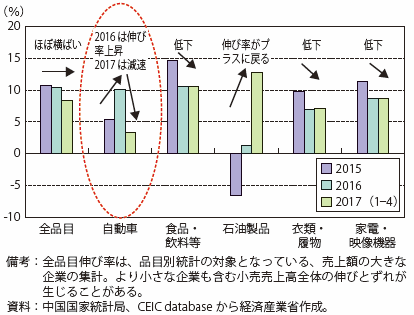
90 排気量1600cc以下の小型車の自動車取得税の税率10%を5%に引き下げる措置。2015年10月に導入され、2016年12月に終了の予定であったが、反動による販売減を考慮して、2017年12月まで延長された。ただし、減税幅は5%から2.5%に圧縮(税率10%を7.5%に引下げ)された。2017年初めの自動車の伸び率低下も、当初懸念された反動から考慮すれば、むしろ堅調との見方もある。
91 一方で、自動車の中ではSUV(スポーツ多目的車)の販売が台数ベースで減税対象の小型車よりも高い伸びを示しており、より豊かなものを求める消費行動に変化してきていることを示唆していると見ることもできる。例えば、2016年のSUVの販売台数伸び率は約44%で、小型車(1600cc以下)は約21%であった。
(3)投資
固定資産投資は、長期的に減速が続いてきたが、2016年中頃から政府のインフラ投資等を背景に、伸び率が下げ止まり、ほぼ横ばいで推移した(第Ⅰ-3-1-7図)。2017年に入ってからはインフラ投資等が牽引して再び伸び率が上昇している。
第Ⅰ-3-1-7図 中国の固定資産投資の伸び率(年初来累計・前年同期比)
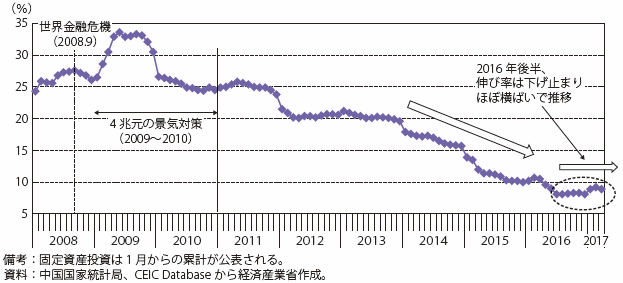
事業主体別には、2016年に入って民間投資が大きく落ち込んだ(第Ⅰ-3-1-8図)。一方、政策的な下支えでインフラ建設の大幅な伸びが続き(第Ⅰ-3-1-9表)、公共事業を受注しやすいといわれる国有企業の投資が全体を支えた。2016年後半に入ってからは、民間からのインフラや不動産への投資が増え始め、民間投資の伸びも下げ止まり、回復の動きが見える。
第Ⅰ-3-1-8図 中国の固定資産投資と民間投資の伸び率(年初来累計・前年同期比)
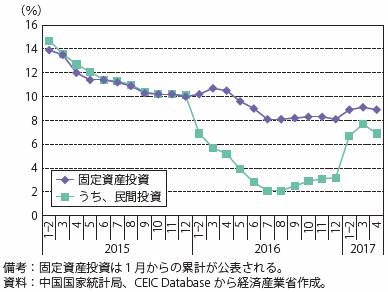
第Ⅰ-3-1-9表 中国の主要業種別固定資産投資(年初来累計・前年同期比)
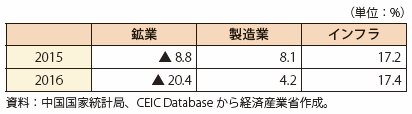
(4)貿易
2016年の貿易は、年間計で見れば輸出入とも前年割れとなった。輸出伸び率のマイナス幅が拡大する一方で、輸入のマイナス幅は縮小して、結果として貿易黒字は縮小した。一方、輸出入の動きを月次で見ると、世界経済の回復に伴って、2016年から2017年初めにかけて、伸び率がプラスに転じて上昇していく傾向も見られる(第Ⅰ-3-1-10図)。
第Ⅰ-3-1-10図 中国の輸出入の伸び率(前年同月比)
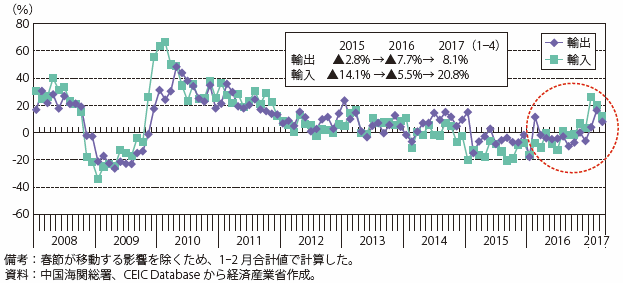
2016年の輸出入を品目別に見ると、輸出では、電気機械の伸びがマイナスに転じるとともに、一般機械のマイナスが続いた。輸入では、依然として伸び率のマイナスが続くものの、資源価格の回復によって、鉱物性燃料、鉱石などのマイナス幅は大幅に縮小した(第Ⅰ-3-1-11図)。
第Ⅰ-3-1-11図 中国の輸出入の品目別寄与度の推移
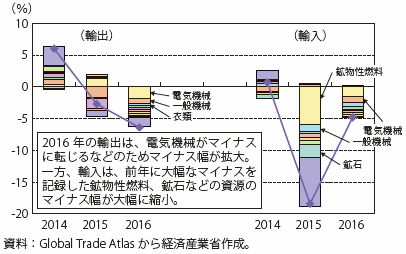
(5)株価・景況感
2016年の上海株式市場は、年初、株価急落により、サーキットブレイカーが発動され、取引停止となった。その後、下落が続いたものの、3月頃からは緩やかな上昇基調で推移している(第Ⅰ-3-1-12図)。
第Ⅰ-3-1-12図 上海総合指数の推移
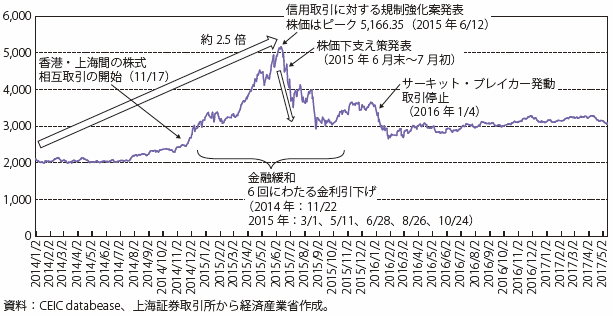
2016年の企業景況感を製造業PMI(購買担当者景気指数)で見ると、2016年後半から景気判断の分岐点である50を上回って上昇した。主要項目の動きを見ると、2016年後半以降に、生産や新規受注が上昇するとともに、新規輸出受注も改善している。企業規模別には、大企業を中心にPMIが上昇する一方、中小企業は依然として厳しい状況が続いている(第Ⅰ-3-1-13図)。
第Ⅰ-3-1-13図 中国の製造業PMI (購買担当者景気指数)の推移
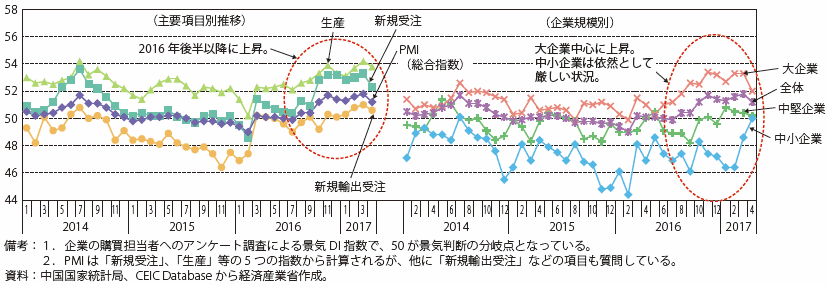
(6)2016年・2017年の政策目標と実績
2016年は、実質GDP成長率等は景気支援策の効果もあり目標を達成した(第Ⅰ-3-1-14表)。ただし、個別項目では小売売上高がほぼ目標どおり伸びる一方で、固定資産投資は目標を下回った。2017年は、実質GDP、固定資産投資、小売売上高等の目標を2016年よりも低めに設定する一方で、新規雇用者数の目標は引き上げて雇用を重視している。金融政策は「穏健中立」としているが、金融リスクや資産バブルを警戒してマネーサプライの目標は小幅ながら引き下げた。財政赤字やインフラ投資は前年並みの水準として、引き続き、景気支援策を続ける方針がうかがえる。2017年は5年に1度の共産党大会を秋に控え、景気支援策を続けながら経済成長を安定させる姿勢が見受けられる。
第Ⅰ-3-1-14表 中国の主要経済目標
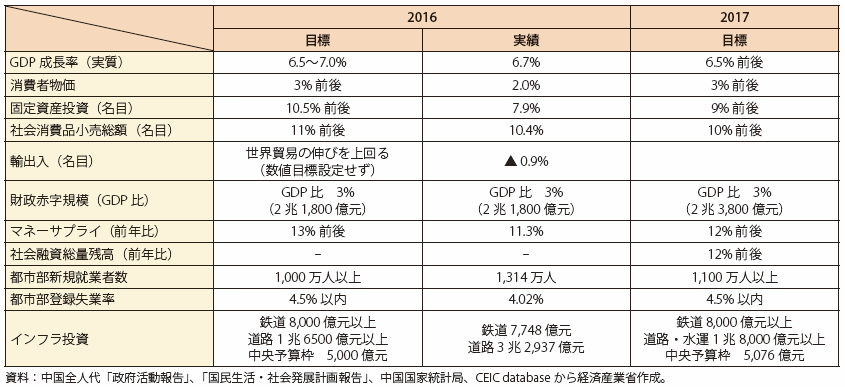
2017年の重点的取組分野として、過剰生産能力、過剰債務、過剰不動産在庫などの構造的問題を解消し、改革の深化、内需の拡大、イノベーションによる経済の高度化等を推進していく方針を掲げている(第Ⅰ-3-1-15表)。
第Ⅰ-3-1-15表 中国の2017年重点的取組分野
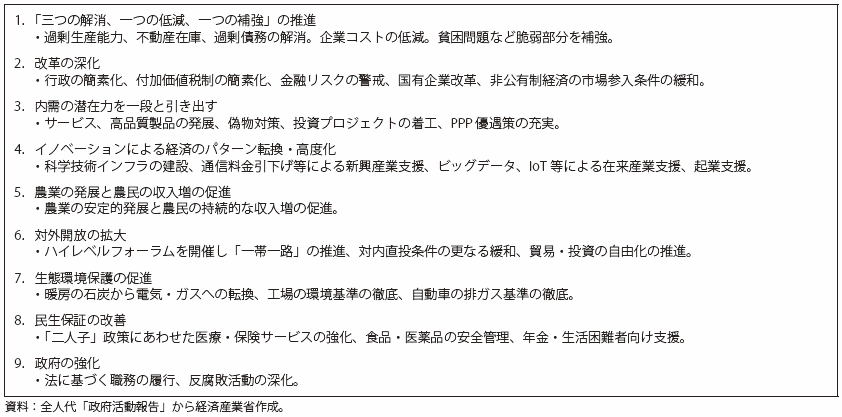
(7)中国の開発戦略(産業高度化・イノベーション、海外展開)
①産業構造の変化
中国は、過剰生産能力等により、製造業の成長が鈍化するなど、GDPや就業人員の面で、第1次、第2次産業(製造業等)から第3次産業(サービス業)へ経済の重心が移行してきている(第Ⅰ-3-1-16図)。
第Ⅰ-3-1-16図 中国の産業構造の推移
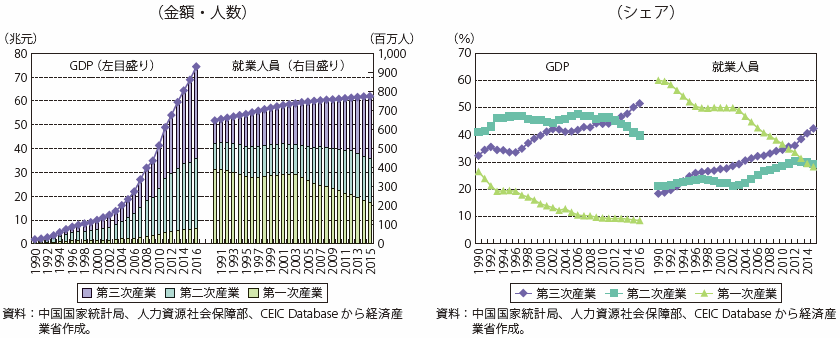
②研究開発・イノベーション
また、中国では、製造業の中でも、イノベーションや研究開発を通じた産業高度化が志向されており、一つの例として、GDPに対する研究開発の比率は主要先進国に迫る勢いで上昇している(第Ⅰ-3-1-17図)。
第Ⅰ-3-1-17図 主要国のGDPに対する研究開発費の比率
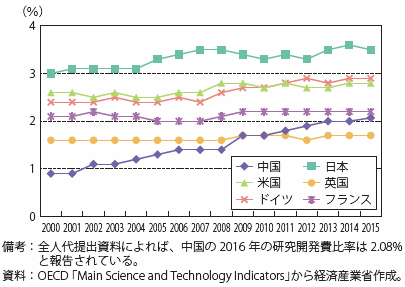
中国のイノベーション活動の水準を世界知的所有権機関(WIPO)等が公表している指数で国際的に比較してみると、既にG7など先進国に迫っている(第Ⅰ-3-1-18表)。
第Ⅰ-3-1-18表 イノベーション能力の国際比較
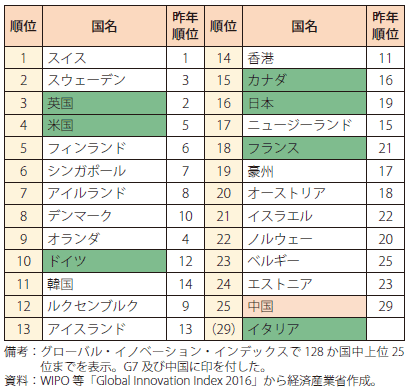
研究開発活動等の成果として特許の動向を見ると、特許協力条約に基づく国際特許出願件数も急速に増加しており、2016年、中国は国ベースで世界第3位となっている(第Ⅰ-3-1-19図)。さらに中国の一部のIT機器メーカーは、申請件数世界第1位、2位を占めるまでに至っている。
第Ⅰ-3-1-19図 国際特許出願件数
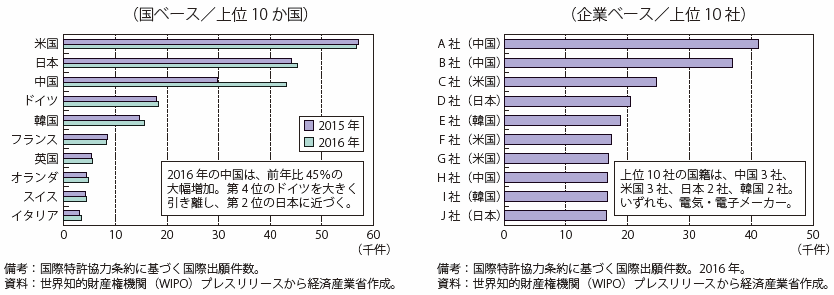
③中国製造2025
このようなイノベーションの促進、情報技術と製造業の融合等によって製造業の強化を図ることを目的とした戦略が2015年に発表された「中国製造2025」である。この戦略では、まず2025年までに中国を製造強国とし、次に2035年までに世界の製造強国の中でも中堅水準まで高め、最終的には建国100年である2049年に中国が世界の製造業トップに立つことを目指している(第Ⅰ-3-1-20表)。その方針としては、イノベーションの促進、情報技術と製造業の融合のほか、品質向上、ブランド化、環境保全への配慮等を掲げている。
第Ⅰ-3-1-20表 「中国製造2025」(Made in China 2025)
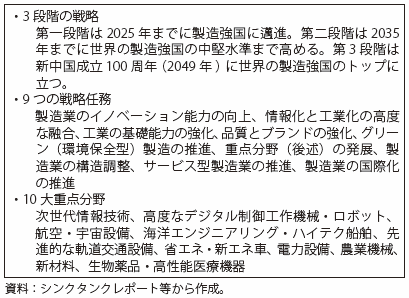
④新シルクロード(一帯一路)構想
中国は、古代のシルクロードになぞらえた「新シルクロード(一帯一路)」構想を提唱している。この構想は、シルクロード沿線地域の道路、鉄道、港湾、通信等のインフラを整備し、人、モノ、資金、情報等の流れを拡大して、中国から欧州にいたる広い地域の経済圏の構築を目指している(第Ⅰ-3-1-21表、第Ⅰ-3-1-22図)92。その対象国に明確な規定はないが、構想の提唱以来、中国は各国に参加を呼びかけており、2017年5月には北京において関係国を招いたハイレベルフォーラムが開催された。
第Ⅰ-3-1-21表 「一帯一路」構想の対象国
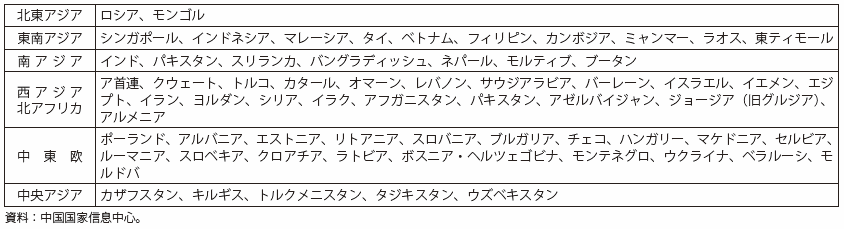
第Ⅰ-3-1-22図 「一帯一路」地図
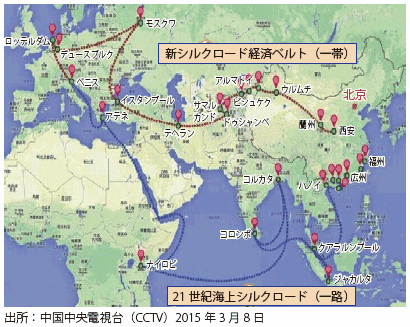
一帯一路の経済的意味としては、関連地域では中国企業の参加の下にインフラプロジェクトが進行しており、相手国のインフラ整備とともに中国において生産過剰とされている鉄鋼等の輸出先となっていると見られる。また、沿線諸国だけでなく、中国内陸部地域の経済開発を促進する効果を指摘する声もある。さらに長期的には、インフラ整備等の下に沿線地域の発展、中国との関係の緊密化を目指している。
プロジェクト推進のための資金的裏付けとしては、中国輸出入銀行や開発銀行などの既存金融機関のほか、「シルクロード基金」が創設されている。また、中国はアジアにおけるインフラ投資を推進するため、アジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立も主導している。
92 中国の習近平国家主席が2013年9月にカザフスタン訪問中に「新シルクロード経済ベルト」構想(陸路)を、翌10月にインドネシア国会で行った講演の中で「21世紀海上シルクロード」構想(海路)を提唱。中国は、この2つのシルクロードをあわせて「新シルクロード(一帯一路)」構想と呼んでいる。
