

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第4章 第4節 中東
第4節 中東
1.中東の経済概略
まず、最初に中東の主要国について、近年の経済動向を見ていく。その後、サウジアラビアとトルコについて、より詳細にその動向を述べていく。
(1)実質GDP成長率及び1人当たり名目GDPの推移
2010年代前半まで比較的成長率が高かったサウジアラビア、UAE、トルコは足下成長率が減速する傾向にある。一方で、2012年以降成長率が悪化していたイランは2016年は高い成長率に回復し、長らく2~3%程度の成長で推移していたエジプトは2015年以降4%超の成長率に回復している(第Ⅰ-4-4-1-1図)。
第Ⅰ-4-4-1-1図 中東主要国の実質GDP成長率の推移
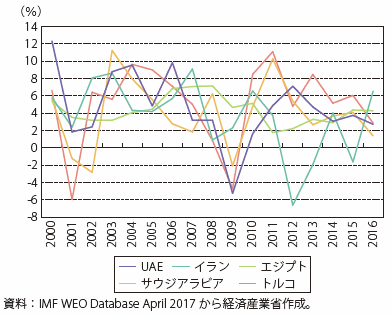
また、1人当たりの名目GDPは、原油価格の下落等により2014年を境に低下傾向にある(第Ⅰ-4-4-1-2図)。
第Ⅰ-4-4-1-2図 中東主要国の一人当たりGDPの推移
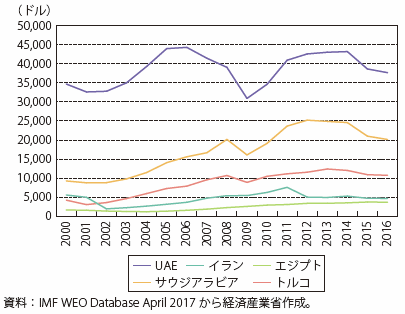
(2)経常収支及び外貨準備のGDP比の推移
経常収支GDP比については、サウジアラビアやUAEがかつてはGDP比で20%を超える経常収支黒字であったが、足下ではこれが大きく低下し、サウジアラビアについては対GDP比5%程度の赤字に、UAEは同5%程度の黒字となっている。一方、イランは、2011年以降対GDP比で黒字額が減少傾向だったが、足下では拡大に転じている(第Ⅰ-4-4-1-3図)。
第Ⅰ-4-4-1-3図 中東主要国の経常収支GDP比の推移
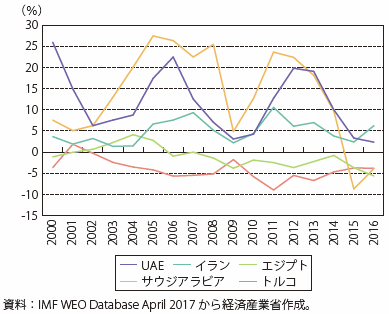
外貨準備については、対GDP比でサウジアラビアが足下低下傾向であり、トルコとエジプトが低い水準で推移している(第Ⅰ-4-4-1-4図)。
第Ⅰ-4-4-1-4図 中東主要国の外貨準備(対GDP比)の推移
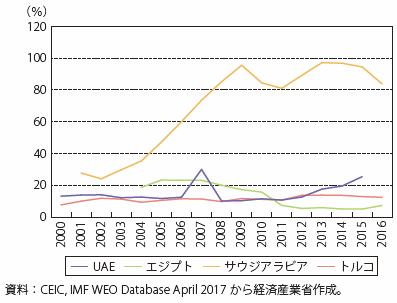
(3)国債CDSの推移
各国国債のCDSの推移を見ると、エジプトが中東域内では常に最も高い水準で推移していたが、足下では300bp付近まで低下してきた。一方、トルコは国内政治情勢の悪化に伴い、2015年以降250bp以上の高い水準で推移している。また、サウジアラビアについても2015年以降の資源価格の弱含み等を反映して、高い水準で推移しているが、足下は資源価格の回復を反映して、低下傾向で100bp付近を推移している(第Ⅰ-4-4-1-5図)。
第Ⅰ-4-4-1-5図 中東主要国のCDSの推移
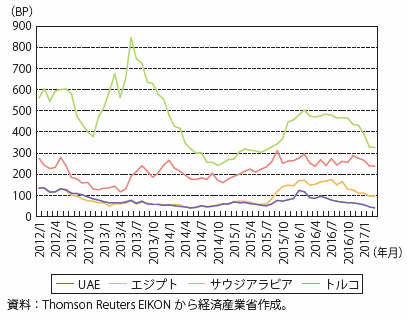
2.トルコ
(1)トルコ経済の動向
①GDP
実質GDPと需要項目別寄与度の推移(第Ⅰ-4-4-2-1図)について、2012年から2016年にかけて年率平均5.5%と世界的に見ても高い実質成長率が、長期的に継続している。実質GDP成長率の伸びは、個人消費および、企業の設備投資による固定資本形成が大きく貢献している。2016年第3四半期は純輸出の落ち込みにより前期比-1.3%だったが第4四半期では個人消費の伸びの回復と純輸出の赤字幅が縮小し、3.5%と引き続き高い数値を記録した。大統領信任による安定した政権、欧州諸国と比較しても良好な財政水準、国民の平均年齢が若く豊富な労働力、健全な銀行セクターといった強みを有する一方、経常赤字解消のためのエネルギーの海外依存の低下、産業の高付加価値化、国内の低貯蓄率等の課題がある。
第Ⅰ-4-4-2-1図 実質GDPと需要項目別寄与度の推移
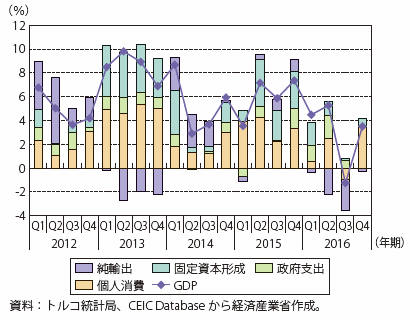
2016年後半はトルコリラの下落が大きな打撃を与えたものの、中央銀行の利上げや原油価格が比較的低いレンジを推移したことに等により、深刻な事態に陥ることはなく、現在回復基調にある。
②CPI
トルコの消費者物価指数(CPI)(前年比)の推移(第Ⅰ-4-4-2-2図)は、2011年に6.5%、2012年には8.9%と大きく上昇したものの、2013年には7.5%に下降するなど、2011年から2015年には上下を繰り返していたが、2015、2016年には連続して漸増し、7.7%(2015年)から1%上昇した。トルコは天然ガス等の資源輸入国であり、CPIは資源(原油)価格の影響を受ける。近年原油価格は下落傾向にありトルコはその恩恵を受けているところだが、貿易収支において恒常的に輸入超過にあるため、トルコリラが下落するとその赤字分が膨らむ。2016年はトルコリラが大きく下落したため、輸入超過が拡大した。なお、いずれの年もインフレターゲットの5%を大幅に超えている。(2015年1月よりトルコ中央銀行(TCMB)はインフレターゲットを5%とし、±2%を許容範囲としているところ。)
第Ⅰ-4-4-2-2図 トルコの消費者物価指数(前年比)の推移
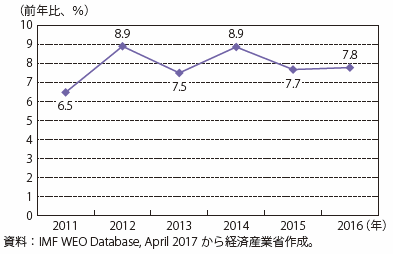
③経常収支
トルコの経常収支推移について、サービス収支が黒字、貿易収支が赤字であることがトルコの経常収支推移によりわかる。2012~2016年にかけて経常収支は継続してマイナスであり、平均440億ドルの赤字となっている(第Ⅰ-4-4-2-3図)。経常収支の対名目GDP比は平均マイナス5.6%となっている。貿易収支は恒常的に輸入超過により赤字である、トルコ独自の経済構造によるものだ。
第Ⅰ-4-4-2-3図 トルコの経常収支推移
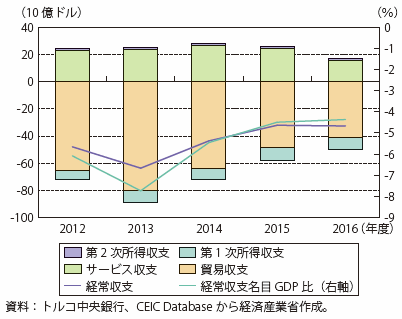
a.サービス収支を牽引する観光収入
サービス収支受取のほとんどは観光収入によるものだ。国営航空会社でトルコのフラッグキャリアであるターキッシュ・エアラインズがイスタンブールを拠点に欧州のほぼ全ての都市(就航国は105ヵ国で世界最多(2014))を網羅して運航し(第4図国際観光客到着数ランキング(UNWTO 2016年)より、トルコはフランス、米国、スペイン等観光大国に次いで、世界第6位である。)トルコの観光収入の多くを占める(第Ⅰ-4-4-2-4表)。
第Ⅰ-4-4-2-4表 国際観光客到着数ランキング
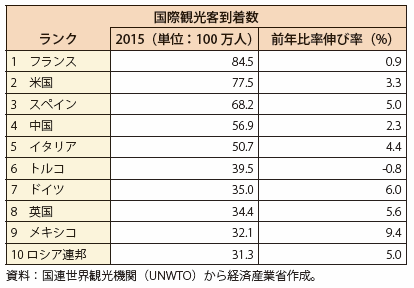
トルコは2023年に建国100周年を迎えるに当たって様々な目標を掲げ、アジアと欧州を結ぶ地政学的に重要な要衝に位置している利点を活かしトルコ共和国建国100周年の2023年には世界で5番目の観光大国になることを目指している200。
200 2023年はトルコ共和国建国100周年にあたり、単独与党の公明発展党は2023年に向け、GDPの世界トップ10入りなどさまざまなプロジェクトに言及している。
④ 財政収支
トルコ財政収支(歳入・歳出)と財政収支の対GDP比について、2008年の世界金融危機の余波や、高成長ゆえの内需拡大により輸入が大幅に増加し、経常収支がマイナスに悪化したことが影響し、2010年財政収支は、-380億トルコリラと大幅な赤字だった(第Ⅰ-4-4-2-5図)。政府は投機的な資本流入を抑制しつつ、経常赤字を縮小することをねらいとして、政策金利の引き上げと預金準備率の引き上げの組み合わせによる金融引き締めを実施し、2011年には-78億トルコリラと赤字額が大きく減少した。その後2015年まで-200億トルコリラ付近を推移していたが、2016年には前述の通り、トルコリラ下落等の影響により-420億トルコリラと2010年と同程度の赤字幅に拡大した。
第Ⅰ-4-4-2-5図 トルコ財政収支(歳入・歳出)と財政収支の対GDP比
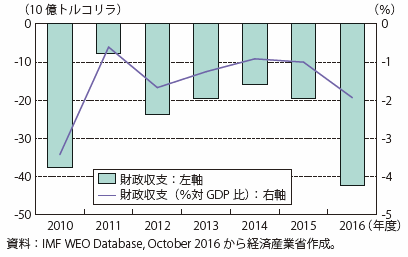
(2)海外からの投資状況
トルコへの対内直接投資額の推移(フロー)(第Ⅰ-4-4-2-6図)について、2005~2008年まで対内直接投資額は各年200億ドル程度に達した。2009年には世界金融危機の影響を受けて86億ドルにとどまったものの、その後は2016年まで140億ドル程度を推移している。
第Ⅰ-4-4-2-6図 トルコへの対内直接投資額の推移(フロー)
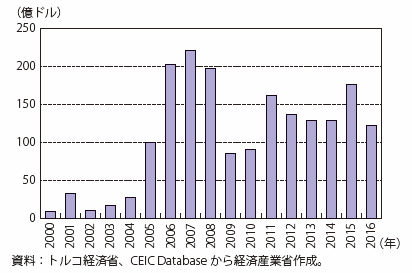
トルコの海外資本が入っている企業数の推移(累計)(第Ⅰ-4-4-2-7図)について、世界金融危機後の2008~2009年とトルコリラの上昇が進んだ2012年、国内経済拡大が鈍化した2013年を除き、2000年以降、増加傾向だった。2016年には昨年から20社減の5,581社だった。
第Ⅰ-4-4-2-7図 海外資本が入っている企業数の推移(累計)
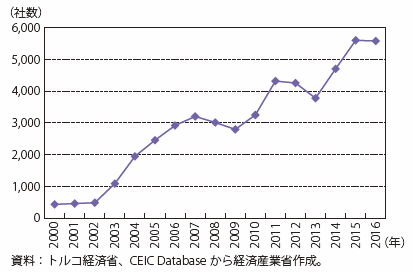
国別のトルコの対内直接投資額割合について2016年は、欧州からはオランダ、イギリス、ドイツ、オーストリアが多く、他に中東諸国全体で18%と全体の約5分の1を占めており、地理的に近い地域と経済的にも密接な関係があるといえる(第Ⅰ-4-4-2-8図)。
第Ⅰ-4-4-2-8図 国別トルコ対内直接投資額の割合(2016年)
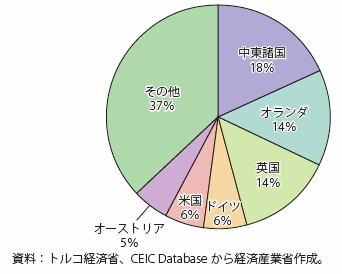
日本からトルコへの対外直接投資額は2013年に4.4億ドルに達した後2014年に2.6億ドルに落ち込んだが、2015~2016年は逓増している(第Ⅰ-4-4-2-9図)。トルコに登記簿上登録している日本企業数も2015年には200社を超えた(第Ⅰ-4-4-2-10表)。
第Ⅰ-4-4-2-9図 日本からトルコへの直接投資額
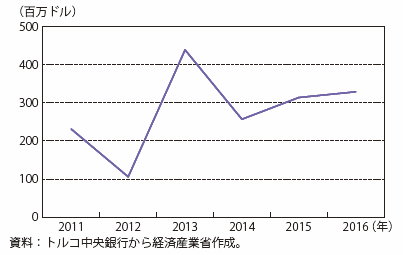
第Ⅰ-4-4-2-10表 トルコに進出している日本企業数(登記ベース)201
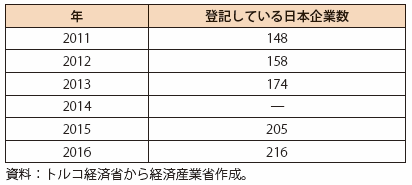
201 2014年は該当データなし。
2016年8月、日本の大手建機会社がトルコ・イズミール市に駐在事務所を開設した。「トルコは農業GDPにおいて欧州で第1位、世界でも7位の農業大国であり、主力事業である農業機械の販売拡大が見込め、さらに現地での旺盛な建設需要がさかんな海上交易を背景に、小型建設機械・船舶用エンジンについても今後も安定した需要が期待でき、トルコは今後大きなビジネスチャンスが見込める有望国」と進出理由及び背景を述べている。また、2016年11月には日本の大手食品会社が現地大手食品会社の全株式を取得した。その背景として、トルコの人口、30歳以下の若年層が50%を占める年齢構成比、安定したGDP成長率の経済・社会基盤に加えて、経済発展に伴い、都市部での女性の社会進出が拡がっており、簡便性の高い調味料・加工食品のニーズが拡大していると述べている。
トルコは、人口が7,867万人(2015年時点)と中東や北アフリカの周辺国と比較して多く、かつ従属人口(人口統計で、14歳までの年少人口と65歳以上老年人口を合計した人口。従属人口以外の人口は生産年齢人口という。)比率が49.7%と小さい(第Ⅰ-4-4-2-11表、第Ⅰ-4-4-2-12表)。また、欧州、アフリカに近接する地理的特性という点で、輸出拠点や生産拠点となるポテンシャルを有する。中央アジア・コーカサスや中東地域から欧州へのエネルギー(石油・天然ガス)輸送の要衝として地政学的に重要といえる。これまでのトルコの経済成長、マーケットとしての利点(人口が多く、若年層世代の厚みがある)(第Ⅰ-4-4-2-11表、第Ⅰ-4-4-2-12表)、中東、欧州、北アフリカへの輸出拠点として有望なことを踏まえ、長期的観点で日本企業の投資は2016年以降も冷静な判断と慎重を期しつつ、継続しているのは着目に値する。
第Ⅰ-4-4-2-11表 トルコ及び周辺国の人口推移
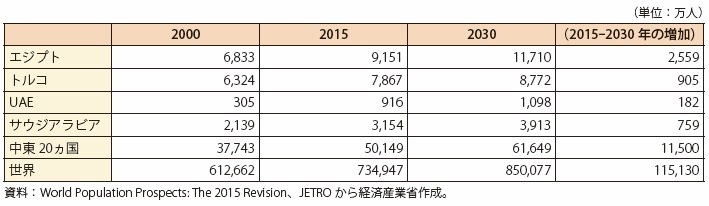
第Ⅰ-4-4-2-12表 トルコと周辺国の従属人口の比較
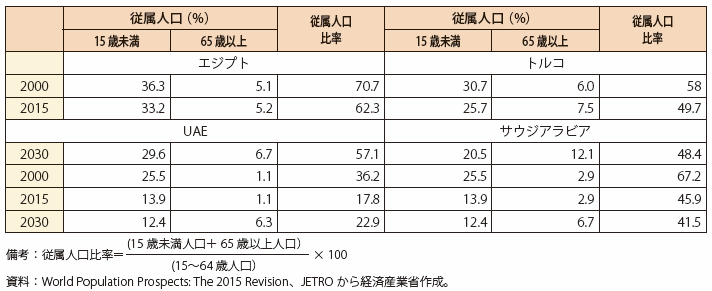
(3)今後注意すべきリスク
【クーデター未遂の影響と今後の経済見通し】
2016年7月15日にトルコ軍の一部がクーデターをおこしたが、数日で政府の鎮圧により収束した。国民の政権支持の姿勢は早期の事態収拾につながり、大統領に対する国民の支持の高さが改めて示された。
クーデターによる直後の影響は、為替市場は大きく反応し、一時対米ドル3.05リラをつけるなど4.5%下落した。トルコ2年国債で0.3%、10年国債で0.6%程度金利が上昇した。金融政策決定会合ではコリドー上限金利の引き下げが行われた。金融市場ではリラ相場が一時的に大幅下落したが、早期の事態解決に加え中銀による市場安定化策を受け、徐々に落ち着きを取り戻した。なお、格付け会社S&Pは、トルコ外貨建長期債務格付けを「BB+」から「BB」へ引き下げる一方、自国通貨建長期債務格付けを「BBB-」から「BB+」へ引き上げた。
今後の経済見通しについては、足下の景気は移民流入などを背景に個人消費を中心とする内需が景気をけん引している。企業の設備投資意欲は後退するなか、今回のクーデター未遂やテロなどの治安悪化は海外からの直接投資を抑制へと促した。2017年4月には、大統領権限を拡大する憲法改正の是非を問う国民投票が行われ賛成票が上回り、国民のエルドアン大統領への信任と政権の安定を示す結果となった。憲法改正案では、首相職を廃止し現行の議院内閣制は大統領が国家元首と行政の長を兼任し、大統領に非常事態宣言の発令権や閣僚の任免権、予算策定の権限などを与える。改憲により、次の大統領選は2019年となり、エルドアン大統領は2029年まで大統領職にとどまることが可能になる。
原油などエネルギーは大部分を輸入に依存しており、為替レート値下げによる貿易赤字の拡大やインフレ率が徐々に上昇している。
当初2017年の成長見通しをIMFは3.8%に上方修正、世界銀行は3.5%と予測していたが、今後引き下げの可能性がある。
トルコには3つの政策金利がある。トルコ中央銀行は、主要政策金利の1週間レポ金利挟み、翌日物貸出金利(上限金利に相当)、翌日物借入金利(下限金利に相当)という「3つの政策金利」によるコリドー(金利レンジ)を形成して、市場金利を誘導するやや複雑な金融政策としている。将来的には金利の一本化を目指している。
2014年1月にはトルコ中央銀行は緊急開催した金融政策会合において、政策金利の大幅な引き上げ(4.5%→10.0%)を決定した。トルコ中央銀行が、このような大胆な政策金利引き上げに踏み切った直接的な原因は、アメリカの量的金融緩和政策の縮小や中国経済の減速による、新興国からの資本流出を懸念しリスク回避目的の、新興国通貨の急落である。アルゼンチンペソ、ブラジルレアルと同様にトルコリラも対米ドルで下落が続き、通貨下落の歯止めのため急激な引き上げを行った。
2016年11月には、トルコリラ安による影響に加え、インフレ抑制を目的として3つの中でも特に重要である1週間レポ金利を7.5%から8%に利上げした。2年10か月ぶりの利上げであり、金融政策会合後の声明文でトルコ中央銀行は「同国経済に底打ちの兆候が出る中、インフレ率も頭打ちしつつあるものの、足許の急激なリラ安はインフレ上振れ要因となる」とし、金融引き締めを通じたインフレ期待の沈静化が必要との認識を示した。
第Ⅰ-4-4-2-13図 トルコ政府総債務残高(対GDP比)
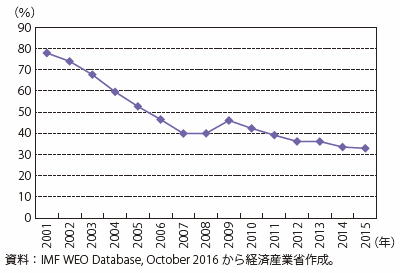
第Ⅰ-4-4-2-14図 トルコリラ為替レート(対USD)推移(直近)
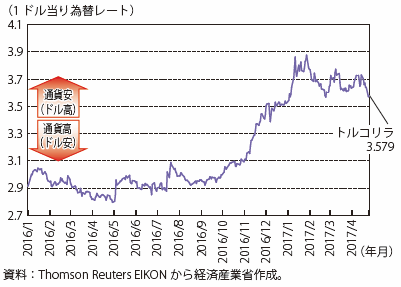
第Ⅰ-4-4-2-15図 トルコの政策金利の推移
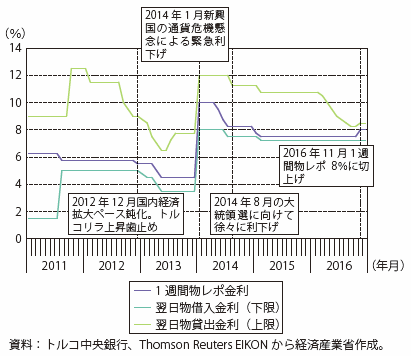
3.サウジアラビア
(1)マクロ経済動向
GDP成長率は世界経済危機(2008年)の影響より2009年には大きく落ち込んだ(-2.1%減)ものの、その後2011年まで漸増し10.3%に達した。主に輸出と資本形成が成長率に大きく寄与している。これは2009年には世界的な経済悪化により一時原油需要が低下したこと、2010~2011年には原油価格が1バレル100ドル付近を推移するなど、原油価格の高騰が背景にある。2012年以降は原油価格が下落したため輸出の寄与度は減少し、2014年にはマイナスに達した(-0.9%)。代わって、政府消費、個人消費が成長率に大きく貢献していることが第Ⅰ-4-4-3-1図よりわかる。
第Ⅰ-4-4-3-1図 サウジアラビアのGDP成長率及び産業別寄与度の推移
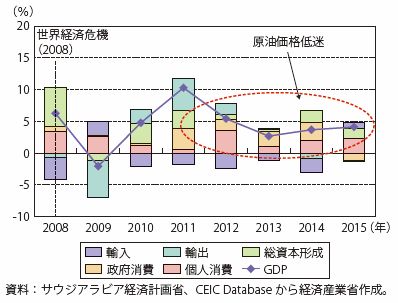
消費者物価指数(CPI)について、サウジアラビア総合統計庁(旧中央統計局)が発表した2016年1月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比4.3%上昇し、過去5年間で最大の伸び率となった。当地の大手投資銀行ジャドワ・インベストメントは、2015年末から実施されたエネルギー価格値上げの影響と分析している。物価の大幅な上昇は、中所得層への負の影響が大きいと警告する経済学者もいる。
第Ⅰ-4-4-3-2図 サウジアラビアの消費者物価指数(CPI)推移(前年同月比)
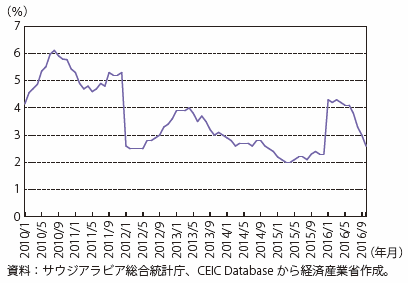
第Ⅰ-4-4-3-3図 サウジアラビアの貿易収支推移
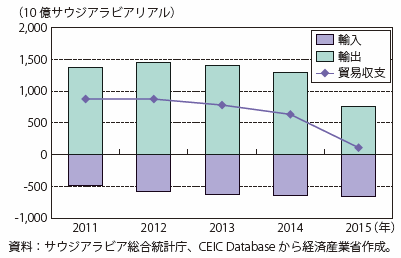
貿易収支について、2011年の輸出額は1.37兆リヤル(以下リヤル)、輸入額は4,934億リヤルだったが、2015年には輸出額は7,633億リヤルに減り、一方輸入は6,550億リヤルまで増加した。原油価格の下落が影響しており、貿易収支黒字分が縮小傾向だったことがわかる。
経常収支については、2010年667億51百万USドルだったが増加が続き、2012年には1,647億64百万USドルと約2.5倍に倍増した。その後黒字は徐々に減り、2015年には534億78百万USドルの赤字となり、大幅な収支悪化となった(第Ⅰ-4-4-3-4図)。
第Ⅰ-4-4-3-4図 サウジアラビアの経常収支推移
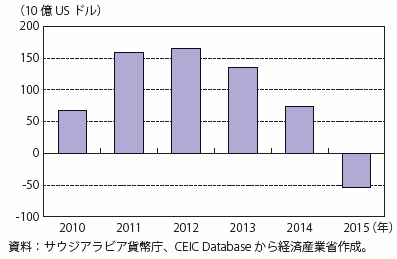
政策金利については、サウジアラビアではドルペッグ制202を採用しており、2010年以降、政策金利も一定である。
202 ドルペッグ制とは、ある国の政府や中央銀行などが金利調節や為替介入を行い、自国の通貨とアメリカドルの為替レートを一定割合に保つ、自国通貨と米ドルとの固定相場制を図る政策である。サウジアラビアやUAEは自国の金利をアメリカの金利と連動させることで為替レートの大幅な変動を回避できる。
(2)油価下落による財政収支への影響
財政収支のうち、歳入は2009年以降漸増し、2012年にはピークの1兆4,400億リヤルに達したもののその後逓減し、2015年には6,150億リヤルまで減少した。歳出は2009年5,960億リヤルから2014年の1兆1,090億リヤルをピークに増加傾向だったが、2015年にはやや縮小し、9,780億リヤルに微減した。
WTI原油価格は2008年2月に1バレル100USドル超えの高止まり、その年の6月には140USドルに達した。しかし、世界経済危機が起きた10月には60ドル台にまで下落した。その後2009年は40~70ドルを推移した。2009年の平均は1バレル当たり63.9USドルだった。上下を繰り返した後2015年11月には40ドル台にまで下落。2015年の平均は49.3USドルで2009年時と比較すると14.6USドルもの差がある。
第Ⅰ-4-4-3-5図 サウジアラビアの財政収支と名目GDP比の推移
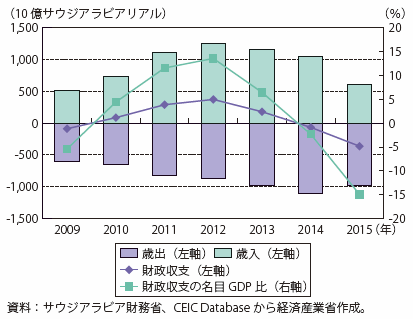
第Ⅰ-4-4-3-6図 2006-2015年の原油価格推移
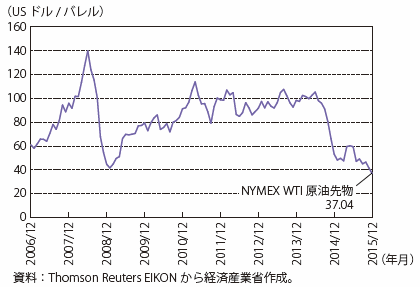
石油依存脱却を目指す国家目標「サウジアラビア・ビジョン2030」203を2016年4月に発表し、非石油部門の収入増のための政策を立案している中での予算編成となり、歳入は6,920億リヤル(約20兆7,600億円、1リヤル=約30円)で2016年度実績(推計値)に比べ31.1%増加した。一方、歳出は8,900億リヤルで前年度実績を7.9%上回った。歳出額は2015年度を上回り過去最大になっている。内訳では、石油収入4,800億リヤル(45.9%増)、非石油収入2,120億リヤル(6.5%増)を見込んでいる。OPEC加盟国の原油減産合意を受けて、2017年度は原油価格上昇による歳入増と非石油部門の増収に期待している。
財政赤字分の1,980億リヤルはGDPの7.7%に相当するが、国債発行や外貨準備高の取り崩しによって補うとしている。なお、歳出には「国家改革計画(NTP)2020」204のための420億リヤルも含まれている。(第Ⅰ-4-4-3-7表)
第Ⅰ-4-4-3-7表 2016~2017年度の歳出入
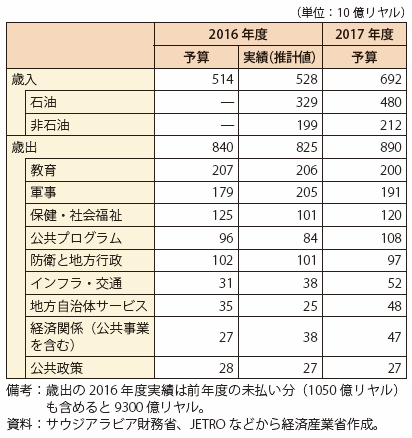
203 2030年までの経済改革計画で石油依存型経済から脱却し、投資収益に基づく国家の建設を目的に投資や観光、製造業や物流の整備育成など経済の多角化がビジョンとして掲げられている。
204 ビジョン2030を実現するために、2020年までに達成すべき目標を具体的に提示しており、具体的には、「非石油収入を5300億リヤルに増やす」「公務員の給与総額を4800億リヤルから4560億リヤルに削減する」「GDPに対する公的債務割合を7.7%から30%に増やす」などが盛り込まれている。
【教育、軍事、保健・社会福祉が歳出の柱】
歳出の内訳は第Ⅰ-4-4-3-8図のとおりで、政策の柱となる教育、軍事、保健・社会福祉にそれぞれ23%、21%、14%が割り当てられている。
第Ⅰ-4-4-3-8図 2017年度予算の歳出内訳
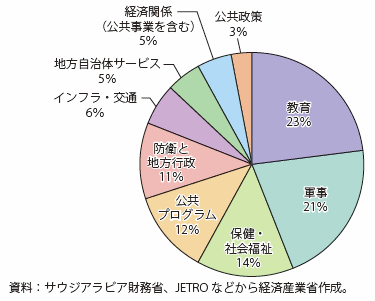
【2016年後半以降原油価格は上昇基調】
2016年~2017年上期の原油価格推移(第Ⅰ-4-4-3-9図)について、2016年11月のOPECと非加盟国の協調減産合意後は上昇基調で世界的な原油先物価格の指標となるWTI価格は50ドル付近を推移している。
第Ⅰ-4-4-3-9図 2016年~2017年上期の原油価格推移
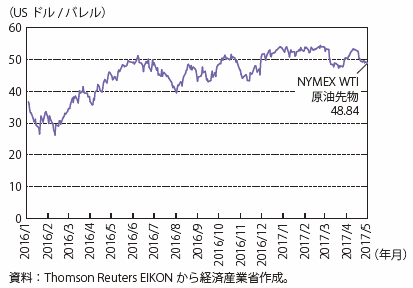
(3)今後注意すべきリスク
①原油価格の動向
サウジアラビアの輸出額の8割が原油である。多くの識者は2017年の動向について、40ドルを割る下落はなく、徐々に上昇基調となると見ているが、世界的な原油供給過剰の恐れが全くないとは言い切れない。1バレル50ドル台以上であればシェール生産が今後も増える可能性が大きい(第Ⅰ-4-4-3-10図)。また、今後もOPECと非加盟国の産油量調整の協調をサウジアラビアなどがまとめられるかが鍵となる。
第Ⅰ-4-4-3-10図 米国原油リグ数の増加
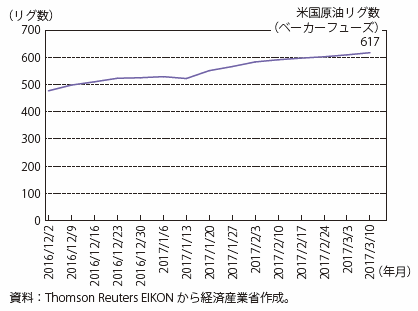
輸出の大部分が鉱物資源燃料のため、ひとたび資源価格が下落すると経済も悪化しやすい傾向がある。鉱物資源燃料に依存した経済構造からの脱却とともに、自国内での石油精製設備に加えて石油産業以外の製造業の発展やインフラ整備など、自国産業の育成・多角化を外国資本企業等の協力を得ながら促進させることが課題である。
②財政再建改革による現地企業への影響
政府は予算と同時に発表した「財政均衡プログラム」(財政再建のための具体的な計画)で、1年前に2016年度予算とともに発表したガソリンなどエネルギーの国内価格値上げ(政府補助金の削減)を引き続き実施する方針を示すとともに、非石油部門の増収を目指す以下のような政策を挙げている。既に導入済みの政策としては、「ビザ代値上げ」「地方自治体のサービス料金値上げ」「エネルギー・水道価格の改定(フェーズ1)」「公務員の給与改定(削減)」がある。さらに、今後2020年までに導入する政策として、「エネルギー価格の再改定」「外国人への課税強化」「付加価値税(VAT)の導入」などを挙げている。このように各種補助金の合理化と合わせ、歳入の多様化を進めている。
2016年1月に実施したガソリンなどへの補助金削減に際しては、小売価格や水道料金の値上げなどにより、1~6月の消費者物価上昇率が前年同期比4%超となるなど、国民への負担が大きかった。今後もエネルギー関連の補助金削減は財政の健全化には欠かせないとしているが、所得の低い国民に対しては相対的に負担を軽減するため手当を支給する方針だ。
政府は国民支援を強化する一方、外国人には一層負担を求める方針だ。しかし、これは海外からの投資を呼び込み、民営化の促進や民間部門の活性化を図ろうとする政策と相反するともみられ、今後どのような影響が出るのか注視が必要だ。
