

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第4章 第3節 ロシア
第3節 ロシア
1.マクロ経済動向
ロシア経済は、緩やかな回復基調にある。2014年7月以降のウクライナ危機発生及びクリミア併合に伴う欧米からの経済制裁に加え、2015年以降、原油価格の下落を主因として、ロシア経済はマイナス成長で推移した。しかし、その後の原油価格の上昇を追い風として、2016年10-12月期に前年比+0.3%と8期ぶりにマイナス成長を脱した。IMFの見通しによれば、2017、2018年は引き続きプラス成長で推移することが見込まれている(第Ⅰ-4-3-1-1図、第Ⅰ-4-3-1-2図)。
第Ⅰ-4-3-1-1図 ロシアの実質GDPの成長率の推移
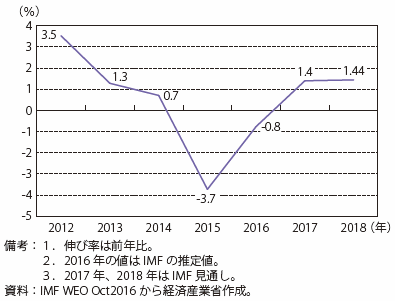
第Ⅰ-4-3-1-2図 ロシアの実質GDP成長率及び需要項目別寄与度の推移
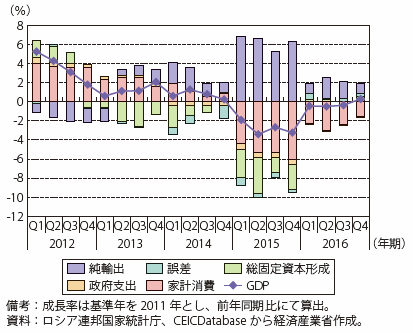
以下、輸出、個人消費、消費者物価、金融市場の動向を中心に概観する。
(1)輸出動向
ロシアの輸出動向をエリア別に見ると、EU27向けは45.7%、CIS諸国向けが13.1%を占めており、EU諸国とCIS諸国向けで58.8%と6割近くを占めている(第Ⅰ-4-3-1-3表、第Ⅰ-4-3-1-4図)。
第Ⅰ-4-3-1-3表 ロシアの主要輸出先及びシェア(2016年)
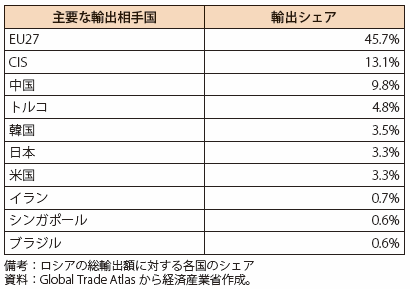
第Ⅰ-4-3-1-4図 地域別輸出シェアの推移
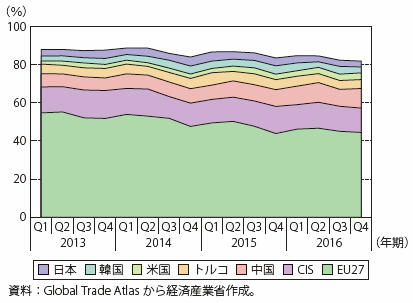
輸出の大半を占めるEU向けが2014年以前の額を回復していないため、ロシアの輸出全体を押し下げる形となっているが、2016年度は後半に向けて輸出回復の基調がみられる(第Ⅰ-4-3-1-5図、第Ⅰ-4-3-1-6図)。
第Ⅰ-4-3-1-5図 ロシアの輸出額推移(前年比)
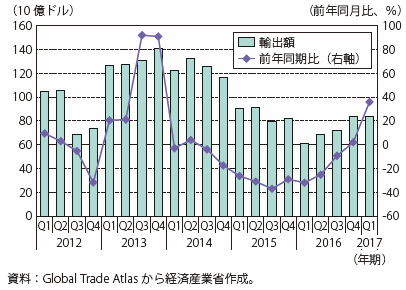
第Ⅰ-4-3-1-6図 輸出額及び輸入額推移(ドルベース)
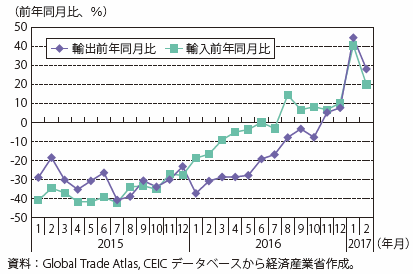
しかし、ウクライナ問題に加え、シリア情勢も重なりロシアと欧米諸国の関係の改善の兆しがみられないこともあり、注視が必要である。また、ロシアの輸出の(47.1%)(2016年時点)を占める石油天然ガス関連の輸出額が減少している。しかしながら、油価の下落に歯止めがかかったことにより、減少傾向に歯止めがかかる可能性もある(第Ⅰ-4-3-1-7図)。
第Ⅰ-4-3-1-7図 ロシアの輸出に占める石油天然ガス関連比
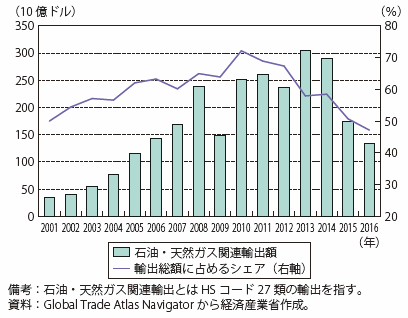
(2)個人消費
個人消費は2015年第1四半期に大きく落ち込み、第4四半期まで下降傾向が続いた。2016年第1四半期から、持ち直し傾向ではあるものの、個人消費は、2014年以前の水準には戻っていない(第Ⅰ-4-3-1-8図)。
関連指標である名目賃金及び小売売上高の動向を見てみると、2015年第1四半期に個人消費が落ち込んだ際には、両者とも減少し、2015年5月には若干持ち直したものの2015年末にかけ減少基調であった。2016年1月から2月には両者とも持ち直しが見られたが、その後も大幅な回復には至っていない(第Ⅰ- 4-3-1-9図)。
第Ⅰ-4-3-1-8図 個人消費の推移
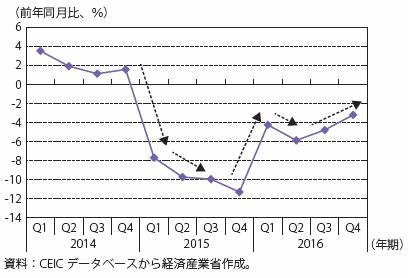
第Ⅰ-4-3-1-9図 小売売上高および名目賃金の推移
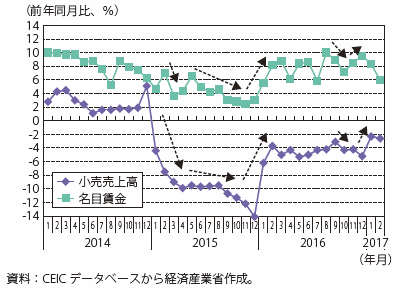
(3)自動車販売
前述のように、2016年第1四半期に、個人消費を取り巻く環境が改善するに伴い、小売売上高の伸びも大幅に改善した。小売売上高への影響が大きい自動車販売動向を見ると、(2)で示した個人消費の改善に呼応して2016年1月以降、自動車販売台数の減少幅が改善しており、2017年3月には前年比9.4%増となり、4か月ぶりにプラスに転じた(第Ⅰ-4-3-1-10図)。
第Ⅰ-4-3-1-10図 国内自動車販売数、伸び率の推移(月次)
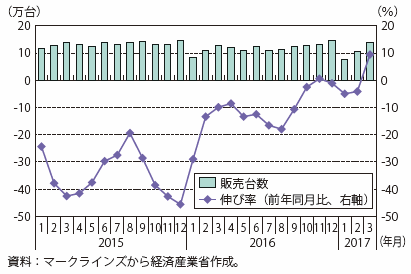
また、2016年通年のロシアの自動車販売台数は142万5791台となり、前年比10%減となったものの、2015年の前年比35%減より減少幅が大幅に小さくなった(第Ⅰ-4-3-1-11図)。
第Ⅰ-4-3-1-11図 国内自動車販売数、伸び率の推移(年次)
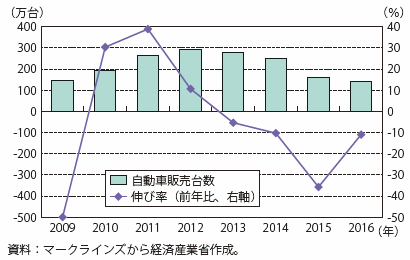
(4)消費者物価指数と政策金利
2014年後半以降は、資源安に伴いルーブルが下落したことで、輸入物価が上昇したため、一時は消費者物価が17%程度まで上昇した。これに併せてロシア中央銀行は政策金利を2014年12月に17%まで引き上げた。しかし2015年後半以降、消費者物価は下落に転じ、その後は2016年1月の8%から2017年3月の4%程度まで徐々に低下している。その後ロシア中央銀行は、政策金利を10%まで徐々に引下げたが、2017年3月にも景気に配慮し、0.25%利下げを実施したため、政策金利は9.75%となった。その後、4月の政策金利は据え置かれたものの、5月には政策金利は0.5%引き下げられ、9.25%となった(第Ⅰ-4-3-1-12図)。
第Ⅰ-4-3-1-12図 ロシアの政策金利と消費者物価指数の推移
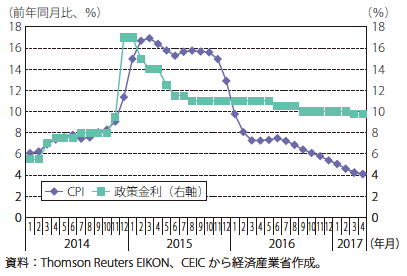
(5)金融市場動向
原油価格の低迷等により、ルーブルは2015年6月以降、2016年1月まで最大約35%下落した。これは、ブラジル等の新興諸国と比べても高水準なものであった。しかし、その後は緩やかな上昇に転じ、2017年に入っても上昇傾向で推移している。株価についても、おおむね右肩上がりで推移している(第Ⅰ-4-3-1-13図、第Ⅰ-4-3-1-14図)。
第Ⅰ-4-3-1-13図 為替レート(対USD)推移
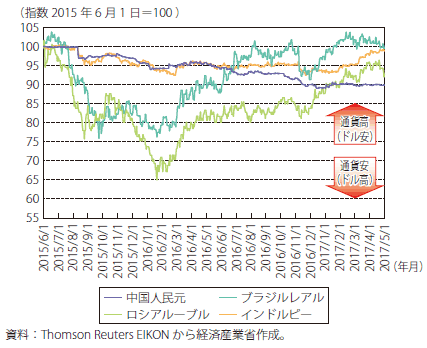
第Ⅰ-4-3-1-14図 新興国の株価指数推移
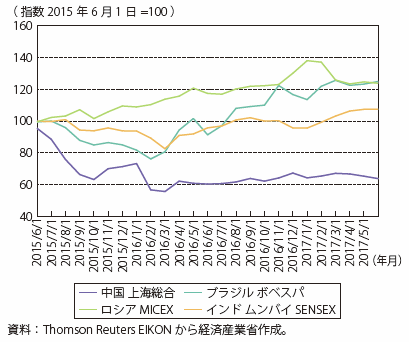
CDSで見ても2015年8月には中国やインドと比較しても金融市場のリスクは高かったが、その後は、緩やかな下降傾向にあり、特に2016年11月以降は警戒水域とされる200の水準以下に低下し、金融市場のリスクは、足下は軽減する傾向が見られる(第Ⅰ-4-3-1-15図)。
第Ⅰ-4-3-1-15図 新興国のCDS (5年物)の推移
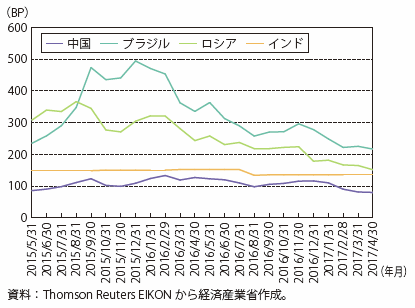
また、外貨準備は、対GDP比で見ても2014年の18.5%から2016年の29.2%まで改善が進んでおり、2016年には新興諸国の中でも最も高い水準となった(第Ⅰ-4-3-1-16図)。また、ロシアのPMIについては、足下は低下しているものの、おおむね上昇傾向にあり、主にサービス業が牽引しており、新興諸国の中でも堅調に推移している(第Ⅰ-4-3-1-17図、第Ⅰ-4-3-1-18図)。
第Ⅰ-4-3-1-16図 新興国の外貨準備(対GDP比)の推移
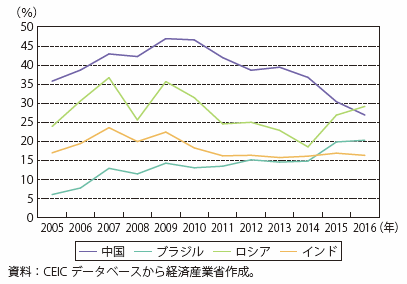
第Ⅰ-4-3-1-17図 ロシアのPMIの推移
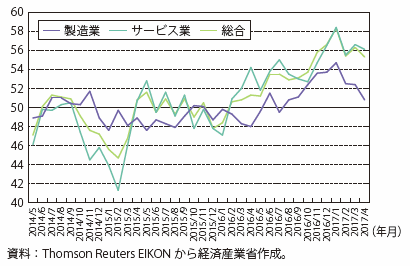
第Ⅰ-4-3-1-18図 新興国のPMI (総合)の推移
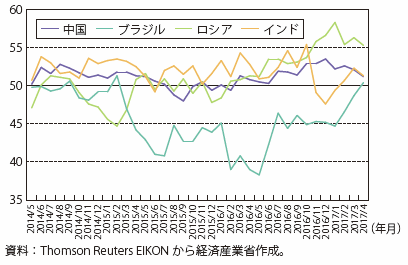
トランプ大統領が選出されたことに伴い、米ロ関係の改善が見込まれていたが、サイバー攻撃疑惑やシリア情勢の不安定化により、現段階では関係改善には至っていない。ロシアの金融市場は今後も注視が必要である。
2.今後注意すべきリスク
ここまで概観したように、輸出や個人消費の低迷により、2016年のロシアの経済成長率はマイナスであったものの、2017年以降は、原油価格の持ち直しを背景として輸出の拡大と個人消費の増加によりプラス成長になることが見込まれる。但し、今後、財政・金融政策が引締め傾向で推移した場合には、その回復ペースは緩やかになる可能性がある。
また、ウクライナ問題やシリア情勢を巡り、欧米諸国との関係改善の兆しが見えず、制裁の解除については不透明である。また原油価格の動向も今後、減産合意や米国シェールガス生産の動向にも左右されるため、引き続き上昇基調で推移するかどうかは、現時点でははっきりしない。このため、今後ともロシア経済は、地政学リスクや原油価格動向によって左右される点に注意が必要である。
