

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第4章 第2節 中南米
第2節 中南米
1.中南米の経済概略
中南米経済は、主要な輸出品である一次産品価格の下落や世界経済の減速に伴い、他の新興・途上国と同様に成長が低迷しているが、資源価格の回復等に伴い、今後は緩やかに回復していくと見込まれている。IMFは中南米地域の経済成長率について、2016年の-1.0%から2017年は+1.1%、2018年は2.0%とプラス成長に転じると見込んでいる(第Ⅰ-4-2-1-1図)(第Ⅰ-4-2-1-2表)(第Ⅰ-4-2-1-3図)。
第Ⅰ-4-2-1-1図 中南米地域及び主要国のGDP成長率の推移
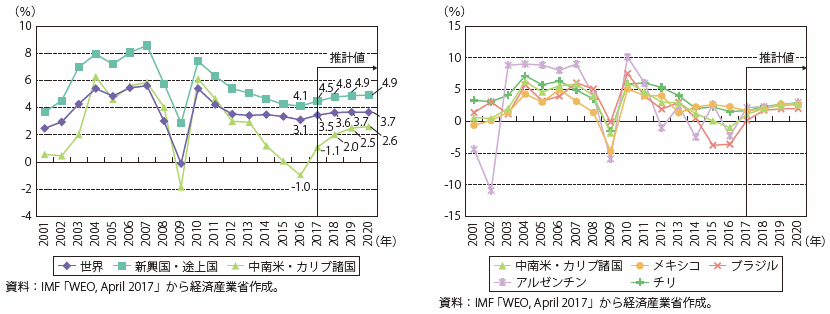
第Ⅰ-4-2-1-2表 中南米主要国の経済・貿易指標の比較
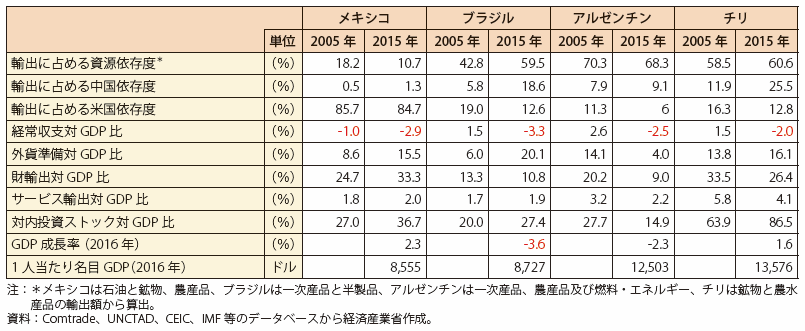
第Ⅰ-4-2-1-3図 中南米主要国の財輸出額、サービス輸出額、対内直接投資額の伸び率の比較
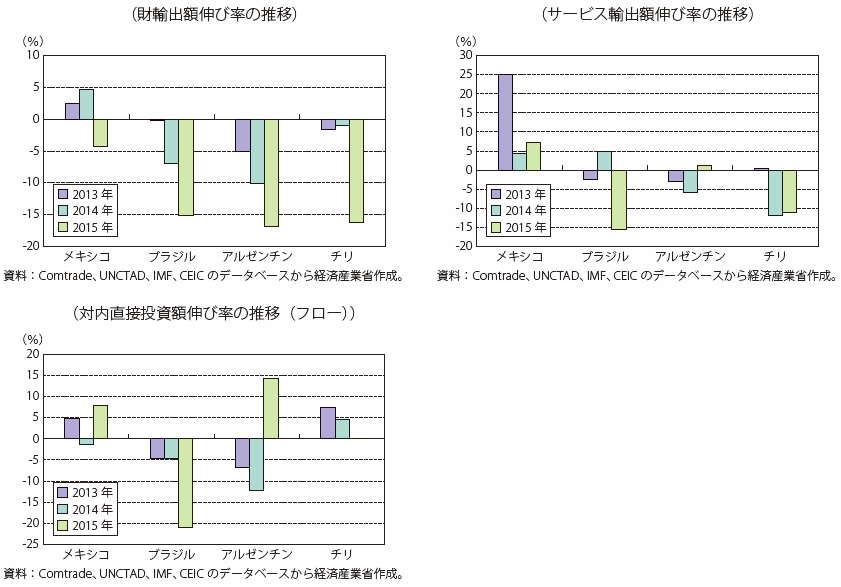
以下では、中南米地域の中で、経済的に影響力が強いメキシコとブラジルについて最近の経済の動向等について概観し、現状と課題について展望する。
2.メキシコ
(1)マクロ経済
①GDP
メキシコの実質GDPは、2016年は前年比+2.3%と2015年の同+2.6%から減速したが、3年連続で2%台の緩やかな成長を続けている。2017年に入り、通貨安を背景としたインフレが加速しており、メキシコ経済の牽引役である個人消費への影響が懸念される。また、米国の対メキシコ政策の先行きの不透明性も対内直接投資や国内の設備投資を抑制させるリスク要因となっている(第Ⅰ-4-2-2-1図)。メキシコ政府、メキシコ中央銀行(以下、中央銀行)及びIMFは、2017年のGDP成長率について、それぞれ1.5-2.5%、1.5-2.5%、1.7%と予測している187。
第Ⅰ-4-2-2-1図 メキシコの実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移
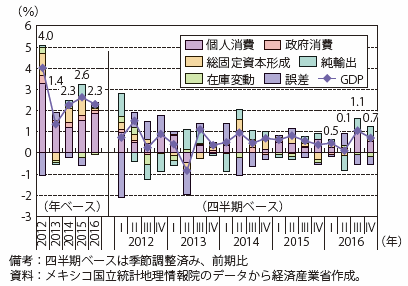
187 財務公債省(2017年5月22日)、中央銀行(同年5月31日)、IMF(同年4月18日)公表。
②生産、消費
鉱工業生産は全体として横ばいで推移している。製造業は堅調であるが、鉱物採取の低下が続いている。消費については、小売売上高は堅調に推移していたが、好調だった自動車の売上げの伸びが足下で失速している(第Ⅰ-4-2-2-2図)(第Ⅰ-4-2-2-3図)。
第Ⅰ-4-2-2-2図 メキシコの鉱工業生産指数の推移
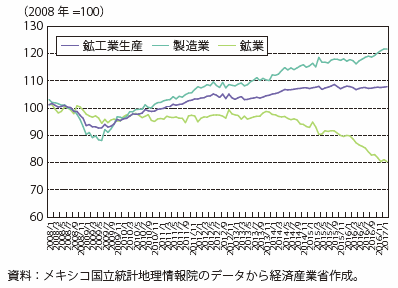
第Ⅰ-4-2-2-3図 メキシコの小売売上高の伸び率の推移
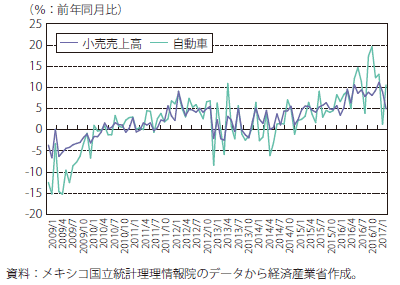
③物価、為替、政策金利
メキシコの消費者物価指数は、2016年10月にメキシコ中央銀行が定めるインフレ目標値(3%±1%)を約1年半ぶりに超えて以来加速を続けており、2017年4月には前年同月比5.8%と目標値上限の4%を大きく超えて推移している。メキシコは産油国でありながら精製設備の不足から、ガソリンを輸入に頼っており、政府のガソリン低価格政策見直しによる価格引上げが、最近の物価上昇に影響している(第Ⅰ-4-2-2-4図)。
第Ⅰ-4-2-2-4図 メキシコの消費者物価と政策金利の推移
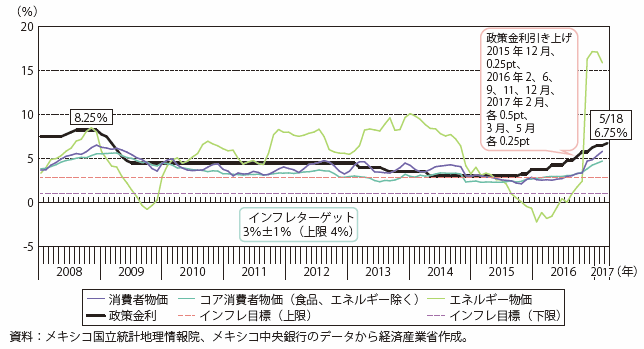
また、米国のトランプ新政権の強硬な通商・移民政策がメキシコ経済に与える影響への懸念から、通貨ペソは2017年1月に過去最安値を更新したが188、同年2月の先物取引を利用した通貨介入政策「為替ヘッジ・プログラム」導入や米国との通商交渉が順調に進むとの期待感から上昇に転じている。メキシコペソは、新興国の中でも取引量の多さと流動性の高さから投機的資金の出入りが大きく、ボラティリティが拡大しやすい通貨であると言われている(第Ⅰ-4-2-2-5図)(第Ⅰ-4-2-2-6図)。
第Ⅰ-4-2-2-5図 メキシコペソの為替レートの推移
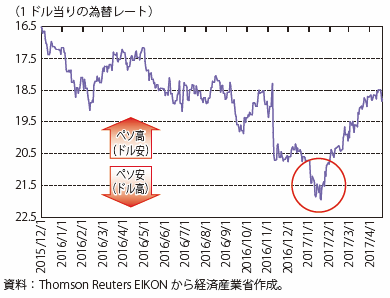
第Ⅰ-4-2-2-6図 新興国通貨の為替取引高の比較
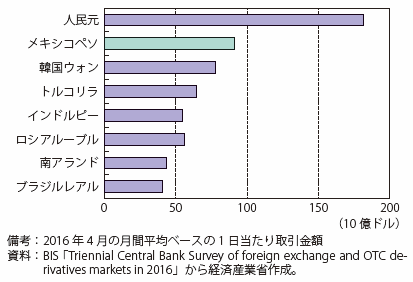
中央銀行は、インフレへの対応と通貨防衛のため、2015年12月の米国の利上げに追随し政策金利を引き上げて以来、2017年5月までに計9回の利上げを実施し、年6.75%となっている。今後も追加的な引き上げが必要となれば、減速している国内経済を一層停滞させる懸念があるため、注意が必要である。
188 2017年1月11日に1ドル=21.8275ペソ(ロイター通信による)。
(2)貿易、投資、国際収支
①貿易
1982年のメキシコ債務危機当時は、メキシコの輸出総額の7割以上を石油が占めていたが、1980年代後半から進められた輸出志向の工業化や90年代の北米自由協定(NAFTA)締結を契機に、メキシコは米州向け輸出・加工拠点として発展を遂げた。2016年には、メキシコの輸出に占める工業製品の割合が8割強に増加した一方、石油の割合は約5%まで低下した。また、メキシコの輸出依存度は2016年で35.7%と中南米諸国の中では高い水準となっている(第Ⅰ-4-2-2-7図)(第Ⅰ-4-2-2-8図)。
第Ⅰ-4-2-2-7図 メキシコの輸出額の品目別構成
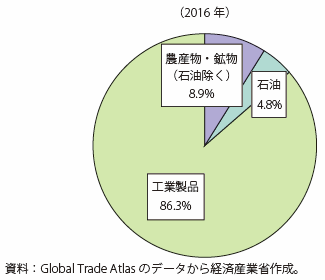
第Ⅰ-4-2-2-8図 中南米主要国の輸出依存度の比較
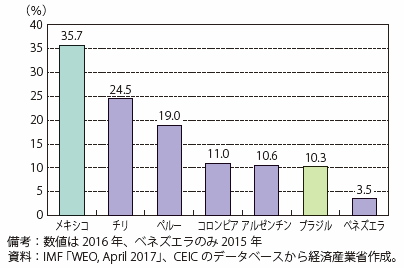
2016年のメキシコの貿易収支は、輸出が3,739億ドル(前年比-1.7%)、輸入が3,871億ドル(同-2.1%)と輸出入ともに減少し、貿易収支は131億ドル(同-10.6%)の赤字だった(第Ⅰ-4-2-2-9図)。
第Ⅰ-4-2-2-9図 メキシコの貿易収支の推移
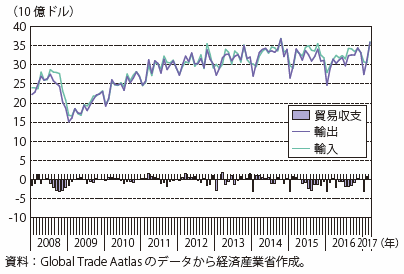
メキシコの主な輸出品は、自動車・同部品、電気機器、一般機械、鉱物性燃料(原油)、輸入品は、電気機器、一般機械、自動車・同部品、鉱物性燃料(ガソリン)となっている(第Ⅰ-4-2-2-10図)(第Ⅰ-4-2-2-11図)。また、2016年の財別の輸入構成比をみると、中間財76.2%、資本財10.4%、消費財10.4%となっており、中間財や資本財を海外から輸入して、国内で加工・組立を行い、最終財を海外に輸出するという貿易形態を取っている(第Ⅰ-4-2-2-12図)。
第Ⅰ-4-2-2-10図 メキシコの主要輸出品目の割合と輸出額の伸び率の推移
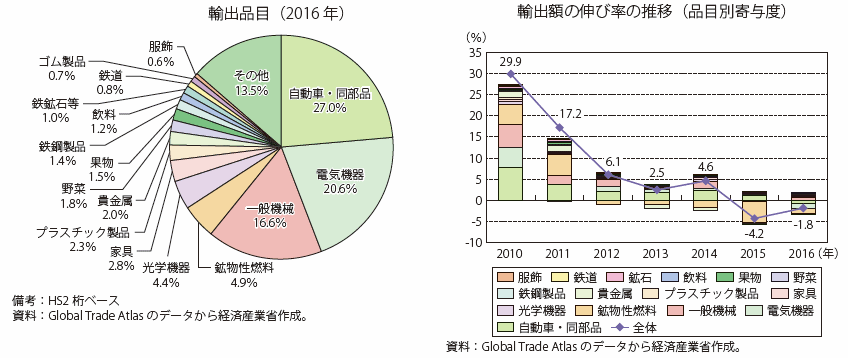
第Ⅰ-4-2-2-11図 メキシコの主要輸入品目の割合と輸入額の伸び率の推移
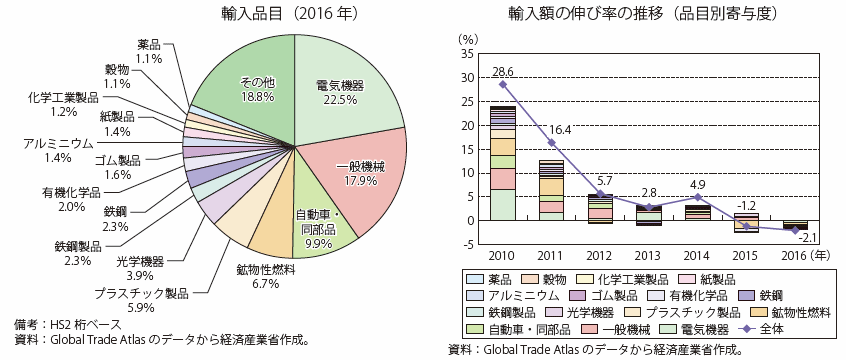
第Ⅰ-4-2-2-12図 メキシコの輸出入額の財別割合
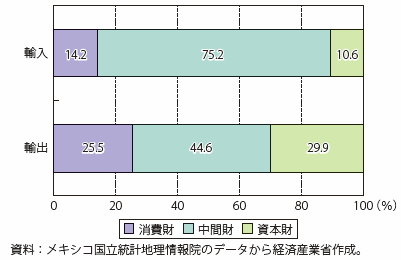
メキシコの主な貿易相手国は米国で、米国への輸出依存度は2016年で約80.9%、輸入依存度も47.3%と極めて高い。対米国の貿易黒字額は拡大している(第Ⅰ-4-2-2-13図)(第Ⅰ-4-2-2-14図)(第Ⅰ-4-2-2-15図)。
第Ⅰ-4-2-2-13図 メキシコの主要輸出相手国の割合と輸出額の推移
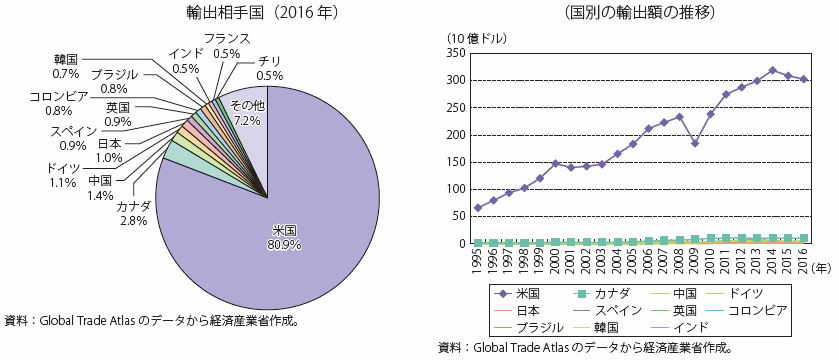
第Ⅰ-4-2-2-14図 メキシコの主要輸入相手国の割合と輸入額の推移
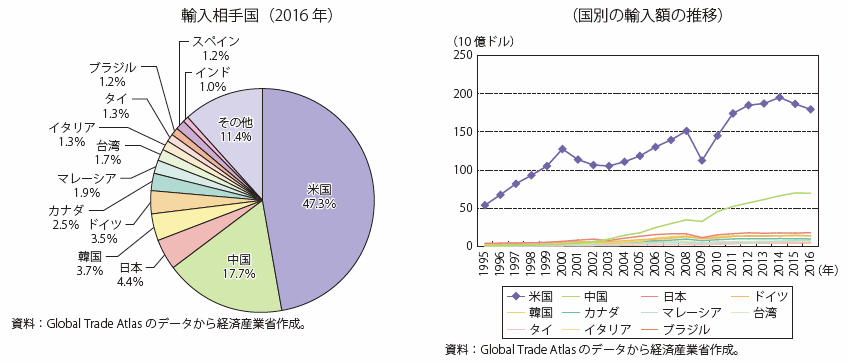
第Ⅰ-4-2-2-15図 メキシコの対米国の貿易収支の推移
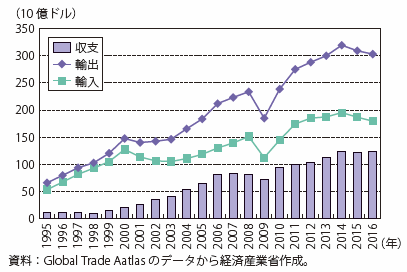
一方、米国にとってもメキシコは、中国、カナダに次ぐ第3位の輸入相手国であり、対メキシコの輸入比率は2016年13.4%で増加傾向にある(第Ⅰ-4-2-2-16図)。メキシコから米国向けの主要な輸出品は、乗用車、自動車部品、トラック、コンピュータ、テレビ、輸入品は、石油(原油除く)、自動車部品、石油ガス、ディーゼルエンジン、乗用車となっている(第Ⅰ-4-2-2-19図)。輸出入双方の上位品目に乗用車及び自動車部品が含まれており、米国とメキシコの間に、自動車産業を中心とするサプライチェーンが構築されていることを示している。なお、米国国際貿易委員会(USITC)によると、米国がメキシコから自動車及び同部品を輸入する際のNAFTA利用率は2016年が93.2%、NAFTA利用額は約701億ドルに上っている(第Ⅰ-4-2-2-17表)(第Ⅰ-4-2-2-18表)。
第Ⅰ-4-2-2-16図 米国の主要輸入相手国の割合と輸入額の推移
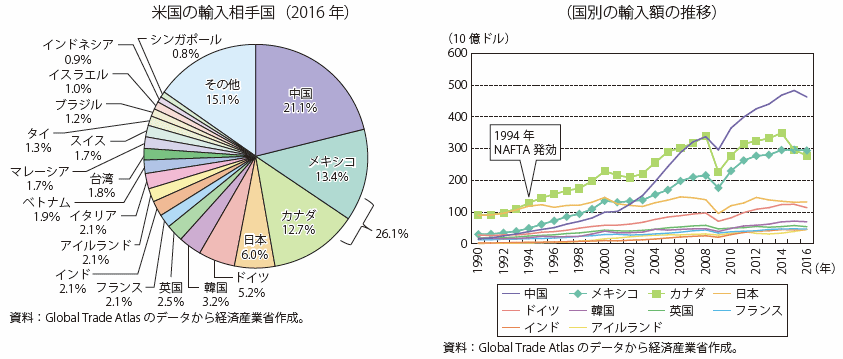
第Ⅰ-4-2-2-17表 米国のメキシコ輸入品のNAFTA利用率
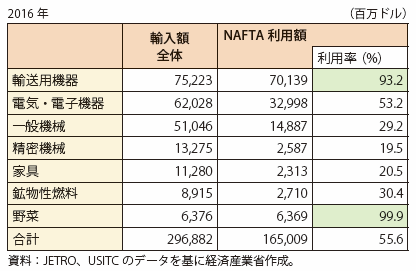
第Ⅰ-4-2-2-18表 NAFTAの自動車関連の原産地規則と各国の最恵国税率
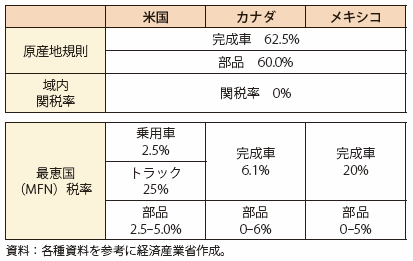
第Ⅰ-4-2-2-19図 NAFTA域内(メキシコ、米国、カナダ)の貿易関係(2016年)
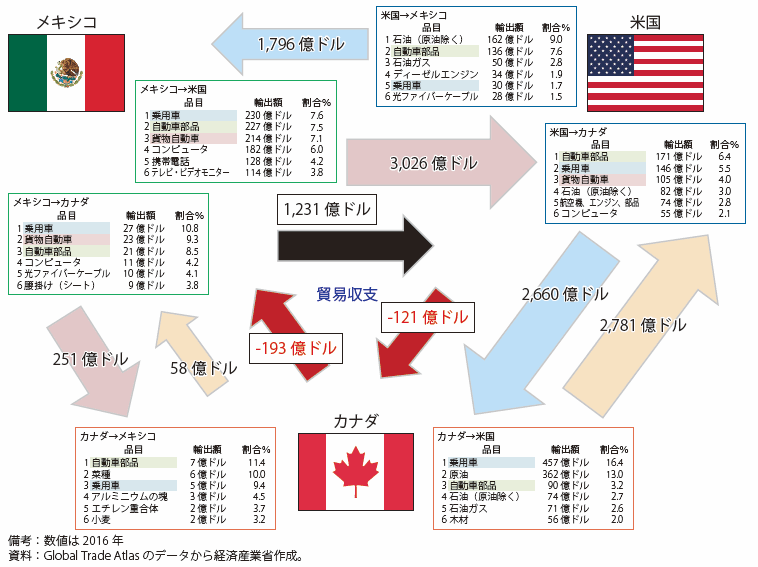
②海外直接投資
2016年のメキシコへの対内直接投資額は約267億ドル(前年比-5.8%)で、米国からの投資が約104億ドルと全体の約4割を占め、次いでスペイン、ドイツ、イスラエル、カナダ、日本189からとなっている(第Ⅰ-4-2-2-20図)。2015年時点のメキシコへの日系進出企業数は957社(第13位)となっている190。
第Ⅰ-4-2-2-20図 メキシコへの対内直接投資額の推移
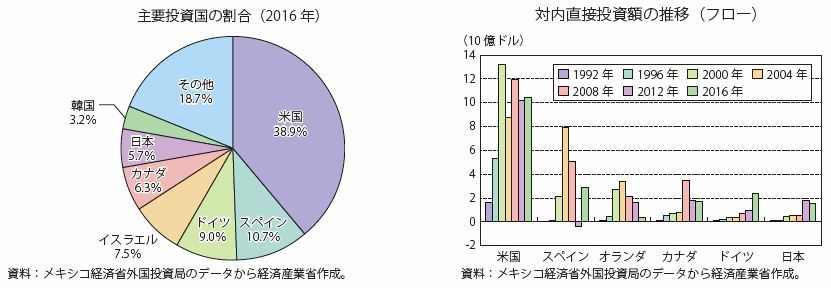
業種別では、製造業が全体の約6割を占め、外国企業がメキシコを米州における製造業の加工・輸出拠点として積極的に活用している様子が伺える。製造業以外では、運輸、金融・保険、情報、商業が続く(第Ⅰ-4-2-2-21図)。2015年は自動車関連の投資が活発に続いている他(第Ⅰ-4-2-2-22図)、金属包装や飲料、航空機等の分野で大型の投資案件がみられた。エネルギー改革の一環としてメキシコ石油公社(PEMEX)が独占してきた基礎石油化学や製油部門への民間企業の参入が認められたほか、油田鉱区の開発・生産事業の入札も開始されており、更なる外国資本の流入が期待される191。
第Ⅰ-4-2-2-21図 メキシコへの対内直接投資額の業種別の割合
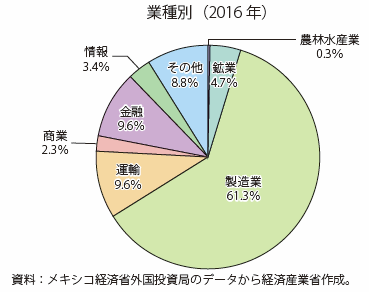
第Ⅰ-4-2-2-22図 メキシコの輸送機器部門への対内直接投資額の推移(フロー)
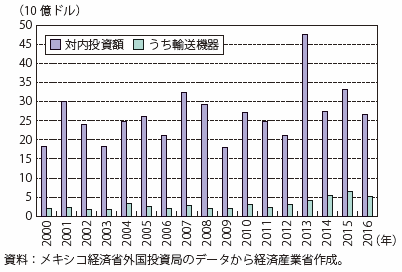
189 JETROによると、日本のメキシコ向け投資の多くは在米現地法人を介して行われ、メキシコの統計上、米国側に計上されるものも多いことから、実際の日本からの投資額は統計の約2倍以上となる。また近年中国からの投資も増加しているが、租税回避地等の第三国を経由した投資については、本統計では捕捉されていない。
190 外務省「海外在留邦人数統計調査 平成28年」
191 2013年12月エネルギー改革に向けた憲法の部分改正(エネルギー改革法)が、ペニャ・ニエト大統領により公布され、メキシコ国営石油公社(PEMEX)が独占してきたメキシコでの石油開発事業への外資企業の参入機会が開かれた。原油埋蔵量が最も期待される深海油田の入札が2016年12月に実施され、日本の石油企業や商社も権益を獲得した。
③国際収支
メキシコの経常収支は、慢性的な赤字状態でやや拡大傾向にあり、2016年は対GDP比-2.6%となった(第Ⅰ-4-2-2-23図)。米国等への出稼ぎ労働者からの送金により、第二次所得収支は黒字が続いており、2016年の在米国メキシコ人からの送金額は、過去最高の約270億ドルで全送金額の95%を占め、メキシコのGDPの2%に相当する規模で、自動車産業輸出に次ぐメキシコの外貨獲得手段となっており、中低所得層の重要な現金収入源となっている(第Ⅰ-4-2-2-24図)。
第Ⅰ-4-2-2-23図 メキシコの経常収支の推移(対GDP比と構成)
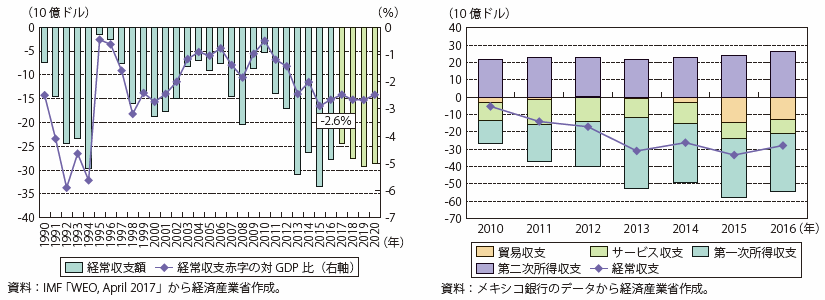
第Ⅰ-4-2-2-24図 メキシコへの海外送金額の推移
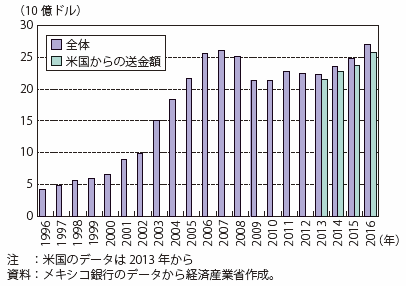
メキシコは、これまで経常収支の赤字を海外からの資金流入で補ってきているが(第Ⅰ-4-2-2-25図)、米新政権のメキシコに対する強硬な通商・移民政策は、為替リスク増大とともに、好調を続けてきたメキシコ向け直接投資や証券投資への影響が懸念される。近年、加速していた日本や欧米自動車メーカー等のグローバル企業のメキシコへ向け投資についても、新規進出や生産拡大計画等について、今後の米国の政策の動向を伺い慎重な姿勢に向かう可能性がある。
第Ⅰ-4-2-2-25図 メキシコの金融収支の推移
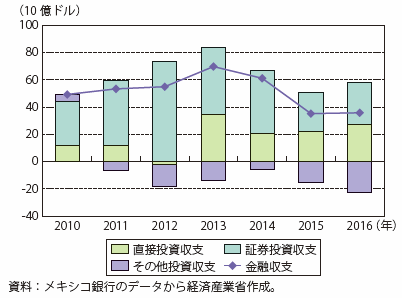
2015年の外貨準備高(ストック)の水準について見てみると、短期対外債務の2.5倍(2.5年分相当)とIMFが保有外貨準備の目安とする1倍以上を上回っていることから、直ちに金融危機を発生させる可能性は、現時点では低いと言える(第Ⅰ-4-2-2-26図)。
第Ⅰ-4-2-2-26図 メキシコの対外債務残高と外貨準備高の推移
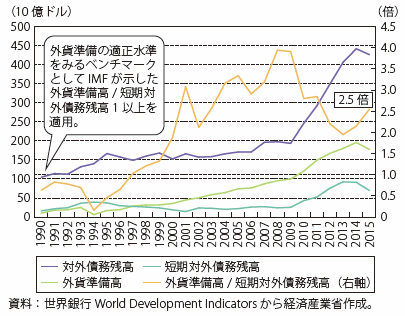
(3)産業、財政
①産業
メキシコは多岐にわたる産業が発達しているが、労働や生産コストの低さを強みとして、自動車産業、電気・電子産業、航空宇宙産業等の製造業が発展しており、広範なFTAネットワーク192を活用した輸出が活発である。産業別にみると、第二次産業(鉱業、電気・ガス・水道、建設、製造業)の全産業のGDPに占める割合は、2016年で32.5%と縮小傾向にあり、中でも原油生産量の減少に伴い鉱業は6.2%に低下している。製造業については16.8%とほぼ横ばいで推移しているが、自動車産業(輸送機器)については3.2%と堅調な伸びをみせている(第Ⅰ-4-2-2-27表)。
第Ⅰ-4-2-2-27表 メキシコの産業部門のGDP構成比の推移
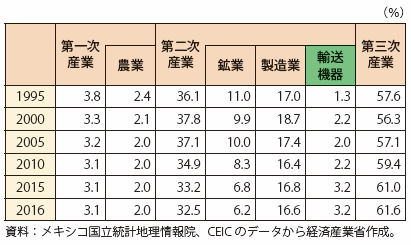
192 米州ではチリに次いで多い世界46カ国(EU28カ国含む)とFTA(自由貿易協定)を締結。(2017年4月現在)
(メキシコの自動車産業)
メキシコの自動車生産台数は、2014年にブラジルを上回り世界第7位となり、その後も拡大を続けている(第Ⅰ-4-2-2-28表)。メキシコの自動車産業は、主要市場(北米、南米、欧州等)へのアクセスの良さや、自動車部品メーカーの産業集積、整備された物流網、低廉で豊富な労働力、さらにはNAFTAを始めとする世界各国・地域との自由貿易協定のネットワークの積極的な活用により、米州地域における生産・輸出拠点としての優位性を有している。近年は、新興国の自動車市場の拡大もあり、メキシコを米州における中小型車の生産・輸出拠点として位置付ける海外自動車・部品メーカーの進出や、生産能力増強の動きが活発化している。小型車は利幅が小さく生産コストの抑制が競争力を左右することから、中国等、新興国の労働者の賃金が上昇する中、労働コストが低廉で安定しているメキシコの優位性が増している193(第Ⅰ-4-2-2-29図)。
第Ⅰ-4-2-2-28表 各国の自動車生産台数の推移
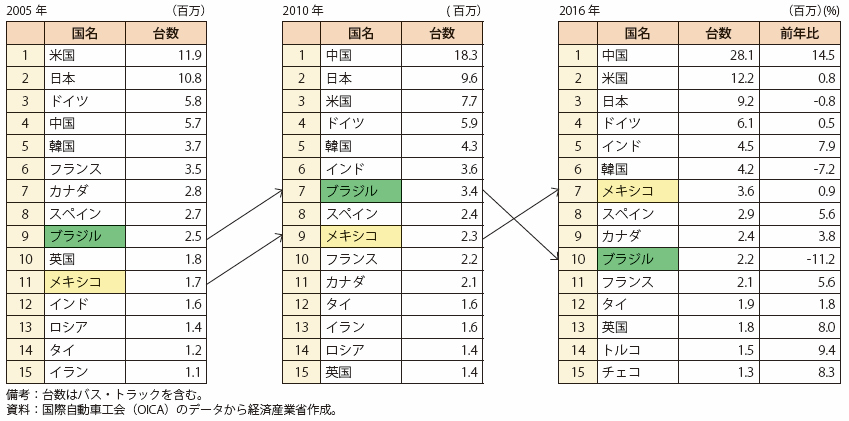
第Ⅰ-4-2-2-29図 一般工職の月額賃金の比較
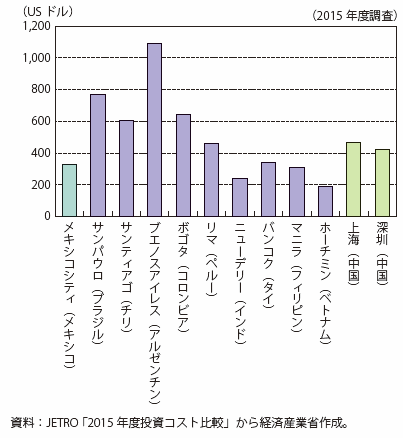
193 自動車や家電等の労働組合が一般的に穏健であることも利点と考えられている。
(メキシコの自動車生産・販売・輸出)
メキシコ自動車工業会(AMIA)によると、メキシコの2016年の自動車生産台数(バス・トラックを除く)は約346万台(前年比+2.0%)、輸出台数は約277万台(前年比+0.3%)と、ともに7年連続で過去最高を更新した(第Ⅰ-4-2-2-30図)。全生産に占める輸出の割合は約8割(79.9%)で、輸出先は米国が約213万台(前年比+7.1%)、以下カナダが約24万台(同-15.2%)、ドイツが約7万台(同-15.2%)となっており、輸出台数に占める米国向け比率は77.1%、カナダが8.9%、二国の合計で86%と北米市場への依存度が極端に高い(第Ⅰ-4-2-2-31図)。また、米国市場における原産国別の販売比率をみると、2007年に7.5%だったメキシコ製が2016年に12.2%まで上昇し、日本製は12.9%から9.3%に低下している(第Ⅰ-4-2-2-32図)。
第Ⅰ-4-2-2-30図 メキシコの自動車の生産・輸出・販売台数の推移
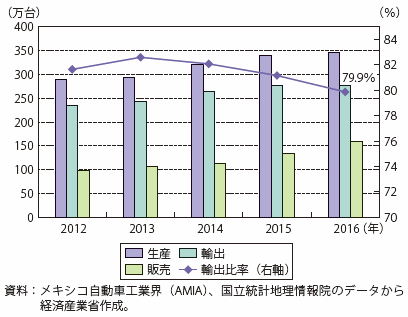
第Ⅰ-4-2-2-31図 自動車の輸出相手国の割合
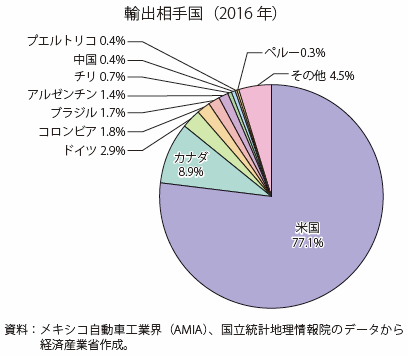
第Ⅰ-4-2-2-32図 米国市場の原産国別自動車販売の比率
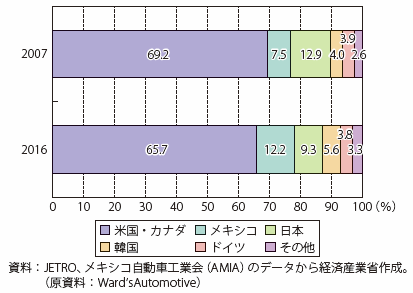
メキシコに進出している海外完成車メーカーは、2016年末時点で合計10社で、国籍別メーカーの生産台数は、米国系メーカーが155万台(シェア45%)、日系メーカーが約139万台(同40%)、欧州系が41万台(同12%)、韓国系が10万台(同3%)となっている(第Ⅰ-4-2-2-33図)。
第Ⅰ-4-2-2-33図 メキシコの国籍別完成車メーカーの生産・輸出・販売台数の比較
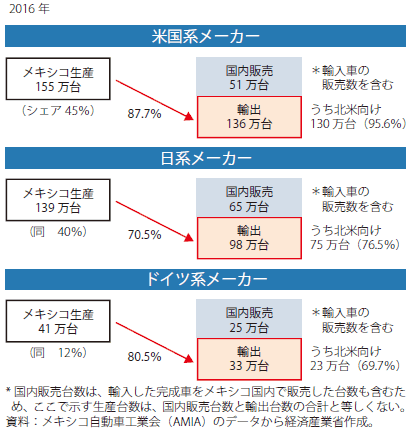
(自動車部品産業)
メキシコ国内では、自動車部品サプライヤーの集積も進んでおり、輸出額も拡大している(第Ⅰ-4-2-2-34図)。2016年、メキシコの自動車部品輸出額の約9割が米国向けとなっており(第Ⅰ-4-2-2-35図)、米国から見てもメキシコは自動車部品輸入額の約3割強を占める輸入先として存在感を強めている(第Ⅰ-4-2-2-36図)。現在、米国がメキシコから輸入する自動車部品の多くは、米国原産の構成部品をメキシコ内で加工したものとなっており、米墨間では国境を越えた自動車産業の分業体制が確立されており、両国の相互の依存度は極めて高い(第Ⅰ-4-2-2-37図)。
第Ⅰ-4-2-2-34図 メキシコの自動車部品の輸出入額の推移
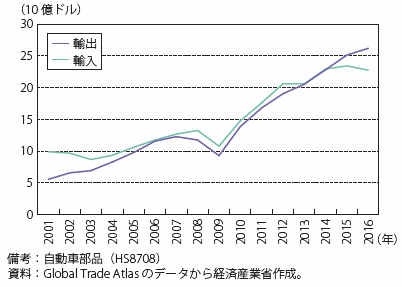
第Ⅰ-4-2-2-35図 メキシコの自動車部品の主要輸出相手国・輸入相手国の割合
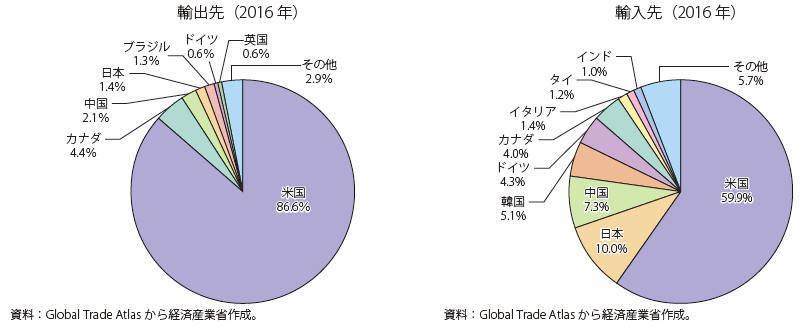
第Ⅰ-4-2-2-36図 米国の自動車部品の輸出相手国の割合と推移
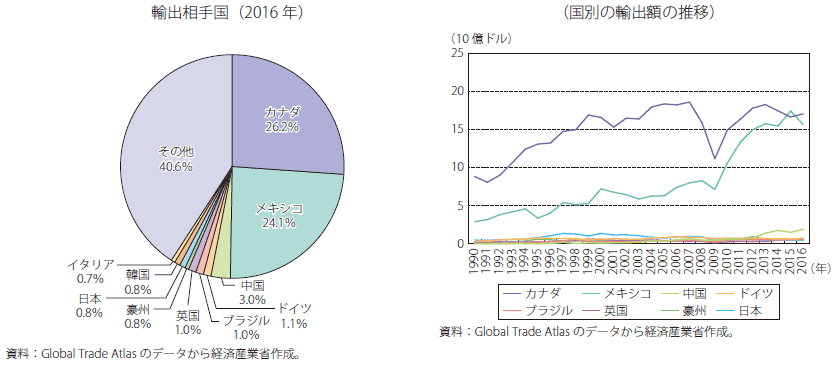
第Ⅰ-4-2-2-37図 米国の自動車部品輸入相手国の割合と推移
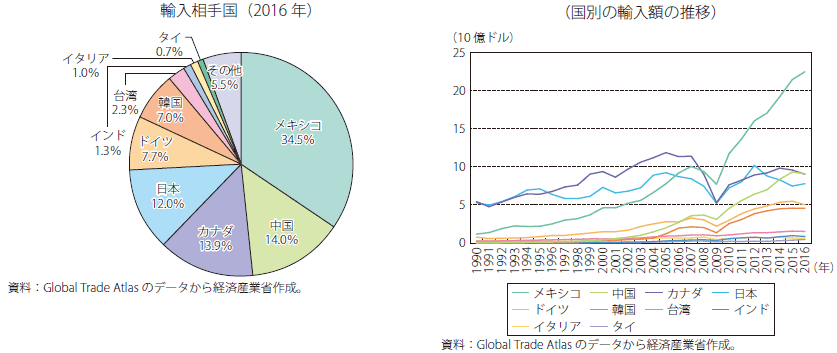
②財政
メキシコ政府は、過去の債務危機や経済危機からの経験から、財政やマクロ経済運営に対する投資家の信頼を確保し、海外直接投資の流入やそれに伴う正規雇用の創出を維持するため、財政規律を重視している。2006年、財政収支の均衡を義務づける財政責任法が施行されて以降、原則、財政赤字を容認しない予算編成が定められている(第Ⅰ-4-2-2-38図)。かつては国家歳入の多くを石油収入に依存し、2008年にはその割合が歳入の45.6%にまで達していたが、その後生産量減少や石油価格下落により、2016年には8.5%まで低下している(第Ⅰ-4-2-2-39図)(第Ⅰ-4-2-2-40図)。経済成長が減速傾向にある中にあっても、政府は財政規律の維持を優先し歳出削減に努めており、増税等による税収基盤の強化により石油関連以外の税収による財源の確保に努めている194。
第Ⅰ-4-2-2-38図 メキシコの財政収支の推移
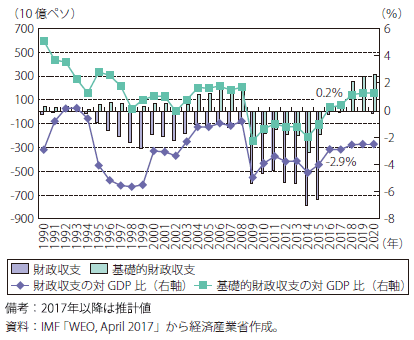
第Ⅰ-4-2-2-39図 メキシコの原油生産量の推移
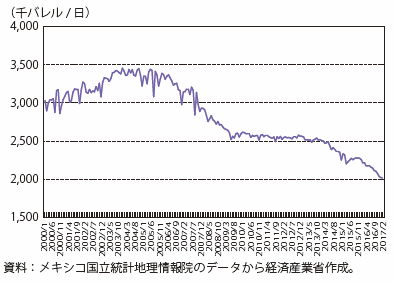
第Ⅰ-4-2-2-40図 メキシコの歳入に占める石油関連収入の割合
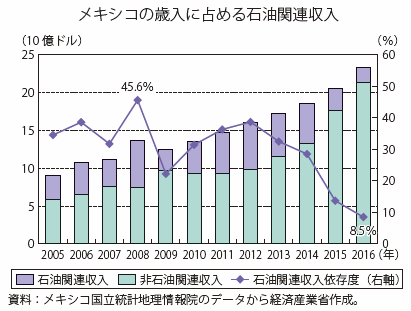
世界経済危機後の2009年、景気後退による歳入減少と景気対策向けの歳出増加により財政赤字は対GDP比で-5.1%に増大したが、2016年には同-2.9%に改善している。政府総債務残高については、2016年で対GDP比58.1%と他の新興国等と比べ低い水準にはあるものの、増加傾向にあることが懸念される(第Ⅰ-4-2-2-41図)。
第Ⅰ-4-2-2-41図 メキシコの政府総債務残高
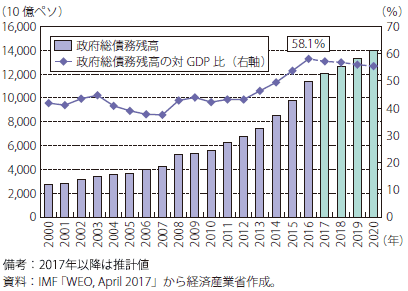
194 財務公債省のデータによると2016年の連邦政府の税収の内訳は、所得税が53%、付加価値税が29%、物品税(ガソリン等)が15%、法人税-0.2%、関税2%となっている。
(4)メキシコ経済のリスク要因
以上、最近のメキシコ経済の動向を見てきたが、米国経済の堅調な拡大により、輸出の増加が期待できるものの、メキシコの経済成長を押し下げるリスク要因として、米国の対メキシコ政策の先行きの不透明性、それに伴うペソ安進行とインフレ率の上昇、金利引き上げによる消費・投資マインドの低下、原油生産量の減少と今後の価格動向、政情不安等による構造改革の実行の遅れ等が挙げられる。
3.ブラジル
(1)マクロ経済
①GDP
2016年のブラジルの実質GDP成長率は-3.6%と、2015年の-3.8%から2年連続してマイナス成長となった。内需(消費、投資)の低迷、高インフレ、高失業率、高金利等により景気停滞が長期化していたが、一次産品価格の持直しや政治混乱の収束、インフレ率の低下等、好転の兆しが見られている(第Ⅰ-4-2-3-1図)。しかし一方で、失業率の悪化は続いており、商品価格の先行きにも不透明感があることから、本格的な回復には、更に時間を要すると思われる。
第Ⅰ-4-2-3-1図 実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移
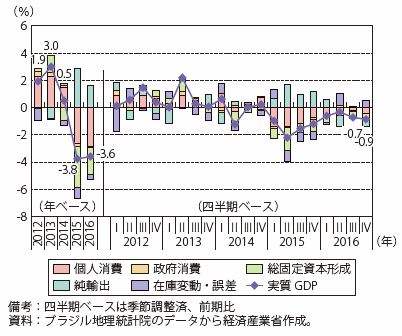
2017年の成長率については、ブラジル政府(財務省)が+1.0%、ブラジル中央銀行(以下、中央銀行)が発表した民間予測が+0.5%、IMFが+0.2%と、プラス成長に転じると予測しているが、回復のペースは緩やかなものとなるとしている195。
195 ブラジル銀行が週次で発表しているエコノミスト等への調査に基づくGDP成長率予測に関し、1月27日時点で2017年のGDP成長率を0.5%、2018年のGDP成長率を2.20%としている。
②生産、消費
鉱工業生産は低迷を続けているが、鉱物採取に回復の兆しがみられる。消費は低迷を続けており、小売売上高の伸び率は長期にわたり減速している(第Ⅰ-4-2-3-2図)(第Ⅰ-4-2-3-3図)。
第Ⅰ-4-2-3-2図 ブラジルの鉱工業生産の推移
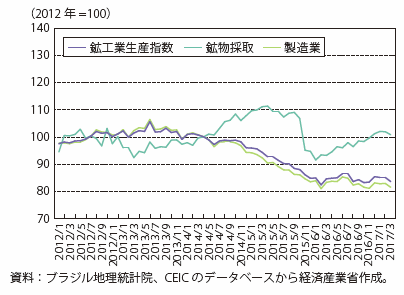
第Ⅰ-4-2-3-3図 ブラジルの小売売上高の伸び率の推移
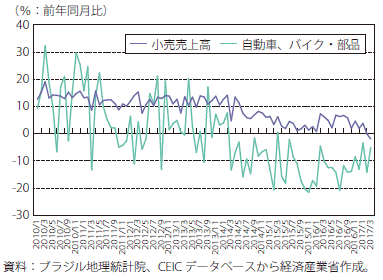
③物価、政策金利、為替
ブラジルの消費者物価指数(IPCA)は、公共料金引き上げの影響の緩和や、通貨レアル高による輸入物価上昇の抑制と国内消費の減退等により伸び率が鈍化し、2016年(通年)は前年比+6.29%と、インフレ目標値(4.5±2%)の上限値6.5%を下回った。さらに2017年3月は、7か月連続で前月を下回り推移し、同+4.6%と上記目標値の4.5%に近づいた。ブラジル中央銀行は、2017年4月、政策金利である基準金利を1%引き下げ、年11.25%とした。利下げは5会合連続で、インフレの抑制が想定通りに進んでいることから、今後も緩和のペースを加速するものとみられ、企業の設備投資の増加が期待される(第Ⅰ-4-2-3-4図)。
第Ⅰ-4-2-3-4図 ブラジルの消費者物価と政策金利の推移
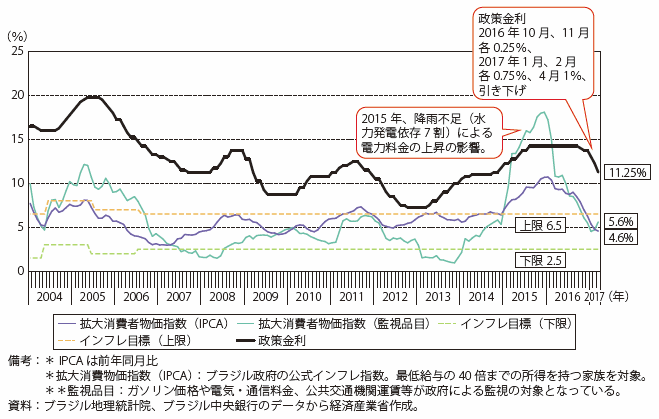
ブラジル通貨レアルは、原油安の長期化や政治的混乱を背景に2014年以来下落していたが、テメル政権の構造改革実現への期待や原油価格の上昇等により、年明け以降、持ち直しがみられた。レアルは2016年11月の米国大統領選挙後1ドルあたり3.5レアル近くまで下落したが、足下では3.0レアル台まで上昇している(第Ⅰ-4-2-3-5図)。
第Ⅰ-4-2-3-5図 ブラジルレアルの為替レートの推移
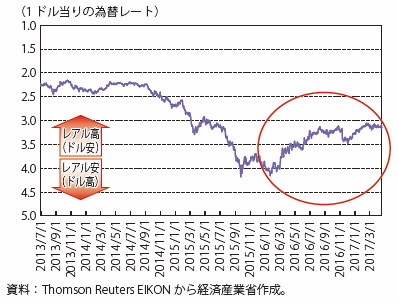
昨年末以来、米国が拡張的な財政政策を実施するとの観測から米国金利の先高観が高まったが、米国の利上げが想定以上のペースで加速すれば、資金流出圧力が高まり、レアル安が起こる可能性もある。レアル安となれば、インフレ低下のペースが遅れ、更に金融緩和基調が弱まることになれば、景気回復を遅らせる要因となる可能性もあることから、注意が必要である。
④雇用、所得
ブラジルの失業率は、17年4月末時点で13.7%と雇用状況の悪化が続いている。企業は雇用拡大に慎重な姿勢を示しており、回復には時間が要するとの見方が強い。失業率の上昇に加え、インフレによる実質所得の減少や債務負担の増大から家計の購買力は低下していたが、足下の実質所得の伸び率は16年12月以降プラスに転じている(第Ⅰ-4-2-3-6図)。
第Ⅰ-4-2-3-6図 ブラジルの失業率と実質所得の伸び率の推移
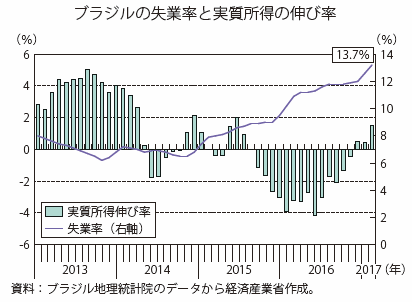
(2)貿易、投資、国際収支
①貿易
2016年のブラジルの貿易は、輸出が1,852億ドル(前年比-3.1%)、輸入が1,375億ドル(同-19.8%)、貿易収支の黒字は477億ドルと過去最高を記録した(第Ⅰ-4-2-3-7図)。
第Ⅰ-4-2-3-7図 ブラジルの貿易収支の推移
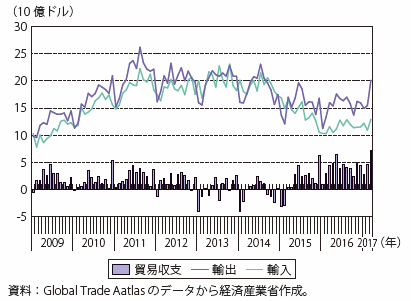
ブラジルは、大豆、砂糖、コーヒー、食肉等の農産品や鉄鉱石、鉱物性燃料等の鉱物資源等の一次産品が主要な輸出品目で、全輸出額の5割弱を占める一方で、航空機、自動車・同部品等の工業製品も4割弱を占めている。また、原油の産出・輸出国であるが、ガソリン等の石油製品や原油も輸入している(第Ⅰ-4-2-3-8図)。
第Ⅰ-4-2-3-8図 ブラジルの主要輸出品目と主要輸入品目の割合
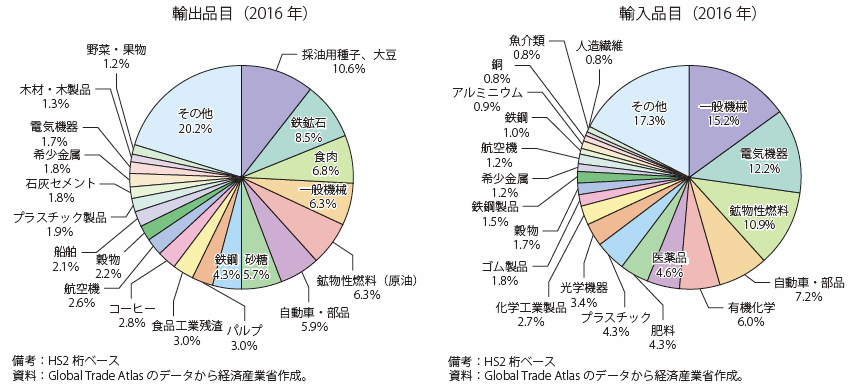
ブラジルにとり、中国及び米国が主要な貿易相手国となっている。輸出については、2016年の全輸出額の19.0%が中国向けで、主に大豆や鉄鉱石、肉類等の一次産品を、次いで12.5%が米国向けで、主に一般機械、航空機、鉄鋼等を輸出している(第Ⅰ-4-2-3-9図)。また、輸入については、同年の全輸入額の17.3%を米国から、主に一般機械、鉱物性燃料、プラスチック製品等を、次いで17.0%を中国から、主に電気機器、一般機械、有機化学品等を輸入している(第Ⅰ-4-2-3-10図)。2000年以降は輸出、輸入ともに米国の占める割合が低下する一方、中国の割合が増加し、中国に対する貿易依存度が高くなってきている。以上のことからブラジルは、一次産品価格の動向や中国及び米国経済の影響を受けやすい構造となっていると言える。
第Ⅰ-4-2-3-9図 ブラジルの主要輸出相手国の割合と推移
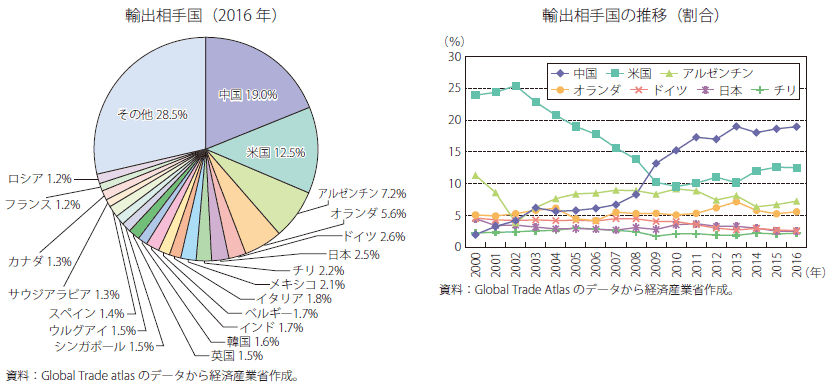
第Ⅰ-4-2-3-10図 ブラジルの主要輸入相手国の割合と推移
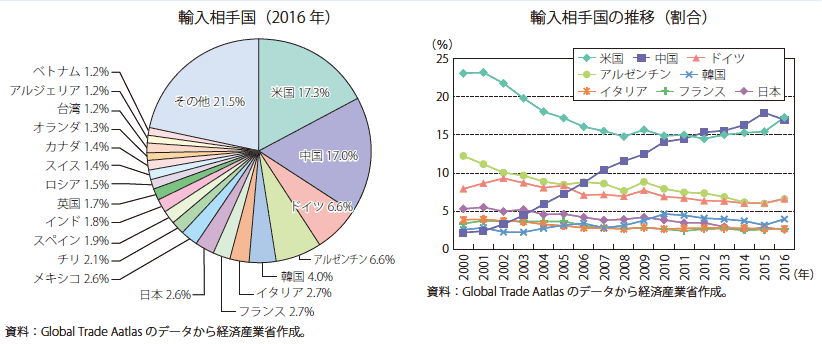
2016年のブラジルの輸出についてみると、一次産品の上位品目の大豆、鉄鉱石、原油、食肉、コーヒー等が減少したが、自動車や航空機等の工業製品が増加した(第Ⅰ-4-2-3-11図)米国の自動車市場が堅調だったことや、コロンビアとの間で無関税輸入枠を相互に設定したことが良い影響を与えたほか、中国国内の民間航空機の旅客輸送量の増加を背景とした航空機も増加した。2017年以降は、原油や鉄鉱石等の国際市況の回復や穀物生産量の増加により、輸出の伸びが期待されている(第Ⅰ-4-2-3-12図)。
第Ⅰ-4-2-3-11図 ブラジルの輸出額の伸び率の推移
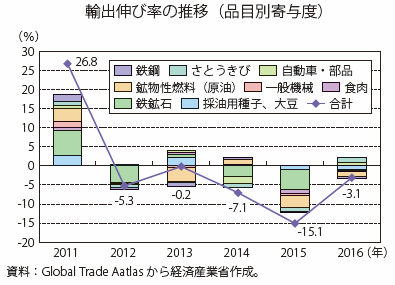
第Ⅰ-4-2-3-12図 商品先物指数の推移
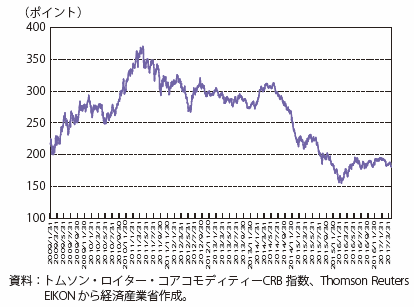
②海外直接投資
ブラジルでは、長期の経済停滞にかかわらず、中長期的な成長のポテンシャル等196から海外からの直接投資は堅調に推移してきたが量的拡大ペースには一服感が見られる(第Ⅰ-4-2-3-13図)。2015年時点のブラジルへの日系進出企業(拠点)数は705社(第17位)となっている197。
第Ⅰ-4-2-3-13図 ブラジルの対内直接投資額の推移(フロー)
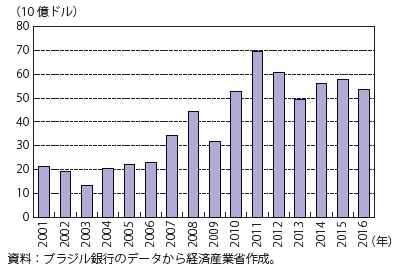
2016年のブラジルの対内直接投資額(フロー)は約530億ドル(前年比+3.2%)で、国・地域別で見る第3位の米国以外は、オランダ、ルクセンブルク、英国、スペイン等の欧州諸国が上位を占めている(第Ⅰ-4-2-3-14図)。中国については、日本に次いで第13位(8億8千万ドル)で198、近年、中国企業による電力等のインフラ部門への投資が積極的に行われている。対内投資の業種別割合は、サービス業が約6割、農業・畜産・鉱業が約14%、工業が約26%となっているが(第Ⅰ-4-2-3-14図)、2015年1月に外資系企業の医療分野への直接・間接的な資本参加が可能となったことから、今後は健康・医療分野への投資の伸びが見込まれる。
第Ⅰ-4-2-3-14図 ブラジルへの主要対内直接投資国と業種の割合
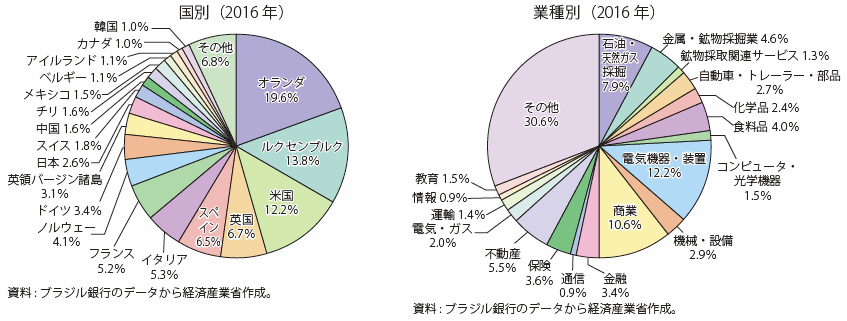
196 内需主導型経済、労働人口の増加、豊富な資源等。
197 外務省「海外在留邦人数統計調査 平成28年」
198 中国からの投資の多くが租税回避地域を回避して行われており、正確な数字が統計上に現れていない。
③国際収支
ブラジルの経常収支は2008年以降赤字が続いており、金融、通信、小売等の業種で外国企業のプレゼンスが大きいことから、第一次所得収支は流出超で恒常的に赤字となっている。また一次産品価格下落等の影響で、2014年は貿易収支が赤字に転じたが、価格の持ち直しにより15年には黒字に回復し、2016年の経常赤字は235億ドル(対名目GDP比-1.3%)と改善がみられている(第Ⅰ-4-2-3-15図)。
第Ⅰ-4-2-3-15図 ブラジルの経常収支の推移(対GDP比と構成)
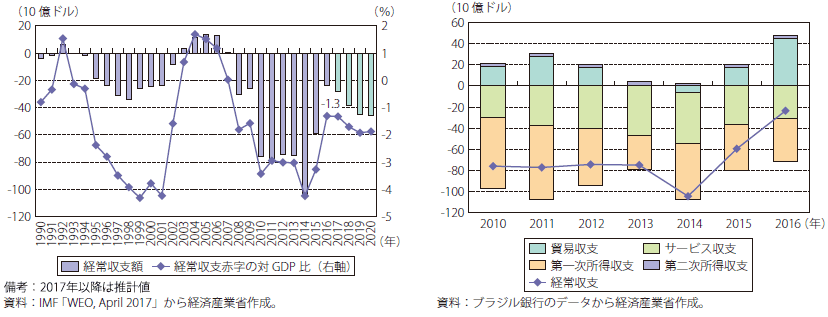
ブラジルの経常収支赤字は、ブラジル経済への信認を背景とした直接投資や証券投資による資本流入によりカバーされてきたが、2016年には証券投資がマイナスに転じており、今後の安定した外資繰りに懸念が生じている(第Ⅰ-4-2-3-16図)。
第Ⅰ-4-2-3-16図 ブラジルの金融収支の構成の推移
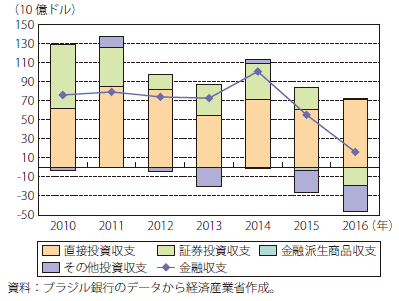
2015年の外貨準備高(ストック)の水準を見てみると、短期対外債務の6.8倍(6.8年分相当)とIMFが保有外貨準備の目安とする1倍以上を十分に上回っていることから、ブラジルの外部ショックへの耐性は高まっており、金融危機発生のリスクは低いといえる(第Ⅰ-4-2-3-17図)。
第Ⅰ-4-2-3-17図 ブラジルの対外債務残高と外貨準備高の推移
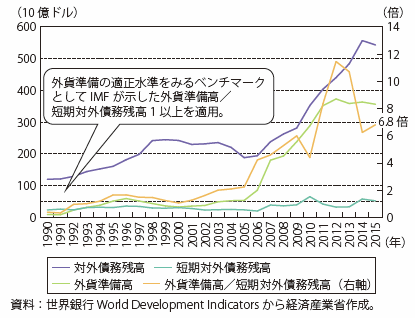
(3)構造改革
2016年8月末に発足したテメル政権は、経済再生と財政健全化に向けた構造改革を進めている。
a)歳出に上限を設定するための憲法改定
前政権下の低所得者層向けの社会保障支出拡大の政策は低所得者層の底上げには貢献したが、高水準のインフレや財政悪化を招く要因となった。2016年12月、テメル政権は「歳出上限設定の憲法改正案(歳出上限法)」を成立させた。歳出上限設定とは、連邦政府支出の増加率を前年の物価上昇率以下に抑えることを義務付けるもので2036年まで20年間続く。
(財政)
ブラジルでは、財政責任法に基づき、予算段階で各政府の基礎的財政収支に対する目標設定が義務づけられている。2016年の中央連邦政府の同収支の赤字幅については、目標を1,705億レアル(GDP比-2.75%)と設定し、16年(実績)は赤字額が1,558レアル(同-2.47%)となり目標を達成した(第Ⅰ-4-2-3-18図)。政府は、2020年に赤字解消を目指しているが、依然として政府債務残高の増大が懸念されている。(第Ⅰ-4-2-3-19図)。
第Ⅰ-4-2-3-18図 ブラジルの財政収支の推移
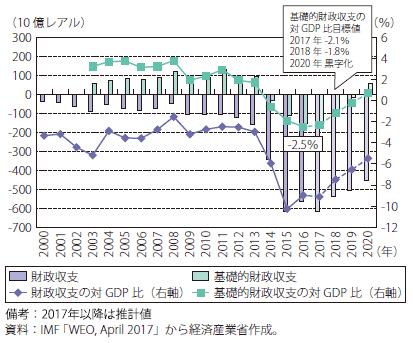
第Ⅰ-4-2-3-19図 ブラジルの政府総債務残高の推移
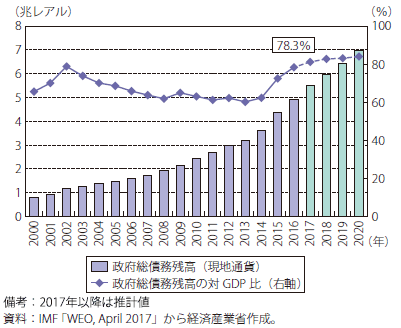
b) 年金改革のための憲法改定
ブラジルの年金財政は恒常的な赤字で、社会保障費が連邦政府の歳出額の4割199にのぼり、財政赤字拡大の要因となっている。政府は2016年12月、「年金改革に関する憲法改正案」を発表し、議会に特別委員会を設置し改革の内容についての議論を開始した。改正の内容は、年金受給年齢の引上げや保険料支払期間の厳格化、サラリーマンや公務員、農村部労働者に分かれた年金制度の統一、受給年齢の男女差解消等となっている。
199 ブラジル銀行によると2016年ブラジルの社会保障費は約537億レアルで歳出の約40.9%。
c)労働法改正
ブラジル進出外国企業の多くが、硬直的で労働者保護色の強いブラジルの労働法(統一労働法:1943年制定)の問題を指摘しているが、2016年12月、政府は同法の近代化を図るため改正案を国会に提出し、現在、審議が行われている。改正の内容は、労働協約の裁量の拡大・運用の柔軟化で、臨時雇用契約やパートタイム労働についても制限緩和の対象としている。
〈ブラジルのビジネス環境〉
ブラジル経済や産業の成長を妨げ、海外企業のブラジル進出を困難にしている要因として、複雑で高率な税制や極端に労働者保護に偏った労働法制、交通・インフラの未整備といった「ブラジルコスト」が知られている(第Ⅰ-4-2-3-20表)。以下ブラジルのビジネス環境についての外部評価の結果を紹介する。
第Ⅰ-4-2-3-20表 ブラジルコストの例
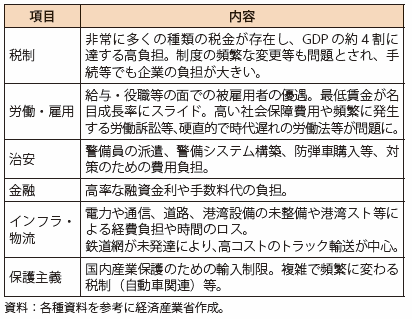
○ビジネス環境ランキング
世界銀行の「2017年ビジネス環境総合ランキング」によると、中南米では、メキシコ(47位)を首位に、コロンビア、ぺルー、チリの太平洋同盟の国々が50位台で続いているのに対し、メルコスールではアルゼンチン(116位)、ブラジル(123位)と低位に留まっている(第Ⅰ-4-2-3-21表)。
第Ⅰ-4-2-3-21表 世界銀行ビジネス環境総合ランキングの結果
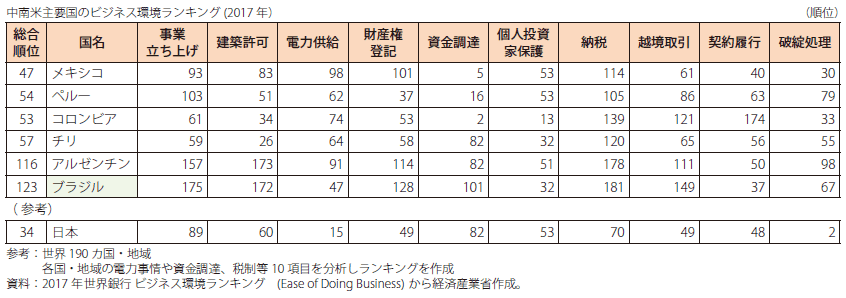
ブラジルのビジネス環境評価の下位の項目として、納税(181位)、事業立ち上げ(175位)、建築許可(172位)、越境取引(149位)、財産権登記(128位)、資金調達(101位)等が挙げられている。中でもブラジル特有の複雑で高率な税制が障害として度々指摘されてきており、同報告書によると、ブラジル国内の企業は納税の準備のために年間2,038時間も費やしており、中南米諸国の平均343時間、高所得国(OECD加盟国)の同163時間を大きく上回っている。また起業に要する手続数や日数等についても改善の必要性が指摘されている。
○進出日系企業調査
JETROの「2016年度中南米進出日系企業実態調査」によると、ブラジルにおける投資環境面のメリットとして「市場の規模や成長性」を挙げる企業が多い一方で、デメリットとして税務面等の様々なリスクを指摘する企業が多い。「税制・税務手続の煩雑さ」を挙げる企業が86.5%と最も多く、「人件費の高騰」、「不安定な為替」、「不安定な政治・社会情勢」、「労働争議・訴訟」、「行政手続の煩雑さ(許認可等)」が続いている(第Ⅰ-4-2-3-22図)。また、2000年代以降進出した企業のうち、初期投資が回収できた企業は14.3%に過ぎないことも、固有のコストの高さが影響しているものと考えられる。
第Ⅰ-4-2-3-22図 ブラジルの投資環境面のリスク調査結果
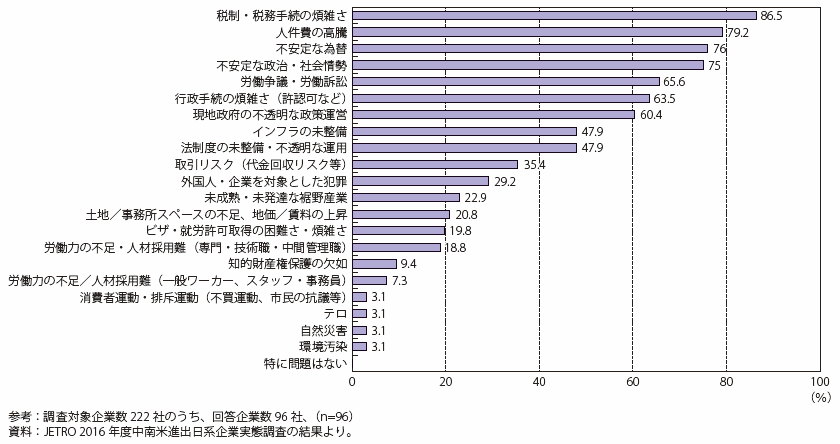
(4)ブラジル経済のリスク要因
以上、ブラジル経済の動向を見てきたが、ブラジルの経済成長を押し下げるリスク要因として、失業率の更なる上昇と民間消費回復の鈍化、世界や中国の経済の減速、原油を含む一次産品価格の動向、米国の予想を上回るペースでの利上げによる金融市場への影響、政治情勢の不安定や汚職問題の長期化等による構造改革実行への影響等が挙げられる。
テメル政権の一連の構造改革は、金融市場からの期待や評価は高い一方で、財源確保や制度見直し等による国民への負担が重く、国民や議会から支持を得ることは容易なことではないが、ブラジル経済再生に向けて、政府が明確な道筋を示し、着実に実行していくことが重要である。
