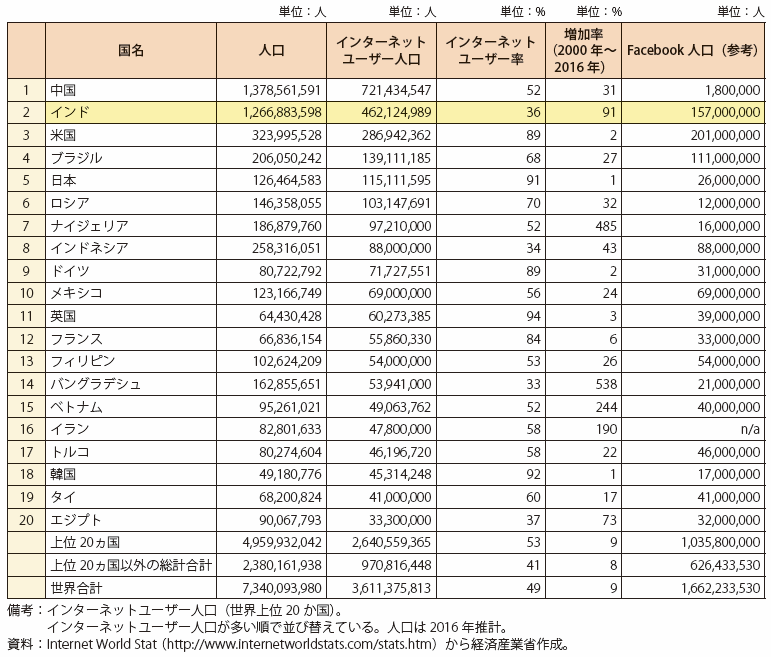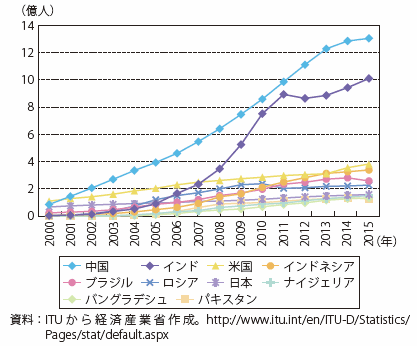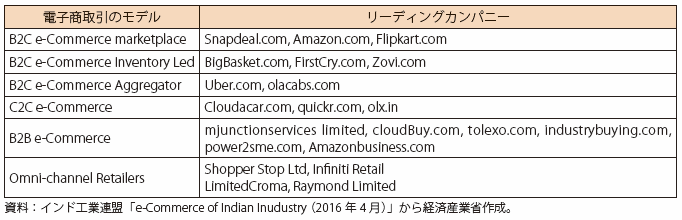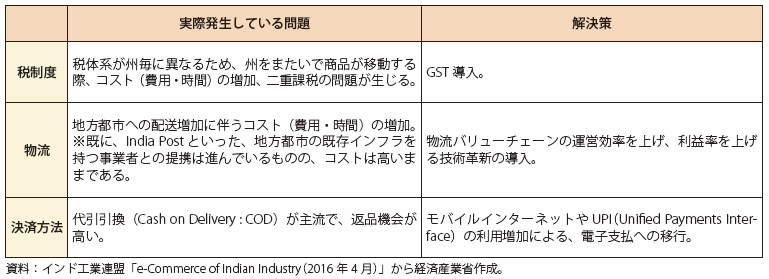- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第4章 第1節 南西アジア・東南アジア
第4章 その他新興国経済動向
第1節 南西アジア・東南アジア
1.南西アジア・東南アジアの経済概略
ここでは、インド、フィリピン、ベトナムを取り上げる。この3国は、近年高い成長率を示している117(第Ⅰ-4-1-1-1図)が、各国の成長要因を調べると、内需の強さ、サービス業の堅調さ、資源依存度の相対的な低さ、対米国の貿易黒字と対中国の貿易赤字の拡大、海外労働者送金の大きな役割等、共通点を抽出することができる。
第Ⅰ-4-1-1-1図 インドとASEAN主要国の実質GDP成長率の推移
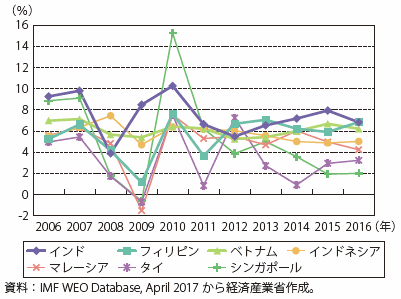
117 3国は有望な市場と注目されていることから、代表的な株価指数(VN指数、SENSEX指数、フィリピン株価指数)は堅調に推移しており、市場関係者の中では、各国の頭文字を使った「新VIP」という呼び方がされることもある。
(1)内需の強さ
3国は、1人当たり名目GDP額が、他のASEAN先発国と比較して低く、耐久消費財の需要が拡大する3,000ドルに向かって上昇する局面にある(第Ⅰ-4-1-1-2図)。中間層の増加、人口規模の大きさと平均年齢の若さ118から、内需が成長エンジンとなっている。
第Ⅰ-4-1-1-2図 インドとASEAN主要国の一人当たり名目GDP額の推移
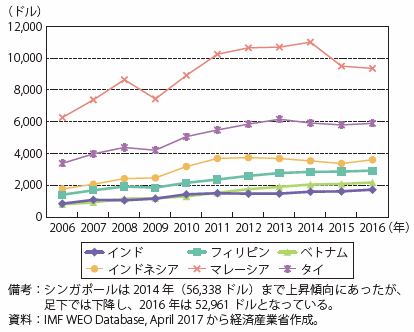
118 人口規模については、インドの約13億人は桁違いであるが、フィリピン、ベトナムも1億人前後と大きい。また、国民の平均年齢は、インドが26歳、フィリピンが26歳、ベトナムは30歳と若い(日本は46歳)。
(2)サービス業の堅調さ
3国は、サービス業付加価値額の年成長率が、他のASEAN先発国と比較して高い(第Ⅰ-4-1-1-3表)。また、サービス輸出も伸びている(第Ⅰ-4-1-1-4表)。
第Ⅰ-4-1-1-3表 インドとASEAN主要国のサービス業(付加価値額)の年成長率
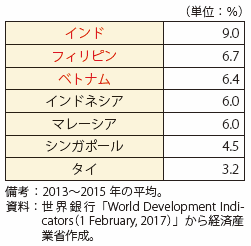
第Ⅰ-4-1-1-4表 インドとASEAN主要国の財・サービス輸出の伸び率(前年比)
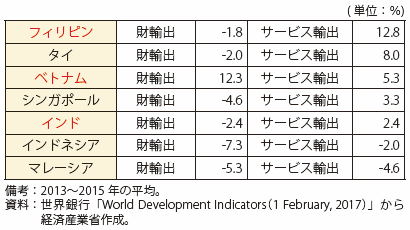
(3)資源依存度の低さ
3国は、資源輸出に依存している国ではない119ため、近年の資源価格の下落は、輸入額の低下となり、成長の追い風になっている。なお、インド、フィリピンについては、そもそも輸出依存度が低いが、ベトナムは、外資系企業による輸出が成長に大きく寄与しており、輸出依存度は高い点が異なる(第Ⅰ-4-1-1-5図)。
第Ⅰ-4-1-1-5図 インドとASEAN主要国の資源依存度と輸出依存度
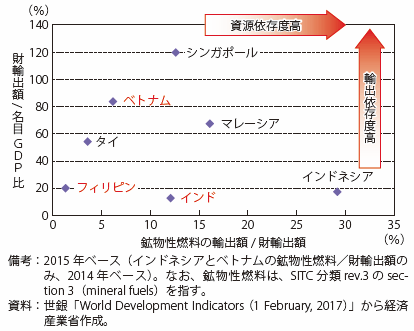
119 ベトナムでは、かつて、原油が主力輸出品であった。2008年は原油の輸出額が104億ドルあったものの、年々減少傾向にあり、2016年はわずか23億ドルとなっている。
(4)対米国の貿易黒字と対中国の貿易赤字の拡大
3国は、主要輸出国が米国であり(インド、ベトナム共に、輸出国の第1位。フィリピンに関しては、日本に次いで第2位)、輸入国の第1位が中国である。3国とも、対米国の貿易黒字、対中国の貿易赤字は拡大傾向にある120。これは、堅調な米国景気を反映した米国への輸出増加121、国内における電気電子産業の進展による中国からの輸入増加122が、主な背景と考えられる。なお、他のASEAN先発国と比較し、相対的に、輸出に占める米国の割合は高く、中国の割合は低い(第Ⅰ-4-1-1-6図)。
第Ⅰ-4-1-1-6図 インドとASEAN主要国の輸出依存度(対米国・対中国)
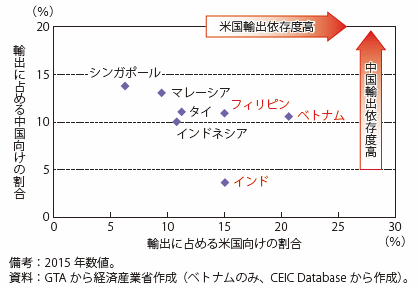
120 品目や推移等詳細は、各国の節を参照されたい。
121 消費財を中心として輸出が増加している。
122 国内における電気電子産業の進展の一方で、基幹部品製造までは至っていないため、結果的に中国からの電子部品等の輸入が増加している。
(5)海外労働者送金の大きな役割
3国は、堪能な英語、IT等専門性、器用さや勤勉さ、先進国と比較し低賃金であるなどと評価される人材面のメリットを生かし、海外で働く国民が多い。特に、米国での労働者は多く、彼らからの海外送金は、本国経済へ大きく貢献している(第Ⅰ-4-1-1-7表)。
第Ⅰ-4-1-1-7表 インド・ASEAN主要国の米国永住権取得者数(フローベース)の推移
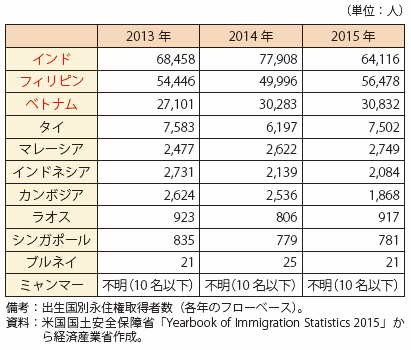
以上、近年高成長を示す3国の共通点を挙げたが、各国の政策とその進捗、持続的に成長をするための課題、リスク要因は様々である。以下、各国別に概観してゆく。
2.インド
(1)マクロ経済動向
2014年5月、単独の政党としては30年ぶりに下院で過半数を獲得したインド人民党(BJP)のモディ政権123が始動して約3年が経った。モディ首相は「開発、成長、雇用」の実現に向け、矢継ぎ早に数々のスローガンを打ち立て、インドの進むべき方向性を国内外に示している。また、国内産業振興策、税制改革、金融セクター改革等の構造改革にも取り組んでおり、高い支持率を維持している。
123 前政権(国民会議派連合政権)下での低成長、インフレ、汚職の他、連合政権であるが故の政策決定の遅滞、政情不安といった諸問題を迅速に解決する、強いリーダーシップを国民が期待した結果、とする見方が多い。なお、任期は5年である。
①GDP
近年の実質GDP成長率を見ると、個人消費がけん引し、2014年度、2015年度は7%台と高い水準にある。原油安の影響などでインフレ圧力が後退し、家計の実質購買力が高くなっていることが成長を後押ししている。
投資124については、公共投資がけん引し、年ベースで拡大傾向にある一方、企業の過剰債務問題や銀行の不良債権問題から、民間投資が弱いことが指摘されている。また、2016年度に入ると、それまで堅調だった公共投資に代わり、政府消費が成長に寄与している(第Ⅰ-4-1-2-1図)。
第Ⅰ-4-1-2-1図 インドの実質GDP成長率及び需要別寄与度の推移
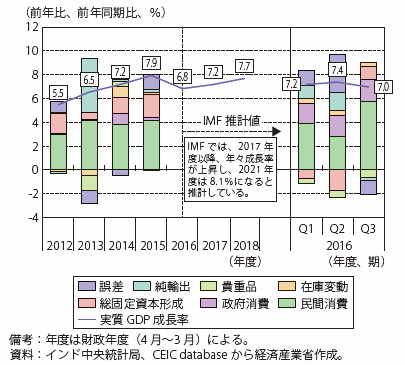
実質GVA125成長率を見ると、サービス産業が成長をけん引していることが分かる(第Ⅰ-4-1-2-2図)。
第Ⅰ-4-1-2-2図 インドの実質GVA成長率及び産業別寄与度の推移
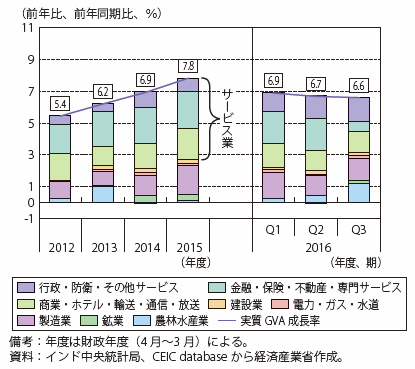
GVA(総付加価値)の産業項目別構成126は、農林水産業が15.4%、工業が31.4%(うち製造業は17.8%)、サービス産業が53.2%である。なお、サービス産業の主な内訳は、割合が大きな順に、不動産・住宅・専門サービス業、商業・修理業、金融サービス業となっている(第Ⅰ-4-1-2-3図)。
第Ⅰ-4-1-2-3図 インドのサービス産業の内訳
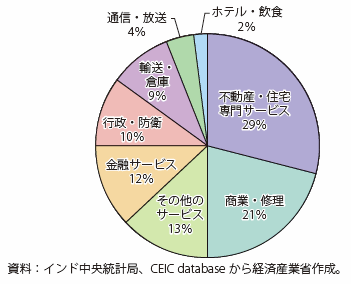
124 第Ⅰ-4-1-2-1図の総固定資本形成に該当する。
125 生産側から推計された総付加価値。GDPはこのGVAに純間接税(NIT:間接税-補助金)を加算したもの。NITの変動に左右されるGDPより、月次景気指標に近い動きをする指標として評価され、供給サイドの実質成長率を見る際によく使われる。
126 GVA at Basic Price 2011-12の2015年ベース。インド中央統計局データによる。
②貿易収支
貿易収支は赤字が常態である。しかし、輸出依存度が低いため、成長への影響は他の新興国と比較すると限定的であるといえる。2015年、2016年と輸出入ともに縮小しているが、原油価格の下落などにより、赤字幅は縮小傾向にある。
輸出の推移を見ると、減少傾向だった宝飾品が2016年に回復したほか、医療用品の輸出が年々増加している。輸入の推移を見ると、鉱物性燃料が大きく減少している(第Ⅰ-4-1-2-4表)。経済成長に伴い、原油の輸入量は年々増加しているにもかかわらず、単価下落の影響により、2016年の輸入金額は2012年と比較し、約6割も減少した127。
第Ⅰ-4-1-2-4表 インドの貿易収支と主な輸出入品目の推移
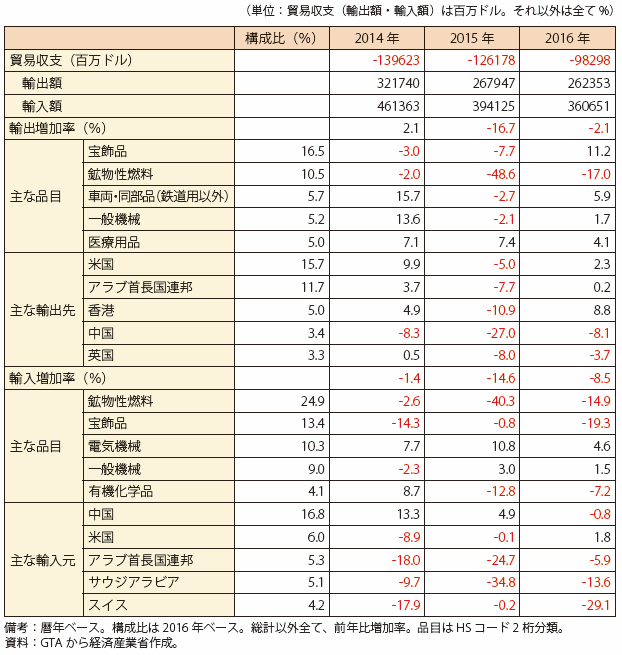
米国との貿易は、2009年以降2014年まで、輸出拡大に従い、貿易黒字幅が拡大した。足下では、輸出入ともに横ばいとなっており、2016年の貿易黒字は約200億ドルである(第Ⅰ-4-1-2-5図)。主な輸出品は、ダイヤモンドなどの貴石・貴金属、医薬品などの医療用品128である。主な輸入品は、一般機械、航空機・同部品129である130。
第Ⅰ-4-1-2-5図 インド貿易収支(対米国)の推移
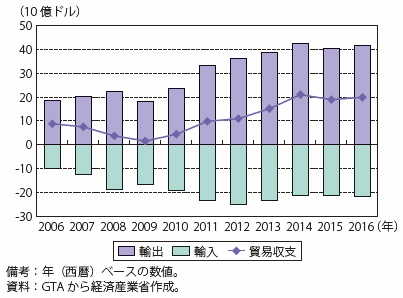
中国との貿易は、総じて、年々中国からの輸入が拡大しており、2006年には約78億ドルだった貿易赤字が、2016年は約517億ドルまで拡大している(第Ⅰ-4-1-2-6図)。主な輸入品は、携帯電話、半導体デバイス等の電気機械や、有機化学品である。主な輸出品は、綿糸などの綿・綿織物、鉄鋼等の鉱石である131。
第Ⅰ-4-1-2-6図 インド貿易収支(対中国)の推移
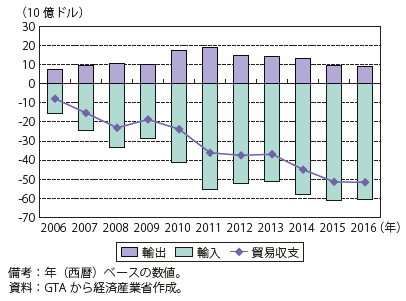
127 インド中央統計局データによる。
128 2006年から2016年の10年間で、医薬品等の医療用品が11.1倍に増加している。
129 2006年から2016年の10年間で、飛行機・同部品が4.4倍に増加している。
130 GTAデータによる。
131 GTAデータによる。
③国際収支
経常収支は赤字が常態であり、内訳は、貿易収支、第一次所得収支が赤字、サービス収支、第二次所得収支が黒字である。2015年度の経常収支は約221億ドルの赤字、名目GDP比は▲1.1%であり、近年改善している。2016年度に入っても、同割合は、低い水準で抑えられている。これは、原油価格下落に伴う貿易赤字の縮小が主な要因である。通信・情報といったITサービス・ソフトウェア産業に関するサービス輸出は堅調に増加しており、サービス収支黒字に大きく寄与している。第一次所得収支は、直接投資配当支払の増加に従い、赤字が増加傾向にある。第二次所得収支132は、主に労働者送金受取の減少により、黒字が減少傾向にあるが、サービス収支とともに、経常収支の赤字の抑制に大きく寄与している構造には変わりがない(第Ⅰ-4-1-2-7表)。
第Ⅰ-4-1-2-7表 インドの経常収支の推移
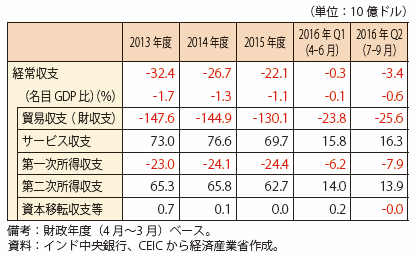
金融収支は、近年、減少傾向にあるものの、堅調な資金流入が見てとれる。モディ政権の構造改革への期待感から、直接投資が底堅く推移している一方、足の速い証券投資に流出の動きもある(第Ⅰ-4-1-2-8表)。
第Ⅰ-4-1-2-8表 インドの金融収支の推移
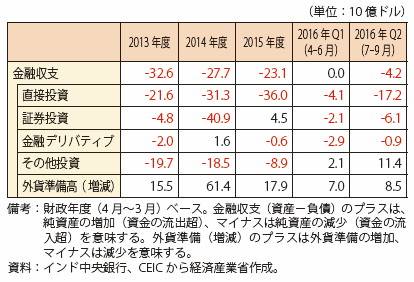
132 第二次所得収支は、経常移転(無償で提供する取引)であり、例えば、労働者送金やODAが該当する。
(2)成長を持続するための課題
モディ政権の一連の構造改革は、着実に前進している。国民への積極的な語りかけが奏功し、短期的な混乱や痛みを伴っても、長期的なロードマップに賛同する国民が多い。成長の持続には、構造改革の継続が必要であるが、主に以下が注目されている。
①GST(物品・サービス税)の導入
2017年7月導入を目指し、GST (物品・サービス税)133の制度設計がされている。GSTの導入により、連邦政府と州政府が管轄する複数の物品・サービス関連の間接税134が一元化され、課税の重複を回避できること、州をまたいだ事業展開が容易になること等が期待されている(第Ⅰ-4-1-2-9図)。従来の複雑な税体系では、ビジネス上の非効率性、特定の品目における高い税率、低いコンプライアンス意識、脱税の横行等を招いていたため、今後は、政府による徴税率が高くなることも見込まれている。
第Ⅰ-4-1-2-9図 インドにおいてGSTを導入することにより期待される効果
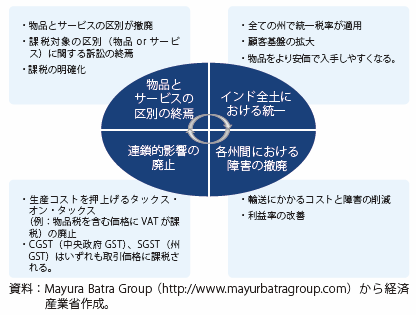
短期的には、一部の物品・サービス品目での税率上昇も生じるが、中長期的には、ビジネス環境の改善を通じ、経済成長を加速させると見込まれている。政府は、GST導入による税制の効率化により、実質GDP成長率が2%程度押し上げられるとの試算をしている。
ただし、GSTの実行には、細則の協議、ITインフラの整備135等、多くのプロセスが残されている。
133 2017年3月末にGST法案が下院、4月初旬に上院を通過した。GSTが議論され始めたのは、現野党である国民会議派・シン前政権下の2006年度のことであり、10年が経過している。
134 インド憲法では中央政府と州政府双方に徴税権を認めている。課税対象が分かれている他、各州によって税率が異なるなど、複雑なものとなっている。
135 2016年11月に、納税者、銀行、州政府、インド中央銀行とのウェブ上での情報のやり取りを行う政府のポータルサイトが運用開始されている。
②脱現金主義の促進
2016年11月、モディ首相は、脱税・汚職・偽造等の不正資金136を撲滅するなどの目的のため、高額紙幣の廃止137を決行した。短期的には、貨幣不足により、企業決済や消費などに混乱を与えたが、これを機に、国民が銀行との取引機会を拡大させた138ことは、長期的には、信用創造などの観点で同国へのプラスの効果があると内外から評価されている。なお、同国では、社会給付も現金により提供されるため、給付の過程で搾取されることも大きな問題であった。モディ首相は、国民全員に銀行口座をもたせ、社会給付を直接届けるという「金融包摂」の政策を積極的に推進しており、問題解決に向けて前進したといえる。
また、今回の措置を契機に、現金を使用しない決済手段(キャッシュレス)の普及が見込まれている。モディ首相は月に1度の国民向けラジオ番組を通し、電子決済などを用いたキャッシュレス社会の実現について発信し続けている。政府は、電子決済にも用いられるPOS(販売時点情報管理システム)の機器製造者に対して、機器に課される物品税、機器の部品や原材料の輸入にかかる追加関税などのほか、カード決済にかかるサービス税の免除を発表するなど、現金取引からの脱却を促している。
136 インドの地下経済はGDPの2割を占めると言われている。「ブラックマネー」と言われる統計上表れない通貨が流通していることが、同国の長年の課題である。
137 モディ首相は、2016年11月8日の夜、テレビ演説で、11月9日午前零時(演説のわずか4時間後に当たる)から現行の500ルピー(約800円、1ルピー=約1.6円に相当)紙幣と1,000ルピー紙幣を無効とする旨を発表した。国民は、11月10日から12月30日までに、廃止対象紙幣を銀行に預け入れるか、新紙幣(500ルピー札と2,000ルピー札)と交換する必要に迫られた。インド準備銀行は、発表後1か月間で旧紙幣の9割を回収できたとしている。
138 同国は、現金決済が主流であり、国民の半数は銀行口座を保有していない。政府主導で「国民皆銀行口座」を奨励したが、銀行口座を開設しても預金がないというケースが多いと言われている。
③健全な金融システムの構築(不良債権処理)
国営銀行と民間銀行の債権総額とそれぞれの不良債権比率を見ると、債権全体139の7~8割をも占める国営銀行の不良債権比率が上昇していることが分かる(第Ⅰ-4-1-2-10図)。同国における国営銀行の与信審査は従来厳格なものではなかった140という見方が多い。
第Ⅰ-4-1-2-10図 インドの国営銀行・民間銀行の債権額と不良債権比率の推移
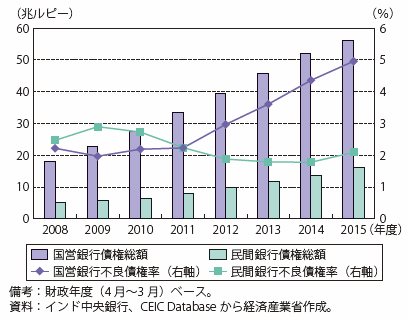
政府と中銀は、銀行の資本強化141、国営銀行のガバナンス改革142等の対策を進めている。製造業の発展を通じた成長を目指す同国にとって、資金供給源である銀行経営は重要であり、早期に健全な金融システムを構築することが求められている。
139 商業銀行(国営銀行、民間銀行、外資系銀行)の全債権を指す。
140 世界経済危機の影響で、国内景気が減速し融資リスクが高まった際、2008年8月のインド中銀の特例措置に基づき、返済期間の延長や利息支払の猶予を行った債権は、不良債権ではなく正常債権として分類された。2013年5月、中銀はこの特例措置を解除した。同年9月、2003~2006年にIMFのチーフエコノミストを務めたラグラム・ラジャン氏が中銀総裁に就任し、各銀行に対し、資産の質の査定を実施するよう指示したほか、2017年3月までに適切な引当金を積んで損失計上をし、不良債権処理を終了すべきとの方針を出した。これを受けて、各銀行が債権分類基準を厳格化したことが不良債権比率上昇の要因である。
141 2015年3月から4年間の間に、政府による国営銀行への7,000億ルピーの注入が計画され、2016年7月に第一弾として13行に対する2,292億ルピーの注入が行われた。
142 2016年4月に、国有銀行改革を担うBanks Board Bureau(BBB)が設立されており、国営銀行の役員の任命を始めとしたガバナンスの改善に当たり、国営銀行の再編や増資を進めていく任務を担うことが期待されている。
④破産法の成立による倒産処理の効率化
2016年5月、インドの破産法143が成立した。本法は、同国初の統一的に体系化された倒産処理の基本法であり、倒産処理の円滑化、迅速化等を目的としている。同国では、複数の破綻処理機関や関連法規が存在していたが、本法により一本化されることとなった。世界銀行が公表したDoing Business 2017によれば、インドは、「破綻処理のたやすさ」の項目で、190か国中136位にランキングされ、破綻処理期間は4.3年をも要するとされている(第Ⅰ-4-1-2-11表)。本法では、破綻処理日数を180日に制限することが示されていることから、今後の破綻処理の効率化、不良債権処理の加速化、産業の新陳代謝の促進等が期待される。また、 外国企業にとっては、同国で事業を行う上で、債権を取得することのリスクを低下させることから、本法は歓迎されている。
第Ⅰ-4-1-2-11表 倒産処理のたやすさ総合ランキングと倒産処理にかかる年数
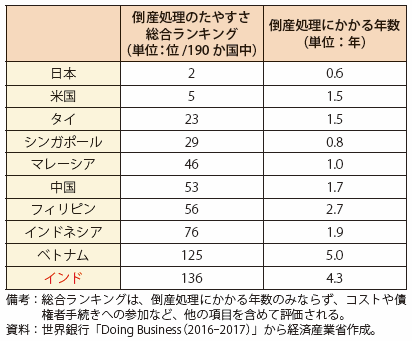
143 The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016。本法の適用対象は、金融機関以外の全ての会社、組合及び個人であり、金融機関の倒産処理については、本法の制定後、本法とは別の倒産法を制定することが予定されている。
⑤対内直接投資の積極的な誘致
政府は、国内の資本、技術及び技能を補完し、一層の経済成長の拡大を実現するため、対内直接投資を誘致している。モディ政権発足直後より、主要セクターにおける出資比率の上限の引上げや撤廃、手続の簡素化(政府認可ルートから自動認可ルートへの変更)等、外資規制緩和策を相次いで打ち出している。現在のFDI政策(Consolidated FDI Policy)144の内容は以下のとおりとなっている(第Ⅰ-4-1-2-12表)。
第Ⅰ-4-1-2-12表 インドの対内直接投資に関する政策内容
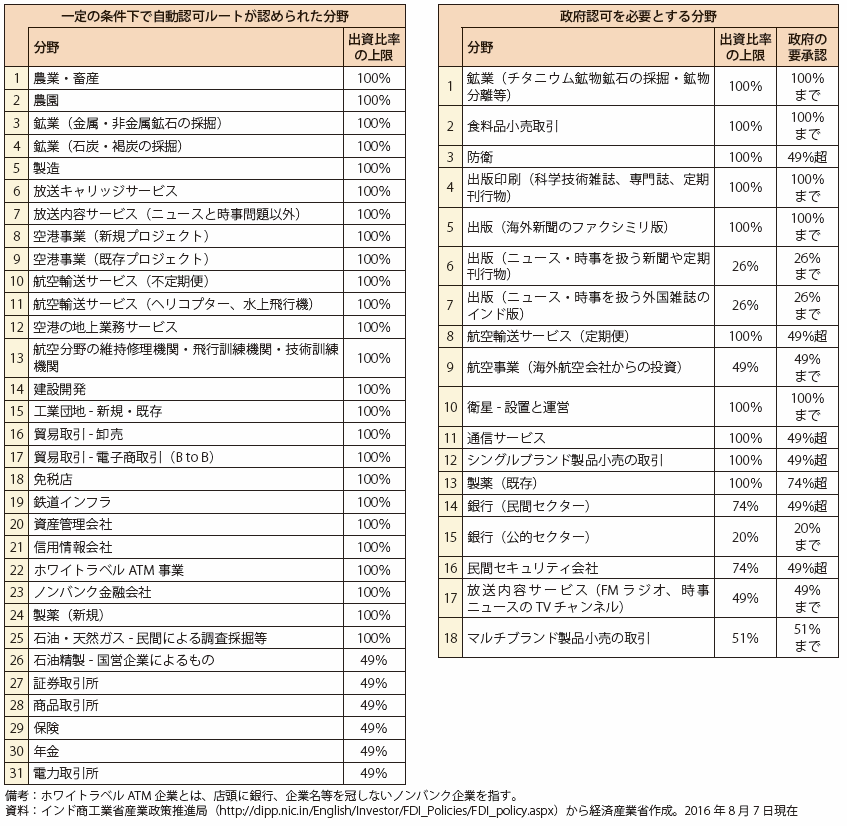
政府の積極的な外資規制緩和策により、対内直接投資額は上昇し、2016年は過去最高の464億ドルとなった。国別では、モーリシャス(全投資額の32.5%)、シンガポール(同21.2%)、日本(同12.5%)が多く、業種別では、サービス(同21.9%)、通信(同12.5%)、貿易(同6.7%)と非製造業が中心である(第Ⅰ-4-1-2-13図、第Ⅰ-4-1-2-14図)。
第Ⅰ-4-1-2-13図 インドの対内直接投資の推移(国別)

第Ⅰ-4-1-2-14図 インドの対内直接投資の推移(業種別)
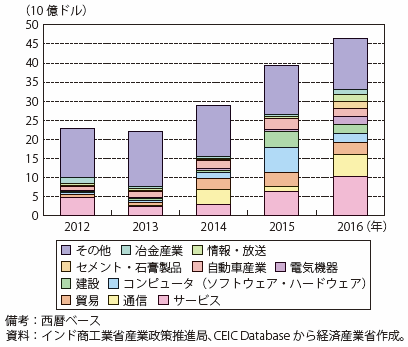
なお、鉱工業生産指数の推移を見ると、製造業の勢いが持続して拡大しているとは言い難い(第Ⅰ-4-1-2-15図)。モディ政権は、若年層の雇用確保及び輸入削減を目的とした製造業振興に重点をおいており、製造業のGDP比率を、現在の約15%から2022年までに25%まで引き上げようとしている。モディ政権が海外に声高に発信する製造業誘致のキャンペーン「Make in India」によって、同国への投資分野が今後どのような動きを見せるかが注目される。
第Ⅰ-4-1-2-15図 インドの鉱工業生産指数(前年同月比)の推移
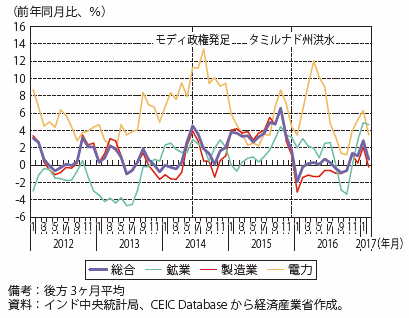
144 FDIの規制を変更する際は、商工業省の産業政策促進局 (Department of Industrial Policy and Promotion: DIPP) が、報道発表(Press Note)として、変更内容を随時公表している。なお、投資家の便宜を考慮し、規制内容を一つにまとめた「統合版FDIポリシー(Consolidated FDI Policy)」を年1回公表している。本文中に掲載した内容は、2016年6月7日に施行された内容である。最新の情報や詳細を把握するために、DIPPのHPも併せて参照されたい。
⑥農村や貧困層に配慮した包括的成長とインフラの促進
モディ政権は、農村や貧困層への配慮とインフラの必要性を強調している。2017年度予算では、「Transform Energise and Clean India:TEC India」を標語に掲げ、ガバナンス・国民生活の質の向上、若者・社会的弱者の支援、贈賄・不透明な政治資金の一掃を目指している。これを踏まえ、優先分野は以下となっている(第Ⅰ-4-1-2-16表)。
第Ⅰ-4-1-2-16表 インドの2017年度予算における優先10分野
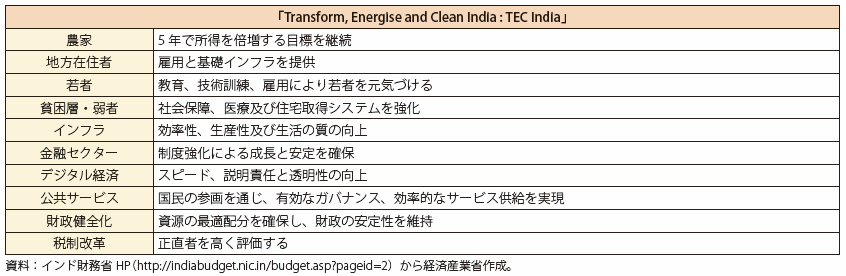
(3)リスク要因
①原油を含む鉱物性燃料価格のリスク
IEAは、①世界のエネルギー需要は、2040 年に2013 年と比較し、約3割増加し、インドはその増加分の約4分の1を占める最大の需要増国になること、②インドのエネルギー需要は、2040 年に2倍以上に増加し、需要のけん引車は中国からインドに変わること、③中でも、原油需要の伸びは世界最大になり、世界の石炭需要に占める同国のシェアは20%以上に達すること、を予測している145。
同国は、資源輸入国であるため、原油など鉱物性燃料の価格上昇は大きなリスク要因である。足下では、原油安の長期化に伴い、インフレ圧力の後退など内需依存度の強い同国の追い風となっているが、急速な経済成長に伴う需要増に対応するためには、原油価格に左右されないためのリスクヘッジが重要となる。例えば、太陽光や風力発電など低炭素エネルギーの導入が対応策の一つになろう。
145 World Energy Outlook 2015におけるインドに関する分析。
②米国新政権の政策
同国は、輸出依存度が低く、財貿易の観点では、米国の影響度は限定的である。しかし、米国新政権が、モノやカネ、人の自由な移動に制約を与えるような施策146をとれば、英語を話せる人材やITなど専門性が求められる高度人材が多い同国は、海外労働者送金やBPO147ビジネスへの打撃により、現在の成長エンジンである内需、サービス業の勢いをそぐ可能性があることが懸念される。
146 2017年4月、専門技能を持つ外国人向けのビザ(査証)「H1B」の審査を厳格化する方針を表明している。当該ビザは、インドを中心とする移民技術者が多く取得している。
147 企業の業務プロセスの一部を専門企業に外部委託すること。
3.フィリピン
(1)マクロ経済動向
2016年6月、ロドリゴ・ドゥテルテ氏が大統領に就任した。過激な発言で「フィリピンのドナルド・トランプ153」と揶揄されることもあるが、ダバオ市長154を長く務めた政治家出身であり、治安対策に注力し、犯罪で悪名高かった同市を安全な都市にした実績が、国民に評価されている。
前大統領であるベニグノ・アキノ氏は、2010年6月の就任以来、政治の安定、財政健全化、高い経済成長を達成し、対外的に高い評価を得て任期を全うした。それにもかかわらず、同氏から後継者指名された候補者が落選し、ドゥテルテ氏が選出されたのは、汚職や犯罪、地域格差や所得格差、都市部の交通インフラといった諸問題の解決が遅滞していることに不満をもつ国民が、決断力・実行力のある強いリーダーを求めたことにある、という見方が多い。
153 ドゥテルテ氏が71歳、トランプ氏が70歳と、それぞれ歴代最高齢での大統領就任となった(フィリピンについては、1986年の民主化以降の大統領で比較)。
154 ダバオはマニラ、セブに次ぐ第3の都市。ドゥテルテ氏の父は旧ダバオ州の知事であった。同氏はダバオ地検で検事として働いた後、ダバオ市長(1988~1998年、2001~2010年、2013~2016年)として約20年以上務めた。
①GDP
過去3か年の実質GDP成長率を見ると、底堅い個人消費と投資がけん引し、年ベースでは、6%台の高い成長率を見せている。四半期ベースでは、2015年第1四半期から、成長率が上昇し、2016年第2、3四半期は7.1%という高水準となった。2016年第4四半期は6.6%に減速したものの、これは、選挙関連の押し上げが一服したものと見られている。2017年は選挙の反動、輸出不振の継続は想定されるものの、今後も個人消費155、インフラ投資が成長をけん引していくものと見込まれている(第Ⅰ-4-1-3-1図)。
第Ⅰ-4-1-3-1図 フィリピンの実質GDP成長率及び需要別寄与度の推移
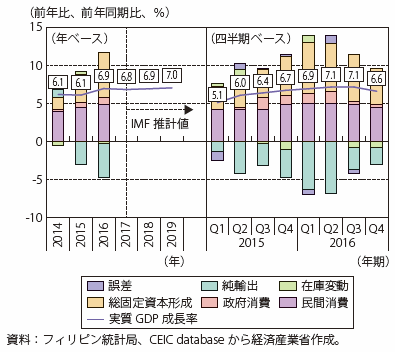
同国の成長は、名目GDPの6割弱を占めるサービス業がけん引している。2016年ベースでは、実質GDP成長率6.8%に対する寄与度が4.3%にも上り、同業に従事する労働者も約6割と多くを占める(第Ⅰ-4-1-3-2図)。
第Ⅰ-4-1-3-2図 フィリピンの実質GDP成長率及び産業別寄与度の推移
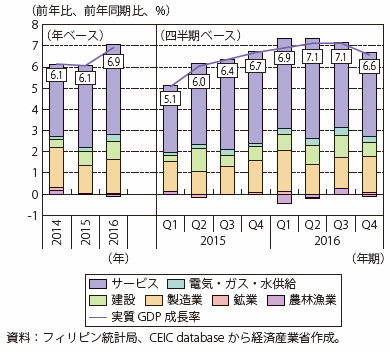
サービス輸出は年々増加しているが、主にビジネス・プロセス・アウトソーシング156関連(以下、BPO)が大きく寄与している。BPO産業サービスの輸出先は、7割超を米国が占めており、サプライチェーンにうまく組み込まれている。また、2011年、2012年と欧州からBPO産業への対内直接投資が増加したことも影響し、サービス輸出先として欧州の割合も増加している(第Ⅰ-4-1-3-3図、第Ⅰ-4-1-3-4図)。同国は、インドと同様、英語力、コスト競争力、24時間サービスを可能とする時差等の強みにより、欧米企業からの対内直接投資先に選ばれている。BPO産業の発展は、雇用拡大、所得水準の上昇を通じ、海外労働者送金とともに、同国の民間消費を支えている。
第Ⅰ-4-1-3-3図 フィリピンのサービス・BPO関連輸出額の推移
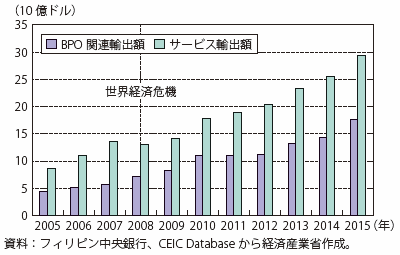
第Ⅰ-4-1-3-4図 フィリピンのBPO輸出先の推移
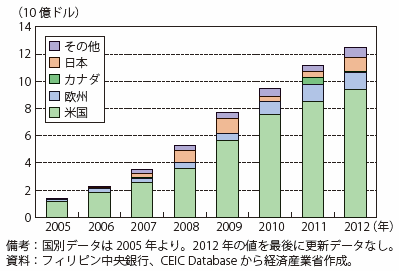
155 2015年の同国の1人当たり名目GDPは2,863ドルであり、10年で2.4倍(2005年は1,209ドル)となった。自動車等の耐久消費財が広く普及し始めるとされる3,000ドルに近づいている。
156 企業の業務プロセスの一部を専門企業に外部委託すること。
②貿易収支
同国は貿易赤字が常態であるが、2014年以降、年々赤字が拡大している。これは、旺盛な内需により、資本財や消費財(特に耐久消費財)の輸入が増加していること、その一方で、輸出の約5割を占める主力輸出品目である電子部品・製品(特に、半導体製造装置・部品、電子データ処理機器)の輸出が、中国など主要輸出先の需要減退により減少していることが要因である(第Ⅰ-4-1-3-5表)。
第Ⅰ-4-1-3-5表 フィリピンの貿易収支と主な輸出入品目の推移
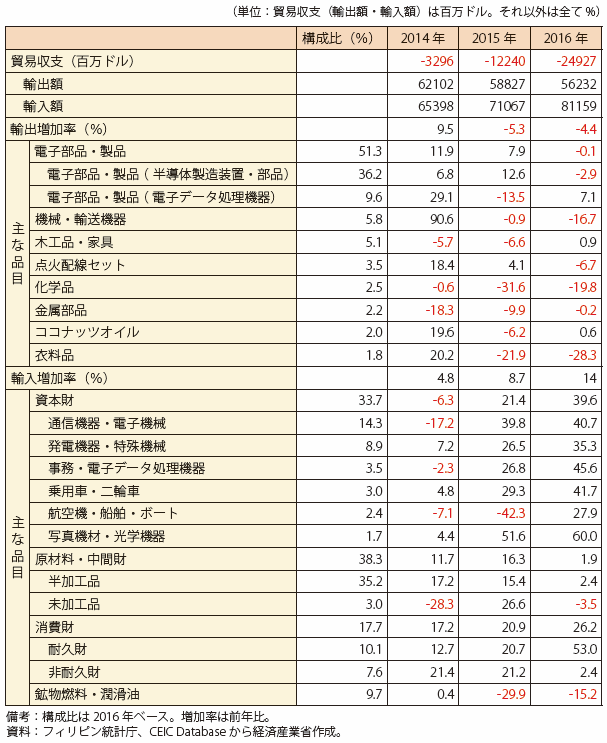
米国との貿易の推移を見ると、2012年から、フィリピンからの輸出は増加したが、2016年は輸出入ともに減少した。貿易黒字額は足下では減少しており、2016年は約14.3億ドルである(第Ⅰ-4-1-3-6図)。主な輸出品、輸入品はともに集積回路などの電気機械であり、米国のサプライチェーンに組み込まれていることが分かる。
第Ⅰ-4-1-3-6図 フィリピン貿易収支(対米国)の推移
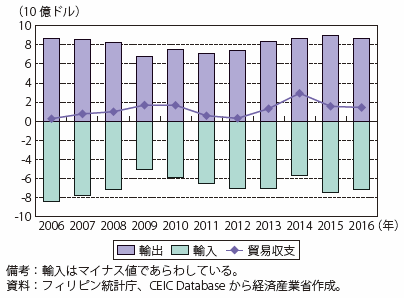
中国との貿易の推移を見ると、従来はフィリピンからの輸出超で貿易黒字であったが、近年は貿易赤字が大きく拡大し、2016年は約87.8億ドルである(第Ⅰ-4-1-3-7図)。主な輸入品は、携帯電話や集積回路などの電気機械である。近年、電気電子産業が進展したことから、同国は中国の主要輸出国になっている157。なお、主な輸出品は、自動データ処理機械・同付属品などの一般機械である158。
第Ⅰ-4-1-3-7図 フィリピン貿易収支(対中国)の推移
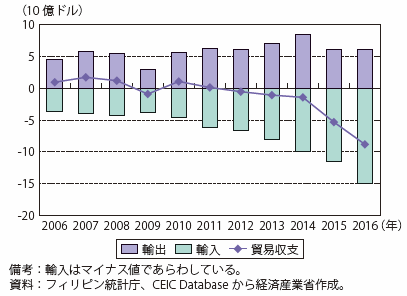
157 電気電子産業の進展の一方で、基幹部品製造までは至っていないため、結果的に中国からの電子部品等の輸入が増加している。
158 フィリピンにとって、90年代までは、輸出入ともに米国が最大の貿易相手であったが、2000年以降、アジア域内貿易が拡大した。
③国際収支
同国は、貿易収支の赤字を、海外労働者送金などの第二次所得収支及びサービス収支の黒字が相殺して、経常黒字を確保しているという特色がある。経常収支の推移を見ると、2015年以降、貿易赤字の増加により経常黒字は減少しており、2016年の経常収支は約6億ドル、経常収支対名目GDP比は約0.2%となっている。主に、好調な民間需要による輸入の増加と、外需低迷に伴う輸出の減少が主な要因である(第Ⅰ-4-1-3-8図)。
第Ⅰ-4-1-3-8図 フィリピンの経常収支の推移
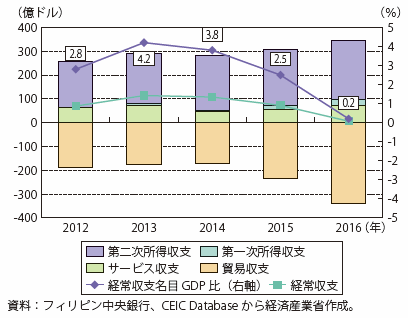
フィリピン人が海外で就労する歴史は長く、名目GDPの約1割にも上る海外労働者送金は、同国の民間消費を大きく支えている。直近10年の海外労働者送金額の推移を見ると、伸び率は鈍化傾向だが、年々増加している。米国からの送金額の割合が最も多く、2016年では33.2%であるが、2006年では51.1%を占めていた。年々、米国の割合は低下傾向にある159一方、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールといった中東地域からの送金額の割合は、2006年の14.9%から2016年の27.6%と拡大している。同地域から、家事手伝い、看護士・介護士、販売員、エンジニア等の人材需要が増加したことが要因と思われる(第Ⅰ-4-1-3-9図)。
第Ⅰ-4-1-3-9図 フィリピンの海外労働者送金額(上位10か国)と伸び率の推移
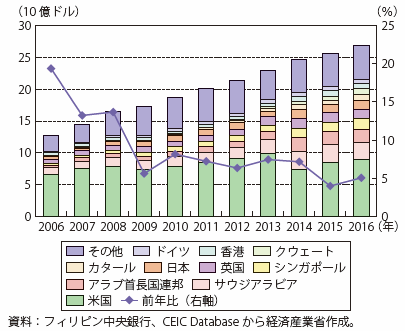
海外労働者送金額が増加する一方、海外労働者数には変化が見える。2000年に入り、海外労働者数は年々増加したが、2012年以降その伸び率は鈍化している。また、国内の失業率は2013年以降大きく改善し、2006年の8.0%から2016年には5.5%となった。失業率の低下は、内需の堅調さによる小売や建設部門の他、BPO産業の要員の増加を反映していると思われる(第Ⅰ-4-1-3-10図)。
第Ⅰ-4-1-3-10図 フィリピンの海外労働者数と失業率の推移
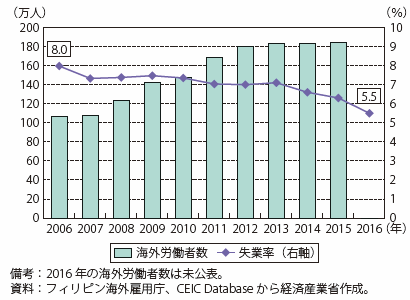
2016年金融収支の純資産は、5.3億ドルの増加(資金の流出超)となったが、2013年以降、純資産は縮小している。足の速いその他投資、証券投資160において資金の流出超となったが、対内直接投資では資金が流入した(第Ⅰ-4-1-3-11図)。
第Ⅰ-4-1-3-11図 フィリピンの金融収支の推移
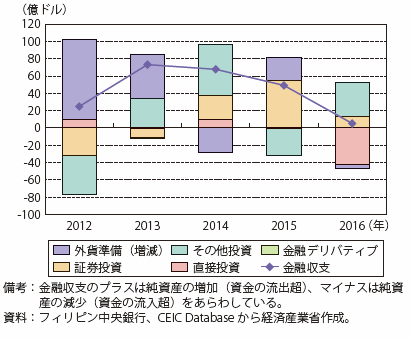
159 海外送金総額に占める米国からの送金割合は、1994年は87%と高く、それ以降は、総じて下降傾向にある。
160 2015年は、12月に実施された米国利上げによる資金流出、2016年は、新政権への期待感からの資金流入、新大統領の発言による警戒感からの資金流出などが見られ、安定していない。
(2)成長を持続するための課題
①人口ボーナスを生かす
フィリピンの人口は、約1億100万人161であり、特に若年層が多い。出生率、人口増加率、失業率162を見ると、同国は、全ての項目につき、近隣主要国の中で最も高い水準となっている(第Ⅰ-4-1-3-12表)。同国の成長が期待されている要因として、少子高齢化が進む国が多い中で、生産年齢人口比率の上昇、すなわち人口ボーナスが今後も続くと見込まれることが挙げられる。人口ボーナスは労働集約型の製造業に有効とする見方があるが、同国においては、製造業よりも先にサービス業が発展したために、生かされていない。今後、増加し続ける労働力を吸収する国内の雇用機会が創出されれば、人口ボーナスが更なる経済成長に有効に結び付くと思われる。
第Ⅰ-4-1-3-12表 出生率・人口増加率・失業率に関する近隣主要国との比較
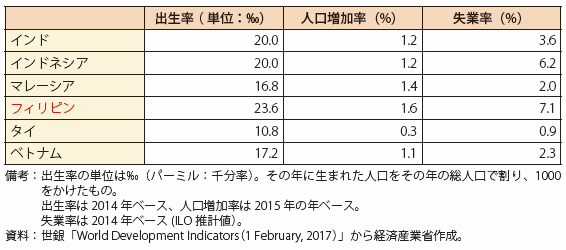
161 2015年の国勢調査による。
162 先述のとおり、同国の失業率は足下では下落しており、雇用環境は改善しているといえる。
②格差の是正(包括的成長)
同国には、大きな地域格差、所得格差が存在し、同国のジニ係数163は43.0%、貧困率164は25.2%(どちらも2012年値)と、近隣主要国の中で極めて高い水準となっている(第Ⅰ-4-1-3-13表)。歴代の政権が、この問題を解消すべく対策を実施してきたが、いまだに十分な効果が得られていない。その理由の一つとして、貧困対策のために中央政府から給付された予算が、地元政治家などの有力者に恣意的に利用され、末端まで届かないことが指摘されている。今後、汚職撲滅が進展し、経済成長の恩恵が全ての人に行き届くような仕組みが構築されれば、前政権が目指した「包括的成長(Inclusive Growth)」が実効性あるものになる。
第Ⅰ-4-1-3-13表 ジニ係数と貧困率に関する近隣主要国との比較
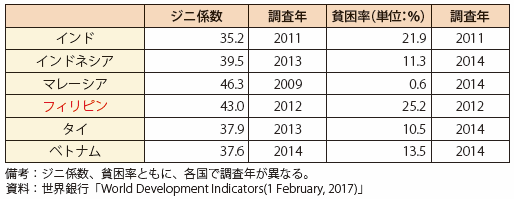
163 国内における個人又は世帯所得が、完全に平等な状態からどの程度かい離しているかを示す。0の場合は完全に平等、100の場合は完全に不平等を示す。
164 国家の貧困線以下の人口割合を指す。世帯調査による人口加重サブグループ推定に基づいている。
③インフラ整備
成長が加速する同国にとって、インフラ整備は大きな課題である(第Ⅰ-4-1-3-14図)。例えば、首都マニラの交通渋滞は深刻化しており、JICAがまとめた報告書165によると、渋滞による社会的な損失166は、1日当たり24億ペソに値するとされている。前アキノ政権(2010~2016年)では、インフラ整備を推進したことで、総固定資本形成が成長率に大きく寄与した。また、民間の資金や技術力を活用する官民連携手法(PPP)を推奨したことも高く評価されている。しかし、投資比率167は、アジア主要国と比較すると低い水準であることが分かる(第Ⅰ-4-1-3-15図)。今後も成長を持続していくためには、国内民間投資の促進や、対内直接投資の誘致が有効であろう。
第Ⅰ-4-1-3-14図 フィリピンのインフラ評価(アジア主要国との比較)
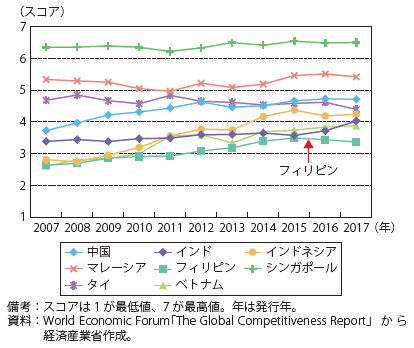
第Ⅰ-4-1-3-15図 フィリピンの投資比率 (アジア主要国との比較)
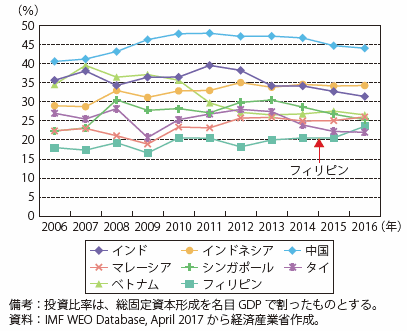
165 フィリピン国家経済開発庁(NEDA)は、計画に一貫性がなかったマニラ首都圏のインフラ整備と交通計画を、セクター横断的な視点で整理し、2030年の理想的な交通ネットワーク計画を策定するため、JICAに調査を要請した。その調査報告書では、2030年に目指す交通ネットワークを「ドリームプラン」と名付け、約300キロの鉄道、約500キロの高速道路の整備、公共交通機関の合理化、交通管理を行う複数のプロジェクトを提案している。
166 交通機関の走行費用と利用者の時間コストを元に計算されている。
167 投資比率とは、総固定資本形成を名目GDPで割ったものとする。
④外資規制緩和
同国の憲法では、外資の出資比率規制がされており、少なくとも内資が60%以上出資している企業しか公共施設を運営できない。この憲法上の制限によって、外資を生かしたインフラ整備が不可能になっていた。現政権では、憲法を改正し、外資規制を緩和する方向である。これが実現すれば、対内直接投資が増加し、雇用機会の増加、インフラ整備の促進が見込まれる。
近年、対内直接投資額(認可ベース)は下降傾向であり、2016年は46.1億ドルに留まっている。投資国別で見ると、上位から、オランダ(全投資額の22.6%)、オーストラリア(同14.8%)、米国(同14.3%)となっている。業種別で見ると、上位から、製造(同43.8%)、電気・ガス・蒸気・空調供給(同25.4%)、BPO関連サービスに該当する管理サポートサービス(同11.8%)となっている(第Ⅰ-4-1-3-16図、第Ⅰ-4-1-3-17図)。
第Ⅰ-4-1-3-16図 フィリピンの対内直接投資の推移(国別)
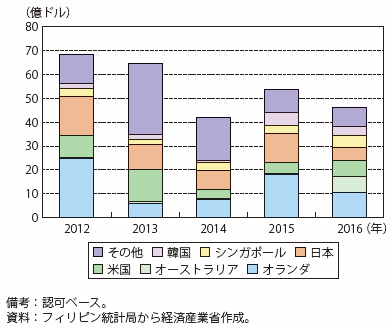
第Ⅰ-4-1-3-17図 フィリピンの対内直接投資の推移(業種別)
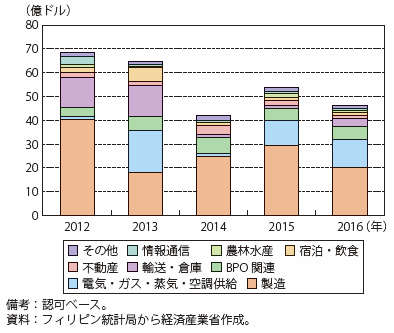
(3)リスク要因
①ドゥテルテ大統領の政策と外交のリスク
ドゥテルテ大統領は、治安を改善し、役所の腐敗と非効率を一掃すれば、国内外からの投資が集まるとの考えが基本にあり、大統領就任後すぐに、麻薬と汚職の撲滅に取り組んでいる。とりわけ、麻薬取締りは厳しく、その強権的な手法が国際機関や他国から批判されており、米国(当時はオバマ大統領)など、同国を批判した国への暴言が外交問題にまで発展した。麻薬と汚職の撲滅は、ビジネス環境の改善を促すと期待されるが、その手法に対する評価や外交問題の不確実性により、一時的な投資の減速、株価の低下や通貨安など、経済への影響が懸念される。
同国の外交に関しては、特に、対米国と対中国の姿勢が注目されている。前アキノ政権では、米国との同盟関係を重視し、中国と距離を置く姿勢168をとっていたが、ドゥテルテ大統領は、2016年9月、自主独立外交(independent foreign policy)を行うと発言した。その後、2016年10月に中国を訪問し、240億ドル相当の経済協力を取り付けたり、同年12月、アジアインフラ投資銀行に正式加盟し、融資を約束したりするといった動きがある。
168 前アキノ政権は、中国との南シナ海を巡る領有権問題を契機として、親米路線を強め、米国と共同で軍事活動を行う方針をとった。また、この領有権問題について、ASEAN首脳会議や国際海洋法条約に基づく仲裁裁判所を通じた平和的解決を目指していた。
②米国新政権の政策
トランプ大統領の貿易や移民政策は、同国にとってのリスクである。英語が公用語であることで、米国からの海外労働者送金、米国企業からアウトソースされるBPOビジネスは、同国の経済成長に大きく寄与してきた。上述のように、米国からの送金額は、海外からの送金額の中で33.2%と最も多く、BPO産業サービスの輸出先の中で、米国への輸出が占める割合は7割超を占めている。
今後、米国新政権が、モノやカネ、人の自由な移動に制約を与えるような施策をとれば、海外労働者送金やBPOビジネスへの打撃により、現在の成長エンジンである内需、サービス業の勢いをそぐ可能性があることが懸念される。
4.ベトナム
(1)マクロ経済動向
2016年5月、グエン・スアン・フック氏169が首相に就任した。新指導部は、前指導部が推進した経済改革170に継続して取り組むとしており、基本方針に大きな変更はない。最初の5年間(2016年~2020年)の基本方針として、公的債務などの財政管理、国営企業改革、農業・地方の開発等の課題に対処しつつ、自由貿易の更なる推進による高い成長と早期の現代的な工業化を目指すとしている。
169 前指導部で副首相を務めていた。
170 強いリーダーシップで、2007年の世界貿易機関(WTO)への加盟、2016年の環太平洋戦略的連携協定(TPP)への署名など、成果を出してきた。
①GDP
近年の実質GDP成長率の推移を見ると、年々、民間消費の寄与度が上昇している。また、2013年を境に、純輸出が成長のけん引役から一転、押し下げ要因に変化している一方、総固定資本形成の寄与度が上昇している(第Ⅰ-4-1-4-1図)。
第Ⅰ-4-1-4-1図 ベトナムの実質GDP成長率及び需要別寄与度の推移
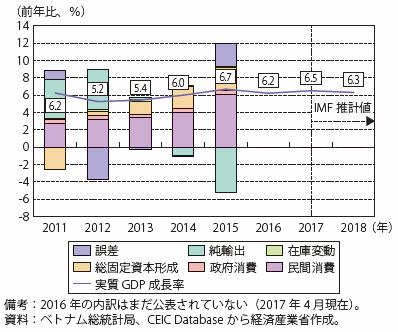
2016年の実質GDP成長率は前年比6.2%となり、前年(同6.7%)より成長が減速した。原油減産でマイナス成長となった鉱業、天候不順の影響を受けた農林水産業が成長を押し下げた一方、堅調な内需を背景にしたサービス業、外資企業を中心に好調な製造業が全体の成長を下支えした(第Ⅰ-4-1-4-2図)。
第Ⅰ-4-1-4-2図 ベトナムの実質GDP成長率及び産業別寄与度の推移
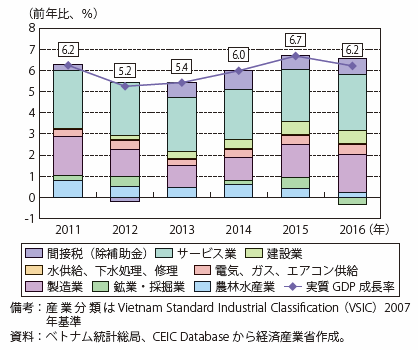
なお、サービス産業は、名目GDPの約43%(2016年ベース)を占めており、その内訳を見ると、割合が大きな順に、小売・卸売・車両修理業、金融・保険業、宿泊・飲食業、不動産業となっている(第Ⅰ-4-1-4-3図)。
第Ⅰ-4-1-4-3図 ベトナムのサービス産業の内訳
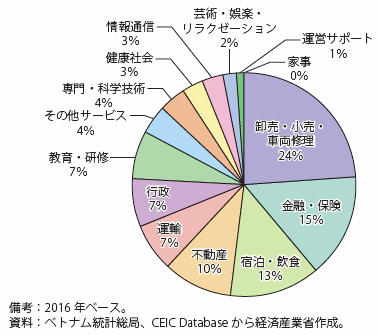
②貿易収支
同国は貿易赤字が常態171であったが、2012年から2016年まで、2015年を除き黒字となった。これは、同国が、海外企業から製造業(韓国メーカーによるスマートフォンの製造が代表例)の生産(主に加工)拠点として選ばれ、投資が流入し、その製品の輸出が拡大していることによる。なお、2015年の赤字の要因は、中国からの機械・同部品や、中国や韓国からのコンピュータ・電子部品の輸入額の増加と、水産業など国内企業の輸出が低迷したことにある。
ベトナムの輸出品目の推移を見ると、2013年に、携帯電話・部品がそれまで1位だった縫製品を抜いた172。携帯電話・部品は、統計を取り始めた2010年から2016年の7年間で、約15倍にも増加している。また、水産物や原油が足下で減少している一方、コンピュータ・電子部品は同期間で5倍に増加している。
ベトナムの輸出金額においては、外資系企業が約70%と多くを占める特徴がある。外資系企業の輸出の伸び(前年比、2016年ベース)が、12.1%と拡大を維持している一方、約30%を占める国内企業の輸出の伸びは同2.5%と勢いに欠ける。
ベトナムの輸入品目の推移を見ると、近年、機械・同部品、コンピュータ電子製品・同部品が大きく増加している173。これは、製造組立て拠点の増加が主たる要因である。なお、ベトナムの輸入金額においては、外資系企業が約59%、国内企業が約41%を占める(第Ⅰ-4-1-4-4表)。
第Ⅰ-4-1-4-4表 ベトナムの貿易収支と主な輸出入品目の推移
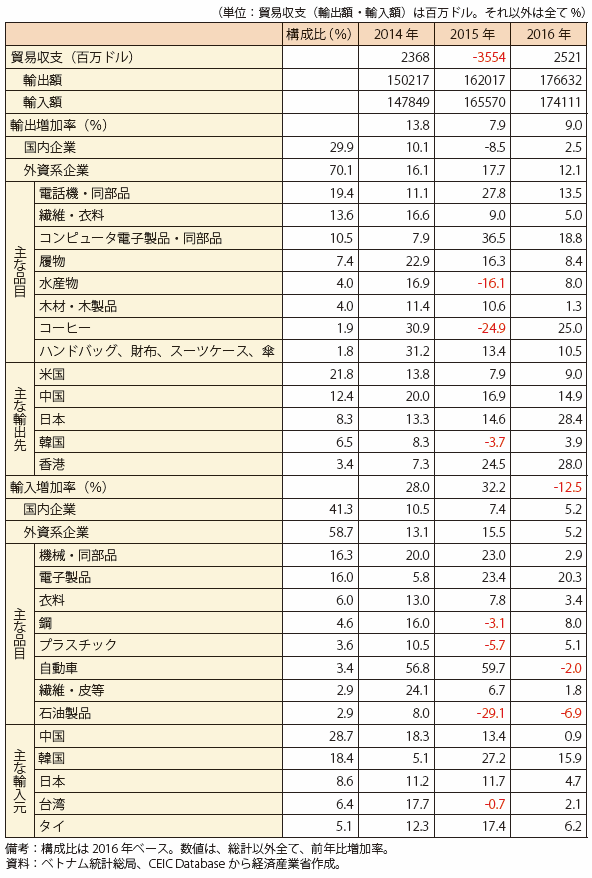
米国との貿易推移を見ると、ベトナムの大幅な輸出超であり、2016年の貿易黒字額は約260億ドルとなっている(第Ⅰ-4-1-4-5図)。主な輸出品は、携帯電話、衣料、履物である。主な輸入品としては、集積回路、アルミニウム(棒状)等である。
第Ⅰ-4-1-4-5図 ベトナムの貿易収支(対米国)の推移
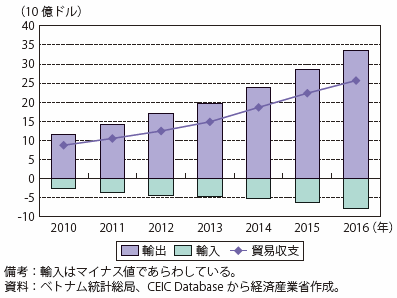
中国との貿易推移を見ると、ベトナムの大幅な輸入超であり、2016年の貿易赤字額は約280億ドルとなっている(第Ⅰ-4-1-4-6図)。主な輸入品は、携帯電話・部品、集積回路等の電気機器及び部品、自動データ処理機などの一般機械の他、鉄鋼174、繊維、アルミニウム、プラスチックである。金額的には相対的に低いが、主な輸出品は、集積回路などの電気機器である。中国と距離的に近い北部ベトナムを中心に、スマートフォンなどのIT機器産業が進展してきていることから、同国は中国の主要輸出国になっている175。
第Ⅰ-4-1-4-6図 ベトナムの貿易収支(対中国)の推移(右)
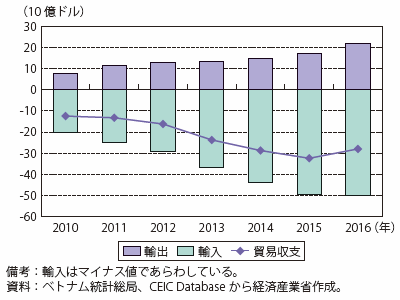
171 データで遡及できる1955年以来(1992年に4000万ドルというわずかな黒字を記録した以外)、2011年までの長い期間、貿易赤字であった。
172 2008年まで、原油が輸出品目の第1位であり、その後、縫製品に替わった。
173 2016年は、機械・同部品については減少した。
174 2016年7月、ベトナムは、鉄鋼製品に対するセーフガード措置を2016年8月から20年3月まで発動する決定をした。これは、中国における鉄鋼の過剰生産により、その在庫が廉価でベトナムに流入したことに起因する。
175 電気電子産業の進展の一方で、基幹部品製造までは至っていないため、結果的に中国からの電子部品等の輸入が増加している。なお、電子製品は小型で単価が高いため、陸路越境輸送が多く利用されている。
③対内直接投資176
対内直接投資(認可ベース)は、2013年以降、200億ドル超と堅調である。投資国別(2015年ベース、以下同じ)では、韓国が1位であり、全体の約29.0%を占めている。業種別では、製造業が1位であり、全体の約68.1%を占めている。なかでも、韓国メーカーによる携帯電話などの電気機器に関する投資が大きい177。その他、TPP協定の発効によるベトナムのメリットを見込み、台湾、韓国、香港等の非参加国・地域からの縫製品への投資が活発化した(第Ⅰ-4-1-4-7図、第Ⅰ-4-1-4-8図)。
第Ⅰ-4-1-4-7図 ベトナムの対内直接投資の推移(国別)
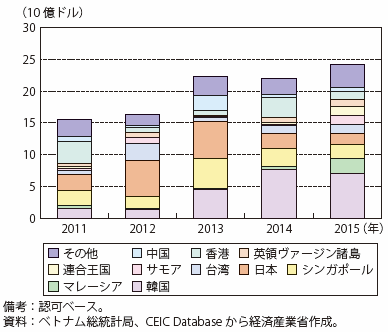
第Ⅰ-4-1-4-8図 ベトナムの対内直接投資の推移(業種別)
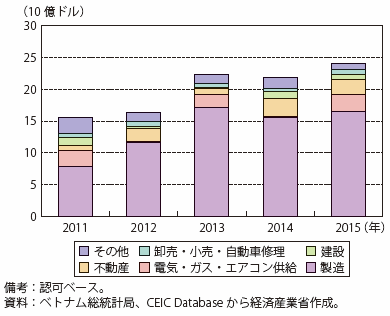
176 同国政府から公表されている対内直接投資額(年ベース)の数値は2015年が最新となる。
177 韓国からの新規投資は、2015年は2014年より金額ベースで減少をしたが、件数ベースでは増加した。韓国の携帯電話メーカーによる大型投資が一巡し、中小規模の部品メーカーを含む周辺産業が拡大したことが要因と考えられる。
④国際収支178
経常収支(2015年ベース)は、9億ドル(GDP比0.5%)の黒字であり、前年の94億ドル(GDP比5.0%)の黒字から大幅に減少した。外資系企業による電子部品などの輸入が増加した一方、水産品など、国内企業の輸出が伸び悩んだことが主たる要因である。また、サービス収支が、訪越旅行客の伸び悩みなどにより悪化したこと、第二次所得収支が、海外労働者送金の減少などにより黒字幅が縮小したことも寄与した(第Ⅰ-4-1-4-9表)。
第Ⅰ-4-1-4-9表 ベトナムの経常収支
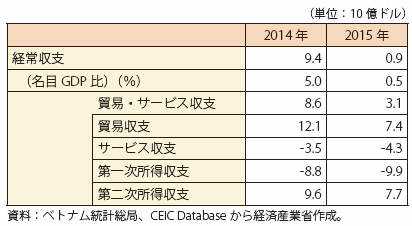
金融収支(2015年ベース)は、前年の28億ドルの増加(資金の流出超)から、76億ドルの減少(資金の流入超)となった。2015年12月に実施された米国による利上げに伴い、中銀が外貨売り介入を行い、ベトナム通貨ドンを買い支えたことにより、外貨準備が60億ドル減少したことが主たる要因である。対内直接投資は、製造業を中心に堅調に推移しており、2015年は、107億ドルの減少(資金の流入超)となった(第Ⅰ-4-1-4-10表)。
第Ⅰ-4-1-4-10表 ベトナムの金融収支
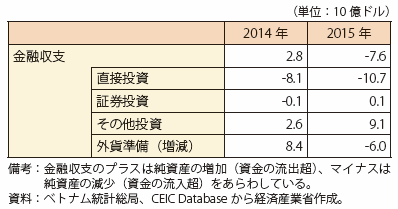
178 同国政府から公表されている経常収支、金融収支の年ベースの数値は2015年が最新となる。
(2)成長を持続するための課題
①国有企業改革の推進
1986年、ドイモイ(刷新)路線が採択されてから約30年間、中央集権的な計画経済から市場経済へ移行が進められてきたが、現在でも、名目GDPに占める国有比率は約28.7%(2015年ベース)と高い水準にある179(第Ⅰ-4-1-4-11図)。国有企業に対する保護政策は、民間企業の参加を阻害し、経済効率性を下げている。同国経済の一層の成長のためには、株式会社化を含めた、国有企業の整理が大きな課題である。政府は、期限付の数値目標をたて、株式会社化を推進しているものの、実際は、国内の利害関係によりなかなか進展していない180。また、株式会社化が実現しても、株式の多くを政府が継続所有するなど、実態が変わらない例も少なくない。
第Ⅰ-4-1-4-11図 ベトナムの名目GDPに対する所有別構成と国有比率の推移

179 2005年の国有比率は37.6%であり、年々低下傾向にはある。
180 2016年、当初計画されていた国内乳業最大手ビナミルクなど、国内有力企業の株式会社化が延期となった。
②銀行の不良債権比率の改善
同国の銀行の不良債権比率は高く、他のASEAN主要国と比較すると最も高い181。この主な要因は、国有企業への貸付である。政府は、2013年、中央銀行の傘下に不良債権処理会社(VAMC)を設立し、不良債権の買取りを開始した。その結果、2015年末には、不良債権比率は2.6%と政府目標である3%を下回ったとされている。しかしながら、不良債権がVAMCに移管されるのみで、VAMCによる売却という最終処理がされたものは、いまだ少ないことが懸念される。
181 世界銀行「WDI」のデータでは、銀行の不良債権比率は、ベトナムが3.4%、インドネシアが3.0%、タイが2.9%、フィリピンが2.0%、マレーシアが1.7%となっている。なお、ベトナムのみ2015年の数値であり、それ以外の国は、2016年の数値である。
③国内裾野産業の育成による輸入依存の脱却
中国や韓国に対する大きな貿易赤字は、同国がグローバルバリューチェーンに組み込まれ、経済成長が拡大している結果ともいえる。しかし、最終製品に組み込む部品などを輸入だけに依存せず、国内裾野産業の育成による内製化を促進することが、持続的成長のために必要である。内製化のためには、自国の技術者や経営者の育成や、外資系企業の進んだ技術を取り入れる技術移転などを政府が推進することが不可欠であろう。なお、2016年、中小企業の定義から、予算、税制、金融といった各種支援、政府調達への配慮まで広範に規定した「中小企業支援法案」が議会に提出された。中小企業支援の財源確保問題が疑問視され、成立には至らなかったが、修正案を2017年の議会に再提出し、2018年の施行を目指している。このような国内企業、とりわけ中小企業の育成策を実際に遂行できるかが大きな課題となっている。
④財政赤字の改善
同国の財政収支は、課税ベースが小さいこと、徴税システムの未成熟などの要因により、赤字が常態化している。財政収支対名目GDP比をASEAN10か国で比較すると、最も悪い水準である182。
同国の財政収支対名目GDP比は、2011年に一旦は改善したものの、2012年、AFTA(ASEAN自由貿易地域)の協定に基づく1,600品目もの関税撤廃実施により、歳入が急減し大幅な赤字となった。それ以降も年々悪化し、2015年の財政収支対名目GDP比183は▲4.6%である。2016年は▲4.3%と若干の改善が見られた。政府は2020年までに▲3.5%とすることを目標としている(第Ⅰ-4-1-4-12図、第Ⅰ-4-1-4-13図)。
第Ⅰ-4-1-4-12図 ベトナムの財政収支の推移
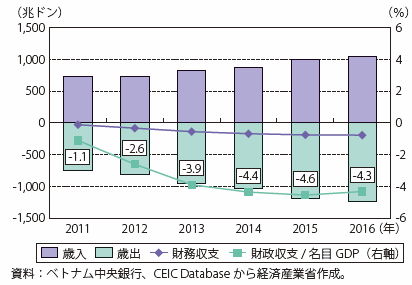
第Ⅰ-4-1-4-13図 ベトナムの財政収支対GDP比の推移(ASEAN主要国との比較)
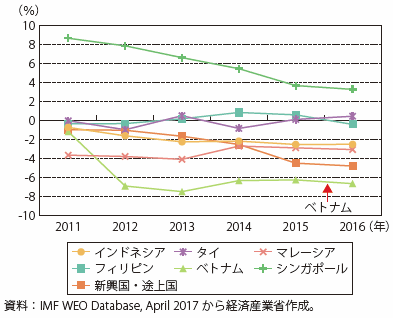
大幅な財政赤字は、通貨の信頼性を低下させ、インフレを生じさせることで、マクロ経済を不安定にしかねない。今後、課税ベースの拡大、徴税システムの改善のほか、長年の課題であるインフラ(特に交通・物流)整備184に、官民協力事業PPP (Public Private Partnership)を積極的に活用するなど、財政改善に向けた取組が必要となっている。
182 IMF WEO Database, October 2016によれば、2012~2014年までベトナムが最下位である。2015年、2016年(推計値)も、原油価格下落の影響を大きく受けたブルネイを除けば、最下位となっている。
183 債務返済を含まない場合で算出している。
184 同国は、北部にハノイ、南部にホーチミンという2大都市があり、およそ1,800km離れているが、それを結ぶ物流インフラが十分ではなく二極化している。
(3)リスク要因
①外資依存型の成長スタイル
成長の源泉を特定の国、企業、モノに過度に依存すると、それらの安定性が揺らいだだけで、国の経済を左右しかねない。例えば、2016年秋、外資系企業の輸出品がリコールとなったことで、同国の輸出における大きな不安定要素となった185。外資系企業の製造業への進出は、雇用創出効果が大きく、同国の内需喚起を支えている大きな要因であるものの、そのメリットを享受しながら、今後は、国、企業(業種)、製品の多様化といったリスク分散を図る必要があろう。
185 2016年10月、韓国サムスン電子は、発火事故が相次いだ新型スマートフォン「ギャラクシーノート7(Galaxy Note 7)」の生産・販売を打ち切った。ベトナム統計総局によると、同社がベトナム工場で生産した同機種250万台を回収したことにより、9月の輸出総額は前月比で▲6.8%減少したとしており、1社の経営状態が1国のマクロ経済に大きな影響を与えうることが見て取れる。
②米国新政権の政策
米国新政権の貿易や移民政策は、同国にとってリスクである。
TPPにより、署名国の中で最もメリットを享受すると試算されていた同国であるが、トランプ大統領がTPP離脱を表明したことにより、先行利益を求めて世界から同国へ流入した投資が、今後どのような動きを見せるか不透明になっている。
ベトナムの輸出依存度(輸出総額/名目GDP、2016年ベース)は92.1%と、インド・ASEAN諸国の中では、シンガポールの111.0%に次いで高く、特に、米国輸出依存度(米国への輸出総額/名目GDP、2016年ベース)は18.6%と一番高い。2006年と2016年の10年間の輸出依存度と対米国輸出依存度の変化を見ると、他国が依存度を軒並み下げている一方、ベトナムは対照的な動きをしていることが分かる(第Ⅰ-4-1-4-14図)。
第Ⅰ-4-1-4-14図 インド・ASEAN主要国の輸出依存度と米国輸出依存度(10年間の変化)
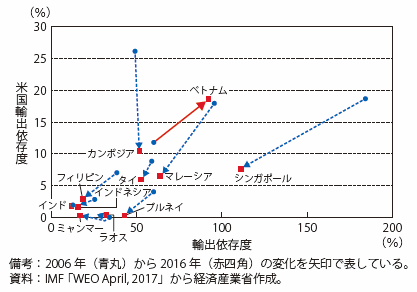
インテルやゼネラル・エレクトリック(GE)等米国企業はベトナムで大きく展開しており、次世代のエンジニアを育成するなどの同国への成長への貢献度も大きい。加えて、越僑は全世界に存在しているが、最も多いのは米国とされており、彼らからベトナムへの送金は同国のGDPに大きく寄与している。
今後、米国新政権が、モノやカネ、人の自由な移動に制約を与えるような施策をとれば、携帯電話、衣料といった主力品の輸出減少、米国企業によってもたらされていた雇用、研修、技術移転の機会喪失、送金減少による内需の低迷等により、成長の勢いをそがれる可能性が懸念される186。
186 このような懸念がある中、2018年の発効を目指すEUとのFTAは、輸出先の多様化といった視点で期待されている。発効へ向け、着実に手続を進めていくことが重要となっている。