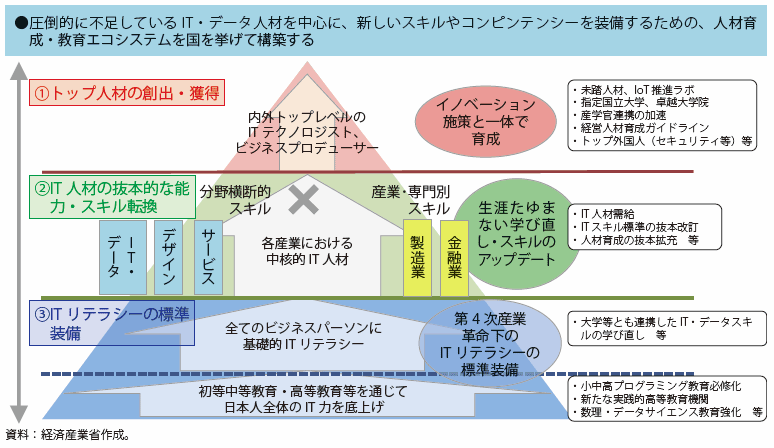第2節 第4次産業革命下の人材・雇用政策
1.第4次産業革命による人材・雇用へのインパクト
第4次産業革命によって、雇用のあり方が大きく変化しようとしている。第4次産業革命によって、①実社会のあらゆる事業・情報が、データ化・ネットワークを通じて自由にやりとり可能になり、②集まった大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で利用可能になった。そのほか、③人工知能によって機械が自ら学習し、人間を超える高度な判断が可能になったほか、④多様かつ複雑な作業についても自動化が可能になった。これらの技術革新によって、これまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能になり、産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性が出てきた。
これらのAIやロボット等テクノロジーの出現により、定型労働に加えて非定型労働においても省人化が進展し、人手不足の解消につながる反面、バックオフィス業務等、我が国の雇用のボリュームゾーンである従来型のミドルスキルのホワイトカラーの仕事は、大きく減少していく可能性が高い。一方で、第4次産業革命によるビジネスプロセスの変化は、ミドルスキルも含めて新たな雇用ニーズを生み出していくため、こうした就業構造の転換に対応した人材育成や、成長分野への労働移動が必要となる。
この議論は、我が国のみならず、世界中で巻き起こりつつある。本年1月に開催されたダボス会議でも主要なテーマとして取り上げられ、第4次産業革命による生産性向上の恩恵だけでなく、雇用への影響についても焦点があたった。昨今の世界的なポピュリズムの高まりの背景には、技術革新から取り残された人々の強い不安がある。参加者からは、継続的な教育(リトレーニング)の重要性や透明性の確保が重要との指摘が相次いだ。また、ドイツの連邦労働社会省(BMAS)は、2030年の労働市場予測を発表し、少子高齢化を見据えて、移民による労働力供給に重点を置いた「ベースシナリオ」と、「インダストリ4.0」を中心としたデジタル化の促進に重点を置いた「デジタル化促進シナリオ」の2つを提示している。このような環境変化を不可逆的なものと捉え、目指すべき将来像を描いていくことが必要となる(第Ⅲ-4-2-1図)。
第Ⅲ-4-2-1図 第4次産業革命による人材・雇用へのインパクト
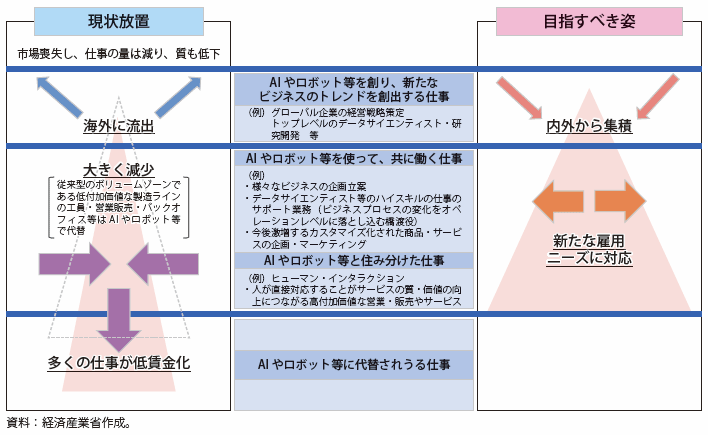
2.2030年代に目指すべき将来像
第4次産業革命や少子高齢化といった構造的な変革のトレンドは、日本企業と人材を取り巻くあらゆる要素に変革を迫る。少子高齢化によって、人口が減少していく日本においては、「働き方の多様化・柔軟化」により労働供給の間口を拡げることと、生産性の向上の両方を追求することが、待ったなしの状況である。また第4次産業革命によって、産業構造は変化し、「ゲームのルール」が“Winner-takes-all”へと移行するとともに、付加価値を生み出す競争力の源泉が、「モノ」や「カネ」から「ヒト(人材)」に移っていく。「未来への投資」である人材への投資によって、働き手ひとりひとりの能力・スキルを産業構造の変化に合わせ、生産性を向上させていくことが重要となる。
このような世界において、「個人」は、付加価値の源泉の変化に対応し、能力・スキルを生涯アップデートし続け、ひとりひとりがプロフェッショナルとしての価値を身につけ、その前提として、市場環境やライフステージの変化に対応しつつ、常に自身のキャリアをリデザインし続ける「キャリア・オーナーシップ」を持つことが重要となる。また、企業は、競争力のコアが「知の源泉たる人材」に移行したとの認識に立ち、多様な能力・スキルを持った人材を惹きつけ、プロジェクト・ベースで付加価値を生み出すシステムを企業活動の中心に据えることが必要となる。そしてそのためには、人材のニーズに応じて場所・時間・契約形態等にとらわれない「柔軟かつ多様な働き方」を取り入れるとともに、職務内容を明確化し、「仕事の内容」や「成果」に応じた評価・処遇を徹底することが重要となる。最後に、社会全体としては、「知の源泉たる人材」を獲得・育成・最適配置するエコシステムを、国全体として構築するとともに、企業が人材教育や保障の多くを提供していた時代が現実には過去のものとなる中、「影」の側面を最小化させるためにも、社会保障制度等の社会システムの刷新が必要となる。
3.政策の方向性
目指すべき将来像へと移行するための最大の鍵は、「人材への投資を通じた生産性向上」とそれを中心とした経済社会システムの改革であり、包括的に政策を推進していくべきである。第4次産業革命で、あらゆる産業でITやデータとの組み合わせが進行する中、我が国の国際競争力を強化し、持続的な経済成長を実現させるためには、ITを駆使しながら創造性や付加価値を発揮し、日本が持つ強みを更に伸ばす人材の育成が急務であり、トップレベル人材、ミドル層のIT専門人材、そして基礎的なITリテラシーを備えたあらゆる企業人、3つの層それぞれについてIT・データ分野を中心とした教育・人材育成を抜本的に強化することが必要である。(第Ⅲ-4-2-2図)
この教育・人材育成の抜本強化にあたっては、下記の4つの視点を念頭にトータルパッケージでの政策を構築していくことが必要となる。
①人生100年時代に対応した、「社会人の生涯学び直し」も含めた教育・人材育成システムの再構築
②学び・働く「個人」に光を当てた支援
③第4次産業革命時代の競争の決め手となる「IT力」への重点化
④産業界の今後のニーズに合致した実践的な能力・スキルを養成するために、全体観をもって産官学の取組を統合
さらに、教育・人材育成の抜本強化を効果的なものとするためには、働く一人ひとりの活力と主体性を引き出し、企業の生産性向上と新しい価値創出力強化に結びつけるための働き方の実現が不可欠である。
具体的には、働き手の能力を有効に発揮させるため、職務や能力等の内容の明確化とそれに基づく公正な評価を推進し、それに則った賃金制度など処遇体系全体を可能な限り速やかに構築していくことが望まれる。加えて、それぞれのライフステージに応じて、副業や雇用関係によらない多様な働き方(フリーランス等)なども、選択肢の一つとして確立していくことが必要となる。また、産業構造が急速に変化していく中で、企業も個人も柔軟かつ迅速に対応していくことが必要であり、生産性・成長性の高い産業への「人の流れ」を実現する労働市場改革も重要である。本年3月にとりまとめられた「働き方改革実行計画」を前提として、「教育・人材育成の抜本拡充」と「働き方改革」を一体として進めて行くことが必要となる。
グローバルな人材獲得競争において優秀な人材を確保し、産業構造の急激な変化に対応し新たな価値創造を実現するためには、ダイバーシティが企業競争力の源泉となる。競争戦略としての意識・取組は道半ばであり、これまでの取組を一段引き上げ、企業の経営力強化の視点から、事業戦略に紐付いた人材・ダイバーシティ戦略の全社的な取組=ダイバーシティ2.0を促していく必要がある。
第Ⅲ-4-2-2図 第4次産業革命の下で求められる人材