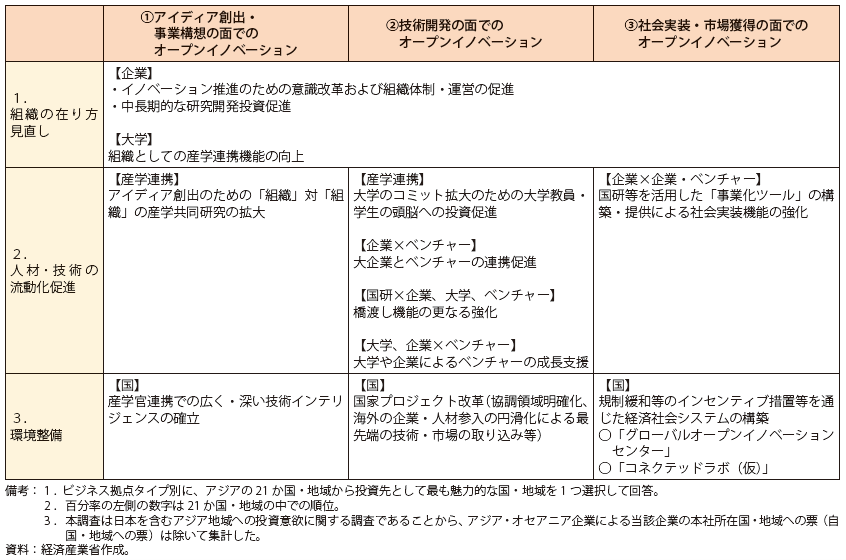第4節 オープンイノベーションの推進
1.イノベーション創出に向けた方向性
近年、グローバル化、市場ニーズの多様化、新興国の台頭を背景として、あらゆる製品、サービスのライフサイクルが短期化しており、企業は、自前の経営資源の限界を打破した戦略を構築し、よりスピード感を持って価値を創出することがますます必要になってきている(第Ⅲ-4-4-1図)。
第Ⅲ-4-4-1図 技術の不確実性の高まり(製品寿命の短期化と技術の加速度的進展)
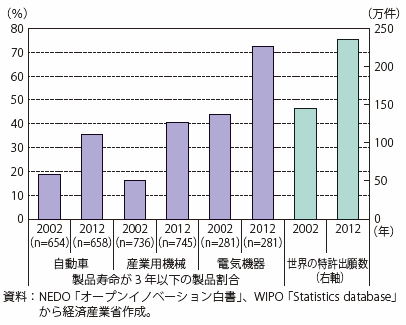
これら現下の状況を踏まえると、イノベーションの創出のためには、日本の持つ「強み」「優位性」を活かした戦略策定の下、国内外問わず優秀な人材・技術を確保・流動化しながら、企業・大学・ベンチャー企業等、プレイヤーの垣根を打破してそれを流動化させ、各プレイヤーが総じて付加価値を創出するためのオープンイノベーション32の推進が重要である。
32 オープンイノベーション:“企業内部と外部のアイディアを有機的に結合させ、価値を創造すること”、であり、①組織の外部で生み出された知識を社内の経営資源と戦略的に組み合わせることと、②社内で活用されていない経営資源を社外で活用することにより、イノベーションを創出すること、の両方を指す。(出典:Henry Chesbrough著、大前恵一郎訳『OPEN INNOVATIONハーバード流イノベーション戦略のすべて』、「一橋ビジネスレビュー オープンイノベーションの衝撃」(東洋経済新報社)2012年9月)
2.オープンイノベーションの重要性と現状
平成27年度経済産業省産業技術調査(企業の研究開発投資性向に関する調査)(以下、「平成27年度企業投資調査」という。)によると、その重要性が増しているにもかかわらず、半数以上の企業が10年前と比較してオープンイノベーションが活発化していない状況である。また、研究開発においても、自社単独のみで開発する割合が61%、事業化されなかった技術等がそのまま死蔵される割合が63%である等、インバウンド、アウトバウンドともにオープンイノベーションが進んでいない(第Ⅲ-4-4-2表、第Ⅲ-4-4-3表)。
第Ⅲ-4-4-2表 研究開発全体における自社単独/外部連携の割合(件数ベース、n=97)
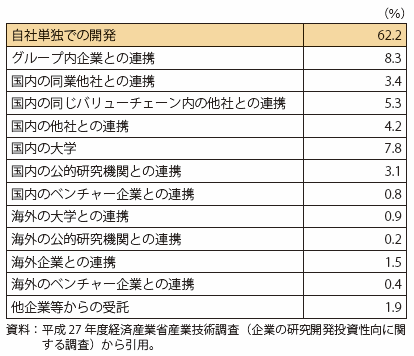
第Ⅲ-4-4-3表 事業化されなかった場合の技術・アイデア等の扱い(n=97)
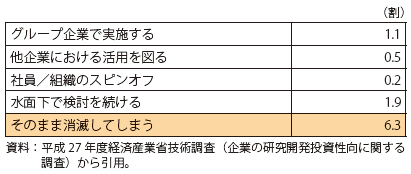
新規事業の創出を実現するためには、大学との連携によってコア技術を尖らせることや、ベンチャー企業が保有する技術などの外部のアイディアを活用することが不可欠かつ効果的であることについて、企業が深く理解することが必要である。また、大学においても、大学で生まれた技術が、企業の活動と連携することで社会実装されることが公益に繋がっていくという考え方の下、積極的に産学連携を進めていくことが重要である(第Ⅱ-4-4-3表)。
3.オープンイノベーション促進のために我が国として行っている施策
経団連提言「産学官連携による共同研究の強化に向けて」(平成28年2月16日)においても企業による大学とのオープンイノベーションの加速への期待が明確化されており、企業によるオープンイノベーションの迅速化・深化に向け、「組織」対「組織」の本格的な産学官連携体制の構築がますます重要になっている。
第5回「未来投資に向けた官民対話」(平成28年4月12日)において、安倍総理は「我が国の大学は、生まれ変わる。産学連携の体制を強化し、企業から大学・研究開発法人への投資を、今後10年間で3倍にふやすことを目指す。」と発言しており、我が国としてもオープンイノベーションを促進させていくために、「グローバルオープンイノベーションセンター」の創設をはじめとした、以下のような施策を行っている(第Ⅲ-4-4-4表)。
第Ⅲ-4-4-4表 我が国のイノベーションを進めるための施策(全体像)