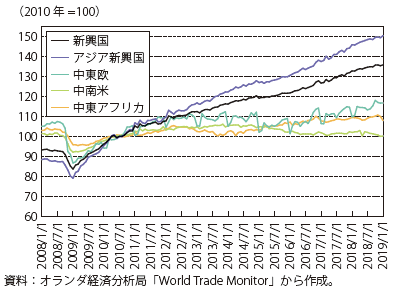- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第1部 第1章 第1節 足下の世界経済動向
第1章 世界経済の動向
第1節 足下の世界経済動向
1.世界GDPの動向
国際通貨基金(IMF)によれば、2018年の世界の実質GDP成長率(以下、成長率)は前年比+3.6%と、2011年以来6年ぶりの高い成長率だった2017年の同+3.8%から低下した(第Ⅰ-1-1-1図)、(第Ⅰ-1-1-2表)。
第Ⅰ-1-1-1図 世界の実質GDP成長率の推移と見通し
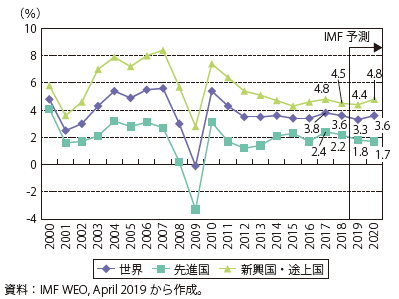
第Ⅰ-1-1-2表 IMFの主要国・地域のGDP成長率見通し
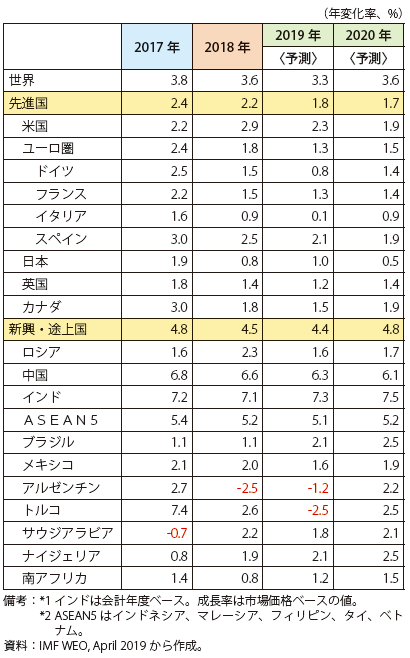
2018年上半期の世界経済は、2017年に引き続き+3.8%と堅調に推移した。しかし、2018年は2017年に見られた世界同時的な回復とは異なり、国・地域により回復の勢いに差が見られた。年後半からは、中国、ドイツやイタリアを含むユーロ圏、一部新興国で弱さが見られた。また、米中貿易摩擦の激化や関税引上げ、企業の景況感の悪化、主要国の金融市場の引締め、英国のEU離脱等の政策の不確実性の高まり等を受け、下半期は同+3.2%と成長の勢いが弱まった。
先進国の成長率は、2018年は前年比+2.2%と2017年の同+2.4%から低下、新興・途上国についても同+4.5%と2017年の同+4.8%から低下した。
今後の世界経済の見通しについてIMFは、2019年前半は伸び悩みの状態が続くが、緩和的なスタンスに転換した主要先進国の金融政策による下支えに加え、中国の景気刺激策、2018年に悪化したアルゼンチンやトルコ等の新興国経済の回復等により、2019年後半から再加速すると見ており、2019年のGDP成長率は前年比+3.3%と2010年以来の最も低い水準になるものの、2020年には同+3.6%に回復すると予測している。
しかし、IMFによれば、この世界の回復の予測はアルゼンチン、トルコ及びその他新興国の経済状態の改善を踏まえたもので、大きな不確実性をはらんでいる。また、先進国については、米国の財政刺激策の効果の剥落とともに徐々に減速を続け、高齢化や生産性の伸び悩みにより、潜在成長率に収斂していくと考えられる。一方で新興国は、中国とインドが世界の経済成長をけん引し、新興国全体として約5%の安定成長が期待されるが、一次産品価格低迷等が一部の国の見通しを弱め、かなりのばらつきが見られると述べている。
成長に対するリスクは依然として下振れが優勢であり、貿易摩擦の激化による政策の不確実性の高まり、市場心理の悪化による安全資産選好、各国金融政策の更なる引締め、中国経済の想定以上の減速、英国の合意なきEU離脱等がリスクとして挙げられる。
世界経済見通しについて、IMFや世界銀行、OECD等の国際機関は定期的に公表している。2018年後半に世界経済の成長リスクが顕在化してきたことから、世界及び主要国の実質GDP成長率の予測を相次いで下方修正した(第Ⅰ-1-1-3表)。
第Ⅰ-1-1-3表 国際機関の世界経済見通し
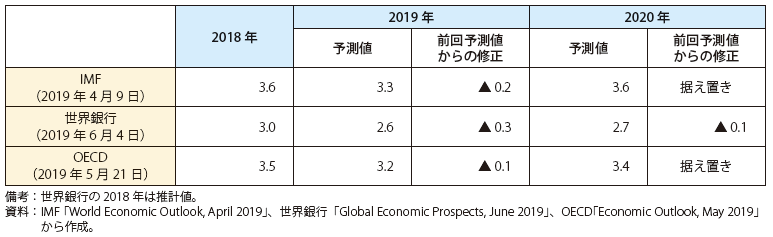
2.財貿易の動向
世界貿易機関(WTO)によると、2018年の世界の財貿易量の伸び率は前年比+3.0%と、6年ぶりの高成長だった2017年の+4.6%から大幅に低下した。
幅広い貿易財に対する関税賦課や報復措置、世界経済の成長の鈍化、金融市場の不安定性や先進国の金融環境の引き締まり等を背景に、2018年第4四半期の落ち込みが顕著となり、貿易の伸びが鈍化した。
地域別で見ると、輸出ではアジアが2017年の+6.8%から2018年は+3.8%へ、欧州が同+3.7%から同+1.6%へと減少した。輸入についても、アジアが同+8.3%から同+5.0%に減少した(第Ⅰ-1-1-4表)。
第Ⅰ-1-1-4表 世界の財貿易量の伸び率と見通し
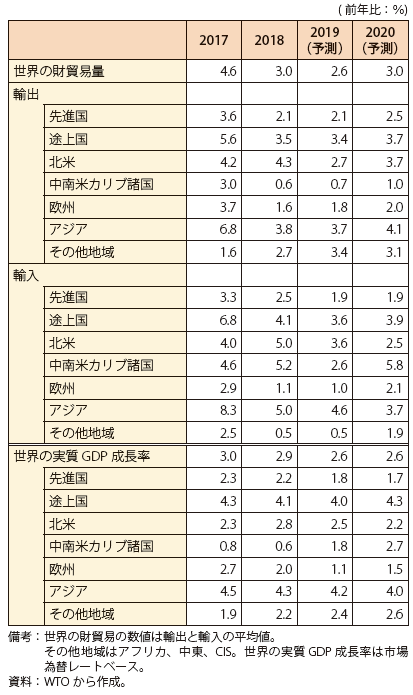
世界の貿易量の伸び率が、世界のGDP成長率と比べて伸び悩む状況は、「スロートレード」と呼ばれ、最近では2012年以降に観測され、世界貿易が経済成長をけん引する力が弱まった状態が2016年まで続いた。しかし、2017年には、貿易量の伸び率と実質GDP成長率の比率が1.5まで回復し、2018年についても貿易の伸び率が+3.0%、GDP成長率が+2.9%1と貿易の伸びがわずかに上回り、2017年に続き、スロートレードの状況が回避された(第Ⅰ-1-1-5図)。
第Ⅰ-1-1-5図 世界貿易量伸び率と実質GDP伸び率の比較
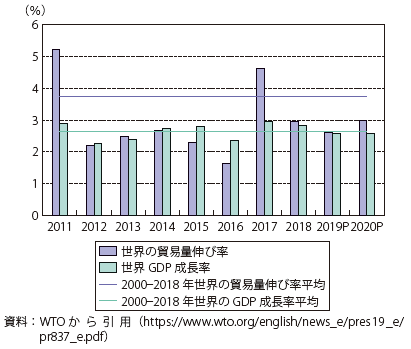
今後の世界貿易の見通しについてWTOは、米中貿易の緊張と経済の不確実性の高まりから、2019年の貿易量の伸びは前年比+2.6%と更に低下するが、2020年には、貿易の緊張が和らぐことを前提に+3.0%まで回復すると見込んでいる。
1 WTOが公表する実質GDP成長率(市場為替ベース)
3.景況感の動向
景気先行指標である世界の購買担当者指数(PMI)を見ると、2018年の世界の製造業PMIは、業況の改善と悪化の分かれ目となる50の水準を上回り推移したが、2018年1月の54.3をピークに徐々に低下を続けた。同PMIは、2019年3月には50.6と、50をわずかに超える水準に留まり、足下の世界の製造業は勢いを失った状態にある(第Ⅰ-1-1-6図)。
地域別では、先進国が2019年3月に50.0と中立水準まで低下し、新興国は3月に51.0と2月の50.6からやや持ち直しを見せている(第Ⅰ-1-1-6図)。
第Ⅰ-1-1-6図 世界の製造業PMIの推移
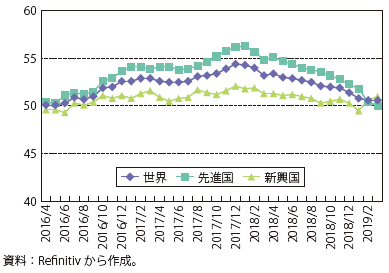
国別に見ると、新興国では、中国が2月49.9から3月は50.8と明確に上昇しており、景気刺激策の効果を指摘する声もある。また中国と貿易関係が強い韓国、台湾、ベトナム等も連動して上昇した。先進国では、ユーロ圏が2月49.3から3月は47.5に悪化し、2か月連続で50を下回った。特にドイツが前月47.6から44.1と低下が著しかった(第Ⅰ-1-1-7図)、(第Ⅰ-1-1-8図)。
第Ⅰ-1-1-7図 主要国・地域の製造業PMIの推移(米国、中国、日本、ユーロ圏、ドイツ)
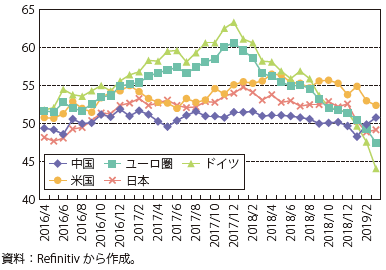
第Ⅰ-1-1-8図 製造業PMI (アジア)
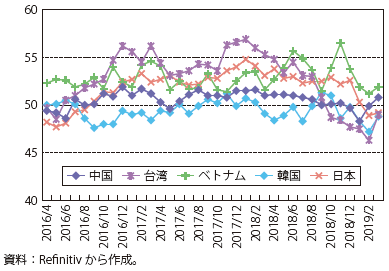
次に2018年の世界のサービス業PMIについて見ると、業況の分かれ目となる50の水準を大きく上回り、低迷が続く製造業とは対照的に、堅調に推移している。
世界のサービス業は、2018年2月の54.8をピークに、伸び率は低下傾向にあったが、2019年2月に53.3、3月53.7と回復を示している。先進国が2月と3月がともに53.7、新興国が2月52.1から3月53.6と上昇しており、サービス業が世界経済の成長をけん引しているといえる(第Ⅰ-1-1-9図)。
第Ⅰ-1-1-9図 世界のサービス業PMIの推移
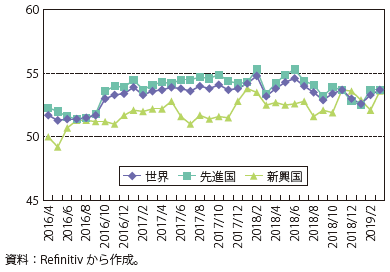
国別に見ると、米国が2018年以降、55近辺の高い水準で推移しており、好調な世界のサービス業を主導している。中国も2018年11月以降、春節の影響で2月に一時的な落ち込みがあったが、54近辺の高い水準で推移しており、好調ぶりが伺える。ドイツは2018年9月以降低下を続けていたが12月から順調に回復し2019年3月には55.4となり、ユーロ圏も連動して高水準の回復を維持している(第Ⅰ-1-1-10図)。
第Ⅰ-1-1-10図 主要国・地域のサービス業PMIの推移(米国、中国、日本、ユーロ圏、ドイツ)
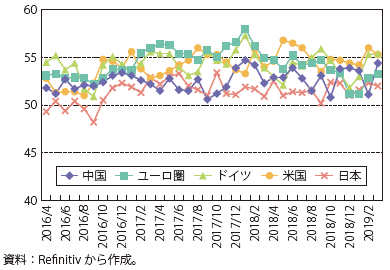
4.サービス貿易の動向
国連貿易開発会議(UNCTAD)及びWTOによると、2018年の世界のサービス貿易額(輸出額ベース)は5兆7,983億ドルで、前年比+7.7%と2017年の+8.4%に続き堅調に増加した。
国・地域別で見るとサービス輸出は米国が8,080億ドルと国別最大で、輸入額も5,360億ドルと国別で最大となった。輸出についてみると、新興国ではエジプト、モロッコ、中国等、先進国ではオランダ、アイルランド、イスラエルが前年比2桁の伸びを示している(第Ⅰ-1-1-11表)。
第Ⅰ-1-1-11表 地域別サービス貿易額の推移
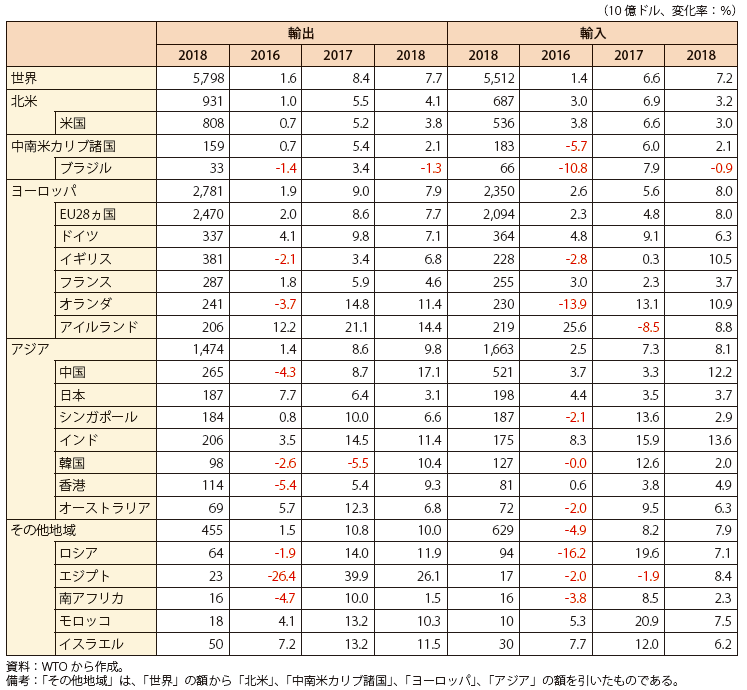
項目別で見ると、全ての項目が増加したが、財関連サービスが前年比+10.6%と大幅に増加し、輸送サービスが+7.1%に減速した(第Ⅰ-1-1-12図)。
第Ⅰ-1-1-12図 世界の項目別サービス貿易の伸び率の推移(輸出額ベース)
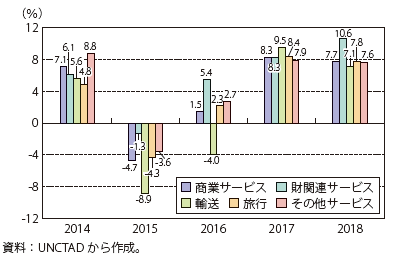
サービス貿易が、財貿易も含めた貿易全体に占める割合(輸出額ベース)は、2011年を底に拡大し、2013年以降は20%以上で推移している(第Ⅰ-1-1-13図)。
第Ⅰ-1-1-13図 サービス貿易の貿易全体に占める割合推移(輸出額ベース)
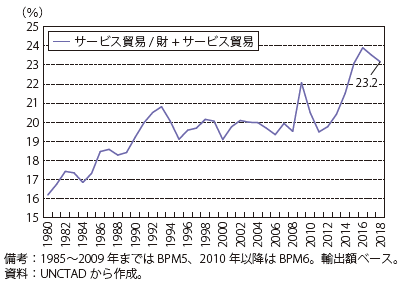
サービス貿易と財貿易(輸出額)の伸び率を比較すると、2018年は、サービス貿易が前年比+7.7%(2017年:+8.3%)、財貿易が同+9.8%(同+10.6%)と2017年に続き、財貿易の拡大がサービス貿易の拡大を上回っているが、いずれも堅調に推移している(第Ⅰ-1-1-14図)。
第Ⅰ-1-1-14図 財貿易とサービス貿易の伸び率推移(輸出額ベース)
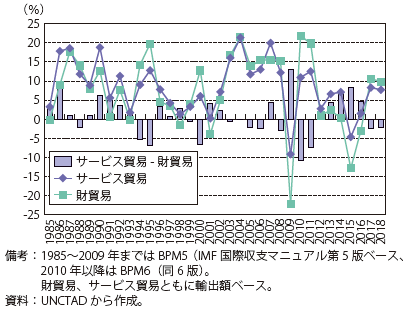
5.鉱工業生産指数の動向
オランダ経済分析局によると、世界の鉱工業生産指数は、新興国については2009年秋に、2008年の世界経済危機以前のピークの水準まで回復し、その後も堅調に推移している(第Ⅰ-1-1-15図)。
第Ⅰ-1-1-15図 鉱工業生産(世界)
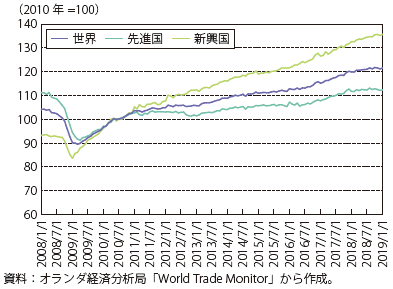
地域別にみると、先進国では、米国が2014年11月をピークに成長が低下したが、2017年9月以降再び堅調に上昇し、先進国の鉱工業生産をけん引している。ユーロ圏では、2010年に発生した欧州債務危機の影響で成長が腰折れしたが、2016年5月以降上昇し、2017年以降は横ばいとなったが、足下では低下が見られる。日本は、2011年の東日本大震災の影響等により大きく低下、その後も低迷が続いていたが、2014年以降はほぼ横ばいで推移し、足下では低下が見られる(第Ⅰ-1-1-16図)。新興国は中国を含むアジア新興国がけん引しているが、中東欧、中東アフリカ、中南米は長期間横ばいで、中南米は停滞している(第Ⅰ-1-1-17図)。
第Ⅰ-1-1-16図 鉱工業生産(先進国)
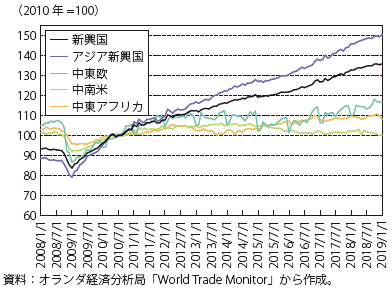
第Ⅰ-1-1-17図 鉱工業生産(新興国)