

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第1部 第2章 第2節 資源価格の動向
第2節 資源価格の動向
資源は、食料や燃料、原材料等として、我々の日常生活や産業活動に不可欠なものであり、資源価格の動向は、資源の輸出国・輸入国双方の貿易収支、生産、物価等、経済活動に重大な影響を与えることから、世界経済の安定的な成長・発展のために、動向を注視していく必要がある。本節では、資源価格と原油価格、並びに原油価格に大きな影響を持つ米国の原油生産の動向について見ていく。
1.資源価格の動向
資源(一次産品)価格は、2014年半ばから、新興国経済の減速やシェール革命による原油供給の増加等により下落し、資源国の経済に影響を与えたが、2015年末から回復傾向に転じた。2017年半ばから2018年前半までは、世界的な景気拡大に伴う資源需要増加への期待から、資源価格は上昇したが、2018年後半には、世界や中国の経済減速による需給の緩和、米中貿易摩擦による通商政策の先行きへの懸念等により、価格の動きは不安定となった30(第Ⅰ-2-2-1図)。
第Ⅰ-2-2-1図 資源価格の推移
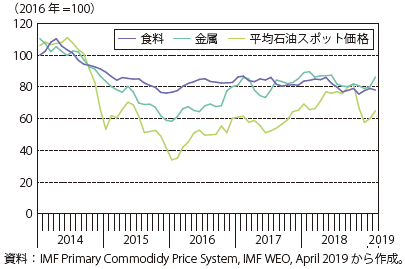
資源価格の下落は、資源輸出国と資源輸入国に異なる影響を与える。輸出国にとっては、対外収支や財政収支の悪化を招き、通貨下落やインフレを伴う。さらには資本の流出により深刻な景気後退を招く可能性が懸念される。他方、資源輸入国にとっては、対外収支や財政収支の改善やインフレ圧力の低下、個人消費や投資、企業収益等の改善も期待され、成長の後押しに寄与すると考えられる31。
最近の一次産品市場の動向について、世界銀行は、「2018年に個別の一次産品への関税とブロードベースの関税の両方が課されたことにより、貿易フローが減少又は変動し、一部の国の間では大豆、鉄鋼、アルミニウムなどの一次産品の価格差が広がった。さらに全般的には、世界規模の貿易の脆弱化及び成長見通しの引き下げについての懸念が生じている」32と指摘。「一次産品価格の見通しは、追加関税や制裁の可能性などの政策関連のリスクが多数あることから非常に不透明」と述べている。
30 2018年後半でみるとエネルギーは上昇の後に急落、金属はわずかに上昇、食料はほぼ横ばいと、品目により動きはまちまちだった。
31 IMFは15年4月に発表した「世界経済見通し(WEO)」の中で、原油価格の下落により、世界のGDPは15年に0.5~0.74%、16年には0.54~0.92%押し上げられるとのシミュレーション結果を紹介し、資源安(特に原油安)は世界経済にネットでプラスの影響を与えると予測した。
32 World Bank, Commodity Markets Outlook, Octoberb 2018年
2.原油価格の動向
原油価格(WTI原油先物価格)は、2011年以降1バレル100ドル近辺で高止まりしていたが、世界経済の減速懸念の高まりで需要が伸び悩む中、米国産シェールオイルの増産で原油が供給超過となったことを背景に、2014年7月以降下落基調となり、11月に石油輸出機構(OPEC)総会で減産が見送られたことを受け、12月半ばに一時53ドル台、更に2015年1月に44ドル台に急落した。
その後、20ドル台後半まで値下がりし、低価格で推移していたが、2017年には、世界的な景気拡大による需要の増大やOPECプラス(OPEC加盟国と非OPEC加盟国)による協調減産の効果から、年初の50ドル前半から年末には60ドル近辺までに上昇した。さらに、2018年は、年初に60ドル台半ばまで上昇し、米国株価下落の影響により2月と3月前半は一時的に弱含んだものの、5月に米国がイランに対する制裁再開を表明したこと等から再び上昇に転じた。また6月のOPEC総会で協調減産の一部緩和が合意された33ことで、市場は産油国の増産余力の減少を懸念し始め、10月3日には一時76ドル90セントと約4年ぶりの高値をつけた。経済危機に陥ったベネズエラや国内混乱が続くリビアからの供給減少等も価格上昇の要因となったと言われる。
2018年10月には、米国の金利上昇、米中貿易摩擦、政策の不透明性の高まりにより米国株式市場が大きく下落し世界同時株安が発生34、また11月5日には米国のイランへの経済制裁が再開されたものの、原油輸出については日本や中国を含む8か国・地域に対して180日間の猶予期間が設けられ、供給不安が後退したこと等により、原油価格は低下を始め、12月末には43ドル前半まで大幅に下落した(第Ⅰ-2-2-2図)。
第Ⅰ-2-2-2図 原油価格の推移(2014年以降)
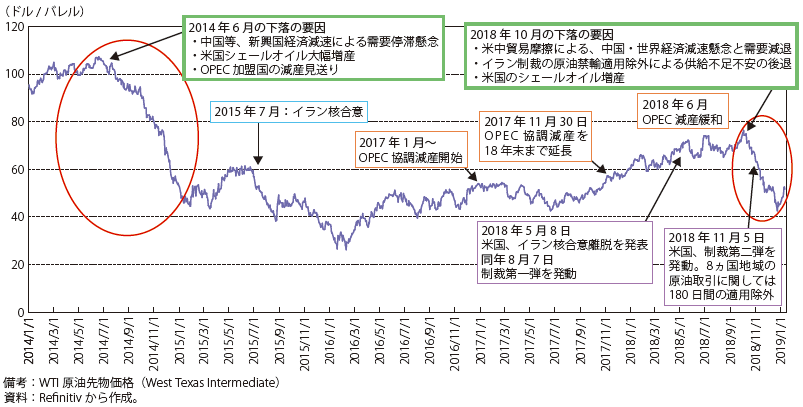
こうした下落の局面下で、2018年12月7日、OPECと非OPEC加盟国の合同閣僚級会合が開催され、2019年1月から6カ月間、日量120万バレル(OEPC諸国80万バレル、非OPEC同40万バレル)の減産について合意され、供給過剰感は徐々に後退していることから、足下(2019年3月)の原油価格は50ドル台で推移している(第Ⅰ-2-2-3表)。
第Ⅰ-2-2-3表 OPECプラスの減産合意の国別目標(2019年1月~6月)
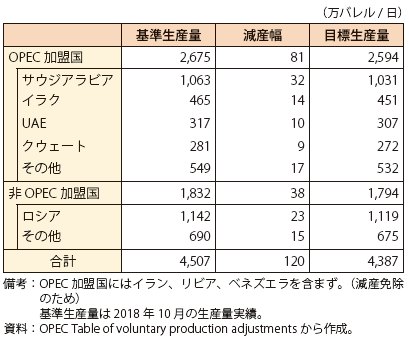
33 2017年1月から日量180万バレルの協調減産をしてきたが、実際には280万バレル規模で減産されていた。閣僚会合の場では具体的な緩和幅は明示されなかった。
34 10月10日の米国株式市場は、NYダウが前日比831ドルと急落。しかし急落の引き金となるような出来事は見当たらず、投資家の利益確定の側面が強いと考えられている。
3.米国の原油生産の動向
2000年代後半に起きた「シェール革命」により、米国の原油生産量は急激に増大し、米国の生産動向が原油価格に与える影響が大きくなっている。以下では米国の原油生産の動向について概観する。
米国エネルギー情報局(EIA)によると、2018年の米国の原油生産量は日量1,095万バレルと前年より約17%増加し、ロシアとサウジアラビアを上回り、1973年以来45年ぶりに世界最大の原油生産国となった(第Ⅰ-2-2-4図)。トランプ政権はエネルギーの国内生産拡大が雇用を創出すると主張し、規制緩和によりシェールオイルの増産を促してきた35。EIAは米国の生産量の増加は2027年まで続き、最大で日量1,400万バレル台に達すると予測している(第Ⅰ-2-2-5表)。
第Ⅰ-2-2-4図 世界の原油生産量の推移(国別)
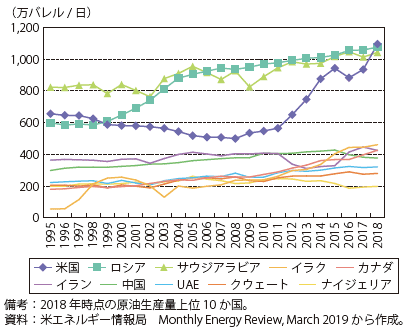
第Ⅰ-2-2-5表 米国EIAの国・地域別原油及び液体燃料生産量と見通し
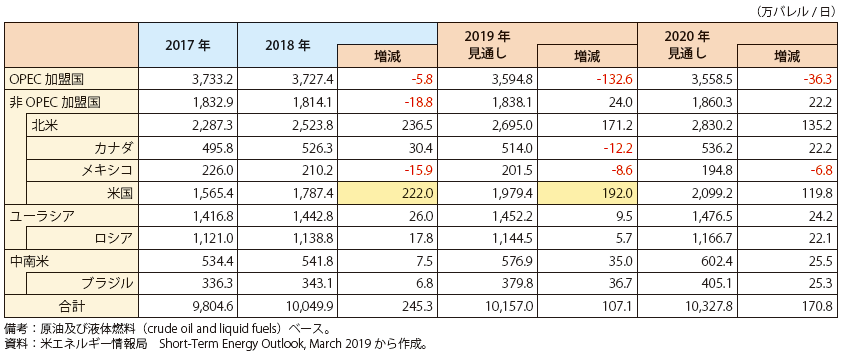
また、原油の生産量の増加により、輸出量も増加しており、輸入量から輸出量を差し引いた純輸入量は減少を続けている。国際エネルギー機関(IEA)は、2024年に米国の石油輸出量はロシアを抜き、サウジアラビアに次ぐ世界第二位になると予測している(第Ⅰ-2-2-6図)。
第Ⅰ-2-2-6図 米国の石油輸出入量の推移
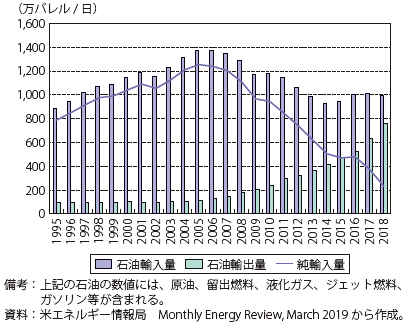
米国の原油生産はシェール開発の進展を背景に増加を続けているが、米国最大の油田地帯であるパーミアン地区のパイプラインの輸送不足問題の解消により、今後供給能力は一層向上する見込みである。米国のシェール主要7鉱区のシェールオイル生産量は18年12月時点で日量823万バレルと米国の原油生産量の約7割を占め、そのうちの5割弱をパーミアン地区が生産している(第Ⅰ-2-2-7図)。
第Ⅰ-2-2-7図 米国のシェールオイル生産量の推移(地区別)
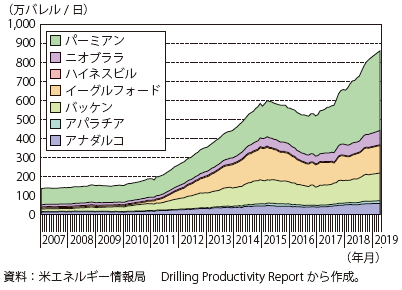
原油生産の水準を示す石油掘削装置(リグ)稼働数は、原油価格に連動して増減し、足下では、ほぼ横ばいで推移している。油井の質や輸送距離によっても異なるが、シェールオイルの採算ラインは1バレル50ドル前後36とされ、掘削技術の向上等で年々下がってきていると言われている37(第Ⅰ-2-2-8図)。
第Ⅰ-2-2-8図 米国のシェールリグ稼働数の推移
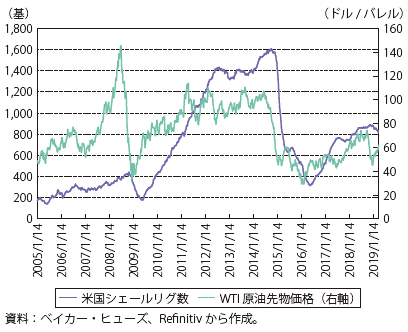
既に見てきたように、OPECは、世界の原油需給を均衡させるため、ロシア等の主要非OPEC加盟国と協調し、原油の減産を実施しているが、世界の石油生産に占めるOPECのシェアは約4割38まで低下しており、OPECの減産計画を上回る規模で、米国の生産が拡大していることから、米国の存在感が高まる中で、OPECの影響力の低下が想定される。また、トランプ大統領は、OPECが減産により原油価格を引き上げているとツイッターで非難し、増産による価格の抑制を求めている。
2019年については、OPECとロシア等OPEC非加盟国が協調し、1月から日量120万バレルの減産が開始されていることに加え、5月には米国のイラン制裁の適用除外の期限を迎え、制裁の再開で相当量の原油輸出が制限される可能性がある。また、ベネズエラ情勢の混乱等もあり、供給面での不確実性は高まっている。その一方で米国のシェールオイルの増産は続き、世界の原油供給は需要を上回る状況が続くと予想される(第Ⅰ-2-2-9図)。
第Ⅰ-2-2-9図 IEAの世界の原油需給量の推移
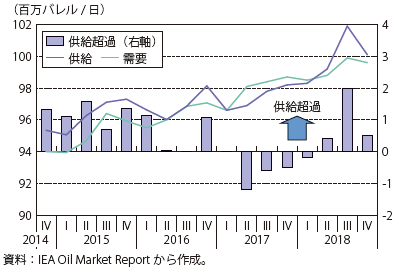
35 トランプ政権は、「アメリカ第一主義のエネルギー計画(An America First Energy Plan)」の中で、「シェール革命により何百万人のアメリカ人に雇用と繁栄をもたらす。」「50兆ドル程度と考えられる未開発のシェールガスおよびシェールオイルを自国民のために活用する。」と述べている。
36 ダラス連銀が2019年3月13‐21日に管内に拠点または本社を置く石油・ガス会社160社に実施したアンケート調査の結果を参考にした。(Dallas Fed Energy Survey, First Quarter, March 27, 2019)
37 シェール企業は過去、相場が上昇基調に乗ると機動的にリグを増やしてきたが、生産量に表れるまで数カ月はかかり、タイムラグが生じる。
38 2018年時点でOPECのシェアは43.6%(EIAのデータから計算)。
