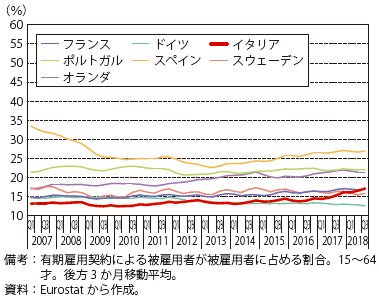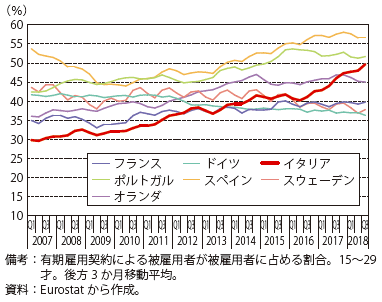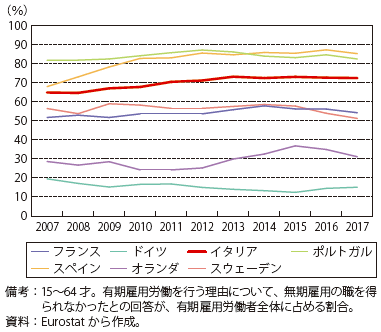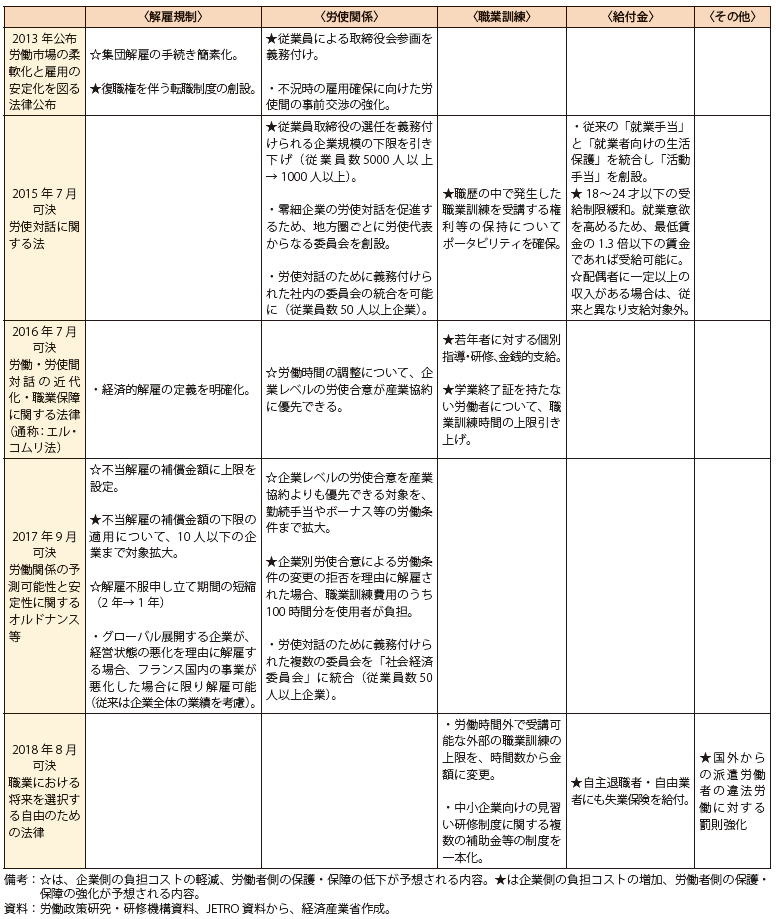- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第1部 第3章 第2節 欧州
第2節 欧州
1.ユーロ圏経済
(1)概況
2017年の好景気から一転、ユーロ圏経済は2018年に入り鈍化した。
2018年初頭における経済減速は、悪天候やストライキ等の一時的要因が重なったものであったが、米国による鉄鋼・アルミの輸入関税引上げをきっかけに始まった貿易摩擦が、第2四半期以降、域内経済に影を落としている。
2018年の実質GDP成長率は、通年で1.8%増と前年より鈍化した。鈍化の要因としては、需要項目別では、輸出に加え、家計消費と総固定資本形成の低迷が挙げられる(第Ⅰ-3-2-1図)。
第Ⅰ-3-2-1図 ユーロ圏の実質GDP成長率(需要項目別寄与度)
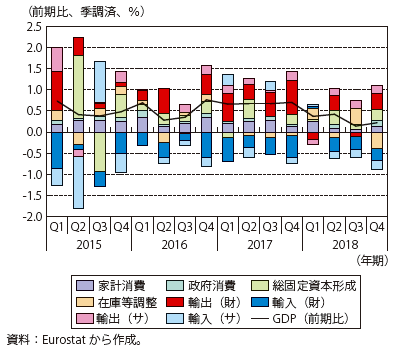
セクター別では、製造業の縮小に加えて、サービス関連セクターにおける勢いの弱まりが見られる(第Ⅰ- 3-2-2図)。
第Ⅰ-3-2-2図 ユーロ圏の実質付加価値成長率(産業別寄与度)
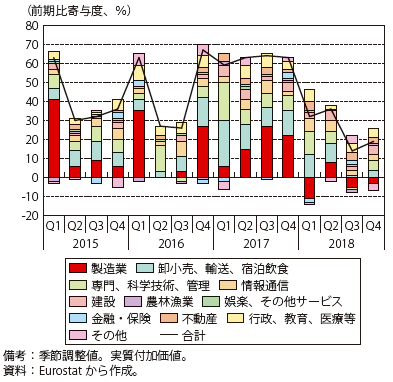
製造業の縮小については、自動車セクターにおける新燃費測定基準(WLTP)への対応の遅れや、河川の水位低下による物流遮断といった一時的要因があったと見られているが、新興国経済の減速や、先行き不透明感による企業マインドの低下も影響していると考えられ、こうした要素が引き続き域内経済を下押しする可能性が懸念されている。
ユーロ圏の経済信頼感指数は、前年までの顕著な改善傾向が、2018年に入り、一転して悪化傾向となっている。中でも製造業については2019年に入っても悪化の歯止めがかからず、米国をめぐる貿易摩擦及び英国のEU離脱をめぐる先行き不透明感が、企業の信頼感を下押ししている可能性が指摘されている(第Ⅰ-3-2-3図)。
第Ⅰ-3-2-3図 ユーロ圏の景況感(業種別)
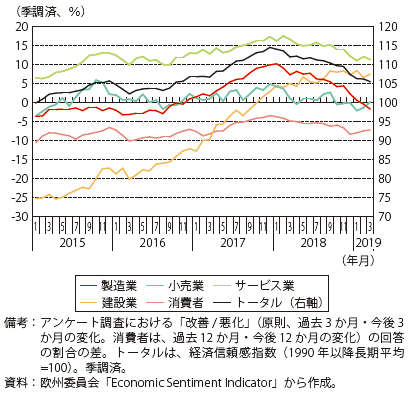
国別に見ると、ドイツは、自動車の新燃費測定基準への対応の遅れにより生産が縮小したことで、実質GDP成長率は、第3四半期に前期比0.2%減とマイナスを記録した(第Ⅰ-3-2-4図)。経済信頼感については、2018年3月以降、顕著に悪化しており(第Ⅰ-3-2-5図)、貿易摩擦や英国のEU離脱をめぐる先行き不透明感が企業マインドを下押ししている可能性が指摘されている。
第Ⅰ-3-2-4図 ユーロ圏諸国と英国の実質GDP成長率(前期比)
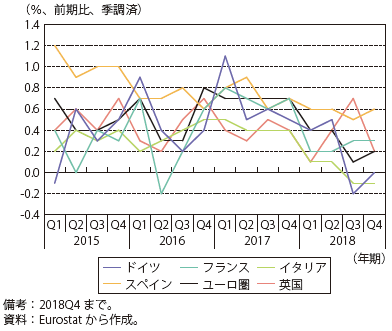
第Ⅰ-3-2-5図 ユーロ圏主要国の経済信頼感指数
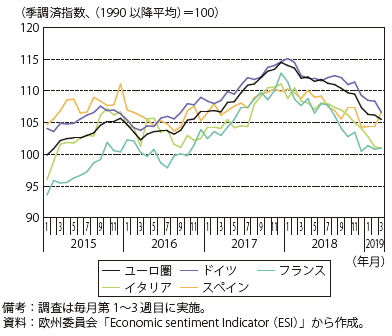
フランスについては、実質GDP成長率が第1四半期に大きく鈍化したものの、第3四半期以降、輸出や総固定資本形成の伸びにより緩やかに加速した(第Ⅰ- 3-2-6図)。ただし、経済信頼感指数は2018年夏以降、大きく悪化している。特に、燃料税引上げへの反発から発生した黄色いベスト運動は、11月以降、同国の経済信頼感を下押しした可能性がある。
第Ⅰ-3-2-6図 ユーロ圏諸国の総固定資本形成推移
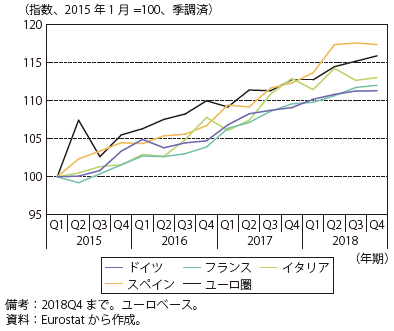
イタリアについては、下半期に景気後退(実質GDP成長率が前期比で2期連続のマイナス)に陥った。主な輸出相手国の経済減退が輸出に影響したほか、国内の政治的混乱等を背景に企業マインドが幅広いセクターで低迷していると見られている。
スペインについては、2017年に比べ減速しているものの、実質GDP成長率は、通年で2.6%とユーロ圏平均を大きく上回る成長率を維持している。
(2)生産及び貿易
ユーロ圏の鉱工業生産指数は、2017年までの拡大傾向から一転、2018年に入り減少傾向で推移している(第Ⅰ-3-2-7図)。2018年年初は寒波やユーロの上昇が影響したと見られるが、8月以降は、自動車セクターにおける新規制への対応の遅れから、ドイツを中心に自動車製造業の生産が顕著に落ち込んだ(第Ⅰ- 3-2-8図)。さらに、河川の水位低下により物流が遮断されたことで、秋以降は、やはりドイツを中心に、化学品製造業の生産に大きな影響が生じた。
第Ⅰ-3-2-7図 ユーロ圏の鉱工業生産指数
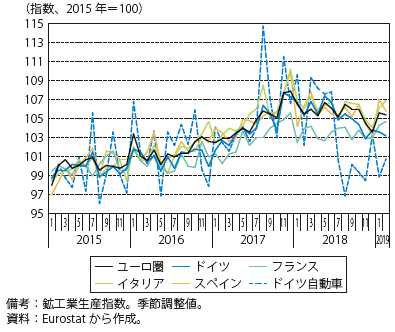
第Ⅰ-3-2-8図 ドイツの生産指数(製造業業種別)
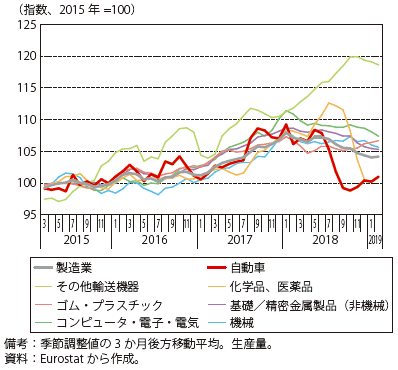
ただし、自動車や化学品製造業以外でも、2017年までの拡大傾向は既にほとんど見られない(第Ⅰ-3-2-9図)。輸出受注は2018年秋以降、悪化が続いており(第Ⅰ-3-2-10図)、ユーロ圏域内を含む世界経済の減速による影響が示唆される。
第Ⅰ-3-2-9図 ユーロ圏の生産指数(製造業業種別)
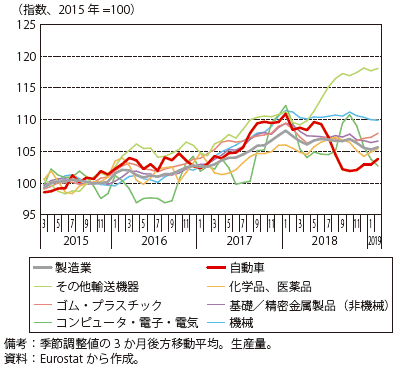
第Ⅰ-3-2-10図 ユーロ圏製造業の景況感
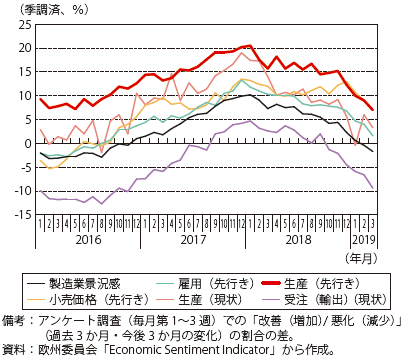
ユーロ圏の輸出を相手国別に見ると、2018年に入り、主要貿易相手国であるトルコ向けの減少と中国向けの伸びの鈍化が顕著である(第Ⅰ-3-2-11図、第Ⅰ-3-2-12図)。
第Ⅰ-3-2-11図 ユーロ圏の輸出(相手先別寄与度)
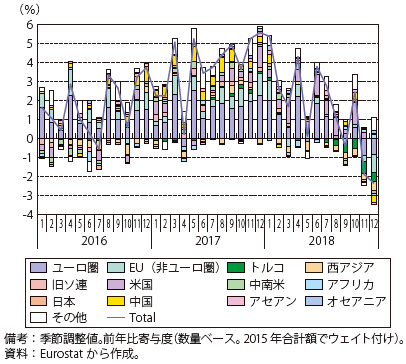
第Ⅰ-3-2-12図 ユーロ圏の輸出伸び率(相手先別)
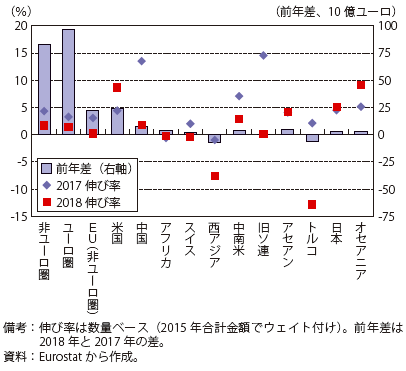
トルコは、8月に生じたトルコ・ショック(通貨リラの大幅な下落による金融市場の動揺)の影響により内需が大幅に悪化した。また中国については、2018年初頭からの景気減速に、米国との貿易摩擦も加わり、2018年は5月以降、生産が減少している。こうした主な貿易相手国における需要の減退が、ユーロ圏の輸出と生産に影響したと考えられる(第Ⅰ-3-2-13図)。
第Ⅰ-3-2-13図 ユーロ圏の輸出に占める各国の割合
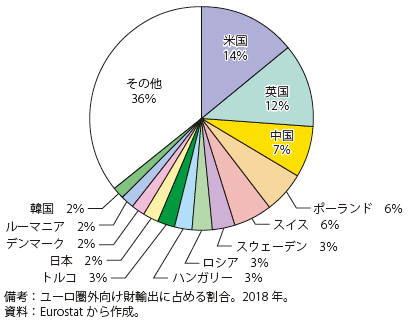
品目別に見ると、ユーロ圏域内向けの輸出は、2018年夏以降の機械・輸送機器の減少が顕著である。また、素材系製造品やその他製造品も伸びが鈍化している(第Ⅰ-3-2-14図)。また、ユーロ圏域外向けについては、2018年初頭に大きく落ち込んだ後は低い伸び率で推移し、秋以降は再び伸びが鈍化した(第Ⅰ-3-2-15図)。
第Ⅰ-3-2-14図 ユーロ圏の輸出(域内向け・品目別)
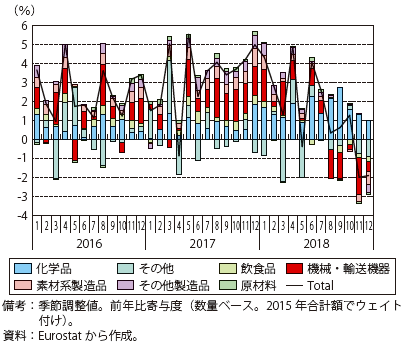
第Ⅰ-3-2-15図 ユーロ圏の輸出(域外向け・品目別)
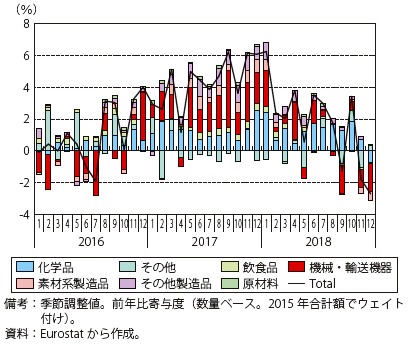
トルコ向けの輸出は、機械・輸送機器が2018年7月以降、大幅に減少したほか、飲食品、化学品、また素材系製造品と幅広い分野で減少しており、産業全体でトルコの需要が減少したことが明らかである(第Ⅰ-3-2-16図)。
第Ⅰ-3-2-16図 ユーロ圏の輸出(トルコ向け・品目別)
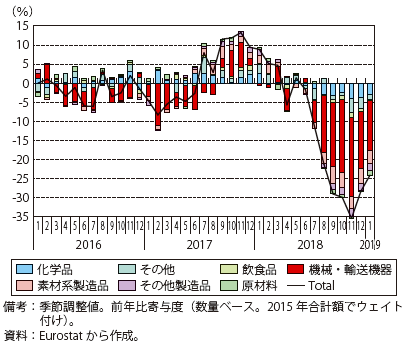
中国向けの輸出については、2018年上半期に伸びが大幅に落ちたが、9月以降は中国政府による景気支援策の効果もあり、回復が見られる(第Ⅰ-3-2-17図)。
第Ⅰ-3-2-17図 ユーロ圏の輸出(中国向け・品目別)
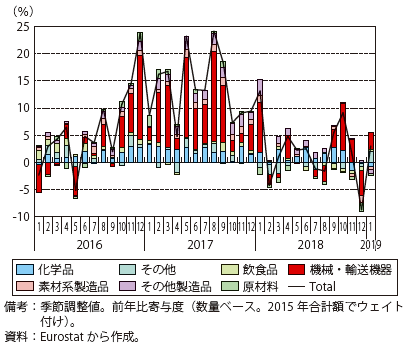
一方、米国は2018年3月以降、EUを含め世界各国から輸入する鉄鋼・アルミニウムについて関税を引上げた。これに対し、欧州委員会は2018年3月から実施していた鉄鋼に関するセーフガード調査の結果において、米国の輸入関税引上げによって、従来第三国から米国に輸出されていた鉄鋼の一部がEUに流れた結果、EU域内産業への脅威となっていると判断している。これを踏まえ、2019年2月2日から鉄鋼輸入に関わるセーフガード措置の確定措置64を発動した。実際に、EUへの鉄鋼輸入は2018年に前年より増加している。
なお、米国との貿易摩擦が関係するセクターとして、他に自動車がある。EUは2018年6月、米国の鉄鋼・アルミニウムの輸入関税率引上げに対する報復関税措置の形で、米国からの輸入品の一部について関税率を引上げたが、米国は、これを受けてさらに、EUが貿易障壁を取り除かない場合、EUからの輸入自動車に対して20%65の関税を課すと表明した。
その後、米国トランプ大統領とユンカー欧州委員長による、通商協力を内容とする共同声明66(7月25日発出)において、相互の関税撤廃に向けて協力する対象品目から自動車は除外された。さらに2019年2月、米国商務省は、通商拡大法232条に基づく自動車関税に関する報告書をトランプ大統領に提出し、これを受けて2019年5月、トランプ大統領は通商代表に対してEU、日本及びその他通商代表が適切とみなす国との合意の交渉を追求し、180日以内に交渉結果について報告することを指示する大統領令を発出した。トランプ大統領がこの報告書を受けて、自動車の輸入関税を引上げる可能性は不明だが、米国向けの自動車輸出は、特にドイツの自動車輸出における比重が大きく67、仮に米国が自動車の関税を引上げた場合には、鉄鋼とアルミニウムに対する関税引上げ以上の大きな経済的影響が生じると見られている。
最大の貿易相手国である米国と中国をめぐる貿易摩擦の悪化は、中国向け輸出の伸びの鈍化という形で、既にユーロ圏製造業に影響を与えているが、さらにEUの米国向け自動車輸出における関税引上げの可能性は、英国のEU離脱と相まって、先行き見通しに関する不透明感を高め、企業のマインドを悪化させている。
64 暫定措置は2018年7月19日から発動されていた。
65 その後、米国トランプ大統領は、通商拡大法232条に基づき、輸入自動車と自動車部品に最大25%の関税を課す可能性を示している。
66 欧州委員会「2018年7月25日プレスリリース」、(http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm![]() )。
)。
67 米国向け自動車輸出は、ドイツの自動車輸出の15%、財輸出の1.6%、名目GDPの0.6%を占める。
(3)雇用
ユーロ圏の雇用は堅調に推移している。2013年に11%に達していた失業率は、欧州債務危機後に経済が回復する中で、スペイン、ギリシャ、ポルトガルを中心に顕著に低下し、2018年11月には8%を下回った(第Ⅰ-3-2-18図)。被雇用者数も、ユーロ圏経済の回復とともに、2013年以降、緩やかに増加している(第Ⅰ-3-2-19図)。
第Ⅰ-3-2-18図 ユーロ圏の失業率推移
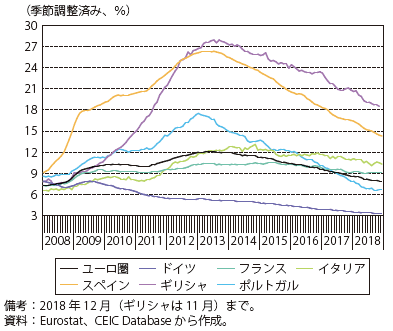
第Ⅰ-3-2-19図 ユーロ圏の被雇用者数推移
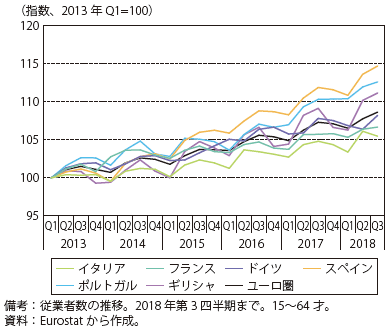
しかし、南欧諸国では、若者を中心に失業率が高い年齢層が見られる(第Ⅰ-3-2-20図)。特に、イタリアの若年失業率はなかなか低下せず、2018年末には、着実に若年失業率を低下させてきたスペインがほぼ同率となった(第Ⅰ-3-2-21図)。
第Ⅰ-3-2-20図 ユーロ圏諸国の失業率(年齢別)
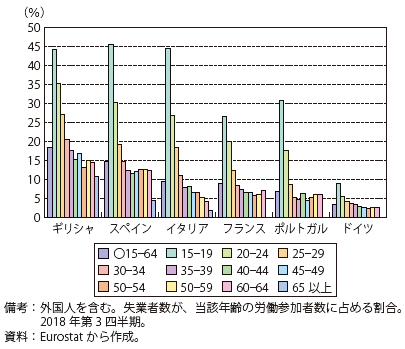
第Ⅰ-3-2-21図 ユーロ圏諸国の若年失業率の推移
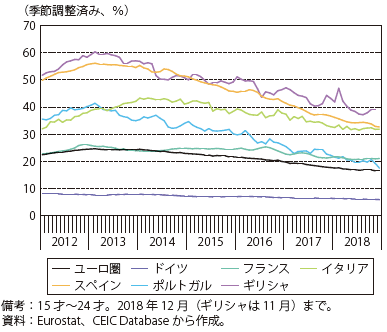
なお、移民労働者が全体の失業率を押し上げている可能性や、さらに、高等教育課程への在籍期間や学生割合の違いを排除するため、外国人を除き、年齢層を25才以上に絞って確認すると(第Ⅰ-3-2-22図)、ギリシャ(複数の年齢層)に加え、イタリアとスペインの25~29才の年齢層において、失業率が15%を超えている。さらにイタリアは、被雇用者が同年齢層の人口に占める割合において、25~29才で僅か54%、30~34才でも70%とギリシャと並んで低く(第Ⅰ-3-2-23図)、貧困率においてもEU平均を大きく上回っている(第Ⅰ-3-2-24図)。
第Ⅰ-3-2-22図 ユーロ圏諸国の失業率(外国人を除く)
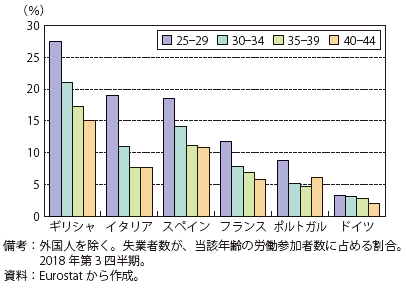
第Ⅰ-3-2-23図 ユーロ圏諸国の被雇用者の割合(外国人を除く)
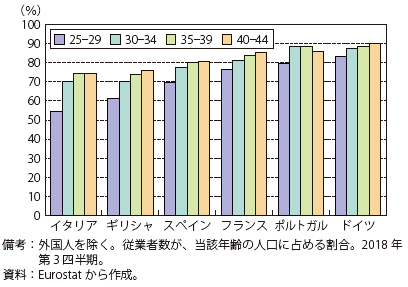
第Ⅰ-3-2-24図 EU各国の貧困率(年齢層別)
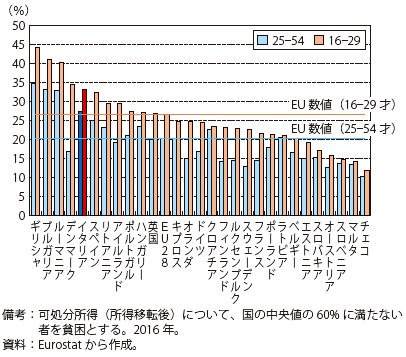
(4)イタリアとフランスの財政問題
イタリアでは、2018年6月、イタリア・ファーストを掲げる「五つ星運動」及び「同盟」からなる連立政権が誕生した。政権公約では、移民対策のほかに、税制、年金、雇用対策といった財政拡張型の政策が多く盛り込まれた。具体的には、税制に関しては、家計と企業に対する一律の所得税(フラット・タックス)の導入、及び付加価値税の自動引上げの停止、雇用に関しては、失業者の労働市場復帰のための「国民の所得」の導入、年金に関しては、年金受給年齢引上げを定めた「フォルネロ法」の廃止、実年齢と年金保険料支払年数の合計が100に達した時点での需給開始、等である。
政権公約を全て実現した場合、財政赤字は対GDP比で3%を大きく上回ると考えられ、財政を監視する欧州委員会と同国が対立する可能性や、最悪の場合、対立の悪化により同国のユーロ圏離脱につながる可能性が懸念された。
10月に連立政権が欧州委員会に提出した2019年度予算案には、上記「国民の所得」や年金改革といった財政支出が盛り込まれ、財政赤字比率は2.4%となり、EUの財政赤字基準である3%を下回ったが、前政権が約束していた0.8%を大幅に上回った(第Ⅰ-3-2-25図、第Ⅰ-3-2-26表)。
第Ⅰ-3-2-25図 イタリアの財政収支比率
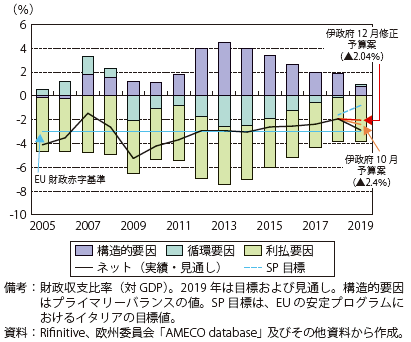
第Ⅰ-3-2-26表 ユーロ圏各国の財政赤字目標68
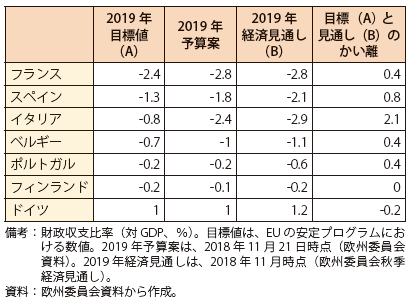
一度修正予算案が提出された後、欧州委員会は、EUの財政規律を大きく逸脱するものであるとして再度差戻し、「過剰財政赤字の是正手続(EDP)」を開始するための報告書69を公表するに至った。
一時はEDPに基づく制裁の発動も懸念され、イタリアの国債利回りが上昇するなど金融市場の緊張が見られたが(第Ⅰ-3-2-27図)、12月に入り、同国政府は財政赤字比率を2.04%にまで引下げた再修正予算案を提出し、これをEU側も受入れることで制裁措置の発動は回避された。
第Ⅰ-3-2-27図 南欧諸国の国債利回り推移
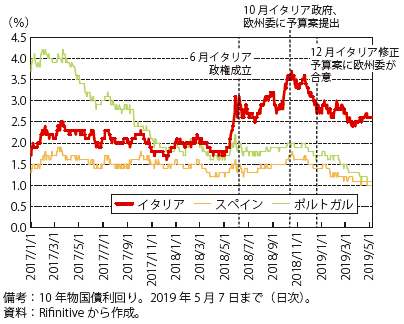
ただし、同国の具体的な財政赤字削減策は明らかにされておらず、財政状況に対する懸念は引き続き同国の国債利回りを押し上げている。資金調達環境の悪化を通じて、多くの不良債権を抱える中小規模の銀行の負担が拡大する可能性を懸念する声もある。
EUでは、財政規律の形骸化が欧州債務危機を引き起こした反省から、2011年に、財政規律の厳格化や監視・運営の強化が図られた70。ただし、欧州経済の回復が遅れる中で、緊縮財政によるネガティブな側面を回避する必要性が指摘され、2013年以降は、深刻な景気後退に陥った場合や、構造改革などを通じて中期的な財政均衡に向けた措置を取っているといった場合には、例外規定が適用され、緊縮財政のペースは緩められた71。
イタリアについても、2013年にEDP対象を外れた後は、高い政府債務比率(第Ⅰ-3-2-28図)を抱えつつも例外規定の適用によりEDPに基づく是正対象国になっていないが、2019年度予算案については欧州委員会から厳しい姿勢が示された。その背景には、予算案に示された財政赤字比率と目標値の大きなかい離に加えて、欧州理事会による勧告72に対する深刻な逸脱があったとされたが、その中でも構造改革については、全般的に遅れており、むしろ一部では後退している、との評価が示されている73。
第Ⅰ-3-2-28図 欧州主要国の政府債務比率推移
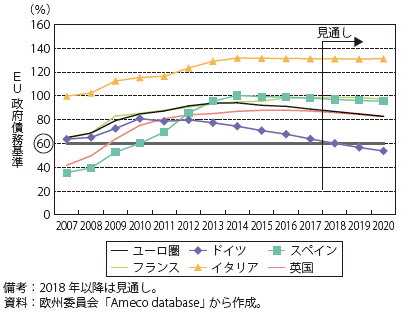
具体的には、高い政府債務比率を抱える同国については、財政均衡の達成に向けて、効率的な教育システムや労働市場の構築、あるいは企業の税負担軽減等、様々な構造改革を通じた経済成長が必要であるが、特に、予定される年金開始年齢の引下げについては、政府債務の持続可能性を高める目的で進めてきた年金改革を後退させるほか、労働供給を低下させ潜在成長率を抑制する可能性がある、との懸念が示された。
なお、2019年4月、イタリア政府は2019年の経済成長率を0.2%に下方修正した。これにより、同国の財政赤字比率(対GDP比)が再び2.4%に上昇することから、同国の財政に対する市場の懸念が再び高まる可能性がある。
一方、フランスでは、燃料税の引上げを前に、低・中所得者層を中心とする大規模な抗議行動が勃発した。黄色いベスト運動と呼ばれるこの抗議行動は、燃料税の引上げ反対に加えて、最低賃金の引上げや、年金の増額、富裕税の再導入等を求め、2018年11月から2019年まで継続している。
国民による激しい抗議行動を受けて、政府は2018年12月、燃料税の引上げ中止を決定したほか、ボーナスに関する税・社会保険料の免除74、残業代に関する所得税に関する雇用者負担の軽減75等を内容とする緊急経済措置を決定した。また、最低賃金の引上げも決定された。
同国の財政赤字比率は、2018年9月に欧州委員会に提出された2019年予算案では2.8%であったが、12月に決定された緊急経済措置を考慮すると、EUの財政赤字比率の上限である3%を超える可能性もあると見られている。
欧州委員会は、今のところフランスに対して厳しい姿勢を示していないが、10月に提出された予算案に対しては、政府予算の削減計画が不透明であるといった懸念を示す等、さらなる財政健全化を求める一方で、経済成長のための構造改革を強く求めている76。
EUの財政規律は、欧州債務危機とその後の回復の過程を経て、財政健全化だけでなく経済成長に配慮する方向に変化してきた。イタリアやフランスのように、EU市民の不満に対応し財政支出の拡大を伴う政策が求められる場面では、欧州委員会の柔軟な対応が歓迎される一方で、放漫財政に対する金融市場の目は厳しく、最近のイタリアの財政懸念の高まりに国債利回りが敏感に反応したことを踏まえても、財政健全化の重要性は低下していない。
なお、EUの財政監視制度については、欧州委員会の勧告に強制力はなく、また、その制裁の有効性を疑問視する声もある。一方で、欧州委員会の裁量の余地が大きすぎるとの批判に加え、債務危機対応により複雑化しすぎており、公共財政の長期的な持続可能性向上のためには、債務削減だけに焦点を当てるべきとの見解も見られる77。単一通貨圏としての持続性を確保するためには、各国の財政健全化が必要不可欠だが、財政規律そのものに様々な論点がある中、今後、有効に機能するような枠組みが作られるか見通すことは難しいのが現状と言える。
なお、単一通貨圏における経済の安定化を図るため、各国の財政健全化促進に加えて、経済的なショックに対応するユーロ圏の共通予算の創設78も検討されている。ただし、これに関しても、その必要性や規模、制度設計についての考え方には各国に温度差があるとされている。
68 イタリアの政府債務比率は132%と、ユーロ圏加盟国の中でギリシャに次いで高く、これ以上の政府債務の拡大を回避するために、厳しい構造財政収支目標が設定されている。フランスの政府債務比率は98.5%とイタリアの水準を大幅に下回っており、構造財政収支目標が相対的に緩い。(European Commission(2018a))。
69 European Commission(2018b)、吉田(2018)。
70 2011年12月「安定・成長協定」に基づく財政規律とマクロ経済政策監視メカニズムを強化した「経済ガバナンス強化パッケージ(six pack)が発効。2013年1月、財政均衡化を憲法等に盛り込むことなどを義務付ける「財政協定(Fiscal Compact)」が、16カ国の批准により発効(2019年4月時点では、署名25か国に加えて、クロアチアとチェコが批准済み)。
71 一定の条件を満たす場合には、安定・成長協定の例外規定が適用され、財政赤字あるいは政府債務に関する閾値を超えても、「予防」のステージにとどまり「是正」のステージに進まない。
72 Council of the European Union (2018).
73 European Commission (2018c).
74 対象は、報酬が最低賃金の3倍未満である被雇用者に対して、2019年3月末までに支払われるボーナス。
75 最大5,000ユーロ。
76 European Commission (2018d).政府支出の削減を求めつつも、経済成長のため、政府投資拡大を認め、また、引き続き企業の税負担を軽減する必要性が示されている。
77 欧州委員会の助言機関である欧州財政委員会(EFB)は、EUの財政規律について、複雑すぎる上に、公共財政の長期的な持続可能性向上につながっていないとして、GDP比3%以下とする既存の財政赤字目標を廃止し、債務削減だけに焦点を当てることを提言している。(European Fiscal Board(2018))
78 EUの次期予算枠組み(2021~2027)に、「ユーロ圏の収斂(れん)と競争力のための予算」を設けるための議論が進展している。
2.英国経済
(1)概況
英国は、欧州債務危機以降、他の欧州主要国に比べて高い経済成長率を維持してきたが、EU離脱に関する国民投票が行われた2016年以降は鈍化しており、2018年の実質GDP成長率は通年で1.4%増にとどまった。
家計消費については、ポンド安の影響で2017年にも既に伸びが鈍化していたが、2018年にはさらに、新興国経済の減速により輸出が減退したほか、EU離脱をめぐる先行き不透明感を背景に総固定資本形成が鈍化した(第Ⅰ-3-2-29図、第Ⅰ-3-2-30図)。
第Ⅰ-3-2-29図 英国の実質GDP成長率推移
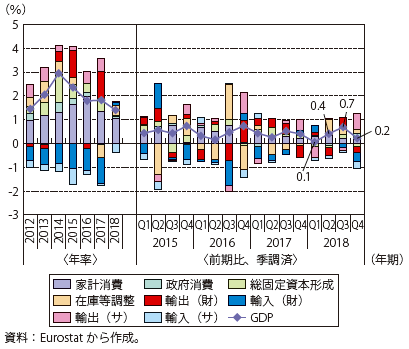
第Ⅰ-3-2-30図 英国の総固定資本形成推移
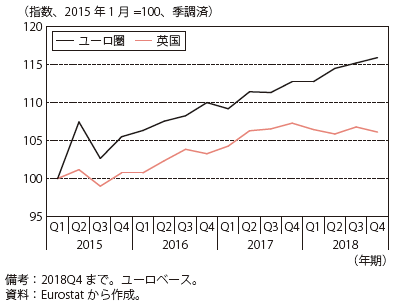
また、2018年夏以降、EU離脱に向けた英国政府とEUの交渉が難航し、合意なき離脱の可能性が少しずつ意識されていく中で、企業や消費者のマインドは冷え込んだ。経済信頼感指数を見ると、2018年初めから低水準で推移していた製造業に加えて、2018年秋以降はサービス業においても顕著に悪化している(第Ⅰ-3-2-31図)。特にサービス業については、2019年2月時点で、雇用見通しが2012年以来、ビジネスの先行き見通しが2013年以来の水準まで低下している(第Ⅰ-3-2-32図)。また、企業の投資意欲については、製造業で2018年第3四半期から、サービス業では第4四半期から低下している(第Ⅰ-3-2-34図)。
第Ⅰ-3-2-31図 英国の経済信頼感指数推移
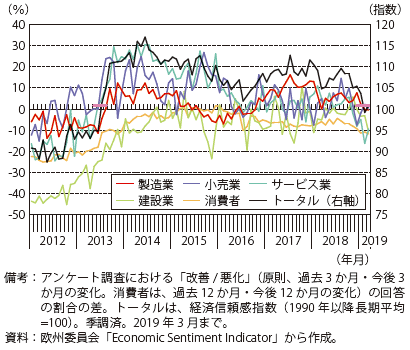
第Ⅰ-3-2-32図 英国のサービス業景況感推移
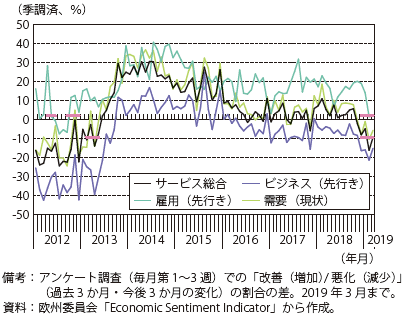
第Ⅰ-3-2-33図 英国の製造業景況感推移
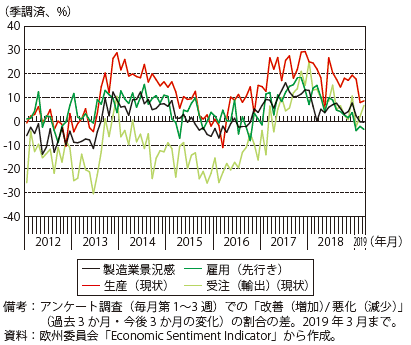
第Ⅰ-3-2-34図 英国企業の投資意欲推移
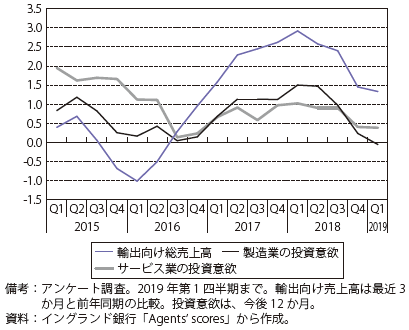
(2)金融市場
2016年のEU離脱をめぐる国民投票後、ポンドは対ドルで下落し、その影響で英国のインフレ率は上昇した。インフレ率の上昇に伴い実質賃金も大幅に低下していたが、インフレ率は2017年末をピークに鈍化しており、2018年の間、実質賃金は上昇傾向で推移した(第Ⅰ-3-2-35図)。
第Ⅰ-3-2-35図 英国の実質賃金とインフレ率推移
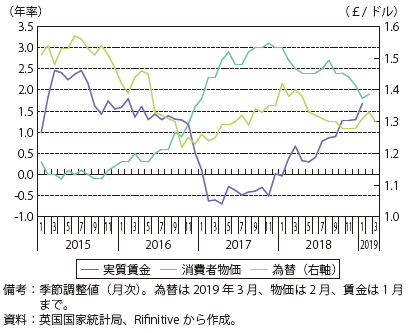
イングランド銀行(英国中央銀行)は、2018年8月、労働コスト等国内要因によるインフレ圧力が高まっているとして、政策金利の引上げを実施した。政策金利は2016年の国民投票直後の8月に引下げられていたが、それ以降2度目の引上げとなった。
2018年夏以降、合意なき離脱の可能性が意識される中で、ポンドは下落し、2018年秋には2017年初頭の水準まで低下した。
(3)BREXITによる企業への影響見通し
①BREXITをめぐる主な動き
英国のEU離脱期限は、当初2019年3月29日に設定されていたが、2019年3月に入っても、英国議会は「離脱協定案」(英国政府とEUが2018年11月に交渉妥結)を承認できず、EUとの間で何の合意もないままに英国がEUを離脱することになるのではないか、との懸念が高まった。
しかし、合意なき離脱による経済へのダメージは甚大であり回避すべきとの考えの下、EU首脳会議は3週間の間に、同国の離脱期限を、3月29日から4月12日へ、さらに10月31日へと2度に渡り延期した96。
経済界が最も懸念していた「合意なき離脱」がひとまず回避されたものの、合意なき離脱となる可能性は排除されておらず、以下では、合意なき離脱となった場合の経済への影響及び対応について概観する。
2018年夏以降、英国政府と欧州委員会は、可能性がゼロではないとして、「合意なき離脱」に向けた準備を行うよう、民間に対し一連の通知を発出しており、民間企業は一定の準備をしてきたと見られる。少なくとも英国においては、2019年3月時点で、企業の3分の2が、「合意なき離脱」に備え、英国とEUの貿易に関係する在庫の拡大や、EUへの拠点設置等、一定の準備を行っていた模様である97。
しかし、事前に準備できることには当然ながら限界があり、「合意なき離脱」に陥った場合には、新たな関税コストの発生のほか、貿易手続を行うインフラ制度の不足に伴う港湾手続の混乱、REACH98等のEU域内で適用される規制や標準の取扱いをめぐる混乱、クロスボーダーでのサービス提供に関する混乱、さらに、既に英国で労働しているEU市民及びEUで労働している英国民の扱いに関する混乱等、様々なレベルに悪影響が生じると見られている。
なお、関税コストについては、当初の離脱予定日を目前にした3月13日、英国政府が、「合意なき離脱」の場合に英国の輸入額の87%相当の関税の一時的な撤廃を行う旨を発表99しており、EUから英国への輸入の多くは関税負担を免れることとなった。ただし、自動車完成品や一部の食料品については、市場環境が厳しい等の理由で、関税撤廃の対象外であり、また、英国からEUへの輸入に関しては、新たに関税負担が生じることとなる。
非関税障壁に関しても、多くの影響が生じる。これまで、EU域内で承認等を受けていれば、EU内の他の加盟国に自由に上市することが可能であった製品であっても、「合意なき離脱」に陥った場合には、英国において、あるいはEU域内において、新たに登録や承認をやり直す必要が生じる場合が多い。
例えば、化学品については、既に英国内で登録された化学品を欧州経済領域(EEA)に上市する際には、EEA域内で登録し直すことが求められる。逆に、EEA域内で登録されていた化学品を英国で上市する際には、英国内で登録し直すことが求められる100。
医薬品については、EUで承認された医薬品は、自動的に英国に受入れられる。しかし、英国で取得した市販承認は、EU内で自動的に承認されず、EU27か国のいずれかに所在する市販承認申請取得者に承認を移管する必要がある。
CEマーキング等の製品の認証については、EU認証機関による認証等を受けた製品は、英国で上市することが可能である(ただし時限付き)が、英国の認証機関による認証はEU内で無効であり、EUの認証機関で再認証を取るか認証を移管する必要が生じる。
英国にとって、EUは最大の貿易パートナーである。EUにとって、英国は輸入額の4%、輸出額の6%101を占めるに過ぎないが、複雑に構築されてきたサプライチェーンでは、その一部が停滞するだけでも、関係する企業に影響が波及していく可能性がある。
「合意なき離脱」によるマクロ経済への影響については、複数の機関が見通しを公表しているが、その中でドイツのハレ研究所は、合意なき離脱によりEUからの輸入が25%減少した場合に起こり得る事態を分析し、60万人の雇用に影響するとの結果を発表した(第Ⅰ-3-2-36表)。
第Ⅰ-3-2-36表 ドイツ ハレ研究所調査結果102
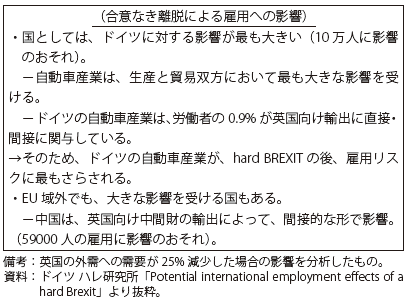
これによると、最も影響を受けるのはドイツの自動車産業とされている。ドイツの自動車産業は英国産業の中間投入に向けた輸出が非常に多く、サプライチェーンの分断による影響が大きいものと推測される。
また、中長期的には、EUによる労働者の流入が減少することで、労働力不足が加速するリスクや、同国のイノベーションを支える高度外国人材の流入が減少するリスクが懸念されている。
英国政府の見通し103によれば、「合意なき離脱」がGDPに与える影響は、移民の流入が確保される場合は15年間で7.7%の減少だが、EEAからの労働者流入が制限される場合の減少幅は9.3%に拡大する(第Ⅰ-3-2-37表)。
第Ⅰ-3-2-37表 英国政府の長期(15年)見通し(GDPに与える影響)
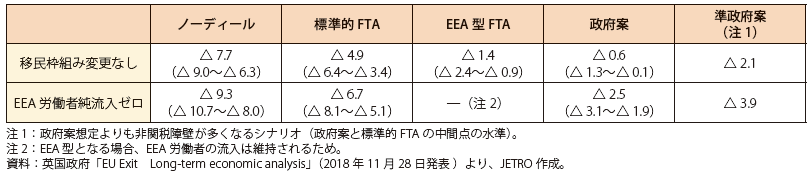
第Ⅰ-3-2-38表 イングランド銀行による中期(5年)見通し(GDPに与える影響)
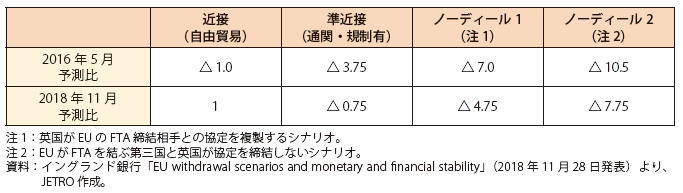
一方、英国議会が2019年10月31日までに「離脱協定案」を承認した場合には、11月1日から、英国は秩序立った形でEUを離脱することとなる104。
その場合の離脱の形、また離脱した後のEUとの関係については、当該「離脱協定案」及び同時に公表された「政治宣言案」が指針となっている。
「離脱協定案」は、英国の離脱後から開始する移行期間中のEUにおける英国の取扱いや、移行期間終了後の市民の権利、また、アイルランドと北アイルランドに関する規定、また離脱清算金等を主な内容とする。
市民の権利については、EUに居住する英国民と英国に居住するEU市民は、いずれも移行期間終了後もそれ以前と同じ権利を有し、さらに、同期間終了時点で5年以上継続して居住していれば、英国民がEUで、EU市民が英国で永住権を持つとされるなど、既存の市民を広めに受入る方向である。ただし、「離脱協定案」については、「最終的に全てが合意されない限りは、何も合意されていないと見なす」との交渉原則があるため、離脱協定全体で合意がなされるまでは、規定されているどの内容も確定しないことに留意する必要がある。さらにアイルランドと北アイルランドに関する規定は、英国議会による「離脱協定案」の否決の主要な要因の一つであり、離脱後の状況を想定するには不確定要素が大きい。
「政治宣言案」は、移行期間終了後の英国とEUの将来関係についての方向性を示している。英国政府とEU当局がともに目指すものという位置づけで法的拘束力はないが、現時点で将来の産業界への影響を考える際には貴重な指針と言える。
具体的には、物品貿易に関しては、関税や数量割当てがなく、原産地規則の検査のない状況が期待されている。また、医薬品、化学、航空等、様々なセクターに関して、EU機関と英国機関の協力等に支えられた、包括的な自由貿易圏が念頭に置かれている。
サービスと投資に関しては、広範な分野において、WTOの取決めを大幅に上回る自由度の確保が期待されている。具体的には、市場アクセス等に関する内外無差別の徹底、また、規制調和の協力枠組みの設置等が記載されている。
また、知的財産権については、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)等を超えて、知的財産権の保護と執行を提供することが期待されている。
以上を含む、「政治宣言」に記載されたような経済パートナーシップが実現されれば、英国のEU離脱は、産業界の混乱なく行われるかもしれない。ただし、いずれも具体的な交渉は、2020年末までの移行期間の間に行うものとされており、今後の交渉の行方を追う必要がある。
96 2019年3月21日のEU首脳会議において、英国議会が3月29日までに離脱協定案を承認しない場合、離脱期限を4月12日とすることが決定された(離脱協定案が議会で承認された場合は、離脱期限を5月22日とするとされた)。
しかし、3月29日までに英国議会による離脱協定案に対する承認が得られず、かつ新たな方針も提示されない中で、2019年4月10日に開催されたEU首脳会議では、離脱期限を2019年10月31日に延期することが決定された。
なお、4月10日のEU首脳会議においては、10月31日までの延期が認められたものの、2019年5月22日までに英国議会が離脱協定案を承認せず、かつ5月23日から開始する欧州議会選挙に英国が参加しない場合には、離脱期限を2019年5月31日とすることが決定されていた。英国政府は5月7日、欧州議会選挙への参加を表明した。
97 英国中央銀行の2019年3月の調査(約300社対象)によれば、合意なき離脱に備えて何らかの対応を行っている英国企業は全体の3分の2に上った。
98 EUの「化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則」。
99 UK Treasury “Temporary tariff regime for no deal Brexit published”, 13 March 2019, (https://www.gov.uk/government/news/temporary-tariff-regime-for-no-deal-brexit-published![]() ).合意なき離脱から最大12か月適用される見込み。
).合意なき離脱から最大12か月適用される見込み。
100 なお、英国側は、英国内に登録し直す際、既にEEA内で登録されたものであれば、基本的に承認することを予定している。
101 2017年。
102 Halle Institute for Economic Research (2019).
103 UK Government (2018).
104 2019年9月までの間に英国議会が離脱協定案に合意する場合は、離脱日を、合意した日の翌月の1日に前倒しすることも可能である。
②企業立地に対するBREXITの影響
EU単一市場から離脱することにより、英国は、これまで享受してきたEU市場への自由なアクセスを失う。最大の貿易パートナーであるEUとの貿易における関税障壁や非関税障壁の発生により、英国企業の環境が従来に比べ悪化することは否定できず、今後、英国への企業投資は縮小するとの見方が多い。
英国に立地していたEUの機関のうち、欧州医薬品庁は既にオランダ・アムステルダムに移転し105、欧州銀行監督庁もフランス・パリへの移転が決定しているが、企業に関しても、非関税障壁による影響が大きいセクターを中心に、拠点を移す動きが見られている。
JETROの調査によれば、欧州進出日系企業も、生産拠点を有する企業の約6割が、移転や撤退等を実施(若しくは決定)した、あるいは検討している、と回答している(第Ⅰ-3-2-39図、第Ⅰ-3-2-40図)。さらに、2019年に入り合意なき離脱の可能性が高まる中で、複数の製造企業が英国拠点の縮小を発表しており、英国のEU離脱による影響を指摘する声が多い。
第Ⅰ-3-2-39図 英国のEU離脱に備えた移転・撤退等を決定した拠点(欧州進出日系企業)
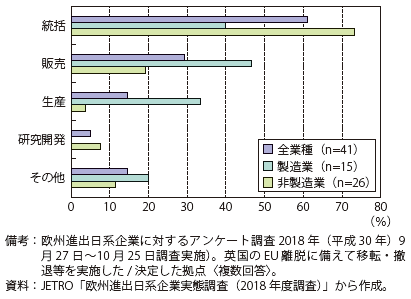
第Ⅰ-3-2-40図 英国のEU離脱に備えた移転・撤退等を予定する拠点(欧州進出日系企業)
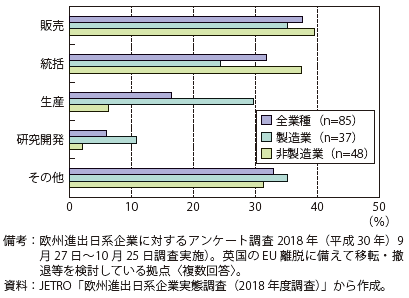
一方、同じJETROの調査によると、欧州進出日系企業の多くが、今後1~2年の間に、英国において、販売、生産(高付加価値品)、研究開発等の機能拡大を予定していると回答している(第Ⅰ-3-2-41表)。英国のEU離脱を控え、同国での活動を、価格重視の製品から、品質や技術での差別化を図る製品に軸足を移そうとする姿勢が示唆されていると言える106が、拡大するとの回答は、少なくとも秩序だったEU離脱107においては、EU離脱による影響を重視しないセクターやビジネスの形が存在することが示唆される。
第Ⅰ-3-2-41表 今後、機能拡大を予定している国・機能(欧州進出日系企業)
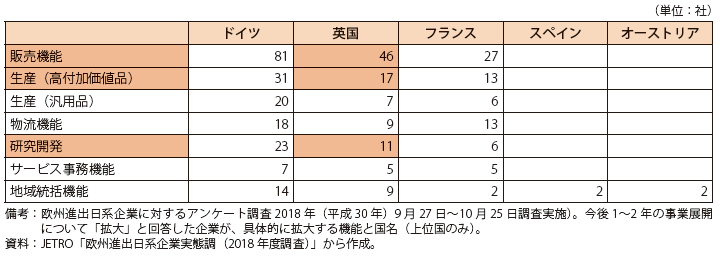
英国企業に対する外国企業によるM&A件数は2015年以降2018年までほぼ横ばいで推移している(第Ⅰ-3-2-42図)。また、外国企業による買収先としての順位(件数ベース)は、EU、米国及び日本と比較すると、2014年以降、米国に次ぐ2位を維持しており、EU離脱を前にしても、外国企業からの魅力が低下しているとは言い難い。
第Ⅰ-3-2-42図 日米欧企業に対するクロスボーダーM&A (被買収企業の国籍別割合の推移)
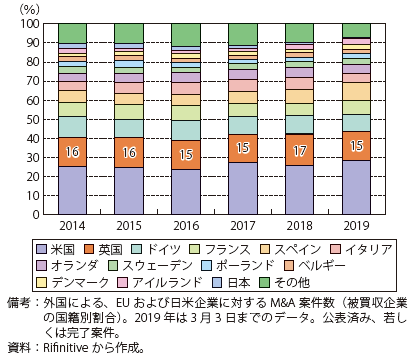
上記M&Aの対象セクターは、ハイテク、卸売、金融、メディア・娯楽、通信等が多い(第Ⅰ-3-2-43図、第Ⅰ-3-2-44図)が、ICTセクターを中心とする新しいビジネスにおいては、製造業に比べてEU離脱による影響が小さいと考えられ、2018年にも、米アップルによる、音楽認識アプリのシャザムの買収や、米セールスフォース・ドットコムによるデータセンター建設等の投資等が発表されている。
第Ⅰ-3-2-43図 英国企業に対するクロスボーダーM&A件数(被買収企業のセクター別)
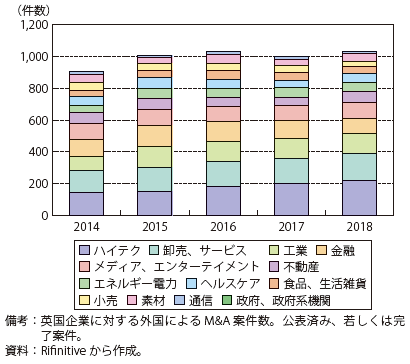
第Ⅰ-3-2-44図 日米欧企業に対するクロスボーダーM&A (被買収企業の国籍×セクター)
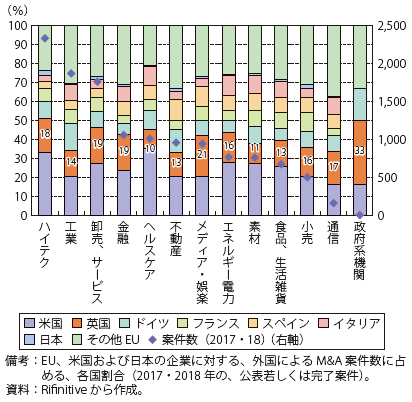
英国は従来、研究開発の水準が高く、また、近年は企業のイノベーションを育むエコシステムに対する評価も高い。また、EU離脱を前にして、英国政府は2017年11月、国内及び世界でチャンスを掴んでいくためとして、同国の強みを活かしつつ、変化する世界経済を志向した「産業戦略」108を打ち出した。
同「産業戦略」は、同国の生産性を高めるための「アイディア」「人材」「インフラ」「ビジネス環境」「地域」の5つの基盤を設定しているが、そのうちの一つ、「アイディア」は、先進的イノベーション経済国家の構築を図るべく、R&Dへの投資(対GDP比率)の引上げや研究開発費の税額控除率(tax credit)の引上げ等を掲げる。また、「人材」は、優れた技術教育システムの確立や、STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics)分野の教育への追加投資、デジタル分野等の職業訓練への追加投資等を内容とする。
また、2018年12月には、EEA市民の優遇を廃し、技能に基づき滞在を許可する新制度を導入する計画を発表した。具体的には、EEAからの移民にも、第三国からの移民と同様にビザを要求する一方で、技能労働者の受入を拡大する、また、留学生ビザについては、卒業後の滞在可能期間を拡大する、といった内容である。EU離脱によって、EUから流入していた高度人材の流れが低下したとしても、引き続き技術立国としての立場の確保を図る施策といえる。
EU単一市場へのアクセスにおいて制約を受けることによる経済への悪影響は否定できない。しかし、研究開発や人材、イノベーションに適したビジネス環境といった強みは、EU離脱後にそのまま低下するわけではない。むしろ、イノベーションに関する強みを活かし、かつ、高度人材の確保のために対処し、新しい成長分野に資源を投入するというアプローチは、どの国にも求められるものであり、今後の成長性はこれらに対する取組方次第と考えられる。
105 2019年3月12日より、オランダで正式に稼働。
106 独立行政法人日本貿易振興機構(2018b)。
107 調査が2018年秋であり、合意なき離脱の可能性は、ゼロではないが非常に低いとの見方が多かった。
108 2017年11月27日公表。(UK Government(2017))