

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第1部 第3章 第4節 東南アジア・南西アジア
第4節 東南アジア・南西アジア
本節では、東南アジア・南西アジア地域の中でも経済規模が大きく、2019年に選挙112が行われるインドネシア、タイ、インドの3国を取り上げ、足下の主要マクロ経済指標とともに、政権発足から約5年間の推移、今後懸念されるリスクを概観する(第Ⅰ-3-4-1表)。
第Ⅰ-3-4-1表 東南アジア・南西アジア主要国の主要経済指標
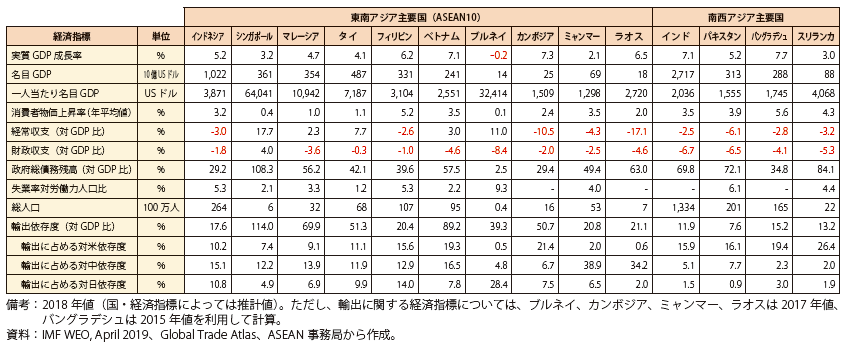
112 インドネシアは4月17日に総選挙・大統領選挙、タイは3月24日に総選挙、インドは4月11日から5月19日に7回に分けて下院総選挙が行われる。
1.インドネシア
(1)マクロ経済動向
①GDP
2018年の実質GDP成長率は前年比5.2%と、2017年の5.1%からわずかに加速した。これは3年連続の拡大、現政権における最高値だが、2014年に7%へ引上げることを公約として当選したジョコ・ウィドド大統領の目標はいまだに達成されていない。
需要別では、雇用・所得環境の改善により民間消費が底堅かった113ほか、インフラ整備の促進による総固定資本形成、政府消費等の拡大が成長を下支えした。輸出は堅調であるものの、それを上回る輸入114により純輸出はマイナスに寄与した(第Ⅰ-3-4-2図)。
第Ⅰ-3-4-2図 インドネシアの実質GDP成長率(需要項目別寄与度)の推移
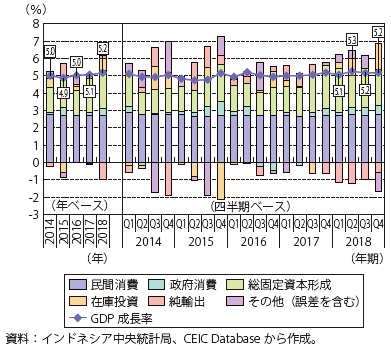
産業別では、サービス産業が寄与度ベースで、前年の2.4%から2.5%とわずかに加速した。製造業は4年連続で同0.9%と横ばいで推移している(第Ⅰ-2-4-3図)。
第Ⅰ-3-4-3図 インドネシアの実質GDP成長率(産業項目別寄与度)の推移
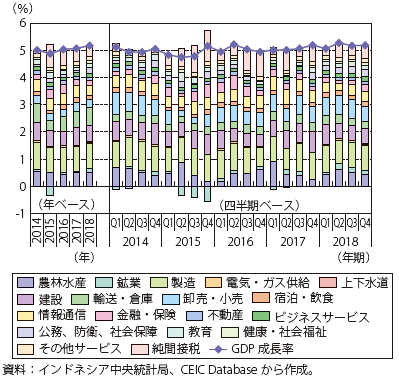
113 公務員賞与の増額といった財政支出や、アジア競技大会やIMF世界銀行総会といった大きな国際イベントの開催が個人消費を下支えしたと指摘されている。
114 輸入額が拡大した要因として、2018年夏のいわゆる「トルコショック」に伴う金融市場の動揺が、トルコと同様、経済のファンダメンタルズがぜい弱とされる「フラジャイル・ファイブ」にカテゴライズされている同国にも影響し、通貨ルピア相場が下落、一時約20年ぶりの安値を更新(2018年10月)したことが挙げられる。同国は消費財の多くを輸入していることもあり、通貨安により輸入額が大幅に拡大した。
②生産
2018年の鉱工業生産指数(前年同月比)は、6月、コンピュータ・電子・光学製品等の縮小により▲7.1%と大きく縮小したが、総じて底堅く推移した(第Ⅰ-3-4-4図)。
第Ⅰ-3-4-4図 インドネシアの鉱工業生産指数(前年同月比)の推移
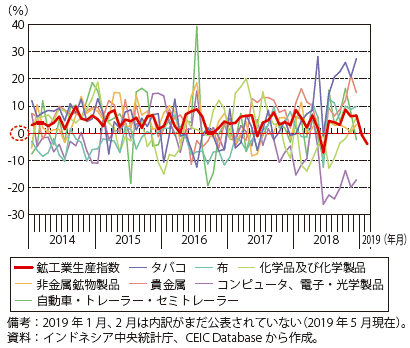
③消費
2018年の小売売上高指数(前年同期比)は、1月、▲1.8%と縮小したが、その後は回復した。事務用品・通信は大きく縮小傾向にある一方で、他の品目は拡大傾向にあり、特に燃料、文化・娯楽の伸びが大きい。ただし、総じて2桁で拡大していた2014年から2016年と比較すると鈍化している(第Ⅰ-3-4-5図)。
第Ⅰ-3-4-5図 インドネシアの小売売上高指数(前年同月比)の推移
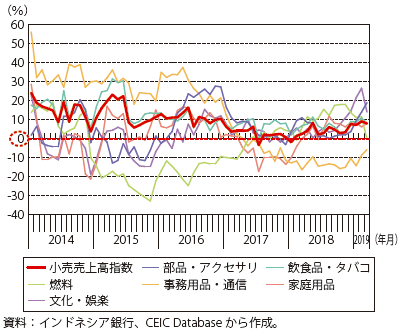
次に、購買意欲を反映する代表的な指標である自動車・自動二輪車の国内販売台数の推移を見る。自動車については、2014年、2015年と減少したが、それ以降は増加傾向に、自動二輪車については、2015年以降減少していたが、2018年では増加に転じた(第Ⅰ-3-4-6図)。
第Ⅰ-3-4-6図 インドネシアの自動車・自動二輪車の国内販売台数の推移
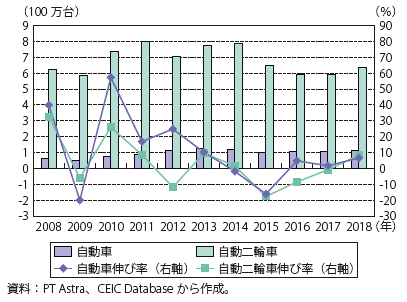
④投資
2018年の固定資本形成(前年比)は9.6%と、2年連続で拡大した。現政権が発足した2014年は、約75%を占める建設が牽引し12.6%と大きく拡大したが、それ以降2年連続で鈍化していた(第Ⅰ-3-4-7図)。
第Ⅰ-3-4-7図 インドネシアの固定資本形成(前年比・寄与度)の推移
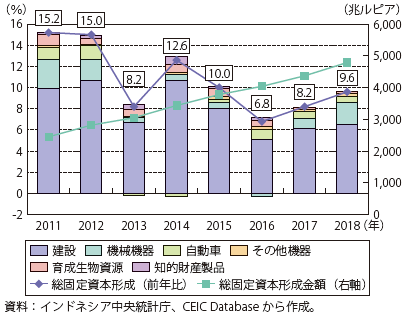
⑤経常収支
2018年の経常収支は▲310億ドルの赤字と、前年の▲162億ドルから赤字が拡大した。民間需要の増加、通貨ルピー相場の低下により、輸入額が輸出額を上回り増加したため、貿易収支が赤字に転じたことが要因である。
政府は9月、国産パーム油のバイオ燃料転用促進策や前払い法人税115の税率引上げなど、貿易赤字の改善のための施策を相次ぎ行った。
なお、名目GDPに占める経常収支の比率は2014年以降改善傾向にあったが、2018年では▲3.0%と、前年の▲1.6%から5年ぶりに悪化した(第Ⅰ-3-4-8図)。
第Ⅰ-3-4-8図 インドネシアの経常収支の推移
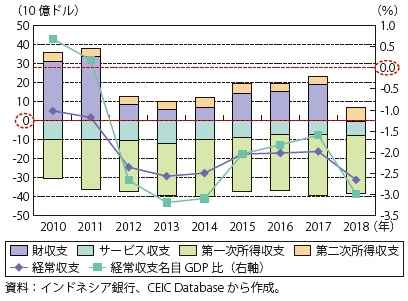
115 輸入の際に法人税を前払いする制度。原則、還付を受けることができる制度だが、還付条件が複雑なこともあり、還付が受けられない事が多く、事実上輸入税の増税であると不満の声がある。なお、2018年9月から消費財1,147品目を対象に前払い税率を大幅に引上げた。
⑥為替・政策金利・消費者物価指数
2018年10月、国際金融市場の動揺を受け、通貨ルピアの対ドル相場は一時約20年ぶりの安値となり、中央銀行は通貨安を阻止するため断続的に政策金利の利上げを実施した。
消費者物価は、政権発足後から総じて下落傾向で推移した。足下では通貨ルピア相場も落ち着いてきたことから、引き続き政府のインフレ目標範囲内で安定的に推移すると期待されている(第Ⅰ-3-4-9図、第Ⅰ-3-4-10図)。
第Ⅰ-3-4-9図 インドネシアルピア相場(対ドル)の推移
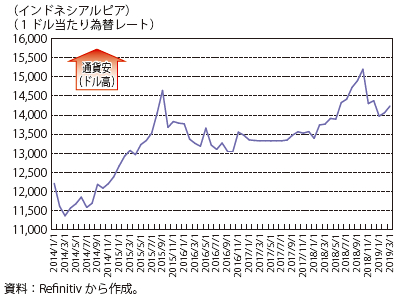
第Ⅰ-3-4-10図 インドネシアの消費者物価指数(前年同月比・寄与度)と政策金利の推移
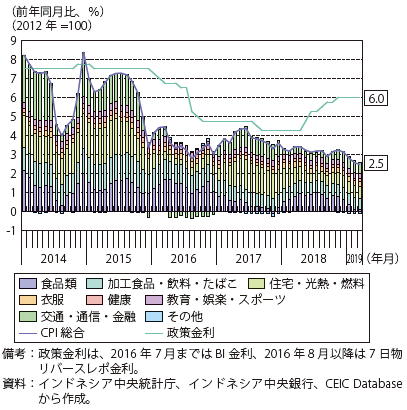
⑦海外直接投資(対内直接投資)
2018年の海外直接投資額(実行ベース)は、293億ドルと、前年の322億ドルから減少した。業種別では、第3次産業が、輸送・交通・通信業、不動産業を中心に増加したものの、第2次産業が、貴金属、食品、化学・医療等多くの分野で減少した他、第1次産業も鉱業を中心に減少した(第Ⅰ-3-4-11図)。なお、国別では、ASEANの8割超を占めるシンガポール116、日本、中国117の順で投資額が大きく、この順位は2016年から変わっていない(第Ⅰ-3-4-12図)。
第Ⅰ-3-4-11図 インドネシアの対内直接投資(業種別)の推移
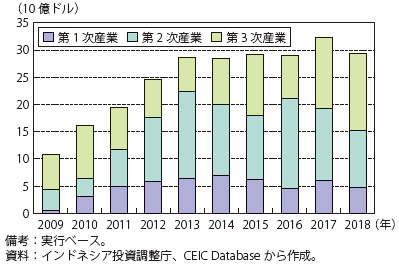
第Ⅰ-3-4-12図 インドネシアの対内直接投資(主要国・地域別)の推移

現政権の発足当初は、出資規制の緩和や手続の簡素化、経済特区(SEZ)での投資に対する税額控除等を行うなど、海外資本の呼びこみに積極的だったが、足下では、一旦決定したデジタル分野での規制緩和を国内企業の反対により撤回するなど、改革からの逆行も見られ、その影響を受けている。また、選挙前で様子見をする企業行動が反映されたという指摘もある。
116 多国籍企業のシンガポール統括拠点からの投資、インドネシア財閥による資金還流を含むと見られている。
117 中国は2016年以降存在感が増大している。
(2)懸念されるリスク要因
2019年4月17日、大統領選と総選挙が行われ、ジョコ・ウィドド現大統領の再選が確実視されている118。
選挙運動開始日119に、日本の全面支援による同国初の地下鉄を含む都市高速鉄道(MRT)の式典で開業宣言をし、現政権でのインフラ整備の功績をアピールしたことに象徴されるとおり、政権1期目はインフラ開発に注力し、安定した経済成長を維持したと言える。
政権2期目に向けた選挙公約では、貧困層や地方への補助金を含む社会保障に注力する方針を表明している。政権1期目でインフラ開発に注力できたのは燃料補助金の廃止を断行したことが大きい。しかしながら、2018年に入って燃料補助金を復活したこともあり、一連の構造改革が失速する可能性がある。なお、財政赤字対GDP比は2018年の▲2.1%から▲1.8%と縮小する目標を設定している。
2014年10月にジョコ政権が発足して以来、底堅い民間消費に支えられ安定した経済成長を維持してきたが、2億6,000人の人口を豊かにするためには7%台の成長率が必要といわれている。
慢性的な財源不足の中、公務員賞与や補助金の増額をする等バラマキ的な財政支出を続けることはできないこと、好調だった対内直接投資が規制強化のために停滞しているなど、今後の持続的な経済成長への懸念材料は少なくない。
118 選挙管理委員会による最終的な選挙結果は2019年5月22日までに公表される見通し。
119 2019年3月24日、ジャカルタ中心部を南北に結ぶ路線の一部区間(15.7km)が開業した。
2.タイ
(1)マクロ経済動向
①GDP
2018年の実質GDP成長率は前年比4.1%と、2017年の4.0%からわずかに上向き、4年連続の拡大となった。需要別では、米中貿易摩擦に伴う世界経済の減速を主因に、年後半で輸出が伸び悩み、6年ぶりに純輸出がマイナスとなったものの、民間消費、民間投資の拡大が成長を下支えした(第Ⅰ-3-4-13図)。産業別では、7月の観光船事故120の影響を受けた観光関連(ホテル飲食業・輸送通信業等)のほか、金融仲介業がわずかに縮小したものの、農業、鉱業、建設業が底堅く推移したことで成長を維持した(第Ⅰ-3-4-14図)。
第Ⅰ-3-4-13図 タイの実質GDP成長率(需要項目別寄与度)の推移
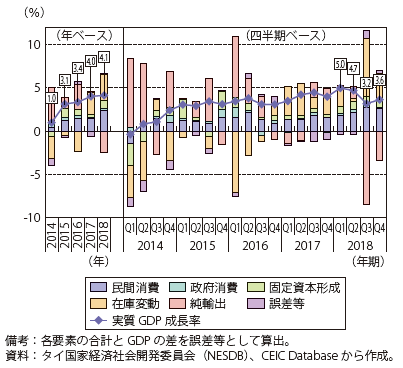
第Ⅰ-3-4-14図 タイの実質GDP成長率(産業項目別寄与度)の推移
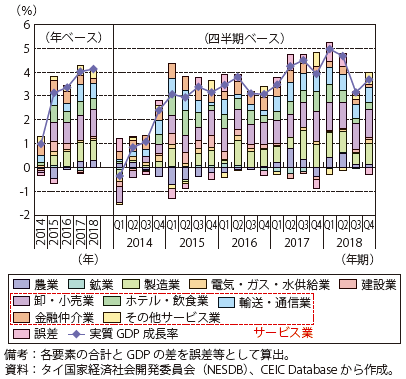
120 7月、プーケット沖で中国人観光客を乗せた観光船が沈没した。2017年のタイへの外国人観光客(約3,538万人)のうち中国人は980万人と全体の約3割を占めており、事故後に中国からのキャンセルが相次ぐ等、観光業への影響が懸念された。結果的に、他国からの観光客が堅調だったため、年ベースでは大きく落ち込むことはなかった。なお、タイの国際観光収入は約575億ドルで世界第4位の観光大国である(数値は全て国連世界観光機関の公表値)。
②生産
2018年の製造業生産指数(前年同月比)は、米中貿易摩擦に伴う世界経済の減速を主因に9月は▲2.7%と17か月ぶりに縮小した。10月以降はわずかながら拡大に戻ったが、内訳では、ゴム・プラスチック製品、電気機器など主要品が大きく縮小している(第Ⅰ-3-4-15図)。
第Ⅰ-3-4-15図 タイの製造業生産指数(前年同月比)の推移
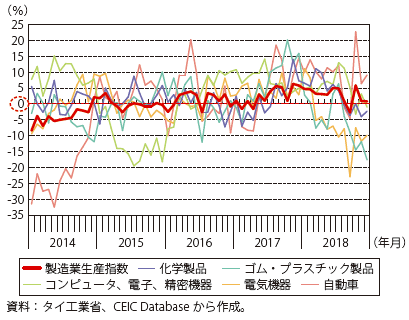
③消費
2018年の小売売上高指数(前年同月比)の推移を見ると、2018年後半から2桁の伸びを示しており消費の好調さが見て取れる(第Ⅰ-3-4-16図)。特に自動車は、2011~2012年に自動車購入優遇税制を利用した購入の代替需要121により好調な売上となった。
第Ⅰ-3-4-16図 タイの小売売上高指数(前年同月比)の推移
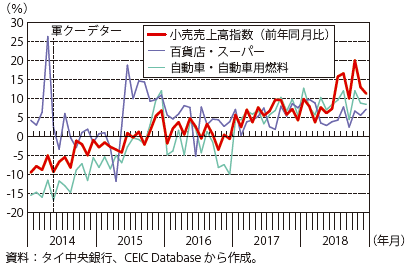
121 2011年9月から2012年末にかけてファーストカーポリシー(自動車の初回購入者に物品税を還付する税制優遇措置)が実施され、低所得者層を中心に自動車の売上が増加した。購入者は自動車を5年間保有する義務があったが、その期間を経たことで買い替え需要が高まっている。
④経常収支
2018年の経常収支は377億ドルと、貿易黒字の減少が主因で前年の502億ドルから縮小したものの、2014年以降5年連続の黒字となった。なお、拡大傾向にあったサービス収支は横ばいとなったものの、近年の海外観光客の増加により経常収支の黒字に大きく寄与している(第Ⅰ-3-4-17図)。
第Ⅰ-3-4-17図 タイの経常収支の推移
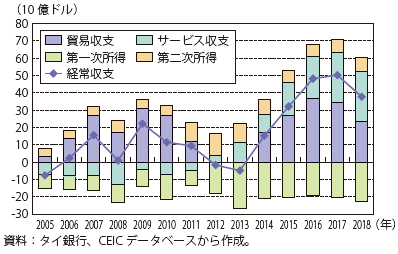
⑤為替・政策金利・消費者物価指数
2018年は米国の利上げ、欧州中央銀行政策委員会の動向、米中貿易摩擦への懸念などにより一時バーツ安が進んだが足下では落ち着いている。タイ中央銀行は同国の高い金融市場の流動性、経済の堅調な推移を踏まえ、通貨安に対抗するための利上げは急がず、2015年4月以来政策金利を1.50%に据え置いていた122。しかし、2018年12月、将来の景気後退に備え金融政策の実施余地を確保すること等を理由に1.75%に利上げした。利上げは2011年8月以来7年4か月ぶりであった。
2018年の消費者物価指数(CPI)上昇率123は、燃料価格の上昇を背景に運輸・通信の伸びが上昇したものの足下では落ちつき、年平均では1.1%と低位になった(第Ⅰ-3-4-18図、第Ⅰ-3-4-19図)。
第Ⅰ-3-4-18図 タイバーツ相場(対ドル)の推移
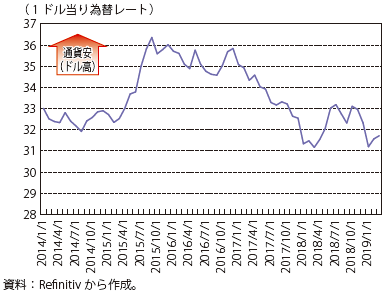
第Ⅰ-3-4-19図 タイの消費者物価指数(前年同月比・寄与度)と政策金利の推移
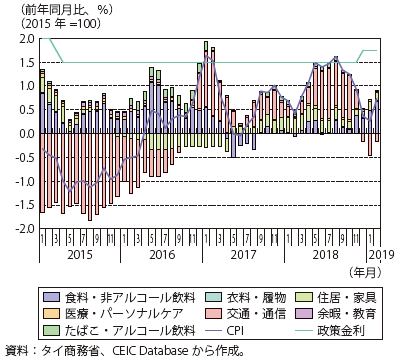
122 タイ中央銀行は、2014年3月から2015年4月にかけ、政策金利を2.25%から1.5%に段階的に引下げ、その後3年8か月の間、1.5%で据え置いていた。
123 タイ中央銀行はインフレターゲットを年平均2.5%(最低1%、最高4%)に設定している。
⑥海外直接投資(対内直接投資)
2018年の海外直接投資額(認可ベース)は2,556億バーツ124であり、日本は約37%と最大の割合を占めている(第Ⅰ-3-4-20図)。産業高度化に向けた長期国家戦略である「タイランド4.0政策」の重点地域である東部経済回廊(EEC)の対象3県125への投資が同国の海外直接投資を牽引しており、件数ベースではデジタル分野、金額ベースでは次世代自動車が最大の投資先となっている(第Ⅰ-3-4-21図)。
第Ⅰ-3-4-20図 タイの対内直接投資(国別)の推移
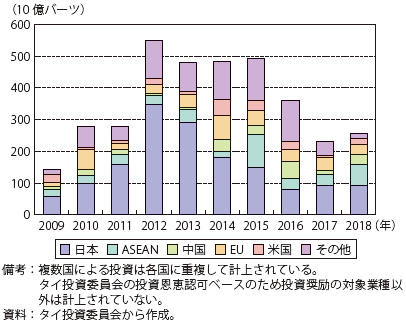
第Ⅰ-3-4-21図 東部経済回廊(EEC)への投資額と投資件数(分野別)
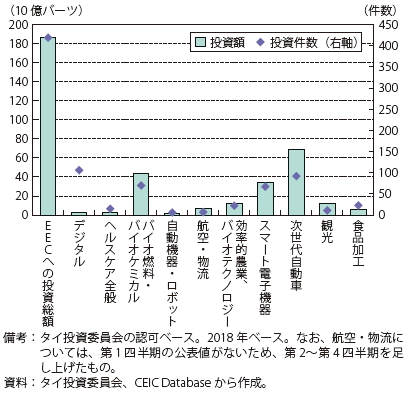
124 前年2017年の2,308億バーツから約11%増加した。日本は937億ドルであった。
125 チョンブリ、ラヨーン、チャチュンサオのバンコク東部3県。
(2)懸念されるリスク要因
2014年5月の軍クーデター後、事実上の軍事政権下にあったが、2019年3月に民政移管に向けた総選挙が実施された。その結果、選挙管理委員会から親軍政党が最大票を獲得したとの発表があったものの、投票の不正等を指摘する声もあり、政局が不透明となっている。
軍事政権側はプラユット首相のリーダーシップによる5年間の経済成長と安定性の成果を強調しているが、今後の政治動向によっては、海外投資の減少など経済が減速する懸念がある。
同国は、「タイランド4.0政策」に沿って、2036年までに、1人当たりGDPを現在の6,000ドル前後から1万5,000ドルに引上げることを目指している。高齢化が進む中、「豊かになる前に老いる」ことを回避するため、都会と農村の格差是正、人材教育、周辺国との連結性の推進など様々な施策を打つ必要がある。これらの重要課題に対しては、政党問わず継続して取り組まれると想定される。
なお、同国は、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)への新規加入に関心を有しているほか、2019年のASEAN議長国としてASEAN諸国の意見集約や調整を行う役割を担うなど重要な局面にある。同国政治の安定と政策の継続性が内外から期待されている。
3.インド
(1)マクロ経済動向
①GVA126
実質GVA成長率(年度ベース127)は、2014年5月のモディ政権発足後、高額紙幣廃止、物品・サービス税(GST)導入等の構造改革の断行により、一時的混乱、成長鈍化が見られたものの、総じて高水準で推移している。ただし、足下では、GVAの5割超を占めるサービス業、2割弱を占める製造業双方で減速傾向にあり、2018年に入り3期連続で鈍化している(第Ⅰ-3-4-22図)。
第Ⅰ-3-4-22図 インドの実質GVA成長率(産業項目別寄与度)の推移
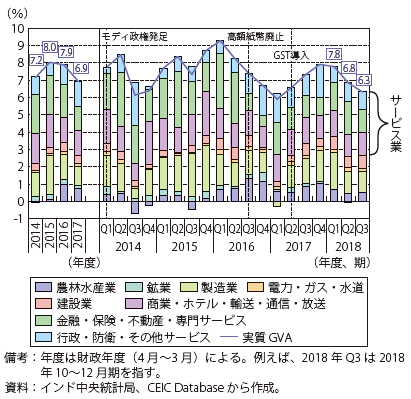
126 生産側から推計された実質総付加価値。純間接税に左右されるGDPより、月次景気指標に近い動きをすると言われている。
127 インドの財政年度は、日本と同様、4月から翌年3月である。
②消費
購買意欲を反映する代表的な指標である自動車の国内販売台数の推移を見る。乗用車、自動二輪車共に、高額紙幣廃止やGST導入といった一連の構造改革の影響を受けながらも総じて上昇傾向で推移していたが、足下では特に乗用車について横ばいまたは減少しており、民間消費の減速が想定できる(第Ⅰ-3-4-23図)。
第Ⅰ-3-4-23図 インドの自動車(乗用車・二輪車)国内販売台数の推移
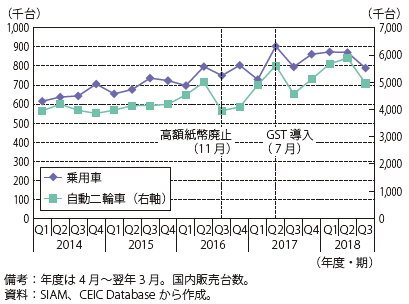
128 なお、名目GVA額に占める製造業の割合を見てみると、2014年度は16.3%、2018年度は16.6%とほぼ横ばいとなっている。
③生産
鉱工業生産指数(前年同月比)は、現政権下では、GST導入直前で企業が在庫抑制に動いた2017年6月が例外的にマイナスに縮小したものの、総じて底堅く推移したと言える(第Ⅰ-3-4-24図)。
第Ⅰ-3-4-24図 インドの鉱工業生産指数(前年同月比)の推移
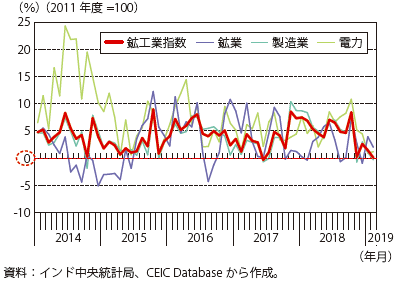
なお、雇用創出等を目指した外資系製造業誘致キャンペーン「メイク・イン・インディア(インドでものづくりを)」では、2022年までに製造業のGDP比率を15%から25%に上げる目標128を立てているが、未だわずかな上昇に留まっており、今後の推移が注目される。
④投資
2017年度の総固定資本形成(前年比)は9.7%と、前年度の4.7%から拡大した。総額の約18%を占める製造業と、約2.4%を占める金融サービスへの投資額が増加したことが主な要因である(第Ⅰ-3-4-25図)。
第Ⅰ-3-4-25図 インドの総固定資本形成(前年比・寄与度)の推移
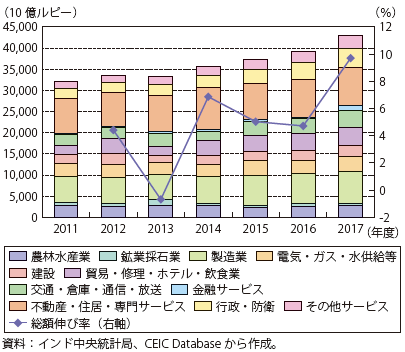
なお、今後も堅調な投資を継続させるためには、銀行、特に国有銀行の不良債権処理に関する施策129の着実な進捗が必要であると指摘されている(第Ⅰ-3-4-26図)。
第Ⅰ-3-4-26図 インドの銀行(国営・民間)債権額と不良債権比率
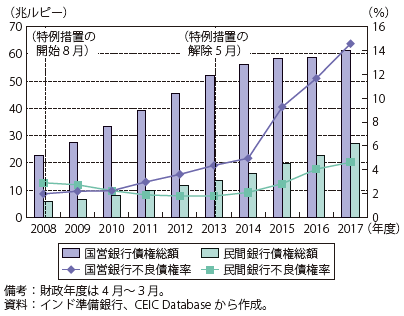
129 国営銀行の与信審査が厳格なものではなく、本来、不良債権と認識すべき融資案件が多かったが、2008年8月のインド中央銀行の特例措置により、一定の条件のもとで正常債権として分類されることとなった。2013年5月、この特例措置が解除され、債券分類基準が厳格化したことで、不良債権率が大きく上昇した。
⑤経常収支
経常収支は2017年度に入り貿易赤字の増加が主因で減少傾向にあり、それに伴い名目GDPに占める経常赤字の比率も大きくなっている。一方、サービス収支、二次所得収支は底堅く推移している(第Ⅰ-3-4-27図)。
第Ⅰ-3-4-27図 インドの経常収支の推移
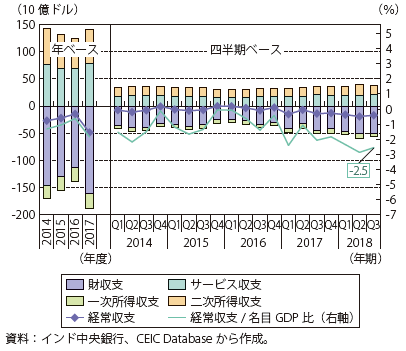
⑥財政収支
財政収支対名目GDP比は年々改善しており、財政面での安定性向上が見られる。政府は財政赤字の削減を継続し、2020年度に3%に縮小することを目標に掲げている(第Ⅰ-3-4-28図)。
第Ⅰ-3-4-28図 インドの財政収支と対名目GDP比の推移
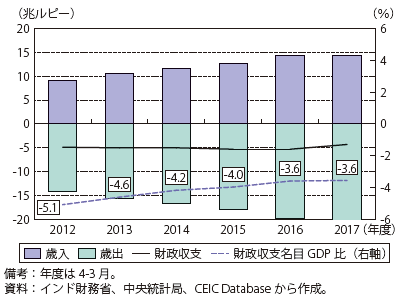
⑦為替・政策金利・消費者物価指数
2018年は国際金融の不透明性130が主因で一時ルピー安が進んだものの、足下では持ち直している。中央銀行は2018年6月、2014年1月以来約4年半ぶりとなる利上げ(6.0%→6.25%)を、8月に追加利上げ(6.25%→6.50%)を行った。なお、同国の消費者物価指数(CPI)上昇率は食料品価格に大きく左右され、前政権は高いインフレに悩まされてきたが、農作物の買取り価格の引上げ率を低く設定したほか、インフレターゲットを設定するなど現政権の施策が奏功し、中央銀行の目標範囲内(4±2%)で推移した(第Ⅰ-3-4-29図、第Ⅰ-3-4-30図)。
第Ⅰ-3-4-29図 インドルピー相場(対ドル)の推移
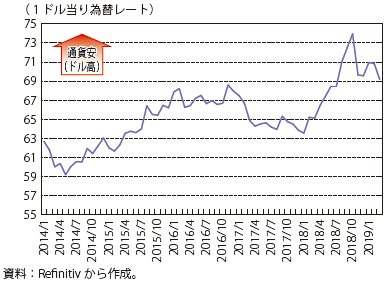
第Ⅰ-3-4-30図 インドの消費者物価指数(前年同月比)と政策金利の推移
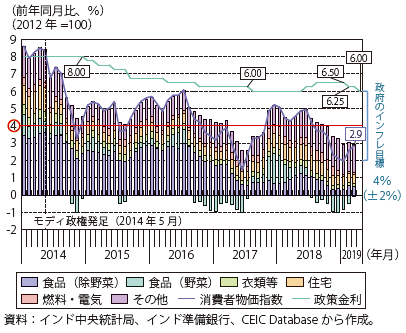
130 2018年8月のいわゆる「トルコショック」を発端に、トルコと同様、慢性的に双子の赤字(経常赤字・財政赤字)国である新興国の通貨安が加速した。
⑧海外直接投資(対内直接投資)
2018年131の海外直接投資額は424億ドルであり、前年の436億ドルから減少した。業種別では、サービス分野、貿易、自動車産業は増加したものの、コンピュータ分野(ソフト・ハード)、建設・インフラ分野が減少した。国別では、シンガポールが38%と最大の割合を占めている(第Ⅰ-3-4-31図、第Ⅰ-3-4-32図)。
第Ⅰ-3-4-31図 インドの対内直接投資(業種別)の推移
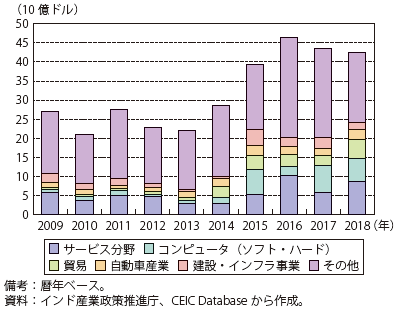
第Ⅰ-3-4-32図 インドの対内直接投資(国別)の推移
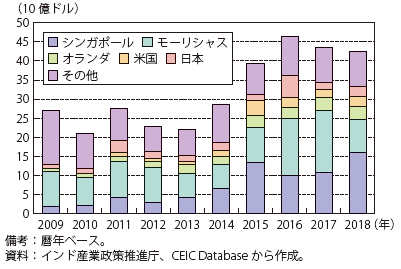
131 暦年ベース。
(2)懸念されるリスク要因
「開発、成長、雇用」を掲げて圧勝したモディ政権が発足して約5年間、GST導入による税制簡素化、高額紙幣廃止によるブラックマネー対策、倒産法整備による事業再生・清算手続きの迅速化、外資規制緩和、インフラ整備など、様々な構造改革が矢継ぎ早に実行された。その結果、国民からの高い支持率、世界ビジネス環境ランキングの上昇132などで示される通り、モディ政権の政策が国内外から高く評価されている。アジア開発銀行(ADB)は、2019年版「アジア経済見通し」の中で、アジア太平洋地域全体の成長率は米中の貿易摩擦等が影響し、2018年の5.9%から、2019年は5.7%、2020年は5.6%に下振れすると予想しているが、インドについては、政策金利の引下げや農民への所得支援などで内需が拡大し、2018年の7.0%から、2019年は7.2%、2020年は7.3%の高成長を予想している。
一方で、同国では、雇用創出の不十分さ、農村と都会の格差問題などが今後の大きな課題とされており、政府は2019年度の予算案において、所得減税や農家への所得支援策を盛り込んでいる。
2019年4~5月に下院総選挙が予定されており、選挙後の同国政策の継続性を国内外が注目している。
132 世界銀行から毎年公表されるビジネス環境ランキングで、インドは総合で2014年の142位から2018年の77位へ大きく浮上した(全190か国中)。なお、評価対象は10項目(起業・建設許可・電力事情・不動産登記・資金調達・少数株主保護・納税・貿易・契約執行・破綻処理)で構成されており、現政権下では、不動産登記以外の全項目で改善している。特に、電力事情、建設許可、貿易、破綻処理は著しく改善した(投資家保護、資金調達は、前政権から高い評価を得ている)。
