

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第1部 第3章 第6節 ロシア
第6節 ロシア
1.マクロ経済動向
本節では、主要経済指標の動向を中心に、2018年のロシア経済を概観する。その中で、通算4期目(2018年5月~2024年5月)となるウラジーミル・プーチン大統領の進める政策にも着目しつつ、政策の背景にあるロシア経済の抱える課題についても見ていく。
経済分析を行う前に着目したいのが、2018年5月にプーチン大統領が発表した「2024年までの国家目標と戦略的成長課題に関する大統領令150」である。この中で、以下9つの目標が掲げられた(第Ⅰ-3-6-1表)。
第Ⅰ-3-6-1表 ロシアの2024年までの国家目標
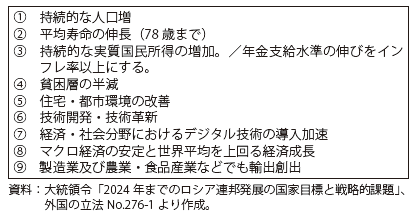
その上で、2019年2月には、9項目をより具体化し、目標の実現に向け、13分野での国家事業が公表された。国家事業には、非資源分野の競争力の向上(6年以内に同分野の輸出額を1.5倍以上に)、対内投資の増加に向けたビジネス環境の改善、経済発展の障壁となるインフラ問題の改善、労働生産性の向上、デジタル技術の加速化などが挙げられた。
(1)GDP
2018年の実質GDP成長率は、+2.3%と前年から僅かに加速した。要因の一つが原油価格の回復である151。原油価格が下落した2015年には、成長率は▲2.5%と大きく落ち込んだ(第Ⅰ-3-6-2図)。その後、油価は2016年には底を打ち、上昇基調で推移してきた。油価の回復に伴い、ロシア経済も緩慢ながらも回復し、2018年には6年ぶりの2%を超える成長となった(第Ⅰ-3-6-2図)。加えて、成長の牽引役となったのが、GDPの過半を占める家計消費と純輸出152である。
第Ⅰ-3-6-2図 ロシアの実質GDP成長率及び需要項目別寄与度の推移
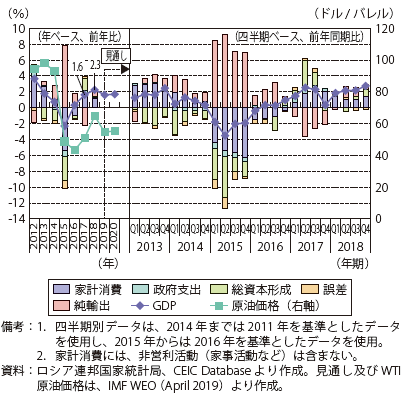
業種別でみると、第一次産業では前年からマイナスの伸びとなった一方、第二次産業及び第三次産業ではプラスの伸びとなった(第Ⅰ-3-6-3表)。第二次産業では、建設業が前年の▲1.2%から+4.7%と大幅に回復し、鉱業も+3.9%の伸びとなった。第三次産業では、宿泊・外食産業、金融・保険業で+6%を超える伸びとなった。特に、前者はサッカーW杯開催の影響と見られる。
第Ⅰ-3-6-3表 ロシアの業種別GDPの伸び率
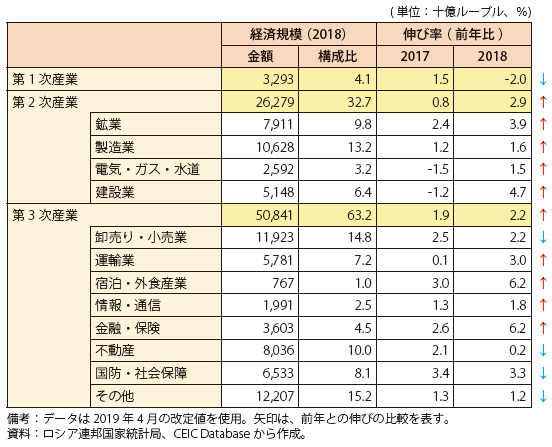
150 http://kremlin.ru/acts/news/57425![]()
151 WTI原油価格は、2017年の1バレル50.9ドルから2018年には27.2%上昇して同64.7ドルとなった(IMF WEO April 2019)。
152 2018年は、ルーブル安となったため、数量ベースで石油・ガス以外の輸出が増加し、輸入の増加が抑制された。結果として、純輸出が増加したとされる。田畑(2019)
(2)家計部門
2014年のクリミア危機に伴う欧米からの経済制裁や、原油価格の下落によって通貨ルーブルは大きく下落した(第Ⅰ-3-6-4図)。通貨安により輸入インフレ圧力が高まったことに加え、欧米からの経済制裁への対抗措置の結果153、農産品を中心に物資不足となり、インフレ率が大きく上昇した154。原油価格が底を打ちルーブルが安定したことや、輸入代替策によって食料品の価格が低下したことにより、2015年後半には、インフレ率は低下した(第Ⅰ-3-6-5図)。インフレ率低下に伴い、実質賃金が増加し小売売上高も緩やかながらも回復し、2017年央には、前年比でプラスの伸びとなっていた155。
第Ⅰ-3-6-4図 ロシアの為替レートとWTI原油価格の推移
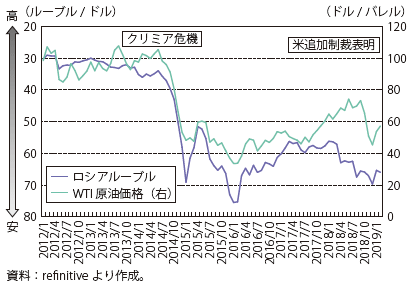
第Ⅰ-3-6-5図 ロシアの消費者物価指数(前年同月比)と政策金利の推移
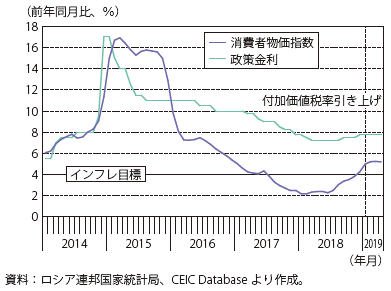
2018年は、油価が上昇したにも関わらずルーブル安が続いた156。背景には、クリミア危機や米国大統領選関与の疑いから実施された制裁があると見られる157。
ルーブルの減価に伴って、インフレ率は上昇し、実質賃金及び小売売上高ともに伸びが鈍化している(第Ⅰ-3-6-6図)。また、2019年1月より付加価値税率(18%→20%)が引上げられたこともインフレ率上昇の大きな要因とみられ、経済成長のエンジンである家計消費については、今後も注視が必要である。
第Ⅰ-3-6-6図 ロシアの実質賃金と小売売上高(前年同月比)の推移
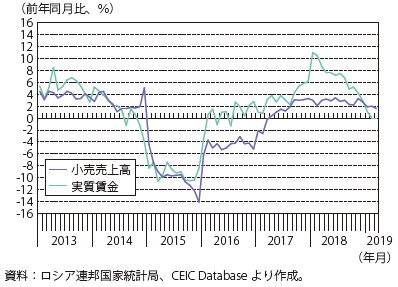
153 2014年8月、米・EU・加・豪・ノルウェーを原産地とする農産品・食料品の輸入禁止措置を導入。2015年8月にウクライナ、アルバニア、モンテネグロ、アイスランド、リヒテンシュタインを追加。
154 ニッセイ基礎研究所「ロシア経済の見通し」神戸(2018)
155 2018年1月の実質賃金の上昇は、同月の最低賃金引上げに伴う名目賃金の上昇の影響が大きい。金野(2018)
156 エネルギー価格が上昇すると、エネルギー資源の輸出額が増え、貿易収支が拡大する。その結果、経常収支黒字が拡大し、外国為替市場に外貨が流入し、通貨ルーブルが増価しやすい。井上(2019)
157 米国は、2018年4月と8月に追加制裁を実施した。
(3)企業部門
次に、企業部門についてみる。鉱工業生産指数は2018年に入り堅調に推移していたが、2018年後半には、製造業の軟調が生産全体の重荷となった。一方、鉱業は着実な増加基調が保たれていたものの足下では、増勢が鈍化している。これは、2018年央の原油価格上昇を受け、OPECプラスの減産目標が緩和されたが、12月には協調減産が合意され、再び増産に歯止めがかかっていることが影響していると考えられる(第Ⅰ-3-6-7図)。
第Ⅰ-3-6-7図 ロシアの鉱工業生産の伸び率(前年同月比)推移
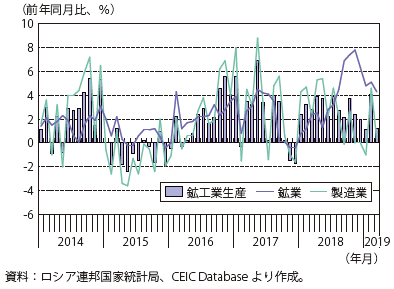
景況感は、景気判断の基準となる50を上回って推移しているものの、2018年末頃から頭打ちとなっており、付加価値税の引上げや年金改革など内需への影響懸念、世界経済の減速など外需の影響懸念等が起因していると考えられる(第Ⅰ-3-6-8図)。
第Ⅰ-3-6-8図 ロシアの景況感の推移
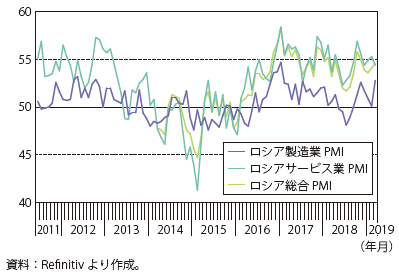
(4)貿易
ロシアは、輸出の過半を石油・ガスを中心とした鉱物性燃料が占め、一般機械や電子機器等の高付加価値製品を輸入する貿易構造であり、貿易構造の多角化が目下の課題となっている。前述の国家目標においても言及されており、「今後6年間で非原料・非エネルギー輸出158を年間2500億ドル」に拡大する159という目標が示されている。しかし、2018年時点で、非原料・非エネルギー輸出額は、約1,350億ドル程度となっており、未だ目標達成までは乖離があり、今後の行方が注目される(第Ⅰ-3-6-9図)。政府は、輸出促進を目的に公的企業であるロシア輸出センター160を設立し、輸出企業への支援を行っている。具体的には、輸出に関する情報提供から輸出手続きのサポート、資金調達など金融面の支援まで幅広く支援している。
第Ⅰ-3-6-9図 ロシアの輸出構造の推移
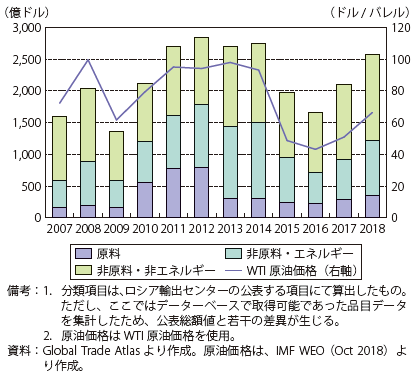
次に、主要な貿易相手国をみると、依然としてEU諸国が最も大きい割合を占めている一方、EU諸国の占める割合は逓減しており、中国の占める割合は、徐々に大きくなっている。直近(2018年)では、輸出入ともに、中国の占める割合が過去最大となり、輸出総額に占める割合は約12%、輸入総額に占める割合は、約22%となった。輸出総額に占める中国への輸出割合は、クリミア危機のあった2014年以降から堅調に増加している。主な輸出先であるEU諸国に代わる販路としての中国の存在感の高まりが示唆される(第Ⅰ-3-6-10図)。
第Ⅰ-3-6-10図 ロシアの輸出相手国のシェアの推移
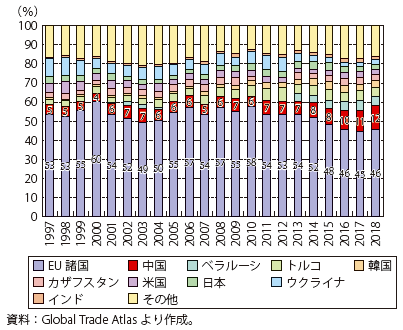
直近(2018年時点)と1998年時点で、輸入相手国のシェアを比較すると、EU諸国やウクライナ、カザフスタンなどの旧ソ連諸国の占める割合が逓減していることが分かる。他方、中国の占める割合は、継続して増加しており、20年前の1998年には、約3%のシェアにすぎなかったが、直近では約22%と約7倍を超える割合となっている(第Ⅰ-3-6-11図)。
第Ⅰ-3-6-11図 ロシアの輸入相手国のシェアの推移
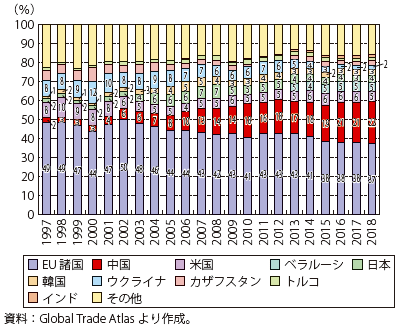
中国から輸入されている品目をみると、電気機器及び一般機械が輸入の大半を占めている。資源を始めとする原料を輸出し、高度な製品を輸入するという貿易構造は、対中国においても当てはまると言えよう(第Ⅰ-3-6-12図)。
第Ⅰ-3-6-12図 ロシアの中国からの品目別輸入額の推移
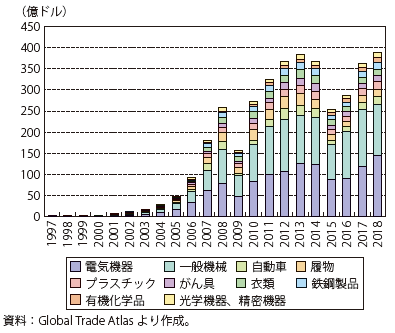
158 ロシア輸出センターのHPに分類品目とHSコードの対応表が公表されている。ウェブサイト閲覧は、2019年3月時点。https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/![]()
159 ロシアが非原料・非エネルギー輸出を増やしたい動機の一つとして、原料・エネルギー輸出に特有の価格乱高下に影響されたくない為であるとの見方もある。服部(2019)
160 2018年9月の時点では、約9,000社の輸出企業がロシア輸出センターの支援を受けたとされている。2018年には、中国、ウズベキスタン、インドに拠点が開設された。2021年までには、外国に50程度の拠点を設ける予定となっている。服部(2019)
(5)投資
また、経済成長の加速化に向けた優先課題として、対内直接投資の増加に向けたビジネス環境の改善が挙げられている。近年、ロシアのビジネス環境は大幅に改善しており、世界銀行が公表しているビジネスしやすさランキングでは、2019年には31位と2011年の123位から大きく上昇した。項目別では、電力事情や不動産登記などのランクが上昇し、ほぼ全ての項目で日本を上回る結果であった(日本は総合で第39位)(第Ⅰ-3-6-13図)。このように、ビジネス環境は改善しているという見方がある一方、対内直接投資は伸び悩んでおり161、2017年は前年比12%減の285億ドルとなった。業種別では、鉱業、金融・保険業への資本流入が大きく、投資面でも資源分野への依存が見られる(第Ⅰ-3-6-14図)。
第Ⅰ-3-6-13図 ロシアのビジネス環境
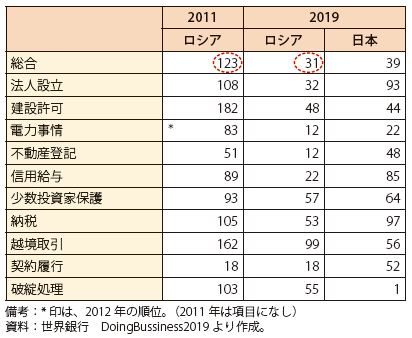
第Ⅰ-3-6-14図 ロシアの対内直接投資額の推移(業種別、ネット、フロー)
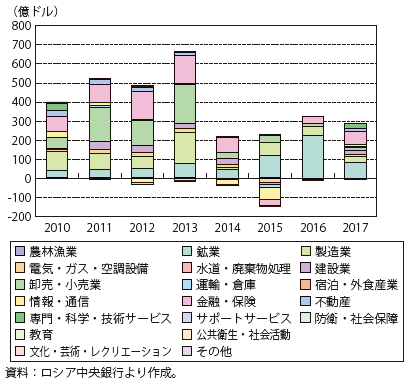
161 日系企業がロシアへ投資する際のリスクとしては、不安定な為替、行政手続の煩雑さ、税制・税務手続の煩雑さ等が挙げられている。JETRO「ロシア進出日系企業調査2017」
2.年金改革と付加価値税率引上げの背景
2019年1月、年金受給開始年齢の延長を柱とした法案162が施行された163。背景には、人口減少や少子高齢化に伴う現役世代への負担の増加、ひいては財政逼迫の懸念がある。我が国と同様、ロシアも少子高齢化が大きな課題となっており、特にソビエト連邦崩壊後に生まれた20歳以下の人口が少ないと指摘されている。総人口に占める高齢者割合164は、上昇基調で推移しており、2018年時点では4人に1人が高齢者となっている。今後、さらに少子高齢化が進み、人口は減少していくと予想されており、2030年には、1億4,500万人まで減少すると予想されている165。(第Ⅰ-3-6-15図・第Ⅰ-3-6-16図)
第Ⅰ-3-6-15図 ロシアの年齢階層別人口の推移
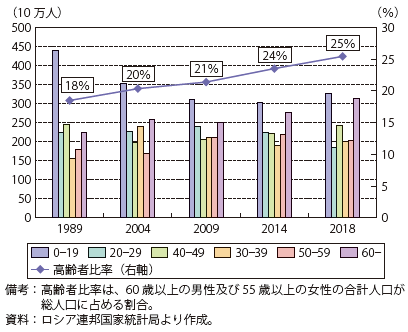
第Ⅰ-3-6-16図 ロシアの人口予測の推移
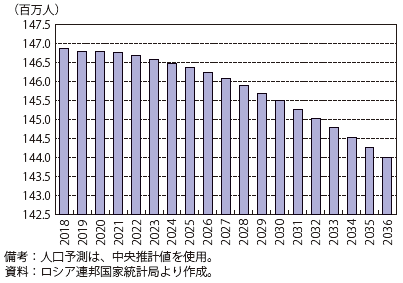
また、財政上の課題も年金改革を後押しした。同国の歳入の約4割は、石油・ガス関連の収入で賄っている166(第Ⅰ-3-6-17表)。そのため、原油価格の動向によっても国家の財政運営が左右される側面がある。実際に、原油価格が大きく下落した年には、歳入が前年より減少し、財政収支が赤字になっている167(第Ⅰ-3-6-18図)。プーチン大統領は、原油価格の下落や石油埋蔵量の減少からも、石油やガスの輸出による歳入に依存することに警鐘を鳴らしていた。その上で、長期的な財政の運営の為にも、年金制度改革の必要性を訴えた。
第Ⅰ-3-6-17表 ロシア連邦財政(歳入)の推移
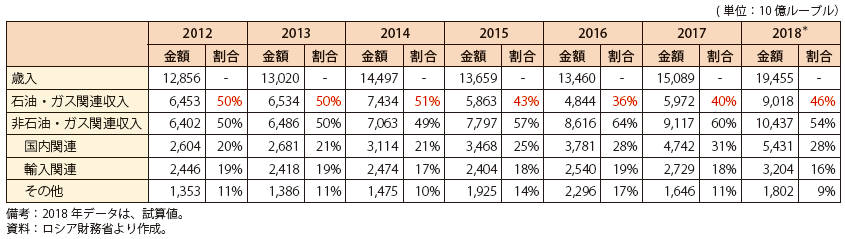
第Ⅰ-3-6-18図 ロシアの連邦財政収支推移
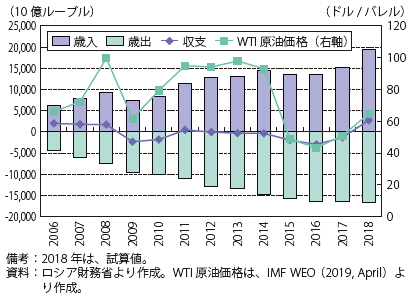
それらを背景に、2019年1月より付加価値税率が引上げられ、先述の大統領令で示された国家目標を達成するためにも、政府は財政の健全化を進めようとしている。
162 年金給付開始年齢は、男性は60歳から65歳に、女性は55歳から60歳に引上げるとする。その他、年金の早期給付(一定期間年金保険料を納付したものには、規定より2年早く給付する等)、極北地域や専門職、多子家庭の母親、農業従事者、公務員、それぞれの年金給付条件の変更や失業手当の引上げなどが含まれている。
163 「年金給付及びその決定に関する個々の連邦法令の改正に関する法律(2018年10月3日成立 連邦法第350号)」(外国の立法No278-1)
164 ここでは、ロシア連邦国家統計局の公表に倣い、60歳以上の男性及び55歳以上の女性を高齢者とした。
165 2010年代半ば以降には、ロシアで出生率が極めて低い水準にあった当時(1993年~2000年代半ば)に生まれた世代が成人し、出産年齢を迎える。その為、ソ連崩壊直後から見られた出生率の劇的低下が影響を表すのは、2010年代半ばと指摘されている。その後、2005・2006年のプーチン大統領(当時)による年次教書演説でも出生率が低迷している問題は触れられ、2006年12月に育児手当等の増額、さらに「母親基金」と称する育児支援制度が定められた。その後、2007・2008年には、出生率はソ連崩壊後最も高い値を示したものの、出生率が上昇してから、国レベルの人口動態に影響を与えるのは、出生率上昇によって拡大した層が成年を迎えて、出産年齢に達する20~30年後と見られる。雲(2014)
166 石油・ガス関連収入は、石油・ガスの採掘税や輸出関税を指す。
167 原油価格が基礎原油価格を下回った場合、歳入の不足分は国民福祉基金の取り崩しによってファイナンスされるため、歳出総額は削減されない。また、原油価格が基礎原油価格を上回った場合、追加石油ガス収入の金額が国民福祉基金に繰り入れられ歳出増には回されない。
3.今後の展望
2019年のロシア経済については、財政改善に向けた年金制度改革や付加価値税率の引上げに伴い、実質所得が減少することが見込まれ、個人消費を中心に成長の鈍化を懸念する見方が多い。
さらに、クリミア危機や米国大統領選への関与の疑いから実施されている経済制裁が解除される見込みは現時点では低い。制裁は、ロシア経済の不透明感とリスクを高め、ロシア内外からの投資の抑制要因となりうる。長期的にみると、エネルギー分野等においても投資資金や技術の不足が懸念されている。
また、前述のとおり、政府は2024年迄の国家目標達成に向け、成果目標を掲げており、加えて、予算構成などを公表している168(第Ⅰ-3-6-19表)。国家事業の個別予算編成をみると、人的資本分野では、「人口動態」や「保健」、生活環境分野では「安全で高品質な自動車道路」、経済成長分野では「基幹インフラの更新」、「デジタル経済」などに予算が多く注ぎ込まれる予定となっている。しかし、多額の資金投下が予定されている分野でも、外部資金を元に予算を組まれているものもある。民間資金が呼び込まれず、目標実現が困難になる可能性もあり、今後の実現性には注視が必要である。
第Ⅰ-3-6-19表 ロシアの2024年までの国家事業の予算編成
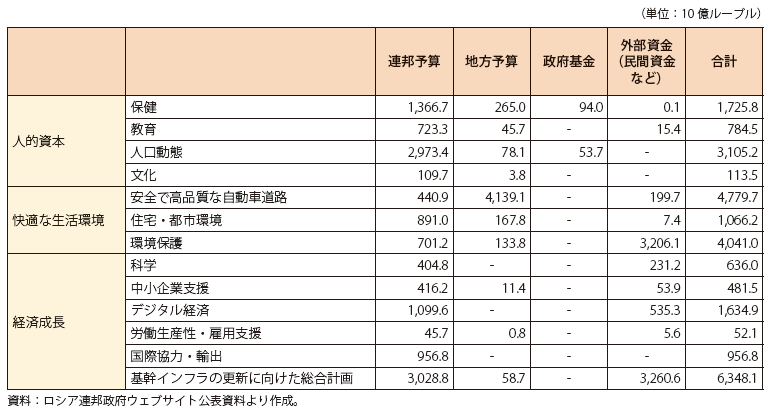
168 http://government.ru/news/35675/![]()
ウェブサイト閲覧日は、2019年4月10日時点。
