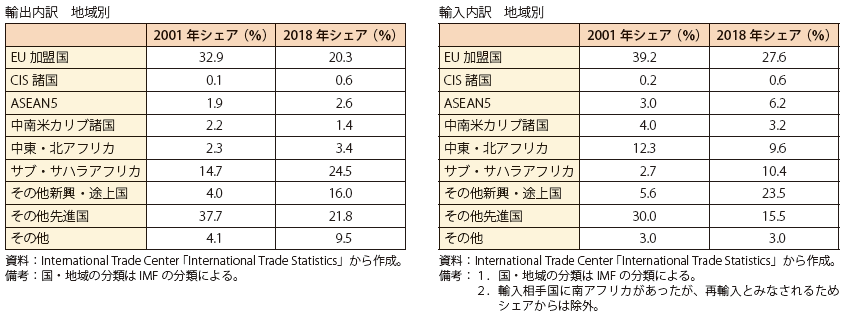- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第1部 第3章 第7節 中東・アフリカ
第7節 中東・アフリカ
本白書の第1部第2章では、新興国の金融リスクについて分析をした。2018年は、トルコやアルゼンチンを始めとする一部の新興国で通貨の大幅な下落が起こるなど、新興国発の金融危機への懸念が大きく取り上げられた年であった。本節では、新興国の金融リスクで話題となったトルコ、南アフリカを中心に経済動向について見ていきたい。
1.中東
(1)中東諸国のGDP
まず、中東諸国169の経済を概括する。2017年の中東諸国のGDPの構成を見ると、1位のトルコ、2位のサウジアラビア、3位のイランの3か国で中東諸国のGDPの58%と過半数を占めている(第Ⅰ-3-7-1図)。
第Ⅰ-3-7-1図 中東諸国におけるGDPシェア(2017年)
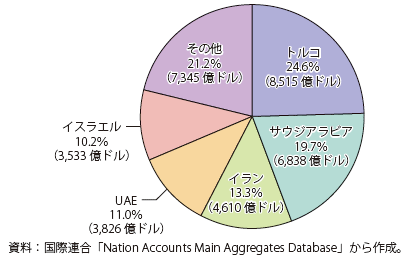
中東主要国の実質GDP成長率の推移を見ると、ITバブルが崩壊した2001年に伸びが減速又は縮小し、世界金融危機の2009年には縮小する国が相次いだ(第Ⅰ-3-7-2図)。2018年の実質GDP成長率は、2.0%と2017年の1.8%から緩やかに加速しており、2018年のトルコ・ショックともいわれるトルコ発の金融市場の動揺による他の中東諸国への影響は限定的であったと考えられる。
第Ⅰ-3-7-2図 中東主要国の実質GDP成長率の推移
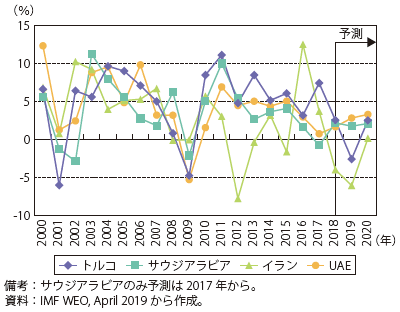
169 本項では中東を外務省のHPに併せて、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、レバノンの15か国を指す。
(2)トルコの経済動向
①GDP
トルコの2018年第4四半期実質GDP成長率(前年同期比)は、トルコ軍のクーデター未遂事件でマイナス成長となった2016年第3四半期以来、9四半期ぶりにマイナス(▲3.0%)に転じた(第Ⅰ-3-7-3図)。2018年8月に米国がトルコに制裁を課したことを契機にトルコ・リラが暴落、8月13日には6.859リラ/ドルの底値をつけ、年初来の下落率は81%となった170。この急激な通貨下落はトルコ・ショック171といわれ、その後のトルコ経済に大きな打撃を与え、GDP成長率は2018年第1四半期の7.4%から第4四半期には▲3.0%まで下落した。トルコ経済を牽引してきた民間消費や固定資産形成が大きく減少し、それぞれ▲5.8%、▲3.8%とGDP成長率の減少に大きくマイナス寄与した。一方、純輸出が同年第2四半期からプラスに寄与しており、第4四半期には8.6%とプラス寄与度が拡大している。この純輸出の拡大は、通貨安が輸出にプラスに寄与することも大きな要因と考えられる。
第Ⅰ-3-7-3図 トルコの実質GDP成長率と需要項目別寄与度
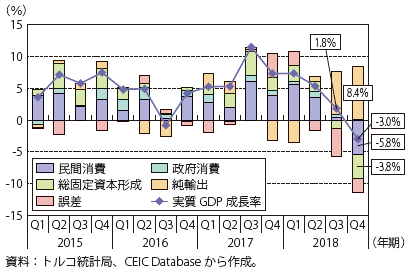
170 通貨下落の詳細については第1部第2章第1節を参照。
171 トルコ・ショックによる金融市場への影響については、第1部第2章第1節新興国の金融リスク4.(2)を参照のこと。
②トルコ・ショックによる影響
トルコ・ショックによる通貨の大幅下落の影響は、消費者信頼感指数や雇用にも広がった。消費者信頼感指数は、同年7月をピークに大きく下落し、12月には58.2まで下落した。また、失業率は、同年4月頃から上昇に転じており、12月には13.5%まで上昇した(第Ⅰ-3-7-4図)。このように、トルコ・ショックによる金融市場の動揺はトルコの実態経済にまで大きく影響を及ぼしたといえる172。
第Ⅰ-3-7-4図 失業率と消費者信頼感指数
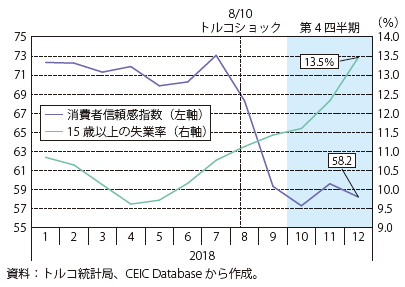
③経常収支
次にトルコの経常収支の推移を見ていく(第Ⅰ-3-7-5図)。トルコの経常収支は、恒常的に赤字が続いており、中でも貿易収支の赤字が経常収支の赤字の大半を占めている。
第Ⅰ-3-7-5図 経常収支の推移
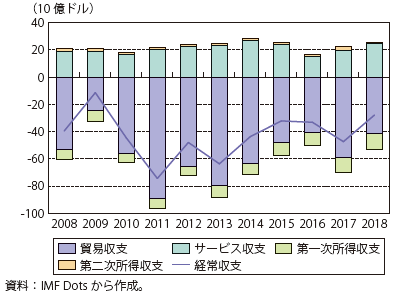
一方、サービス収支は黒字が続いている。サービス収支の中でも旅行収支が黒字を牽引しており(第Ⅰ-3-7-6図)、トルコの大きな収入源になっている。旅行収支は、2016年、クーデター未遂事件が要因で落ち込んだが、その後は回復し、2018年はサービス収支も事件以前の2015年の水準まで戻っている。
第Ⅰ-3-7-6図 サービス収支の推移
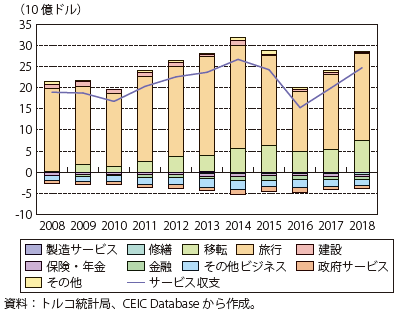
訪トルコ外国人数及び観光収入の四半期ごとの伸び率を見ていく。トルコを訪れる外国人の人数と観光収入の前年同期比の伸び率は2018年を通じてプラスで推移しており、トルコ・ショック下でも伸び率は鈍化したものの、外国人観光客の人数、観光収入とも増加しており、悪影響は限定的である。逆に通貨安が割安感に繋がり、旅行客の増加にはプラスに寄与したものと考えられる。他方で、トルコ国籍の旅行者(国内旅行)の観光収入の伸び率は、2018年の第3四半期は▲19.9%とマイナスとなっており、通貨下落による雇用悪化など経済悪化が影響していると思われる(第Ⅰ-3-7-7図)。
第Ⅰ-3-7-7図 訪トルコ外国人数、観光収入(全体・外国人・トルコ国籍)の前年同期比の伸び率
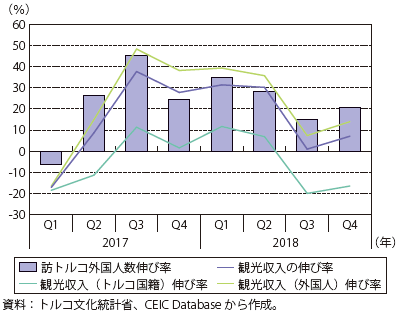
④貿易動向
トルコの財貿易収支を見ると、2018年1月までは、旺盛な内需を背景に貿易赤字が拡大傾向にあった。しかし、トルコ・リラが対ドルで下落し始めた2018年2月から次第に輸入(前年同月比)の伸び率が鈍化し始め、2018年12月には同▲28%まで落ち込み、輸出は微増で推移したため、貿易収支の赤字幅は大きく縮小した (第Ⅰ-3-7-8図)。この背景には、通貨下落による輸入単価の上昇、雇用悪化や物価高騰等による内需の大きな落ち込みがあると指摘されている。
第Ⅰ-3-7-8図 トルコの貿易収支、輸出・輸入の前年同月比の伸び率
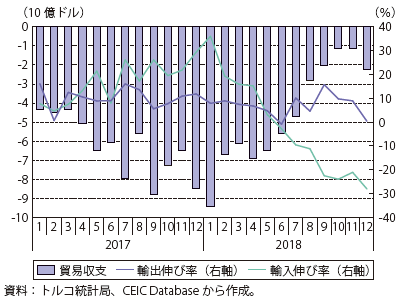
次に、トルコの主要輸出入品目を見ていく。主要輸出品目は、自動車、自動車の部分品、衣類などである。欧州にも近く地理的条件に恵まれるトルコには世界の自動車メーカーの工場が進出しており、現地組み立てを行い自動車の完成車輸出を行っている。また繊維産業はトルコ経済を牽引しており、多くの衣類が輸出されている。その他主要輸入品目としては、天然資源や自動車部品が挙げられる(第Ⅰ-3-7-9表)。
第Ⅰ-3-7-9表 輸出入内訳 上位品目別及び上位国別・品目別(2018年)
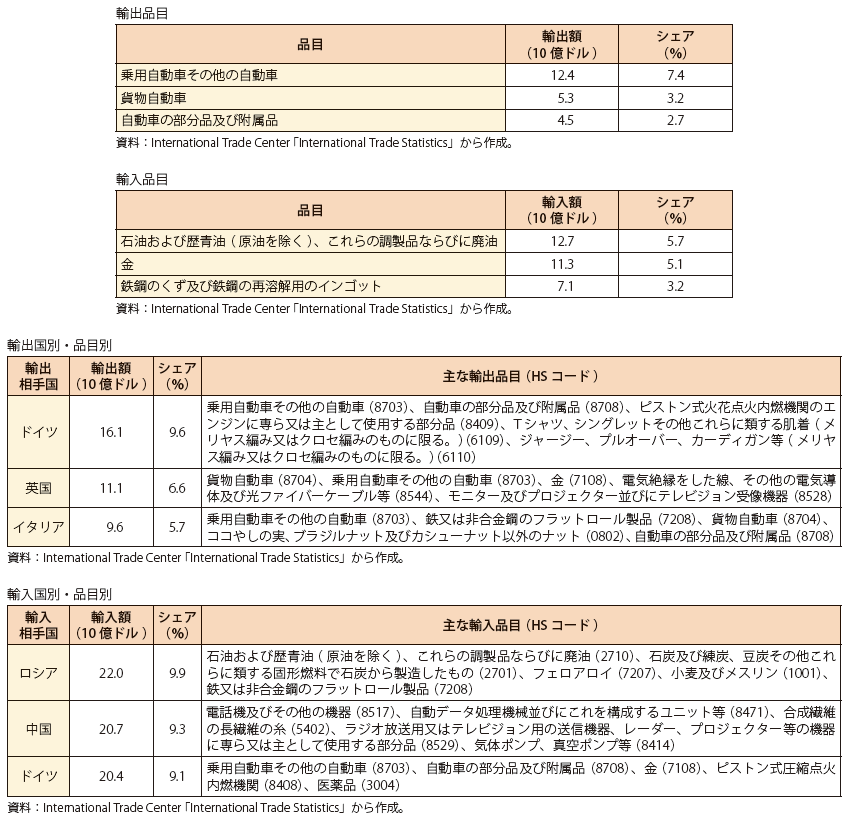
貿易相手国では、ロシア、中国、ドイツの3か国からの輸入が輸入全体の約3割を占める。地域別に前年同月と比較した輸入額の推移(第Ⅰ-3-7-10図)を見ると、多くの地域からの輸入が減っているが、特にEUとアジアからの輸入が大きく減っている。輸出については、ドイツ、英国、イタリアを始め欧州に多く輸出しており、地理的に近い欧州との関係の強さがうかがわれる。なお、日トルコ間については、現在、経済連携協定(EPA)の協議が続いており、日トルコEPAが発効されることになれば、日トルコ間貿易の一層の活発化の他、同協定のもとビジネス環境の整備が進められ、二国間ビジネスの円滑化・投資の活発化が期待される。
第Ⅰ-3-7-10図 トルコの地域別輸入額の前年同月との差の推移
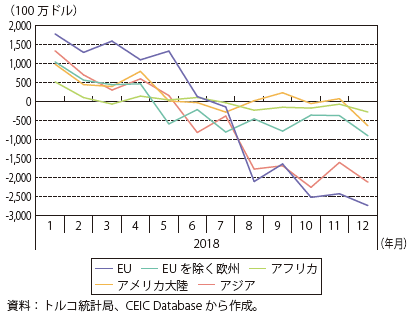
2.アフリカ
(1)サブサハラ・アフリカ地域のGDP
サブサハラ・アフリカ地域173では、人口の急速な増加とともに、潤沢な鉱物性資源が確認され資源開発が進むなど、経済規模も拡大している。
実質GDP成長率は、2009年の世界金融危機後に一時急減速したものの、2015年までは年によって多少の変動はあれど5~7%と総じて高い成長率を維持してきた。2015年、2016年には、原油価格など一次産品価格の下落により174大きく減速し、その後、2017年には回復基調に戻ったが、2018年にかけては再び足踏みをしており2018年のGDP成長率は3.0%と推計されている(第Ⅰ-3-7-11図)。
第Ⅰ-3-7-11図 サブサハラ・アフリカ地域の実質GDP成長率の推移
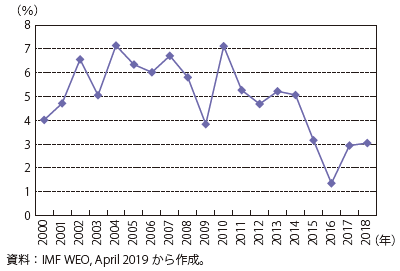
サブサハラ・アフリカ地域の名目GDPのシェアを見ると、高い順に、ナイジェリア、南アフリカ、アンゴラ、エチオピア、ケニアと続き、ナイジェリアと南アフリカで約半分を占めている(第Ⅰ-3-7-12図)。
第Ⅰ-3-7-12図 サブサハラ・アフリカ地域の名目GDPシェア(2017年)
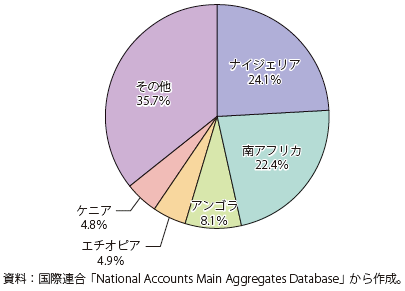
173 本項ではサブサハラ・アフリカ地域を外務省のHPに合わせて、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レソトの49カ国を指す。
174 2014年から2016年にかけて原油価格が半値以下に下落したことにより域内産油国であるナイジェリアやアンゴラの国内総生産が減少した。「アフリカの経済成長は急激な減速から回復基調に」(世界銀行2017年4月)では、(原油価格を含む)一次産品価格の下落によって域内主要国のナイジェリア、南アフリカ、アンゴラの経済が停滞したとしている。
(2) 南アフリカの経済動向
①GDP
南アフリカの実質GDP成長率を見ると、2000年から2008年にかけて平均4.2%と高成長が続き、2009年の世界金融危機では一時的にマイナスに転じるも、翌年には3.0%と再びプラス成長に戻った。しかし、その後は総じて鈍化傾向になり、2010年から2018年にかけては平均1.9%と低成長となっている(第Ⅰ-3-7-13図)。
第Ⅰ-3-7-13図 南アフリカの実質GDP成長率の推移
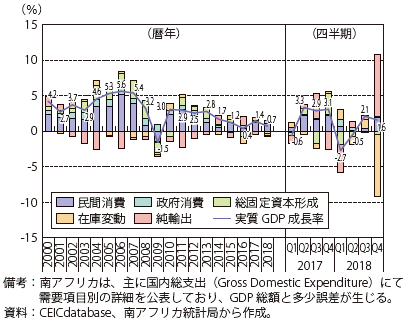
②産業構造
南アフリカの産業構成を産業別粗付加価値額(GVA175)比率で見ると、2018年には第三次産業の割合はおおよそ70%であり、先進国並みの割合となっている。産業別では、「金融業、不動産業及び業務サービス」(以下、金融業とする)22.4%が最も高く、「卸小売業及び外食宿泊業」15.1%、「政府サービス」16.7%、「製造業」13.5%と続き、「鉱業」は6位の8.1%しかない(図Ⅰ-3-7-14図)。
第Ⅰ-3-7-14図 南アフリカの産業別粗付加価値額(GVA)比率(2018年)
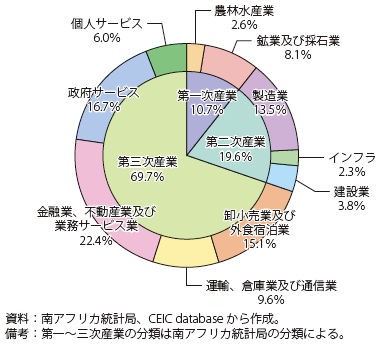
南アフリカはこれまで鉱業で稼いだ資金を製造業や金融業の発展のために投資してきた。製造業は、成長軌道に乗れなかったものの176、金融業はアフリカの金融センターとも言われるほど成長してきた177。鉱業、製造業、金融業の成長について、GVAに占める割合の推移で見ていく。1950年と2018年時点で比較すると、金融業は、GVAに占める割合が右肩上がりで推移しており、同期間8.9%から22.4%まで上昇した。製造業は1981年にピークの22.5%となり、その後おおよそ横ばいで推移していたが、1990年代後半から減少している。鉱業は1980年にピークの19.4%まで上昇したが、その後は低下が著しく、2018年に8.1%まで落ち込んでいる。なお、南アフリカの白金、クロム、チタンの生産量は世界第1位であり、鉱物資源の輸出額が全品目の輸出総額の半分を占めており、鉱業はいまだ主要な産業の一つである178(第Ⅰ-3-7-15図)。
第Ⅰ-3-7-15図 鉱業、製造業、金融業のGVAに占める割合の推移

175 生産側から推計された実質総付加価値。純間接税に左右されるGDPより、月次景気指標に近い動きをすると言われている。
176 例えば、ケープタウン大学(2017)によれば、南アの製造業セクターはGDP成長率と雇用創出の両面において成果が乏しい“the manufacturing sector has performed poorly, both in terms of GDP growth and job creation.”とされている。(http://www.dpru.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/36/Publications/Working_Papers/DPRU%20WP201702.pdf![]() )
)
177 野村総合研究所「アフリカの金融セクター」2011年 https://ab-network.jp/wp-content/uploads/2013/12/f2557ddfa5d469d682051b684a0c8910.pdf![]()
178 http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2018/12/trend2018_za.pdf![]()
③経常収支
南アフリカの経常収支の推移について見ると、2003年以降赤字が続いている。2016年以降は貿易収支が黒字に転じているが、所得収支が経常収支の赤字幅を拡大させており、2018年には経常収支の赤字額の約9割を所得収支が占めている(第Ⅰ-3-7-16図)。継続した外貨流入がなければ、経常収支の赤字は改善されないが、南アフリカにおいては、実質GDP成長率の需要項目別寄与度における固定資本形成が低調である(第Ⅰ-3-7-13図)ことの背景ともなっているが、外国からの直接投資額が十分でない状況がある。南アフリカ準備銀行によると、非居住者による投資がより多様化し、大きな増減がないことから、赤字が固定化していると指摘する。配当金や利子といった所得支払いが近年大幅に増えている理由は、南アフリカ政府が負債を高い利率で大量に借りていることが要因としている179。
第Ⅰ-3-7-16図 南アフリカの経常収支の推移
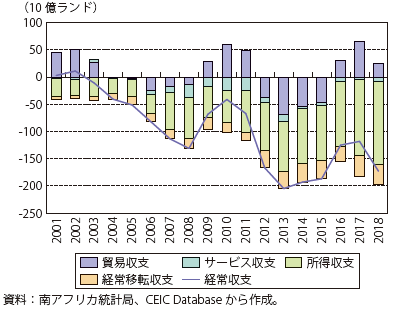
④貿易動向
南アフリカの輸出入について見ていく。白金、クロム、チタン、ダイヤモンドといった鉱物資源に恵まれる南アフリカは、これらの鉱物資源が主な輸出品目となっている。しかし、資源国でありながら石油に乏しいため、石油を多く輸入している。石油の他には機械類を輸入している。
輸出品目の上位を鉱物資源が占める中、自動車も多く輸出している。南アフリカの自動車産業は1995年9月に始まった自動車産業開発プログラム(Motor Industry Development Programme)により発展し、生産や輸出を伸ばした。MIDPは2012年まで行われ、プログラム実施期間である1995年から2012年までの間に生産台数は37.6万台から50.4万台まで増加し、輸出台数は1.2万台から27.7万台まで伸びた180。南アフリカは2013年には、2020年までの次の自動車政策である自動車生産発展プログラム(Automotive Production Development Programme)を、2018年には2021年から2035年までの更なる計画(South African Automotive Masterplan 2035)を発表し、2035年までに世界の自動車生産高の1%に達すること等を目標に掲げている。貿易の相手国では、輸出、輸入とも上位3か国は中国、ドイツ、米国となっている(第Ⅰ-3-7-17表)。中国へは鉄鉱などの鉱物資源を多く輸出しているが、欧米諸国や日本、ボツワナ、ナミビアには完成車も輸出している。
第Ⅰ-3-7-17表 輸出入内訳 上位品目別及び上位国別・品目別(2018年)
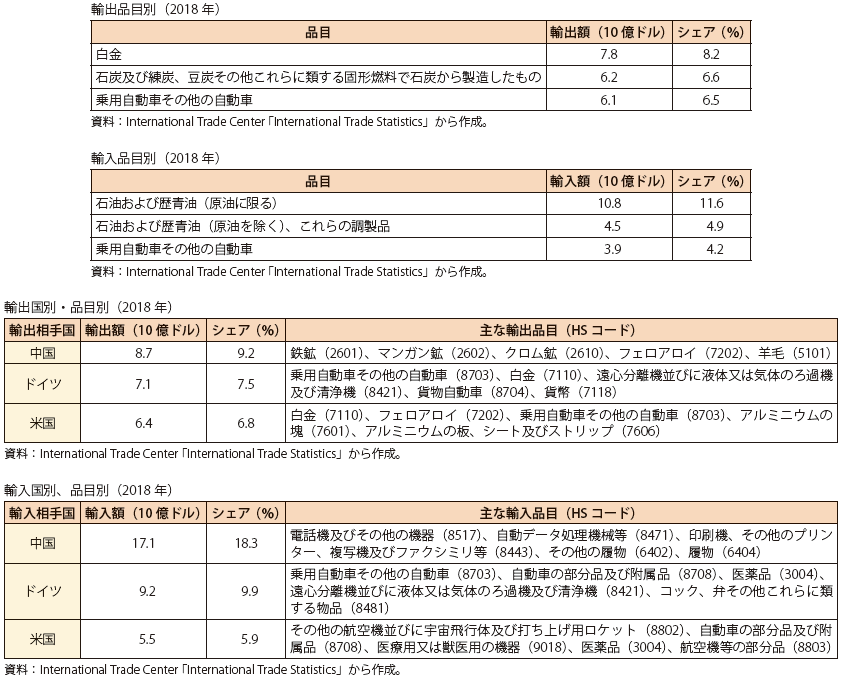
南アフリカの貿易の地域別のシェアを2001年と2018年で比較すると、2001年では輸出、輸入ともにEU加盟国とその他先進国で約7割を占めていた。ところが2018年には4割ほどまでに低下し、その代わりCIS諸国やASEAN5、サブサハラ・アフリカ、その他新興・途上国のシェアが上昇しており、南アフリカの貿易相手地域が広まったことがうかがえる(第Ⅰ-3-7-18表)。
第Ⅰ-3-7-18表 輸出内訳 地域別(2018年)