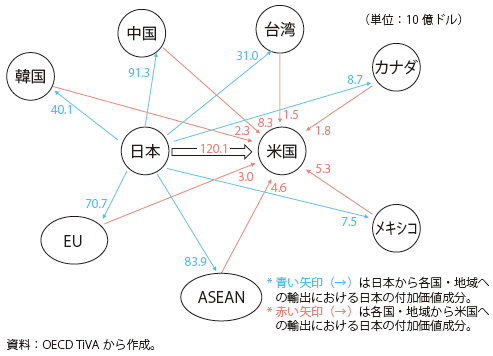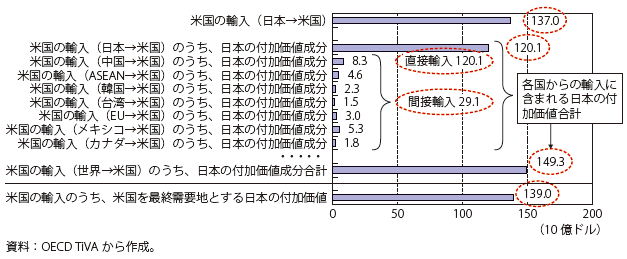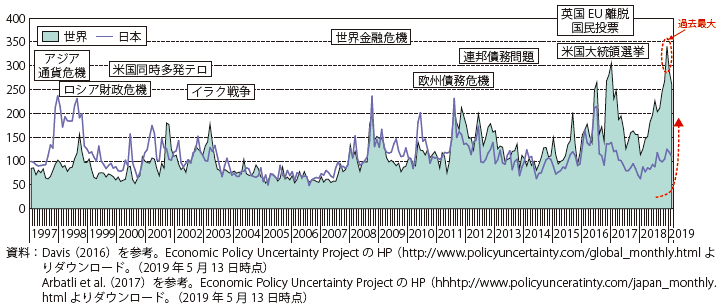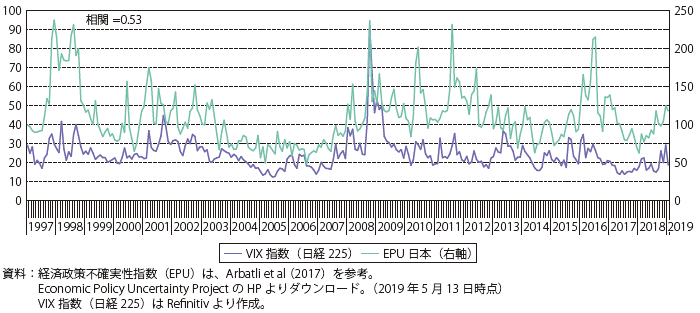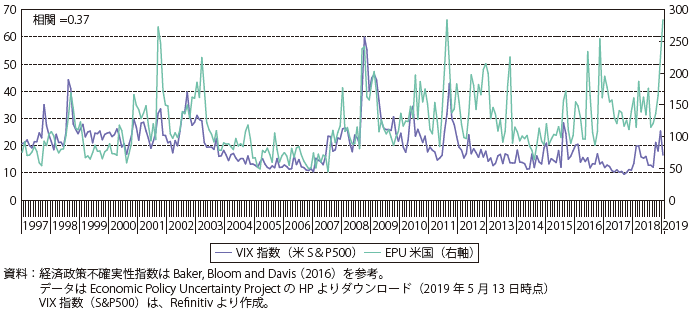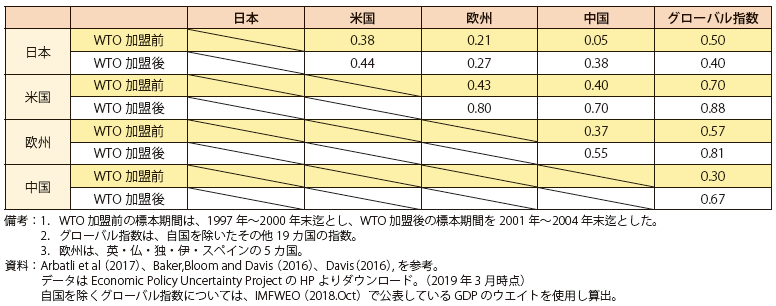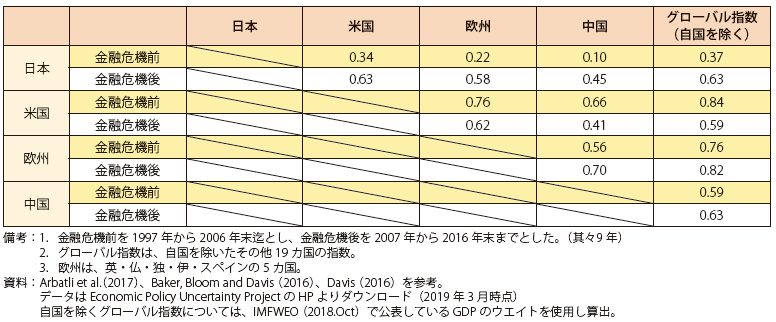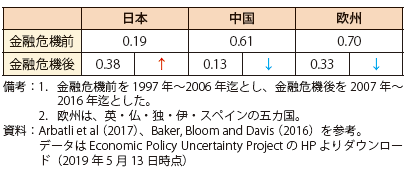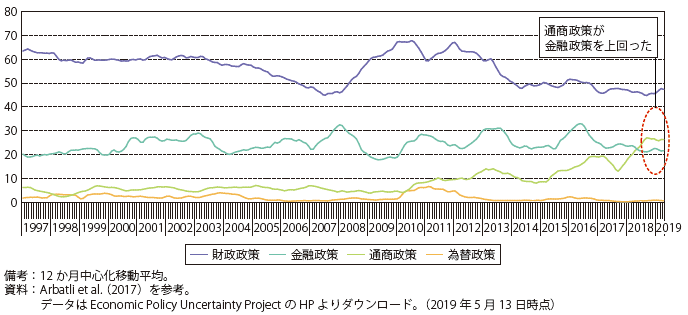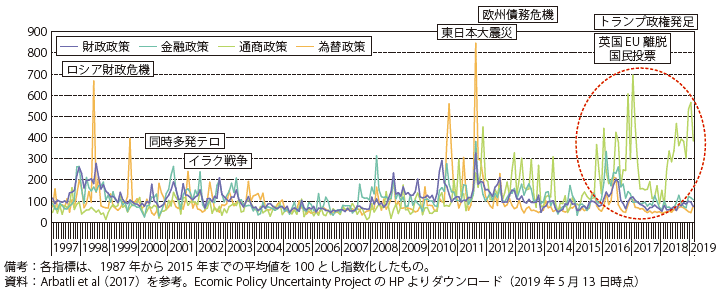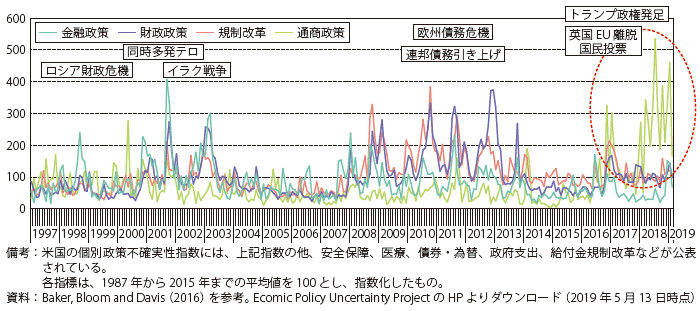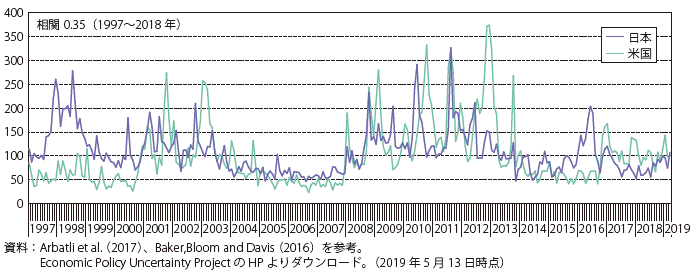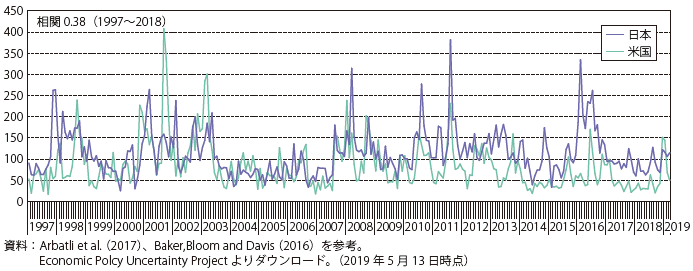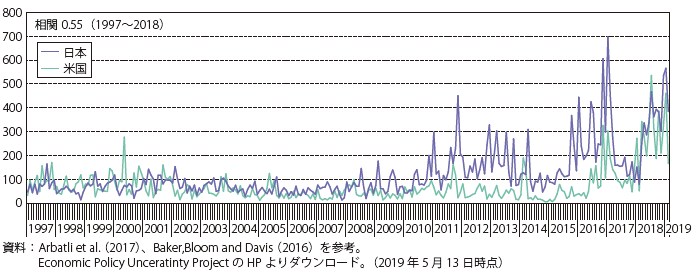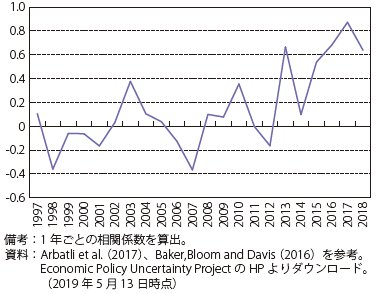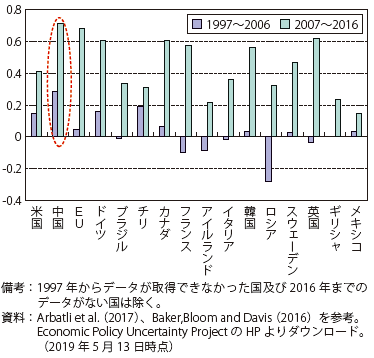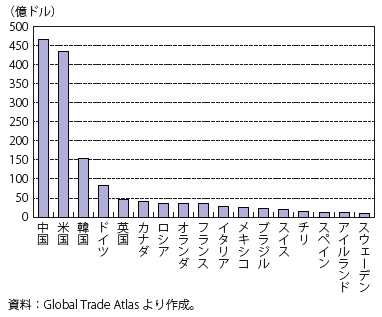- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第1章 第1節 各国・各地域間で深まる経済関係の実態
第1章 国を超えて密接に結びつくグローバル経済の現状
第1節 各国・各地域間で深まる経済関係の実態
自由貿易拡大に支えられたグローバル化の進展
グローバル化は、一般的に資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投資が増大することによって世界における経済的な結びつきが深まることを意味する1とされている。また、経済学的には、製品とサービスの貿易を通じた市場の統合、直接投資や資本取引の統合、アイデアの国境を跨いだ移動がグローバル化を意味しているという2。
グローバル化は、まず蒸気機関の発明による輸送費の大幅な低減により進展し、生産と消費の場所が切り離された(第1次アンバンドリング)ことで貿易が活発に行われるようになった。次にICTの普及により組織化コストが激減したことで、先進国の企業がコストを削減するため、労働集約的な生産工程の一部を切り離した(第2次アンバンドリング)。これにより、①部品の貿易、②生産施設、主要な技術者・管理職、研修、技術、国際的な投資の移動、③生産分散化を調整するためのサービス需要、が生じ伝統的な製品の貿易に留まらない複雑で多様な21世紀型貿易が出現したと言われている3。
さらにヒトを移動させるコストが下がれば、労働サービスが労働者から物理的に切り離され、歴史に残るようなインパクトになるかも知れないとされる(第3次アンバンドリング)。例えば、途上国の労働者が遠隔でロボットを使って先進国の警備業務や家事代行業務を行う、先進国の技術者が途上国の資本設備を遠隔で修理する等の「バーチャル移住」が先進国と途上国間で進み、第2次アンバンドリングが製造業にもたらした長短の結果がそのままサービス分野に引き継がれ、豊かな国の労働者が、貧しい国の賃金労働者と直接、賃金競争することになる可能性が指摘されている4。このように現在のグローバル化は、モノだけでなく人や知識も自由に世界中を移動するようになっている(第Ⅱ-1-1-1-1表)。
第Ⅱ-1-1-1-1表 グローバル化の変遷
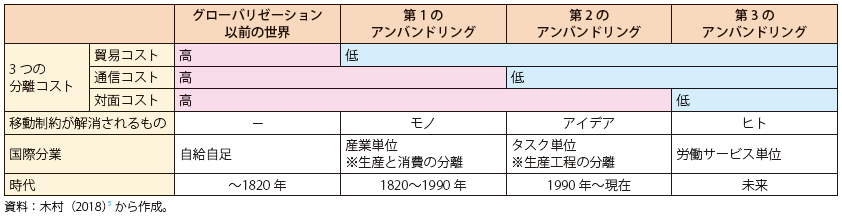
1 内閣府(2004)、p. 149
2 Frankel (2006)
3 ボールドウィン(2018)、Richard Baldwin (2012)「21世紀型貿易と21世紀型WTO」 RIETI (https://www.rieti.go.jp/jp/special/p_a_w/014.html![]() )
)
4 ボールドウィン(2018)、p. 364
1.財・サービスのグローバル化
(1)貿易の拡大と経済発展
まずモノについて、貿易が経済に与える影響はマクロ経済学とミクロ経済学の両面から、経済のパイ拡大、輸入による購買力向上、国レベルでの全要素生産性の上昇、企業レベルでの生産性向上等のメリットがあると分析がされてきた。この点、WTOによれば多くの研究が国際貿易量と経済成長には正の関係があるとしている6。
貿易が行われる理由は、生産技術の相違に要因があるとするリカードの比較優位理論や生産要素賦存7の相違に要因があるとするヘクシャー=オリーン・モデル、規模の経済と製品種類の多様化による消費者利益が先進国間や企業内で貿易が行われる要因であるとするクルーグマンの新貿易理論を基礎として考えられてきた。さらに、生産性が高い企業だけが輸送費を伴うコストが上乗せされる貿易を行うとしたメリッツの「新」新貿易理論にまで至っている。
他方で、貿易を行う動機や必要性が存在したとしても、自由貿易8が行える環境が整っていることに加え、企業が貿易や更に広い意味でのグローバル化に伴う活動を行うに際して、その取引コストを上回る便益がなければ、貿易を含むグローバル化は進展しないため、取引コスト低減を図らないと世界の国々は貿易やグローバル化により発生する成長機会を逃してしまう可能性がある。
貿易を制限する伝統的な手段としては関税がある。関税自体が各国の貿易収支に与える影響はマクロ経済的には小さいものの、長期間、大規模かつ持続的な関税引下げは、企業の対内及び対外直接投資や生産構造を調整するため、企業のGVCへの参加も含め、国際分業を形成する可能性があると言われている9。この点、先進国、新興・途上国とも1995年にWTOが設立された以降の関税率は低下傾向が続いており、特に新興・途上国の平均関税率は1995年の24.2%から2017年には6.7%へ低下した。この間、世界の貿易額は約3.5倍、世界の名目GDPは2.6倍に増加し、世界経済は貿易自由化の進展とともに成長してきたといえる(第Ⅱ-1-1-1-2図)。
第Ⅱ-1-1-1-2図 世界の貿易額と関税率の推移
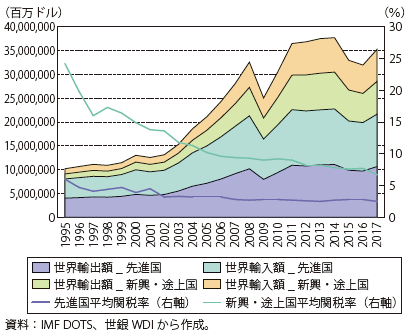
関税の他にも近年では、公正かつ必要不可欠な貿易制限的措置であるか否か外形上は容易に判断し難い技術基準や投資規制等の導入による非関税障壁によって企業の自由貿易を含むグローバルな活動が阻害されるケースが増大してきている10。
また、貿易に欠かせない輸送費の推移を1990年から見ると、2015年までの間に大幅に低下してきたことが分かる(第Ⅱ-1-1-1-3図)。
第Ⅱ-1-1-1-3図 世界の国際輸送コスト指数の推移(1990年=100)
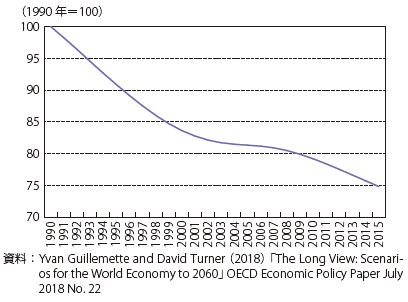
なお、関税や輸送コストも含んだ貿易の取引コストについては、国連アジア太平洋経済社会委員会(以下、ESCAP)が推計しており11、時系列の分析では以下のとおりとなっている。
これによれば、異なる地域間の組合せにより貿易コストに差異があることが分かる。
以下、輸入する地域ごとに貿易コストの変化を見ると2009年以降に各地域の貿易コストは総じて低下傾向にあるものの、アフリカ、中南米、ロシアCISの貿易コストは高めになっており、これを低下させることで更に貿易拡大をする余地が大きいと考えられる(第Ⅱ-1-1-1-4図)。
第Ⅱ-1-1-1-4図 輸入地域ごとの貿易コスト指数の推移
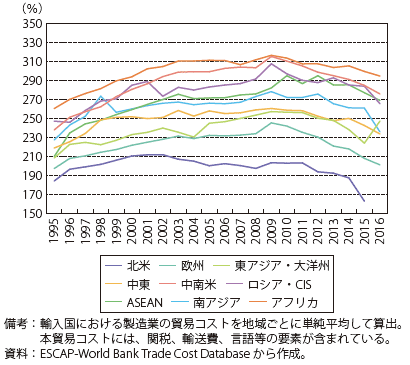
ここでWTOが設立され貿易の自由化が進展した1995年以降の世界における財、サービスの輸出額の推移を見てみる。先進国、新興・途上国の両方において財、サービスとも増加しているが、その中でも新興・途上国の財輸出が急激に増加していることが分かる。
また、サービス輸出についても財輸出に比べて金額は小さいものの先進国、新興・途上国とも着実に増加しており、1995年から2017年にかけて3.8倍となった。新興・途上国全体は増加していないように見えるが、サービス貿易はデータが財輸出ほど整備されておらず、現時点では欠損値が多いためである。そこで、データが存在するBRICSのサービス輸出に限って見て見ると、1995年から2017年にかけて14.7倍となっており、新興・途上国においてもサービス輸出が拡大してきていることがうかがわれる(第Ⅱ-1-1-1-5図)。
第Ⅱ-1-1-1-5図 世界の財、サービス輸出額の推移
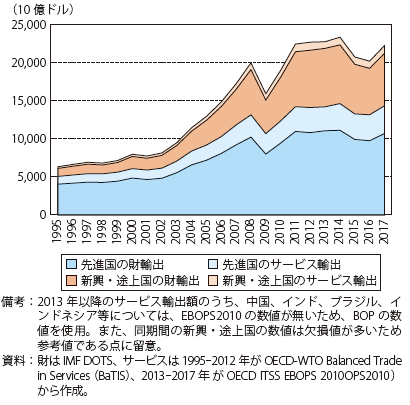
次に主要国・地域において貿易が自国経済にとってどれほどの意味があるのかを、OECDが国際産業連関表を基に算出した付加価値貿易のデータ(OECD TiVA)から見てみる。従来の貿易統計は生産物(財)を対象としているのに対し、付加価値貿易は製品やサービスができあがるまでに、どの国でいくらの価値が加わったかを推計したものである12。各国の国内生産に占める付加価値輸出の割合は、2005年から2015年にかけて一部の国を除き高まっており、各国において輸出は自国の経済成長にとって不可欠なものとなっている(第Ⅱ-1-1-1-6図)。
第Ⅱ-1-1-1-6図 主要国の生産に占める付加価値輸出割合(産業別)
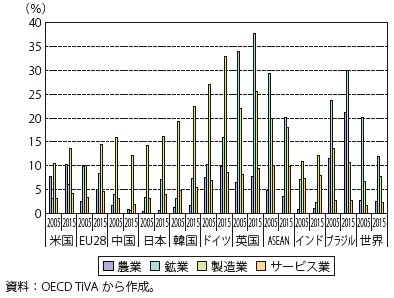
米国、EU28、中国、インドといった国内・域内市場が大きな国・地域は、生産に占める付加価値輸出の割合が低めになる傾向はあるものの、製造業においては生産に占める付加価値輸出の割合は10%を超えており、国内生産を維持して雇用を確保して消費に結びつけるためにも世界市場との繋がりが不可欠になっていることがうかがわれる。
また、ドイツ、英国の付加価値輸出割合が他の主要国・地域より高いのは、EU域内での貿易が多いためと考えられる。EU28の生産に占める付加価値輸出の割合を見ると、製造業においては米国とほぼ同じであり、各国の生産を域内市場で消費しているものと思われる。
さらに、世界の生産に占める付加価値輸出の割合を見ると鉱業を除いて主要国より低い傾向にあり、国内生産したものを輸出せずに国内でのみ消費している国々が多い可能性があり、今後も各国間の貿易が成長する余地があると推察される。
主要国における産業構造を国内生産の産業別割合から見ると、中国においては2005年、2015年とも製造業の国内生産割合が約50%となっており、生産に占める付加価値輸出の割合が2005年で16.0%、2015年で12.2%と近年では国内生産の輸出依存が縮小傾向ではあるものの、国内生産の10%超が海外での消費に向けられるため、貿易が国内経済に与える影響が大きいことがうかがわれる(第Ⅱ-1-1-1-7図、及び8図)。
第Ⅱ-1-1-1-7図 主要国の産業構造の変化(2005年)
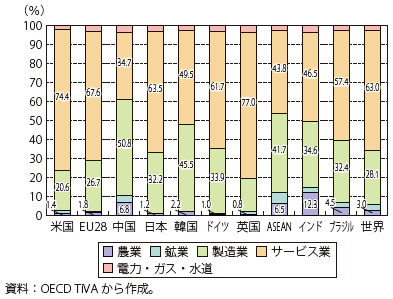
第Ⅱ-1-1-1-8図 主要国の産業構造の変化(2015年)
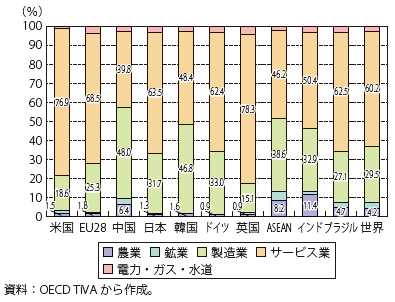
また、中国に次いで国内産業に占める製造業の割合が高い韓国においては、生産に占める付加価値輸出の割合が2005年で19.2%、2015年で22.4%となっており、中国以上に製造業の輸出に国内経済が依拠しているといえる。同様に日本においても生産に占める付加価値輸出の割合が2005年の14.2%から2015年の16.1%と高まり、外需の重要性が高まっているように見える。他にドイツ、英国等のEU加盟国において、生産に占める付加価値輸出の割合が高いが、これはEU域内貿易が活発に行われているためと推察される。
なお、米国、EU28、日本、韓国、ASEAN、インドとも、製造業においては国内生産に占める付加価値輸出の割合が2005年より2015年のほうが高まっており、海外市場との繋がりが強くなってきたことを示している。
次に世界貿易で大きな割合を占めている主要国間の貿易を見ることで、貿易の主軸となっている国がどのように変化してきたかを見てみる13。ここでは、世界貿易(輸出額と輸入額の合計)に占める二国間貿易(輸出額と輸入額の合計)の割合が0.1%以上を占める取引を地図上に表記した。
世界貿易に占める割合が0.1%以上の二国間貿易取引は、2000年では米国が25ヵ国(うち先進国15ヵ国、新興・途上国10ヵ国)、ドイツが19ヵ国(うち先進国14ヵ国、新興・途上国5ヵ国)、日本が16ヵ国(うち先進国10ヵ国、新興・途上国6ヵ国)、中国が6ヵ国(うち先進国5ヵ国、新興・途上国1ヵ国)との間で0.1%以上となっていた。中国の新興・途上国の貿易相手はサウジアラビアで資源取引が中心と考えられ、2000年時点では、米国、ドイツ、日本が世界貿易の主要なハブになっていた。
また、世界貿易において金額の大きい貿易取引は主に先進国間55組14、先進国と新興・途上国間25組で、新興・途上国間は中国とサウジアラビア、及びブラジルとアルゼンチンの2組のみだった(第Ⅱ-1-1-1-9図)。
第Ⅱ-1-1-1-9図 世界貿易額の0.1%以上を占める二国間貿易(2000年)
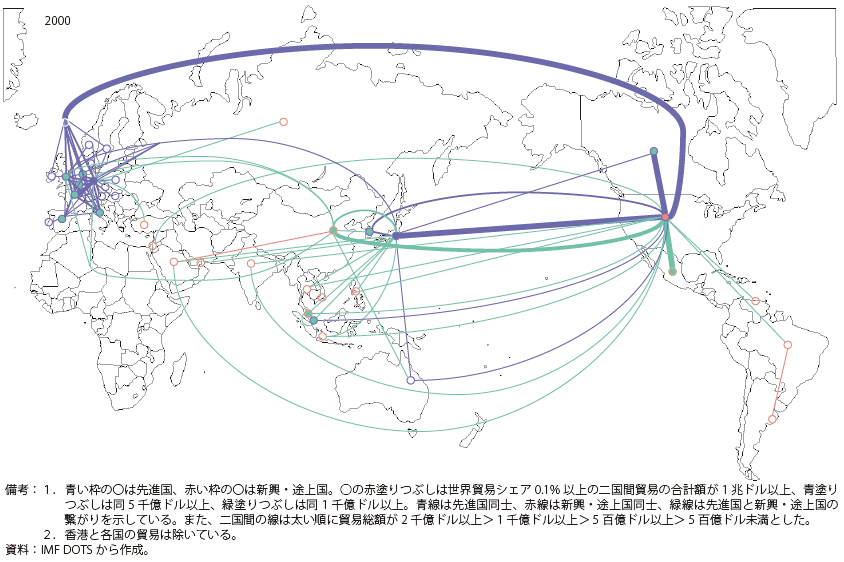
2000年から2017年にかけては、貿易のハブとなる国に大きな変化が生じることになった。世界貿易に占める2国間貿易の割合が0.1%以上の貿易取引は、中国が25ヵ国(うち先進国12ヵ国、新興・途上国13か国)、米国が19ヵ国(うち先進国12ヵ国、新興・途上国7か国)、ドイツが18ヵ国(うち先進国14ヵ国、新興・途上国4ヵ国)、日本が7ヵ国(うち先進国5ヵ国、新興・途上国2ヵ国)となり、中国が米国に代わって最も多くの国と規模の大きな貿易を行うようになった。しかしながら、中国が大規模貿易の相手国数を先進国、新興・途上国の双方で大幅に増やしているのに対して、米国、ドイツ、日本とも貿易相手国、相手国数、及び先進国を中心とした貿易構造という点では、ほとんど変化が見られない。このことは、2017年では先進国間41組、先進国と新興・途上国間25組、新興・途上国間は14組となっており、先進国間では0.1%以上の割合を占める貿易取引が減少したのに対し、新興・途上国間の貿易比率が高まっていることからもうかがわれる。
なお、先進国と新興・途上国間の貿易の組合せのうち、中国が含まれるものは2000年には25組中5組だったが、2017年には25組中12組となった他、2000年には名前の挙がっていなかったベトナムが米国、韓国との貿易で世界シェア0.1%以上となっている。その他の新興・途上国と先進国の組合せでは変化はほとんど見られない。
2017年時点では中国を中心とした新興・途上国間の貿易ネットワーク(地図中の赤線)が主にASEAN、インド、中南米との間で進展していることがうかがわれる(第Ⅱ-1-1-1-10図)。
第Ⅱ-1-1-1-10図 世界貿易額の0.1%以上を占める二国間貿易(2017年)
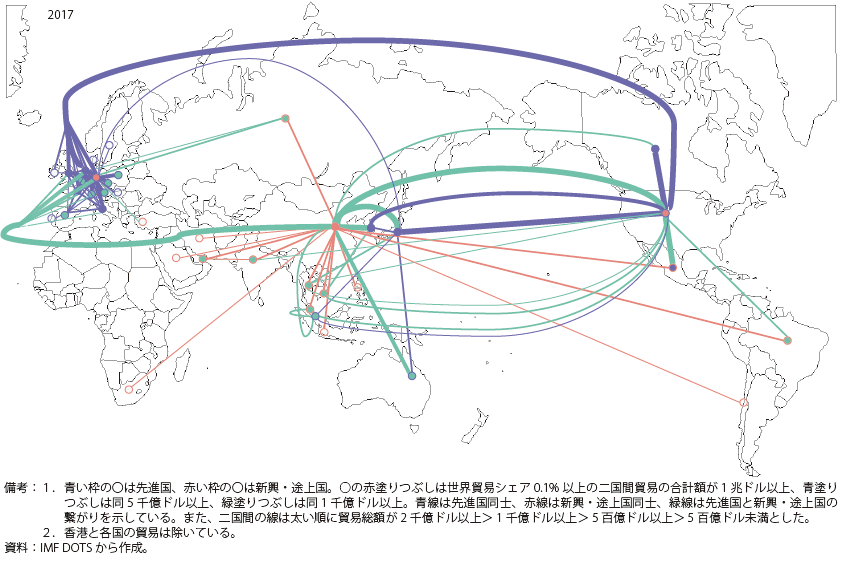
5 木村(2018)、p. 8-14
6 経済産業省(2017)、p. 176-179
7 各国は、労働力、資本力、技術力等で相対的に比較優位を持つ生産要素を集約的に用いて生産される財を輸出入する。
8 「自由貿易」とは、一般に国家が、貿易に対して制限を加えないことをいう。
9 IMF (2019), p. 115-116.
10 第Ⅱ部第2章4節参照。
11 ESCAP (2017).
12 猪俣(2014)、広田(2017)。
13 加藤、永沼(2013)。
14 地図の表記と同様に香港を除いた数でカウント。
(2)グローバル・バリュー・チェーン(GVC)の深化
既に見てきたように、関税の引下げを始めとする貿易の自由化に支えられて、世界的に貿易額が拡大してきた。その過程で量的な拡大だけでなく、中間財を中心とする貿易構造への変化があり、その背景に国際的な生産分業が指摘されている(第Ⅱ-1-1-1-11図)。
第Ⅱ-1-1-1-11図 世界の財別輸出の推移
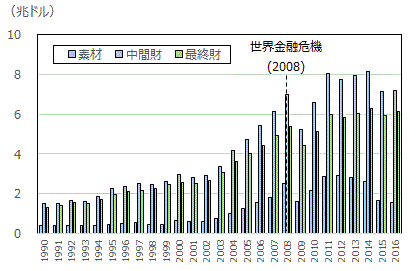
貿易自由化によって貿易コストが低下すれば、生産活動を工程間で分割して複数の国で行うことが可能となる。単純な国際的生産分業のモデルとしては、まず、基幹部品など付加価値の高い中間財を資本・技術の豊かな地域で生産する(第Ⅱ-1-1-1-12図)。次にその中間財を賃金の安い国に輸出して組立工程を行うことで生産工程の最適化を行うことができる。最終生産物は消費地に送られるが、生産国内に十分な市場がない場合は、中間財の生産国に輸出されることも、大きな市場を有する第三国に輸出されることもある。この第三国へ輸出されるケースが「三角貿易」と呼ばれるものである。生産分業の複雑化に伴って、中間財が生産拠点間を次々に移動していくことになり、中間財貿易が拡大していく。15
第Ⅱ-1-1-1-12図 国際的な生産分業のモデル
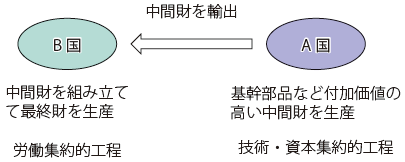
このような国際的な生産活動の連鎖は、一つの製品を各国が協力して次々に仕上げていくということに他ならない。各国における生産活動は相互補完的であり、各国経済も相互依存関係を深めることになる。もし、国際的な生産活動の連鎖のどこかに障害が生じれば1国の問題にとどまらず全体のシステムに影響が及ぶ可能性がある。
2010年代、中間財を始めとする貿易額の拡大が停滞しているとの指摘がある。特に2015年、2016年は中間財が最終財に比べて大きく減少しているように見える。
中間財の貿易額は、構造的には国際的生産分業が拡大する過程で増加していくと考えられる。例えば、直接投資によって海外に生産拠点が移転する場合には、国内から新たな生産拠点向けに中間財の輸出が増加する。多くの企業が次々に海外移転をしていけば、それに応じて中間財貿易は一層拡大する。しかし、個々の生産拠点において操業年数とともに、部品供給業者の現地進出や現地地場企業の技術水準の向上等によって現地で中間財が生産されるようになれば、本国からの中間財輸出は減少する可能性もある。例えば後で見るように日系製造業はASEANで現地調達が拡大し、最近の日本からの調達額はほぼ横ばいとなっている(第3章第3節参照)。こうしたバランスによって中間財輸出額の増減も変わってくるので、必ずしも中間財が最終財に比べて早いペースで拡大するとは限らない。いずれにしても、依然として中間財の貿易額が高水準であり、各国間の自由な貿易が重要であることには変わりがない。なお、2015年及び2016年については、そのような構造的要因とともに、資源価格の低下という特殊な要因の影響も考えられる。両年とも素材・中間財が減少しているが、2014年前半をピークに原油を始めとする資源価格が低下している(第Ⅱ-1-1-1-13図)。主要業種別に素材・中間財の貿易額を見ると、資源価格の影響を受けやすい石油・石炭が大きく落ち込み、化学、鉄鋼等も減少している。一方、電気機械、輸送機械等の中間財(機械部品等)は必ずしも減少していない(第Ⅱ-1-1-1-14図)。
第Ⅱ-1-1-1-13図 資源価格の推移
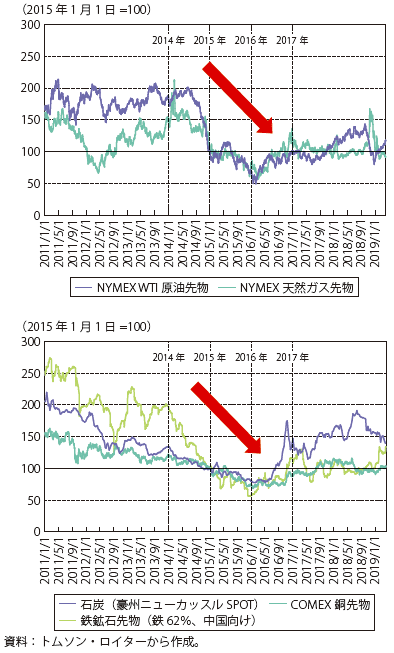
第Ⅱ-1-1-1-14図 素材及び中間財輸出の主要業種別内訳
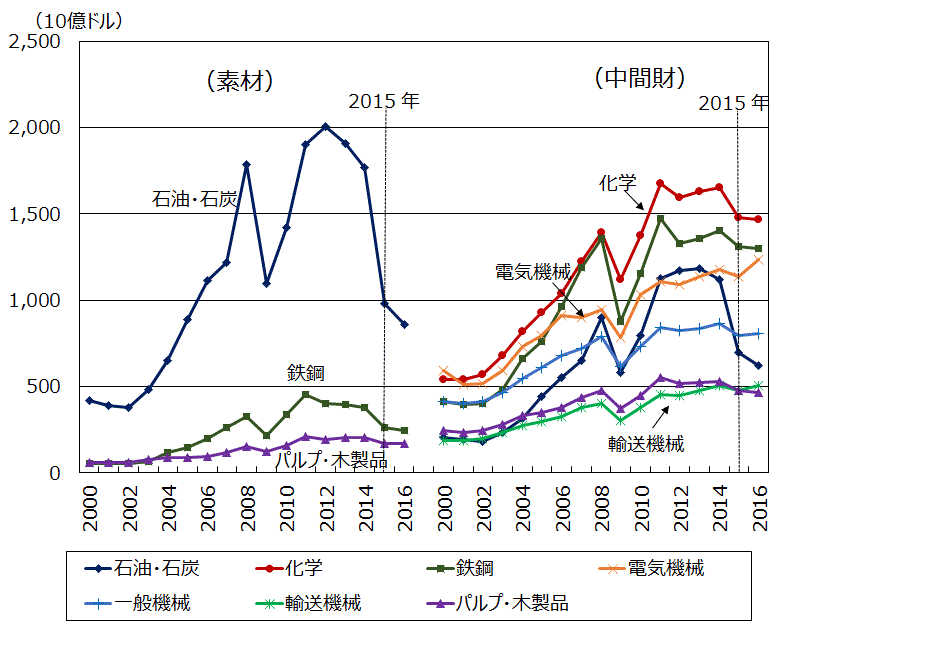
世界の中でも特に日本を含む東アジアは、機械産業を中心に中間財のシェアが高く、国際的生産分業の展開が指摘されている(第Ⅱ-1-1-1-15図)。
第Ⅱ-1-1-1-15図 東アジアの域内輸出の推移
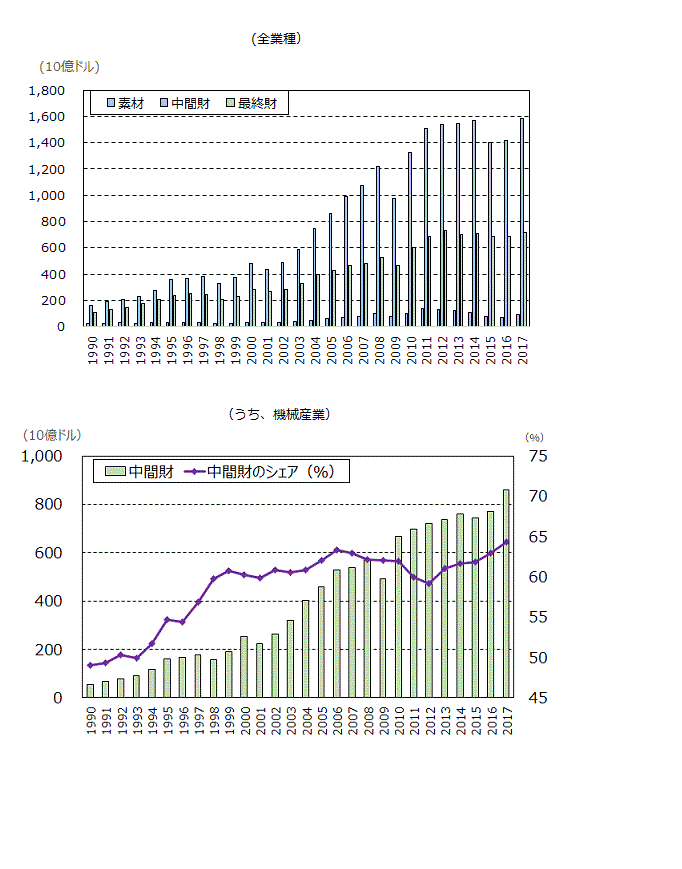
東アジアでは、資本・技術が豊かな先進国と、低廉な労働力に恵まれた新興国という2つの異なるタイプの国が存在し、国際的な生産分業が展開しやすい環境にあった。上記のモデルで言えば、日本、韓国で基幹部品など中間財を生産し、中国、ASEANで組立工程を行う。最終製品は、現地国内での販売、日本・韓国への逆輸出とともに、域外の欧米諸国へ輸出される。この欧米諸国への輸出がいわゆる三角貿易といわれる形態である。
東アジアの域内貿易を他の地域と比較すると、中間財、特に部品のシェアが高いことが目を引く(第Ⅱ-1-1-1-16図)。国際的な生産分業は他の地域でも見られたものの、東アジアが最も顕著に域内で国際的生産分業を展開した。特に中国は「世界の工場」といわれるほど輸出を拡大した。
第Ⅱ-1-1-1-16図 主要地域の域内貿易
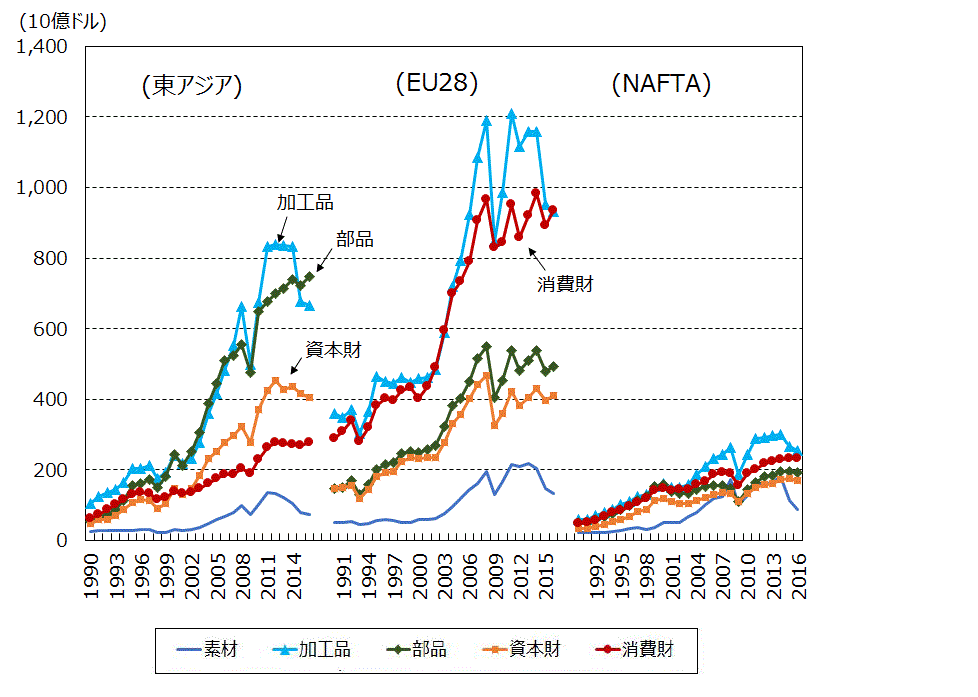
東アジアの貿易構造は、域内貿易と域外貿易(特に欧米等先進国向け)では財別構成が異なる。域内貿易においては中間財(機械部品や鉄鋼・化学品などの加工品)が中心であった。また、最終財の中では、消費財よりも資本財(工作機械、建設機械、パソコンなど)の方が貿易額が大きく、生産のための貿易の色彩が濃い。反対に、域外への輸出では域内で組み立てられたと見られる最終財のシェアが高い。なお、東アジア域内でも、日本、韓国等の先進国へは最終財の輸出シェアが高い。
このような東アジアと世界主要地域との貿易フローを俯瞰したのが第Ⅱ-1-1-1-17図である。矢印は貿易フローで、大きさが大きいほど貿易額が大きく、色が濃いほど中間財比率が高い。
第Ⅱ-1-1-1-17図 世界的な貿易フロー
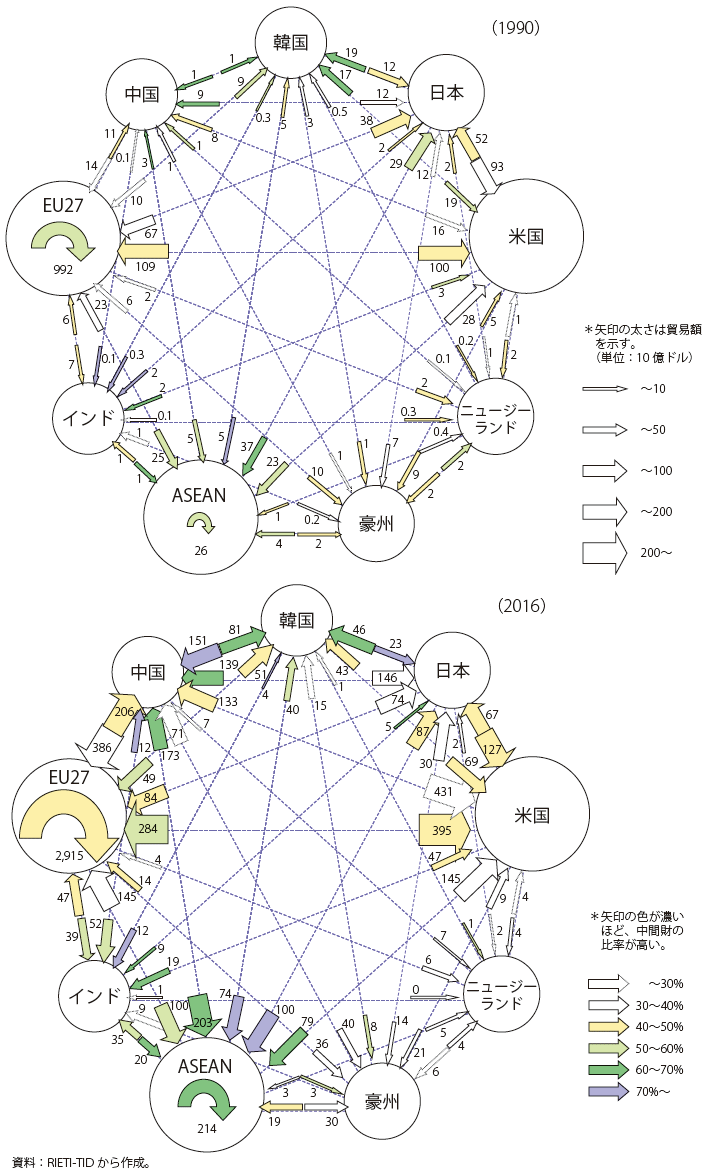
1990年と2016年を比べてみれば、まだ1990年にはアジアにおける中間財貿易は限られていたが、2016年には矢印がより大きくより濃くなっており、中間財貿易が拡大していることを示している。アジアの中で、日本・韓国から中間財が中国・ASEANに輸出されるとともに、ASEAN域内、中国・ASEAN間においても相互に中間財が輸出されている。一方、中国・ASEANから欧米向けには最終財中心に輸出がされており、地場の輸出品とともに、輸入中間財等をもとに組み立てられた完成品が第三国に輸出される、いわゆる三角貿易の存在を示唆している。このようにアジアでは、多くの国がより深くグローバル・バリュー・チェーン(GVC)に参加し、より複雑な依存関係を構築している。
15 このような国際的な生産の連鎖、それに伴う財・サービスの流れは、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)、グローバル・サプライ・チェーン(GSC)などと呼ばれる。両者については、必ずしも明確な定義があるわけではないが、いわゆる製品のスマイルカーブにおいて、企画、研究開発、生産、販売、メンテナンス等の全工程を広く意味する場合はグローバル・バリュー・チェーン、その中で特に生産工程に焦点を当てて、資材の供給網という意味で用いる場合はグローバル・サプライ・チェーンを使うことが多い。本白書においては、主として生産工程における財の流れに焦点を置きつつも、後で説明する付加価値貿易のように、財の中に体化されているサービス部分も含めて広く分析することから、グローバル・バリュー・チェーンを使い、GVCと略して表記する。
(3)次にくるグローバル化
今後、GVCが更に世界中で拡大するか否かについては、見解が分かれている。この点、GVCに加わりたいと考えている低コスト労働者が世界中に何十億人も存在し、そうした国の政府の多くがGVCに加わる努力をしおり、高賃金の先進国から低賃金の発展途上国へと製造業の仕事が流入し続け、流入先となる発展途上国はますます広がり続けるという見方がある16。また、世界金融危機から回復した2011年以降に世界全体の貿易がほぼ横ばいの中、東アジアのGVCを介した一般機械産業の部品貿易が東アジア域内貿易において復活していることを理由に、東アジアの同産業についてはGVCが今後も成長し続けるとの見方がある17。
他方で、2011年をピークにGVCの拡大ペースは減速しており、その背景にはアジアにおける人件費上昇や企業のデジタル経済化、自動化、サービス化の戦略が存在しているとの見方も存在しており18、世界の総輸出額増加の鈍化と合わせてGVC関連輸出の総輸出に占める割合が停滞しているようにも見える(第Ⅱ-1-1-1-18図)。
第Ⅱ-1-1-1-18図 総輸出に占めるGVC関連輸出の割合
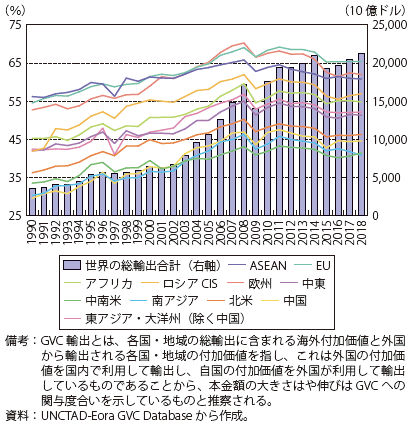
2000年以降の世界的な貿易額の急増が鈍化している中、今後、更なる企業のグローバル化が広がるか否かは、GVCが新興・途上国に広がった理由が主に生産の効率化を目的として、安価な労働力のある途上国へと生産工程の一部を分散したことから、企業が節約できるコストと新規に増加するコスト(輸送費、投資、人材教育等のコスト)を比較したうえで、得られる全体のベネフィットの大小により工程間分業が進展するか否かが決まるとの指摘が参考になる。
現在の中国の賃金は上昇しており、これはGVCにとっては抑制要因となるが、まだ賃金の低い取り残された後発途上国にGVCが広がる可能性は高まるとされる。さらに、生産工程に新しい技術が導入されて、途上国で得られるコスト優位性を考慮する必要がなくなれば、生産拠点が輸送費等の必要のない国内に回帰する誘因になり、他にも資源価格高騰による輸送コストの上昇、各国における規制の導入や災害の発生もGVCの形成に影響を与えることになるという19。この点、例えば世界の生産年齢人口に占める地域別の割合を見ると、南アジア、中国、アフリカの占める割合が高く、労働力を多く必要とする産業においては、これらの地域に引き続きGVCが展開していく可能性はある(第Ⅱ-1-1-1-19図)。
第Ⅱ-1-1-1-19図 世界の生産年齢人口に占める地域・国別の割合
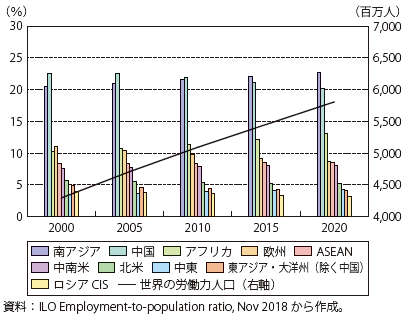
また、GVCの広がりは、海外直接投資やM&Aの動向を見ることによっても、ある程度の状況を確認することができると考える。必ずしも全ての直接投資が企業のGVCに繋がるものではないとの認識の下、世界の対内直接投資残高伸び率を見ると、2000年代前半に比べて2010年以降はほとんどの地域で鈍化しており、OECDの見解のとおり2011年をピークにGVCが停滞していることがうかがわれる。他方で、南アジアを筆頭に北米、ASEAN、東アジア・大洋州では世界の対内直接投資残高伸び率と比較して高い伸びとなっている。また、南アジアの対内直接投資残高の名目GDPに占める割合は、その規模に比して他の地域より低いこともあり、今後、対内直接投資の増加により外国企業との繋がりが拡大し、同地域がGVCに大きく関与していくことにある可能性もある(第Ⅱ-1-1-1-20図)。
第Ⅱ-1-1-1-20図 地域ごとに見た対内直接投資残高の伸び率
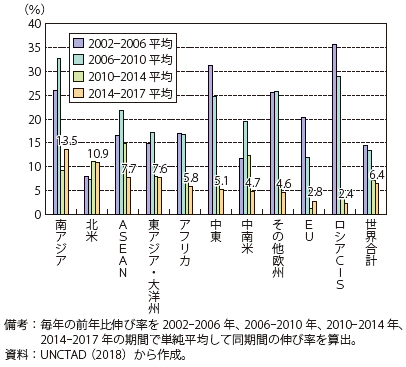
16 ボールドウィン(2018)、pp 358
17 Obashi, A.and Kimura, K (2018)、小橋(2018)、pp 22-47。
18 OECD (2018).
19 黒岩(2019)。
2.資本のグローバル化
前項では、財・サービスの観点からグローバル化がいかに進展してきたかを確認した。本項では、資本(カネ)の観点からグローバル化の進展を見ていきたい。
(1)直接投資の動向
世界のカネの流れを直接投資残高の面から見ると、世界全体の金額は増加しているものの、地域別に分類すると、その金額の多くはEU28、北米に向けられている。2000年以降、東アジア、ASEAN、ロシアCIS、中南米等が世界の直接投資残高の伸びに大きく寄与した時期もあったが、2017年では米国とEU28の寄与度が高くなっており、投資金額規模としては先進国が引き続き大部分を占める投資先となっていると考えられる(第Ⅱ-1-1-2-1図)。
第Ⅱ-1-1-2-1図 地域別対内直接投資残高と同伸び率の地域別寄与度
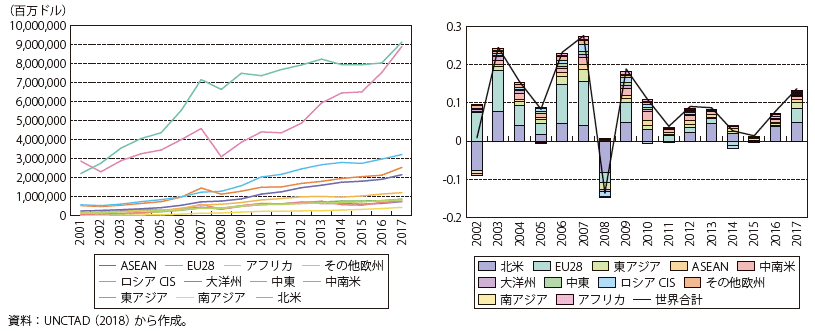
直接投資残高の金額全体で見ると北米とEU28が多いものの、他の地域においても直接投資残高は着実に増加してきており、経済規模の大きくない新興・途上国にとっては、海外からの対内直接投資の増加が自国の経済成長に一定程度の影響を与えるようになってきていると考えられる。対内直接投資残高の各地域名目GDPに占める割合の変化を見ると、各地域ともその割合は2001年から2017年にかけて増加しており、ASEAN、EU28、その他欧州、中南米が2017年時点で50%を超えている。他方で、南アジア、東アジア・大洋州、中東は、GDP規模に比べて対内直接投資の占める割合が相対的に低くなっており、経済規模から考えると投資の受け入れ余地が他の地域に比べて大きいように思われる(第Ⅱ-1-1-2-2図)。
第Ⅱ-1-1-2-2図 名目GDPに占める対内直接投資残の割合の変化
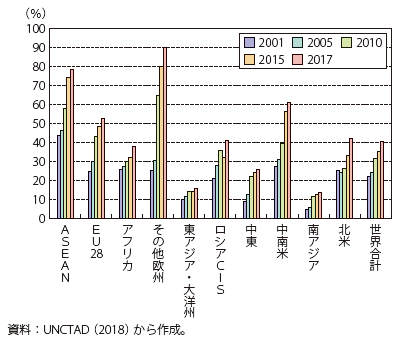
地域ごとに名目GDP、同伸び率、及び対内直接投資残高伸び率の2009年から2017年の変化を見てみる。2002年から2009年にかけて新興・途上国が構成する地域の名目GDPは、金額規模では先進国に及ばないものの、GDP平均伸び率は10%超、対内直接投資残高平均伸び率も概ね15%を超えるなどは先進国を大幅に上回る成長をしていた。他方で、2010から2017年にかけては、新興・途上国が構成する地域の名目GDPと対内直接投資残高の平均伸び率は、ASEANと南アジアが比較的高い水準を維持しているものの、先進国と同じ水準まで低下した(第Ⅰ-1-2-3図)。
第Ⅱ-1-1-2-3図 名目GDP、同伸び率及び対内直接投資残高伸び率の変化(2009、2017)
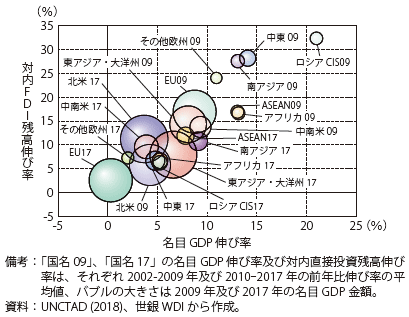
次に海外直接投資の主要な資金供給元である米国、日本、中国、及びドイツがどの国・地域に重点的に投資を行い、緊密度を高めているのか否かについて、各国の投資残高上位25ヵ国・地域を抽出して緊密度、投資残高伸び率、投資残高の変化を2009年から2017年にかけて見てみる。
グラフの縦軸は、主要国がどの国・地域を投資先として重視し、重点的に投資を行っているかを比較するため、「(X国のY国への投資/X国の世界への投資)÷(世界のY国への投資/世界の世界への投資)」で算出した指数を表している。下図にある米国を例にすると、米国は日本に対して、世界全体が日本に対して行う投資より3.8倍も多く投資をしていることを表している。すなわち米国は、世界平均よりも多くの金額を日本に投資をしており、米国にとって日本が相対的に重点的な投資相手国であることを意味している。
米国は、2009年と2017年のいずれもEU28向けの投資残高が最大となっている。また、残高の規模は及ばないものの、カナダ、日本も相対的に残高が大きく、緊密度が高い重点的な投資先となっている。他に緊密度が高い国・地域としては、バミューダ、ルクセンブルク、英領ヴァージン等のタックスヘイブンが多いことが特徴となっている。
2009年から2017年にかけては、ASEANへの投資残高伸び率が高くなっており、緊密度は相対的に高くはないものの、米国と同地域の結びつきが強くなっていることがうかがわれる。他、投資残高の上位25ヵ国・地域の伸び率では、イスラエル、UAE、インド、中国向けが高くなっている(第Ⅱ-1-1-2-4図)。
第Ⅱ-1-1-2-4図 米国の重点的な投資先国・地域
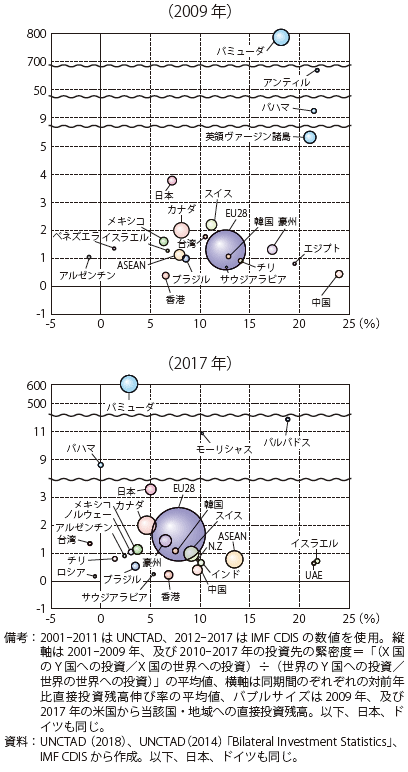
さらに、中国の投資関連数値の変化を見てみる。中国は、2009年と2017年とも香港への投資残高が突出しており、世界全体と比較すると10倍以上の比率で重点的に投資を行っている。香港以外ではケイマン、英領ヴァージンへの投資残高が相対的に大きく、タックスヘイブン向けに重点的に投資を行ってきたことが分かる。
中国は2009年から2017年にかけて、米国、日本、ドイツと比べると対世界への投資残高を大幅に増加させ、投資先も多様化してきたことがグラフからも見てとれる。同期間における中国の上位25ヵ国・地域に対する投資残高伸び率は、いずれの国、地域においても10%超の水準を維持し続けている。2017年時点での投資残高上位25ヵ国・地域においては、ASEAN、米国、EU28、豪州への投資残高が増加している他、先進国では上位の投資先として挙がらないカザフスタン、コンゴ民主共和国、パキスタン、ベネズエラ等へ積極的に投資が行われていることが特徴となっており、特定の新興・途上国に加え、米、EU等の先進国・地域とも多様性に富んだ関係が投資を通じて構築されつつあることが推察される。また、中国の投資残高が10億ドル以上で、かつ緊密度が高い国・地域は、ラオス、ジンバブエ、タジキスタン、キルギスタン、カンボジア、ミャンマー、モンゴル、パプアニューギニア、ザンビアが挙げられ、世界による投資の5倍以上の緊密度合いとなっている(第Ⅱ-1-1-2-5図)。
第Ⅱ-1-1-2-5図 中国の重点的な投資先国・地域
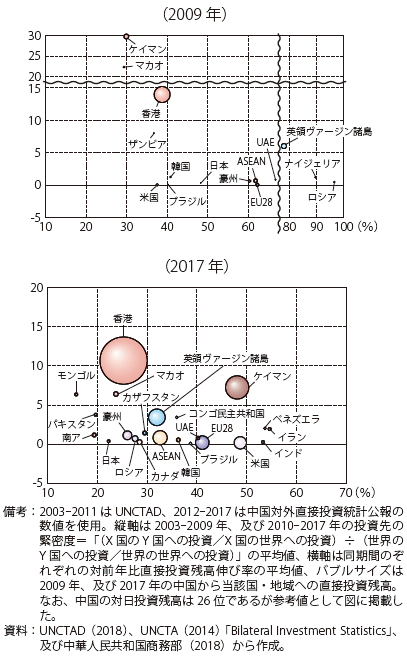
日本の投資残高を見ると、2009年時点では中国、ブラジル、インド等の新興・途上国・地域向けの伸び率が20%超と高かったが、2017年時点で20%を超えるのはメキシコ、スイス、UAEのみで海外直接投資残高伸び率は緩やかになった。同期間においてはメキシコ向けの投資残高が6.1倍と最も大きく増加した他、UAE 5.2倍、英国4.8倍、ベトナム4.7倍となっている。
また、2010-2017年における投資の緊密度を見ると、日本は、フィリピン5.7、タイ5.6、ケイマン4.9、台湾4.0、韓国3.5と世界全体に比べて重点的に投資をしており、さらに他のASEAN加盟国、豪州、中国とも緊密度が高く、アジア・太平洋地域が重点的な投資先になっている(第Ⅱ-1-1-2-6図)。
第Ⅱ-1-1-2-6図 日本の重点的な投資先国・地域
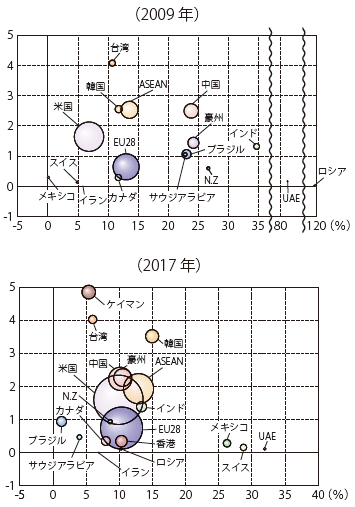
ドイツは、EU28(除くドイツ)への投資を重点的に行ってきており、投資残高伸び率は2001-2009年時に比べて2010-2017年時には低下したものの、緊密度は高まった。ドイツの投資残高伸び率は、米国、日本、中国に比して2017年まで大幅に低下しているが、中国、インド等の新興・途上国・地域に対する投資残高は、それぞれ2.7倍、3.2倍となり、活発に行われている。他、ドイツが投資で緊密度の高い国・地域は、2002-2009年、2010-2017年ともバミューダが13.7と最も高いが投資残高は20億ドル程度と大きくはない。2017年時点で投資残高が100億ドル超で2010-2017年の期間に緊密度の高い国・地域としては、ルクセンブルク13.7、オーストリア5.2、ギリシャ 3.4、ハンガリー 3.3、チェコ3.1、オランダ3.0となっており、これらの国以外もEU域内国が上位を占めている。ドイツは、米国、日本、中国に比してアジアとの緊密度が低くなっている(第Ⅱ-1-1-2-7図)。
第Ⅱ-1-1-2-7図 ドイツの重点的な投資先国・地域
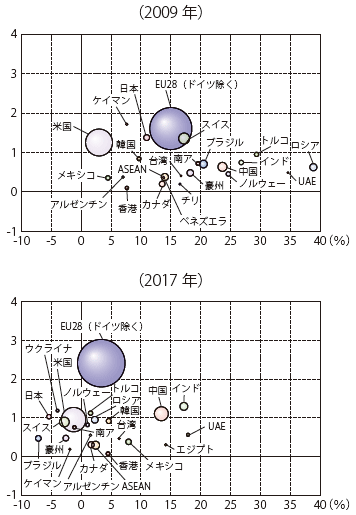
各国の投資残高の規模を比較できるよう、米国、中国、日本、ドイツの投資残高上位5ヵ国・地域を以下の図に表した。2017年時点で、中国がタックスヘイブンを中心に重点的かつ急速に投資を行っている様子がうかがわれる(第Ⅱ-1-1-2-8図)。
第Ⅱ-1-1-2-8図 米中日独の主要な投資先国・地域
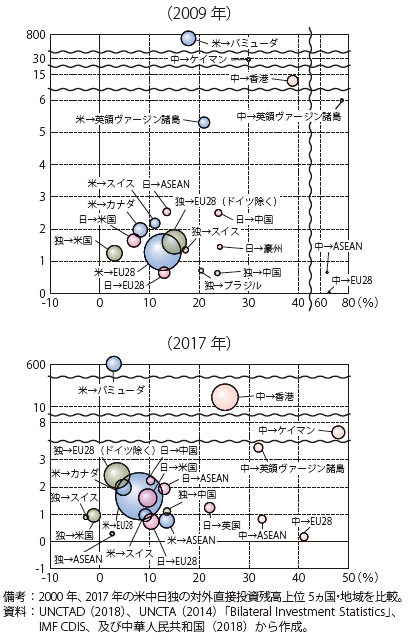
(2)グローバル企業の資本ネットワークによる海外展開
①資本ネットワークの概観
先進国の製造企業は、生産コストの低い地域、あるいは市場規模の大きい地域を求めて、海外に拠点を拡大してきた。日本の場合、地理的に近いアジアに生産拠点を設け、日本から一部の部品を調達して生産した上で、現地あるいは第三国に輸出するパターンや、主要市場である米国やその近辺の地域で生産するパターンが多い。他の主要国はどのように展開しているのだろうか。また、近年では、先進国企業のみならず、新興国の企業による海外展開も多く見られている。海外におけるビジネスの内容は、生産や販売を中心としつつも多様化している可能性がある。
本項では、主要国製造企業のグローバル展開について、地域やセクターによる違いを概観するとともに、製造業企業のビジネスに占める海外の比重について、可能な範囲で確認していく。
ここでは、各国企業による海外展開を確認するため、ビューロー・ヴァン・ダイク社(Bureau van Dijk)のORBISデータベース25を用いる。同データベースは、世界の160のデータプロバイダを通じて世界207ヵ国の企業情報をカバーする。企業数が約3億社と非常に多く、また、株主情報が収録されているため、全世界の企業間の資本関係ネットワークを捉えることが可能という点が特徴的である。ただし、地域により企業の捕捉率や財務情報の収録の度合いが異なることに注意する必要がある。
はじめに、主要国の企業がどの地域に強いのか、企業の分布を概観する。
第Ⅱ-1-1-2-9図は、日本、米国、中国、及びEUに所在する企業が出資する26海外の製造企業について、出資元企業の所在国別の割合(当該4つの国・地域の合計に対する割合)を表す27。
第Ⅱ-1-1-2-9図 日米中・EU企業が出資(25%以上)する海外企業の分布(製造業)
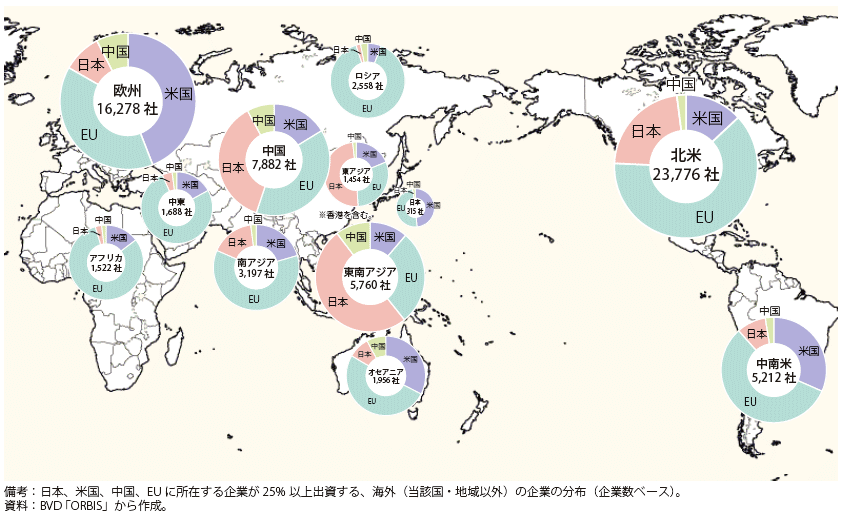
新興国への進出を見ると、中東、アフリカ、ロシアでは、製造業・サービス業ともにEUが特に大きな割合を占めている。データベースに収録された企業に限定されるものの、これらの地域ではEU系の企業が外資系企業の7~8割に上っている。
日本と中国を比較すると、製造業に関しては、全体的に日系企業が中国系企業を大きく上回るが、ロシアでは中国系企業の方が日系企業を上回っているほか、欧州とオセアニアでは同等の割合である。サービス業に関しては、中国系企業の方が多い地域、日系企業の方が多い地域が分かれる。中国系企業が日系企業を上回るのは、欧州とロシアのほかに、オセアニア、中東である。東アジア、南アジア、北米、アフリカでは日系企業の方が多い。
日本とEUを比較すると、製造業に関しては、EU系企業は、北米で日系企業の約3倍、南アジアで約4倍、中南米とオセアニアで約6倍、中東とアフリカでは10倍以上と、EU系企業が日系企業を大きく上回る。一方、中国・香港ではほぼ同等、東南アジアと東アジアは日系企業がEU系企業の2倍近くあり、強みのある地域といえる。サービス業に関しては、東アジアを除いて、全てEU系企業が日系企業を上回る。ロシア、中東、中南米及びアフリカではEU系企業が日系企業の10倍以上と差が顕著であるが、他にも、オセアニアで約9倍、北米と南アジアで約5倍以上、東南アジアと中国(香港含む)で2倍弱となっている。
米国とEUを比較すると、全体的にEU系企業が米国系企業よりも大きな割合を占めているが、日本においては、米国の割合が他の地域におけるよりも大きく、製造業ではEUと同等の割合であり、サービス業でもEUとの差が他の地域に比べ小さい。その他、南アジアと東アジアのサービス業、またオセアニア、東アジアと中南米の製造業においては、他の地域に比べて差が小さく、米国がより強みを持つ地域であると考えられる。
以上より、日本については、製造業に関しては、東南アジア、東アジア及び中国・香港では他国に比べても多く進出しているといえるが、それ以外の地域における存在感は大きくない。サービス業に関しては、東南アジアと東アジア及び中国・香港における割合が比較的大きいが、それ以外の地域では、製造業での進出をさらに下回る割合となることが確認された。
なお、EU系製造企業については、北米が進出先として最大であるが、かつて宗主国として支配した地域が世界に広がっており、多くの地域においてEUが占める割合は非常に大きいことが確認された。
中国と米国系企業の最大の進出先は、製造業・サービス業ともに欧州となっている。
第Ⅱ-1-1-2-10図 日米中・EU企業が出資(25%以上)する海外企業の分布(サービス業)
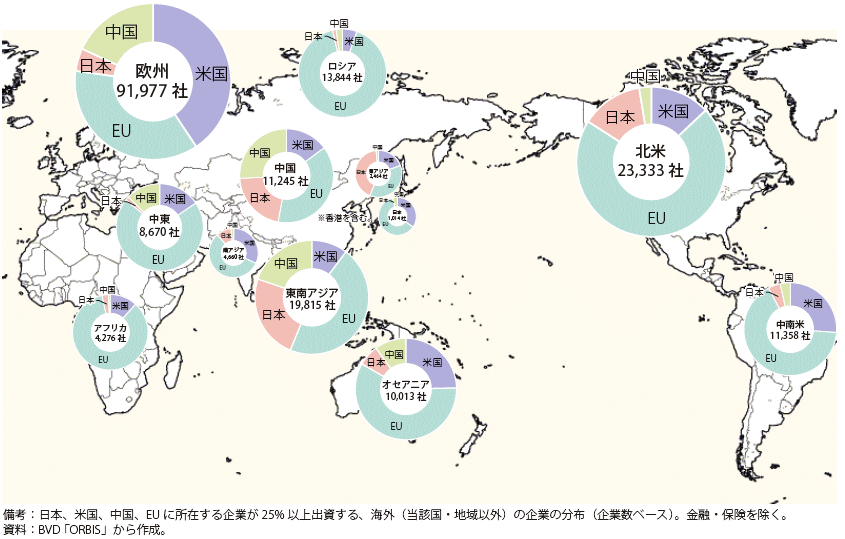
4か国・地域による合計進出企業数(参考値)28を進出先別に確認すると、欧州と北米が受け入れる企業数が、製造業・サービス業ともに非常に多い。それに対して日本が受け入れる企業数は、製造業・サービス業とも顕著に少ない。外資系企業の受入という点で、国内におけるグローバル化が主要国に比べ抑制的である可能性がある。
次に、親会社を製造業に絞り、主要国からどのようなセクターで海外に展開しているのかを確認する。
中国、ドイツ、米国及び日本の製造業企業の海外子会社について、その数と売上高をセクター別に確認すると、親企業と同じ製造業と並んで、生産したものを販売する卸小売業が多い(第Ⅱ-1-1-2-11図、第Ⅱ-1-1-2-12図)。
第Ⅱ-1-1-2-11図 製造企業の海外子会社のセクター内訳(企業数ベース)
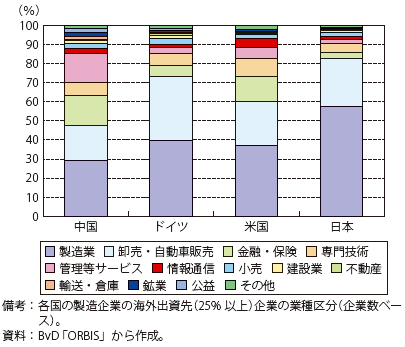
第Ⅱ-1-1-2-12図 製造企業の海外子会社の製造業内訳(企業数ベース)
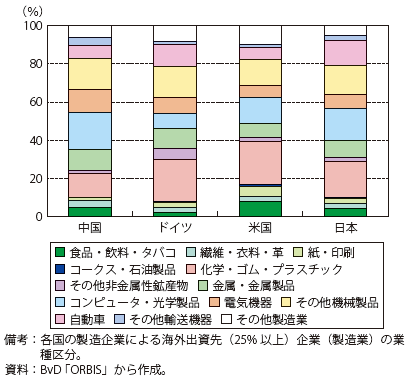
一方、日本を除く3か国については、卸小売以外の非製造業も多く、専門技術サービスが5%以上見られるほか、中国と米国については、管理等サービスも5%以上、金融・保険セクターが10%以上見られる。
親会社が製造業であるにも拘わらず、ビジネスの拡大や事業内容の高度化を目的として、製造と販売以外の分野に進出する流れは国内でも見られているが、同様の流れが海外子会社との関係にも現れているといえる。
製造業に関しては、その内訳は、化学品、自動車、コンピュータ・光学製品、その他機械製品、金属・金属製品、食品関連等、各国とも多様である。国別に見ると、ドイツ、日本、及び米国は、化学品が2~3割と大きい。また、その他機械製品、電気機器、及びコンピュータ・光学製品を合わせた機械関連製造業は、中国が5割弱、日本が4割、米国とドイツが3割前後といずれも大きい。日本とドイツについては、自動車が1割以上を占めている。中国については、コンピュータ・光学製品が最も大きく、製造業の2割を占めている。
次に、地域別・セクター別に確認していく。
まず日本の製造企業の海外子会社を見ると、どの地域でも卸売業と製造業の割合が大きいが、英国等の欧州を中心に、専門技術サービスが一定数、また、英国と南アジアでは管理等サービスが5%程度見られる。情報通信も、企業数は少ないが各地に進出している様子が確認できる(第Ⅱ-1-1-2-13図、第Ⅱ-1-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-1-2-13図 日本製造企業の海外子会社数(産業内訳)
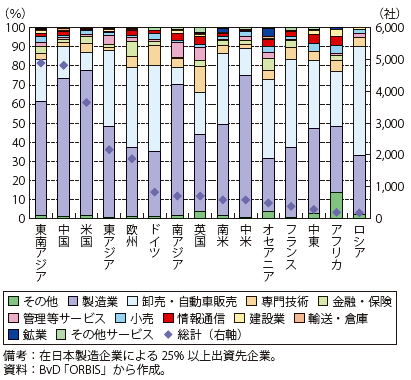
第Ⅱ-1-1-2-14図 日本製造企業の海外子会社数(製造業内訳)
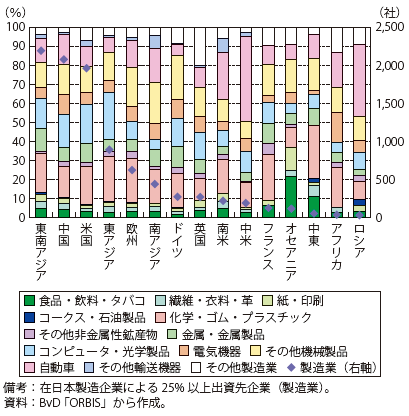
製造業の内訳は、自動車、化学品、金属関連、食品関連、電気機器、コンピュータ・光学製品、その他機械等、多様である。
ドイツ製造企業の海外子会社は、日系企業と同様に、製造業と卸売業の割合が非常に大きいが、英国など一部の国においては、専門技術サービスの割合が高い(第Ⅱ-1-1-2-15図、第Ⅱ-1-1-2-16図)。製造業の内訳では、化学、機械、自動車等が多い。
第Ⅱ-1-1-2-15図 ドイツ製造企業の海外子会社数(産業業内訳)
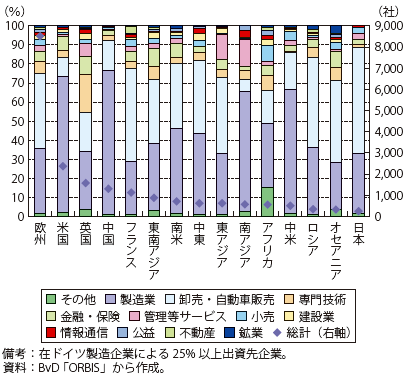
第Ⅱ-1-1-2-16図 ドイツ製造企業の海外子会社数(製造業内訳)
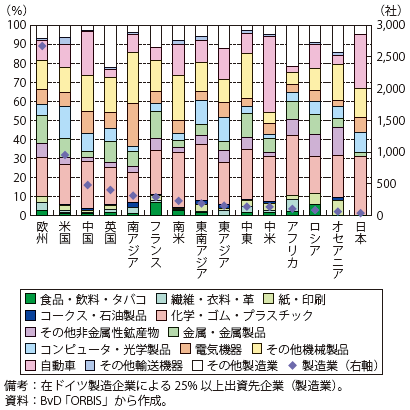
中国製造企業の海外子会社は、オセアニア、アフリカ、南アメリカに鉱業が見られるほか、日本とロシアでは卸売業の割合が5割を超える。また、欧州、米国及び南アジアでは専門技術サービスが1割以上を、東アジアでは管理等サービスが3割以上を占める。製造業の中では、コンピュータ・光学製品製造業が、米国と東アジアを始め、多くの地域で大きな割合を占める。その他機械製品については、南アジア、欧州及び中東で大きな割合を占める(第Ⅱ-1-1-2-17図、Ⅱ-1-1-2-18図)。
第Ⅱ-1-1-2-17図 中国製造企業の海外子会社数(産業内訳)
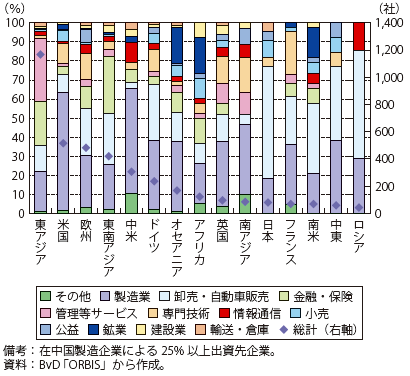
第Ⅱ-1-1-2-18図 中国製造企業の海外子会社数(製造業内訳)
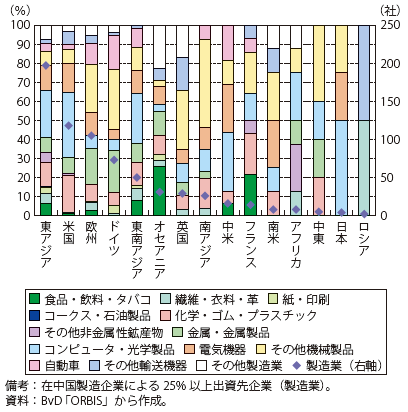
米国製造企業の海外子会社は、中国系企業と同様に、製造業と卸売業以外のセクター割合が大きい。専門技術サービスは欧州で多く、情報通信は英国、南アジア及び中東で割合が大きい(第Ⅱ-1-1-2-19図)。製造業では、化学品が各地域で2~3割を占める。また、コンピュータ・光学製品やその他機械製品が各地域に見られる(第Ⅱ-1-1-2-20図)。
第Ⅱ-1-1-2-19図 米国製造企業の海外子会社数(産業内訳)
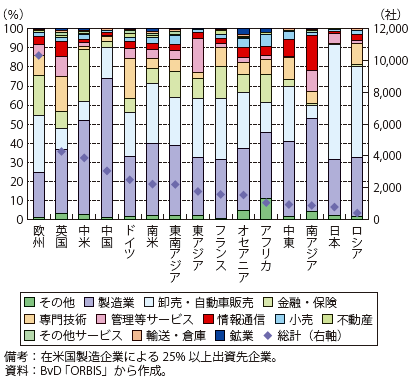
第Ⅱ-1-1-2-20図 米国製造企業の海外子会社数(製造業内訳)
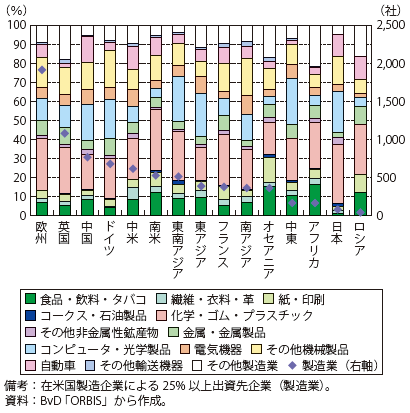
ここまで、製造企業の海外展開に関して主要国の特徴を確認してきた。日本は、東南アジアでは他の主要国に比べシェアが高いが、それ以外の地域におけるシェアは大きくなく、中にはごく僅かのシェアにとどまる地域もある。サービス業に関しては、地理的に近いアジア地域においてもEU系企業の割合を下回る。また、海外展開の多くが製造業と卸売業であり、業種としての広がりは弱い。
もちろん、国内ビジネスの活性化が重要であり、我が国企業が強みを持つ分野をさらに伸ばし、かつ成長性の高い新しい分野に挑戦していくことが必要であるが、同時に、上記の結果は、我が国企業について、引き続き、グローバルにビジネスを拡大する余地を示唆するものである。
25 図表中では、ビューロー・ヴァン・ダイク社を「BvD」と略記する。
26 出資比率25%以上。子会社は、事業活動中であり、かつ、ORBISに①~③(①2015年以降の財務データ、②住所と電話番号、③住所とメールアドレス)のいずれかがある企業。
27 円グラフの大きさは、今回確認した4か国・地域を最終親会社とする海外子会社の合計数を踏まえている。しかし、企業収録率の低い地域も含まれるため、地域別の合計企業数と円グラフの大きさは、あくまで参考である。
28 ORBISでは、地域ごとに企業収録率が異なる。主に新興国では収録率が低いことに留意する必要がある。
②新興国における外資系企業
次に、日本製造企業の子会社が多く拠点を有している東南アジア地域における、外資系企業の展開を確認する。
アセアン10か国における外資系企業について、親会社の所在国・地域別に割合を確認すると、日本が全体の約2割と最大である。国単位では、米国と英国が続くが、欧州全体では約3割と日本を上回る(第Ⅱ-1-1-2-21図)。
第Ⅱ-1-1-2-21図 アセアンにおける外資系企業の親会社所在国・地域別割合(全産業)
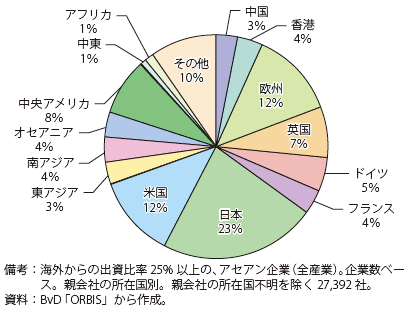
なお、製造業に限定すると、日本のシェアは4割強に拡大する。(第Ⅱ-1-1-2-22図)。
第Ⅱ-1-1-2-22図 アセアンにおける外資系企業の親会社所在国・地域別割合(製造業)
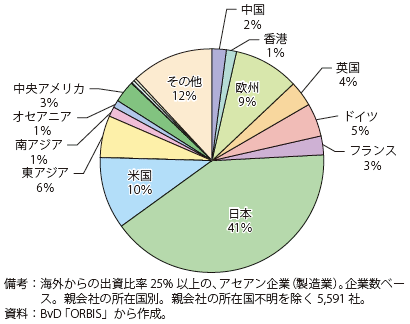
アセアン地域における全ての外資系企業の展開をセクター別に見ると、製造業、卸売業、及び金融・保険がそれぞれ約2割を占めるほか、専門技術サービスや管理等サービスも一定数見られている(第Ⅱ-1-1-2-23図)。
第Ⅱ-1-1-2-23図 アセアンにおける外資系企業のセクター内訳(企業数ベース)
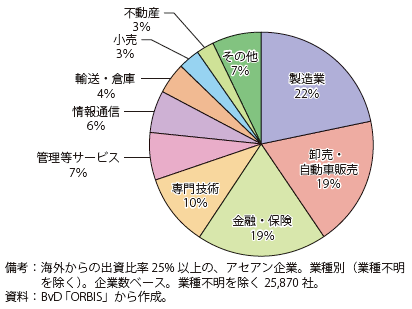
製造業の中では、化学品が2割を占めるほか、機械関連29は合計すると約4割に達する(第Ⅱ-1-1-2-24図)。
第Ⅱ-1-1-2-24図 アセアンにおける外資系企業の製造業内訳(企業数ベース)
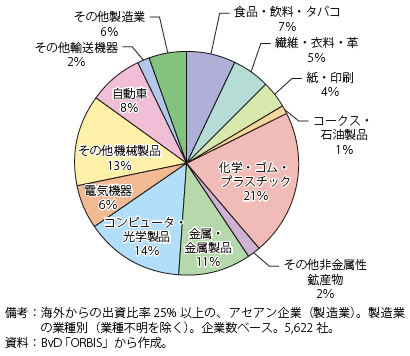
次に、親会社の所在国・地域別に業種展開を確認すると、ほとんどの国が、卸売と製造業を中心とするが、特に日本と東アジア系の企業の製造業割合は大きく、4割前後に達する。また、専門技術サービスに関しては、欧州、米国、オセアニア系の企業がそれぞれ1割以上となっている(第Ⅱ-1-1-2-25図)。
第Ⅱ-1-1-2-25図 アセアンにおける外資系企業のセクター内訳(企業数ベース)
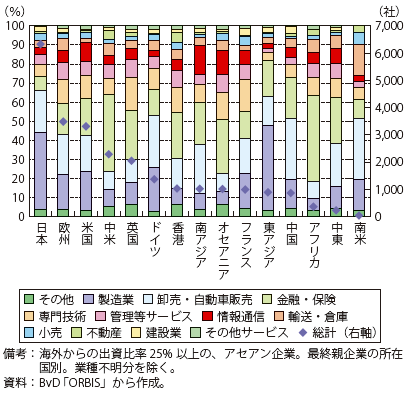
製造業については、多くの国・地域による進出において化学品が2~3割を占めている。また、コンピュータ・光学製品や電気機器、その他一般機械も多い。日本とドイツ系の企業については、自動車が1割前後と比較的大きい(第Ⅱ-1-1-2-26図)。
第Ⅱ-1-1-2-26図 アセアンにおける外資系企業の製造業業種内訳(企業数ベース)
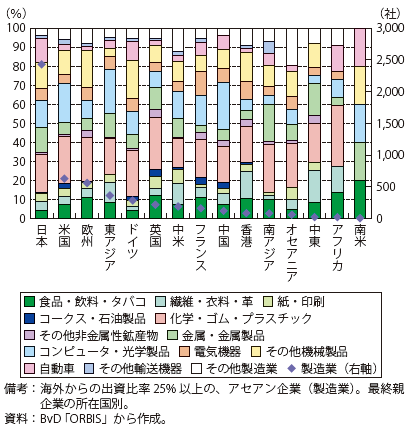
29 コンピュータ・光学製品、電気機器、その他機械製品、自動車、その他輸送機器。
③製造企業の売上高における海外の比重(試算)
次に、製造業に関する、海外子会社と国内におけるビジネスの規模について、売上高での比較を試みる。
これまでと同様にビューロー・ヴァン・ダイク社のORBISを使用するが、企業売上高が連結財務データのみであるケースが多いため、一定の仮定の下、連結データを合計することによる同一企業売上高の重複を排除した。
財務情報収録率に関する地域ごとの違いに関しては、日本に関してのみ、経済産業省「海外事業活動基本調査」(以後、「海事」)を使用して、財務情報収録企業数が少ない地域について調整を行った。具体的には、「海事」の売上高を基礎とした上で、ORBISの方が「海事」よりも売上高の数値を有する企業数が多い地域の、売上高に関する両データベースの差を踏まえて推計した(日本推計③は、企業数が増えず、売上高のみ増えるとした場合、日本推計④は、売上高に加えて企業数も拡大するとした場合。詳細は「補論」に記載した。)。
なお、米国は財務情報収録率が顕著に低いため、国内と海外の比較を行わない。
まずORBISのみで試算すると、国内製造業を1とした場合、その海外子会社(製造業)の売上高は、日本は2割弱30、ドイツは4割弱、中国は1%であった。海外子会社の業種を産業全体(金融・保険以外)とすると、日本は約3割、ドイツは7割弱、中国は4%であった(第Ⅱ-1-1-2-27図)。
第Ⅱ-1-1-2-27図 各国製造企業の国内売上高と海外子会社の売上高比率(試算)
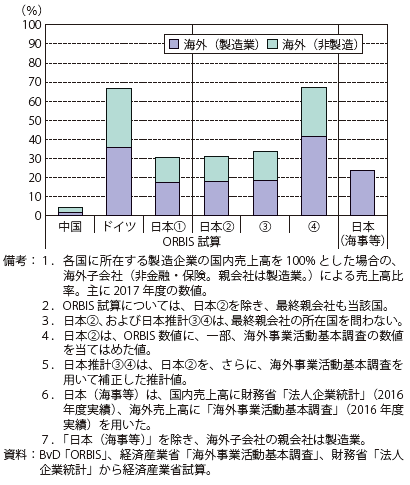
次に、ORBISで試算した日本の数値について、海事を用いて推計すると、海外割合は、製造業が最大約4割、産業全体で最大7割弱まで拡大した31。
推計は日本についてしか行っていないが、ドイツは、日本と同様にORBISにおける国内企業の財務情報収録率が高いため、同図における試算結果よりも海外割合が拡大する可能性が考えられる。
これらはあくまで試算であるが、先進国における製造業の生産が伸び悩む中、企業が海外に生産・販売拠点を拡大してきたことや、国内よりも海外ビジネスの比重が大きい企業も多く見られることに鑑みれば、あり得る数値である。
ビジネスにおける海外の比重の大きさは、海外の政治・経済情勢が影響しやすくなる一つの要因であると同時に、成長市場をつかむ重要な要素である。日本企業については、これまでに見てきたように、グローバルな企業展開が弱く、引き続き、海外展開の環境を整えることが必要である。
一方、新興国における労働コストの上昇に加えて、主要な海外展開先である中国と米国をめぐる貿易摩擦は、製造企業の海外投資計画に影響を与えている。我が国の製造企業の認識を見ると32、近年、海外拠点を第三国に移転させるケースや、日本国内に戻すケースが見られていたが、米中貿易摩擦がそうした動きの要因の一つに加わる形となっている。厳しいコスト競争の中で、海外に拠点を設けて生産・販売を行うような企業の中には、関税により影響を受ける企業が少なくない。貿易摩擦が加速し、あるいは長期的なものとなれば、大きなコストを負担しても拠点を移動せざるを得ない企業が増加する可能性が懸念される。
30 米国を始めとして、一部の国の財務情報が他国に比べて顕著に少ないため、日本の海外子会社については、経済産業省「海外事業活動基本調査(2017年調査)」(2016年度実績)を用いて財務情報を補足し推計を行った。
31 別途、①「海外事業活動基本調査(2017年調査)」(2016年度実績)に基づく海外現地法人売上高(製造業)を、②財務省「法人企業統計」(2016年度実績)の国内企業売上高(製造業)で割ると、23.8%となる。①の回答率は74.1%。そのうち海外現地法人(製造業)に関する売上高回答率は82%。海外現地法人(製造業)の回答率も74.1%と仮定すると、調査対象の海外現地法人のうち、売上高を回答した割合は61%。先の23.8%を、単純に同回答率で割り戻すと、39%となり、本項の推計値と近似する。
32 経済産業省(2019)。
④M&Aによる企業ネットワークの拡大
グローバル企業の海外展開は、新たに自社拠点を設置する場合と、現地企業に対する出資や買収による場合に分かれるが、以下では、出資や買収による海外展開について確認していく。
一般に、企業の買収、あるいは出資は、規模のメリットの追求や、仕入れコストの削減、また、販売網の獲得、新規事業の獲得、新しい技術の獲得といった様々な目的のもとに行われているとされるが、その中でも国境をまたぐM&Aは長期的に増加傾向にある(第Ⅱ-1-1-2-28図)。また、セクター別では、欧米、日本及び中国企業による案件としては、情報通信関連の案件数が多い(第Ⅱ-1-1-2-29図)。
第Ⅱ-1-1-2-28図 クロスボーダーM&Aの推移
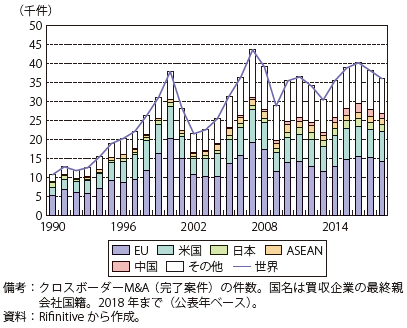
第Ⅱ-1-1-2-29図 クロスボーダーM&Aのセクター別伸び
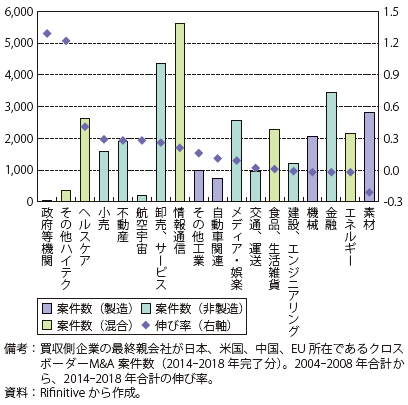
以下では、近年のM&Aの中でも特に案件数が多い情報通信セクターと、製造業の中で案件数の多い機械セクターにおけるM&Aや出資による海外展開を、企業データベース33により確認していく。なお、米国、EU、中国、日本に親会社を持つ企業によるM&Aを対象として見ていくこととする。
機械セクターにおけるM&Aは、欧州と北米において活発である。オセアニア、南アジアと中南米では、米国とEU企業によるM&A案件(M&Aの買収先・出資先34)数が同等であり、日本、中国・香港、東アジア及び中東では米国企業による案件がEU企業よりも多い。一方、ロシアとアフリカでは、EU企業による案件が4分の3以上を占める。日本は、アジア地域では比較的割合が大きいが、東南アジアを除いては、EUあるいは米国を下回る。また、欧州と北米においては、中国企業と日本企業による割合はほぼ同等であり、中南米と中東においては、中国企業による割合が日本企業による割合を上回っている(第Ⅱ-1-1-2-30図)。
第Ⅱ-1-1-2-30図 日米中・EU企業によるクロスボーダーM&Aを通じた出資先企業の分布(機械セクター)
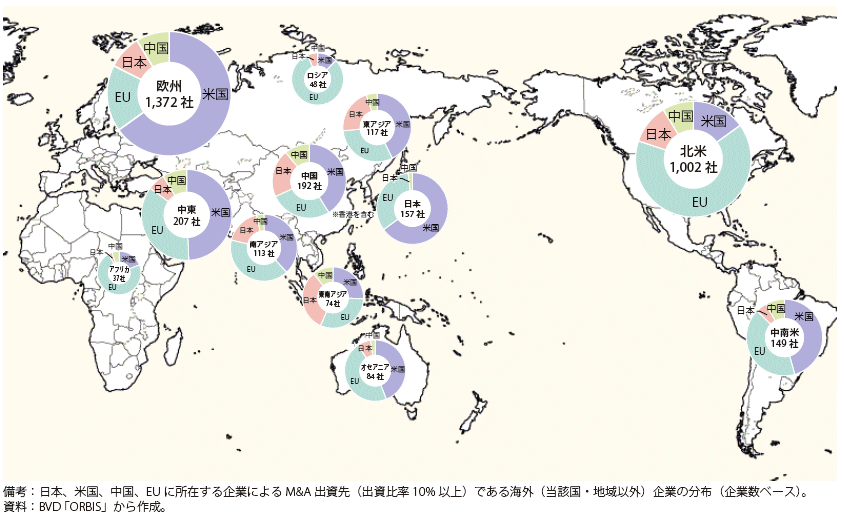
情報通信セクターにおけるM&Aの買収先・出資先地域は、最も多いのが北米、次いで欧州である。
同セクターでは、米国企業による案件の割合が多く、欧州では約8割、中国と南アジア、日本では約4分の3、と多くの地域で非常に大きな割合を占めている。日本企業は、東南アジアでは他の地域におけるより割合が大きいが、米国をやや下回る(第Ⅱ-1-1-2-31図)。
第Ⅱ-1-1-2-31図 日米中・EU企業によるクロスボーダーM&Aを通じた出資先企業の分布(情報通信セクター)
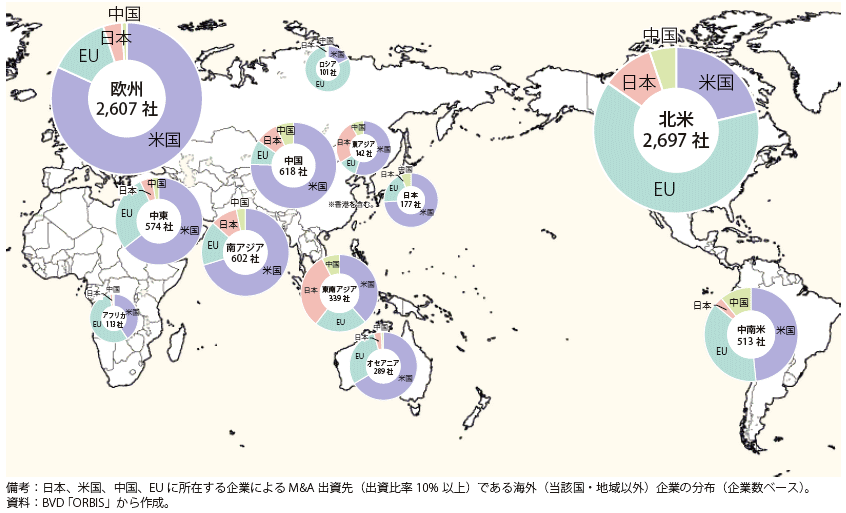
M&Aによる海外展開と、子会社の海外保有による海外展開とでは、どのような違いがあるのだろうか。
まず、機械セクターについて、①M&Aによる案件(M&Aによる買収先・出資先。出資比率10%以上。)数と、②親会社として保有する(ここでは、50%以上出資を基準とする)海外企業の数35について、その比率(①÷②)を確認したものが、第Ⅱ-1-1-2-32表であるが、ほとんどのカテゴリーが、100%を下回る(同図において、同比率が100%を超える場合は黄色、200%を超える場合は赤色とした)。つまり、親会社として海外に保有する企業の数が、近年のM&Aによる出資先の数を上回る。例えば、米国企業による欧州への出資において、M&Aを通じた出資先の数は、親会社としての出資先数の39%、また、EU企業による北米への出資は、M&Aによる出資先数が親会社としての出資先数の9%にとどまる。
第Ⅱ-1-1-2-32表 海外子会社とM&Aのバランス(機械セクター)
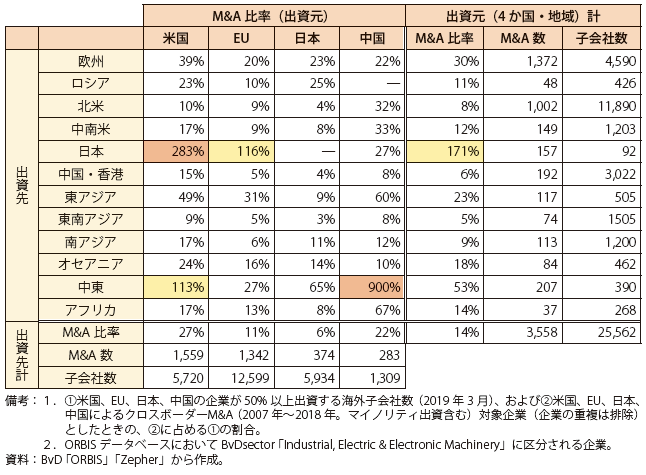
M&Aによる出資先数が親会社としての出資先数を上回るのは、今回確認した中では、米国とEU企業による日本への出資、及び米国と中国企業による中東への出資のみであった。
以上より、機械セクターにおいては、海外企業との資本ネットワークの多くは、海外企業との親子関係であるといえる。
機械セクターではM&Aの割合が低いことが確認できたが、さらに、M&Aの取引タイプ36の中でマイノリティ出資がどの程度含まれているのかを確認すると、多くのケースで4割未満にとどまった(第Ⅱ-1-1-2-33表)37。例えば、米国企業によるアフリカへの出資や、EU企業による中南米への出資、日本企業による東南アジアへの出資を始めとして、多くのカテゴリーが4割未満(黄色)となっている。
第Ⅱ-1-1-2-33表 M&Aにおけるマイノリティ出資割合(機械)
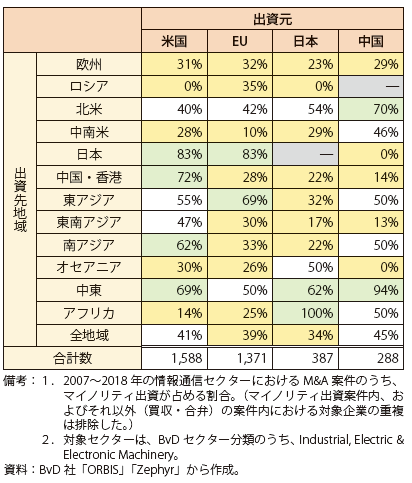
つまり、機械セクターにおいては、M&Aが海外子会社保有より少ないだけでなく、M&Aの内容そのものも、強い出資関係を締結するケースが多いといえる。
同様に情報通信セクターについても、M&Aによる海外展開と、子会社保有による海外展開の比率を確認すると、機械セクターとは異なり、多くのカテゴリーで、M&Aを通じた出資先の数が、親会社としての出資先数を上回っている(第Ⅱ-1-1-2-34表)。具体的には、EU企業による北米への出資や、米国企業による日本、中国(及び香港)及び中東への出資や、中国企業による北米、中南米、日本、中東への出資等において、色のついたセルが見られる。
第Ⅱ-1-1-2-34表 海外子会社とM&Aのバランス(情報通信セクター)
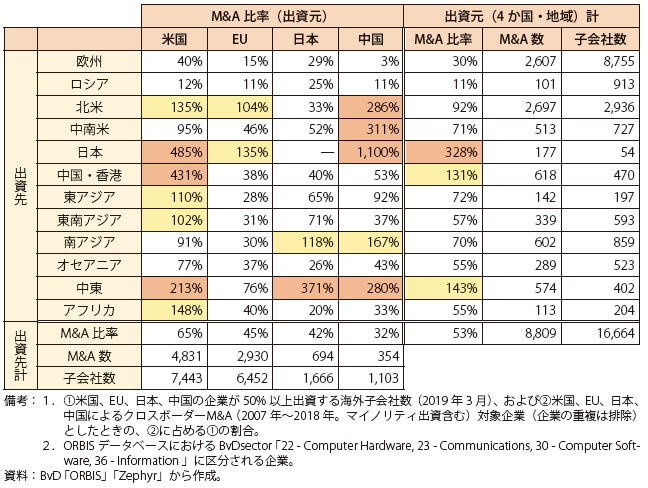
情報通信セクターでは、親子関係ではなく、より低い出資関係によって海外企業と提携する形が取られるケースが多いといえる。
念のため、機械セクターと同様に、M&Aにおけるマイノリティ出資案件の割合を確認すると、ほとんどのケースにおいて6割以上(緑色)と高い数値であった(第Ⅱ-1-1-2-35表)。
第Ⅱ-1-1-2-35表 M&Aにおけるマイノリティ出資割合(情報通信)
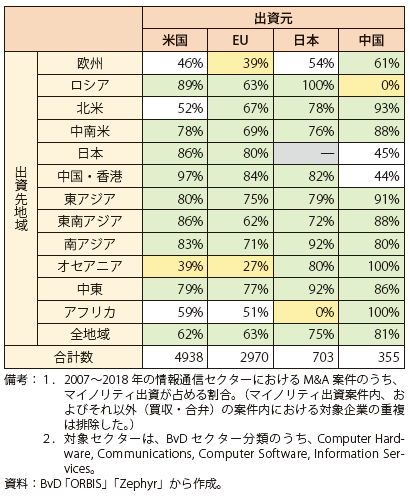
マイノリティ出資は、相手先企業に対する経営権がない分、相手企業を思うように活用することができないというデメリットがある反面、提携先企業との相乗効果を期待することができ、さらに、相乗効果の様子次第で買収に向けたステップに進むことも可能というメリットが見られる38。また、被買収企業にとっての「買収される」ことに対する抵抗感に比べて、マイノリティ出資による「資本提携」は受け入れられやすい面があるという。
今回確認したデータより、我が国製造業による海外展開の典型の一つといえる機械セクターに関しては、海外子会社を保有する形を取ることが多い一方で、情報通信セクターでは、子会社を支配的に保有するというよりは、資本提携でとどまるケースが多いことが確認できた。本項(2)①(第Ⅱ部第1章第1節2(2)①)において、製造企業が、海外で情報通信セクターを含むほかの業種に展開している様子を確認したが、製造業が情報通信セクターに展開するといった場合に、相手先企業との相乗効果について様子を見ながらの企業提携、あるいは、相手先企業のビジネスをより活かした形での企業提携といった形が、より好まれている可能性が考えられる。
M&Aの目的は、先に述べたように多様であるが、最近は、自らにない技術の獲得を目的とした新興国企業によるM&Aが注目されていることから、以下では、特許データ39を使用して、M&A等による特許保有の違いについて確認していく。
M&Aによる出資先企業が保有する特許は、どのような分野で多いのだろうか。①自国企業が保有する特許と、②M&Aを通じた海外出資先が保有する特許を比較すると、後者が前者より多い分野が複数見られる。
②÷①の比率をセクター別に比較すると、日本については、特に目立つのはデジタル通信、電気通信である。逆にその比率が低い分野としては光学、高分子化学・ポリマー、工作機械等が見られ、我が国が技術に強みのある分野と考えられる(第Ⅱ-1-1-2-38図、第Ⅱ-1-1-2-39図)。反面、先に見たデジタル通信や電気通信といった分野は、我が国にとってまだ技術的に弱い分野であり、海外企業の技術に対して出資によってアクセスを拡げようとしている可能性が示唆される。
第Ⅱ-1-1-2-36図 (参考)日米中・EU企業が出資(出資比率25%以上)する海外企業の分布(情報通信セクター)
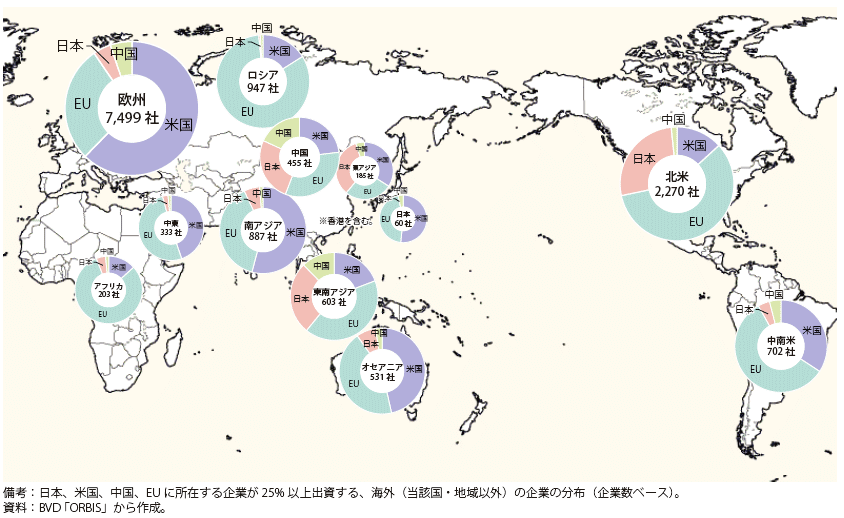
第Ⅱ-1-1-2-37図 (参考)日米中・EU企業が出資(出資比率25%以上)する海外企業の分布(機械セクター)
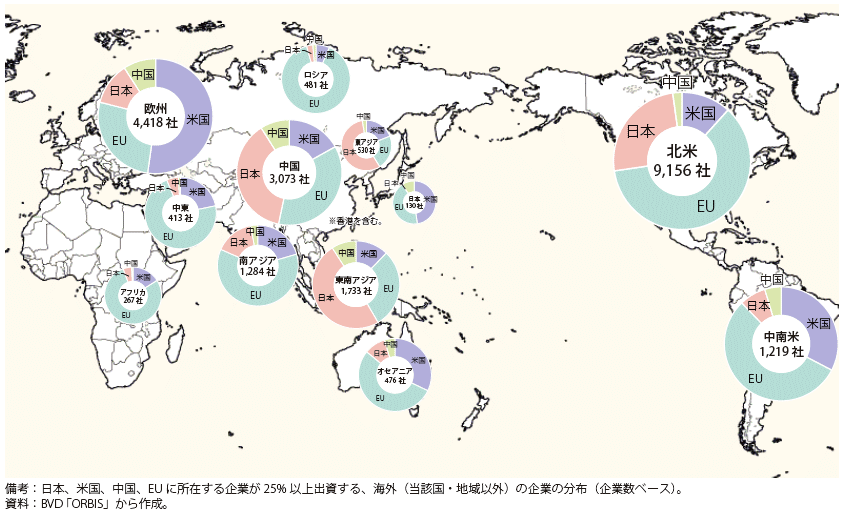
第Ⅱ-1-1-2-38図 M&Aを通じた出資先企業が保有する特許の割合(対自国企業が保有する特許金額40)
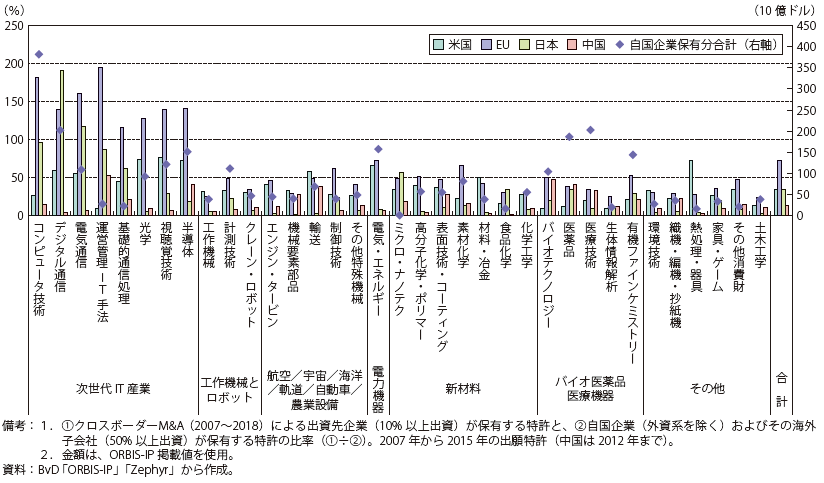
第Ⅱ-1-1-2-39図 M&Aを通じた出資先企業が保有する特許の割合(対自国企業が保有する出願特許数)
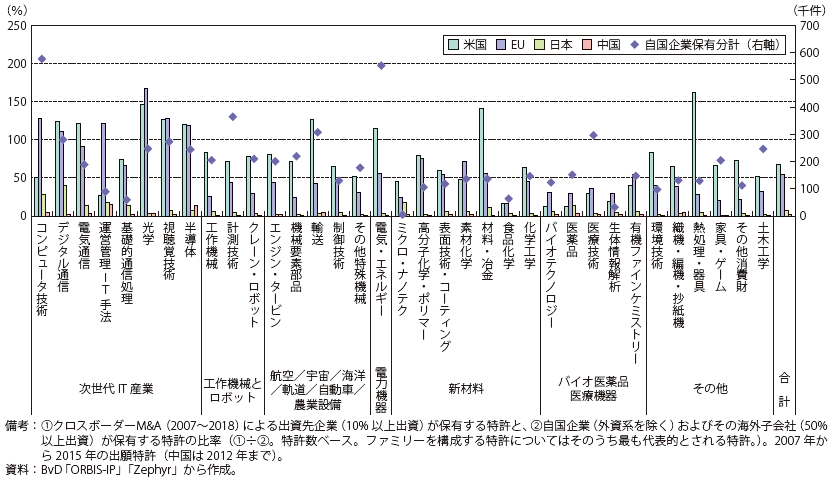
特許金額に関する同比率と、特許件数に関する同比率について、その傾向を確認すると、EUと米国に関しては、件数に関する同比率が全体的に高い。M&Aを通じて資本ネットワークを大きく拡大し、多くの特許へのアクセス可能性を高めているといえる。
一方、中国と日本については、件数よりも金額の同比率が高い傾向がある。さらに1件あたり金額に関する同比率を見ると、中国が顕著に高いセクターが多く、M&Aによって質の高い特許にアクセスしているといえる(第Ⅱ-1-1-2-40図)。中国にとっては、M&Aを通じてアクセスする技術の重要性が高く、他国と比較しても、より技術獲得目的でM&Aを行っている可能性が示唆される。
第Ⅱ-1-1-2-40図 M&Aを通じた出資先企業が保有する特許の推計単価41比率(対自国企業が保有する出願特許)
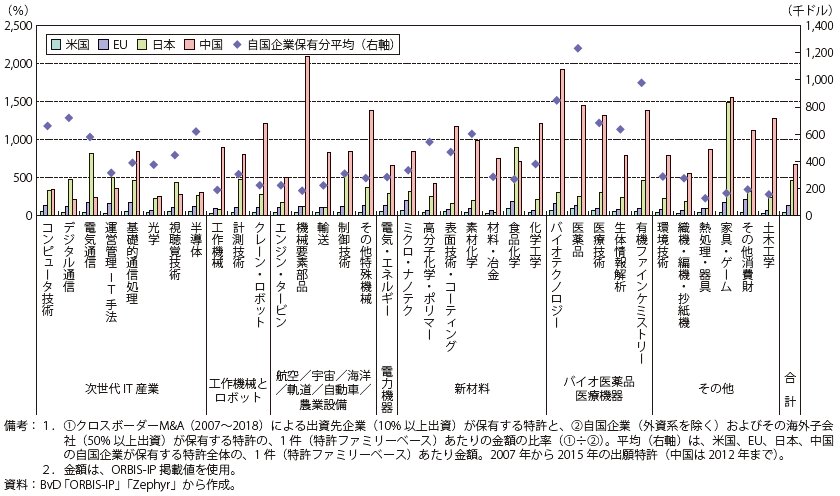
33 ビューロー・ヴァン・ダイク(Bureau van Dijk)社の「Zephyr」を使用した。図表中では企業名を「BvD」と略記する。
34 M&Aの案件の数ではなく、M&Aの対象企業の数(複数のM&A案件に同一の企業が含まれる場合があるが、そのような企業の重複を排除した)。また、ZephyrにおけるM&Aのうち、取引タイプが獲得、統合、合弁、minority出資であり、かつ、親企業(米国、EU、日本、中国)による出資比率が10%以上の企業を抽出した。
35 50%以上出資のM&Aについては、①②どちらにも含まれる。
36 今回M&Aとしているのは、取引タイプのうち、買収(acquisition)、統合(merger)、合弁(joint venture)、及びマイノリティ出資(minority stake)(2007年から2018年の公表案件)。
37 同図では、4割未満を黄色、6割以上を緑色とした。
38 経済産業省(2018)等参照。
39 ビューロー・ヴァン・ダイク(Bureau van Dijk)社のORBIS Intellectual Propertyデータベース。図表中では、企業名を「BvD」、データ名を「ORBIS-IP」と略記する。
40 金額は、ビューロー・ヴァン・ダイク社のORBIS Intellectual Propertyデータベース掲載の推計値を使用した。
41 第Ⅱ-1-1-2-38図と同様、単価を算出する際に使用した特許金額は、ビューロー・ヴァン・ダイク社のORBIS Intellectual Propertyデータベース掲載の推計値を使用した。
3.知のグローバル化
(1)海外における研究開発の拡大
これまで、資本関係による企業のグローバルネットワークを確認してきたが、知識や技術に関しても、企業のグローバル展開が進んでいる。海外拠点の機能は、かつては生産と販売が主体であったが、近年は、研究開発の重要性が増している。日本企業に対するアンケート調査42によると、海外拠点で拡大する機能として、生産と販売を回答する割合が依然として最も大きいが、新製品開発を目的とする研究開発との回答割合は2017年度まで徐々に増加している(第Ⅱ-1-1-3-1図)。
第Ⅱ-1-1-3-1図 日系海外現地法人が今後拡大予定の機能
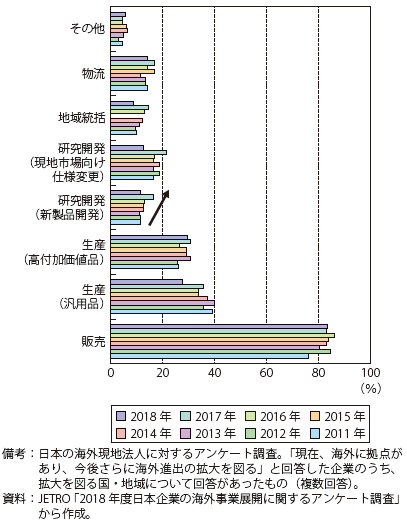
製造業の日系海外現地法人の研究開発費は、2000年代以降大きく伸びており、日本国内よりも伸び率が高い国が多い(第Ⅱ-1-1-3-2図)。地域別に見ると、アジアでは売上高とともに研究開発費も大きく伸びている。特に中国やインド、韓国、タイは、研究開発費の伸び率が売上高の伸び率を上回る。研究開発費の規模の面でも、中国は米国に次いで大きく(第Ⅱ-1-1-3-3図)、海外現地法人に占める割合では、2002年度の2%から、2016年度には18%にまで拡大している43(第Ⅱ-1-1-3-4図)。台湾や韓国、ASEAN等と合わせたアジアの割合は、同期間に約3倍に拡大している。
第Ⅱ-1-1-3-2図 日系海外現地法人(製造業)の研究開発費(実質値)
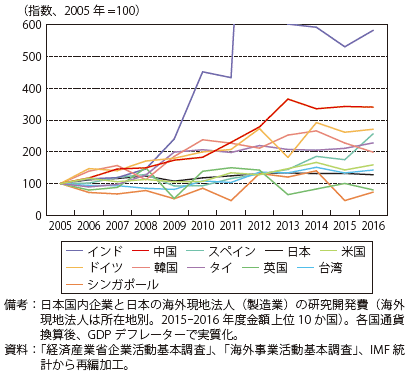
第Ⅱ-1-1-3-3図 日系海外現地法人(製造業)の研究開発費と売上高の実質伸び率
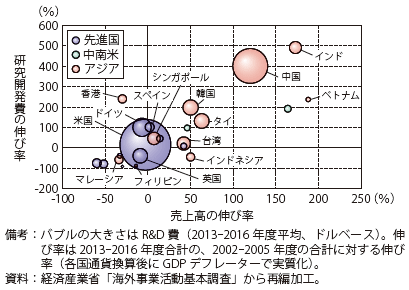
第Ⅱ-1-1-3-4図 日系海外現地法人の研究開発費(製造業)に占める各国割合
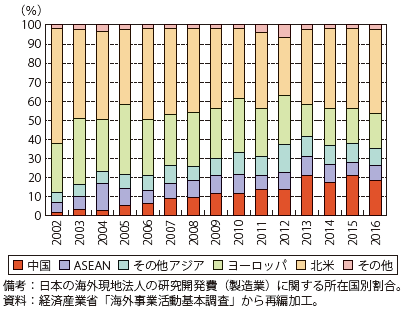
では、海外ではどういったセクターで研究開発が行われているのだろうか。日系海外現地法人の研究開発費における製造業の割合44を見ると、2000年代に一貫して低下している。2010年代にやや回復したものの、2016年度の水準は2000年代初頭に比べ20%ポイントも低い(第Ⅱ-1-1-3-5図)。
第Ⅱ-1-1-3-5図 日系海外現地法人の研究開発費に占める製造業の割合
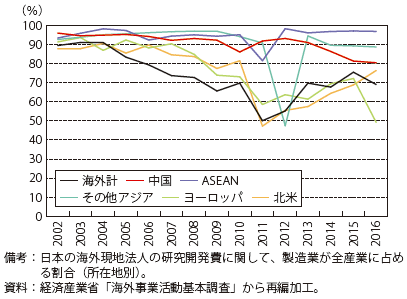
金額規模で見ると、自動車部品製造業、医薬品製造業、卸売業が大きい(第Ⅱ-1-1-3-6図)。また、情報通信業や医薬品製造業は、売上高に比して研究開発費が大きい(第Ⅱ-1-1-3-7図)。
第Ⅱ-1-1-3-6図 日系海外現地法人の研究開発費の規模と伸び率(セクター別)
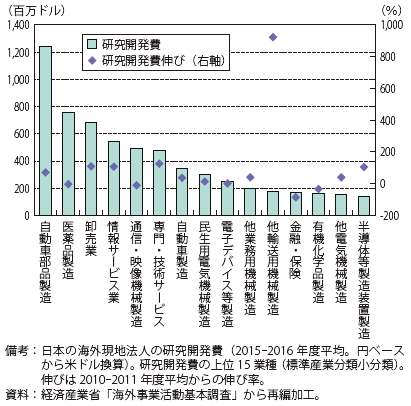
第Ⅱ-1-1-3-7図 日系海外現地法人の研究開発費に関するセクター別割合(2015-2016年度)
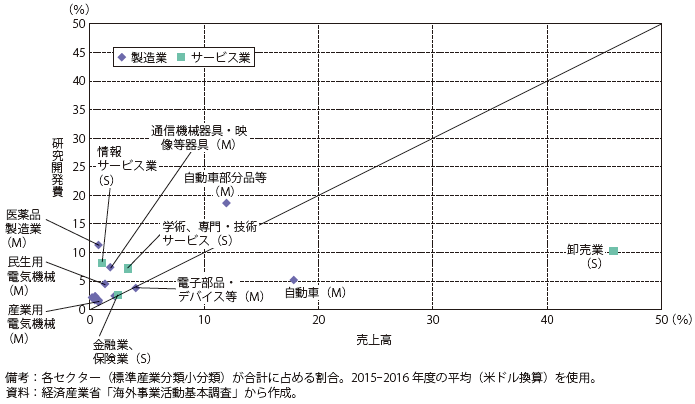
一方、近年の伸び率が特に高いのは、専門・技術サービス、情報サービス業、卸売業、半導体等製造装置製造業等であるが、ほとんどのセクターにおいて、売上高の伸びを研究開発費の伸びが大きく上回っている(第Ⅱ-1-1-3-8図)。海外拠点において知識生産活動が活発化していることが示唆される。
第Ⅱ-1-1-3-8図 研究開発費と売上高のセクター別伸び率(日系海外現地法人)45
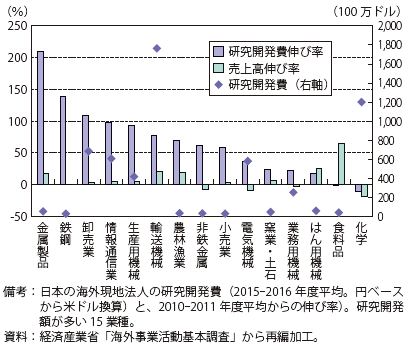
海外現地法人における研究開発費は、海外進出企業の増加や規模の拡大とともに伸びた。しかし、売上高を大きく上回る研究開発費の伸びは、進出先である新興国におけるイノベーション環境の向上や、市場に合わせた製品開発の必要性等を背景に、海外現地法人の研究開発の重要性が高まっていることを示唆している。
42 独立行政法人日本貿易振興機構(2019)。
43 米ドル(円ベースから年平均レートで換算)。
44 「経済産業省企業活動基本調査」の対象産業全体。
45 第Ⅱ-1-1-3-8図の業種分類は、標準産業分類の小分類を、今回の分析において独自に整理したもの。
(2)新興国への技術波及46
新興国の発展において、先進国の技術的知識の導入・活用はキャッチアップに非常に重要な役割を果たす。特に、経済発展の過程で、研究開発集約度の低い産業から高い産業へと産業構造が徐々に変化していくパターンが、典型的なキャッチアップ型工業化と言えるだろう。日本においても、戦後の急成長は海外技術を積極的に導入することにより実現したと考えられている。
知識・技術の波及については、その経路として、貿易(財・技術)や外国直接投資(以下、FDI)の重要性が指摘されている。
知識・技術の波及経路のうち、1)貿易による経路については、輸出される製品に技術情報が組み込まれていることから、製品を使用し分析したり、使用するための指導を受けたりすることで技術波及を生じる47。また、貿易パートナーとの人的コンタクトもイノベーションのきっかけとなり得る48。
2)FDIによる経路については、企業進出先において、同一セクターの地場企業による観察・模倣や、部材の供給企業に対する技術提供、買収先企業に対する技術提供等によって技術波及が生じるとされている49。なお、FDIについては、Fosfuri et. al.50が、外資企業の現地雇用者が国内企業に転職することによる技術波及を、またRodriguez-Clare51が、多国籍企業と現地企業との密な取引関係が技術情報を波及させることで、途上国の企業にプラスに働くことを示している。
飯野等(2019)52は、このような先進国企業の海外進出に伴う新興国への知識の波及の影響を明らかにするため、外国への特許出願を、海外進出の代理変数とみなして、その動向を確認した。
特許出願先別に見ると、2000年以降、日本やドイツの特許庁に対する特許出願数が緩やかに減っているのに対して、中国特許庁への出願が伸びており、シェアで見ると、日本やドイツの低下が顕著である(第Ⅱ-1-1-3-9図、第Ⅱ-1-1-3-10図)。
第Ⅱ-1-1-3-9図 各国・地域特許当局への特許出願件数の推移(所在国・地域が明らかな出願人のみ)
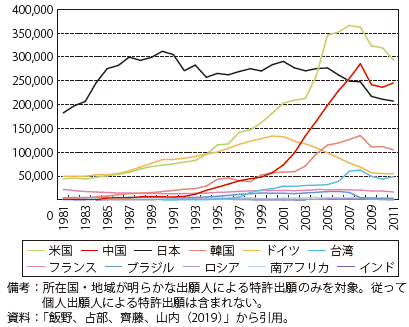
第Ⅱ-1-1-3-10図 各国・地域特許当局のシェア(国・地域別特許当局向け出願件数の合計に占めるシェア)の推移
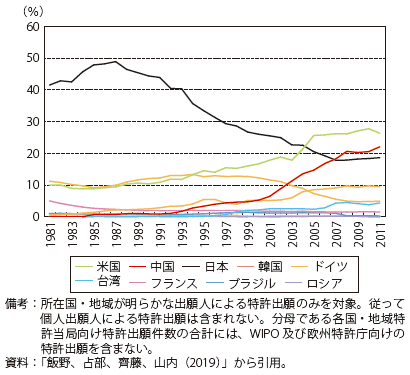
しかし、中国特許庁への出願が伸びていると言っても、出願企業の構成はどのようになっているのだろうか。
各国・地域特許当局に対する出願に占める出願企業の所在国53の順位により、新興国における出願企業の所在国別の動向を確認すると、韓国特許庁への出願件数で見た韓国企業の順位は、1980年代に、3位から1位に上昇した。すなわち、技術的に進んでいる外国からの出願件数に、自国からの出願件数がキャッチアップし、追い抜いたことになる。次に、中国特許庁への出願件数における中国企業の順位は、1990年代に緩やかに上昇し、2005年以降は1位を確保している。同様に台湾及びブラジルも、自国・地域における出願件数の順位が徐々に上昇していることが確認された(第Ⅱ-1-1-3-11表)。
第Ⅱ-1-1-3-11表 自国・地域の特許当局に対する出願件数における出願国・地域別順位
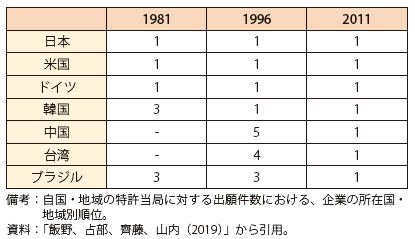
第Ⅱ-1-1-3-12図 中国の特許出願件数と被引用件数順位の推移
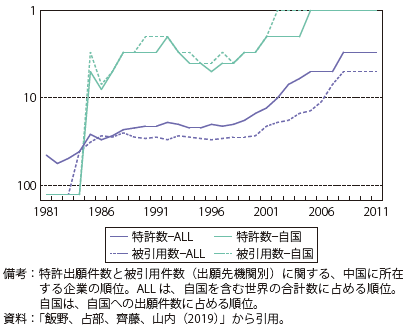
自国への出願件数における順位だけでなく、自国への出願を含む世界の合計出願件数における順位を合わせて見ると、中国については、1980年代に自国への特許出願件数と自国における被引用件数が上昇し、その後に、自国を含む世界への出願件数及び被引用件数が上昇している。韓国及び台湾についても、同様に、まず自国・地域の特許当局に対する出願件数順位が上昇した後で、自国・地域を含む世界の特許当局に対する出願件数順位が上昇していることが確認できる。
すなわち、新興国の知識生産活動が発展する初期段階においては、自国よりも海外からの特許出願が大きいが、特許出願とともに海外から技術・知識が流入することで、国内の技術力が向上し、その技術知識を活用して海外進出が活発になるという、ある種共通した流れの存在が示唆される。新興国の知識生産活動の発展において、海外の技術知識の流入が寄与している可能性がある。
46 本項(2)における主な文章及び全ての図表は、飯野、占部、齊藤、山内(2019)(「新興国における知識生産活動とグローバルネットワーク」、経済産業研究所)を参照、あるいは引用した。
47 Eaton and Kortum (1996).
48 Kiriyama (2012).
49 Kiriyama (2012).
50 Fosfuri, Motta, and Rønde (2001)
51 Rodriguez-Clare (1996).
52 飯野、占部、齊藤、山内(2019)。
53 第Ⅱ-1-1-3-11表及び第Ⅱ-1-1-3-12図では、特許出願人企業の本社住所の所在地により集計したが、その企業を50%以上保有する企業の住所の所在地により集計しても、分析結果に大きな違いはない。
(3)特許申請と企業の海外展開の連動性54
外国への特許出願は、本項(2)のとおり、新興国への技術波及に寄与する面があり、知識・技術の海外への広がりの一端を表すと考えることができるが、基本的には、自社の技術の保護や事業領域の確保を目的として行われるものである。
グローバル化が進む中で、海外展開と特許出願先との関係は、どのように変化しているのだろうか。飯野等は、財貿易及びFDIについて、外国への特許出願との連動性の確認を行った。
分析対象は、米国、ドイツ、フランス、日本、ブラジル、中国、韓国、台湾、ロシア、インド、南アフリカの11か国・地域に関する、相互の、特許出願、貿易及びFDIデータである。
第Ⅱ-1-1-3-13図と第Ⅱ-1-1-3-14図は特許の外国への出願、第Ⅱ-1-1-3-15図と第Ⅱ-1-1-3-16図は対外FDI、第Ⅱ-1-1-3-17図と第Ⅱ-1-1-3-18図は輸出のネットワークである。線の色は、線の端にある円の色と同じであり、それぞれ、特許出願、対外FDI、輸出の主体の国・地域を表している。つまり、線の端にある円は、同じ色の線の起点(from)である。また、線の太さは量を表している。
第Ⅱ-1-1-3-13図 特許出願ネットワーク(2010)55
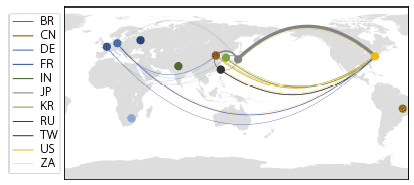
第Ⅱ-1-1-3-14図 特許出願ネットワーク(2001)
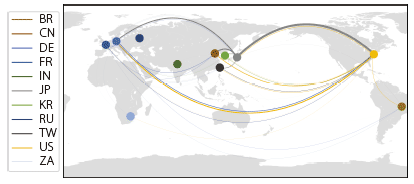
第Ⅱ-1-1-3-15図 対外FDIネットワーク(2010)
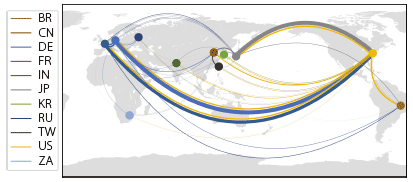
第Ⅱ-1-1-3-16図 対外FDIネットワーク(2001)
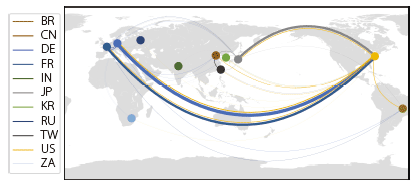
第Ⅱ-1-1-3-17図 貿易(輸出)ネットワーク(2010)
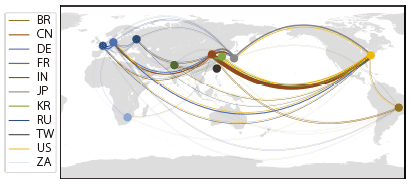
第Ⅱ-1-1-3-18図 貿易(輸出)ネットワーク(2001)
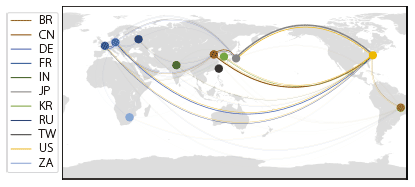
外国特許庁への出願状況を確認すると、多くの線は2001年より2010年の方が太くなっており、技術知識のやり取りが活発になっているように見えるが、中でも日本をはじめ、各国・地域から米国へ向かう線と、米国から中国へ向かう線が顕著に太くなっている(第Ⅱ-1-1-3-13図、第Ⅱ-1-1-3-14図)。
また、対外FDIのネットワークは、欧州や日本から米国へ向けた線が、2001年より2010年の方が太くなっている。貿易(輸出)ネットワークの線については、中国から米国をはじめ各国・地域に向かう線と、米国や日本をはじめ、各国・地域から中国へ向かう線が太くなっている。
特許出願の流れを、FDIや貿易の流れと重ね合わせて見ると、日本について言えば、特許の出願先は米国に向けて太くなったが、対外FDIの向かう先としても米国が太くなっている。米国について言えば、特許の出願先と貿易(輸出)の向かう先として中国が太くなっている。ドイツとフランスについて見れば、特許出願、対外FDI、貿易(輸出)の全てが向かう先として米国が太くなっている。これらを踏まえると、少なくとも先進国については、特許出願の流れは、FDIや貿易の流れと近いように見える。
次に、これら主な先進国(米国、ドイツ、フランス、日本)企業の特許出願先と、FDI進出先あるいは輸出先との相関性を確認すると、特許出願先と輸出先との相関性は緩やかに低下しており、逆に、特許出願先とFDIによる進出先との相関性が高まっていることが確認された(第Ⅱ-1-1-3-19図)。先進国企業の海外売上高の割合が徐々に拡大する中で、FDIの重要性が高まり、相対的に輸出の重要性が低下していることが示唆される。
第Ⅱ-1-1-3-19図 特許と貿易・FDIの連動性(先進国)
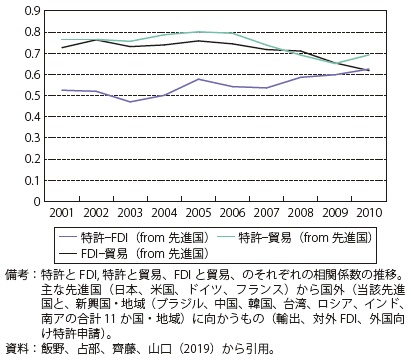
ただし、先進国における貿易と特許の相関性は、低下してはいるものの、FDIと特許の相関性を上回る。海外拠点を有する企業は輸出企業のうち一部にすぎないことを踏まえれば、工業品の輸出国にとって、輸出先と特許申請先の連動性の高さは自然であり、引き続きその重要性が示されているといえる。
一方、FDIと貿易の相関性については、先進国では緩やかに低下している。先進国企業によるFDI進出は生産目的が多いが、そこで生産に必要な中間財の調達が、当該先進国からの輸入から、現地調達に切り替わってきたこと等により、FDI進出先と輸出先の相関性が低下した可能性が考えられる。
以上より、国を越えた特許申請、すなわち、技術・知識の広がりは、FDI及び貿易と連動していること、また、その連動性は変化しており、FDIに伴う技術・知識の広がりが従来よりも大きくなっている一方で、貿易に伴う広がりは、その重要性がやや低下している可能性が確認できたと言える。
さらに、特許と貿易に関する連動性は先進国だけでなく新興国でも高まっており、技術・知識の広がりの方向性が多様になっている可能性が考えられる。
一方、FDIの進出先及び特許出願先は、中国や米国等、一部の国・地域に偏り、進出元あるいは出願元の国への流入が小さいケースが多く見られるなど、その流れは非対称であった。日本をはじめとして、FDIや特許出願の流入が非常に弱い場合は、海外からの技術・知識の流入も弱い可能性が考えられる。
54 本項(3)における主な文章及び全ての図表は、主に、飯野、占部、齊藤、山内(2019)を参照、あるいは引用した。
55 第Ⅱ-1-1-3-13図から第Ⅱ-1-1-3-18図における記号は、線の起点となる国・地域名を表す。(BR:ブラジル、CN:中国、DE:ドイツ、FR:フランス、IN:インド、JP:日本、KR:韓国、RU:ロシア、TW:台湾、US:米国、ZA:南アフリカ。)
(4)イノベーションに関する企業のグローバルなネットワーク56
異なる知識の結合は大きなイノベーションを引き起こす重要な要素であると言われている。特に、地理的に離れた人々は異なる知識を有することが多く57、その意味で国際的な知識や技術の伝播は、国内のイノベーションに大きく影響する可能性がある。
国際知識伝播の経路には、貿易(財・技術)、対外直接投資のほかに、国際共同研究があるが、飯野等58は、特に企業間の国際共同研究に焦点を当て、それが知識伝播を促して企業のイノベーションの質に与える効果を、企業間の特許の共同出願を共同研究とみなすことで、実証的に検証した。
飯野等によると、国際共同特許は、特許の質(被引用件数)を高める効果がある。
同研究では、主要6か国(日本、ドイツ、フランス、米国、中国、韓国)59について、特許の共同出願を行ったことがある企業と、国際共同研究を行ったことがある企業を抽出し、共同出願あるいは国際共同出願と、被引用件数との相関関係を分析している60。その結果、共同出願あるいは国際共同出願のネットワークに入っている企業の方が、そうでない企業に比べて特許の被引用数が多いこと、また、被引用件数に与える効果の度合いは、多くの場合、共同出願ネットワークよりも、国際共同出願ネットワークの方が大きいことが明らかにされた(第Ⅱ-1-1-3-20表)。すなわち、国際的なネットワークを有することが、企業の研究の質を高めるということである。
第Ⅱ-1-1-3-20表 国際共同研究と特許の質の相関(回帰分析)
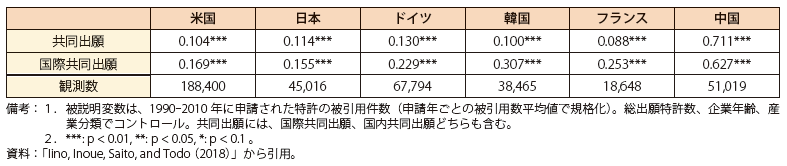
主要国の国際共同特許の割合を見ると、中国とフランスが2000年代に大きく伸びている一方で、日本の国際共同出願比率は世界平均を下回っている(第Ⅱ-1-1-3-21図)。
第Ⅱ-1-1-3-21図 国際共同特許の割合(全ての特許に占める割合)の推移
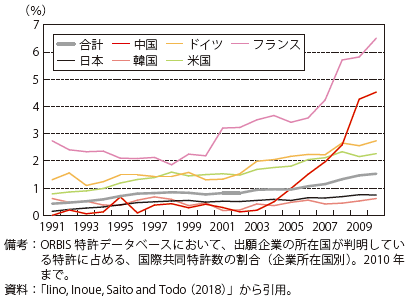
戸堂、柏木(2017)61によると、特許の共同所有により表される共同研究ネットワークにおいて、日本企業は、国内では密なつながりを持っているが、世界の企業と十分につながれていない。特許の共同所有ネットワークを可視化した図(第Ⅱ-1-1-3-22図)からは、欧米や中国に比べて、日本企業のクラスターは、主要国の企業ネットワークの中心から外れて独立していることが確認でき、他国と比べて国際化が貧弱であると言う。
第Ⅱ-1-1-3-22図 世界企業の共同研究ネットワーク(2011-2013年)
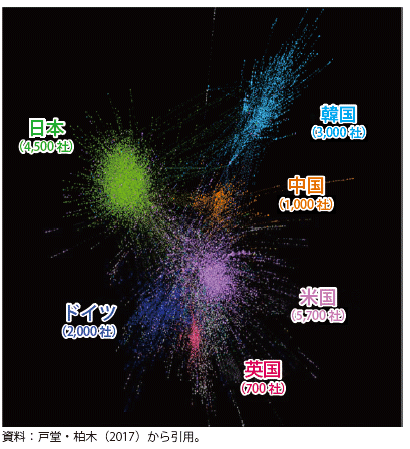
日本企業が国内に閉じる傾向については、国内に研究パートナーが十分存在することが背景とも言われており62、そうだとすれば、海外企業との繋がりが弱いことによるイノベーションに関する問題は小さい可能性もある。しかし、国際共同特許と特許の質の相関性は1990年代よりも2000年代に高まっており63、さらに、技術・知識の進歩のスピードが求められる中で、外国企業を含めた企業ネットワークの拡充や、外国からの技術・知識の流入については、その重要性が増しているのではないだろうか。
56 主に、経済産業研究所分析(①、②)を引用・参照した。(①Iino, Inoue, Saito and Todo (2018) “How Does the Global Network of Research Collaboration Affect the Quality of Innovation?”、②戸堂、柏木(2017)「グローバルな企業ネットワークから見た日本企業の現状」))
57 Todo, Matous, and Inoue (2015).
58 Iino, Inoue, Saito and Todo (2018).
59 2000~2010年に出願された、特許出願人が企業である特許総数の8割を当該6か国が占める。
60 総出願特許数、企業年齢、産業分類でコントロール。1991~2010年まで。
61 戸堂、柏木(2017)。
62 また、戸堂、柏木(2017)は、共同研究ネットワークにおける多様性の分析により、日本企業が、国内では多様な相手と共同研究を行っていることを示唆している。
63 飯野、井上、齊藤、戸堂(2018)。
4.ヒトの移動
世界のヒトの移動がどのように変化してきたかを移住者、留学生、観光客の側面から見てみる。
まず移住者については、中南米、中東、アフリカから米国やEU15への流入は2000年から2016年にかけて引き続き多く、特に中東からOECD加盟国への移住は3.5倍になり、中でもEU15は4.1倍と最も高い伸びとなった他、米国も2.3倍となっている。
また、中国、南アジアから先進国への流入も増加しており、中国は豪州で2000年から2016年にかけて3.6倍、EU15で同2.3倍になった。南アジアは豪州で同7.8倍、EU15で同2.4倍、北米で同1.6倍と増加した。
各国・地域における移住者の出身国・地域別の割合を見ると、北米においては中南米からの移住者が2000年37.0%から2016年34.9%と若干低下し、南アジアが同10.7%から同12.1%、ASEANが同9.0%から同11.6%、アフリカが同6.0%から同10.1%と割合を高めた。EU15は欧州からの移住者が引き続き多くを占めているものの、中東が2000年8.1%から2016年16.2%となり、それまで欧州以外で最大の割合だったアフリカの同13.7%から同10.9%を上回り最大の勢力となった。日本はASEANが2000年34.1%から2016年35.3%と高くなり、中国が同27.2%から同24.2%と割合を下げた。また、2017年には南アジアが7.1%と上位3位に入り、当該地域との繋がりが高まっていることがうかがわれる。他、豪州においても2000年6.7%から2016年26.6%と南アジアからの移住者の存在が高まっている。以上のことから移民の面からは、中東と南アジアが急速に先進国とのヒトの交流を拡大していることがうかがわれる(第Ⅱ-1-1-4-1図)。
第Ⅱ-1-1-4-1図 先進国における新興・途上国からの人の流入者数の変化
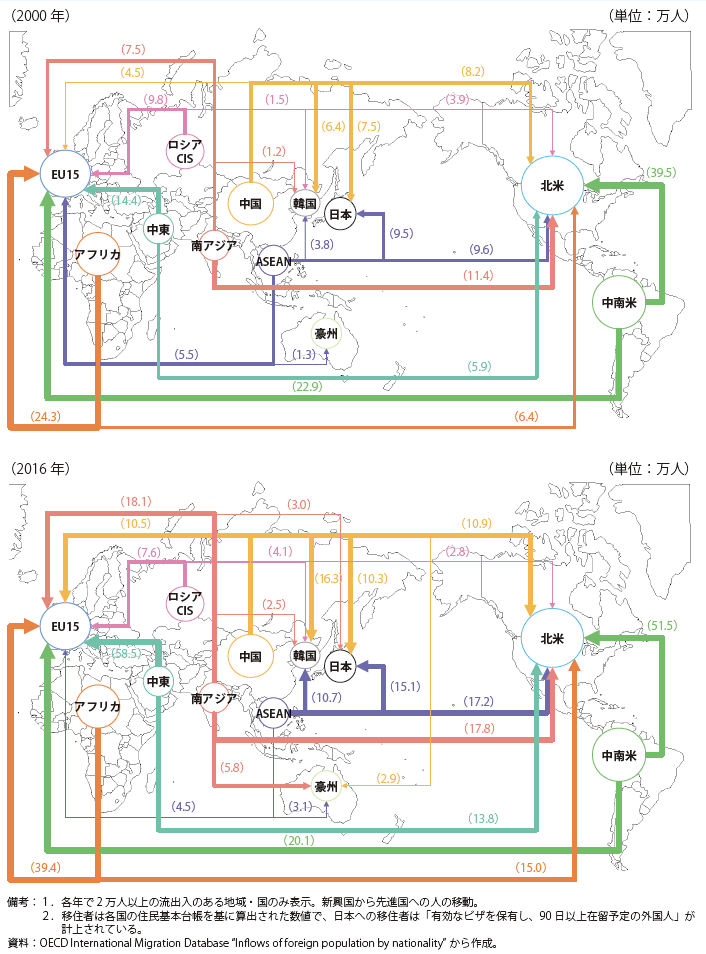
次に、主要国における高等教育レベル64における各国インバウンド留学生数の推移を見ると、新興・途上国や地域から先進国への留学生が大幅に増加し、各地域間の人の流れが太くなり世界各国・地域の高度人材の結びつきが広がってきたことが分かる。
OECD加盟国への留学生は2000年から2016年にかけて、約152万人から約350万人と2.3倍になった。中でも中国から留学生は、約11万人から約79万人となり7.3倍もの大幅な増加となった。これによりOECD加盟国への留学生のうち中国人が占める割合は、2000年の7.1%から2016年には22.4%となり、2000年時点で23.3%と最大の割合を占めていたEU15の留学生(2016年時点で13.3%)を上回るようになった。
また、北米における中国人留学生の割合は同10.5%から31.9%、EU15においては同2.4%から同11.3%まで高まった。日本においても中国人留学生の割合が同47.0%から同53.4%になった。他方で、中国人留学生は日本よりEU15、豪州を留学先に選択するようになっており、OECD加盟国における中国人留学生数の国・地域別に見た割合は、日本が2000年25.9%から2016年9.7%と低下したのに対し、豪州が同4.6%から同14.2%へ、EU15が同16.6%から同21.1%へと高まった。
なお、日本においては、ASEAN(2000年から2016年にかけて5.3倍)、南アジア(同7.4倍)からの留学生が増加しており、特にASEAN留学生が日本へ留学する割合は、2000年の4.8%から2016年には12.7%と高まり、以前と比べてASEAN留学生が日本を選好するようになったことがうかがわれる(第Ⅱ-1-1-4-2図)。
第Ⅱ-1-1-4-2図 先進国及び中国における高等教育レベルに属する留学生の流入者数の変化
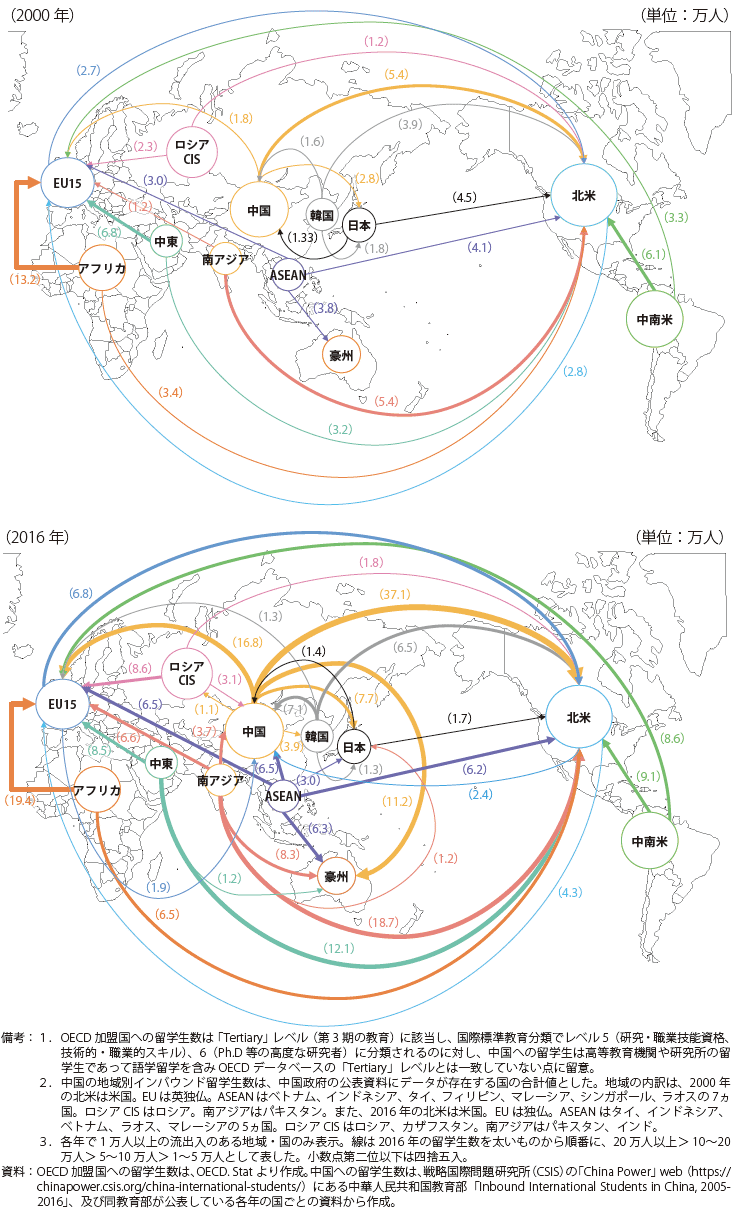
なお、中国のインバウンド留学生は数の増加に比して質も高まっており、上述の留学生に占める学位取得コースに留学している割合は2000年の26.3%から2016年には47.4%へ高まっており、中国の高等教育機関が海外から高度人材を惹きつけるようになったことを示している。
また、高等教育に限定しない短期・長期の留学生も大幅に増加してきている。中でもASEAN、南アジア、アフリカからの留学生を惹きつけており、中国とこれら新興・途上国を有する地域との結びつきが深まっていることがうかがわれる(第Ⅱ-1-1-4-3図)。
第Ⅱ-1-1-4-3図 中国の出身地域別留学生数の推移
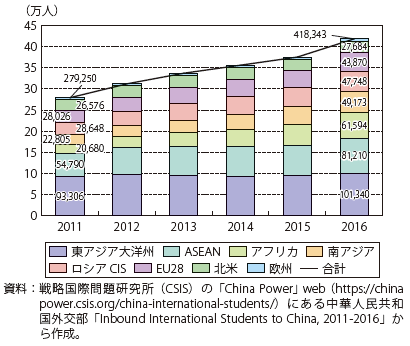
また、世界の人の移動(出国、入国ベースでの人の動きであって、目的が旅行か否かを問わない)を見ると、アウトバウンドでは東アジア・大洋州の伸びが大きい。また、インバウンドでは2017年にASEANが北米を超えている。他方で、東アジア・大洋州とASEANを除く新興国地域では、大きな変化は起きていないように思われる(第Ⅱ-1-1-4-4図)。
第Ⅱ-1-1-4-4図 世界の地域別に見たインバウンド、アウトバウンド旅行者数の変化
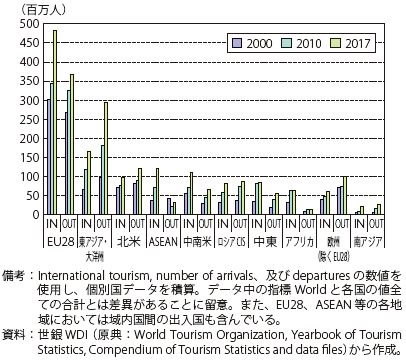
64 “Tertiary(第3期教育)”レベルの留学生数。第3期の教育は、国際標準教育分類でレベル5(研究・職業技能資格、技術的・職業的スキル)、6(Ph.D等の高度な研究者)に分類される。