

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第1章 第2節 米中という二大経済国と各国・地域の経済関係
第2節 米中という二大経済国と各国・地域の経済関係
中国は、GDPに代表される経済規模の拡大とともに、諸外国との貿易・投資も拡大し、関係を強めている。昨年の通商白書は主として中国の側から貿易・投資の動向や特徴を論じた。一方で、GDP世界首位の米国は従来から諸外国と強い関係を有している。ここでは次章で検討するような米中間の保護主義的な動きを念頭に、世界の主要地域・国の側から、GDP第1位・第2位の米国・中国との貿易・投資等の面での関係について両国を比較するような形で考察してみる。
1.貿易面における結びつき
まず、貿易面での関係から見ていく。現在、世界の各国・地域にとって米国・中国は二大貿易相手国として、強い結びつきを有している。IMFの統計によれば、2017年の世界の総貿易額35.3兆ドルのうち、世界の貿易相手国の順位を見ると、僅かな差で第1位は中国4.1兆ドル(シェア11.6%)、第2位が米国3.8兆ドル(同10.6%)となっている(第Ⅱ-1-2-1表)。しかし、輸出と輸入に分けてみると状況は異なり、輸出相手国としては米国(同12.8%)が最大であり、中国(同9.4%)が第2位となっている。反対に輸入相手国としては、中国(13.7%)は米国(8.5%)を大きく上回っている。これは中国が世界の工場として各国に輸出をする一方で、依然としてマーケットとしては米国の持つ意味が大きいことを示している。
第Ⅱ-1-2-1表 世界の貿易相手国(2017年)
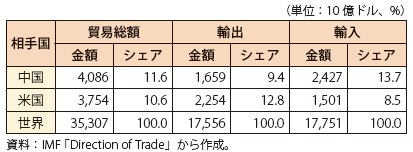
一方、このような関係を時系列で見ると、2000年代初頭、貿易総額で見て米国と中国は3倍の開きがあった。しかし、次第に米国のシェアが低下する一方で、中国のシェアが上昇してきた(第Ⅱ-1-2-2図)。両国の貿易総額は2010年にほぼ拮抗し、それ以降は米国のシェアもやや上昇の動きも見える。現在、世界にとって、両国とも重要な貿易相手国であり、両国とも無視することのできない存在となっている。特に、依然として米国が最大の輸出先である点は重要であり、世界のマーケットとしての米国への依存が高いと言える。輸入における結びつきも重要ではあるが、ここでは、各国の米国・中国への依存という趣旨から、主として各国の対米・対中向けの輸出に焦点を当てて見ていく。
第Ⅱ-1-2-2図 世界の貿易相手国の推移
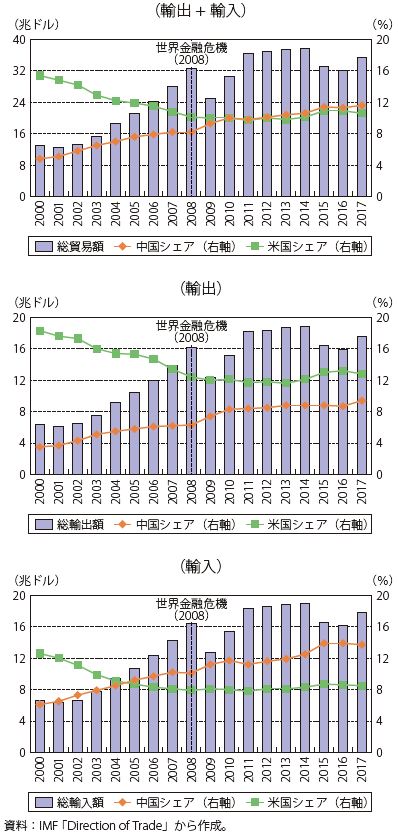
国・地域別に対米国・対中国向け輸出シェアの変化(2000年→2017年)を見てみると、総じて中国向けシェアが大きくなっている(第Ⅱ-1-2-3図)。ただし、地域によって程度の相違があり、日本は米国向けシェアがやや低下する一方で、中国向けシェアが上昇し、現状では米国・中国向けがほぼ等しくなっている。これに対して、韓国、台湾は中国向けシェアが大きく拡大して、中国向けシェアが米国向けを大きく上回っている。ASEANも中国向けシェアが拡大しているが、ASEAN全体としては中国向けシェアが米国向けをやや上回る程度でとどまっている。
第Ⅱ-1-2-3図 主要地域の輸出に占める米国・中国のシェア(2000年→2017年)
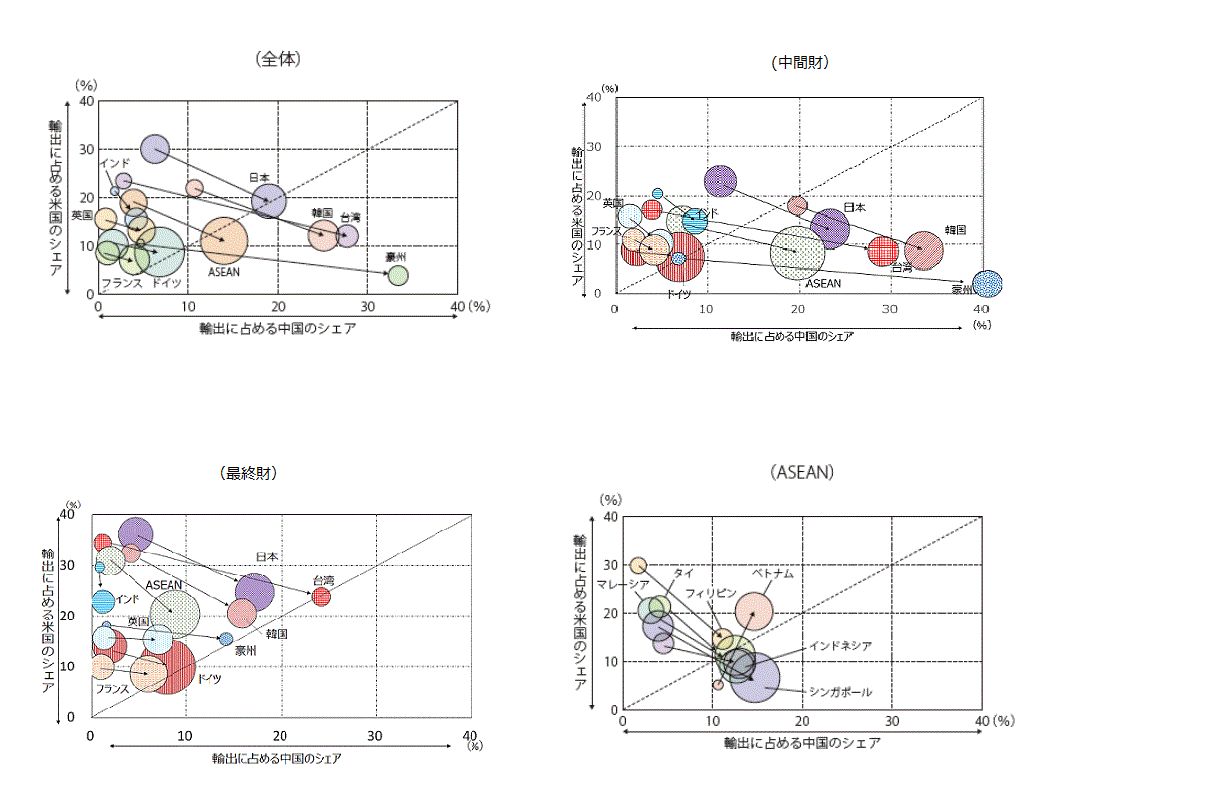
この動きを製品の生産工程で分けて中間財・最終財別に表示すると、これらの国の中間財輸出では中国向けシェアがより大きく上昇しており、日本、韓国、台湾、ASEANは中国とつながるGVCに組み入れられたことを示唆している。
それに対して、最終財輸出では、依然として米国向けシェアの方がわずかに高い。これは最終需要地として依然として米国の存在が大きいことを示している。しかし、その差は縮まってきており、米国・中国がほぼ拮抗してきているといえる。
なお、ASEANの中を国別に見ると相違があり、シンガポール、マレーシア、インドネシアは中国向けシェアの方が大きく、フィリピンは米国向けが大きい。タイは米中向けがほぼ等しい。ベトナムは全く異なる動きをしており、米国向けが急速に拡大している。
総じて中国向けシェアの高いアジアの中で、インドは例外的に中間財においても最終財においても中国向けが低い。インドは現状では必ずしもアジアのGVCの中に組み込まれているわけではないことを示している。
ほかの地域に目を向けると、ドイツを先頭に、フランス、英国などの欧州諸国が緩やかに中国向けシェアを高めている。ただし、欧州の場合は欧州域内向けシェアが輸出の過半を占めるため、米国・中国向けシェアはそれぞれ1割以下であり、ドイツにおいてさえ依然として米国向けシェアの方が高い。
豪州は、中間財において大きく中国向けシェアが拡大しており、中国に鉄鉱石、石炭等の資源輸出が拡大していることを裏付けている。
これらの相違は、GVCに組み込まれているかどうか、所属する地域における域内統合の程度、地理的な近接性等が影響していると考えられる。アジアの日本、韓国、台湾、ASEANはGVCに組み込まれており、中間財輸出を通じて中国と強い結びつきを有している。仮に米中間で貿易制限措置が導入された場合は、欧州やインドなどに比べてより大きな影響を被るおそれがある。
なお、米国・中国との経済関係の強さは輸出に占めるシェアとともに、そもそも各国の経済が輸出にどの程度依存しているかにも関係している。そこで経済規模(GDP)に対する輸出の比率(輸出依存度)を見ると、輸出主導型の経済成長を遂げてきたといわれるアジア諸国に輸出依存度の高い国が多い。ASEANは全体としてGDPに対する輸出依存度が47.0%。その中でも特にシンガポールが100%を超えるほか、ベトナムが90%台、マレーシアが約70%、タイが約50%と高い国が続く。これらの国々は米中向け輸出を通じて大きな影響を受けると考えられる(第Ⅱ-1-2-4表)。
第Ⅱ-1-2-4表 主要国・地域の輸出依存度(2017年)
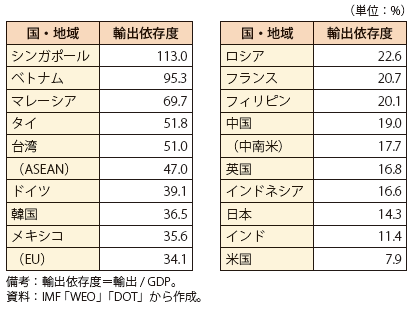
(1)ASEAN
ここからは主要地域・国ごとに貿易動向や輸出品目構成を見ていく。
①主要輸出相手国の推移
現在、ASEANの輸出相手国はASEAN域内が1/4を占め、域外では中国、米国、日本が上位にきている(第Ⅱ-1-2-5表)。ASEANは域内向けの輸出が大きいこともあって米国・中国への輸出シェアは日本や韓国よりも低い。過去からの推移を見ると2000年代初頭、米国と中国のシェアには大きな差があったが、中国のシェアが次第に拡大し、世界金融危機後に米国シェアを追い抜くことになった(第Ⅱ-1-2-6図)。ただし、GVCを考慮すると、単純に中国のシェアが高まっているとも言い切れない。その点についてASEANの輸出品構成を見て考察する。
第Ⅱ-1-2-5表 ASEANの主要輸出相手国・地域(2017)
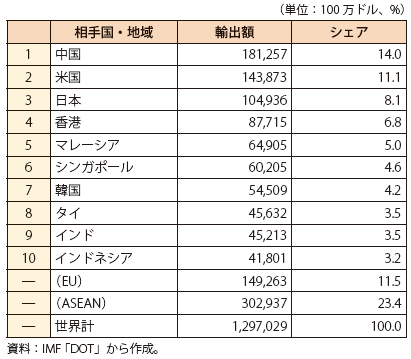
第Ⅱ-1-2-6図 ASEANの輸出の推移
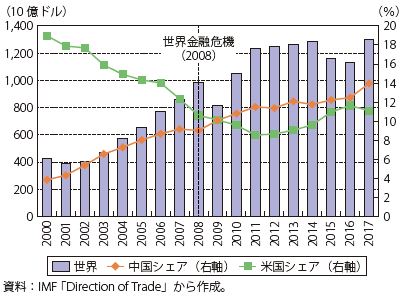
②主要輸出品目
統計の便宜上、ASEANから米国・中国への輸出品構成を中国のASEANからの輸入で見てみると72、鉱物性燃料など資源のほか、集積回路、半導体デバイスなど電気機器を中心とした、GVCに利用される品目(GVC関連品)が多い(第Ⅱ-1-2-7図)。これらの中間財は、最終的には米国向けに輸出され、仮に米中間で貿易制限措置が課された場合はASEANも影響を受けるおそれがある。一方の米国のASEANからの輸入は、集積回路等の中間財もあるが、パソコン、プリンターのほか、衣類、履き物、家具などの軽工業関係の消費財が多く、これらの輸入品は米国内で消費される部分が多いと思われる(第Ⅱ-1-2-8図)。
第Ⅱ-1-2-7図 中国のASEAN諸国からの輸入(2017)
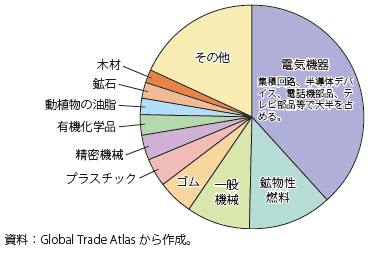
第Ⅱ-1-2-8図 米国のASEAN諸国からの輸入(2017)
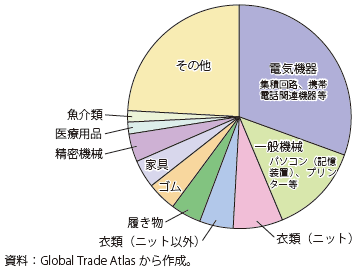
中国の米国向け輸出において、どの程度ASEANから輸入した中間財が利用されているかは、通常の貿易統計からでは見えにくい。そこでOECDの付加価値統計を利用して考察してみることにする。
③付加価値貿易から見た米中との関係
まず、ASEANの輸出先を通常の貿易で見た総輸出と付加価値統計で見た最終需要地向け付加価値輸出で比較してみる(第Ⅱ-1-2-9表)73。中国は総輸出で見た場合に比べて、最終需要地向け付加価値輸出で見た場合の方がシェアは低下し、米国は反対に高くなっている。これは中国でASEANから輸入された中間財が加工され、米国に輸出されて最終的には米国で需要されていることを示唆している。
第Ⅱ-1-2-9表 ASEANの輸出相手国別シェア(総輸出及び最終需要地向け付加価値輸出/2015)
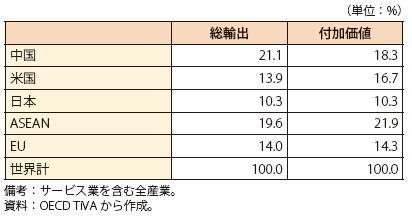
次に、どの程度のASEANの付加価値が中国経由で米国に輸入されているか、言い方を変えれば、どの程度、中国の米国向け輸出にASEANの付加価値が含まれているかを考察する。
第Ⅱ-1-2-10図はASEANで生産された付加価値が主要経由国・地域別に米国・中国に輸出される様子を示している74。ASEANの世界全体に対する付加価値輸出額は7,098億ドル。そのうち、直接・間接に中国に輸出されるのが1,207億ドル75、更にそのうち、中国の米国向け輸出に含まれるのは94億ドル(この額をAとする)である。一方、ASEANから直接・間接に米国に輸出される付加価値は1244億ドル(同B)。したがって、中国経由で米国に輸出される付加価値の全体に対するシェアは(A)/(B)で7.6%である。
第Ⅱ-1-2-10図 ASEANの米国・中国向け付加価値輸出(主要経由国・地域別/ 2015年)
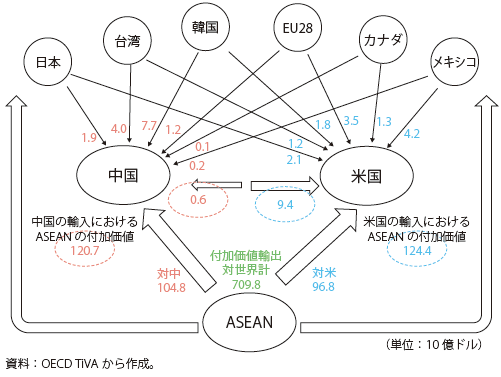
ASEANからの輸出を経由国という視点で見ると、米国向けはASEANからの直接輸出が77.8%であり、中国を経由した間接的な輸出のシェアが7.6%となる(第Ⅱ-1-2-11図)。仮に米中間の貿易に制限が課された場合、ASEANにとってはこの中国を経由した米国向け付加価値輸出が影響を受ける。なお、反対に中国向け輸出は直接輸出のシェアが高く、米国を経由したシェアは0.5%にとどまっている。
第Ⅱ-1-2-11図 ASEANの主要経由国・地域別の対米・対中付加価値輸出
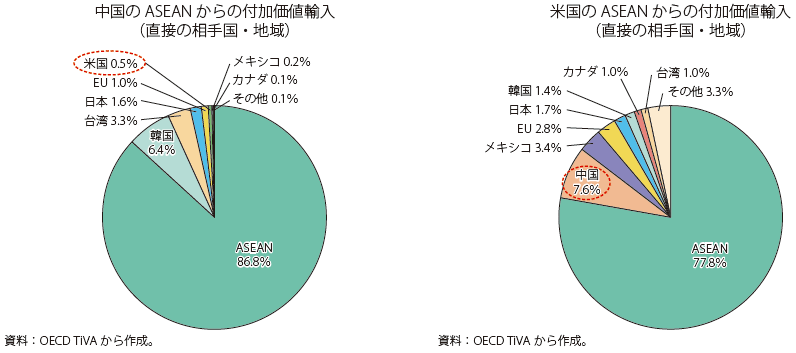
他に第Ⅱ-1-2-10図から気づくこととして、ASEANの中国向け付加価値は、中国に直接輸出されるだけでなく、東アジアの中で日本、台湾、韓国を経由して中国に届くものもある。このように付加価値の経路が網の目のように入り組んでいるため、仮に米中間で貿易制限措置が課された場合は、ASEANの中国向けの付加価値輸出に影響が生じるだけでなく、日本、韓国、台湾向け等の付加価値輸出にまで影響が及ぶ可能性もある。さらにASEANと同様に、日本、韓国、台湾等の中国を経由した付加価値輸出にも影響が生じると見られる。
72 ASEAN10か国の中で、国によっては品目内訳など詳細データが取得できない国もあるため、ここでは相手側の米国・中国統計で考察する。
73 総輸出の対象産業はサービスを含む全産業。対象を製造業だけに限定しなかったのは、通関統計に計上される財の中にはサービス業から投入された付加価値も含まれているため。ただし、製品に体化されたサービス業付加価値のほかに、純然たるサービスの形で輸出されるものもある。
74 ASEANの付加価値輸出額は、視点により様々な集計方法があるが、ここでは経由国に焦点を当てた分析をするため、二国間貿易におけるASEANの付加価値成分を表示した。ASEANから複数の第三国を経由して米国・中国に輸出される場合は米国・中国に至る直前の輸出国・地域を示している。データとしては特に記載がない限りOECDが公表しているTrade in value added database(OECD TiVA)を利用する。数値は国際産業連関表に基づいてOECDが推計したものであり、必ずしも実測と一致するとは限らない。なお、視点の相違による様々な付加価値貿易額の取り方については第1章第1節コラムにおいて詳しく述べる。
75 ここでは中国の各国・地域からの輸入におけるASEANの付加価値額を表示した。これ以降の主要経由国・地域別の付加価値輸出のグラフにおいても同様。一方、OECD TiVAではASEANの中国への輸出におけるASEANの付加価値額も推計しており、その額はより大きな額となっている。このように中国側の輸入における数値の方が小さくなる点はASEANに限らず日本など他国でも同様に見られる。
(2)インド
①主要輸出相手国の推移
インドについてもASEANと同様の考察をしてみる。インドの最大の輸出相手国は米国であり、第3位の中国とは3倍の開きがある(第Ⅱ-1-2-12表)。過去からの推移を見ても、一時期、米中の差が縮まったものの再び開いている(第Ⅱ-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-2-12表 インドの主要輸出相手国・地域(2018年)
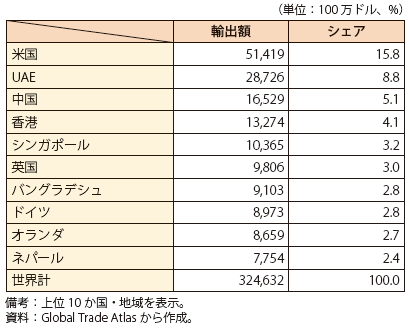
第Ⅱ-1-2-13図 インドの輸出の推移
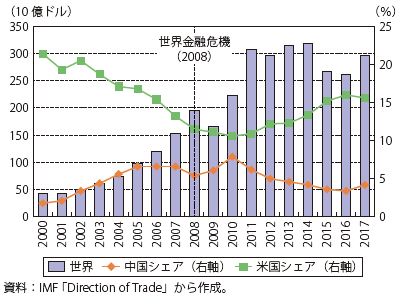
②主要輸出品目
インドから中国向け輸出品は、貴石・貴金属、綿、銅、鉱石、鉱物性燃料など資源関係が多い(第Ⅱ-1-2-14図)。既に見たASEANがアジアのGVCに組み込まれ、中国向けに集積回路、半導体デバイス等を輸出しているのとは異なる。インドから米国向け輸出は貴石・貴金属、鉱物性燃料など資源のほか、医薬品、一般機械、自動車、衣類などのシェアが高い(第Ⅱ-1-2-15図)。
第Ⅱ-1-2-14図 中国のインドからの輸入(2018年)
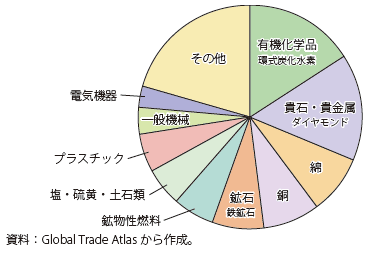
第Ⅱ-1-2-15図 米国のインドからの輸入(2018年)
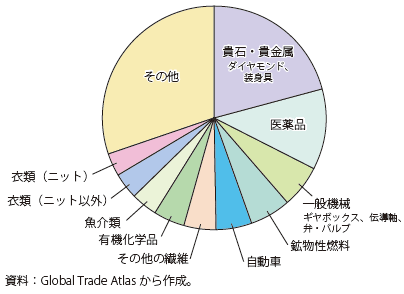
③ 付加価値貿易から見た米中との関係
インドについてもASEANと同様の考察を行うと、直接・間接を含めた米国向け付加価値輸出のうち、中国を経由するものは1.4%と限られている(第Ⅱ-1-2-16図、17図、18図)。
第Ⅱ-1-2-16図 インドの米国・中国向け付加価値輸出(主要経由国・地域別 / 2015年)
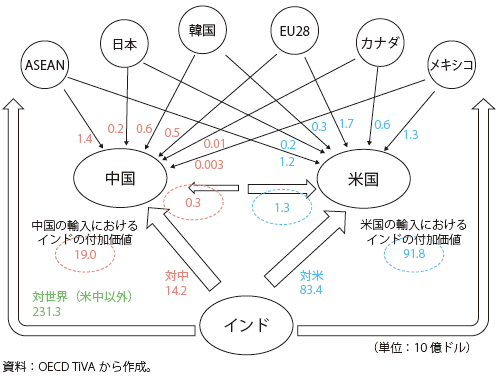
第Ⅱ-1-2-17図 中国のインドからの付加価値輸入(直接の相手国・地域)
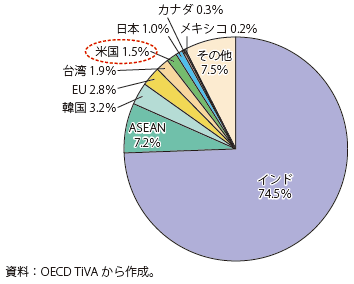
第Ⅱ-1-2-18図 米国のインドからの付加価値輸入(直接の相手国・地域)
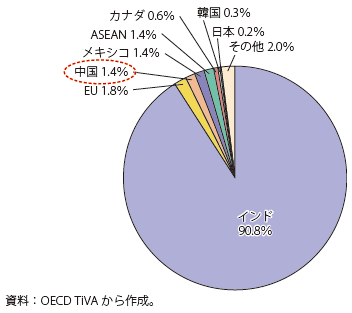
(3)韓国
①主要輸出相手国の推移
韓国にとっては、中国が最大の輸出国であり、第2位の米国の2倍以上の規模となっている(第Ⅱ-1-2-19表)。過去からの経緯で見ても2000年代中頃には中国向け輸出が米国向けを追い抜いて推移している(第Ⅱ-1-2-20図)。
第Ⅱ-1-2-19表 韓国の主要輸出相手国・地域(2018年)
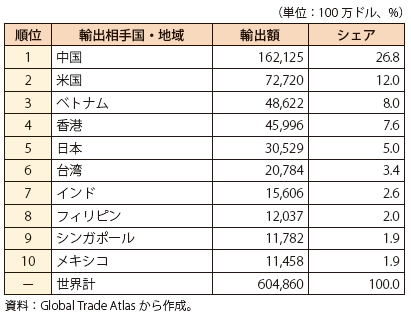
第Ⅱ-1-2-20図 韓国の輸出(うち、米中向けシェア)の推移
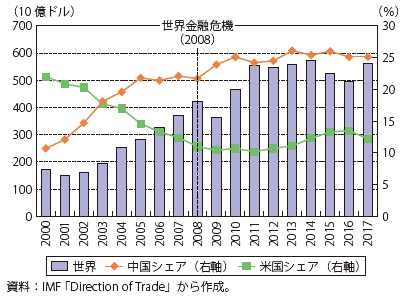
②主要輸出品目
韓国は、中国向けに集積回路、半導体デバイスなどを輸出しており、GVCを通じて、米国に完成品が輸出されている可能性がある(第Ⅱ-1-2-21図)。その点で韓国の貿易構造はASEANに近い。
第Ⅱ-1-2-21図 韓国の米中向け輸出(2018年)
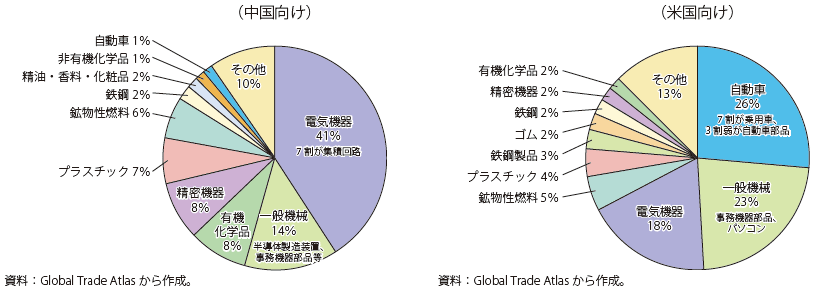
③付加価値貿易から見た米中との関係
韓国の場合は、ASEANの場合と同様に、米国に直接・間接に輸出される付加価値の12.8%までが中国を経由している(第Ⅱ-1-2-22図、23図、24図)。
第Ⅱ-1-2-22図 韓国の米国・中国向け付加価値輸出(主要経由国・地域別 / 2015年)
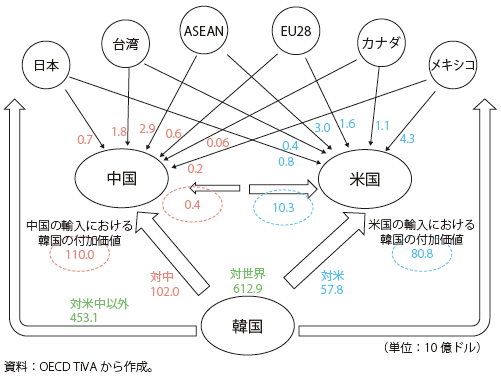
第Ⅱ-1-2-23図 中国の韓国からの付加価値輸入(直接の相手国・地域)
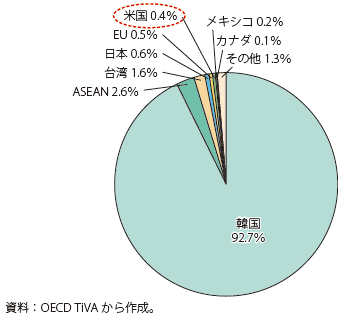
第Ⅱ-1-2-24図 米国の韓国からの付加価値輸入(直接の相手国・地域)
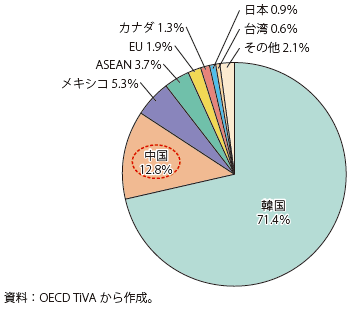
(4)日本
①主要輸出相手国の推移
日本を中心としたGVCについては第3章で詳しく述べるが、ここでは米国・中国向けの輸出について簡単に触れる。
日本にとって、米国、中国は二大輸出相手国で規模的にはほぼ拮抗している(第Ⅱ-1-2-25表、26図)。
第Ⅱ-1-2-25表 日本の主要輸出相手国・地域(2018)
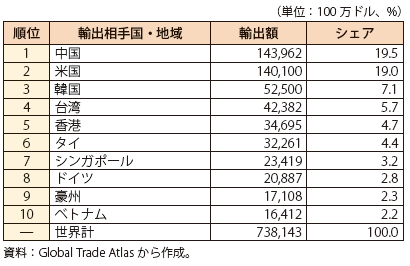
第Ⅱ-1-2-26図 日本の輸出の推移
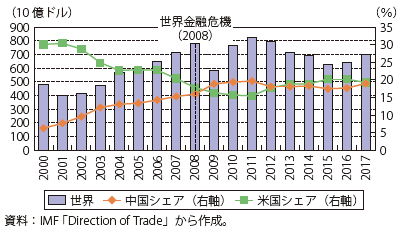
②主要輸出品目
日本もアジアにおけるGVCに関わっており、中国向けに集積回路等の中間財とともに、半導体製造装置等の生産設備を輸出している(第Ⅱ-1-2-27図)。一方、米国向けには乗用車を中心とした自動車、土木機械、プリンター、エンジン等の一般機械を輸出している(第Ⅱ-1-2-28図)。
第Ⅱ-1-2-27図 日本の主要輸出品目(中国向け)
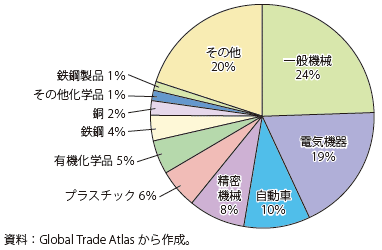
第Ⅱ-1-2-28図 日本の主要輸出品目(米国向け)
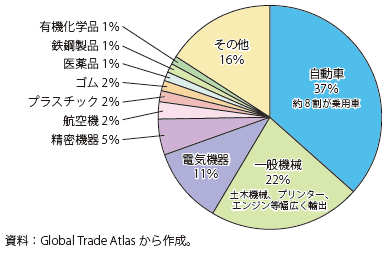
③付加価値貿易から見た米中との関係
付加価値統計で見ると、日本から直接・間接の付加価値輸出のうち、中国を経由するものは5.5%にあたる(第Ⅱ-1-2-29図、30図、31図)。この数値は、韓国、ASEANよりは低い。
第Ⅱ-1-2-29図 日本の米国・中国向け付加価値輸出(主要経由国・地域別 / 2015年)
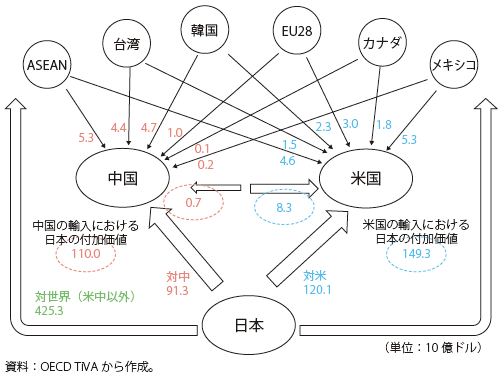
第Ⅱ-1-2-30図 中国の日本からの付加価値輸入(直接の相手国・地域)
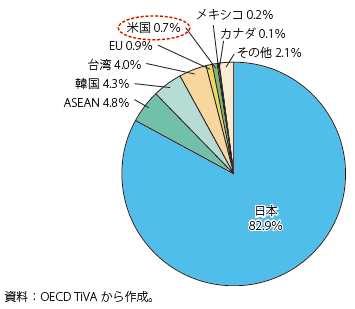
第Ⅱ-1-2-31図 米国の日本からの付加価値輸入(直接の相手国・地域)
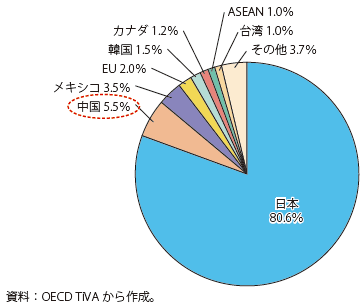
これまでの考察で出てきた、各国の対米付加価値輸出における中国を経由国とするシェアをアジア以外の地域についても含めてまとめると第Ⅱ-1-2-32表のようになる。台湾、韓国、ASEAN、日本は直接・間接の対米付加価値輸出のうち、かなりの部分を中国経由で輸出している。特に台湾が約20%と高いシェアとなっており、韓国が続いている。その背景にはアジアにおけるGVCの存在が示唆される。
第Ⅱ-1-2-32表 主要国・地域の米中間の直接輸入における付加価値成分(2015)
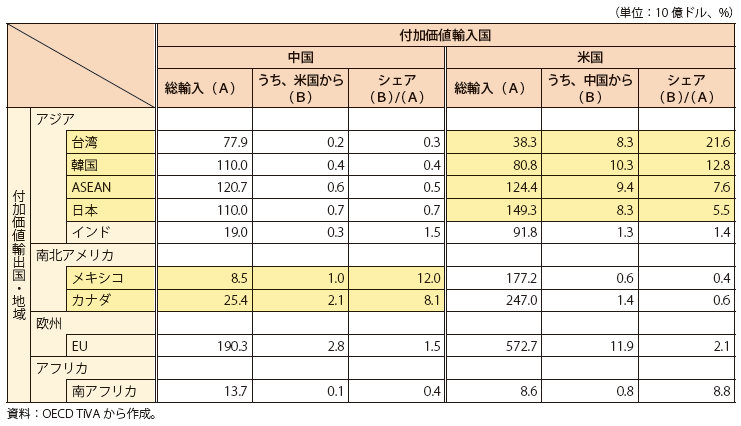
一方、同様の考察をメキシコ、カナダについて行うと、両国の直接・間接の対中国付加価値輸出の一定の割合が米国経由で輸出されている。米国、メキシコ、カナダの間にもGVCの存在が示唆される。
EUについては、米国・中国を経由して米中に輸出されている付加価値は、ある程度は存在するものの、必ずしも高いシェアとはいえない。なお、アフリカの南アフリカ共和国について同様の作業をすると、中国経由で米国に輸出される付加価値が1割近くあるが、これは同国が天然資源に恵まれ、様々な製品に利用され得る貴金属、鉱石、鉄鋼、銅など資源を中国に輸出していることに関係していると考えられる。
このように台湾、韓国を始め、アジア諸国・地域は中国につながるGVCに組み込まれている。東アジア諸国から中国を経由して米国に輸出される付加価値のシェアを機械産業に焦点を当てて時系列で見ると、次第に拡大していることが分かる(第Ⅱ-1-2-33図)。例えば、東アジア諸国の対米付加価値輸出の最終経由国を2005年と2015年で比較して見ると、2時点とも自国から直接輸出するシェアが最も高いが、それに次いで中国のシェアが高く、そのシェアは上昇している(第Ⅱ-1-2-34図)。この10年間に中国のほか、メキシコのシェアも上昇しており、東アジアからメキシコを経由して米国に至るGVCの存在も示唆される。
第Ⅱ-1-2-33図 東アジア(日・韓・台・ASEAN)の米国向け付加価値輸出(機械産業)に占める中国経由のシェア
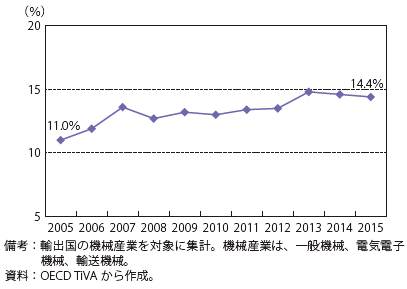
第Ⅱ-1-2-34図 東アジア(中国以外)の米国向け付加価値輸出(機械産業)の最終経由国・地域
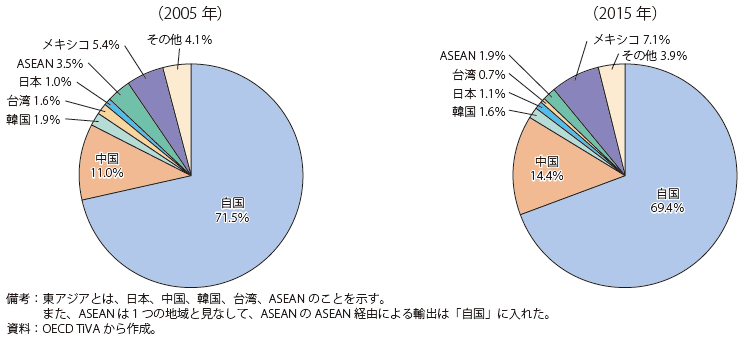
中国の米国向け輸出における付加価値の原産国・地域を見ると、中国が82%を占めるが、残りの18%については、EU、韓国、米国、ASEAN、台湾、日本がほぼ同水準で寄与している(第Ⅱ-1-2-35図)。米国の付加価値も中国経由で自国へ再輸入されている。仮に米中両国間で貿易が制限された場合は、米国を含むこれらの国が影響を受けることになる。
第Ⅱ-1-2-35図 中国の米国向け財・サービス輸出に占める各国・地域の付加価値割合(中国を除く、2015年時点)
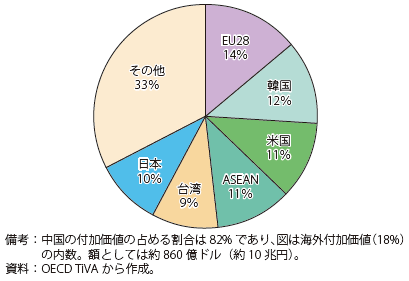
2.投資面における結びつき
貿易と同様に直接投資についても主要国と米国・中国との結びつきを見てみる。
まず、米国・中国の側から対外直接投資の動向を見る。中国は、2000年頃まで外貨準備も限られており、むしろ対内直接投資の受入によって経済振興を図ってきた。中国が対外直接投資を活発化させたのは2000年代に入ってからで、その後は急速に対外直接投資を拡大している。米国・中国の対外直接投資残高の推移を比べてみると、現状では米国が圧倒的に大きいが急速に差が縮まっている(第Ⅱ-1-2-36図)。その地域別構成を見ると、中国の場合は、アジア、ラテンアメリカが多いが、その実態は香港、バージン諸島、ケイマン諸島など金融センター向けで全体の75%を占め、これらの地域から第三国に再投資されていると思われる(第Ⅱ-1-2-37図)。米国の場合は、欧州向けが全体の59%と大きく、中南米の17%が続いている(第Ⅱ-1-2-38図、39図)。
第Ⅱ-1-2-36図 米国・中国の対外直接投資残高の推移
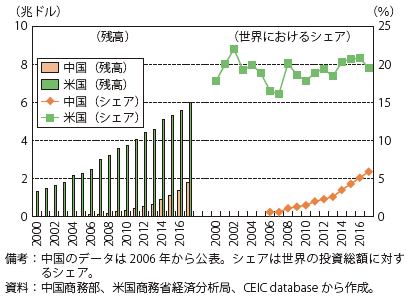
第Ⅱ-1-2-37図 中国の対外直接投資残高
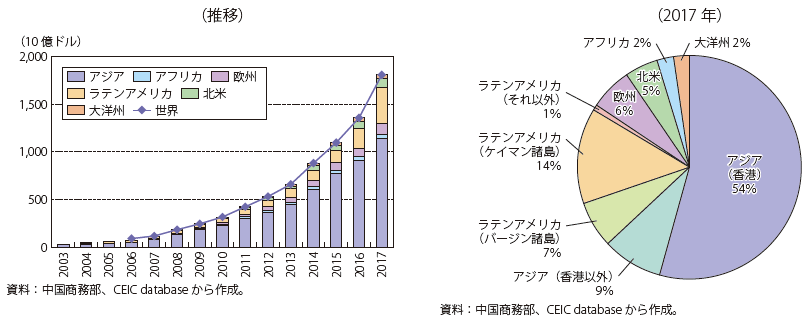
第Ⅱ-1-2-38図 米国の対外直接投資残高の推移
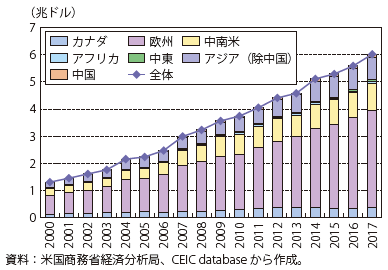
第Ⅱ-1-2-39図 米国の対外直接投資残高(2017年)
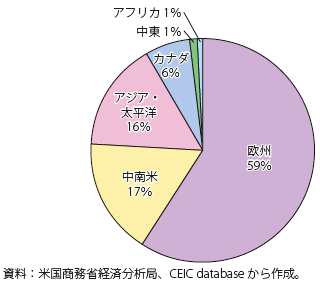
次に投資受入国の側から、対内投資残高に対する米国・中国のシェアを見てみる。アジア・太平洋地域においては中国のシェアが高く、他の地域は総じて米国のシェアの方が高い(第Ⅱ-1-2-40図)76。例えば、欧州は米国が突出して高く、中南米は中国もある程度シェアがあるものの、米国シェアの方が高い。なお、アフリカは両国ともシェアが比較的低くほぼ同程度となっている。
第Ⅱ-1-2-40図 対内直接投資残高に占める米中のシェア(地域別)
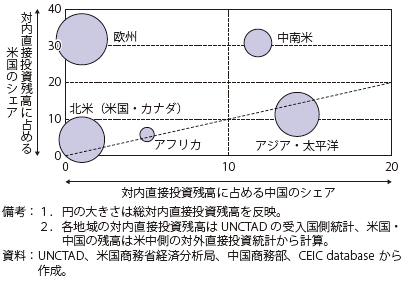
国別に見ると、主要国では米国のシェアが高いが、既に見たように中国は、香港、バージン諸島、ケイマン諸島等の金融センター向けが多いため、必ずしも実態を反映していない可能性はある。なお、ロシア、南アフリカでは米国・中国がほぼ拮抗している(第Ⅱ-1-2-41図)。
第Ⅱ-1-2-41図 対内直接投資残高に占める米中のシェア(国・地域別)
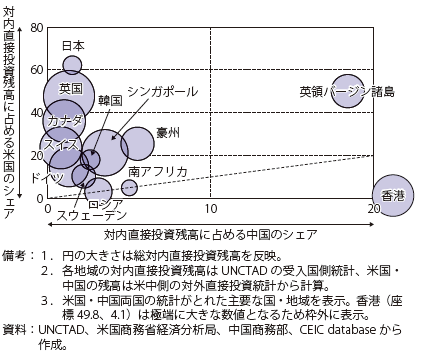
76 各地域の対内直接投資残高はUNCTADの受入国側統計、米国・中国の残高は米国・中国側の対外直接投資統計から計算。データの出典が異なるため、一部の国については、統計の整合性がとれない場合が出てくることには注意が必要。例えば、計算上、米国はオランダの残高のほぼ全額、ルクセンブルクの残高の4倍を有していることになる。このような理由から、国別シェアを表示した第Ⅱ-1-2-41図においては、オランダ、ルクセンブルクは表示から除外した。
3.中国の一帯一路と経済協力
中国は、古代のシルクロードになぞらえた「一帯一路(新シルクロード)」構想を提唱している77。この構想は沿線地域の道路、鉄道、港湾、通信等のインフラを整備し、人、モノ、資金、情報等の流れを拡大して、中国から欧州に至る広い地域の経済圏の構築を目指すもので、その対象国に明確な規定はないが、中国は各国に広く参加を呼びかけている。インフラ整備のための資金的裏付けとしては、中国輸出入銀行や開発銀行など既存金融機関のほか、シルクロード基金が創設された。また、中国はアジアにおけるインフラ投資を推進するため、アジアインフラ投資銀行の設立も主導した。
中国は、一帯一路構想を提唱する以前から、アジア、アフリカ諸国を中心にインフラ整備などのプロジェクトを経済協力として実施してきている78。その金額は次第に増加しており、対象国は金額ベースでアジアが約半分を占めるが、アフリカのシェアが拡大している(第Ⅱ-1-2-42図、43図、44図)。これらの地域で、中国の資金を利用してインフラ整備が進めば、中国との人、モノ、資金、情報の流れが活性化して経済関係の強化につながる可能性がある。ただし、一方ではプロジェクトのための借款となるため、返済能力以上の借入れによる債務問題を懸念する指摘もある。
第Ⅱ-1-2-42図 中国の経済協力(プロジェクト完成額)の推移
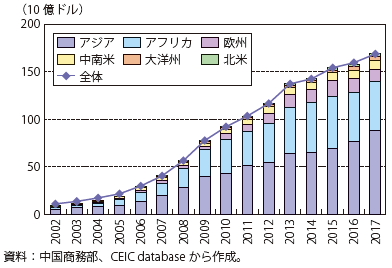
第Ⅱ-1-2-43図 中国の経済協力の地域別シェア(プロジェクト完成額 / 2017年)
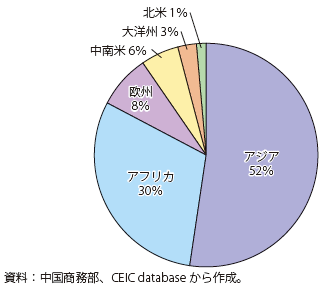
第Ⅱ-1-2-44図 中国の経済協力(プロジェクト出完成額 / 2017年)
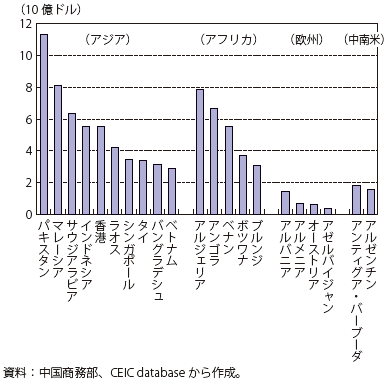
77 中国の習近平国家主席が2013年9月にカザフスタン訪問中に「新シルクロード経済ベルト」構想(陸路)を、翌10月にインドネシア国会で行った講演の中で「21世紀海上シルクロード」構想(海路)を提唱。この2つのシルクロードをあわせて「新シルクロード(一帯一路)」構想と呼んでいる。2017年5月には、北京で「一帯一路国際協力ハイレベルフォーラム」が開催され、世界100余の国と国際機関が参加した。今年2019年も5月にハイレベルフォーラムが開催された。
78 中国の「対外経済合作」は「Economic Cooperation with Foreign Countries or Regions」(中国国家統計局「中国統計年鑑」)と英訳されるが、中国はOECDに加盟しておらず、日本で考えられるODA等による開発途上国への協力とは異なる可能性はある。「対外経済合作」は「対外工事請負」と「対外労務協力」を包括する概念とされている。
4.米国と中国の関係について
ここまで、世界の主要地域の米国・中国との経済的結びつきを考察してきたが、米国と中国の直接の経済関係を考えてみる。米国は中国との貿易不均衡を問題としているが、両国の貿易・投資を見ていくと、経済的に強く結びついている様子がうかがわれる。
(1)貿易面
まず、貿易面では、中国の対米輸出額が拡大しているだけでなく、米国から見ても対中輸出額は年々拡大し、現在、中国はカナダ、メキシコに次ぐ第3位の輸出相手国となっている(第Ⅱ-1-2-45図、46表)。
第Ⅱ-1-2-45図 米国の主要相手国別の輸出の推移
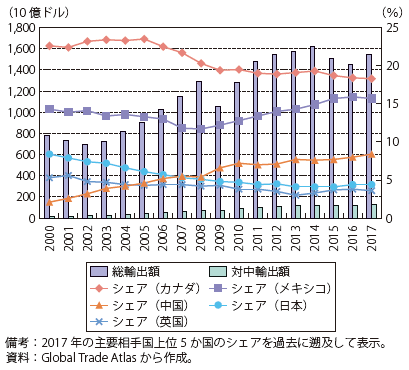
第Ⅱ-1-2-46表 米国の主要輸出先上位10か国・地域(2017)
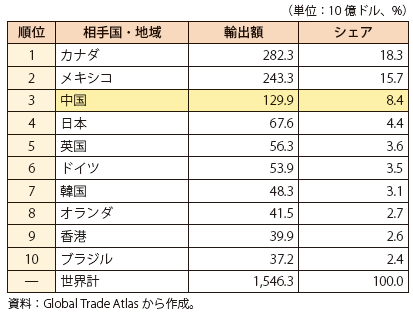
また、米中間の貿易を付加価値という観点から見ると、GVCを反映して、第三国も巻き込んで複雑に関係している。例えば、米国の中国への付加価値の輸出は直接輸出だけでなく、第三国を経由して輸出される分もある(第Ⅱ-1-2-47図)。中国が輸入する米国の付加価値は、中国国内で需要されるだけでなく、中国国内で製品に組み込まれて世界に再輸出される部分もある。そのうちの一部は米国に輸出されており、通常の貿易統計で、中国からの輸入と認識されているものの中には米国の付加価値が逆輸入されている場合がある。米国の輸出の中には中国の付加価値が一定の割合で組み込まれている。特に輸出にお互いの付加価値が含まれているという事実は、輸出のために相互に中間財を輸入しあって生産活動を行っていることを意味する。
第Ⅱ-1-2-47図 米国・中国の直接・間接の付加価値輸出(2015)
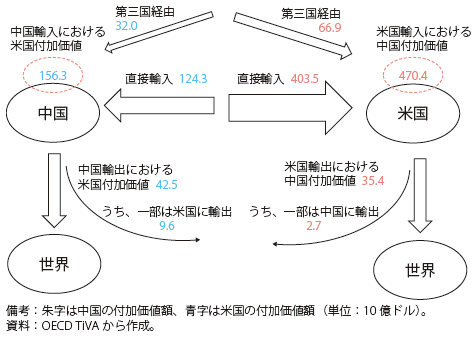
(2)投資面
米国の対中直接投資に目を向けると、中国に立地して活動する米国企業は多い。米国商務省経済分析局が公表している米国多国籍企業の統計で、世界に展開する米国系海外子会社の活動における中国の重要度を見てみる。海外子会社の立地国別売上額においては、中国はカナダに次ぐ第2位で、第3位のドイツ、第4位の英国を上回っている(第Ⅱ-1-2-48表)。米国企業にとって全海外子会社の売上額の約1割弱を中国立地子会社があげていることになる。利益額においては、アイルランド、オランダ、シンガポールなど金融センターが上位に挙げられているが、中国も上位10か国に入り、ドイツとほぼ匹敵する規模の利益を計上している。付加価値額においても中国は同様に第7位と重要な拠点となっている。このように中国は米国多国籍企業にとって重要な経済活動の舞台となっているのが現状である。
第Ⅱ-1-2-48表 米国企業の海外子会社の活動実績(2015年)
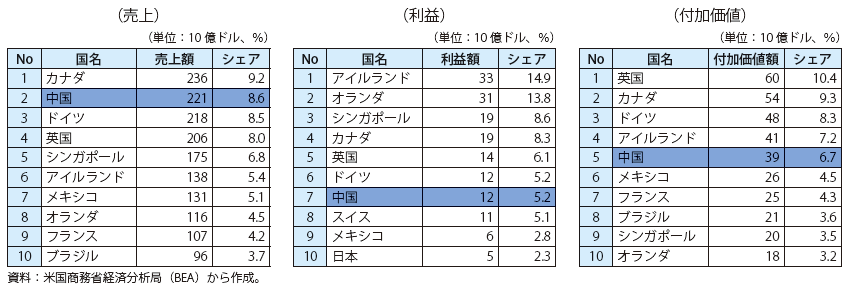
(3)その他
米国は経常収支の赤字を計上しているが、国際収支上、経常収支の赤字は金融収支でファイナンスする必要がある。米国の国際的な資金調達の重要な手段のひとつである米国債の国別保有額を見ると、中国、日本が突出して大きな残高を有し、2018年末時点で中国が最大の保有国となっている(第Ⅱ-1-2-49図)。過去からの推移を見ると、2000年代初頭は日本が第一位の保有国であったが、世界金融危機直後の2009年に逆転し現在に至っている(第Ⅱ-1-2-50図)。
第Ⅱ-1-2-49図 米国債保有残高の上位国・地域(2018年12月末)
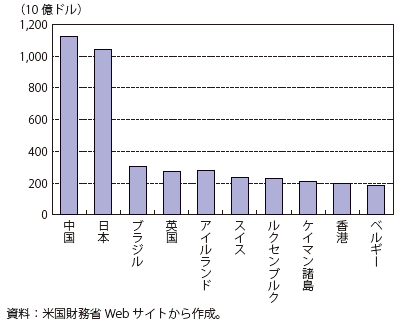
第Ⅱ-1-2-50図 日本・中国の米国債保有額の推移
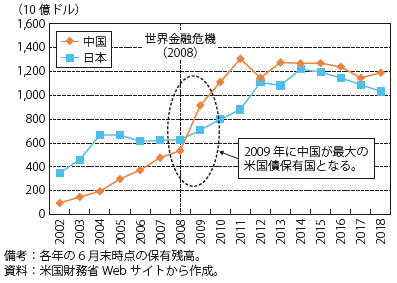
このように米国にとって中国は、貿易面では重要な輸出先であり、投資面では米国海外子会社の活動の舞台であり、金融収支面では米国債の最大の引受国となっている。
