

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第2章 第1節 保護主義の歴史とそれを乗り越え進展した自由貿易
第2章 自由貿易に迫る危機と新たな国際秩序の必要性
第1節 保護主義の歴史とそれを乗り越え進展した自由貿易
1.歴史の俯瞰
前章で論じてきたように、世界経済は自由貿易の拡大とともに大きく発展を遂げてきた。しかし、歴史を振り返ると、自由貿易は度重なる保護主義的思想・措置とのせめぎあいの中、拡大してきたといえる。ここでは、歴史的な保護主義思想や懸念の高まりと、それを受けた保護主義抑止のための国際協調の動きを俯瞰的に捉えてみたい。
その手法として、新聞報道における保護主義に関連する記事割合の長期的な推移に着目する。明確な因果関係を述べることは難しいものの、世の中の関心を反映するともいえる新聞報道における保護主義関連の記事割合の変動は、世界における保護主義的な動きと一定程度連動するものと想定できる。
第II-2-1-1図における保護主義指標①は、日・米・欧の6紙79について、1960年~2018年の期間において「保護主義」に相当する単語が記載されている記事の割合について、期間平均を100となるように指数化したものである。なお1960年代以前については、「保護主義」という言葉がまだ報道上浸透していなかったことにより、大幅に記事数は減少する。そのため1960年以前のトレンドについて観察するために、日本の主要2紙(日経新聞・読売新聞)に絞った上で、保護主義を具体的に指し示す措置80についての記事割合指数化したものが、保護主義指標②となる。
第Ⅱ-2-1-1図 新聞報道における「保護主義」に関連する記事割合の推移
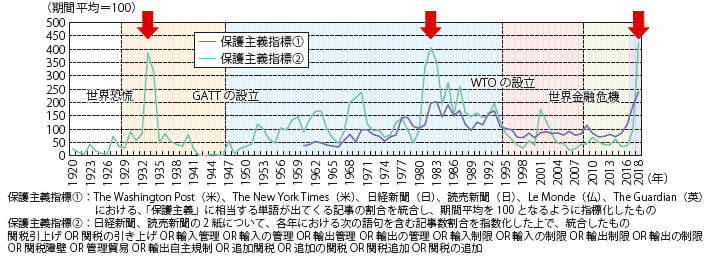
これらの2つの指標より、①世界恐慌後、②1980年代の日米間を代表とする貿易摩擦期、そして③米国トランプ政権の誕生以降の足下の2~3年において、特に保護主義思想・動きが高まったと考えられる。一方で2009年の世界金融危機時においては、世界的な景気後退によって、保護主義の高まりが懸念されたにも関わらず、関税率の観点からも新聞報道数の観点からも大きな動きは見て取れず、保護主義の蔓延は回避されたと見られる。
以上の結果及び国際的な多角的自由貿易体制の動向を踏まえ、①世界恐慌以降、②GATTの設立以降、③WTOの設立以降、④世界金融危機以降、⑤トランプ政権の成立以降、の5つの時代区分ごとに保護主義と国際協調の歴史を振り返ることとする。
79 日経新聞(日経テレコンよりデータ取得)、読売新聞(ヨミダス歴史館よりデータ取得)、The Washington Post(LexisNexisよりデータ取得)、The New York Times(The New York Times HPよりデータ取得)、Le Monde(Le Monde HPよりデータ取得)、The Guardian((The Guardian HP及びLexisNexisよりデータ取得))の6紙。英字新聞は「protectionism」、仏字新聞は「protectionnisme」、邦字新聞は「保護AND(貿易OR通商)」で検索した割合。
80 具体的には次の語句:関税引上げOR関税の引上げOR輸入管理OR輸入の管理OR輸出管理OR輸出の管理OR輸入制限OR輸入の制限OR輸出制限OR輸出の制限OR関税障壁OR管理貿易OR輸出自主規制OR追加関税OR追加の関税OR関税追加OR関税の追加。
2.保護主義と国際協調の歴史
①世界恐慌後~第二次世界大戦
1929年10月24日の「暗黒の木曜日」に起きたウォール街の株価大暴落を契機として、世界経済は連鎖的な不況に陥っていった。1930年に米国が自国農業保護のための高関税や輸入制限などを導入する「スムート・ホーレイ関税法」を成立させたことを契機とし、各国は、自国産業を守るための関税引上げ、輸入数量制限や輸入割当の導入、輸出補助金の交付による輸出促進、為替制限による輸入の抑制、金本位制からの離脱による平価の切り下げなど、あらゆる保護主義的措置を打ち出した81。こうした保護主義的措置の応酬により、世界貿易は阻害され、1932年の主要75ヵ国の総輸入は1929年の4割以下にまで減少した(第II-2-1-2図、第II-2-1-3表)。
第Ⅱ-2-1-2図 日米英独仏の貿易額推移
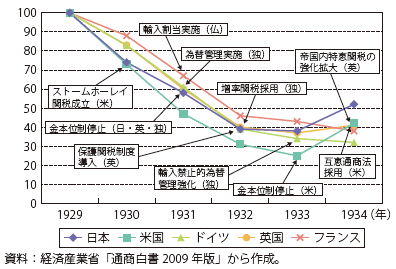
第Ⅱ-2-1-3表 1929~1932の世界貿易額の推移
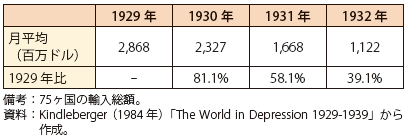
こうした中、各主要国は自国の植民地や海外領土との間では特恵関税を設定することで市場・資源を確保する一方で、圏外諸国に対しては高い関税を設ける排他的な経済圏を構築していく。共通通貨を用いた排他的な貿易体制の構築による世界的なブロック経済化である(第II-2-1-4表)。ブロック経済は、自由貿易を阻害し、不況を長期化させただけではなく、各国の経済ナショナリズムの台頭、ブロック相互間の政治的・経済的な摩擦を強め、第二次世界大戦を引き起こす一つの要因となった。
第Ⅱ-2-1-4表 列強のブロック経済化
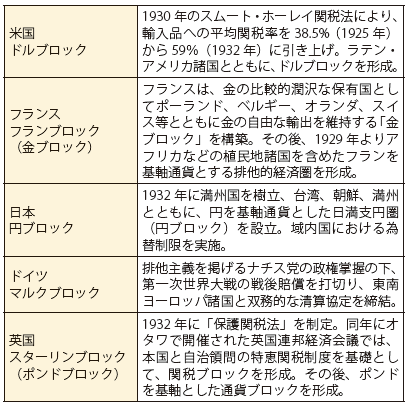
81 渡辺(2011)、p. 69。
②GATT時代(1948年~)
1930年代に蔓延した保護主義が第二次世界大戦の一因となったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し、1948年に、最恵国待遇(GATT第1条)・内国民待遇(同第3条)を大原則とするGATT(関税及び貿易に関する一般協定)が発効した。
GATT体制においては、数次の「ラウンド」と呼ばれる大規模な交渉を含む8度の多角的交渉を経て、相当程度の関税削減及び関税以外の貿易関連ルールの整備を実現した。代表的なラウンドとしては、工業品関税の大幅引下げに貢献したケネディ・ラウンド(1964-67年)、非関税障壁の軽減に功のあった東京ラウンド(1973-79年)、サービス、知的財産、投資の3つの新分野にルールの枠組みを導入したウルグアイ・ラウンド(1986-94年)が挙げられる82。特に、関税の大幅な引下げは、GATTが成しえた最大の貢献であり、1945年に40~50%であった先進国の平均関税率は3%前後にまで引下げられた83。GATT体制の下、貿易自由化が進展し、1951年、1955年にそれぞれGATTに加盟したドイツや日本は、貿易拡大を通じて驚異的な経済的発展を遂げた。
しかし、関税水準は大きく低下した一方、関税以外の貿易障壁である非関税措置が関税引下げの効果を損なうものとして増加していく。以下、代表的な事例として米国の管理貿易を取り上げる。
上述したとおり、GATT体制の下、日本やドイツなどの経済的な躍進により、世界経済における米国の優位が絶対的なものから相対的なものに変わりつつあった84。日本の対米輸出は急増し、米国は対米貿易黒字を増大(第II-2-1-5図)させる日本に対し、保護主義的な圧力を強めていった。
第Ⅱ-2-1-5図 米国の対日貿易収支
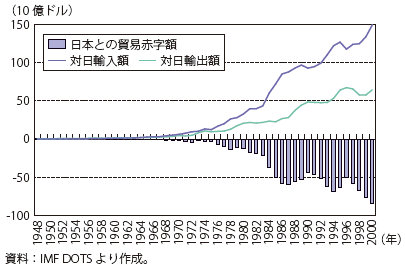
1950年代には、繊維製品を皮切りに、国際競争力を失った個別産業の求めに応じ、貿易相手国に輸入数量制限や輸出自主規制などの貿易制限的措置を要求した。1962年には、輸入増大による国内産業への影響を緩和する権限などを米国大統領に与える通商拡大法を成立させ、さらに1974年には、外国の貿易政策を不公正慣行であると一方的に認定し貿易制裁を課す権限を大統領に与える1974年通商法(301条)を成立させた85。こうした動きも背景に、1970年代には、カラーテレビ、鉄鋼、工作機械などの分野へ輸入制限措置の対象を拡大していく。さらに、1980年代には、拡大する対日貿易赤字を問題視し、半導体や自動車分野において、輸入数量制限以外に個別分野の非関税障壁、市場の構造問題是正など要求をエスカレートさせていった。このような日米摩擦を始めとする貿易摩擦の交渉に際して、特に通商法301条は、米国が相手国からの譲歩を引き出すための交渉カードとして多用された(第II-2-1-6図)。巨大な市場を抱える米国に自国市場から締め出すことをちらつかされ、日本は米国からの外圧に屈する形で、輸出自主規制(VER)の導入により対応していくこととなった(第II-2-1-7表)。
第Ⅱ-2-1-6図 米国による一方的措置(通商拡大法232条、通商法301条)に関する調査開始件数(年間)
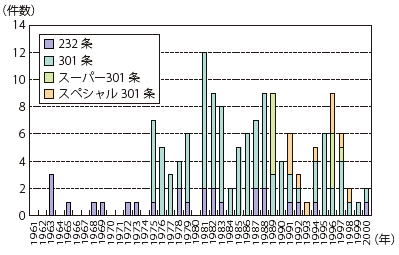
第Ⅱ-2-1-7表 日米貿易摩擦の歴史
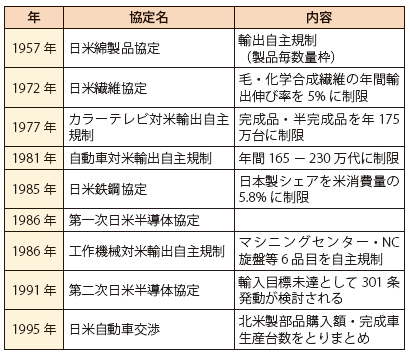
米国は、貿易赤字拡大に伴い、EC、カナダなど他国・地域とも貿易摩擦を激化させ、301条は、日本の他、EC、カナダ、韓国等も対象に発動された86。
さらに、GATT体制が目指す貿易自由化を阻害する動きの一つとして、発展途上国の保護主義の動きが挙げられる。先進諸国における急速な経済発展の結果、これら先進諸国と発展テンポの相対的に遅い発展途上国との間の格差が拡大した(南北格差)。発展途上国は、不安定な一次産品輸出に依存するところが大きく、強い競争力を有する先進諸国との間の貿易の不均衡が恒常化するに至った。こうした中、ラテン・アメリカやアジアにおける多くの発展途上国では輸入代替型工業政策が取られ、高関税や数量制限等の保護主義的措置が導入された。
以上のように、GATTは戦後の世界貿易の拡大を支える多国間自由貿易体制を確立した一方で、米国の管理貿易を始めとする保護主義的措置の高まりを回避できなかった。その一つの要因としては、GATTが貿易自由化のための国際機関(国際貿易機関、ITO)の設立を目指す過程で暫定的に締結・発効された多国間協定に過ぎず、強い規制力を持つ基盤がなかったことが挙げられる。結局、ITOは設立に至らず、GATTは50年近く、脆弱な基盤なまま戦後の国際貿易の基本的な法的枠組みを提供する役割を担うこととなった。特に、紛争処理手続における迅速性・実効性の無さが、結果的にGATTの枠外で独自に設けた一方的措置による紛争解決を図る動きにつながっていったのである87。
82 渡辺(2012)、p. 30。
83 田村(2006)、p. 13 樋口(2006)。
84 外務省(1969)、第12章参照。
85 経済産業省(2012)、p. 423。
86 日本貿易振興会(1986)、p. 55。
87 佐藤(2003)。
③WTOの設立(1995年~)
「自由・無差別・多角主義」を原則にしたGATT体制は関税水準の低下に大きな貢献をしたが、紛争解決手続を始めとする問題点も背景に、貿易摩擦や保護主義的な措置が増加し、その体制の弱さを露呈することとなった。1995年1月に発足したWTOは、こうしたGATTの問題点を改善し、発展的な多角的貿易体制を構築するための枠組みである。GATT体制の機能強化を図り、ウルグアイ・ラウンドの成果を統一的に実施する国際機関であり、物品、サービスの新しい貿易ルールや知的所有権、貿易関連投資措置といった新しい通商ルールを管理するとともに、国際紛争の解決の場として重要な役割を担う88(第II-2-1-8表)。
第Ⅱ-2-1-8表 WTOの特徴
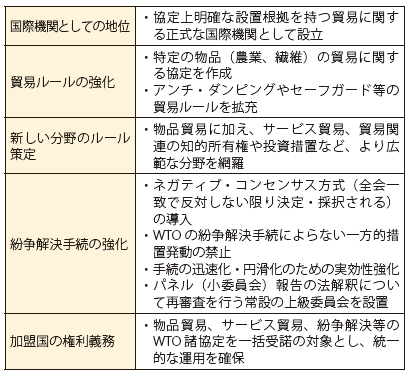
このように、GATT体制から大幅に機能強化されたWTO体制により、多国間における「自由貿易」への枠組みが強化されたといえる。GATT時代に行われた一方的措置による紛争解決も明示的に禁止され、ルールに基づく紛争解決の信頼性が高まった。実際に、WTO体制下での紛争案件数(紛争処理手続を開始するための協議要請が行われた件数)は、GATT時代と比較し、年平均で約4.2倍まで増加した(GATT下の1948~94年までの47年間で314件89、WTO下の1995~2008年までの14年間で388件90)。
この時代の貿易制限的措置の一つの特徴として、WTO協定上認められた貿易救済的措置について触れておきたい。具体的には、アンチ・ダンピング関税措置(AD)、相殺関税措置(CVD)、セーフガード措置(SG)の3つの措置をいう。不公正な貿易取引や輸入の急増などによって国内産業に生じる損害を防止・救済する貿易上の措置であり、WTO協定上認められた正当な措置である。しかし、合法的に追加関税を課したり、輸入数量を制限したりできることから、本来の目的を逸脱した保護主義的措置として濫用される懸念が常に存在する。世界金融危機以降にWTOが約半年に1回報告しているG20各国の貿易制限的措置のモニタリングレポートにおいても、2017年報告以前においては、貿易救済措置を貿易制限的措置の主要な要素として位置づけ、当該措置の濫用に警鐘を鳴らしてきた。
最も頻繁に活用されてきたのはAD措置である。WTOによれば、1995年から2008年末までの14年間に1,947件の発動実績がある。これに対し、CVD措置は111件、SG措置は89件91となっている(第II-2-1-9図)。
第Ⅱ-2-1-9図 AD措置件数推移(1995年~2008年)
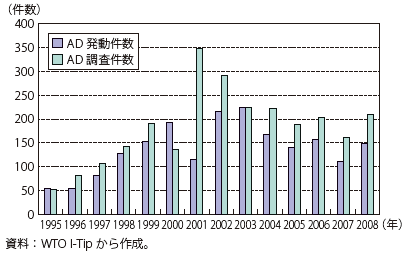
繰り返しになるが、これらの貿易救済措置はあくまでWTO協定上認められた正当な措置であり、保護主義的措置として取り扱うことには議論がある。しかし、AD措置が濫用されれば、貿易自由化の努力が無効化される懸念がある。ウルグアイ・ラウンド交渉後の時点ではAD協定に曖昧な点があったという認識を踏まえ、ドーハ・ラウンド交渉においても、日本が主導する形でAD措置の濫用を防ぐための規律強化に関する議論が進められた。
88 日本貿易振興会(1995)、p. 29。
89 経済産業省「WTOの紛争解決」(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/3_dispute_settlement/31_about/ds.html![]() )。
)。
90 WTO Integrated Trade Intelligence Portal(I-TIP)より算出。
91 WTO Integrated Trade Intelligence Portal(I-TIP)より算出。
④世界金融危機直後(2008年)~トランプ政権誕生以前
2008年9月に米国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが経営破綻したことに端を発し、連鎖的に金融不安が世界に波及し、世界規模の金融危機が発生した。危機は実体経済にも影響し、世界同時不況を引起し、各国で多数の失業者が溢れた。世界金融危機発生前後の世界貿易量の推移をみると、危機が表面化した直後には大幅に減少したものの、2009年の後半からは緩やかに回復し、2010年末には危機発生以前と同水準まで回復し、その後も拡大傾向が続いた(第II-2-1-10図)。
第Ⅱ-2-1-10図 世界金融危機前後の世界の貿易量の推移
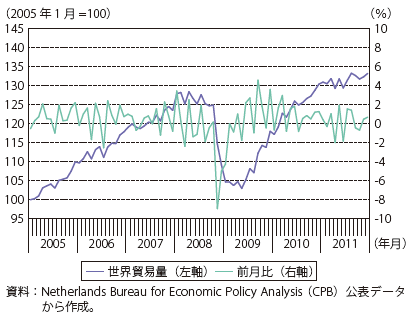
世界金融危機直後には、各国は連鎖的な同時経済不況に陥ったため、国内産業保護のために貿易制限的措置が頻発され、世界的に保護主義が蔓延することが懸念された。しかし、一部の国では自国産業支援や雇用確保を目的とした保護主義的措置を導入する傾向が高まった92が、その影響は、限定的なものに留まったと考えられる。その背景としては、多角的貿易体制を体現するWTOや、加盟国の経済規模が世界のGDPの約8割以上を占めるG2093の場を活用しながら、各国が国際協調を前提として行動した結果、保護主義の抑止が実現したことが大きいと考えられる94。以下、保護主義の抑止に寄与したと思われる、国際的な動向を取り上げたい。
リーマン・ブラザーズの経営破綻を契機に発生した経済・金融危機に対処するため、2008年11月に主要先進国・新興国の首脳が参画するフォーラムとして、従来のG20財務大臣・中央銀行総裁会議を首脳級に格上げした第1回G20サミットがワシントンDCで開催された。保護主義的措置による負の連鎖を防ぎ、世界経済の安定的な成長を図ろうと、反保護主義を共同声明でうたい、主要国が足並みをそろえて保護主義に歯止めをかける役割を果たした95。また、同年11月にリマで開催されたAPEC首脳会議でも同様のコミットメントが首脳レベルから出された(第II-2-1-11表)。これらのG20やAPECにおける保護主義抑止の政治宣言では、保護主義抑止の実効性を高めるため、WTO整合的であっても重大な保護主義的影響を及ぼす措置の最大限の自制に加えて、「スタンドスティル(現状維持)」のコミットメントにより、新たな保護主義的措置を実施しないことを約束している。加盟国は、WTO協定を順守する義務を負うが、政治合意により保護主義抑止に関し協定以上のコミットが表明されるという意義がある。
第Ⅱ-2-1-11表 G20・APEC首脳同声明
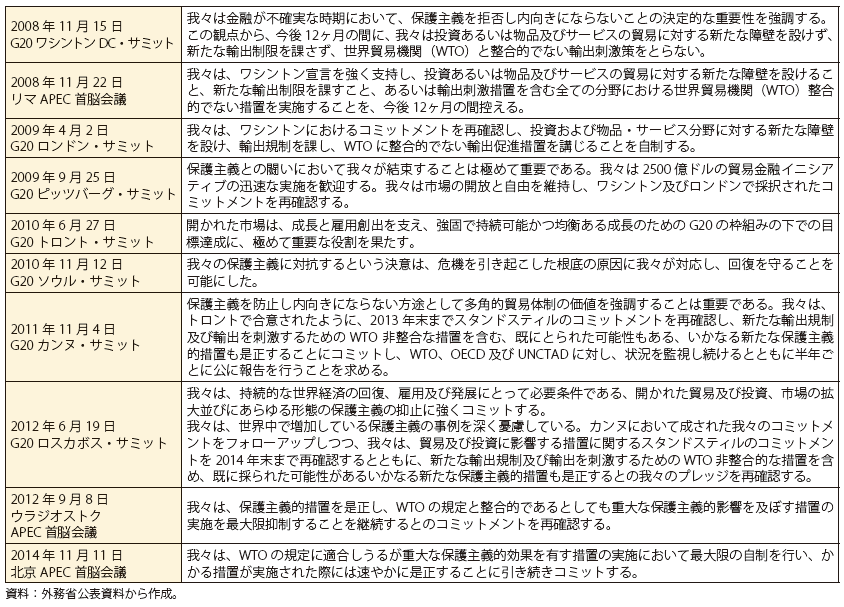
また、WTOでは、2008年末から各国の貿易措置の監視と四半期ごとの報告を行い、2009年9月以降は、WTO、UNCTAD、OECDの三機関が共同で、G20各国の貿易制限的措置の動向をモニタリングし、約半年に一回の頻度で報告書にまとめてきた。報告書の目的は措置の可視化にあり、特段、措置の是正を求めるものでも、法的な効果を持つものでもない。しかし、このプロセスは各国・地域の貿易慣行の透明性向上に寄与し、貿易制限的措置発動をチェックするWTOの「監視機能」に一定の光を当てたものと評価できる96。
以上のように、WTOによる貿易制限的措置のモニタリング強化や、G20やAPECの場における主要国の国際的に高いレベルの政治コミットメントを通じて、世界的な経済不況期においても保護主義の蔓延を回避することが可能となったと考えられる。
92 経済産業省(2009)、第2章第3節参照。
93 外務省「G20サミットに関する基礎的なQ&A」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page25_001040.html![]() )。
)。
94 経済産業省(2011)、p. 72。
95 外務省「金融・世界経済に関する首脳会談 宣言(仮訳)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_aso/fwe_08/sks.html![]() )。
)。
96 ジェトロ「地域・分析レポート「特集:世界の貿易自由化の潮流 コラム WTOが「貿易制限的措置」を再定義」」(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2017/10/3c0756aa16380baf.html![]() )。
)。
⑤トランプ政権誕生以降
世界金融危機後の保護主義の高まりはWTOなどを通じた各国の協調により抑制することができたが、近年、経済危機が生じていないにもかかわらず保護主義的な動きが高まっているといわれている97。実際に、2017年以降、G20諸国が新規に適用した貿易制限的措置件数(月平均数)は増加している。WTOが公表している「G20諸国の貿易及び投資措置に関する報告書(第20版)」によると、2018年5月16日から2018年10月15日の期間において、G20諸国が新規に適用した貿易制限的措置は40件であり、月平均では約8件であった。前回調査期間(2017年10月16日から2018年5月15日)の月平均約6件よりさらに増加した(第II-2-1-12図)。
第Ⅱ-2-1-12図 G20諸国の貿易制限的措置の月別平均件数と輸入制限的措置対象金額の推移
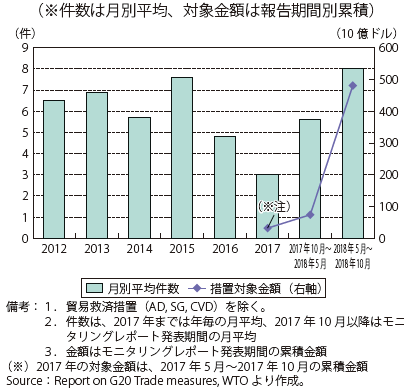
貿易制限的措置には、関税の引上げ、より厳格な通関手続及び輸出税の賦課などが含まれ、中でも輸入関税の引上げが最も多く、約6割を占めた。加えて、WTOは、G20諸国がとった輸入制限的措置の対象となる貿易額を約4,810億ドルと試算しており、前回報告の約740億ドルからおよそ6倍近くとなり、大幅に拡大した。これは、本調査が開始された2012年以降において過去最大となっており、G20諸国の商品輸入額(merchandise imports)の約3.5%、世界の商品輸入額の約2.7%であると報告している。米中が双方に追加関税を課したことや、インドネシアの輸入税率引上げ98、カナダの米国からの輸入への付加税引上げなどが影響した。他方、輸入税・輸出税の撤廃、引下げを含む貿易促進措置数は、33件と報告されている。これには、中国の自動車関税引下げやブラジルの情報通信機器の関税引下げ等が含まれている。また、輸入促進措置の対象となる貿易額は、約2,162億ドルと試算しており、対象となる主要品目は、自動車(HS87)が約40%、一般機械(HS84)、電気機器(HS85)がそれぞれ約10%と報告されている。
このように、関税引下げ措置を始めとする貿易促進措置も適用されてはいるものの、輸入促進措置の対象となる貿易額は、輸入制限的措置が及ぼす貿易額の半分にも満たない額となっている。本期間の月別の貿易促進措置を見ても、貿易制限的措置の月別件数を下回っている。足下では、貿易制限的措置のもたらす影響がより大きくなってきているといえよう。
各国の通商政策を巡る報復措置の応酬が過熱したことが、足下で貿易制限的措置件数が増加している背景にあると見られる。そういった動きの契機の一つとして世界的に注目が集まっているのが、米国発の通商政策の動きである。そこで、以下では、米国のトランプ政権が実施した主な貿易措置と各国の対応を概観していく。
97 2017年以降、G20、主要国首脳、IMF、WTO等で保護主義や貿易摩擦の緊張の高まりに懸念が示されるようになってきた。
98 インドネシア財務省は、消費財に対する輸入時の前払い所得税の税率引上げを決定した。(2018年9月財務大臣規定2018年第110号公布)インドネシアは、輸入金額に対して、品目により原則2.5%~10%の所得税の納付義務がある。今回の税率引上げは、輸入障壁を高めて消費財輸入を削減する狙いがある。背景には、インドネシアの貿易赤字削減や消費下支えにつなげ、経済ファンダメンタルを強固にしようとする政府の狙いがあると見られる。
ア.安全保障への脅威を理由にした措置(1962年通商拡大法232条)
トランプ政権は、2018年3月23日、鉄鋼やアルミニウムの輸入が米国の安全保障に重大な影響を与えるとして、1962年通商拡大法232条に基づく鉄鋼及びアルミニウムへの追加関税(それぞれ、25%と10%)の賦課を開始した。当初は、一時免除国・地域(EU、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、韓国、豪州)を除く、鉄鋼・アルミニウムの対米輸出国・地域に対する102億ドル相当(2017年度の実績)の追加関税措置であったが、さらに同年6月には、一時免除国のうち豪州99を除く6カ国・地域にも、131億ドル相当の追加関税措置と55億ドル相当の輸入割当措置を発動した。米国が措置の対象とした品目は、2017年の米国の輸入額ベースでみると、鉄鋼(HS72類~73類)全体の45.0%、アルミ(HS76類)全体の76.8%を占めている100。
この措置に対して、EU、カナダ、メキシコ、中国、ロシア、トルコの6カ国・地域が関税賦課による対抗措置101を発動している。米国及び対抗措置国6カ国の措置概要は第II-2-1-13表のとおりである。また、報復関税に加えて、WTO協定に基づく紛争解決手続きの活用も併せて行われており、EUやカナダは鉄鋼輸入に対するセーフガード措置の発動102も行っている103。
第Ⅱ-2-1-13表 米国232条措置と対抗措置の内容
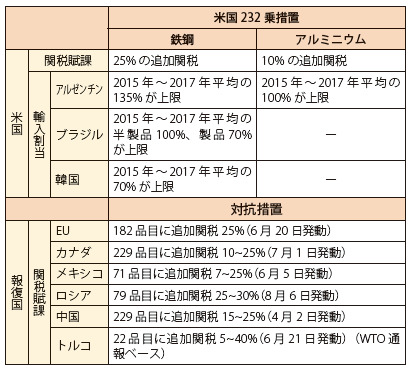
イ.通商協定の違反等を理由にした一方的措置(1974年通商法301条)
トランプ大統領は2018年3月22日、1974年通商法301条に基づく、中国に対する制裁措置を命ずる大統領覚書に署名した。これは、2017年8月からのUSTRの調査結果104において、米国企業の知的財産や技術を中国企業に移転するために中国政府が不当に介入しているとされたことを受け、対中制裁措置の発動を命じたものである。具体的には、中国からの対象品目輸入に対する追加関税の賦課、WTO紛争解決手続きを通じた中国の差別的な技術ライセンス慣行への対処、米国のエマージング技術等に対する中国の投資にかかる規制強化105の提案などが含まれる。追加関税賦課については、2018年に3回にわたって発動されており、第1弾が7月6日、第2弾が8月23日、第3弾が9月24日に発動されている。この対抗措置として、中国も米国からの輸入について米国側の措置の発動日とそれぞれ同日に、追加関税の賦課を開始している(第II-2-1-14図)。
第Ⅱ-2-1-14図 米中関税の規模
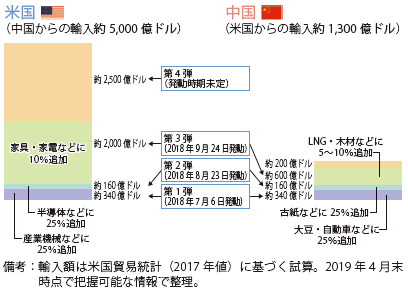
99 鉄鋼・アルミニウムともに除外国となったのは豪州のみ。
100 GTAより作成。なお、鉄鋼・アルミの合算値では53.2%に上る。
101 セーフガード協定第8条2項の「譲許その他の義務であって同理事会が否認しないものの適用を停止することができる」との解釈を巡っては、米国と貿易相手国の間で意見の相違がある。なお、我が国では、(1)WTO協定に基づいて我が国の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合、(2)ある国が、我が国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合などに、指定された貨物の課税価格と同額(従価換算税率100%)以下で割増関税を課す制度が設けられている(関税定率法(第6条))。なお、報復関税は、原則として、WTOの承認を受けて、課されることとされている。
102 EUは、米国側の措置の発動を受けて、2018年3月に鉄鋼輸入に関するセーフガード調査を開始し、7月に暫定セーフガード措置を発動、翌2月には確定措置を発動している。また、カナダも、2018年10月から鉄鋼輸入に対するセーフガード措置を発動している。なお米国は、本措置はセーフガードではないと主張し、対抗措置を行った国・地域へWTO協議要請を行っている。
103 トルコは本対抗措置以外にも、国内産業の保護や貿易赤字の縮小を目的に、追加関税措置を実施している。
104 Office of the United States Trade Representative Executive Office of the President “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation Under Section 301 of the Trade Act of 1974”(2018/3/22)(https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF![]() )、アップデート版(2018/11/20)(https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf
)、アップデート版(2018/11/20)(https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf![]() )。
)。
105 投資審査の強化については、第Ⅰ部第3章第1節米国を参照。
