

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第2章 第2節 貿易制限的措置発動の背景
第2節 貿易制限的措置発動の背景
足下において、貿易制限的措置が増加している背景としては、自由貿易への懐疑の高まり、市場歪曲的措置と疑われる政策・慣行の存在、ハイテク分野での覇権争い等が考えられる。
1.自由貿易への懐疑
現在、世界的な保護主義的思想・行動の広がりの背景として、各国において自由貿易への懐疑、とりわけ貿易によって経済格差がもたらされているのではないか、との不満・不安が高まっていることが指摘されている。
米国のシンクタンクが行ったアンケート調査によると、「貿易が自国経済にとって良いと考えるか否か」という質問に対して「良い」と考える割合が2018年時点においてほとんどの国で8割を超えている。また2010年に行われた同調査結果と比較しても、アルゼンチン・ブラジルを除き、同水準ないしは上昇しているのが分かる(第Ⅱ-2-2-1-1図)。以上のことから各国において大多数の人々が、貿易が自国経済全体にとって有益であると今もなお認識していると考えられる。
第Ⅱ-2-2-1-1図 各国において貿易が自国経済にとって良いと考えられているか否か
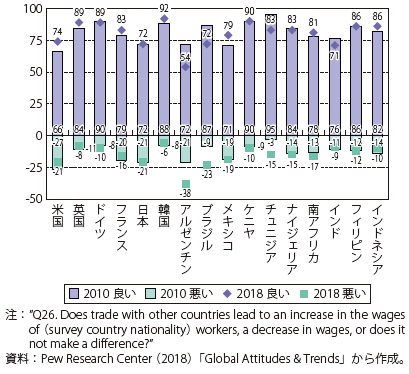
一方で、同アンケート調査における「貿易が給与を増加させると考えられているか否か」という質問に対しては、先進国においては、給与を増加させるよりも減少させると考えている人が多い傾向にある。これとは逆に、新興・途上国においては、貿易は給与を増加させると考える割合が高い。ただし、新興・途上国においても2014年と2018年を比べると、給与が増加すると回答した割合は一部の国を除いて減少又は横ばいとなっており、新興・途上国において貿易が生活を良くするとの期待が減速していることも考えられる(第Ⅱ-2-2-1-2図)。
第Ⅱ-2-2-1-2図 各国において貿易が給与を増加させると考えられているか否か
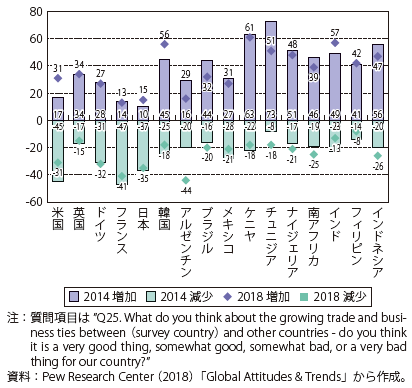
このように、先進国の人々は貿易が経済に有益であることを認めつつ、給与の増加には繋がらないと考える割合が多く、貿易に懐疑的な見方が存在しているといえる。
(1)世界の経済格差の現状
グローバル化が最も進展したといわれている1988年から世界金融危機が起こった2008年までの20年間における、世界の全人口における所得階層別の所得増加率を示した図は、その形状から「エレファントカーブ」と呼ばれている。世界銀行のエコノミストであるLaknerとMilanovicによって2013年に考案されたものであるが106、本書においては、Corlett(2016)がLankerとMilanovicの図に対して指摘されていた問題点107を修正したものを取り上げる(第Ⅱ-2-2-1-3図)。図の横軸は、世界の全人口における所得分位層を表しており、左であるほど所得が低く、右に進むほど高所得層を示す。図の縦軸は、2008年時点の該当所得分位層の所得が、1988年時点の該当所得分位層の所得と比較し、どれほど上昇したかをパーセンテージで示している。
第Ⅱ-2-2-1-3図 Corlettによるエレファントカーブ
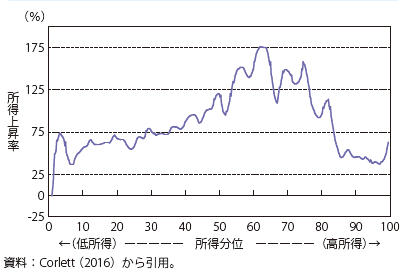
Corlett (2016)の図からは、いずれの所得分位層においても賃金は上昇しているものの、特に①新興国の中間層に該当する50%~70%の所得階層、及び、②先進国の富裕層に該当する最上位層、の2つの階層において上昇が著しく、特に新興国の中間層がグローバルな格差の縮小に貢献したことが考えられる。一方で、先進国の中間層を示す80%~90%前後の層は上昇率が相対的に低く、この間に一部の先進国においては所得の上位層と中間層の間で、格差が拡大した可能性があると考えられる。
106 Lakner and Milanovic (2013)。
107 Corlettは、LankerとMilanovicの当初のエレファントカーブの問題点として、①1988年と2008年の所得分位層を整理するにあたって異なる国をサンプルとして抽出していること、②人口増加率が国・地域によって異なること(新興・途上国の人口増加率が先進国のものに比べて高いため、全体的にカーブが押し下げられていること)、③一部の国特有の事情(日本における「失われた10年」、ソ連諸国の経済低迷)によって全体が押し下げられていること、の3点を挙げ、それによるバイアスを調整した新たなエレファントカーブを2015年に発表した。
(2)国家間格差の現状
国家間の経済格差については、1990年から一貫してジニ係数が低下傾向にあり、格差は縮小し続けている(第Ⅱ-2-2-1-4図)。
第Ⅱ-2-2-1-4図 国家間ジニ係数の推移
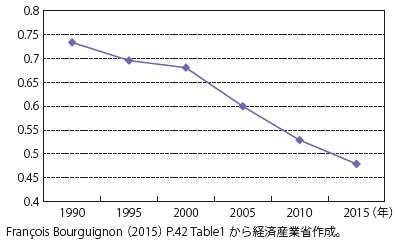
各国別の1人当たりGDPと世界人口に占める割合について、1990年と2017年の2時点間を比較すると、特にアジアNIESや中国等の世界人口の多くを占める新興国の所得上昇が著しく、前述したエレファントカーブにおける50%~70%の所得階層のピークの要因となっていると考えられる。また、新興国が著しい成長を遂げた一方で、サブサハラアフリカ、南アジアの国々は取り残されている(第Ⅱ-2-2-1-5図、第Ⅱ-2-2-1-6図)。
第Ⅱ-2-2-1-5図 世界のGDPヒストグラム(1990年)
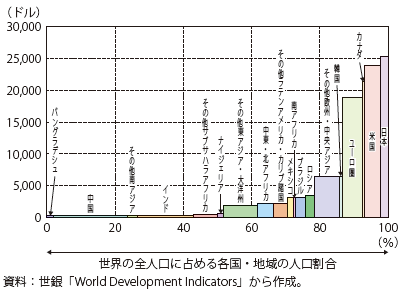
第Ⅱ-2-2-1-6図 世界のGDPヒストグラム(2017年)
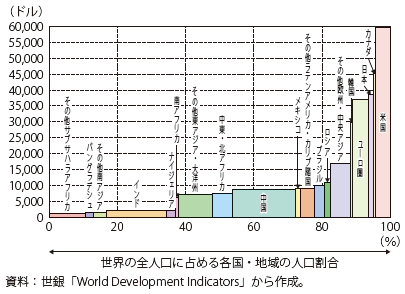
(3)国内格差の現状
各国内における経済格差においては、先進国と新興・途上国において状況が異なる。新興・途上国においては、格差が縮小している一方で、多くの先進国においては、2000年頃を境に格差が拡大傾向に転じている。例えば米国におけるジニ係数は2000年から2016年にかけて0.36から0.39まで上昇した。一方で、ジニ係数の絶対値に着目すると、先進国では直近においても0.3~0.4程度であるのに対して、新興・途上国では0.35~0.5程度であり、総論としては新興・途上国の方が未だ格差が大きいことが分かる。以下、特に先進国における格差の拡大要因について、グローバル化による影響及び技術革新による影響に着目し、分析を行う。
①貿易による労働市場への影響
貿易による労働市場への影響については、古くは1941年にStolper-Samuelsonが、貿易当事国間で貿易財の相対価格が等しくなることによって、賃金についても均等化することを理論上示した(Stolper-Samuelson定理)。その後、財の貿易開放度108を用いた分析は数多くなされたものの、あくまでも財を中心とした製造業等に限定されたものであり、サービス業も含めた一国内の労働市場全体への影響を測ることは困難であった。
Spence and Hlatshwayo(2011)は、Jensen and Kletzer(2005)によって考案された産業の貿易度を計測する手法109を用いることで、米国のサービス業も含めた国内の全業種について貿易産業・非貿易産業に分類し、1990年から2008年にかけての労働市場への影響を分析した。その結果、米国内で増加した2,730万人の雇用全体において、97.7%が医療セクターや政府セクターを中心とする非貿易産業によるものだと示した。また貿易産業においては、マネジメント・コンサルティング業、金融・保険業、システムデザイン業等の給与水準が高い産業において、雇用数が増加したものの、その増加分が主に製造業による雇用減少によって打ち消されたとしている。
同様な分析は近年にフランスにおいてもPhilippe and Giraud(2017)によって行われており、1990年から2015年にかけて、貿易産業に含まれる製造業・農業において合わせて100万人以上の雇用が失われ、貿易産業全体おいては雇用が5.8%減少したと示した。
これらの結果をもって、貿易が直接の原因となって雇用が喪失しているとの因果関係を導き出すことはできないものの、先進各国における貿易産業の雇用減少が、自由貿易への懐疑の広がりの要因になっていることが推測される(第Ⅱ-2-2-1-7図)。
第Ⅱ-2-2-1-7図 貿易産業及び非貿易産業における雇用者数の変化(仏米)
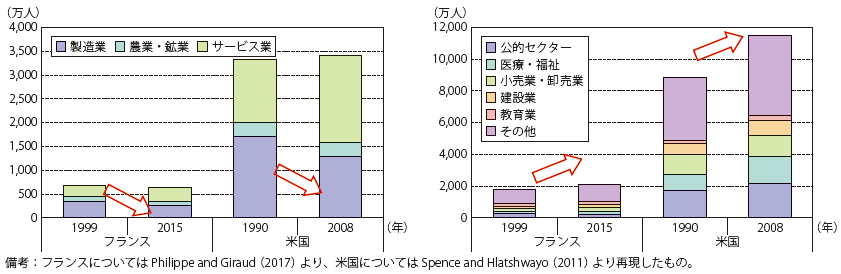
108 一般的な定義は次のとおり。貿易開放度=(輸出額+輸入額)/国内総生産。
109 JensenとKletzerは、貿易産業・非貿易産業に区分するための方法として、各産業における労働者の地域集約度に着目した。ある特定の地域に生産者が集約している産業は、集約による規模の経済や必要な原材料等の制約消費活動に至るまでの移動コストよりも、貿易統計からは観察できないサービス産業における影響を分析する手法を考案した。
②技術革新よる労働市場への影響
IMF(2007)110やOECD(2011)111による格差拡大要因分析においては、グローバル化よりも技術革新が国内格差拡大の大きな要因であると結論づけられている。通商白書においても、2017年版において、IMF(2007)の手法を用いることで、近年においても、技術革新が依然として格差拡大の主要因であることを示した112(第Ⅱ-2-2-1-8表)。
第Ⅱ-2-2-1-8表 格差拡大の要因に関する先行研究
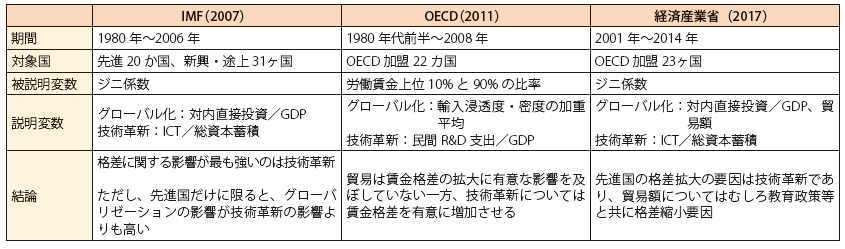
技術革新が労働市場に与える影響について、OECD(2017)113は定型業務の占める割合の多い、中技能労働者が技術によって代替されることによって、格差が拡大していると説明している。
各国の労働者の職能レベル別の雇用変化率に着目すると、先進国においては、高技能労働者・低技能労働者が増加している一方、中技能労働者については減少、ないしは微増程度にとどまっている(第Ⅱ-2-2-1-9図)。
第Ⅱ-2-2-1-9図 先進国の技能レベル別雇用変化率(1995年から2015年)
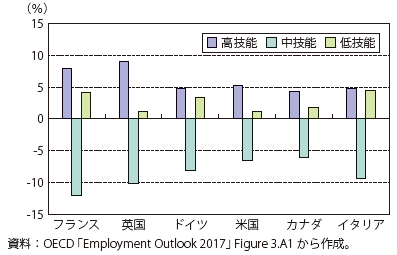
また、新興・途上国に関しても、韓国・タイ等の一部の国を除き、中技能労働者が減少、ないしは高技能・低技能労働者よりも低い増加率であることが分かり、技術による労働の代替は途上国のみならずグローバルな現象であることが分かる(第Ⅱ-2-2-1-10図)。
第Ⅱ-2-2-1-10図 新興・途上国の技能レベル別雇用変化率(2005年から2016年)
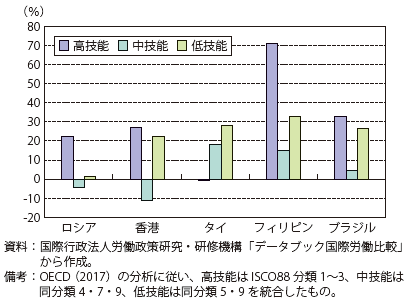
110 IMF (2007)。
111 OECD (2011)。
112 経済産業省(2017)。
113 OECD (2017)。
2.市場歪曲的措置と疑われる政策・慣行の存在
貿易制限的措置は、これまでは主に自国の産業保護を目的に用いられてきたが、近年では、相手国で行われている市場歪曲的な措置・慣行・政策の改善を行うことを目的として発せられているケースも存在する。その一例としては、足下で激化しつつある米中貿易摩擦における米国の通商法301条に基づく中国への追加関税発動措置が挙げられる。WTOに基づく多角的自由貿易体制の下では、特定国でWTO協定の規律に違反するような市場歪曲的措置が行われている場合、WTOルールに則り是正が図られていくべきものであるが、足下のケースでは、WTOの機能への懐疑の広がりなども背景となり、相手国の政策や慣行の是正を求めるために一方的な措置が使われる状況になっているものと考えられる。
ここでは、足下の米中貿易摩擦を事例として取り上げ、米国が問題視する中国の政策・慣行を一つの例として見ていきたい。米国によって、市場歪曲的であると疑われている中国の産業支援は、大きく分けて中国企業を優遇するものと、外国企業に対して様々な制限や規制を加えるものがあると考えられる。前者に関連する措置としては、補助金、優遇的融資、政府系ファンド等を介した資金供給や税制優遇などの金融支援に加えて、政府調達における中国企業の優遇114などがある。後者に関連する措置としては、技術等にかかる中国独自の基準、対内投資について業種ごとに設けられた制限区分115、投資スキームに関する制限116などで外資の参入を阻止している実態があるとされる。さらに、米国の指摘によると、強制技術移転117や海外で経験を積んだ人材の活用、先進国における産業スパイ活動による機微情報の不正な入手118により、技術水準の底上げを図っているとされている119。
114 USTRの「中国のWTO整合性にかかる報告書」において、中国の政府調達条件は自国優遇的であると批判。USTR (2018), “2018 Report to Congress On China’s WTO Compliance”, February 2018. (https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf![]() ) p. 16, 36。
) p. 16, 36。
115 「外商投資産業指導目録」においては、業種ごとに、「奨励」、「許可」、「制限」、「禁止」の分類を定めている。同目録において外商投資が「奨励」されている分野については、海外の高度な新技術を保有する投資会社や先進製造業企業を強化する投資を奨励するとともに、中国企業が生産能力や設備面、技術水準において世界レベルで優位に立てるよう、海外展開を後押しする目的の投資を奨励している。一方で、成熟した分野については、それらを制限することで、国内企業の保護を図っているとされる。例えば、自動車セクターについては、1994年~2010年にかけては「奨励」であったところ、2011年~2014年には「許可」に変更され、2015年には「制限」された。同趣旨の内容については、米中経済安全保障調査委員会(USCC)の報告書にも言及あり。USCC, “2017 Annual Report”, November 15 2017. (https://www.uscc.gov/sites/default/files/Annual_Report/Chapters/Chapter%204%2C%20Section%201%20-%20China%27s%20Pursuit%20of%20Dominance%20in%20Computing%2C%20Robotics%2C%20and%20Biotechnology.pdf![]() )
)
116 例えば、自動車セクターについて、外資進出の条件として国有企業との合弁会社を設立することを求めるなど。
117 例えば、USTRやEUは、強制技術移転問題に関して批判しており、「技術導入契約管理条例」(1985年5月公布)に見られたライセンス契約期間にかかる規定など一部の問題については、「技術輸出入管理条例」(2002年1月施行)により解決されたものの、「中外合弁経営企業法実施条例」に、引き続き従来からの問題点が残っているとしていた。但し、2019年3月18日に公布・施行された「国務院令第709条」により、当該条例の第43条(3)(契約期間)、(4)(技術の継続使用)に関する規定は削除されている。
118 海外で経験を積んだ人材の活用、先進国における産業スパイ活動による機微情報の不正な入手については、例えば前述のUSCCの報告書に言及あり。
119 USTRは、2018年3月22日に公表された「1974年通商法第301条に基づく中国の知的財産とイノベーションに関する法、政策及び慣行にかかる調査報告書」において、中国の問題点について指摘している。第一に、中国は米国企業の中国における活動について、不透明で裁量的な許認可プロセスや外資による出資規制などの各種政策ツールを通じて、制限及び干渉していること、第二に、中国の法律や政策や商慣行によって、米国企業が許認可やその他技術関連の交渉において、市場原理に沿った条件を設定できないように制限していること、第三に、中国政府が、先進技術や知的財産を保有する米国企業への中国企業による出資やM&Aを指示し、不公正な方法で促進していること、第四に、知的財産や営業秘密等に関するサイバー窃盗について言及しており、これら4つの手法を通じて、米国の技術や知的財産等を不正に入手している疑いがあるとしている。USTR (2018), “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974”, March 22 2018.
(1)金融支援の全体像
以上のように、産業支援には様々なものが挙げられるが、ここでは特に、中国の国有企業や民営企業に対する金融支援策に着目する。
「中国製造2025」の公布に関する国務院の通知120には、「金融分野の改革を深め、製造業の融資ルートを広げ、融資コストを引下げる。政策金融・開発金融・商業金融の特徴を積極的に発揮させ、次世代情報技術やハイエンド設備、新材料などの重点分野に対する支援を強化する。」とある。より具体的には、中国輸出入銀行による製造業の海外進出支援や、国家開発銀行の融資増加に加え、国内外での債券発行による資金調達のための支援や、ベンチャー・キャピタルやプライベート・エクイティによる支援など、あらゆる金融支援ツールを総動員する趣旨が記載されている。補助金、融資、政府系ファンドのそれぞれの金融支援の内容については後述するが、おおよその規模の概観を示したのが、第II-2-2-2-1図のグラフ121だ。政府補助金は、上海及び深圳証券取引所に上場されている3,703社122への補助金のうち、財務諸表上確認できる3,612社分を積み上げると2017年1年間で1,346億元(約2.2兆円)に上る。補助金の中には、財務諸表上に表れないものもあり、実態としてはさらに多額の補助金が支給されているものと思われる。また、中国製造2025の対象とも重なる戦略的振興産業への国家開発銀行の融資規模は2017年時点で3,443億元(約5.6兆円)123に上り、中国企業の産業育成策として特に近年急速に増加している政府誘導ファンドの目標規模は2017年時点で5.3兆元(約87兆円)124に上るとされる。
第Ⅱ-2-2-2-1図2017年の政府誘導ファンド、国家開発銀行による融資、政府補助金額の概観
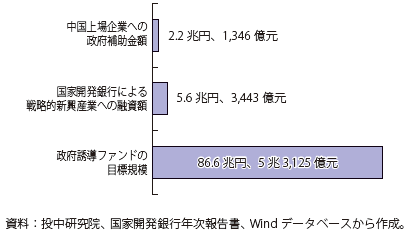
次に、それぞれの金融支援について見ていく。
120 「中国製造2025」の公布に関する国務院の通知の全訳(https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2015/FU/CN20150725.pdf![]() )。
)。
121 1元を16.3円で計算(2019年3月24日時点の為替レート)。
122 中国国内投資家のみが取引できるA株と外国人投資家も取引可能なB株をWindデータベースに基づき集計。
123 国家開発銀行の年次報告書参照。
124 投中研究院(2018)、「2018年政府引導基金特題研究報告」。
(2)補助金
中国政府はWTO整合的と主張している125ものの、中国政府による補助金(低利の融資、税制優遇、債務免除等を含む広義の補助金)を巡っては、先進国を中心とした複数の国から様々な指摘がなされている。例えば、WTOのTPRB(貿易政策検討機関)での議論においても、補助金その他の支援が市場を歪曲させ、過剰生産能力問題の原因となっているといった指摘がなされている。更に、個別の産業分野における補助金については、例えば、鉄鋼グローバルフォーラムや、半導体政府当局会合(GAMS)においても議論がなされている。
ここで、WTO協定において規律される補助金を整理しておく。WTOルール上、あらゆる場合に禁止されるレッド補助金と言われるものと、他国の国内産業に悪影響を与えた場合には撤廃等を求められるいわゆるイエロー補助金の2種類があると考えられる。前者のレッド補助金には、輸出補助金や国内産品優先使用補助金が該当する。後者のイエロー補助金には、補助金の交付対象が明示的に特定の企業・産業に限定されている場合、及び、明示的ではなくとも、事実上、補助金が特定の企業・産業に利用されていると判断される場合に該当するとされる。レッド補助金に該当するとされた場合、対抗措置として相殺関税を課すことができ、また、イエロー補助金に該当するとされた場合には、補助金による悪影響を除去するための適当な措置を講ずるか、あるいは廃止されなければならない、とされている。また、補助金の交付の形態としては、必ずしも名目上補助金と判断されない場合でも、例えば、市場金利と乖離した低利の融資や、企業債務の直接免除、出資転換126等の企業再編にかかる利益供与も補助金に該当する。
中国の政府補助金(狭義の補助金)には、大きく分けて、資産と関係する補助金と収益に関係する補助金がある。前者は、企業が工場等の建設用途のために給付される補助金であり、貸借対照表上の資産(工場等)から直接控除される性質を持つものに代表される127。収益に関係する補助金は、原価費用や損失の補償に使用することを想定して給付されるものである128。例えば、資産の購入について、政府補助金が支給されるとすれば、その分だけ安い価額を貸借対照表上に計上することが可能になるため、単に資産の購入負担を減らすことができるメリットがあるだけでなく、計上する固定資産の圧縮により、固定資産の使用に伴う減価償却費も小さくなるため、結果として、製品の製造コストが下がる効果も生じていると考えられる。一方、収益に関係する補助金は、企業のコストダウンや損失の補償に使用されることで、利益を大きく見せることが可能であると考えられる。
Windデータベースにより、中国において上場されている企業129の年次報告書に記載されている政府補助金額を分野別に集計し、「製造2025」における重点10分野の内訳を示したのが、第II-2-2-2-2図である。これによれば、政府補助金額は過去10年間で着実に増加しており、2017年時点で2009年の3.7倍に当たる1,346億元(約2.2兆円)が支給されている。このうち、「製造2025」関連補助金は2017年時点で全体の4割以上を占めており、中でも次世代情報技術産業(全体に占める割合:12.8%)、省エネルギー・新エネルギー自動車(同9.1%)、新材料(同6.1%)への支給割合が高い。
第Ⅱ-2-2-2-2図企業財務データに基づく政府補助金総額及び「製造2025」関連補助金内訳推移
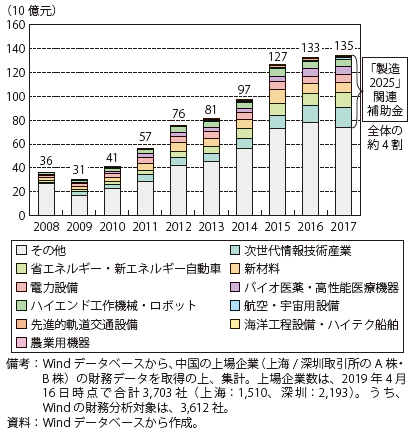
また、上場企業を業種別に分類し、「製造2025」における重点10分野企業の営業収入、営業利潤、政府補助金、短・長期借款、研究開発費、減価償却費のそれぞれについて、2009年から2017年の年平均成長率を比較したのが第II-2-2-2-3表である。政府補助金の年平均成長率は、13.5%~43.2%といずれの分野も高い水準となっている。また、全分野に共通していえるのは、研究開発費と減価償却費の伸び率が営業収入の伸び率を上回っている点である。また、分野別で特に注目すべきなのは、次世代情報技術産業、省エネルギー・新エネルギー自動車であり、営業収入以下全ての項目において、全体の成長率を上回っている。一方で、農業機器は、営業収入(▲1.7%)や営業利益(▲16.2%)の項目はいずれもマイナス成長となっているにも関わらず、補助金成長率(43.2%)が全体(21.4%)の2倍近くとなっている。
第Ⅱ-2-2-2-3表 「製造2025」重点10分野財務項目の年平均成長率(CAGR:2009年~2017年)
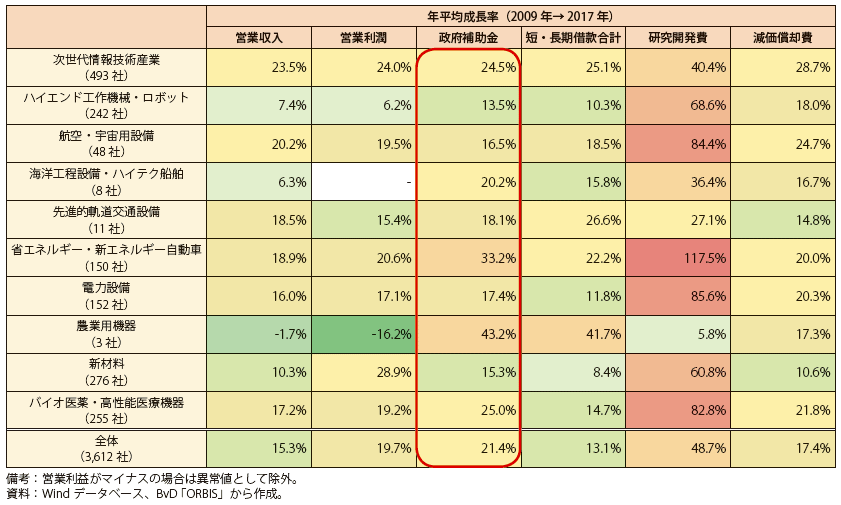
Windのデータベースから取得した中国の全上場企業130の政府補助金受取額を集計すると、補助金受取額の多い企業には、自転車(完成車)、鉄道車両、半導体等の「製造2025」の重点、10分野企業が多い(第Ⅱ-2-2-2-4表)。
第Ⅱ-2-2-2-4表 2017年の政府補助金受取額上位企業
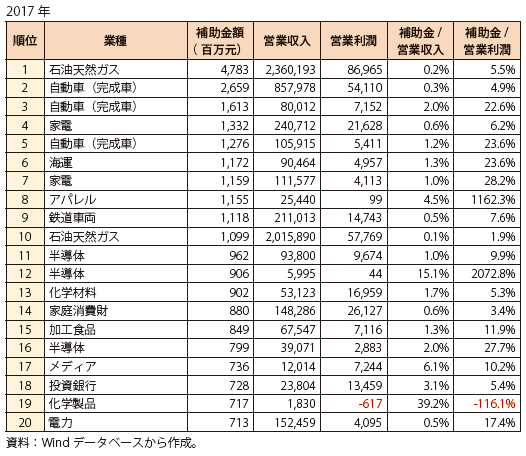
なお、中国において企業に対して交付されている補助金には、自動車セクターの新エネルギー車(NEV)補助金のような、購入補助金も含まれていることに留意する必要がある。すなわち、NEV補助金は、NEV消費を喚起するための補助金制度であり、一義的には消費者のための購入補助金としての性格を有するが、補助金の交付先は消費者ではなく、販売側の企業となっている。
125 中国国務院新聞弁公室、“The Facts and China’s Position on China-US Trade Friction”, September 2018,(https://www.scio.gov.cn/zfbps/.../201809251638289_336183.doc![]() ).
).
126 民間投資者が同様の条件では出資または出資転換しないと考える状況で債務の出資転換を行う場合。
127 資産と関係する補助金は、関係する資産の帳簿価額を相殺するかまたは繰延収益として認識する。資産と関係する政府補助金を繰延収益として認識した場合は、関係する資産の使用寿命内で合理的、系統的な方法で期間に分けて損益に計上する。当該金額で測定した政府補助金は当期損益に直接計上する。
128 収益と関係する補助金は、①企業のその後の期間の関連原価費用または損失の補償に使用する場合は繰延収益として認識し、かつ認識した関連原価費用の期間において当期損益に計上するかまたは関連原価と相殺する。②企業に既に発生した関連原価費用または損失の補償に使用する場合は、当期損益に直接計上するかまたは関連原価と相殺する。
129 上海/深圳取引所のA株・B株を集計(3,703社)。
130 上海・深圳証券取引所に上場されているA株(中国国内投資家のみが取引可能な企業)とB株(外国人投資家も取引可能な企業)について集計。
(3)融資
次に融資について見ていきたい。国家開発銀行は、「製造2025」を受け、同行の5か年計画において、「中国製造2025」の実施に対して融資を少なくとも3,000億元以上行う方針としている。同行の年次報告書によれば、2015年からの3年間で戦略的新興産業への融資規模は着実に増加し、2017年時点で融資全体の6.15%を占める3,443億元(5.6兆円)131に上っている(第II-2-2-2-5図、第II-2-2-2-6図)。
第Ⅱ-2-2-2-5図 国家開発銀行戦略的新興産業への融資推移(2015-17年)、融資セクター内訳(2017年)
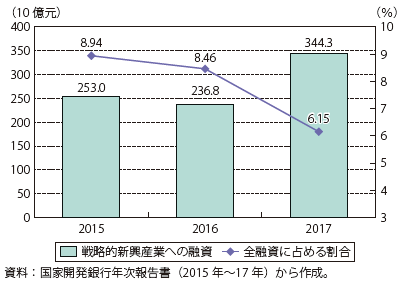
第Ⅱ-2-2-2-6図 国家開発銀行の融資セクター内訳
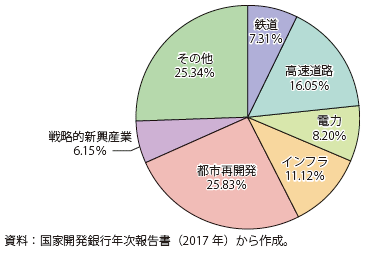
中国企業は、政策銀行である国家開発銀行だけでなく、国有の商業銀行など各種金融機関から融資を受けている。ここで、中国における融資が市場金利よりも低利で貸付がされている可能性についても注目したい。先にも述べたように、低利の融資は広義の補助金とも捉えられ、問題視されている。中国において、市場メカニズムに基づいた貸出金利での融資がなされていない可能性については、米国商務省のレポート132等においても指摘されている。現代的な金融政策が実体経済に影響するプロセスは、中央銀行が公開市場操作を通じて短期金利を調整し、それが市場メカニズムに基づいて長期金利に波及し、最終的に実体経済に影響を及ぼしていると考えられる。しかし、中国では、短期金利のボラティリティが長らく高い状況にあったため、預金・貸出金利の上限または下限に関する規制が既に撤廃133されているにも関わらず、商業銀行が貸出金利を設定する際には、中国人民銀行が公表している基準金利をベンチマーク金利としているのが実態のようだ134。
こうした中、この中国人民銀行の貸出基準金利を参照したレートを下回る低利の融資がなされている可能性が否定できないのではないかと考えている。ここでは、中国が戦略的に支援を行う産業のうち、6業種(二次電池、半導体、有機EL、鉄道車両、自動車(部品、完成車))における売上規模の大きい主要上場企業135について、実際の支払金利を試算した。これら企業の財務諸表に記載されている有利子負債に占める支払利息の割合(利払率)をグラフに表示したものが、第II-2-2-2-7図である。中国人民銀行の発表している貸出基準金利に固定マージンとして1%をプラスした利率を比較基準金利として示している。2019年2月時点の中国人民銀行の貸出基準金利は、1年以内の貸出は4.35%、1~5年で4.75%、5年以上で4.9%であるが、図7においては、過去5年間(2014年2月~2019年2月)の各貸出基準金利の最小値と最大値を抽出し、固定マージン1%を加え、それらの最小値5.4%(1年以内)と最大値7.6%(5年以上)を示している136。これを見ると、業種によって多少のばらつきはあるものの、分析対象企業の多くが、比較基準金利よりも低い結果となった。なお、これら分析対象企業の過去5年間(2013~17年)の借入金(短期・長期)の増加率を見ると、企業・業種によりばらつきはあるものの、業種別年平均増加率が38~96%となるなど、急速に借入を増加させていることが分かる(第II-2-2-2-8表)。
第Ⅱ-2-2-2-7図 対象6業種 利払率の比較
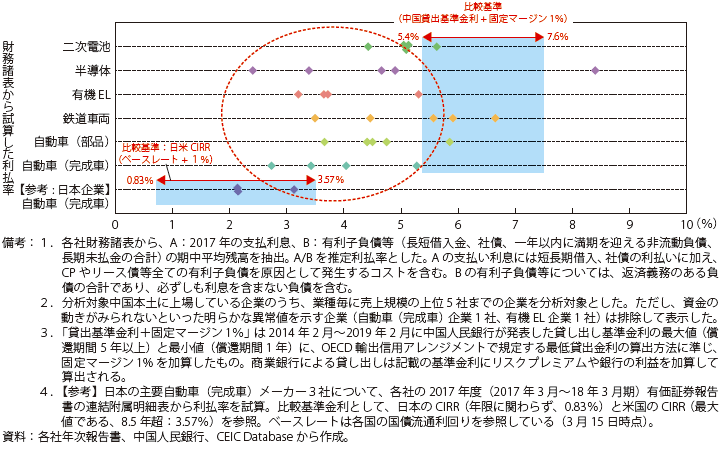
第Ⅱ-2-2-2-8表 対象6業種 借入金(短期・長期)の年平均増加率(2013~17年)
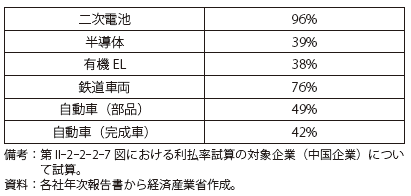
一方で、参考として日本の大手完成車メーカー3社についても、2017年度(2017年3月~18年3月期)有価証券報告書の連結附属明細表に記載の有利子負債額及び利率を元に、各負債額の規模に応じてそれぞれの利率を加重平均し、利払率を試算した。日本の自動車メーカーについては、ドル建てによる資金調達割合が多いことを勘案し、比較基準金利としてレンジの最小値を日本のCIRRである0.83%(年限に関わらず一律)、レンジの最大値を米国のCIRR(8.5年超~)である3.57%を参照している137。これによれば、日本の大手完成車メーカー3社は全て比較基準金利の範囲内に収まる結果となった。
131 国家開発銀行年次報告書参照。
132 U.S. Department of Commerce (2017), “Review of China’s Financial System Memorandum,” Docket C-570-054 (August 1, 2017), p. 8, 12-16 (noting that even though the government nominally removed the last remaining control on lending and deposit rates at the end of 2015, an analysis of interest rate dynamics suggests that interest rates are not yet market-determined) (“DOC Financial System Report”) (Exhibit USA-3).
133 2013年7月に貸出金利の下限規制が撤廃され、2015年10月に預金金利の上限規制も廃止された。
134 みずほ総合研究所調査本部アジア調査部(2017年)、「新しくなる中国の金融政策枠組み」、2017年3月29日、(https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/as170329a.pdf![]() )。
)。
135 対象企業の抽出に当たっては、「製造2025」対象業種のうち、売上高規模及び伸び率や補助金等金融支援の大きさ等を参考に業種を選定し、二次電池、半導体、有機EL、鉄道車両、自動車(部品)、自動車(完成車)の各業種において売上高規模の上位5社を対象とした。
136 一方で、中国の月刊誌である『管理世界』で掲載された企業家向けアンケート(2017年時点)によれば、企業の平均融資コストは全体で8.15%程度とされており、全体としてみれば、貸出基準金利に手数料やリスクプレミアムを加算した相応の額で貸し出されているとされる。これを、企業の属性別にみると、外資企業で6.49%、国有及び国有コントロール企業で6.9%、民営企業で8.17%となっている。
137 OECD輸出信用アレンジメント第20条に基づく最低貸出金利。日本のCIRRは年限に関わらず0.83%、EUは0.48%(~5年以内)~0.88%(8.5年超~)、米国は3.48%(~5年以内)~3.57%(8.5年超)。国際協力銀行ホームページ(2019年3月15日現在:https://www.jbic.go.jp/ja/support-menu/cirr.html)を参照。
(4)政府系ファンド
近年特に注目されているのが、中国の政府系ファンドを通じた金融支援である。中国の政府系ファンドには様々な種類があるが、シルクロード基金のように、中国政府が特定の政策目的の下、直接出資し、投資対象案件について具体的に指示する「政策ファンド」と呼ばれるものや、政府の指導の下、企業の出資者を募り、成長分野に投資する「政府誘導ファンド」など様々なファンドがある138。また、「政府誘導ファンド」と呼ばれるものの中でも、中央政府が主導して設立されたものと、地方政府主導の下設立されたもの139とで大まかに分けられると考えられる。第II-2-2-2-9表は、各種報道やレポート等から、主要な政府系ファンドを一覧化したものである。
中国企業の産業育成策として、特に注目を集めているのが、近年急速に増加している「政府誘導ファンド」である。2017年時点で1,166社のファンドがあり、その目標規模は5.3兆元(約87兆円)に上るとされる(第II-2-2-2-10図)。「政府出資産業投資基金管理暫行弁法」140に定められる「政府誘導ファンド」の投資対象分野は6つあり、①非基本的公共サービス、②インフラ、②住宅保障、③生態環境、④地域発展、⑤戦略的新興産業及び先進製造業、⑥ベンチャーイノベーションとされている。こうした分野における資金需要を満たすことが、政府誘導ファンドの重要な役割であり、特に、各地域の新興ハイテク企業の規模拡大を図ることで先端技術への研究開発投資を促進し、ひいては投資対象企業がM&Aにより外国企業から技術を獲得することも意図しているとの指摘もある141。
第Ⅱ-2-2-2-9表 中国主要政府系ファンド一覧
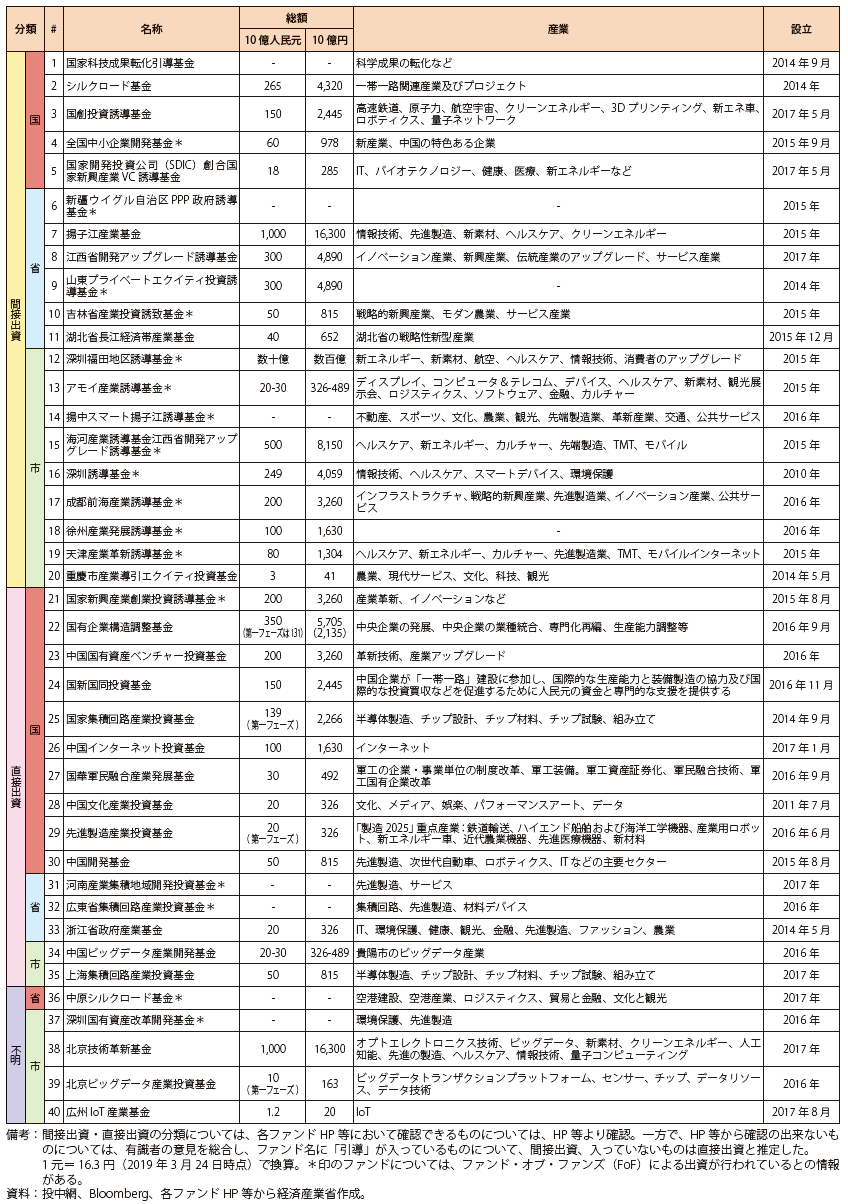
第Ⅱ-2-2-2-10図 政府誘導ファンドの目標規模推移
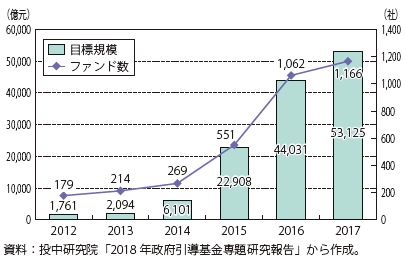
第II-2-2-2-11図は、基本的な政府誘導ファンドの仕組みを図示したものである。まず、中央または地方政府が国有資産主管部門及び国有資本を後ろ盾とした基金管理会社に対して親ファンドの設立を指示する。国有企業等は金融機関やその他の投資家と共同して管理会社を設立する。この管理会社は親ファンドに対して投資判断などの運用指図や政策指導を行う役割を有している。親ファンドは管理会社の運用指図に従って出資者から資金を集めて管理し、リミテッド・パートナー(LP)として実際に投資対象への出資や運用を行うのが一般的だ。親ファンドの出資対象は、個別企業の場合もあるが、多くの場合は特定の分野への投資を行う子ファンドへの出資としてなされる。子ファンドに対する出資比率が15~30%の政府誘導ファンドが全体の9割近くを占めているとされる142。
第Ⅱ-2-2-2-11図 政府誘導ファンドの仕組み
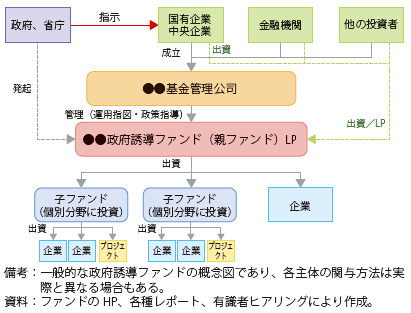
投中研究院のアンケート143では、政府誘導ファンドの属性を五つに分類している(第II-2-2-2-12図)。これによれば、複数回答で最も大きな割合を占めるのが、ベンチャー投資誘導ファンド(73.3%)であり、3位のエンジェル投資誘導ファンド(36.7%)も勘案すると、創業時や創業後間もない企業の支援を目的としたファンドが最も多いことが分かる。2位は、次世代の産業育成を主眼とした産業投資誘導ファンド(58.7%)144であり、例えば、半導体企業の支援で有名な「国家集積回路産業投資基金(通称、大基金)」、産業革新やイノベーションの支援を主眼とした「国家新興産業創業投資誘導基金」、「製造2025」に関連し、新エネ車・省エネ車等の戦略的新興産業に投資する「先進製造産業投資基金」などがある。
第Ⅱ-2-2-2-12図 政府誘導ファンドの各分類の割合(複数回答)
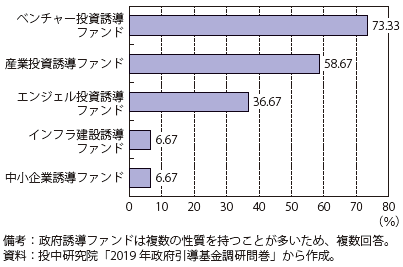
また、前述のアンケートにおいては、政府誘導ファンドの過去3年間の出資先および今後3年間の出資先の見込みについても調査を行っている(第II-2-2-2-13図)。これによれば、医療健康(93%)、TMT(テクノロジー・メディア・テレコム)(93%)、資源エネルギー(63%)、新小売業(50%)が上位の投資先となっている。政府による金融支援策という側面からは、公共性の高い分野への投資が多く、また、TMTや新小売業など、次世代産業に注力していることが分かる。
第Ⅱ-2-2-2-13図 政府誘導ファンドの出資先(複数回答)
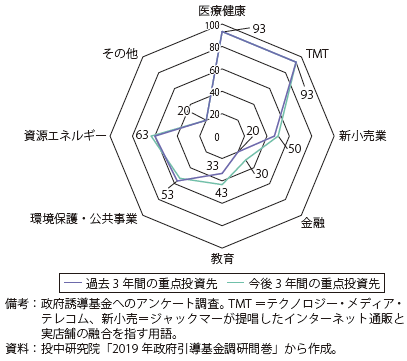
ここで、政府誘導ファンドの具体的な支援プロセスについて概観するため、前述の「国家集積回路産業投資基金(大基金)」を例にとり説明したい。大基金は、2014年に発表された政府文書「国家集積回路産業発展推進要綱」によって、中国における戦略産業である半導体産業の強化のための国家基金の設置が規定され、2014年9月に集積回路(IC)産業チェーンをサポートするために設立された。IC産業は、政府誘導ファンドの資金規模が最大の分野である。企業の資金、IC産業への投資のエコシステムをサポートすることを主眼とし、ICの設計、製造、包装、検査、機器、材料、アプリケーションの各セグメントをリードする2~3社に投資をしているとされる。投資先としては、特にチップ製造を重視しており、第一期の投資割合をみると、製造(65%)、設計(17%)、パッケージング・テスト(10%)、製造産業(4%)、材料(4%)となっている(第II-2-2-2-14図)。大基金は、投資先企業における企業ガバナンスへの関与を強めるなどの特徴もあると言われ145、集積回路という先端産業の主要企業に対し、基金を通じた政府の影響力強化が図られている可能性も示唆される。また、大基金から支援を受けた企業は、国家開発銀行等、政府系金融機関や国有銀行からも融資等の金融支援を受けて、大規模なM&Aや工場等の投資を行っているとされる。例えば、大手半導体グループの紫光集団は、2013年に企業買収によりIC産業に参入後、わずか5年程度でIC分野で10兆円規模の大型設備投資を行う企業に成長した。大基金による第一期の投資段階から多額の出資を受け取るとともに、国家開発銀行からも支援を受け、企業買収や大規模工場建設を繰り返し、短期間で設計から製造(前工程・後工程)まで幅広くカバーする半導体グループとなった。(第II-2-2-2-15図)。また、中国で最大規模かつ最先端技術を誇るIC受託製造(ファウンドリ)企業146である中芯国際も、大基金や上海などの中核都市を基盤としたファンド等からの支援を受け、1兆円近くに上る傘下企業への投資や工場設備投資を繰り返し、生産規模を急速に拡大している(第II-2-2-2-16図)。
第Ⅱ-2-2-2-14図 集積回路産業発展投資基金「第一期」のプロセス別投資割合
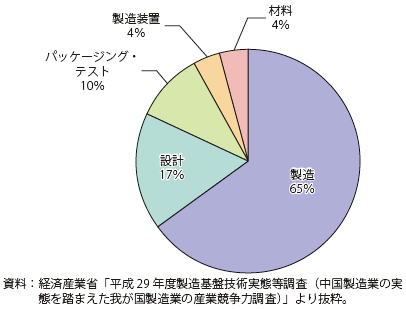
第Ⅱ-2-2-2-15図 半導体関連企業への政府金融支援(紫光集団の例)
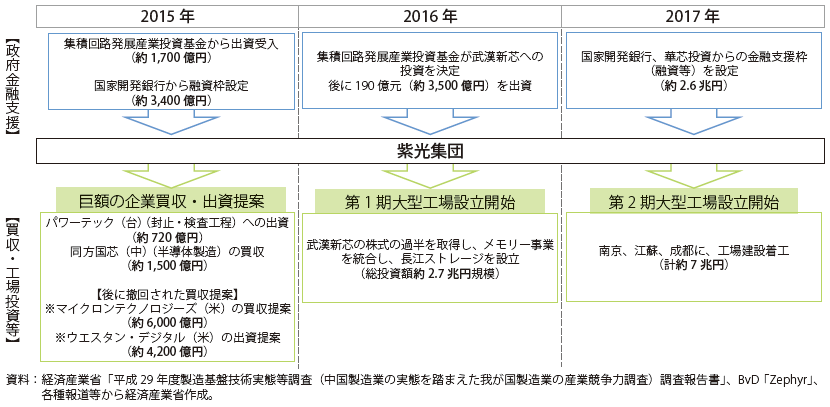
第Ⅱ-2-2-2-16図 半導体関連企業への政府金融支援(中芯国際の例)
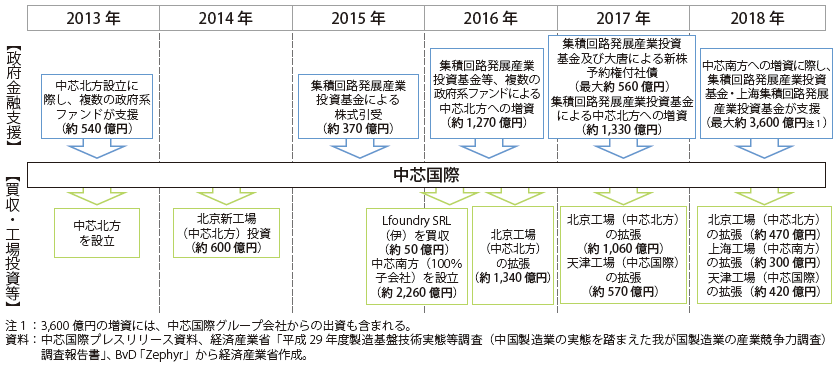
なお、日本のIC産業振興期(1970年代以降)におけるIC産業への政府支援と現在の中国政府による同産業への支援の規模を比較すると、中国政府の支援規模の方が大きいことは注目すべき点である。1970年代の日本では、当時の通商産業省が「大型コンピュータ開発で活用していた「大型技術研究開発制度」を用い、「超LSI技術研究組合」が発足した(1976~79年の4年間の国家プロジェクト)。同組合には日本政府から4年間で290億円が拠出されている147。一方で、中国政府による支援について述べれば、大基金の第1フェーズにおける資金規模だけで、1,387億元(約2.3兆円)に上り、前述のとおり、政府補助金等その他の金融支援も含めると莫大な規模である。ここで、2018年通商白書で分析したIC産業関連企業への政府補助額規模の日中比較をグラフ化して再掲したい(第II-2-2-2-17図)。足下の中国政府のIC産業関連企業への政府補助額は、対売上高で約2~4%規模148であるのに対し、日本のIC産業振興期における日本政府の企業への補助額の対売上高比率149は多く見積もっても0.7%にも満たず、中国の同産業への政府補助はかつての日本の政府支援と比較し規模が大きいといえる。
第Ⅱ-2-2-2-17図 集積回路産業振興期における財政補助の日中比較(政府補助/売上比率)
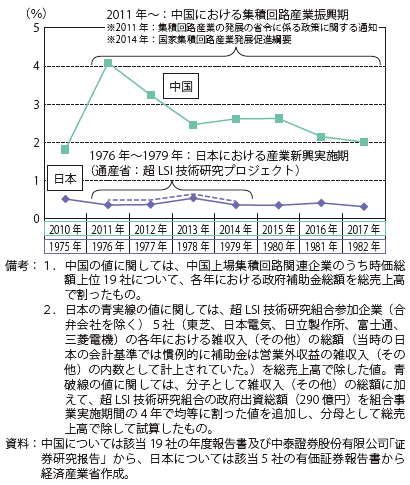
138 「政府誘導ファンド」は、ベンチャー投資等を目的としたファンドなど、政府支援を間接的なものにとどめ、企業の出資者を募る場合が多いとされているが、後述の「産業投資誘導ファンド」など、特定の産業育成を目的として政府が直接の資本支援を行う場合もあるとされる。
139 投中研究院のアンケート(「投中研究:2019政府引導基金調研報告」)によれば、ほとんどの政府誘導ファンドが、地元への投資比率を4割以上設けることが要求されているとされる。
140 創業投資企業管理暫行辦法(http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-11/15/content_99008.htm![]() )
)
141 Malkin, A. (2018). “Made in China 2025 as a Challenge in Global Trade Governance”, August 15 2018, (https://www.cigionline.org/publications/made-china-2025-challenge-global-trade-governance-analysis-and-recommendations![]() )
)
142 投中研究院(2019)、「投中研究:2019政府引導基金調研報告」。
143 同上。
144 2016年に中投顧問産業研究センターが公表した「2016年~2020年中国産業投資基金業界深度分析及び発展計画諮詢建議報告」によれば、「産業投資基金(※産業投資誘導ファンドと同義と解釈)」が政府の産業政策に基づくものであるため、直接資本支援を提供することが基本であり、一般的なVCやPE投資基金に比べて、基金の収益要求が高くなく、基金の期間が長いとされている。さらに、「産業投資基金」の特徴として、①投資対象は主に非上場企業(または上場企業の非公開株式)、②一般的に投資期限が長めであり、通常3~7年(もっと年数の長いものもある)、③投資を受けた企業のマネジメントに関与(出資規模により、会社の重大決定権を有する。企業の付加価値向上のため、財務管理や経営資源の提供、企業統治などを支援)、④投資の狙いは企業の潜在価値に基づき、投資を通じて企業発展を促進すると同時に、タイミングを図って各種の退出により資本の増値収益を確保。退出方法として、IPO、M&A、協議譲渡、買い戻しがある、とされる。
145 国家集積回路産業投資基金の丁総経理に「中国電子報」が行ったインタビュー記事(2017年10月)によれば、投資の特徴として、「基本的に各カテゴリーの業界3位までの企業に投資する」、「設計、製造、設備の中で、特にチップ製造業を重視し、全投資総額の60%を下回らない」とされ、また、投資後の行動として、「会社のガバナンスを高めるために、基金から投資先企業に董事と監事を送り込む」、「投資先企業の勧める統合再編、構造改革を進める」、「重点プロジェクトに対しては、大基金の参加度合いを強化し、戦略決定、資金使途、企業ガバナンスなどで大基金が十分関与するようにする」、「投資した企業に有利な政策措置を勝ち取る」といった特徴が挙げられている。
146 IC受託製造で世界第5位。
147 奥山幸祐(2011)、「半導体の歴史―その20 20世紀後半 超LSIへの道―超エル・エスアイ技術研究組合(1)」、SEAJ Jornal 2011. 9 No. 134を参照。
148 中国上場集積回路関連企業のうち、時価総額上位19社の年度報告書および中泰證券股份有限公司「证券研究报告」から作成。2018年通商白書P 179参照。
149 超LSI技術研究開発組合参加企業5社(合弁会社を除く)を対象に調査。該当企業の有価証券報告書損益計算書から推計。日本の会計基準において、政府補助金を記載する根拠法令はないが、慣例的に政府補助金は営業外収益の雑収入(その他)に計上されるため、政府補助/売上比率として、雑収入(その他)/売上高比率を参照した。雑収入(その他)は損益計算書の営業外収入欄を参照。超LSI技術研究組合事業実施期間の4年間(1976~79年)については、政府補助/売上比率として、同期間における政府補助総額290億円を同年数で割った値に対する5社の総売上高比率を、各社の雑収入(その他)/売上高比率に足し上げた値も併せて試算し、政府補助を最大限見積もった場合として参照している。
(5)多様な金融支援の影響
以上のように、中国では補助金、融資、ファンドと多様なツールを用いて一部の産業に対する金融支援を行っており、それらは経年で見ると増加傾向にあることが確認された。また、数字に表れない補助金や市場金利より低利での融資の可能性、政府系ファンドの出資や巨額の融資が集中する企業の存在などが確認された。
これら補助金その他の金融支援の増加により起こりうる影響として、以下の三点を指摘しておきたい。第一に、大基金の例でも見られたように、半導体や通信といった先端産業の主要企業(特に民営企業)に対し、政府金融支援を通じて政府の影響力が強化されている可能性。第二に、政府支援が呼び水となり民間からの資金調達を集中させることとなり、特定産業に大量の資金が流れ込んだ結果として過剰生産を招く可能性。そして第三に、高度な技術を持つ海外企業の買収資金となる可能性である。
3.ハイテク分野での覇権争い
(1)ハイテク技術開発の重要性の高まり
保護主義思想の高まりの一つの背景として、各国が技術開発競争でしのぎを削るハイテク分野における技術覇権争いも指摘されるところである。
人工知能、ロボット、半導体など、先端的技術分野は今後の成長が見込まれる産業であり、各国が戦略的に技術開発、産業育成に取り組んでいる。中でも、最先端技術の一つである通信分野における次世代通信規格(第5世代移動通信規格/5G)技術は、今後の社会インフラ、産業、生活、教育等の様々な分野に大きな変革をもたらし、かつ、巨大な経済効果ももたらす可能性を秘めるものとして、世界的に大きな注目を浴びている。
5Gは、第4世代と比較すると、最高通信速度が100倍という超高速・大容量、遅延時間が10分の1という超低遅延、基地局当たりの接続機器数が100倍という多数同時接続が主要な性能目標といわれており150、加えて、低コスト、低消費電力等も目指されている。技術的に大きな飛躍ともいえ、5Gは、従来の通信規格の重要な役割である無線アクセス技術の向上という意味合いだけではなく、IoT(Internet of things)やM2M(Machine to machine)等をキーワードとした情報通信技術(ICT)を活用した新規応用分野が急速に拡大する中、様々な応用分野を支える通信インフラとして中心的な役割を果たすものと捉えられている151。現在のインターネット接続デバイス数は数百億個ともいわれており、2020年にはさらに倍増すると見られている152。5Gの普及により、人工知能(AI)、自動運転、ロボット技術、遠隔治療など、様々なサービスの実用化が加速し、既存産業の在り方にも大きな変革をもたらすと考えられる。IHSマークイットの試算によると、5G技術のもたらす世界経済への経済効果はあらゆる分野に及ぶ非常に大きく持続的なものとなり、2035年までに12.3兆ドルにも達するとされる153。
一方で、その応用範囲の多様性から、5G技術の覇権を特定の国が握ることとなると、今後の様々な新規成長産業がその国の影響力のもとに置かれかねないという経済的側面に加え、5Gネットワークを介した情報漏洩やスパイ行為への悪用、自動運転などの重要な社会インフラへの攻撃など、国家安全保障面においても脅威となるとの懸念が一部の国で指摘されている。このため、5Gを巡る技術競争は、経済的観点だけではなく、安全保障の観点からも重要性が増しており、国を挙げての覇権争いの種、競争の激化を呼んでいる。
第Ⅱ-2-2-3-1図 5Gを特徴づける技術的変化
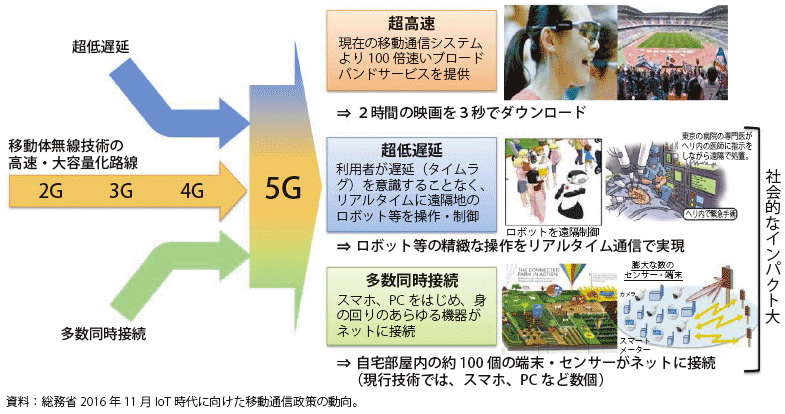
150 特許庁(2017)『平成28年度特許出願技術動向調査報告書 LET-Advanced及び5Gに向けた移動体無線通信システム』、P. 5。
151 特許庁(2017)『平成28年度特許出願技術動向調査報告書 LET-Advanced及び5Gに向けた移動体無線通信システム』、P. 4。
152 特許庁(2017)『平成28年度特許出願技術動向調査報告書 LET-Advanced及び5Gに向けた移動体無線通信システム』、P. 5。
153 HIS Economics/HIS Technology (2017), “The 5G economy: How 5G technology will contribute to the global economy”.
(2)ハイテク分野の技術開発競争
ハイテク分野の技術開発競争において、足下の特筆すべき特徴はこの分野における中国の台頭である。中国では、国務院が2015年に「中国製造2025(Made in China 2025)」を発表し、5Gを含む次世代情報技術、新材料、バイオ医薬など、10の戦略ハイテク分野で有意性のある中国国内産業の発展を加速するとしている(第II-2-2-3-2表)。そうした姿勢は技術開発費の増加においても見てとれる。各国ごとのR&D支出額の推移を見ると、中国が世界第一位の米国に近づく勢いで大きく支出額を増大させているのが分かる(第II-2-2-3-3図)。
第Ⅱ-2-2-3-2表 「中国製造2025」の重点10分野
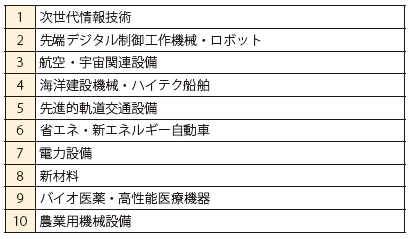
第Ⅱ-2-2-3-3図 各国の研究開発費支出額の推移
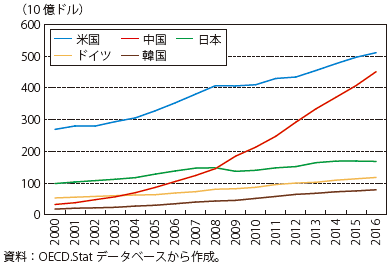
次に、主要なハイテク技術毎に、各国の技術獲得の状況を見ていきたい。
①5G関連特許
ビューロー・ヴァン・ダイク社のOrbis Intellectual Propertyデータベースを用いて5Gに関連する特許出願件数154を国別に時系列(2008年から2017年の10年間)で見てみると(第II-2-2-3-4図)、特許権者(最終親会社、以下同様)が中国企業等である特許出願件数が、特許権者が米国企業等の出願件数を大きく引き離して急増している。一方、特許の評価額155で見ると(第II-2-2-3-5図)、特許権者が中国企業等である特許の評価額は件数に比して増えてはおらず、特許権者が米国企業等である特許の評価額が第2位の日本以下を引き離して高くなっている。
第Ⅱ-2-2-3-4図 5G関連特許 国別・累積出願特許件数(上位5か国)
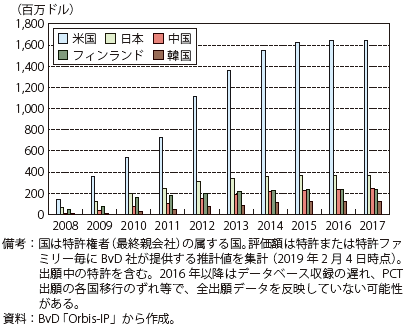
第Ⅱ-2-2-3-5図 5G関連特許 国別・累計特許評価額(上位5か国)
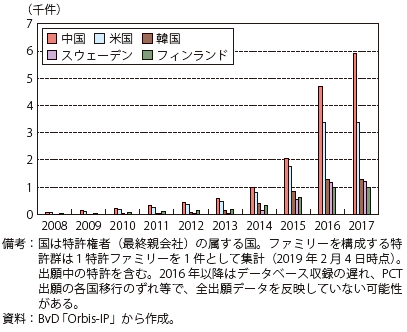
また、5Gに関連する特許の出願件数及び評価額を企業(最終親会社、以下同様)別ランキング(2019年2月4日時点)で見てみると(第II-2-2-3-6表)、特許出願件数では上位10位に中国企業等が4社、米国企業は2社のランクイン。一方、評価額では米国企業3社が上位に位置し、中国企業は5位に1社(ファーウェイ)がランクインするのみである。また、日本企業は件数では10位、評価額では9位、10位と2社がランクインしている。
第Ⅱ-2-2-3-6表 5G関連特許 出願件数・評価額上位企業
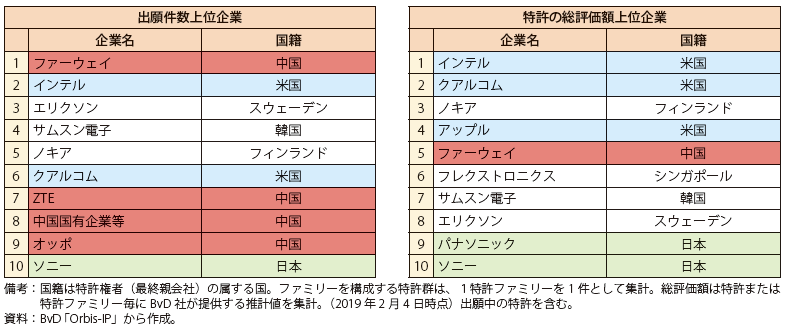
企業別に研究開発費支出を見てみると、5G関連特許の出願件数第一位のファーウェイは、過去10年間の研究開発費が3,940億人民元(約6兆8,123億円)に上り、今後も年間150~200億ドル(約1兆6,650億円~2兆2,200億円)の研究開発予算を計画していると公表している156。また、第二位、第三位であるインテル、エリクソンの2017年度の研究開発費はそれぞれ約130億ドル、約5億ドル157とされる。特許出願上位企業はいずれも巨額の研究開発費の裏付けを有するともいえ、このことからも、先に述べた中国の研究開発費支出の増大が中国のハイテク分野における存在感の増加に繋がっていることが示唆される。
一方で、これらの特許の出願件数と評価額のデータ比較からは、5Gの分野において、中国は関連特許の出願件数を大幅に増やしているものの、特許の評価としては、米国にいまだ大きな差をつけられていることが見て取れる。ただし、中国の研究開発費支出の増大に鑑み、今後特許の質の面でも存在感を増してくる可能性は否定できない。なお、特許の評価額は評価時点、評価目的、評価主体等によって大きく異なり得るものであり、本項における評価額分析はあくまで一つの参考値として捉えるべきものであることに留意が必要である。
5Gを巡る競争において、特許とは異なる側面として、通信インフラ市場の勢力図についても触れておきたい。5Gが実用化されるにあたっては、携帯基地局などの中核設備や無線接続ネットワーク等の通信インフラは必要不可欠であり、携帯通信インフラ市場の獲得も極めて重要な要素である。IHSマークイットの調査によると、2017年の携帯通信インフラ市場(2G、3G、LTE、5Gを含む)では、中国企業が全体の約4割のシェアを占め、国別では最大となっている(第II-2-2-3-7図)。
第Ⅱ-2-2-3-7図 携帯通信インフラ市場シェア(2017年)
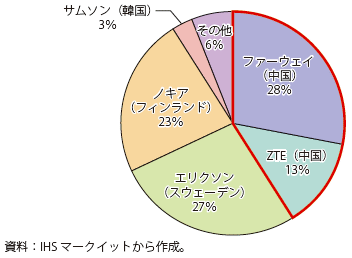
154 足下までの動きを把握するため、認可前の出願数も含む。また、特許売買やM&A等により保有するに至った特許数も含む。(Orbis IPより、次の①から④の全ての条件に該当する特許を抽出[2019年2月4日時点]。①出願年または優先年が2008年以降である。②認可済みまたは申請中である。③IPC分類がH04である。④公報に“5G”の記述を含む。)
155 特許または特許ファミリー毎にBvD社が提供する推計値(IPビジネス・インフォメーション社がマーケットアプローチにより算出した特許価値推計値)を集計。
156 Huawei Japanウェブサイト、(https://www.huawei.com/jp/about-huawei/publications/huawave/31/hw31_exploration_lights![]() )
)
157 BvD Orbisデータベースより抽出。
②リチウムイオン電池
5Gと同様に、最先端技術として各国が技術開発競争を繰り広げる技術として、リチウムイオン電池を取り上げ、国別の特許出願件数、評価額、及び企業別ランキングを以下に見てみる。リチウムイオン電池関連158では、2014年頃までは日本が特許出願件数では世界一であったが、その後中国に抜かれ、中国が大きく件数を増加させている(第II-2-2-3-8図)。一方、評価額で見ると、中国はこの分野においても件数に比して評価額は増加させておらず、いまだ日本が他国を引き離して世界一を維持している(第II-2-2-3-9図)。企業別ランキングでは、出願件数では、10位以内に中国企業等が4社入っているが、評価額では1社もランクインしていない。なお、日本企業は件数では4社だが、評価額では7社がランクインしている(第II-2-2-3-10表)。
第Ⅱ-2-2-3-8図 リチウムイオン電池関連特許 国別・累積特許出願件数(上位5か国)
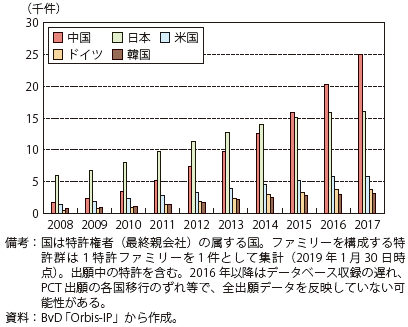
第Ⅱ-2-2-3-9図 リチウムイオン電池関連特許 国別・累積特許評価額(上位5か国)
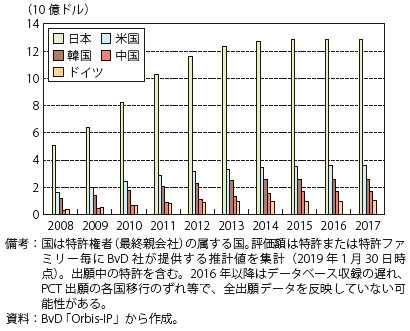
第Ⅱ-2-2-3-10表 リチウムイオン電池関連特許出願件数・評価額 上位企業
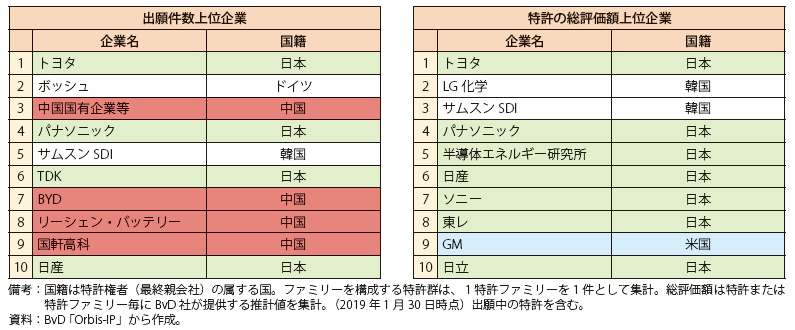
このように、リチウムイオン電池関連の特許においても、中国は出願件数では大幅に伸ばしているものの、評価額では大きくは伸ばしておらず、いまだ質の面では伸び悩んでいることが示唆される。一方、リチウムイオン電池市場において、過半のシェアを占め、かつ特に伸びが著しい車載用電池の分野で市場シェアを見ると、中国企業はリチウムイオン電池関連の特許評価額のシェアに比して車載用電池における供給量シェアが大きいといえる(第II-2-2-3-11図)。
第Ⅱ-2-2-3-11図 車載用リチウムイオン電池の市場シェア(2016年)
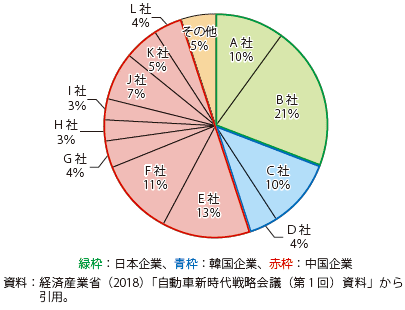
158 足下までの動きを把握するため、認可前の出願数も含む。また、特許売買やM&A等により保有するに至った特許数も含む。(Orbis IPより、次の①から④の全ての条件に該当する特許を抽出[2019年1月30日時点]。①出願年または優先年が2000年以降である。②認可済みまたは申請中である。③IPC分類がH01、H02、C01、C08、B60のいずれかである。④公報に“lithium ion battery”または“li ion battery”の記述を含む。)
③人工知能(AI)
2017年、中国国務院は「次世代AI発展計画」で、2030年までにAIの理論、技術及び応用面で世界をリードするとともに、1兆元(約16.5兆円)159規模のAI産業形成を狙うと発表。同計画によれば、2020年には1,500億元(約2.5兆円)160を超える市場規模が見込まれ、2025年にはその倍以上となる4,000億元のAI産業が目標となっている。大学や研究機関と企業、軍関係の研究連携、AI専門家や科学者の育成、既存学問とAIとの学際研究の推進を掲げる。
世界知的所有権機関(WIPO)のAIレポート161によるとAI関連特許出願件数の企業別ランキングでは、上位2社を米国企業が占め、上位10社中6社を日本企業が占める(第II-2-3-3-12表)。中国企業は上位20社まで見ても1社もランクインしていない。
第Ⅱ-2-2-3-12表 AI関連特許出願件数 上位企業
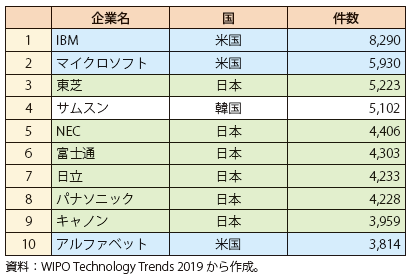
一方で、AI関連特許出願件数を大学・公的研究機関のランキングで見てみると、上位10機関中8機関を中国の機関が占め、残り2機関は韓国の機関となっている(第II-2-3-3-13表)。さらにAI関連特許出願件数において上位500出願人のうち、米国・韓国の大学・公的研究機関はそれぞれ20程度を占めるが、中国の大学・公的研究機関は100以上と圧倒的な数となっている。研究機関のAI特許出願においては中国機関の独壇場となっていることが分かる(第II-2-3-3-14図)。
第Ⅱ-2-3-3-13表 AI関連特許出願件数 上位大学・公的研究機関
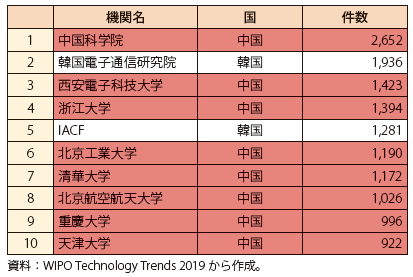
第Ⅱ-2-2-3-14図 AI関連特許出願件数上位500出願人における国・地域別の大学・公的研究機関数
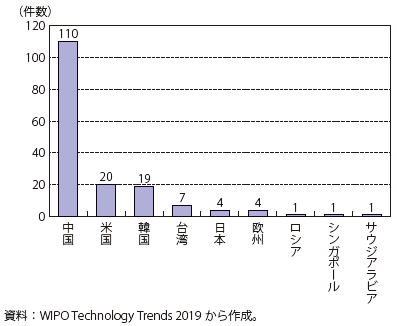
160 1元を16.5円で計算。
161 WIPO, Technology Trends 2019, “Artificial intelligence”.
(3)日米中のハイテク技術
上述のとおり、ハイテク分野の特許出願、及び、マーケットシェアにおいて中国の存在感が増してきている。その背景として、中国はハイテク産業の育成強化のための国家戦略として「中国製造2025(Made in China 2025)」を発表し、国を挙げてハイテク分野の技術獲得・産業育成に取り組んでいる。米国はこうした中国の国家戦略に対し、経済面のみならず安全保障にも関わる先端技術分野で、自国の優先的地位を脅かす試みと位置づけ、危機感を募らせている。米国国防総省は、2018年9月に出した報告書162において、中国は半導体、チップ素材、衛星等の軍民デュアルユース可能な先端基礎産業において主導的な地位を確立することに焦点を当てているとし、幅広くデュアルユース可能な人工知能、ロボット、自動運転車等の先端的基礎技術に投資を行っていると指摘している。また、同年11月に米中経済安全保障再考委員会(USCC)が出した年報レポートでは、中国政府によるイノベーションや技術に関する一連の政策が、中国がその分野で世界的な中核的地位を確立することを意図したものであり、米国の産業競争力や国家安全保障に大きな影響を与えるものであると警告を発している。
上述(2)では、5G関連、リチウムイオン電池関連、AI関連の個別ハイテク技術について特許出願状況を見てきたが、ここでは、「中国製造2025」の重点分野に沿って、日米中の出願特許件数、評価額を比較してみたい。ビューロー・ヴァン・ダイク社のデータベースを用いて2012年から2016年の5年間に日米中各国企業(最終親会社)がWIPOに出願した特許件数、及びその特許評価額をそれぞれ比較してみた163。(第II-2-2-3-15図、第II-2-2-3-16図)。これを見ると、中国製造2025の重点分野についても、中国は総じて件数では存在感を増してきているが、評価額ではいまだ日米に大きく後れを取っていることが見て取れる。また、中国は件数、評価額ともに次世代IT産業分野へ一極集中しており、特に次世代IT産業分野に注力していることが分かる。一方、日本については、米中と比較し、件数に比して評価額が高いことが分かる。また、各国の件数、評価額の伸び率を確認するため、第II-2-2-3-15図、第II-2-2-3-16図では、2007年から2011年の5年間の出願特許数、評価額に比して2012年から2016年の件数、評価額がどの程度伸びているか、倍率も表示した。いずれの分野においても、件数、評価額ともに、伸び率は中国が日米を上回っており、今後、中国が件数のみならず、評価額についても日米をさらに追い上げてくる可能性が示唆される。また、今後デジタル技術とリアルの産業の一体化がますます進むと見られる中、次世代IT産業でより強みを持ちつつある中国の台頭は、他分野にも急速に波及していく可能性もある。
第Ⅱ-2-2-3-15図 日米中企業(親会社で集計)のWIPOへの特許出願件数比較(2012年~2016年累計)
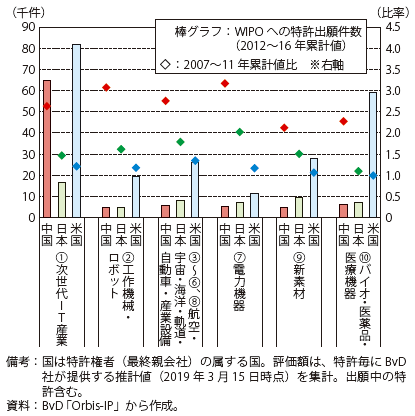
第Ⅱ-2-2-3-16図 日米中企業(親会社で集計)のWIPOへの特許評価額比較(2012年~2016年累計)
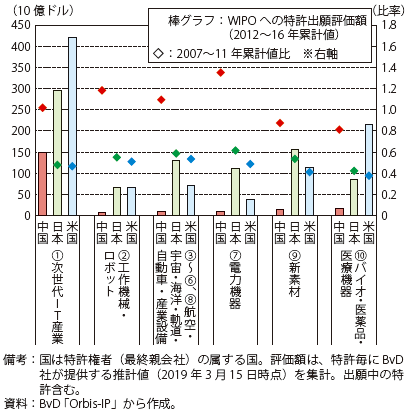
162 米国国務省(2018. 8)“Assessing and strengthening the manufacturing and defense industrial base and supply chain resiliency of the United States”.
163 Orbis IPより、次の①及び②の条件に該当する特許について、WIPO技術分類別に集計した[2019年2月4日時点]。①優先年が2008年~2017年である。②認可済または出願中である。
