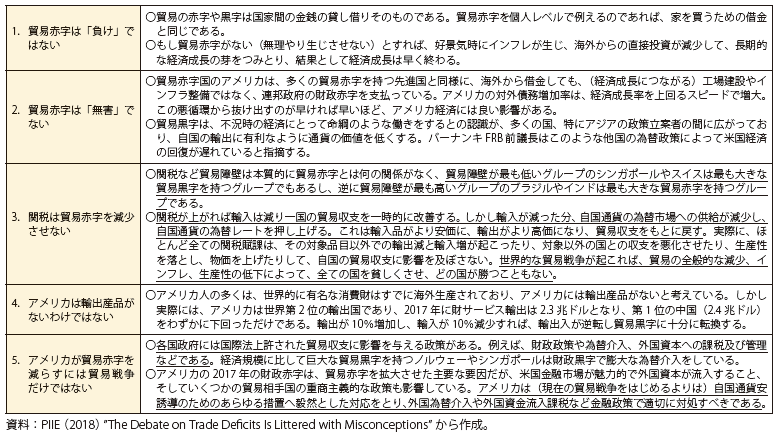- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第2章 第3節 貿易制限的措置の弊害
第3節 貿易制限的措置の弊害
前節までは、貿易制限的措置について、歴史やその背景を考察してきたが、本節においては貿易制限的措置が当事国やその他の国の経済に与える影響について考察する。すでに先に見てきたように、貿易制限的措置には様々な態様があるが、本節では特に、関税引上げが貿易赤字や世界経済にどのような影響を与えるのかについて分析を行う。
1.貿易赤字の影響についての経済学的な視点
まず、貿易収支や関税引上げの影響を経済学や先行実証研究でどのように把握・分析しているのかを確認する。
(1)貯蓄・投資(IS)バランス論
マクロ経済学の考え方では、貿易収支は貯蓄と投資のバランスで決定される。以下、詳しく見ていく(第Ⅱ-2-3-1-1図)。国内総生産(GDP)は、供給面から見ると「国内で生産されたものの儲けの合計」であり、逆に需要面から見ると「国内で支出されたものの合計」とされる。ここで、GDP (Y)を需要面で分解すれば、消費(C)と投資(I)と政府支出(G)と純輸出(輸出-輸入)(EX-IM)に分けられる(以下①の恒等式)。さらに、租税(T)を組み込んで式を変換し、民間貯蓄(国内総生産-租税-消費)(Y-T-C)と政府貯蓄(租税-政府支出)(T-G)の合計を貯蓄(S)とすると、純輸出、つまり貿易収支は、貯蓄と投資のバランスと等しくなることが分かる(以下②の恒等式)。
第Ⅱ-2-3-1-1図 国内総生産と需要項目及び貯蓄・投資バランスと純輸出の恒等式
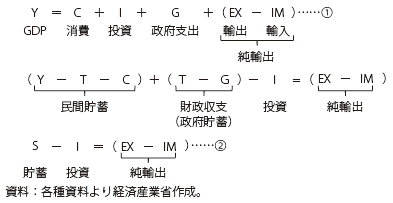
つまり、投資が貯蓄(民間・政府)を上回れば貿易収支は必然的に赤字となることとなり、貿易収支のみを切り取って一国の経済にとっての良し悪しを判断することはできないということである。この点、一般的に「赤字」という言葉の持つマイナスイメージは、必ずしも経済学的な貿易赤字に当てはめるべきではないともいえる。
なお、貯蓄・投資バランスは経常収支と誤差等を除くと一致する。日本と米国の例を見ると、米国は、政府の貯蓄投資バランス(財政収支)が大きな赤字であり、これが民間貯蓄(家計と企業の合計)を上回り、経常収支は赤字となっている。日本は、財政赤字があるが、企業貯蓄が高い水準にあるため、経常収支は黒字となっている(第Ⅱ-2-3-1-2図)。
第Ⅱ-2-3-1-2図 日本の貯蓄・投資バランス(対GDP比)の推移
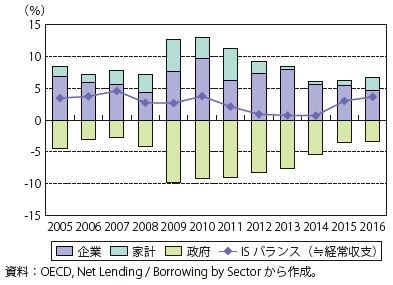
以上のように、国、家計、企業の経済主体の経済活動の結果が、経常収支を決めているともいえ、経常収支をバランスさせるために、関税引上げのみの手法では片手落ちであるといえよう。
第Ⅱ-2-3-1-3図 米国の貯蓄・投資バランス(対GDP比)の推移
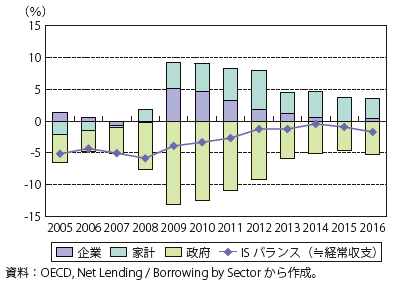
(2)自由貿易下の需給曲線と関税引上げによる社会的総余剰の減少
次に、ミクロ経済学的観点から自由貿易及び関税引上げの影響を見てみたい。
ミクロ経済学では、社会的余剰は、需要曲線と供給曲線の交わる均衡点を基に見ることができるとする。貿易を全くしていない国の国内では、均衡点は第Ⅱ-2-3-1-4図の①となる。一方、自由貿易の下では、均衡点①の均衡価格より国際価格が安価な場合、当該製品は輸入され、新たな均衡点②が生まれる。その結果、消費者はより安価な国際価格で輸入品を入手でき、消費者余剰が高くなるが、国内製品は輸入品に代替されるため国内生産者余剰は減少する。しかし、国全体の余剰の変化を見ると、消費者余剰の増加が生産者余剰の減少を上回り、自由貿易により国全体の社会総余剰(生産者、消費者、関税収入を合算したもの)は増加する。また、均衡点①の均衡価格が国際価格より高価な場合は、国内生産者は供給を増やし当該製品を輸出し、新たな均衡点②’が生まれる。この場合、生産者余剰は増加するが、国内価格の上昇に伴い消費者余剰は減少する。そしてこの場合もまた、国全体の社会総余剰は増加する。
第Ⅱ-2-3-1-4図 自由貿易下の需給曲線と関税引上げによる社会総余剰の減少
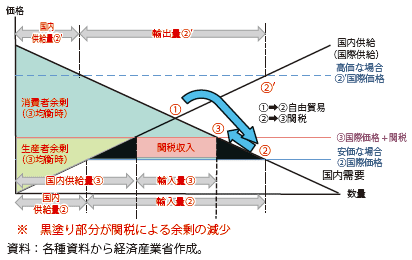
次に、輸入国が輸入関税の引上げを行った場合、輸入品の価格が上昇し、自由貿易下とは異なる新たな国内需要、国内供給、輸入量の均衡点③が決定される。新たな均衡点③では、保護された国内の生産者余剰は増加するが、消費者余剰が減少し、国全体の社会総余剰は減少する。
このように、ミクロ経済学で見た場合、自由貿易下では、輸入国、輸出国双方にとって、国全体の余剰が増加するのに比べ、関税引上げは関税発動国(輸入国)にとっても国全体の余剰を減少させることとなる。
(3)貿易による技術伝播効果
リカルドの自由貿易の比較優位論164に対して、一時的には工業化を進める過程で輸入を制限し、潜在的に成長の可能性のある産業を育てる方が良いという考え方(幼稚産業保護論)がある。このような考え方は、1960年代にUNCTADの事務総長であったラウル・プレビッシュらによって強く主張され、実際にラテンアメリカ諸国で実行された。しかし、幼稚産業保護政策による関税引上げは、貿易や対内直接投資を通じた活発な海外技術の流入を減らし、技術伝播を減少させて経済成長を鈍化させる可能性がある。そもそも貿易は、自国では得られない知識を持つ外国人と触れる機会をもたらす165。輸出者は、外国の求める品質水準や安全基準に適合するために外国の技術を学習・習得しようと努力する166。なお、幼稚産業保護策の場合は、前段の外国人に触れる機会が減り、輸出者の努力は変わらないものの、技術伝播効果が減少すると考えられる。
以下、2つの例を見る。1960年~80年代に幼稚産業保護政策をとったラテンアメリカ諸国は、低い関税率で国を開いたシンガポールや韓国と比べて、一人当たり経済成長率が低い状態にとどまったとの実証研究がある167。シンガポールや韓国など東アジアの高度経済成長の成功事例と対照的に、高い関税率によってラテンアメリカ諸国では経済が停滞したと考えられる。
また、ブラジルは1980年代に自国のパソコン産業に対して保護貿易政策をとったが、その間、ブラジルのパソコンは、国際的な技術進歩から大幅に遅れた。価格が高く性能の劣るパソコンに対して消費者からの反対の声があがり保護政策は撤回された168。このケースは、外国製パソコンをほぼ禁輸し、輸出や対内直接投資を通じた活発な外国技術の流入が減り、技術伝播が起こらなくなったケースととらえられる。
以上のように、関税引上げなど貿易保護政策を取れば、外国技術の流入を減らし、経済成長を阻害すると考えられる169。
164 リカルドは、自由貿易によって各国が比較優位のある財の生産に特化して輸出し、そうでない財を輸入することで、規模の経済が働きより効率的な生産ができるだけでなく、消費者はより価格の安い財を入手できる等と主張した。
165 第Ⅱ部第1章第1節第3項の知のグローバル化(2)新興国への技術波及において、貿易や外国直接投資による技術伝播が新興国の経済発展にもたらした影響をより詳細に述べている。
166 戸堂康之(2015)。
167 戸堂康之(2015)は、1960年代に高い関税率であったチリ(工業製品に対する実効保護率217%)は、1960-80年代の一人当たりの成長率において1.69%に留まった。逆に、低い関税率であったシンガポール(同0%)や韓国(同▲17%)では、同期間に一人当たり成長率においてシンガポールは6.58%、韓国は7.19%を達成した。
168 戸堂康之(2015)は、Luzio and Greenstain(1995)を引用し、ブラジルとアメリカのパソコン価格の推移を比較してブラジル製パソコンが国際競争力を持つことがなかったとした。
169 戸堂康之(2015)は、理論的には貿易保護政策が経済成長を促す場合があることを否定できないが、自由貿易がより経済成長を促すことが研究でかなり実証されており、特に第2次世界大戦後のデータでは、技術伝播の影響が大きくなったため、その傾向が顕著であるとしている。
(4)実証分析(米国国際貿易委員会(2017年)等)
関税引上げが貿易収支にどのような影響を与えるのかについては、これまでもいくつもの実証分析や経済モデル分析が試みられている。Ostry等170は1992年に関税引上げが米国の貿易赤字を縮小するのではないかとの議論に対して、米国の貿易データを用いて統計的な有意な影響の有無を分析した。米国と主要貿易相手国の過去約20年分の貿易額等5つのデータセットを作成し、関税が貿易収支に与える影響が統計上有意ではなかったと示した。しかしUNCTAD171は1999年に、さらにSantos-Paulino等172は2004年に、発展途上国のデータを用いて貿易自由化が貿易収支を悪化させるとの分析結果を発表した。これらの先行研究に対してIMFは2008年173に、先行調査よりもより長期間かつ多くの発展途上国のデータを用いて、貿易自由化が輸出入を増加させることは確かだが、経常収支を悪化させるかどうかは手法によって結果が異なり、頑強なエビデンスは得られなかったとしている。このように、実証分析の分野においては結果が一概にはいえず、関税が貿易収支に影響を及ぼすというコンセンサスは得られていない(第Ⅱ-2-3-1-5表)。
第Ⅱ-2-3-1-5表 関税引上げの影響に関する先行研究
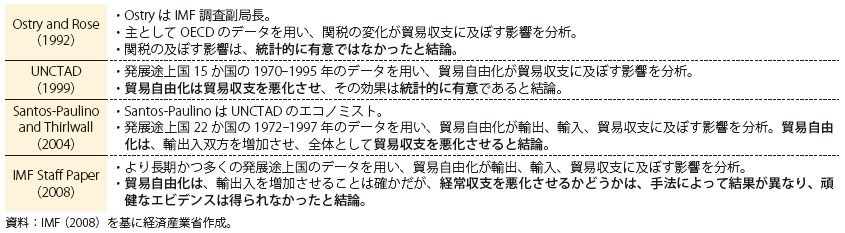
ここで、米国国際貿易委員会(USITC)が、トランプ政権が誕生後の2017年10月に公表したモデル分析174を紹介する。モデルには、米国が10%の追加関税をした場合の長期均衡分析と30年間経過分析があり、それぞれ対象国は中国のみのケースと全世界のケースがある。
まず中国を対象とした長期均衡分析(第Ⅱ-2-3-1-6表)では、米国の課税賦課が、米国の対中国輸入を減少させ、これが米中及びその他世界(以下ROWという。)の生産者物価へ波及する。特に中国の生産者物価が大きく減少(▲1.4%下落)し、中国輸出産品の国際競争力を相対的に高め、逆に割高になった米国輸出産品、ROW輸出産品が中国市場への輸入量を減少させる。また、ROWは米国市場で増加するが中国市場で相対的に競争力を失い減少し、ネットで輸出が減少する。結果として、関税賦課によって、全ての国で輸出入ともマイナスになり、収支は米国のみマイナスとの結果となった。
第Ⅱ-2-3-1-6表 米国が中国に対して10%関税を引上げた場合のモデル分析
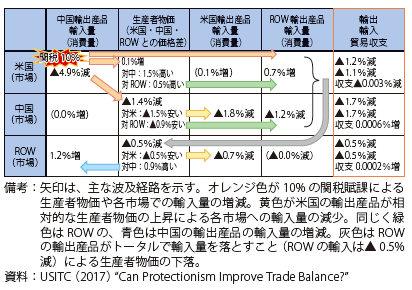
次に対世界の30年間にわたる経過分析を見る。初期に貿易収支は一時的に改善するが、発動後13年以降には▲0.02%程度の押し下げ効果が継続するとの結論となった。また、初期の最も改善が見込まれる時期であっても対GDP比は0.05%程度の改善効果しかなく、米国の貿易赤字は2018年に対名目GDP比で▲4.3%175であり、黒字化にはほど遠いことが分かる。なお、対中国の場合は、全輸入品を対象とした場合の約10分の1程度の影響しかないが、▲0.003%程度の押し下げ効果が継続する結果となった。
170 Jonathan D. Ostry and Andrew K. Rose (1992).
171 UNCTAD (1999).
172 Amelia Santos-Paulino and A.P. Thirlwall (2004).
173 IMF (2008).
174 USITC (2017).
175 米国の2018年貿易赤字の▲8,790億ドルを名目GDP(推計値)205,130億ドルで割り戻した値。
(5)国際機関による関税引上げの影響分析
IMF、OECD、世界銀行などいくつかの国際機関は、2018年の貿易摩擦が世界経済に与える影響試算を発表176している。いずれの分析も関税発動国や被発動国に限らず、他の国々や世界経済に少なからず悪影響を与えるとの分析結果となっている。ここでは、それらの分析のうち、より詳細なシナリオ分析を行っているIMFの分析(2018年10月公表)177を取り上げる(第Ⅱ-2-3-1-7表)。レポート発表時点で米国が発動及び検討する全ての追加関税が賦課され、対象国も報復措置を行うとの前提で、企業活動やマーケットの反応を織り込んで、世界経済に与える影響を試算している。関税発動国、被発動国に関わらず、全ての国、世界経済にとってもマイナスの影響が出るとの結果となっており、先にみた経済学理論やコラム7と同様、関税の掛け合い、貿易戦争ではどこの国も勝つことがないことを端的に示している。
第Ⅱ-2-3-1-7表 IMF 「貿易摩擦の影響シナリオ分析」(2017年からのかい離)(2018年10月9日)
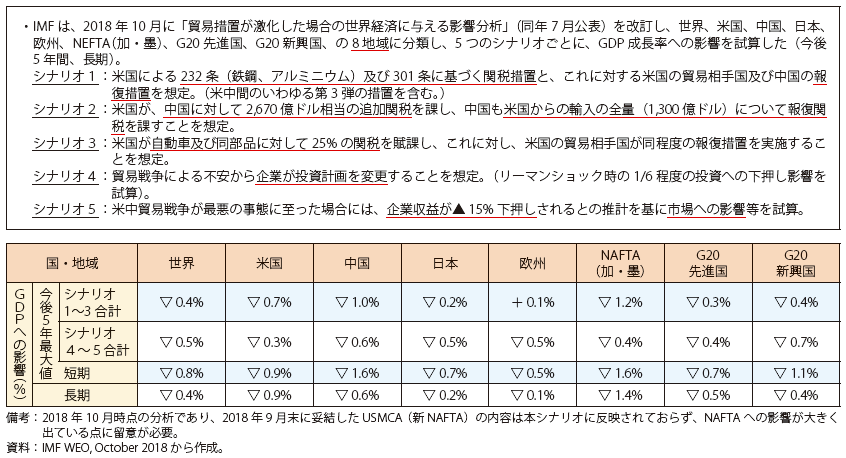
176 本文で述べるIMFの他には、例えば、OECDが2018年11月に影響試算を公表した。米中双方が全ての輸入品に25%の追加関税を発動し、企業の投資計画に悪影響を及ぼすと仮定し、最大で米国に▲1.1ポイント、中国に▲1.3ポイント、世界に▲0.8ポイントの下押し圧力がかかるとした。
177 IMF WEO, October 2018.
(6)まとめ
以上、本項で見てきたように、経済学的には貿易収支のみを取り上げ、良し悪しを論じることには意味がない。また、ミクロ経済学では、関税引上げは一部の生産者には余剰増加につながるものの、消費者余剰を減少させ、国全体の社会的総余剰を減少させることを確認した。また、貿易のもたらす技術伝播効果を考慮すれば、関税引上げなど貿易制限的措置を取れば、外国からの技術伝播を減らし、経済成長を阻害する可能性が高いことを示した。さらに、実証分析においては、関税引上げの貿易収支への影響は一概にはいえないものの、関税引上げが発動国にも結果的に悪影響を及ぼし、ひとたび世界を巻き込んだ貿易戦争に発展すれば、世界全体に悪影響が及び、「どの国も勝つことがない」負の連鎖となることを確認した。
2.貿易制限的措置の影響(ケーススタディ分析)
本項179では、過去に発動された関税引上げ措置について、貿易、物価、雇用、当事国の経済への影響、世界への波及効果についてケーススタディ分析を試みる。関税引上げ措置の影響を分析するために、対象事例は、WTO上級委員会で敗訴又は我が国の不公正貿易報告書において不公正な措置として掲載された事例を扱うこととする。具体的には2002年の米国鉄鋼SG措置、米国太陽電池セル・モジュールへの2012年及び2015年のAD措置・CVD措置並びに2018年のSG措置の2ケースとする。
179 本項は、経済産業省が実施した委託調査「平成30年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(事業環境・市場動向等の調査(AD等の貿易制限的措置が世界経済に与える影響に関する調査))」を基に再構成したものである。なお資料は原出典を表示する。
(1)2002年 米国鉄鋼セーフガード(SG)措置
①措置概要
米ブッシュ政権は誕生して間もない2001年6月に、構造的不況に苦しむ米国鉄鋼産業に対する包括的な救済策を求める声の高まりを受けて、「鉄鋼に係る多国間イニシアティブ」180を発表して鉄鋼SG措置の調査に入った。その後、世界で過剰に生産された鉄鋼が還流し、国内の鉄鋼業界に深刻な影響を与えているとして、2002年3月に鉄鋼14品目に対して3年間8~30%の追加関税を賦課するSG措置を発動した。当該措置発動は、各国からの連鎖的なWTO協議要請や対抗(補償)措置を招くことになった。WTO上級委員会は2003年11月に協定に定める発動要件の十分な説明がないとして当該措置の協定違反を認定した。それを受け、米ブッシュ政権は同12月に措置を撤回するに至った(第Ⅱ-2-3-2-1表)。
第Ⅱ-2-3-2-1表 米国の2002年鉄鋼SG措置概要
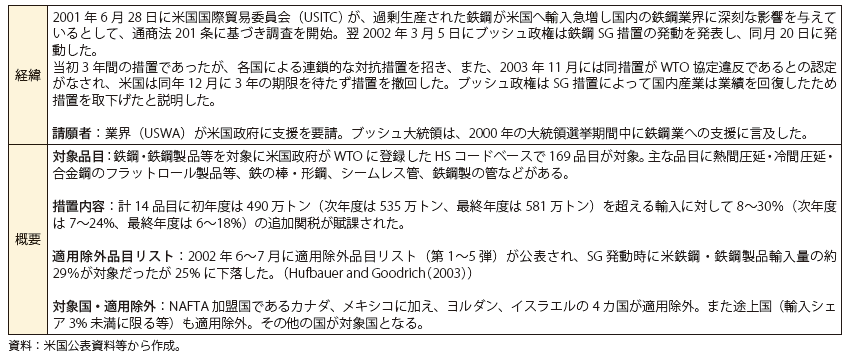
180 本イニシアティブは、①世界的な供給過剰問題への取組、②鉄鋼貿易、国内補助金に関する国際的なルール作りとともに、③国内鉄鋼産業への一時的なセーフガード措置の検討を内容とするもの。
②当時の鉄鋼産業の状況
20世紀前半には世界をリードしていた米国鉄鋼産業は、1970年代から国際競争力を低下させ徐々に衰退の道を辿っていた181。そうした中、当時の米国鉄鋼産業は国際競争力の低下だけでなく、高炉メーカーと新興電炉メーカーによる国内競争の激化、2001年のITバブル崩壊による国内景気の悪化に伴う需要減といった複合的な要因による不況下にあった182。発動前の米国内の鉄鋼需給の状況を見ると、ITバブル崩壊前の2000年までは、97年のアジア通貨危機の影響で一時的な減少が認められるものの見かけ消費量183の増加に支えられ、粗鋼生産量はわずかながら増加傾向にあった(第Ⅱ-2-3-2-2図)。しかし、ITバブル崩壊を契機として、2001年に米国の国内景気が悪化すると、粗鋼生産量及び粗鋼純輸入も減少した。それに伴い雇用者数の減少も拡大し、2000年から2年間で約2割の減少となった。こうした状況の中、米鉄鋼業界団体からの救済要請を受け、米国政府はWTO協定に基づく救済措置を多発するようになり、ピークの2001年には1年間で31件もの救済措置を発動し、翌2002年3月に職権調査に基づき本鉄鋼SG措置を発動するに至った(第Ⅱ-2-3-2-3図)。
第Ⅱ-2-3-2-2図 米国粗鋼の生産、消費、純輸入、雇用者数の推移
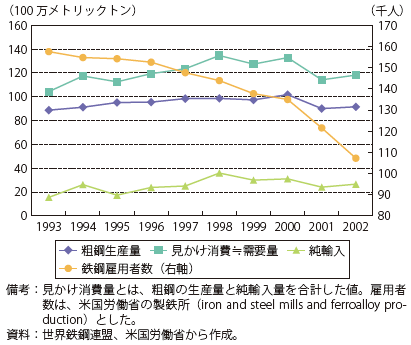
第Ⅱ-2-3-2-3図 米国の鉄鋼・鉄鋼製品への救済措置発動件数の推移
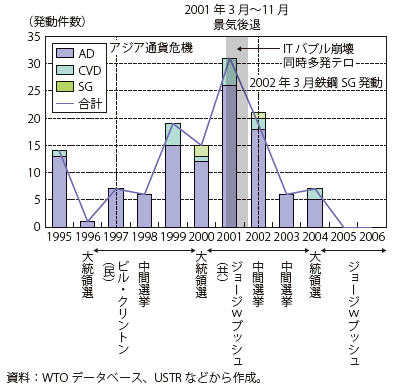
181 米国の2001年の生産量は、中国、日本に次いで世界第三位(約90百万トン(世界シェア10.6%))、消費量においても中国についで世界第二位(約114百万トン(同13.4%))であり主要な鉄鋼生産・消費国であった。数値はWorld Steel Association。
182 Gary Clyde Hufbauer and Ben Goodrich (2003a)によれば、雇用者数が減少した主な理由は、新興電炉メーカー(ニューコア社やスチールダイナミクス社など)の台頭が指摘されている。これら新興電炉メーカーは、原価の安い鉄くずを使った小規模な電炉を持ち、比較的少ない雇用者数で安いコストを実現し、既成の高炉メーカー(USスチール社やAKスチール社など)の販売シェアを奪っていた。
183 見かけ消費量とは、粗鋼生産量+純輸入量(輸入量-輸出量)で算出される値で、ある国の鉄鋼の需要量を表す。
③措置発動国(米国)における貿易への影響
まずは、措置の発動による米国の対象品目の国別輸入の影響について概括する184。米国の2001年における対象品目輸入額は128億ドルであった。国別の内訳としては、本SG措置除外国であるカナダ、メキシコが大きな割合を占めることが分かる(第Ⅱ-2-3-2-4表)。
第Ⅱ-2-3-2-4表 米国の2001年対象品目輸入国ランキング
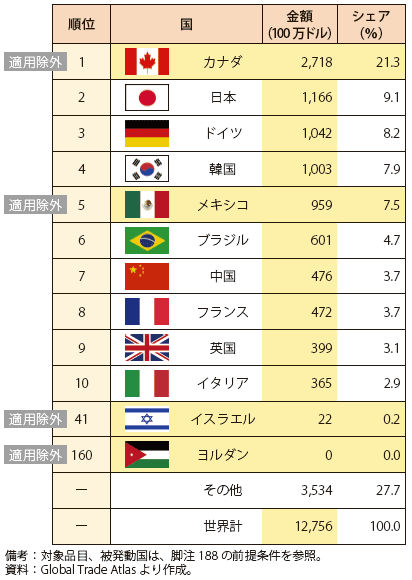
対象品目における被発動国と除外国の輸入を前年同月比で比較すると、措置発動直後に被発動国からの輸入が半減する一方で、除外国からの輸入は増加し、両者の違いが鮮明となった(第Ⅱ-2-3-2-5図)。
第Ⅱ-2-3-2-5図 対象品目の被発動国と除外国の輸入額推移(前年同月比)
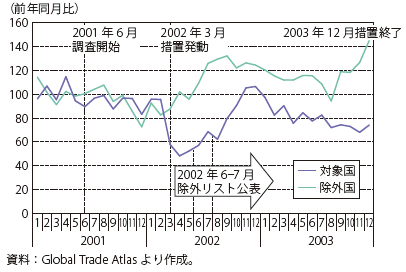
次に米国の、被発動国からの対象品目の輸入価格の推移を見る185。輸入価格は、非対象品目(対象とならなかった鉄鋼・鉄鋼製品等)と比べて、発動後に大きく上昇し、発動時点より最大2割近く上昇した。なお、非対象品目も2003年後半には上昇に転じており、発動時点より1割近く上昇した(第Ⅱ-2-3-2-6図)。
第Ⅱ-2-3-2-6図 被発動国の対象品目と非対象品目の輸入価格指数の推移(フィッシャー指数)
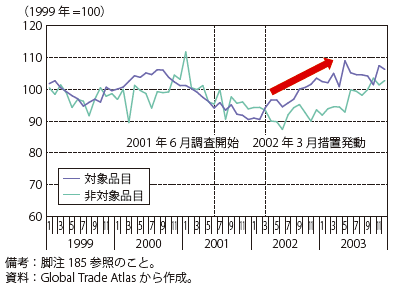
184 本措置の影響分析にあたり、以下を前提条件とした。①対象品目の特定には、米国によりWTOに登録されたHS6桁ベースの対象品目を利用。なお、2002年6、7月の一部対象品目の除外については、除外後も対象品目として数値分析を行った。②被発動国は、除外国となったカナダ、メキシコ、イスラエル、ヨルダン以外とした。また、途上国の適用除外(輸入シェア3%未満に限る等)については、全てを網羅的に分析することが困難であったため、本分析では途上国を一律に被発動国として扱った。③貿易量は、発動国の輸入額のCIF価格(製品価格、保険料、運賃の3要素で構成された価格であり、関税を含まない)で統一した。
185 米国がWTOに登録したHSコード6桁ベースの対象品目は2桁ベースでは72類(鉄鋼)、73類(鉄鋼製品)、83類(卑金属製品)に属する。本分析では、これら3類に属する6桁ベースの品目の中で対象品目と非対象品目を分けた。また輸入単価のフィッシャー指数は、1999年の値を基準値とし算出した。また単価の計算にあたり、対象品目のHS730820、HS720690、HS843143のデータ、非対象品目のHS732421の1999年12月分のデータ、非対象品目のHS732620のデータは価格指数の変動が大きく異常値とみなし削除した。また被発動国の対象品目を分析対象とするため、除外国のうちカナダ、メキシコのデータを世界合計の対象品目、非対象品目のいずれからも削除した。
④措置発動国(米国)の鉄鋼業界における価格、雇用、株価への影響
次に国内価格、マーケット等への影響を見る。2000年代前半の鉄鋼の米国国内需給は、年により多少の増減があるが、継続的に需要超過が続いていた。国内需要は横ばいで推移した一方、本措置による輸入減少も背景に2001年以降、国内供給は緩やかに増加していった(第Ⅱ-2-3-2-7図)。米国の鉄鋼生産、設備稼働率も2001年第4四半期を底に増加に転じており、2002年3月の措置発動によって生産状況が好転している様子が見られる(第Ⅱ-2-3-2-8図)。好調な生産状況は卸売物価指数にも表れており、代表的なベンチマーク指標である熱間圧延コイル(HRC)の価格指数は、措置発動前まで低下傾向にあったのが、発動を契機に急激に上昇した(第Ⅱ-2-3-2-9図)。マーケット価格でも同様の動きが見られ、HRCのマーケット価格は発動後上昇が続き、発動数か月後の7月には2倍近くまで上昇した(第Ⅱ-2-3-2-10図)。一方、卸売物価指数でもマーケット価格においても価格は一時的に上昇しただけで2002年末には元の水準に戻っている。
第Ⅱ-2-3-2-7図 米国国内需要の推移
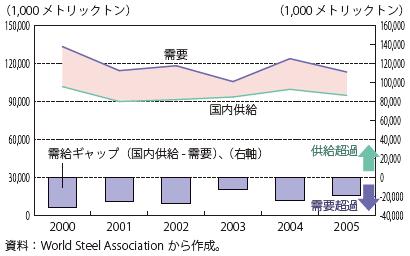
第Ⅱ-2-3-2-8図 米国粗鋼生産量と稼働率の推移
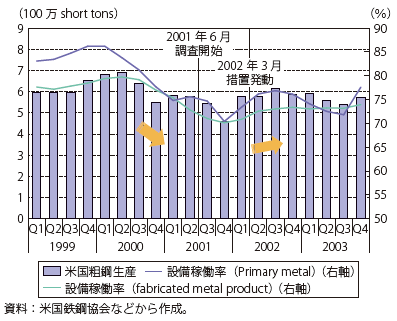
第Ⅱ-2-3-2-9図 米国鉄鋼生産者価格指数の推移
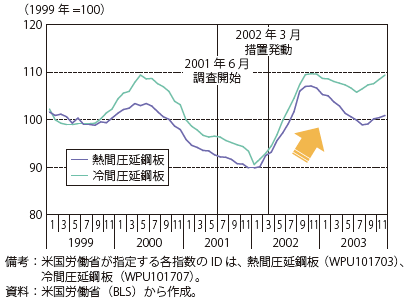
第Ⅱ-2-3-2-10図 米国鉄鋼マーケット価格の推移
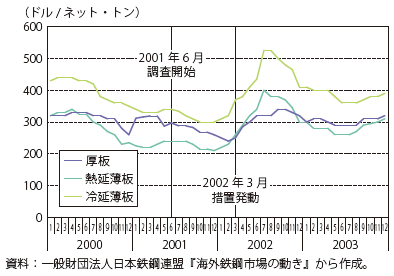
鉄鋼業界の雇用者数を見ると、措置発動の2002年3月まで継続的な減少が続いており、特に2000年頃からの減少が大きく、同年1月に13.8万人であった雇用者数は措置発動時点の2月には10.7万人と22.2%も激減していた(第Ⅱ-2-3-2-11図)。措置発動により、雇用者数の減少に一時的に歯止めがかかり、2002年にかけてわずかに雇用者数は上昇した。しかし、2002年末以降に鉄鋼価格の水準が戻った時期から、雇用者数は再び緩やかな減少傾向に戻っている。なお、措置終了後に少し遅れて鉄鋼業雇用は10万人前後で下げ止まっているが、これは鉄鋼業における雇用者の適正な水準まで減少したことが推察され、本措置が鉄鋼業における雇用者の減少を後ろ倒しにした可能性がある。
第Ⅱ-2-3-2-11図 米国鉄鋼業界雇用者数の推移
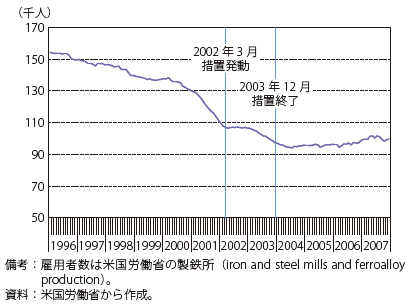
個別企業の業績では、USスチール社とAKスチール社など高炉メーカーは、措置発動後に業績を赤字から黒字へと回復した。他方で、新興電炉メーカーのニューコア社やスチールダイナミクス社は措置発動後に業績がわずかに回復するに留まった(第Ⅱ-2-3-2-12図)186。一方で株価においては、高炉メーカーは措置発動後の一時期を除きS&P平均を下回ることが多く、新興電炉メーカーは措置発動後にS&P平均を大きく上回るトレンドで推移した(第Ⅱ-2-3-2-13図)。
第Ⅱ-2-3-2-12図 米国主要鉄鋼メーカーの業績(純利益)
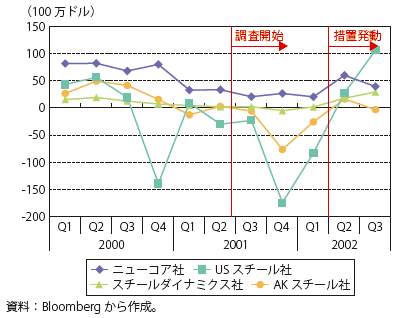
第Ⅱ-2-3-2-13図 米国主要鉄鋼メーカーの株価
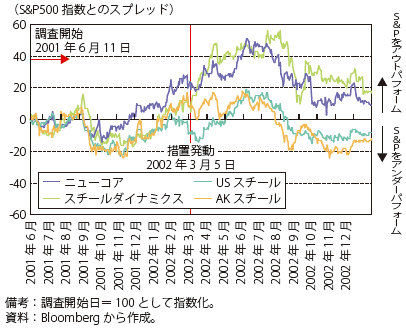
このように、短期的には本SG措置によって海外製品の輸入量が減少し、需要過多となり鋼材価格が上昇することで、米国鉄鋼業界の業績は向上し、雇用の減少も下げ止まった。これらの影響は、第1項のミクロ経済学の理論における、関税引上げによる生産者余剰の増加とも整合的である。
186 高炉メーカーと新興電炉メーカーの業績の違いの背景については脚注186を参照のこと。
⑤措置発動国(米国)の川下産業への影響
ここで、米国内の川下産業への影響を考察したい。本SG措置の対象が、鉄鋼産業という幅広い川下産業を持つため、鋼材価格の上昇は多くの川下産業にコスト増としてマイナスの影響(第1項のミクロ経済学の理論における消費者余剰の減少)を与えると考えられる。
当時の川下産業における雇用を鉄鋼業における雇用と比較すると(第Ⅱ-2-3-2-14図)、両者ともに2001年のITバブル崩壊前後を境に減少しているものの、本措置発動後は、鉄鋼業雇用が下げ止まったが、川下産業の雇用については措置が終了する2003年末頃まで減少し続けた。これらから、本措置の発動は、鋼材価格の上昇を通じて川下産業の雇用者数の減少をもたらした可能性がある。
第Ⅱ-2-3-2-14図 2002年SG措置の雇用への影響(鉄鋼業とその川下産業)
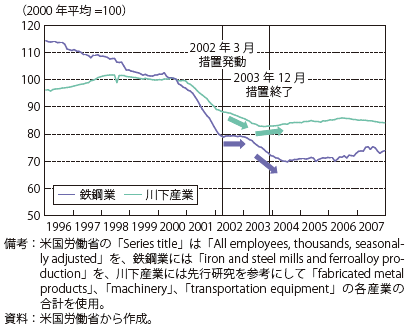
本措置は発動国である米国において、生産者余剰を増加させる一方、消費者余剰の減少を引き起こしたが、生産者余剰と消費者余剰を合わせた増減である国全体の社会的総余剰への影響については、米国政府のUSITCが2003年9月に公表したレポート187において指摘している。同レポートは、一般均衡モデルを用いて、セーフガード措置による関税収入と家計・企業への影響を分析したもので、米国にとってネットで3千万ドルの悪影響があるとの結果を示している(第Ⅱ-2-3-2-15表)。特に、自動車部品、金属タンク・重量ゲージ、鉄道車両製造などの、鉄鋼の川下産業により大きなマイナスの影響があるとした。また、民間シンクタンクのレポートでは、年間4.3万人の雇用喪失があったとの試算結果188や、金属、機械、輸送設備の製造業において2002年に22.4万人の雇用喪失(そのうちラストベルト地帯で顕著に減少)があったとの試算結果189が発表されている。
第Ⅱ-2-3-2-15表 鉄鋼セーフガード措置による一般均衡モデル試算
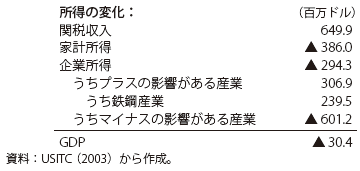
187 USITC (2003).
188 Gary Clyde Hufbauer and Ben Goodrich (2003b).
189 Dr. Joseph Francois and Laura M. Baughman (2003).
⑥本措置の他国への影響
最後に、本SG措置が当時の世界の鋼材価格に及ぼした影響をドイツ及び中国を例に見る(第Ⅱ-2-3-2-16図)。ドイツ・中国においても、2002年3月の米国の本措置発動を受けて鋼材価格がそれまでのトレンドから一転し、上昇に転じたことが見て取れる。さらに、その後それぞれが発動した対抗措置の影響もあり価格はさらに上昇していく。特に、中国は2001年から急速な経済成長による需要増に供給が追い付けない状況に加えて、米中のSG措置による国内マーケットへの影響が大きかったと考えられる。
第Ⅱ-2-3-2-16図 鋼材のマーケット価格の動き(ドイツ、中国)
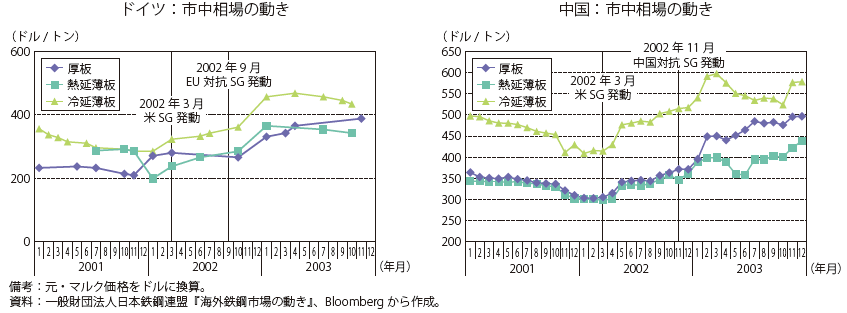
また米国のSG措置によって世界的な規模で貿易制限的措置が連鎖反応を起こしたことも指摘されている190。本措置によって、EU、中国、ハンガリー、チリ、ポーランドが暫定SG措置を発動し、発動した地域が世界の輸入量の約5割弱を占めるまでに至った。これら地域では、輸入コストの上昇に伴い鋼材価格の上昇がみられ、特に中国では高級鋼材や特定用途の鉄鋼製品の供給がひっ迫し、米国のみならず、世界全体の消費者余剰の損失を生んだとされる。また、生産者にとっても、SG措置は非効率な生産設備を残存させるインセンティブとして働き、国内鉄鋼産業の構造調整を遅らせ、長期的には国際競争力の低下に伴う経済損失が発生した。以上のように、本SG措置は、単に発動国にとどまらない世界に広がるスピルオーバーがあったケースといえよう。
190 2003年版不公正貿易報告書。
(2)米国太陽電池セル・モジュール191への2012年及び2015年のアンチ・ダンピング(AD)措置及び相殺関税(CVD)措置並びに2018年のSG措置
①措置概要
2018年1月に米トランプ政権は、太陽電池セル・モジュールの輸入急増が国内産業に重大な損害を与えているとしてSG措置の発動を命じた。米国政府はそれまでに二度(2012年と2015年)にわたって中国製品等の太陽電池セル・モジュールに対してAD措置とCVD措置をそれぞれ発動してきた。しかしこれらの措置から逃れるために、中国企業が生産拠点をマレーシア、ベトナムなど国外に移転し、過去二度の措置を回避してきたと米国政府は指摘し、三度目の措置となる今回の措置を発動した。
1回目の措置は、2012年12月に発動されたAD措置、CVD措置である。中国政府の太陽光発電に対する補助金192が市場歪曲的でありWTO協定に違反するとし、補助金を背景とした中国からの廉価な輸入品により国内産業に損害が生じていると認定した。しかし、当該措置は適用の際の原産国を「太陽電池セルの製造国」と定義したため、製造工程193の一部を担うセル加工を台湾等に出すことで当該措置の適用を回避した中国産モジュール(台湾等でセル加工し、中国で組み立てたモジュール)の対米輸出が急増する結果となった194。2回目の措置は、この急増した台湾産セルによる中国組立てモジュールを対象にすべく、原産国を対中国向けは「モジュール製造国」、対台湾向けは「セル製造国」とし、2015年2月に再びAD措置、CVD措置を発動した。しかし、その後も米国政府による再生可能エネルギー導入事業者への減税を受けた需要拡大を背景に、中国企業等は中国からの輸出を徐々に減少させつつ195、マレーシアやベトナムなどに一部生産拠点を移して輸出を増加させた。米国政府はこのような回避行動に対して、2018年2月に3回目の措置となるSG措置を発動することとなった(第Ⅱ-2-3-2-17表)。
第Ⅱ-2-3-2-17表 2012年からの太陽電池セル・モジュールに対する措置の概要
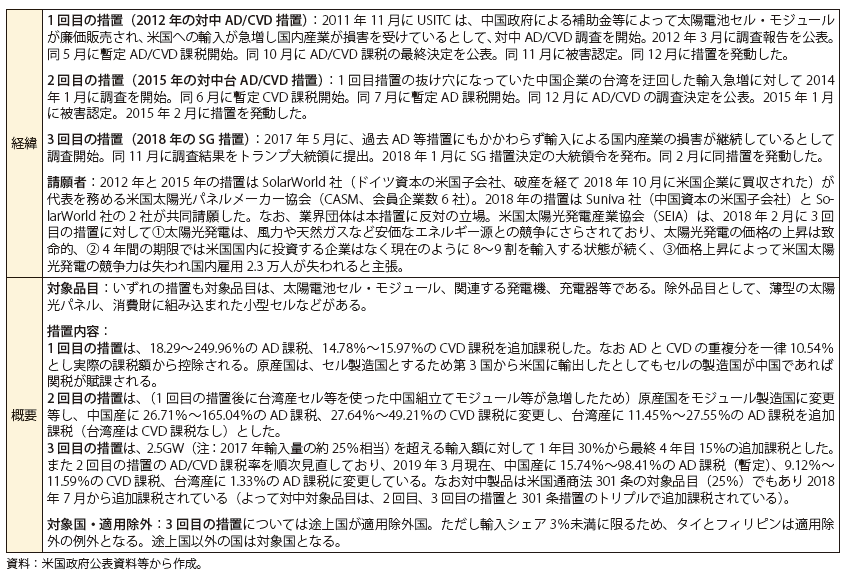
これら措置は、各国からの連鎖的な太陽電池セル・モジュールに関する対中AD措置発動を誘引し、またそれに対する中国の対抗措置を引き起こす契機となった。具体的には、EU、カナダ、トルコが対中AD措置等を発動し、中国政府は米国及びEUに対して対抗措置を発動している。
なお、2018年我が国の不公正貿易報告書でも、本SG措置は取り上げられ、SG措置の原則である「必要最低限な措置」となっておらず、SG措置の発動要件である「事情の予見されなかった発展」の十分な説明がないと報告している。
191 正確には結晶系太陽電池のセルとモジュール(Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules)。なお、太陽電池は、シリコン系太陽電池が現在主流であり、そのうち結晶系と薄膜系があり、結晶系が本措置の対象となっている。
192 蓬田守弘(2015)によれば、米商務省が、中国セル・モジュールメーカーの適正価格未満での①資金借入れ、②土地賃借、②国有企業が専有した原材料調達、を国内補助金とみなし、中国輸出入銀行の輸出信用を輸出補助金と認定した。
193 太陽電池の製造工程は、第一工程では原料となるポリシリコンを精錬し、第二工程ではケイ素の純度が高いインゴット(鋳塊)を切断しウェハー(半導体の薄い円盤状の板)に加工し、第三工程では、太陽電池の基本単位であるセルに加工し、最後の第4工程でセルを複数配列したモジュール(パネル)を組立てる。それぞれの生産工程は最適な立地選択に応じて国際間で分業されている。
194 蓬田守弘(2015)によれば、USITCが、米国太陽電池モジュール市場での台湾等産セルを使った中国製モジュールのシェアは同4.6%から76.2%に拡大する一方で、中国産セルを使ったモジュールのシェアは2011年58.3%から2013年8.1%に激減した。また中国企業から台湾セル製造企業への発注も増加しており、台湾の(セル材料の)ウェハー調達先に占める中国の割合は2011年33.9%から2013年には46.5%に拡大した。
195 中国企業の輸出が徐々に減少した背景として、関税率レビューによる関税率の引下げが一つの要因と考えられる。USITC (2019)によれば、2015年2月の2回目の措置発動時の主要中国企業のAD/CVD措置関税率は合算して80%~100%に上ったが、2015年7月には約25%程度に引下げられている。主要中国企業にとって約25%程度の関税がかかっても米国市場で一定の競争力を保ったと考えられる。
②太陽電池セル・モジュール市場の状況
世界の太陽電池セル・モジュール市場の状態を各国・地域別に着目する。まず、太陽光発電設置容量で太陽光発電市場の推移に着目すると、2007年以降に欧州で急速に市場が拡大したものの2011年以降には縮小し、代わりに中国を始めとするアジア大洋州市場が拡大している(第Ⅱ-2-3-2-18図)。また、2016年以降には米国市場も拡大している196。次に、太陽電池セル・モジュールの主要な輸出国の移り変わりを確認する。太陽電池セル・モジュールの各国輸出額の合計は、2011年の約900億ドルをピークに急落し、600~700億ドルの間で足下は低迷している。低迷の要因としては、米国のみならず主要国間でAD措置等を連鎖的に発動し合ったこと197や最大の生産国かつ輸出国である中国の国内市場が急拡大したことが影響していると考えられる。中国は1996年に輸出額世界第5位に浮上し、2008年に第一位になって以降、第一位の地位を維持している198。その後、前述のように中国企業は、マレーシア、ベトナム等海外での生産を拡大した(第Ⅱ-2-3-2-19図)。
第Ⅱ-2-3-2-18図 世界の太陽光発電設置容量の推移(地域別)
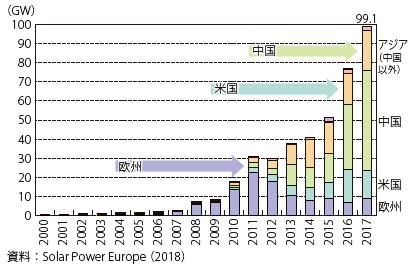
第Ⅱ-2-3-2-19図 世界の太陽電池セル・モジュール輸出額の推移(国別・積上グラフ)
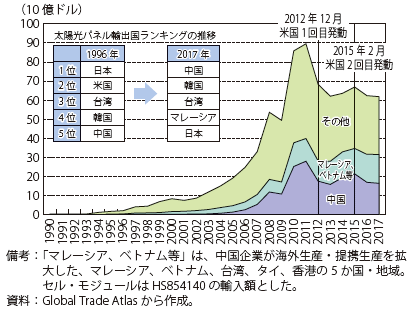
196 各地域の太陽光発電市場の拡大の契機となったのは、いずれも政府による補助政策が契機となっている。欧州では2004年にドイツで太陽光発電の固定価格買取制度が始まったこと、中国では2011年に固定価格買取制度を導入したこと、米国では2009年にグリーン・ニューディール政策を掲げ2015年に再生可能エネルギー導入(太陽光発電を含む)に対する減税が2016年末まで延長等されたことなどが挙げられる。
197 太陽電池セル・モジュールについては、米国が2011年11月に対中AD/CVD措置の調査開始、2012年12月に措置発動。EUは2012年9月及び11月に対中AD/CVD措置の調査開始、2013年6月に暫定措置発動、同12月に措置発動。カナダとトルコが中国製モジュールに対して2015年7月、2017年2月に対中AD措置等を発動。これらに対し、中国は2014年1月と2015年5月にその材料となるポリシリコンに対米国・韓国AD暫定措置、対EU AD措置等を発動している。
198 執筆時点ではマレーシアの2018年データが公表されておらず、2017年まで中国は1位。なお、2018年はマレーシアに抜かれて中国が2位になる可能性がある。
③措置発動国(米国)における貿易への影響
米国の太陽電池セル・モジュール輸入額199の推移に着目すると、2007年頃から米国の輸入は増加傾向に転じ、特に当時輸入の半数を占める中国からの輸入が2010年から急増する(第Ⅱ-2-3-2-20図、第Ⅱ-2-3-2-21図)。これに対して米国政府が2012年12月に1回目の措置を発動すると、2013年には中国及び世界の輸入額は減少する。しかし、2014年には中国企業等は台湾産セル等を中国で組立ててモジュールを輸出する抜け道を利用するようになり200、再びモジュールの輸入額は増加に転じた。モジュールの中国シェアは1回目の措置発動時には10%近くまで減少したが、その後50%近くまで増加し、台湾のシェアを加えると60%を超えるようになった。このため、米国政府は2015年2月に原産国の定義を、「セル生産国」から「モジュール生産国」へと変更し、台湾を原産国の対象に追加する形で2回目の措置を発動した。こうした中、米国では再生可能エネルギー導入に対する減税は2016年末が最終年201であったため、駆込み需要によって国内の太陽光発電市場が急速に拡大し、2016年に世界からの輸入は急増、輸入額は約87億ドルに達した(一方で2017年は反動によって大幅に減少している)(第Ⅱ-2-3-2-22図)。国別でみると中国や台湾からの輸入は月を追うごとに減少し、代わりに対象国として指定されていないマレーシア、韓国、ベトナム、タイといった国からの輸入が増加している。これは中国等の主要企業の製造工場立地の移り変わり(第Ⅱ-2-3-2-23表)とも符合し、中国企業等の迂回輸出によって輸入が増加したと考えられる。その後、米国は2018年2月に3回目の措置を発動した。その結果、2018年の輸入額は約36億ドルと2016年のピークから半減した。国別では中国はほぼなくなり、マレーシア、韓国、ベトナムがシェアを伸ばすも金額ベースでは発動時に大きく減少した。
第Ⅱ-2-3-2-20図 米国の対象品目輸入額の推移(世界・中国)
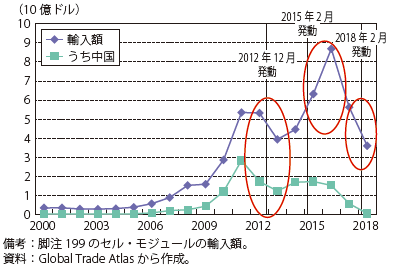
第Ⅱ-2-3-2-21図 米国輸入額の推移(国別・100%積上グラフ)
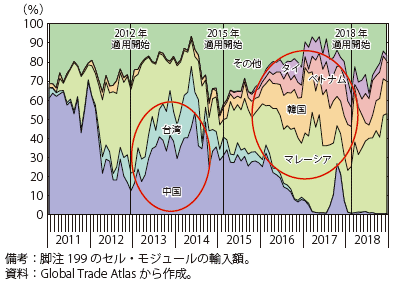
第Ⅱ-2-3-2-22図 米国の太陽電池発電設置容量の推移
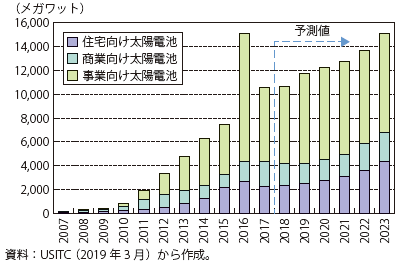
第Ⅱ-2-3-2-23表 主要企業の製造拠点の拡大
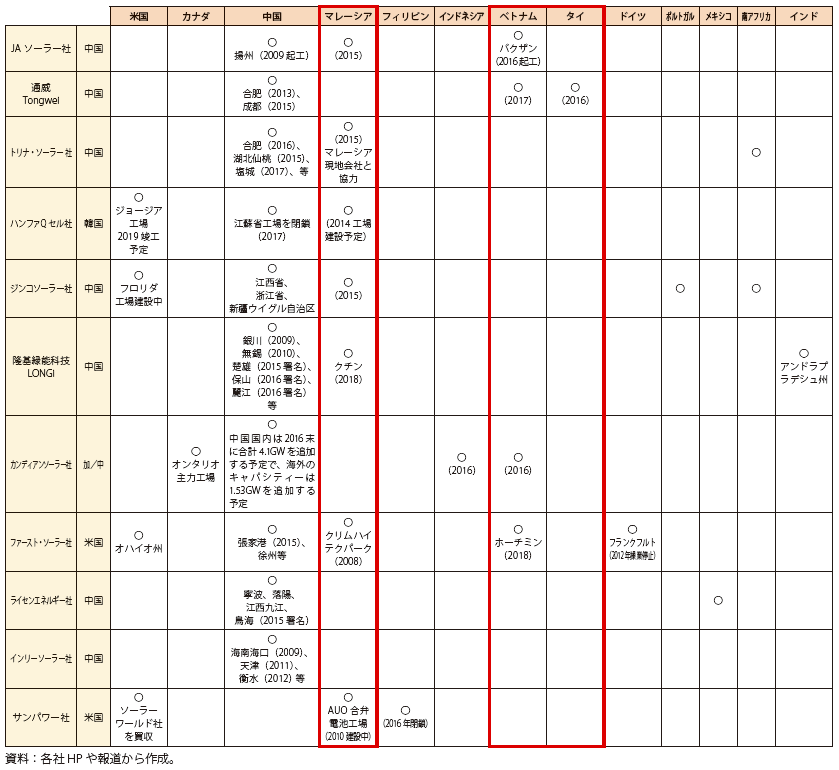
199 HSコード854140.60.20(モジュール)、854140.60.30(セル)等の輸入額。国別グラフはモジュールの影響を見るため、854140.60.20等に限定した。なお、2018年7月から以前の854140.60.20が、854140.60.15と854140.60.35に分割された。
200 脚注198参照のこと。
201 当時2016年末までの期限は、執筆時現在で2019年末までと延長された。
④措置発動国(米国)の太陽光メーカーにおける価格、雇用、株価等への影響
次に米国での物価、雇用、株価などの影響をみる。米国エネルギー省傘下の国家再生エネルギー研究所によれば、米国の太陽電池モジュールの価格は世界価格と比べて割高であったものの、輸入のピークを迎えた2016年に大きく下落し、米国価格(0.39ドル/ワット202)はグローバル価格(0.37ドル/ワット)に最も接近した(第Ⅱ-2-3-2-24図)。しかし2016年の減税駆込み需要の反動で2017年に設置容量が減少し、輸入が減少した2017年第1四半期を境に米国価格は上昇基調に転じる。一方で、グローバル価格はその後も下落しており、その差は2018年第1四半期で0.17ドル/ワットと、1.5倍に膨れ上がった。また2017年~2018年の米国・EU市場における推移については、データの制約から類似価格のものになるが、米国では3回目の措置に向けた調査開始以降、太陽光価格は横ばいで推移している一方でEUでは下落していることから、米国における価格が措置の効果によって世界的なトレンドに比して下がっていない可能性がある(第Ⅱ-2-3-2-24図203、第Ⅱ-2-3-2-25図)。
第Ⅱ-2-3-2-24図 米国と世界の太陽電池モジュールの価格推移
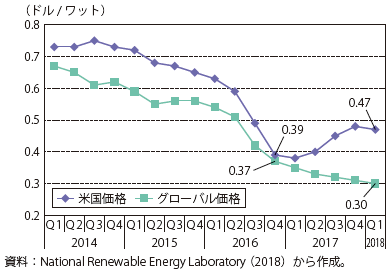
第Ⅱ-2-3-2-25図 米国及びEUの太陽電池モジュール価格の推移(上:米国、下:EU)
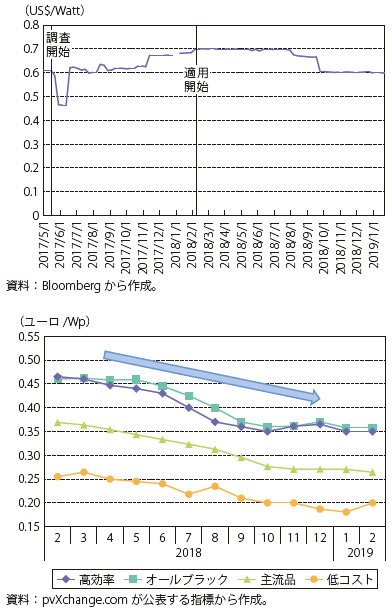
次に、米国の太陽電池企業の雇用と業績に着目する。USITCのレポート204によると、2011年からの輸入急増によって米国セル・モジュール生産者は壊滅的な打撃を受けており、2016年には供給量に占める国内生産量のシェアは4.6%に低下した(第Ⅱ-2-3-2-26図)。同レポートによれば、40社について調査を行った結果、米国内で2012年から2017年前半にかけて28工場が閉鎖しており、米国国内メーカーへの打撃の大きさがうかがわれる。
第Ⅱ-2-3-2-26図 米国の太陽電池セル・モジュールの国内生産量と輸入量の推移
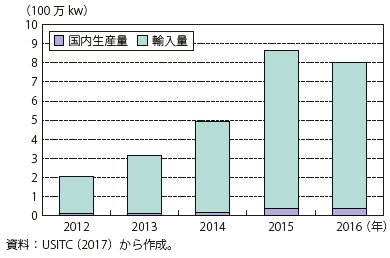
3回目の措置後には、措置の発動後に増産や新工場を発表した企業がある一方で、措置の発動にも関わらず、業績が回復することなく倒産した企業も存在する(第Ⅱ-2-3-2-27表)。
第Ⅱ-2-3-2-27表 SG措置によるメーカーへの影響
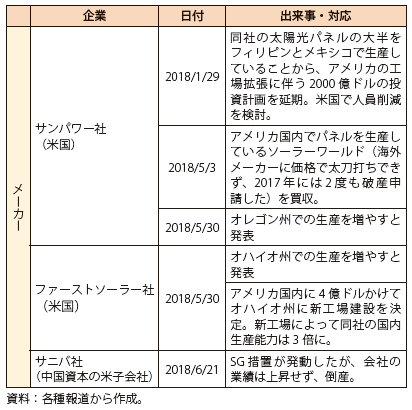
2018年の米国メーカーの業績を、国内生産を増強したとされるファーストソーラー社と、海外生産拠点も有するサンパワー社について見てみると、両社ともに雇用者数は減少から横ばいに転じたものの、売上高は減少した。また、ファーストソーラー社の純利益は0近傍で大きな増減はないが、サンパワー社は赤字で推移している(第Ⅱ-2-3-2-28図、第Ⅱ-2-3-2-29図、第Ⅱ-2-3-2-30図)。このように、SG措置によって保護されたはずの米国メーカーであっても、2018年の時点においては、業績の改善が見られない。
第Ⅱ-2-3-2-28図 米国モジュールメーカー労働者数の推移
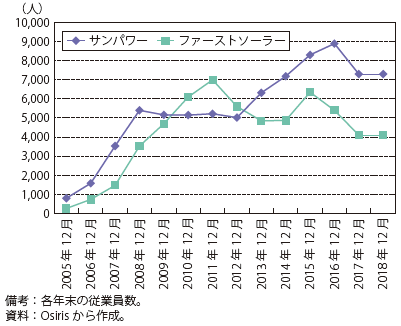
第Ⅱ-2-3-2-29図 米国モジュールメーカー売上高の推移
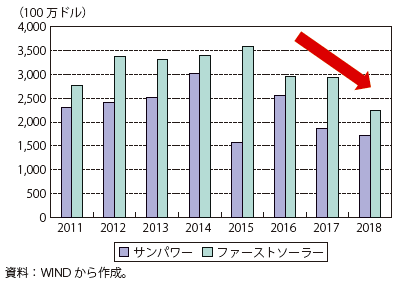
第Ⅱ-2-3-2-30図 米国モジュールメーカー純利益の推移
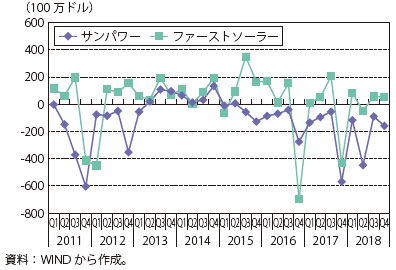
202 1ワット発電するのに必要な太陽光モジュールの単価。
203 National Renewable Energy Laboratory (2018).
204 USITC (2017).
⑤措置発動国(米国)の川下産業への影響
太陽光メーカーにおける川下産業は、主に太陽光パネルの設置・プロジェクト管理会社であるが、太陽光モジュールの価格が措置の発動によって、当初の予定に反して下がらなかったがために、多くの企業がコスト増による新規採用中止やプロジェクト凍結などの負の影響を報告している(第Ⅱ-2-3-2-31表)。
第Ⅱ-2-3-2-31表 SG措置による設置プロジェクト管理企業への影響
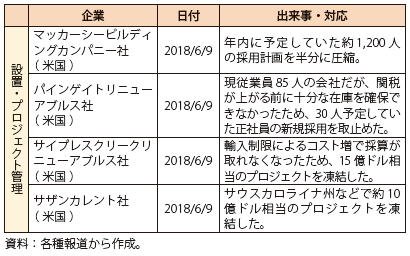
川下産業の雇用について、米業界団体Solar Foundationの統計によれば2018年に設置・プロジェクト管理で業界内で最大の1.0万人減少しており、前述したように本措置によって裨益を受けるはずの製造でも0.3万人が減少した(前年比▲8.6%減)結果、業界全体では1.9万人の雇用が失われた(同▲7.6%減)(第Ⅱ-2-3-2-32表)。
第Ⅱ-2-3-2-32表 太陽光発電の各分野の労働者数の推移205
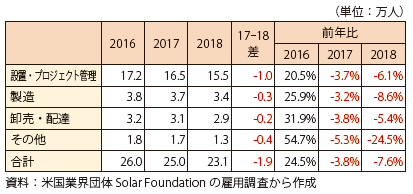
また、報道等206によると、セル・モジュールメーカーによる新規設備投資は10億ドル程度に止まると見込まれる一方で、措置発動によって建設コストが10%押し上げられたことから、米国内の太陽光発電設置の大規模プロジェクトが凍結され、その総額は25億ドル207に上ったとされており、太陽光発電投資への米国内の社会総余剰は15億ドルのマイナスとなるとしている208。
205 The Solar Foundation (2018).
206 ロイター(2018年6月)https://jp.reuters.com/article/us-trump-effect-solar-insight-idJPKCN1J40T1![]()
207 米国太陽光エネルギー産業協会(SEIA)によると2017年の大規模プロジェクトは総額68億ドル程度とされ、25億ドルは3分の1以上に当たる。
208 一方で、USITC(2019)によれば、公開情報をソースとして措置発動以降の6社が2018年11月、2019年初頭、2019年中に主にモジュール製造工程の新設計画を発表し、製造容量が合計3,100メガワットに達するとした。2018年の設置容量が1万メガワットであることを考えれば相当な設置容量であり、今後メーカーを中心に、生産者余剰が増加する可能性もあり得る点には留意が必要である。
⑥措置の他国への影響
米国の当該措置発動後、鉄鋼SGの際と同様に、多くの国がAD/CVD措置やSG措置の調査を開始した。2011年11月に米国が調査を開始すると、EU(2012年9月)、インド(2012年11月)、豪州(2014年5月)、カナダ(2014年12月)が次々と太陽電池セル・モジュールに対して対中AD調査等を開始した。また、EUは2013年8月に民間ベースのEU・中国間の輸出価格約束を締結した(2018年9月終了)。その他、カナダ(2015年7月)、トルコ(2017年2月)が、相次いで対中AD措置等を発動した。これらに対し、中国は、2013年に太陽電池セルの原料となるポリシリコンに対して対米国・韓国・EUに対してそれぞれAD措置等を発動した。
上記でみたように、グローバル価格は下落傾向であったものの、主要な輸出国である中国、米国、EUを巻き込んだ関税措置の応酬は、これらのAD/CVD課税率が100%を超える場合があったことを考慮すれば、価格へも一定の影響を与えて、世界の川下産業や消費者にマイナスの影響を及ぼした可能性も考えられる。
3.足下の貿易制限的措置(米国通商拡大法232条関連、通商法301条関連)の世界経済への影響209
前項では、過去に発動された関税引上げ措置の影響を見てきたが、本項では、2018年3月から始まった通商拡大法232条及び通商法301条に係る措置について、それぞれの経済的影響を俯瞰する。複雑なGVCが組まれている現代においては、貿易制限的措置が及ぼす経済的影響の全容を知るのは困難を極める。しかし、前項までに論じたとおり、関税引上げ措置は、措置の被発動国のみならず、貿易障壁を設けた措置発動国自身の企業や消費者にも損失を生じさせ、さらには当事国以外にも波及的な影響を与えることとなり、市場を歪めるおそれがあると考えられる。
209 本項は、2019年4月時点(貿易データは3月時点)で把握可能な情報で整理した。
(1)通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミニウムへの関税賦課措置の影響
①措置概要
措置の概要については、第1節で既述しているので詳細は省くが、米国の措置発動の流れを図にまとめたものが第Ⅱ-2-3-3-1図、米国の措置とそれに対する主要5か国210の対抗措置の規模を比較したのが第Ⅱ-2-3-3-2図である。
第Ⅱ-2-3-3-1図 米国232条措置発動の流れ(2017年ベース)
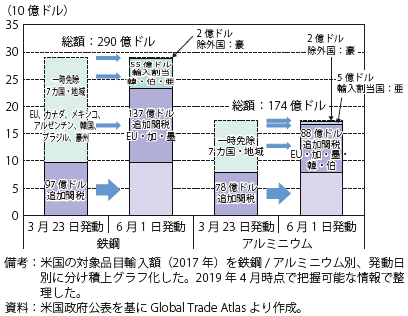
第Ⅱ-2-3-3-2図 米国232条措置と対抗措置の規模(2017年輸入額ベース)
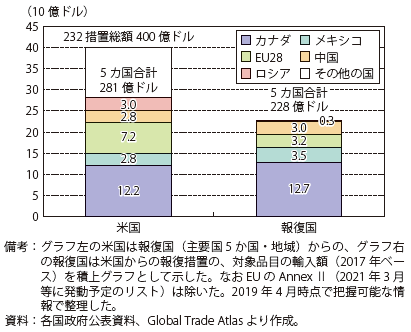
210 米国の措置に対しては、EU、カナダ、メキシコ、中国、ロシア、トルコの6ヵ国・地域が対抗措置を発動しているが、トルコは国内産業保護や貿易赤字の縮小を目的に対抗措置以外にも追加関税措置を実施していることから、本項ではトルコを除く5ヵ国・地域について分析を行う。また、米国政府公表資料においては、HTS(Harmonized Tariff Schedule)と記載されているところ、対応するGlobal Trade AtlasのHS(Harmonized System)コードに基づき集計。
②関税賦課の対象品目における米国輸入額の推移
232条に基づく関税賦課対象品目に係る米国の輸入量は措置発動後の価格ベースで前年比▲6.3%、数量ベースで同▲16.7%と大きく減少している(第Ⅱ-2-3-3-3表)。年ベースで見ても、鉄鋼の輸入量は2018年には前年比▲11%、アルミニウムは同▲13%となっている。一方、輸入額は、発動後に減少はしているものの、年ベースではかろうじて前年比微増にとどまっている。鉄鋼・アルミニウムいずれも輸入数量に比して輸入額の減少が小さかったことを示しており、発動後に単価が高い高付加価値品の輸入割合が増加している可能性も考えられる(第Ⅱ-2-3-3-4表)。
第Ⅱ-2-3-3-3表 米国の対象品目輸入額及び輸入量推移
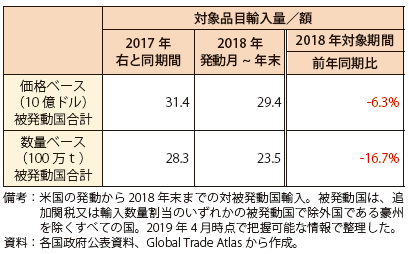
第Ⅱ-2-3-3-4表 対象品目(鉄鋼・アルミニウム製品)に係る米国の輸入額及び輸入量
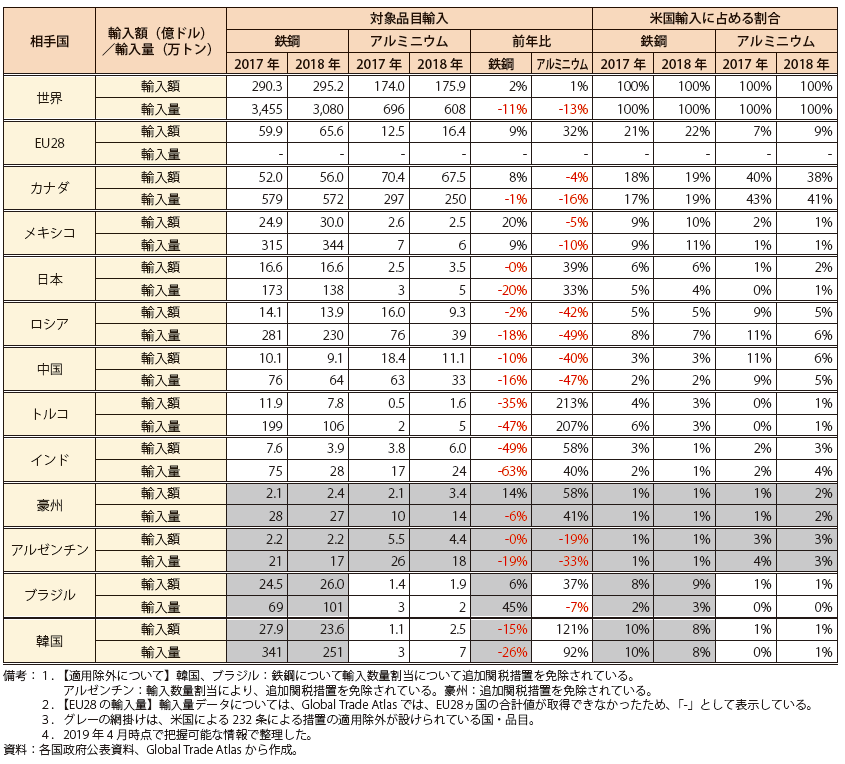
また、当該措置に対する各国の対抗措置が貿易額に与える影響を見ると、対抗措置により追加関税が課された品目に関する米国の輸出額は5か国・地域平均で▲19.7%と大きく減少していることが分かる(第Ⅱ-2-3-3-5表)。
第Ⅱ-2-3-3-5表 対抗措置対象品目に係る米国からの輸入額(各国の措置発動後から2018年末までの期間を前年同期比較したもの)
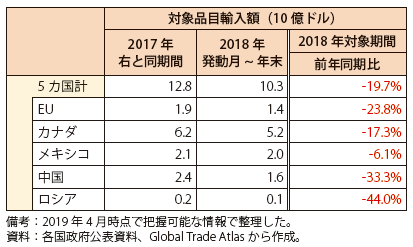
③米国産業界への影響
2018年における米国内の鉄鋼生産量は前年に比べ6%、540万トン増加し、輸入量は前年比で374万トン減少したが、鉄鋼生産量8,660万トン及び輸入量3,080万トンから見れば、影響は軽微なものといえる211。
価格について、代表的なベンチマークである熱間圧延コイル(HRC)のマーケット価格を見てみる。米国の鉄鋼価格は、元々他地域に比べて高値をつけてきたが、措置発動後に一時期にはトン当たり1,000ドル近くまで上がった一方、他地域は横ばいで推移したことから、価格差は最大1.5倍以上にまで広がった(第Ⅱ-2-3-3-6図)。また、第Ⅱ-2-3-3-7図にあるとおり、対象品目の輸入単価(関税賦課前の価格)は措置発動後に上がっているが、対象品目ではない鉄鋼・アルミニウムは、2002年の鉄鋼セーフガード時のように値上がりする動きは見受けられない。こうした鉄鋼価格の上昇等により、米国の主要な鉄鋼メーカーの業績は、232条の調査及び措置発動後に伸びており、工場の新規建設等の投資発表も行われたほか、最大手のニューコア社やスチールダイナミクス社ではそれぞれ400人、230人の新規雇用も発表している。またUSスチール社の2018年の利益は11億ドルと、前年(3.9億ドル)に比べて3倍近くまで伸びている(第Ⅱ-2-3-3-8図、第Ⅱ-2-3-3-9表)。
第Ⅱ-2-3-3-6図 主な地域における鉄鋼(熱間圧延コイル)のマーケット価格の推移
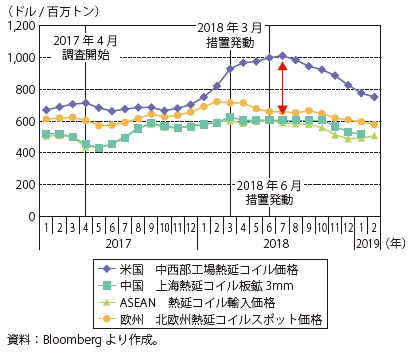
第Ⅱ-2-3-3-7図 米国における対象品目の輸入単価の推移(フィッシャー指数)
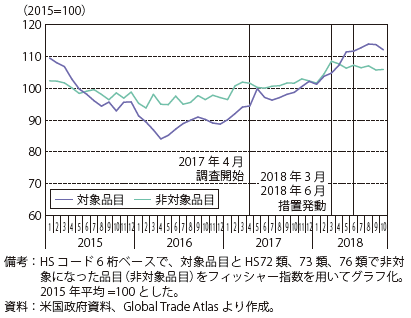
第Ⅱ-2-3-3-8図 米主要鉄鋼メーカーの業績(純利益(GAAP))
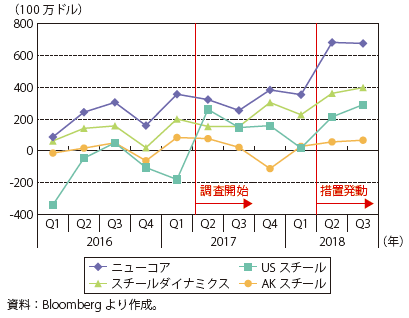
第Ⅱ-2-3-3-9表 米主要鉄鋼メーカーの決算時発表に対する報道
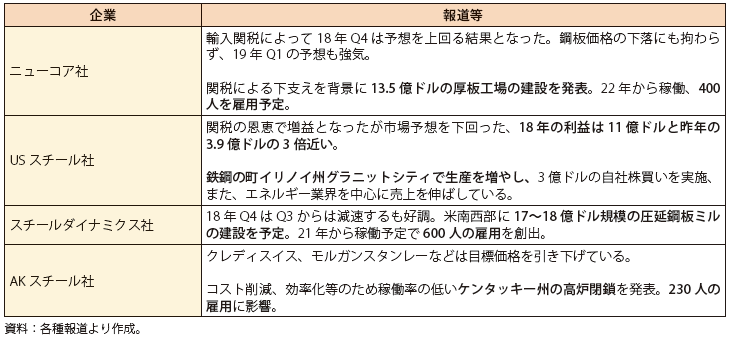
一方で、前節の過去の鉄鋼SGに関する分析でも見られたように、こうした鉄鋼価格の上昇は、鉄鋼を原材料として使用する川下産業にとってはコスト上昇に繋がる。鉄は「産業のコメ」とも言われ、価格上昇は製造業を中心に幅広い産業に悪影響を与える。米国の主要自動車メーカーであるフォード・モーター社は、関税賦課や鉄鋼価格の上昇により約10億ドルの利益が失われるとして、貿易紛争の早急な解決を訴えている212。また、米国民間シンクタンクは、関税措置による企業の税引き前利益の押し上げ効果は24億ドル、創出される雇用は8,700人であるが、このために川下産業の鉄鋼ユーザーが被る負担は56億ドルで、米国全体ではマイナスの影響があり、一人分の雇用を創出するのに65万ドルのコストがかかっていることになると試算している213。
211 USDOC (2019).
212 フォードの2018年の売上げは1603.4億ドル(2017年1567.8億ドル)と増加した一方、利益は対前年比52.5%減の36.8億ドル(2017年77.3億ドル)となっており、利益が大きく減少した。北米以外の市場での販売不振が大きな要因とされている。
213 Gary Clyde Hufbauer and Euijin Jung (2018).
④他国への波及的な影響(EUへの鉄鋼流入の例)
前述したとおり措置の発動後、米国の鉄鋼の輸入量は大きく減少した。一方で輸出先を失った海外製品が、他国市場に流入していると見られる現象も観察されている。その一例として、措置発動以降の米国及びEUの鉄鋼(フラットロール製品、HS7208~7212)の輸入の推移に着目する(第Ⅱ-2-3-3-10図)。
第Ⅱ-2-3-3-10図 米国・EUの鉄鋼輸入額の推移(前年同月差:億ドル)
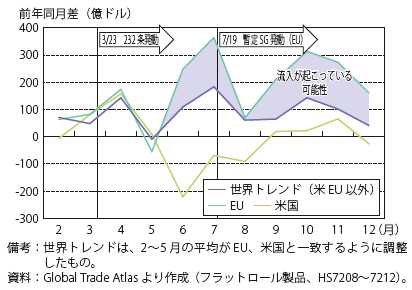
米国、EU、及びその他世界のフラットロール製品の輸入額の月次推移を見ると、2018年5月まではそれぞれが同様のトレンドで動いていたものの、6月以降は、米国とEUが大きく異なる動きを見せている。米国においては前年同月差で、最大で200億ドル程度減少する一方、EU輸入は、対前年同月差で、最大350億ドル増加し、世界トレンドとの比較においても大きく上回った。
米国とEUのフラットロール製品輸入額の前年同月比における国別寄与度に着目すると、特にトルコ、ロシア、中国の3ヶ国の寄与度に米国とEUで逆方向のトレンドが見られる。米国では当該3ヵ国からの輸入が大幅に減少した一方で、EUではこれらの国からの輸入が急増しており、米国向けに輸出されるはずであった鉄鋼が、EU向けに振り替えられた可能性がある。特にトルコ産製品については前年同月比で、EUの輸入を10%程度押し上げるほど増加した(第Ⅱ-2-3-3-11図、第Ⅱ-2-3-3-12図)。
第Ⅱ-2-3-3-11図 米国のフラットロール製品輸入額の推移及び各国寄与度(前年同月比)
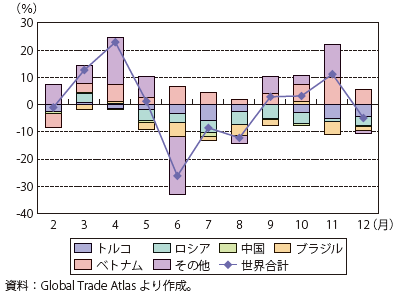
第Ⅱ-2-3-3-12図 EUのフラットロール製品輸入額の推移及び各国寄与度(前年同月比)
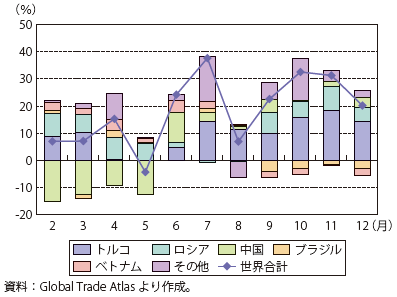
米国の232条措置の波及的な影響によるこのような流入によって国内鉄鋼産業が悪影響を受けることを避けるべく、EUは2018年7月に暫定セーフガード措置を発動し、翌2月には確定措置を発動している。本事例は、まさに米国による貿易制限的措置の影響が第三国に波及し、市場を歪めた例といえるだろう。
(2)通商法301条に基づく関税賦課措置の影響
①米国の措置による貿易への影響
米国の通商法301条に基づく追加関税は、第1節で既述のとおり、2018年に3段階に分けて順次発動された。追加関税の対象品目は6,842品目に上り、2017年の米国の中国からの輸入額5,050億ドルの約5割に相当する。
第1弾の措置については、2018年6月15日に公表された対象品目リストに基づき、同7月6日から25%の追加関税が課されている。産業機械、自動車、情報通信機器、半導体214、航空機・宇宙機などの合計818品目が対象であり、2017年の貿易統計によれば、合計約340億ドル規模の措置である。第Ⅱ-2-3-3-13表は、対象品目リストに記載のHTS2158桁ベースで集計216を行った上で、HS2桁ベースで整理したものである(第2弾、第3弾の集計方法も同様)。第1弾の措置においては、2018年は輸入額の大きい順に、一般機械で前年比▲3.2%、電気機器で同▲12.2%、光学機器で同▲2.6%など、全体で▲5.9%の減少がみられた(第Ⅱ-2-3-3-13表①)。さらに、2018年1月以降の第1弾措置対象品目の中国からの輸入額の前年比伸び率と、中国からの全ての輸入額の前年比伸び率を比較したものが第Ⅱ-2-3-3-14図である(第2弾、第3弾の集計方法も同様)。これによれば、追加関税措置発動が示唆217された4月から追加関税発動前の6月にかけては前年を上回る輸入額で推移している一方、措置が発動された7月以降は、前年度を下回る輸入額で推移しており、年末にかけて前年比伸び率のマイナス幅は拡大している。2018年12月には、第1弾対象品目の中国からの輸入額は前年比72%(前年比:▲28%)となった(第Ⅱ-2-3-3-14図-①)。
第Ⅱ-2-3-3-13表 通商法301条対象品目の中国からの米国の輸入額(品目別)
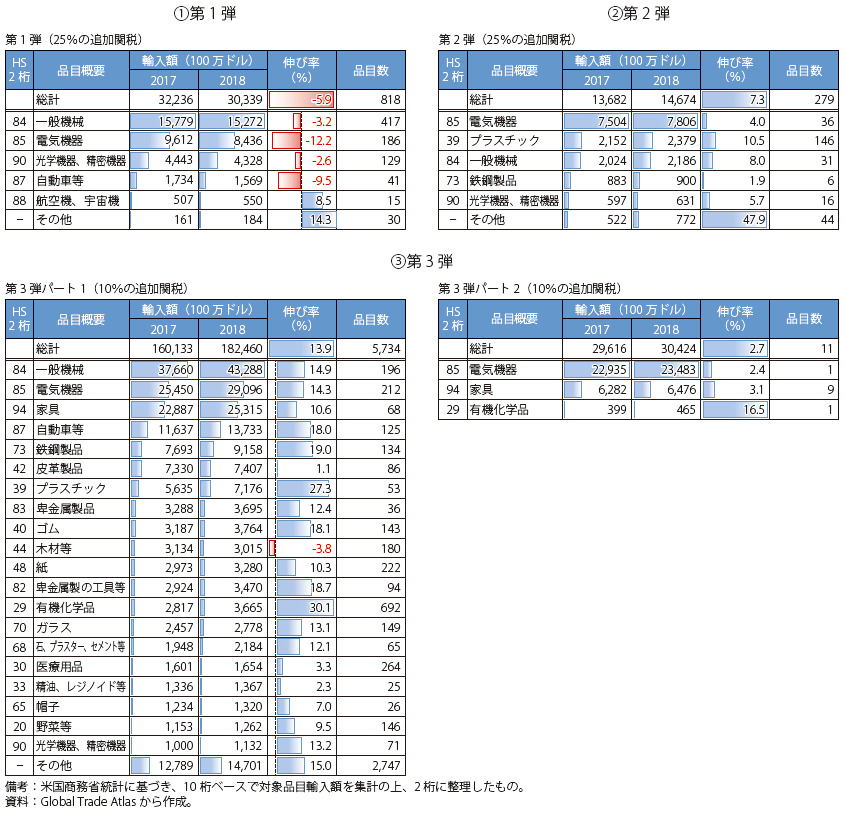
第Ⅱ-2-3-3-14図 通商法301条対象品目の中国からの米国の輸入額推移
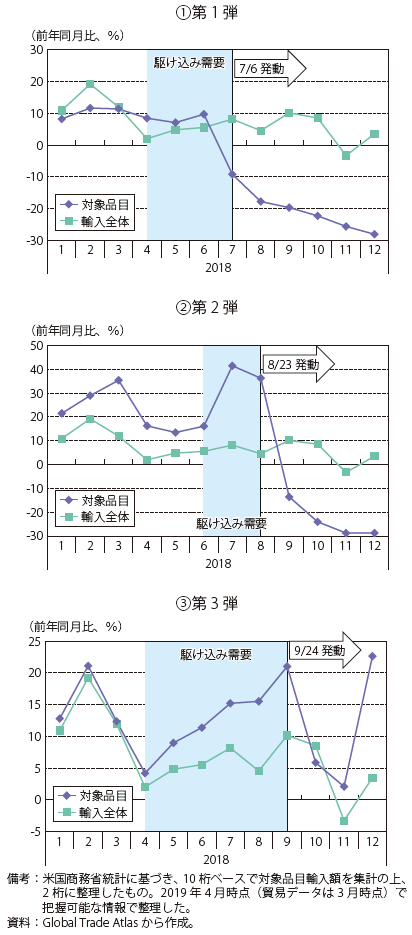
第2弾の措置については、第1弾と同様、6月15日に対象品目リストが公表され、8月7日に最終版リストが確定し、8月23日から25%の追加関税が課されている。半導体、産業機械など、合計279品目が対象であり、2017年の貿易統計によれば、合計約160億ドル規模の措置である。2018年の第2弾対象措置の輸入額は全体で+7.3%の増加となっている(第Ⅱ-2-3 -3-13表-②)。ここで、2018年1月以降の第2弾措置対象品目の中国からの輸入額の前年比伸び率と、中国からの全ての輸入額の前年比伸び率を比較すると、対象品目リストの公表があった6月から発動前の8月にかけて輸入額が急増しており、ピークの7月には前年比+41%を記録している(第Ⅱ-2-3-3-14図-②)。一方で、同図14-②の9月以降の輸入額は、第1弾と同様、追加関税の影響とみられる輸入額伸び率の大幅な減少(9月は前年比:▲14%、12月には同▲29%までマイナス幅が拡大)がみられ、関税発動前の駆け込み需要分が2018年の年間の輸入額の伸びに貢献していることが分かる。
第3弾の措置については、4月5日に1,000億ドルの追加関税賦課について検討の指示があり、6月18日には検討規模が2,000億ドルに拡大した。9月17日には、産業機械、鉄鋼製品、食品、帽子などの5,745の対象品目(2,000億ドル規模)について10%の追加関税が賦課されることが発表され、9月24日から発動されている。第3弾についても、措置の検討の初期段階にあたる5月から、措置が発動される9月までの間、駆け込み需要とみられる輸入額の増加があったことを背景に(第Ⅱ-2-3-3-14図-③)、2018年の対象品目の輸入額は前年比で増加している(第Ⅱ-2-3-3-13表-③)。対象品目リストはパート1とパート2に分かれており、パート1について前年比+13.9%、パート2について前年比+2.7%であった(第Ⅱ-2-3-3-13表-③)218。このように、第3弾の措置の影響とみられる輸入額の減少は観察されず、米国の対中輸入額全体と比較しても、むしろ全体よりも第3弾措置の対象品目の伸び率の方が、ほぼどの月においても高い傾向にあることが示されている(第Ⅱ-2-3-3-14図-③)。
214 HS2桁では、主に85類に分類。
215 米国政府公表資料においては、HTS(Harmonized Tariff Schedule)と記載されているところ、対応するGlobal Trade AtlasのHS(Harmonized System)コードに基づき集計。
216 対象品目リストは、HTS8桁で大括りの対象品目が記載されており、個別に除外の対象となる品目については、HTS10桁の品目番号や除外の対象となる品目の特徴が詳細に記載された形となっているが、本分析においては、全ての除外品目について統計上網羅的に集計することが困難であったため、HTS8桁ベースでの集計とした。
217 米国政府は4月3日に約500億ドル規模の追加関税リストを公表している。
218 第三弾対象品目リスト(https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Tariff%20List-09.17.18.pdf![]() )
)
②中国の対抗措置による貿易への影響
米国側の措置を受けて、中国からも、米国側の3度にわたる追加発動措置の発動日とそれぞれ同日に、米国からの輸入に対する追加関税措置が賦課されている。追加関税の対象品目は、6,085品目に上り、2017年の中国の米国からの輸入額1,300億ドルの約8割に相当する。上記①米国側措置の集計方法と同様に、中国国務院税則委員会から公表されている対象品目リスト(HS8桁ベース)について、中国側の輸入統計を基に分析を行った。
第1弾の措置は、大豆、豚肉、小麦、自動車などの545品目(2017年対米輸入額:約340億ドル)について、25%の追加関税を賦課するものであり、7月6日に発動されている。第1弾の措置による中国の米国からの輸入額の減少は著しく、2018年の対象品目輸入額は前年比▲30.7%減少した(第Ⅱ-2-3-3-15表-①)。より具体的に、第1弾の措置の対象のうち輸入額の大きい上位10品目についてみると、黄大豆(前年比:▲49.4%)、4WD車(同:▲24.9%)、ディーゼル車(同:▲21.7%)、その他冷凍豚肉(同:▲60.6%)などが大きく減少している(第Ⅱ-2-3-3-16表)。また、2018年1月以降の推移をみると、措置の発動が示唆され、検討中の時期に当たる5月(前年比:▲18%)から6月(前年比:▲21%)の輸入額が大きく落ち込んでいる。7月は前年比で僅かに増加(+3%)したものの、8月以降は前年比での減少幅が急速に拡大し、12月時点で前年比▲34%の減少となっている(第Ⅱ-2-3-3-17図-①)。米国側第1弾措置の2018年12月の減少率が前述のとおり前年比▲28%であったことを踏まえると、中国の対抗措置関税による中国の対米輸入額の減少率の方が大きな値を示している(第Ⅱ-2-3-3-18図-①)。なお、対象品目に限らず、輸入全体も2018年11月以降大きく減少をしているが、これは特に同年後半に中国経済の減速が指摘される中、必ずしも追加関税賦課の影響とは限らない要因により対象品目についても輸入額が減少している可能性もあることに留意が必要である(第2弾、第3弾の対象品目においても同様)。
第Ⅱ-2-3-3-15表 中国による対抗措置対象品目の米国からの中国の輸入額(品目別)
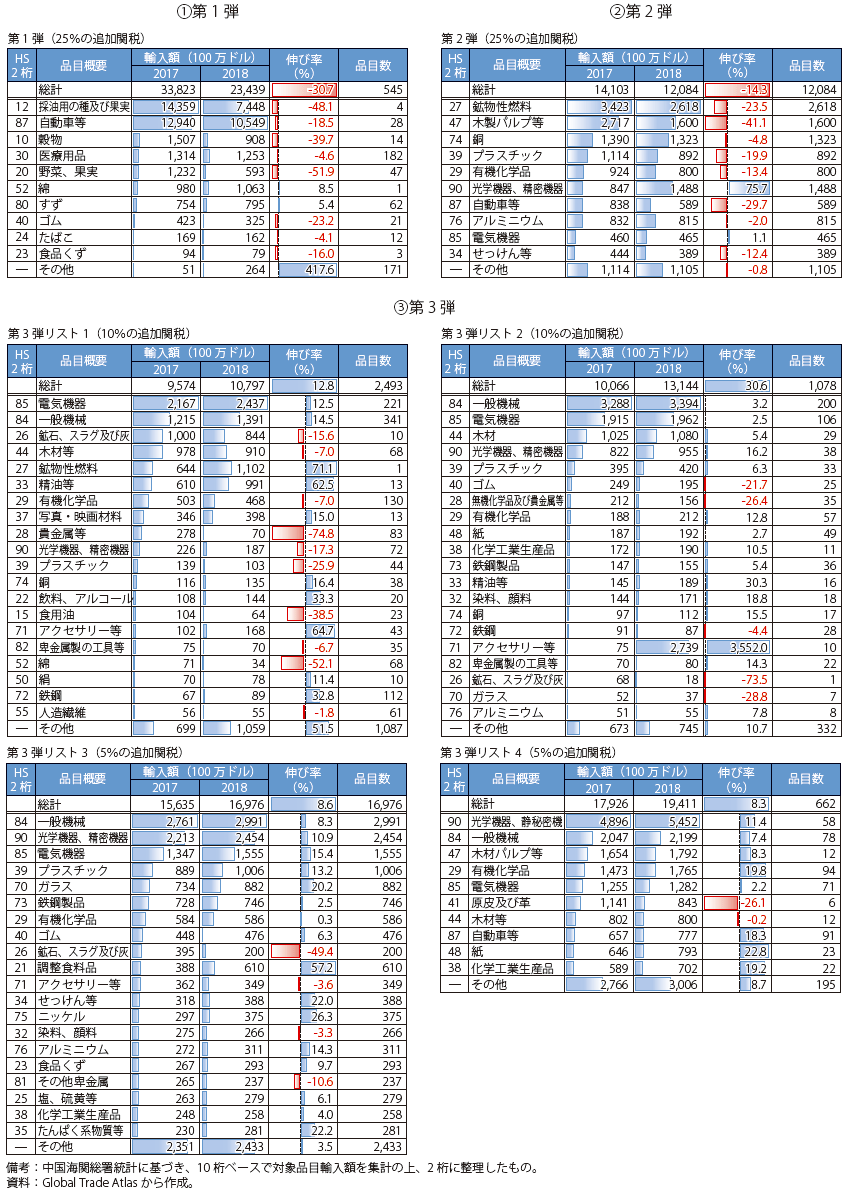
第Ⅱ-2-3-3-16表 中国による対抗措置第1弾対象品目の米国からの中国の輸入額(HS8桁:上位10品目)
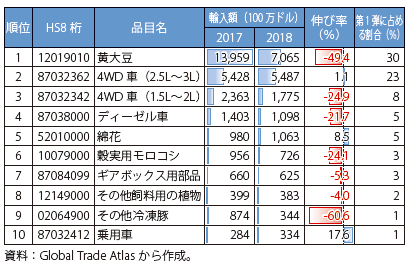
第Ⅱ-2-3-3-17図 中国による対抗措置対象品目の米国からの中国の輸入額推移
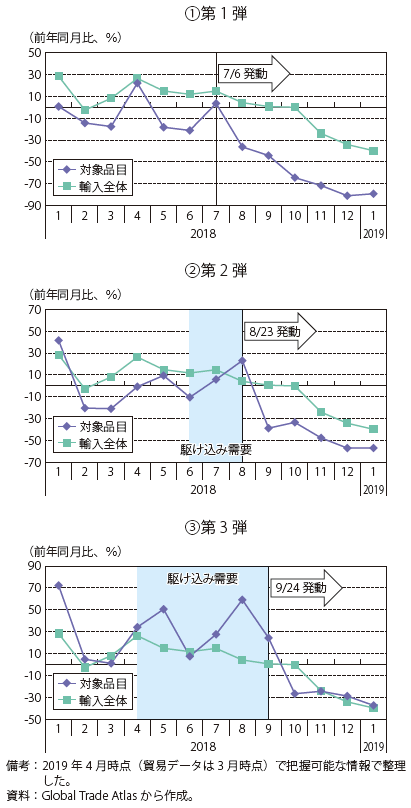
第Ⅱ-2-3-3-18図 301条対象品目の対中輸入額と中国対抗措置関税対象品目の対米輸入額の比較
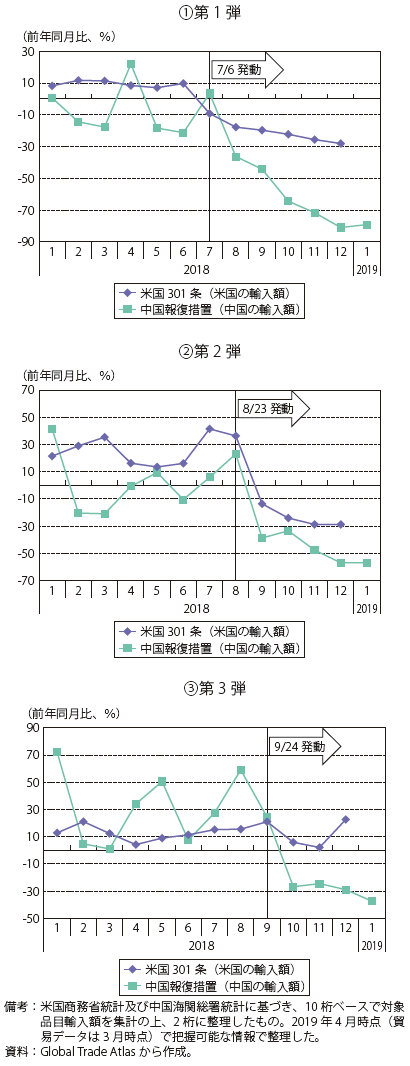
第2弾の措置は、古紙、銅、自動車などの333品目(2017年対米輸入額:約160億ドル)について、25%の追加関税を賦課するものであり、8月23日に発動されている。第1弾と同じく、対象品目の2018年の対米輸入額は大きく減少し、前年比▲14.3%となっている。具体的には、プロパンガスや石炭を含む鉱物性燃料(前年比:▲23.5%)、木製パルプ等(同:▲41.1%)、銅(▲4.8%)などで大きな減少がみられた(第Ⅱ-2-3-3-15表-②)。2018年1月以降の推移をみると、措置の発動直前にあたる7月(前年比:+6%)から8月(同:+23%)の輸入額は、前年度比で増加しているものの、9月以降は第1弾と同様、前年比伸び率が大幅なマイナスで推移している(第Ⅱ-2-3-3-17図-②)。また、301条対象品目の対中輸入額と中国対抗措置関税対象品目の対米輸入額の比較(第Ⅱ-2-3-3-18図-②)においては、措置発動以降に当たる9月以降、中国の輸入額の減少率の方が一貫して大きい。
第3弾の措置は、4つの対象品目リスト(リスト1~4)で構成されている。9月24日から、液化天然ガス、銅鉱、機械類、光学機器などを含むリスト1(2,493品目)及びリスト2(1,078品目)について10%、ガラス、レーザー機器、化学木材パルプなどを含むリスト3(974品目)及びリスト4(662品目)について、5%の追加関税が賦課された。2017年の対象品目の輸入額規模は600億ドルに上る。2018年の対象品目の輸入額は、リスト1~4の全てについて前年比で増加している(第Ⅱ-2-3-3-15表-③)。2018年1月以降の推移をみると、特に5月(前年比:+51%)と8月(前年比:+59%)に、液化天然ガスを中心に伸び率の増加が著しく、年間輸入量の増加に大きく貢献している。一方で、9月以降は前年比で3割から4割ほど対象品目の対米輸入額が減少している(第Ⅱ-2-3-3-17図-③)。このため、301条対象品目の対中輸入額と中国対抗措置関税対象品目の対米輸入額の比較(第Ⅱ-2-3-3-18図-③)における9月以降の推移をみると、前述のとおり、米国側措置による影響はあまり観察されなかったこともあり、中国の対抗措置による中国による対米輸入の減少幅の方が目立つ結果となっている。
③発動国の消費者・需要家への影響
前項の過去の関税引上げや上述の通商拡大法232条の例と同様に、通商法301条に関する関税の引上げに際しても、発動国内の消費者や需要家にもマイナスの影響が考えられる。関税引上げにより輸入が減少し、国内需給に影響し、国内価格の上昇に繋がる。具体例として、中国が第一弾対抗措置として2018年7月に対米輸入に25%の追加関税を賦課した豚肉について、中国国内価格の推移を見ると第Ⅱ-2-3-3-19図のように、措置発動前後で価格が上昇していることが見て取れる。2018年末頃の価格急上昇は中国で発生した豚肉コレラの影響があると考えられるが、それまでの価格上昇は関税引上げの影響が大きく出ているものと思われる。豚肉のような食料品は消費者に直接影響が及ぶ消費財であり、関税賦課により消費者が直接にマイナスの影響を受けるという象徴的な例である。
第Ⅱ-2-3-3-19図 豚肉中国国内価格推移
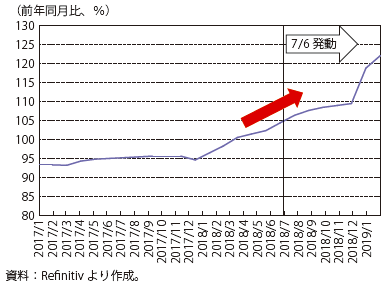
④波及的な影響(大豆の例)
中国が通商法301条に対する対抗措置第1弾(340億ドル)として25%の追加関税賦課を行った品目に、2017年の米国の対中輸出額が122.5億ドルに上る大豆が含まれている。
世界の主要な大豆生産国は米国、ブラジルである(第Ⅱ-2-3-3-20図)。大豆の収穫時期は、北半球では9~1月、南半球では3~7月頃となっており、こうした地理的特性による収穫時期の違いに合わせて、中国は米国とブラジルから大半の大豆を輸入してきた(第Ⅱ-2-3-3-21図)。
第Ⅱ-2-3-3-20図 大豆の世界生産シェア(2018年)
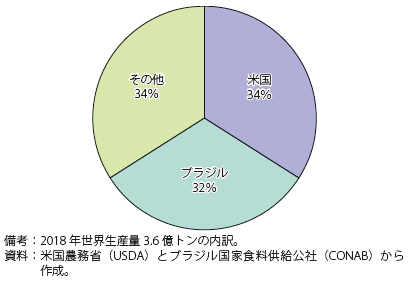
第Ⅱ-2-3-3-21図 米国及びブラジルからの中国大豆輸入額の推移
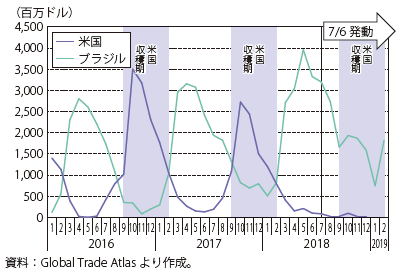
しかし、当該関税賦課により米国の対中大豆輸出は激減し、2018年の下半期は対前年同期比で96.7%も減少し、対世界輸出は同34.7%減少する結果となった(第Ⅱ-2-3-3-22図)。中国は米国産大豆の代わりに、ブラジル産大豆の輸入を増加させて代替したため、ブラジルの同年下半期の対中輸出は前年同期比75.9%の増加、対世界輸出は同63.1%の増加となった(第Ⅱ-2-3-3-23図)。
第Ⅱ-2-3-3-22図 米国の対世界大豆輸出(下半期版、額、量)
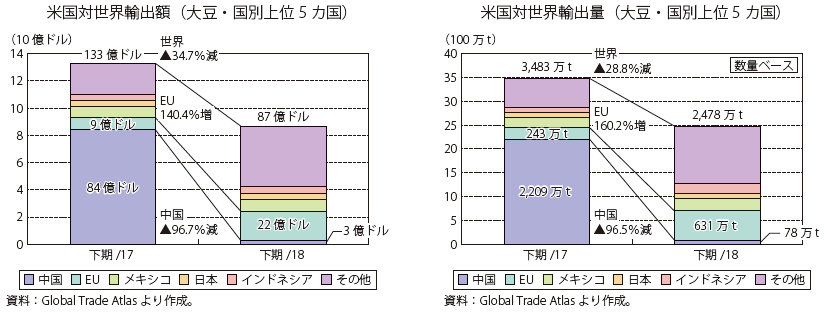
第Ⅱ-2-3-3-23図 ブラジルの対世界大豆輸出(下半期版、額、量)
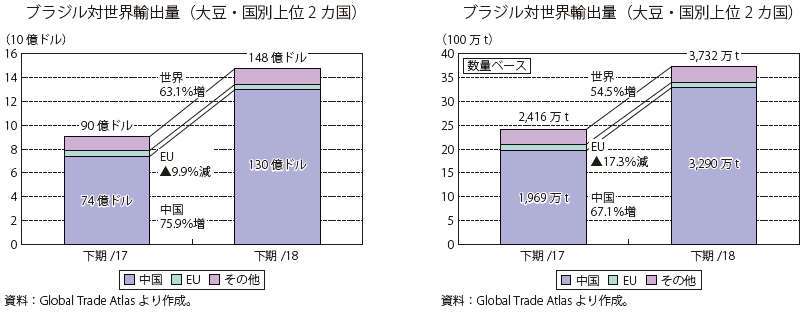
こうした急激な輸入代替は、ブラジル産大豆の輸入単価を上昇させ、世界の輸入単価も引上げた(第Ⅱ-2-3-3-24表)。さらに影響は各地の大豆需給にも及び、各地のマーケット価格にも反映され、ブラジル価格は2018年初比で130以上に上昇し、逆に米国は80まで減少した(第Ⅱ-2-3-3-25図)。
第Ⅱ-2-3-3-24表 世界大豆の輸入単価の推移
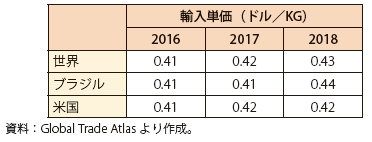
第Ⅱ-2-3-3-25図 大豆価格(米国、ブラジル)
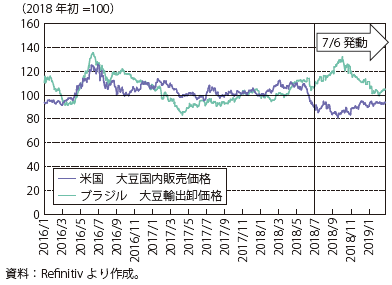
一方、こうした価格変動を受け、EUでは米国からの大豆輸入を増加させている(第Ⅱ-2-3-3-26図)。具体的には、同年下半期のEUの対米国輸入は前年同期比で113.2%増加(米国統計では140.4%増加)した。またその一方で、ブラジルでは同下半期の対EU輸出を9.9%減少させている。なお、EUが米国産大豆の輸入量を増加させた要因としては、主に価格の問題が大きいと考えられる。なお、同年7月25日の日EU首脳間の貿易障壁の撤廃に向けた合意の中で、米国産大豆の貿易拡大を進めるとの項目も含まれている219。
第Ⅱ-2-3-3-26図 EUの大豆輸入(下半期版、額)
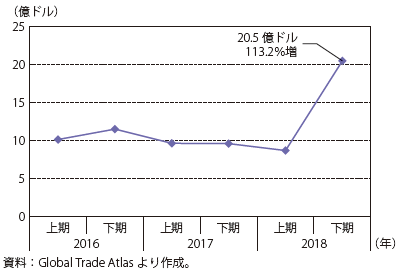
以下、各国における影響をもう少し詳しく見ていく。米国では輸出の急激な大幅減により、既に低い水準にあった国内大豆価格が更に下落し、国内大豆農家が大きなダメージを受けた。大豆農家を中心とする窮状に対し、米国政府は2018年に国内農家向けに貿易摩擦による被害を補てんするための補助金を200億ドル以上拠出したが220、大豆の主要産地である中西部の農家の倒産件数は増加している(第Ⅱ-2-3-3-27図)。米国の好景気を受け、国全体では倒産件数は減少していること221を考えると、中西部の農家への影響の大きさがうかがわれる。
第Ⅱ-2-3-3-27図 米国農家の倒産件数の増加
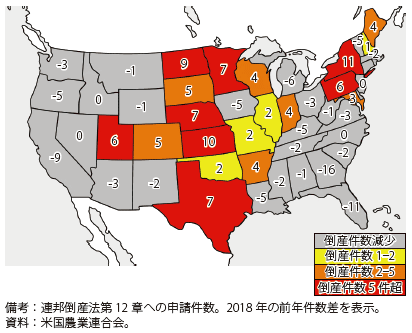
一方、ブラジルでは輸出大豆価格の上昇とともに、中国への大豆輸出量も劇的に増加しており、米中貿易摩擦による漁夫の利を得たようにも捉えられる。しかしながら、季節性を無視して輸出を増やした結果、大豆在庫は大幅に縮小し、2018年末時点の在庫量が75万トンと前年比10分の1に減少している(第Ⅱ-2-3-3-28図)。2018年は在庫放出による輸出増で対応ができたとしても、今後持続的に輸出を拡大し続けることには限界があると思われる。ブラジルの大豆農家は、作付面積を増やして生産を増やすという選択肢もあるものの、米中間の交渉の行方次第では、従来とおり米国の中国向け大豆輸出が再開される可能性もあり、先行きの不確実性という大きなリスクを負うこととなる。なお、大豆の作付面積の推移を見ると、2019年に入り米国の作付面積が減少したことから、足下ではブラジルの作付面積が米国を上回るレベルとなっている(第Ⅱ-2-3-3-29図)。今後の動向については、米中交渉の行方とともに注視が必要であろう。
第Ⅱ-2-3-3-28図 大豆在庫(米国及びブラジル)
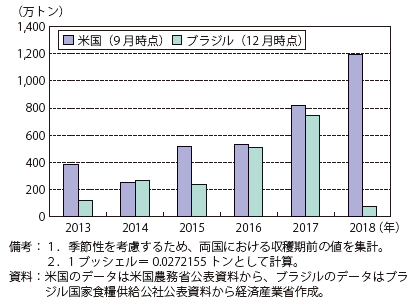
第Ⅱ-2-3-3-29図 大豆作付面積(ブラジルと米国)
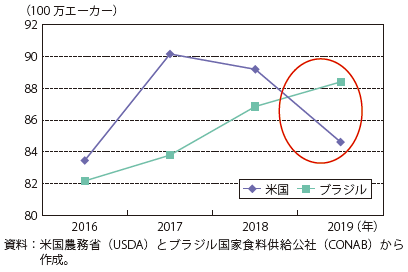
また、中国について見ると、米国からの大豆輸入をブラジル産の大豆輸入で代替したものの、2018年の大豆輸入総量は前年比で減少している(第Ⅱ-2-3-3-30図)。輸入大豆の消費用途である大豆油を他の油に代替するとともに、畜産業の飼料における大豆粕の割合を減少させることで、ニーズを減少させているとの声222もあるが、一方で、飼料の入手が困難なことから廃業寸前に追い込まれているという養豚農家もいるとの報道223もある。上述したとおり、ブラジルが米国産大豆の輸入減少分を代替して対中大豆輸出を増やし続けることが持続的には困難と思われる中、もともとの米国産大豆の輸入量の規模に鑑み、十分に代替が可能な新たな大豆輸出国を見つけることも容易とは思えず、国内需要を短期的に代替商品で対応することにも限界があると思われる。こうしたことから、中国にとっても中長期的には厳しい状況に置かれる可能性が高いと考えられる。
第Ⅱ-2-3-3-30図 中国の対世界大豆輸入
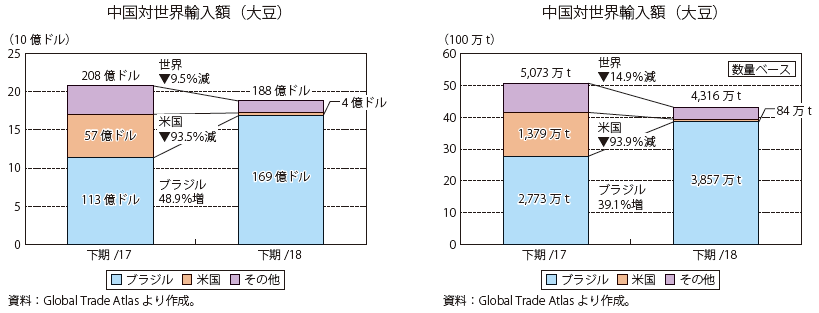
219 Jetroビジネス短信(2018年7月26日)「EU米国首脳会談、摩擦から協調の道探る共同声明(EU、米国)」
220 Jetroビジネス短信(2018年12月27日)「米国農務省が大豆農家への73億ドル支援を発表、貿易紛争の影響緩和支援金第2弾」
221 American Farm Bureau Federation (2019).
222 日経ビジネス(2019年11月2日)「中国・追加関税がもたらした輸入大豆の供給不足」。
223 AERA.dot(2018年12月26日)「米中貿易戦争で中国に大ブーメラン“大豆ショック”で畜産崩壊寸前!」
(3)貿易摩擦の影響分析例
米中の貿易摩擦の激化を受け、数多くの国際機関やシンクタンク等が関税の掛け合いによる経済的影響分析を発表している。ここではIMFとOECDのモデル分析を紹介したい。
IMFは、2018年10月に米国とその貿易相手国との間の追加関税賦課の影響について、5つのシナリオに分け、分析を行っている(第Ⅱ-2-3-3-31図、第Ⅱ-2-3-3-32図)。シナリオ1では、2018年10月時点の米国による通商拡大法232条に基づく鉄鋼及びアルミニウムの輸入に対する関税と、通商法301条に基づく中国からの輸入に対する対象品目224に対する追加関税及び当該追加関税に対する中国の対抗措置関税を想定している。シナリオ2では、シナリオ1に加えて、米国が中国に対して2017年2,670億ドル相当の更なる追加関税を課し、中国も米国からの輸入の全量(シナリオ1との合計:1,300億ドル225)について対抗措置関税を課すことを想定している。シナリオ3では、シナリオ2に加えて、米国が自動車及び同部品に対して25%の関税を賦課し、これに対し、米国の貿易相手国が同程度の対抗措置を実施することを想定している。シナリオ4では、シナリオ3に加えて、貿易戦争による不安から企業が投資計画を変更することを想定している226。シナリオ5では、シナリオ4に加えて、米中貿易摩擦が最悪に至った場合には、企業収益が▲15%下押しされるとの推計を基に市場への影響等を試算している。
第Ⅱ-2-3-3-31図 IMFによる影響分析(シナリオ1~5:米国と中国への影響)
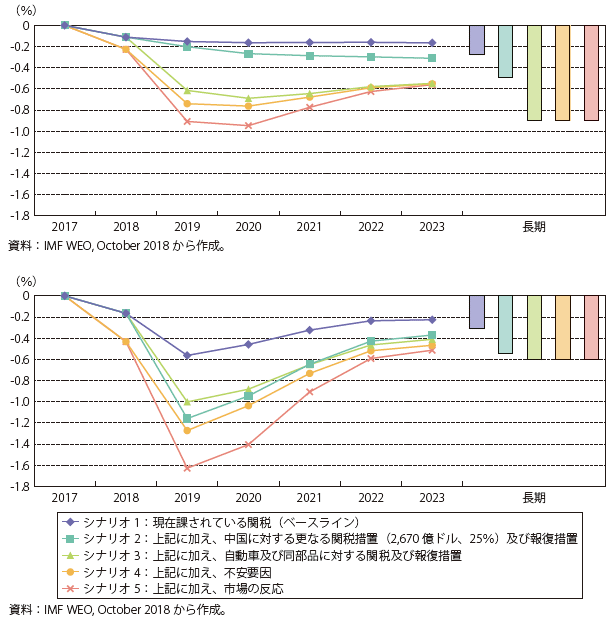
第Ⅱ-2-3-3-32図 IMFによる影響分析(シナリオ5:地域別)
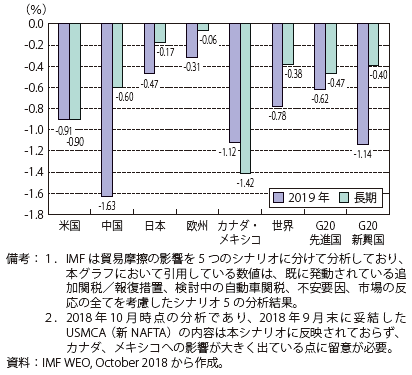
米国による追加関税及び対抗措置関税による影響が顕在化する2019年の米国GDPへの影響をみると、通商法301条及びその対抗措置を前提としたシナリオ1及び2の影響は▲0.2%程度に留まる。一方、同年のシナリオ1及び2の中国GDPへの影響は、▲1.2%弱であり、米国GDPへの影響の約6倍になる。しかし、これにシナリオ3の自動車関税の影響を加えると、自動車を主要輸出品目227とする米国GDPへの悪影響の規模は▲0.6%に跳ね上がり、シナリオ4の信用不安やシナリオ5の市場への影響を加味すると、合計で▲0.9%のマイナスとなる。一方で、中国は、シナリオ3(自動車関税)によるマイナスの拡大はさほど大きくなく、シナリオ5の市場への影響を加味した場合のインパクトが大きい。これは、シナリオ5において、一般的に企業の資金調達環境が先進国に比べて新興国が厳しいため、中国への悪影響が大きく出たものと推察される(第Ⅱ-2-3-3-31図-②)。また、最大の影響を考慮したシナリオ5について、地域別に影響をみると、2019年には全世界で約▲0.8%の影響があり、長期的には、約▲0.4%の影響があると試算されている。なお、本分析は2018年9月までに妥結されたUSMCA(新NAFTA)の内容を反映しておらず、NAFTAへの影響が大きく示されている点に留意が必要である。我が国についても同様に、米国との自動車貿易結びつきの強さを背景に、2019年は約▲0.5%、長期では約▲0.2%の影響が試算されている(第Ⅱ-2-3-3-32図)。
次にOECDによる米中間の追加関税賦課による影響分析を紹介したい。OECDは、2018年11月に4つのシナリオに分けて、米中関税の2021年までのGDP及び貿易への影響について分析を行っている(第Ⅱ-2-3-3-33図)。シナリオ1は、2018年9月までに米中の二国間貿易に課されている関税の影響を分析したものである。シナリオ2は、2019年1月から米国が中国からの物品の輸入2000億ドル相当について、10~25%の追加関税を課し、これに対して、中国が600億ドル規模の対抗措置関税措置を発動することを想定している。シナリオ3は、2019年7月から残りの物品以外の貿易全てについて、25%の関税が課されることを想定している。シナリオ4は、3年間にわたって世界的にリスク・プレミアムが50bps上昇する228ことを想定している。
第Ⅱ-2-3-3-33図 OECDによる影響分析
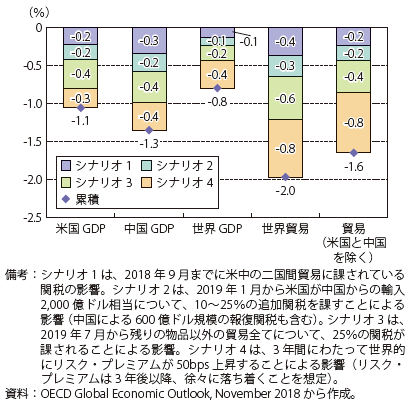
シナリオ1においては、単に世界の貿易量が減少するだけでなく、生産者コストの上昇や消費者物価の高騰229が経済を下押しし、世界のGDPが▲0.1%減少するとされている。特に、短期的には、米中以外の諸国は、米国内市場における競争力が増すことによる恩恵を受けるものの、長期的には巨大市場である米国及び中国における需要の減少によりその代替効果が打ち消されると言及されている。
シナリオ2においては、世界及び米中両国のGDP及び貿易への影響がシナリオ1の2倍程度まで拡大するとされている。特に、米国の消費者物価が+0.6%上昇すると想定されている点が大きい。
シナリオ3においては、2020年及び2021年の米中間の輸入量が約▲2%減少するとされる。また、2021年には、米国における企業投資が約▲2%減少し、消費者物価が+0.9%上昇することによる米国GDPの縮小(約▲0.75%)の影響が大きいとされている。特に、米国と経済的な結びつきの強いメキシコやカナダにおいては、GDPが▲0.25%程度減少するとされている。
シナリオ4においては、通商政策の不確実性やより幅広い品目に対する関税引上げの懸念により、世界中で企業の投資計画に悪影響が及ぶことを想定している。全世界で3年間にわたって投資リスク・プレミアムが50bps上昇すると、資本コストが上昇し、関税による影響と相まって、世界のGDPは2021年までに約▲0.8%縮小するとされている。
なお、これらの分析はあくまで一定の過程を置いた経済モデル分析に過ぎず、実態はモデル分析では考慮しきれない様々な経済的変動要因が存在する。本書執筆時点ではIMF、OECDの二つの分析におけるシナリオ1に該当する状況下にあるが、これらの分析とは異なり、実態としては、先述したとおり経済的影響はより米国に大きく出ているようにも捉えられる。米中の貿易摩擦が長期化あるいは激化した場合に、中長期的にどこまで影響が広がるか、正確に捉えることは非常に困難と言え、これらの分析もあくまで一つの参考として捉えるべきことに留意が必要である。
224 第1弾(2018年7月6日発動)、第2弾(8月23日発動)、第3弾(9月24日発動)を含む。
225 2017年の米国貿易統計に基づく概算値。
226 世界金融危機の1/6程度の投資への下押し影響を試算に組み入れ。
227 2018年米国輸出品目に占める自動車等の割合は7.8%であり、対抗関税措置の影響を大きく受けるものと推察(第Ⅰ部第3章(1)米国参照。)
228 リスク・プレミアムは3年後以降、徐々に落ち着く前提。
229 米国の消費者物価は2019年と2020年に0.2%ずつ上昇するとしている。
(4)貿易制限的措置の弊害
上述のとおり、足下の関税引上げ措置の掛け合いが、世界の貿易の流れを恣意的に変えることとなり、発動国、被発動国という当事国のみならず、第三国へも影響を及ぼしたり、関税引上げ措置の連鎖を招いている現状が確認された。また、当事国間の貿易交渉の進捗次第では、再び貿易の流れが変わる可能性もあり、そうした先行きの不確実性は経済活動を行う様々な主体にとって経営判断における大きなリスクとなり、経済活動の停滞に繋がり、ひいては世界経済の減速にも繋がる危惧が存在する。
また、こうした貿易制限的な一方的措置は、多角的貿易体制を基本とするWTOの理念と基本的に相いれない。WTO協定上、WTOの紛争解決手続に基づかない一方的な制裁措置の発動を明示的に禁止している。多角的貿易体制は、それを規律するWTO協定を始めとする国際ルールを各国が遵守することによって成り立っており、そこで生じた紛争は、一方的措置を用いてではなく、国際ルールに基づく紛争解決手続によって解決されるべきである。また、一方的措置を背景とする交渉により成立した二国間の合意は、その内容が最恵国待遇の原則から逸脱したものとなる可能性があるほか、このような措置は、制裁措置、対抗措置の応酬による一方的措置の悪循環を招来する危険もある。この点からも、一方的措置がWTOの目指す自由貿易体制を害するものとならないよう、注視していく必要がある。