

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第2章 第4節 新たな国際秩序構築の必要性
第4節 新たな国際秩序構築の必要性
第1節において述べたとおり、1930年代に蔓延した保護主義が第二次世界大戦の一因になったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し1948年にGATT、1995年にはGATTを発展的に改組したWTOが設立された。その後、世界金融危機時に各国経済が悪化した際には、保護主義が広まることが懸念されたが、WTOの追加モニタリングやG20を中心とした国際協調の機運の維持によって保護主義の蔓延が回避されてきた。しかし、直近数年間においてはWTOを始めとする多角的貿易体制や国際協調の動きが、保護主義の広がりへの歯止めとしての機能を十分に果たすことができていないとの指摘がある。世界金融危機以降、毎年のG20首脳会議宣言で記載されていた「保護主義と闘う」との文言が、2018年のブエノスアイレスG20首脳会議宣言で初めて記載されなかったことは象徴的な事例と捉えられる。
1.多角的貿易体制の機能不全への危惧
世界銀行、IMF、WTOが2018年9月に共同で発表したレポートである“Reinvigorating Trade and Inclusive Growth”は、2000年代初めから停滞しているWTOを中心とする多角的貿易体制の改革が、更なる世界の経済成長のための鍵であると述べている231。以下、WTOの3つの機能である①ルールメーキング、②監視メカニズム、③紛争解決のそれぞれが直面している課題について紹介する。
231 IMF, World Bank, WTO (2018), p. 4。
(1)ルールメーキングの停滞
1948年に発足したGATT体制の下、締約国は8度に渡る多角的交渉を行い、自由かつ公正な貿易ルールの策定を目指してきた。数次のラウンド交渉232を経て、次第に関税削減が実現され、関税以外の貿易関連ルールも整備された。WTOは、それまでGATTが担ってきたラウンド交渉を通じた物品貿易に係る関税及び非関税障壁の削減や予見可能性を高めるための通商ルールの強化・充実に加え、規律範囲を拡大し、新たにサービス貿易、知的所有権の貿易的側面についても対象としている。一方で、ラウンド交渉は、全会一致を原則としているため、規律範囲の拡大や、加盟国数の増加による利害関係の複雑化により、合意が困難となってきており、ラウンドの期間も年々長期化している(第Ⅱ-2-4-1図)。
第Ⅱ-2-4-1図 WTO加盟国数及びラウンド期間・テーマ数
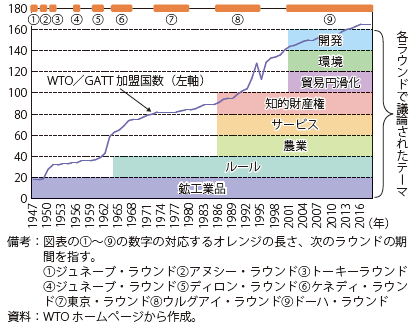
特に2001年に立ち上げられたドーハ・ラウンドは、農林水産物や鉱工業品の貿易のみならず、サービス貿易の自由化に加え、アンチダンピングなどの貿易ルール、貿易と環境、開発のほか、ルール作りを検討すべき分野として投資、競争、貿易円滑化なども含まれた。ラウンド交渉は全会一致を原則としているため、先進国と新興・途上国間の利害対立により交渉がなかなか進まず、2001年の立ち上げ後、交渉の再開と中断を繰り返す一進一退の状況にあった。2008年7月の閣僚会合において特別セーフガード・メカニズム(SSM)を巡る対立によって会合が決裂された後、交渉が停滞した。2011年12月の第8回閣僚会議では、議長総括における「政治ガイダンスの要素」として、ドーハ・ラウンドについて、近い将来の一括受諾の見通しが無いことを認めつつも、「新たなアプローチ」を見出す必要性を共有し、進展が可能な分野で、先行合意を含め議論を進めることが合意された。その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発、が進展可能な分野であるとの共通認識が形成され、2013年12月にインドネシア・バリで開催された第9回WTO閣僚会議において精力的な交渉の結果、WTO設立後初のマルチ協定である貿易円滑化協定を含むバリ・パッケージが合意された。
第10回WTO閣僚会議(MC10)においては、14年間の長期の交渉にも関わらず十分な成果を出せていないドーハ・ラウンド交渉に代わる「新たなアプローチ」が必要であるとする先進国と交渉継続を主張する新興・途上国の間での見解の懸隔が明らかになった。また、GVCの深化やIT技術など時代の変化に対応するための新たな課題についても、米国、EU、日本等の先進国と新たな課題への取組に慎重な姿勢を示すインド、中国等の新興・途上国の間で意見は対立した。
232 1960年に開始された第5回交渉(ディロン・ラウンド)以降、多角的交渉は「○○ラウンド」と呼ばれるようになった。
(2)監視メカニズムの形骸化
WTOの主要機能の一つである監視メカニズムは、
① 自国の法律・政策に関する通報義務
② 貿易政策検討機関(TPRB)によるレビュー
③ 世界金融危機後にWTO事務局によって定められたモニタリング活動(WTO・UNCTAD・OECD共同の監視報告書)
に3つに分類することができる233。
これらのメカニズムは、加盟国の貿易政策・措置に関する情報を、収集・評価・公表することで、貿易紛争に発展することを未然に防止するための活動と位置付けることができる。近年の貿易制限的措置について、Global Trade Alert234より措置の内訳を見ると、輸出関連措置の割合が低下している一方で、補助金235や貿易関連投資措置236といった非関税障壁の割合が増加し複雑化している(第Ⅱ-2-4-2図)。このように、外部から各国の貿易制限的措置の実態を把握することがより困難となっており、加盟国が自国の措置を通報することの重要性が高まっている一方で、通報義務を果たさない国が増えていることが問題視されている237。
第Ⅱ-2-4-2図 貿易制限的措置件数と措置別割合の推移
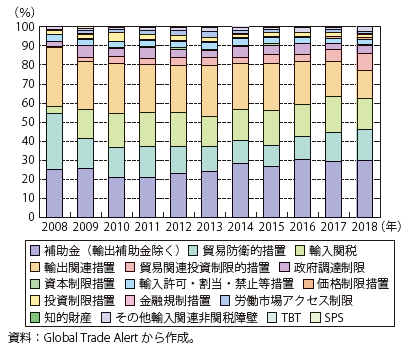
ここでWTOの各協定によって定められている、加盟国に対する通報義務について整理すると、自国の法律・政策による貿易政策・措置は多岐にわたる(第Ⅱ-2-4-3表)。
第Ⅱ-2-4-3表 WTOの各協定に定められている通報が必要な法律・政策一覧
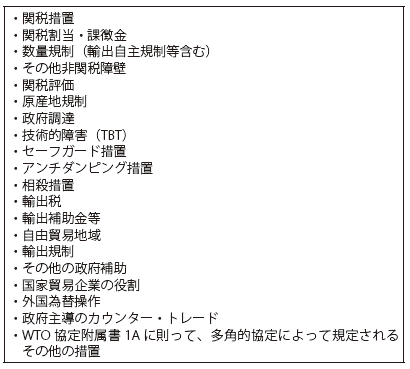
通報義務の中でも、補助金については、規定に該当する措置の有無にかかわらず、毎年6月30日までに、通報を行う義務が各加盟国に対して課されている(委員会での決定により、実際には2年に一度通報することとなっている)。そのため、すべての国が通報義務を順守しているのであれば、通報国の割合は100%にならなければならない。しかし現実においては、2011年には65%を超えていた通報国の割合が、加盟国の増加に伴い年々通報率は減少している(第Ⅱ-2-4-4図)。この要因の一つとしては、通報するキャパシティを持たない途上国238が加盟国として加わったことが考えられる。さらには2015年から2017年にかけては、新たな加盟国はなかったものの、通報率が5%以上低下している。これは、2015年には通報を行っていた国(通報するキャパシティを持つ国)が通報を行わなくなったということであり、意図的な義務違反国が存在239する可能性が示唆される。また、通報が年に1度は行われた場合においても、通報された内容が正確ではなく、通報義務違反となっている可能性がある点にも注意が必要である。
第Ⅱ-2-4-4図 補助金通報国の割合
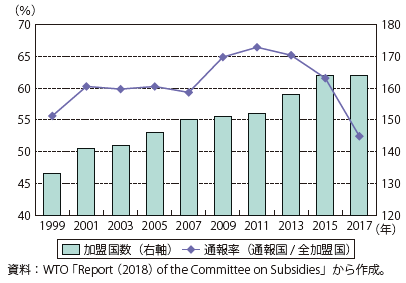
補助金については2011年以降、年々通報率が低下する一方で、加盟国に占める通報国の割合が、年々上昇している通報措置も存在する。その一例として、技術的障害(TBT)の通報国の割合は、1995年時点では、20%前後であったのに対して、2009年以降に一時的な下落はあったものの、2013年以降持ち直し、2018年には50%を超えた(第Ⅱ-2-4-5図)。
第Ⅱ-2-4-5図 TBT通報件数及び割合
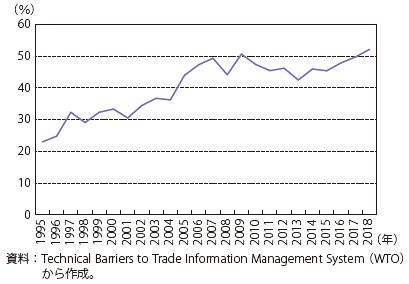
このように加盟国によって積極的に通報が行われる措置については、協定との整合性について理事会・委員会において議論されることによって、貿易紛争よりも加盟国やWTOにとって低いコストで貿易紛争を解消されることが期待される240。
233 WTO (2013) “The History and Future of the World Trade Organization”, p. 271。
234 分類された措置の具体的な内容については、UNCTAD (2015) “International Classification of Non-Tariff Measures 2012 Version”を参照。
235 輸出補助金を除く政府等の資金拠出、貸付、保証、資本注入、収入や価格支援等。
236 ローカルコンテンツ要求・輸入品使用制限等。
237 経済産業省(2018)「不公正貿易報告書」、pp. 240~241。
238 European Commission (2018) “WTO modernization – Introduction to future EU proposals” (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf![]() )。
)。
239 同上。
240 European Commission (2018) “WTO modernization – Introduction to future EU proposals” (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf![]() )。
)。
(3)紛争解決の長期化
各国間で問題のある貿易制限的措置を解消するための有効な手段を果たしてきたWTOの紛争解決手続だが、近年では紛争処理の長期化の問題が指摘されている。そこで、WTO紛争処理に持ち込まれた案件について、パネル設置要請から上級委員会(以下、上級委)採択までの期間がどのように変化したかを見てみる。パネル設置要請から上級委採択までに要する平均日数は、2003年から2005年にかけて長期化し、その後変動を繰り返しながらも趨勢としては増大する傾向にあった。特に2013年以降は長期化の動きが激しくなり、2018年に上級委で採択した案件は、平均で1,180日を要しWTO発足時からの平均期間である704日を大幅に超える期間が紛争処理に要するようになっている。毎年の採択件数に大きな変動は見られないため、容易に解決できない案件が増加していることがうかがえる。これは、協議要請が行われた後にパネルを設置する割合が増加傾向にあることとも関係していると考えられる。1990年代には、二国間協議要請があったもののパネル設置要請が行われず、紛争処理手続に依らずに解決する案件が多く見られたが、近年ではパネル設置要請がされる割合が高くなっており、紛争解決手続の利用が積極的に活用されているためだと考えられるが、他方で、案件が高度に技術的で事実認定が困難であったり、解釈が困難な法的論争が争点となっている等により、審理期間が伸ばされ、遅延する傾向が強いと言われている。
第Ⅱ-2-4-6図 パネル設置要請から上級委員採択までの平均日数と手続日数の内訳
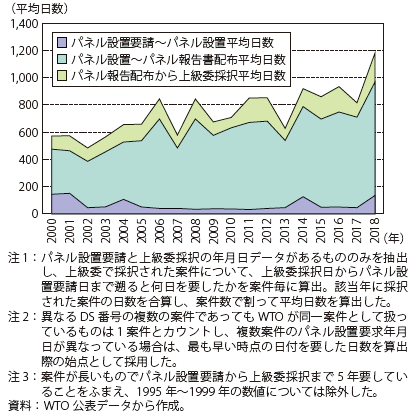
2.地域間協定の進展
近年、世界の主要国によって貿易・投資の拡大のための二国間又は地域における地域間協定(Regional Trade Agreement、以下RTA)の締結が積極的に行われてきている。WTOにおけるルールメーキングの停滞を背景に、基本的な考え方を共有する国・地域との間で通商ルールの構築を迅速に行うことで、制度構築を先取りするものと言える。RTAの発効件数については、1990年代後半より大幅に増加し、2008年をピークにして、2018年3月現在において、累計で約300件のRTAが締結されている。特徴としては、1990年代にかけては、財貿易に関するRTA(関税の引上げ等)が主であったのに対して、2000年代からは、サービス分野におけるルールも含むRTAの割合が上昇している(第Ⅱ-2-4-7図)。
第Ⅱ-2-4-7図 RTA発行件数の推移
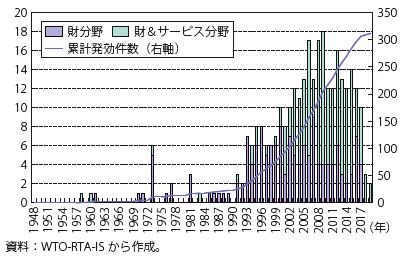
地域別の内訳としては、新興・途上国間においては、財分野にとどまるRTAが3分の2を占めるのに対して、先進国間もしくは先進国と新興・途上国間におけるRTAについては、サービスも含む広範なRTAの件数の方が多い(第Ⅱ-2-4-8図)。
第Ⅱ-2-4-8図 RTAの地域別内訳
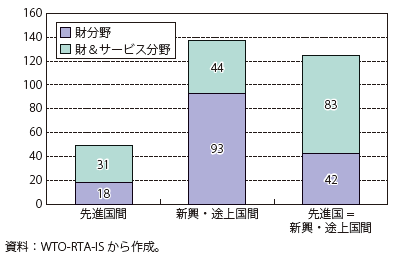
また、国別の締結数に関しては、EUを含むヨーロッパ諸国に次いで、比較的早期の段階からRTAの締結に積極的であったチリ、シンガポール、トルコ、ペルーの締結数が多い(第Ⅱ-2-4-9図)。国別の総締結数では、日本は14位に位置する一方で、サービス分野を含むRTAに限ると、日本はチリ、シンガポール、EUに次いで4位であり、日本が包摂的で、高いレベルのルール作りを牽引していることが分かる(第Ⅱ- 2-4-10図)。
第Ⅱ-2-4-9図 国・地域別RTAの締結数
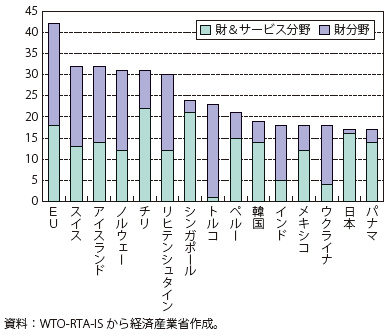
第Ⅱ-2-4-10図 国・地域別RTAの締結数(サービス分野の協定を含む)
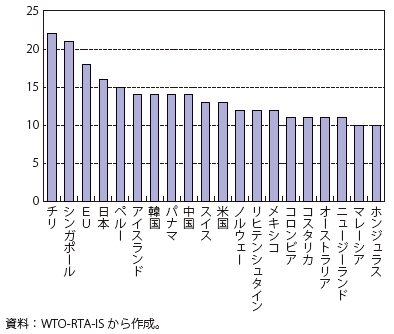
一方で、世界の総輸出・輸入額に占める、RTA締結国間の貿易の割合は、2000年において30%前後であり、その後年々上昇している。しかし、依然として50%を下回っており、164加盟国が対象となるWTOにおけるルールメーキングが、依然として重要であることがうかがえる(第Ⅱ-2-4-11図)。
第Ⅱ-2-4-11図 世界の総輸出入に占めるRTAカバー率
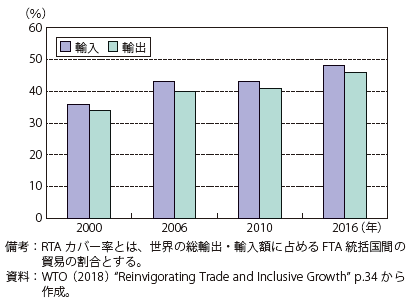
3.新たな分野に対応したルール形成の必要性
(1)デジタル・ディスラプション
デジタル技術を用いた新規参入者の登場によって、既存の産業にゲームチェンジが起こることを「デジタル・ディスラプション」と呼ぶ。1990年代に音楽や小売業界からディスラプションの波が到来し、2000年代にはメディアや観光、人材業等、2010年代には卸売や金融において、それぞれ既存の産業構造に変革が起こされてきた(第Ⅱ-2-4-12表)。
第Ⅱ-2-4-12表 これまでのデジタル・ディスラプションの例
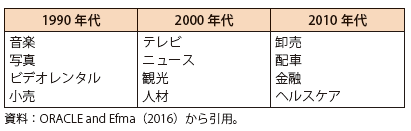
そのインパクトの大きさの一例として、音楽産業においては、2000年代においては、250億ドル規模あったCD、DVD等の世界的な売上は、2000年代からのデジタル媒体での音楽販売の出現によって絶対額・割合ともに低下し約1/5程度まで減少した。その一方で、デジタル媒体については、増加の一途を遂げており、現在は10億ドル程度まで増加し、世界の音楽販売総売上の半分強を占めるまでに至る。さらには、2013年頃より急速にストリーミングの割合が上昇しており、デジタル分野の中においても、ディスラプションが起こっていることが分かる(第Ⅱ-2-4-13図)。
第Ⅱ-2-4-13図 音楽業界の形態別売上の推移
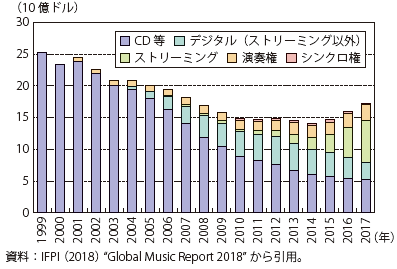
また、日本国内のメディア業界におけるディスラプションのインパクトを捉えるべく、日本におけるメディア別の広告費用に着目すると、広告費用全体の額が毎年増加する中、既存媒体であった新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・プロモーションメディアの絶対額が減少し、全体に占める割合が低下する一方で、インターネットを通じたメディア広告が急速に拡大している(第Ⅱ-2-4-14図)。
第Ⅱ-2-4-14図 日本におけるメディア別広告費用の推移(億円)
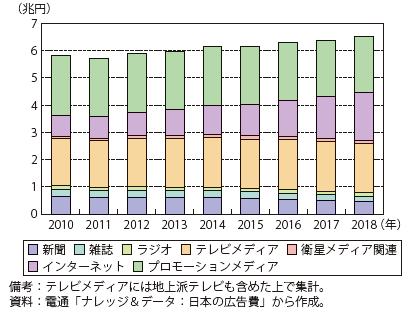
このように、既存の産業構造への大きなインパクトを及ぼし得るデジタル・ディスラプションであるが、あらゆるモノが繋がるIoTの進展によってデータ量が爆発的に増加し、AIやクラウド、ブロックチェーン等の技術によってそれらのデータの利活用が進む中、これまでのように一部の産業ではなく、産業横断的にデジタル・ディスラプションが起こり得る可能性がある。
(2)デジタル貿易の動向
データ量の爆発的な増加に加え、国境を越えたデータのやり取りは、指数関数的な増加を遂げてきた(第Ⅱ-2-4-15図)。また、データ流通の地理的な分布について、情報を大量に高速でやりとりできるブロードバンド契約数の地域別割合に着目する。ブロードバンド契約数は2000年から急激に増加しているが、その割合を地域別に見ると2000年では欧州と北米で65%程度を占めていたが、2017年には東アジア・大洋州だけで46%を占めるようになった。ASEAN、南アジア、ロシア・CIS、中東の新興・途上国地域の割合が高まってきており、世界において情報の流通が地域を問わず急速に拡大していることがうかがえる(第Ⅱ-2-4-16図)。
第Ⅱ-2-4-15図 世界の越境データ通信量及びその将来推計
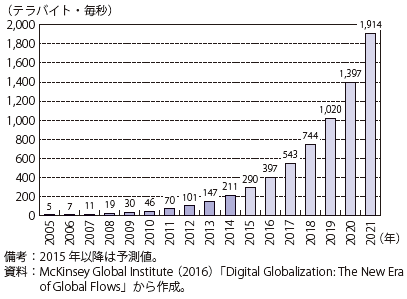
第Ⅱ-2-4-16図 世界の地域別に見たブロードバンド契約件数の推移
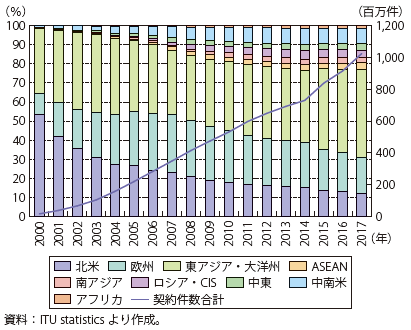
さらには、各国におけるEC市場の広がりによって、EC市場及びサービスを提供するプレーヤーや競争環境もグローバル化している。その一例として、Google Play及びApple Storeにて入手可能な「ショッピング」アプリにおける、各国において最も使用されているアプリ241の国籍に着目する。2018年時点でデータが入手可能な60の国・地域の中で、米国のアプリが1位である国が19か国と最も多く、中国が14か国、アルゼンチンが5か国と次ぐ。なお、自国籍のアプリが最も使用されている国は、60か国中、わずか16か国にとどまる(第Ⅱ-2-4-17図)。
第Ⅱ-2-4-17図 各国内の最も使用されているショッピング・アプリの国籍(2018年)
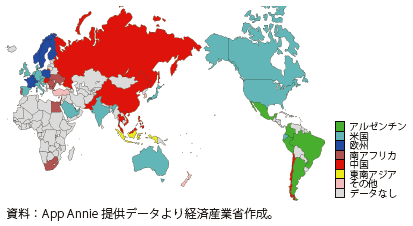
このように、デジタル技術の発展により、国境を越えた経済活動が急速に拡大する中、個人情報や知的財産権等のデータを適切に保護しつつ、自由なデータ流通の実現を目指した、デジタルな空間における国際的なルール作りが急務となっている。
しかし現実においては、データを巡るグローバル競争が厳しさを増す中、各国の産業強化のための恣意的な規制によってビジネス環境が阻害されている。OECDが世界46ヶ国におけるデジタル・サービス貿易に影響を与える国内規制を0~1の間の数値で指標化した「OECDデジタル・サービス貿易制限インデックス」に着目すると、特に新興・途上国において、デジタル貿易における規制度合が高く、BRICs諸国を中心に2013年から2018年にかけて、規制度合が上昇しいていることが分かる(第Ⅱ-2-4-18図)。
第Ⅱ-2-4-18図 OECDデジタル・サービス貿易制限インデックス(2014年、2018年)
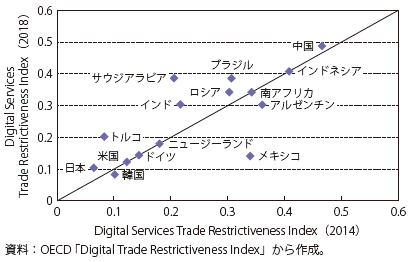
また、具体的なデータ規制の数についても、世界合計が2015年前後に200を超えており、増加率についても、特に2010年以降に伸びが著しく、直近の10年程度で規制数が倍増している(第Ⅱ-2-4-19図)。
第Ⅱ-2-4-19図 世界のデータ規制数
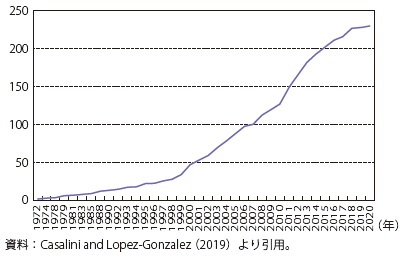
このようなデジタル分野を始めとする新たな分野に対応した国際的なルール形成は喫緊の課題である。
241 単月当たりのアクティブユーザー数(Monthly Active User)の2018年平均を集計。
4.新たなルールベースの国際通商システム構築の必要性
前章でも見てきたように、グローバル化の進展とともに、各国・地域は複雑な相互依存関係を構築しており、世界のいずれの国にとっても持続的・安定的な経済発展のためには円滑な貿易が求められる。WTOを中心とするルールに基づく多角的貿易体制は、自由で公正な貿易を推進・拡大するために不可欠であるとともに、グローバルに経済活動を行う様々な主体にとって、安定的かつ円滑なビジネス環境を提供・維持するものとして重要である。しかし足下では、現状の多角的貿易体制への不満や機能不全への懸念とともに、こうした多角的貿易体制の存続自体への脅威となる保護主義の顕在化に対する懸念が高まっている。グローバルな繁栄、成長、雇用創出を世界各国にもたらし、持続的で安定的な世界経済成長を実現していくためには、国際協調の下、新たな国際秩序を構築することが急務である。
