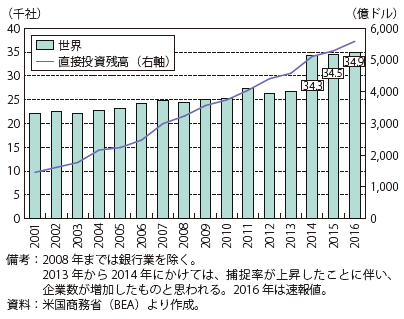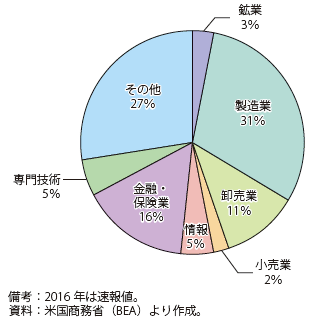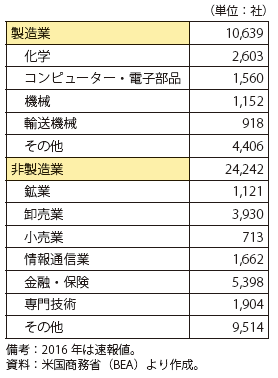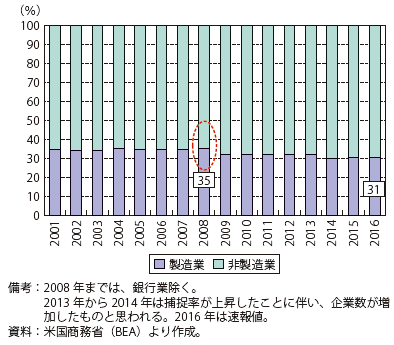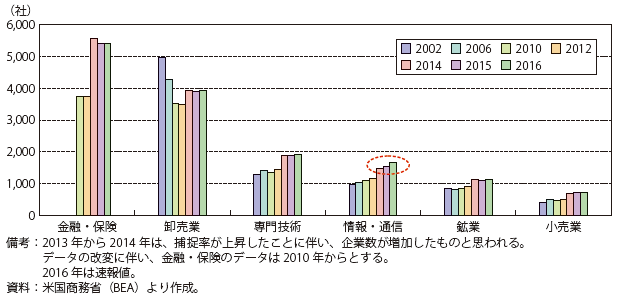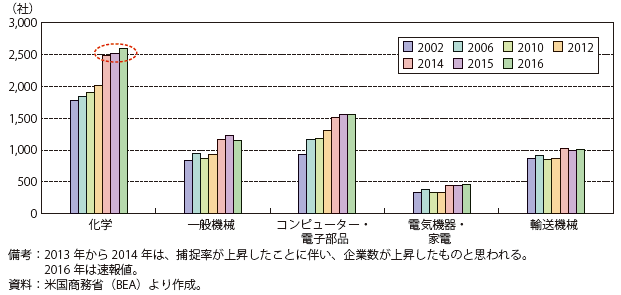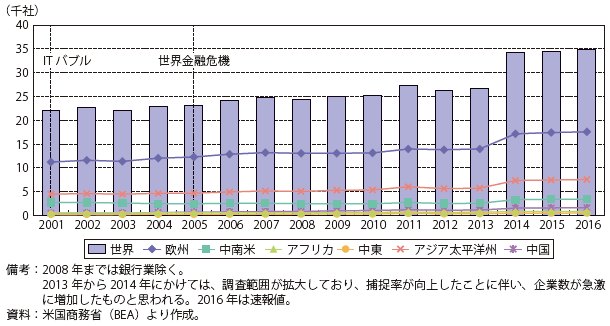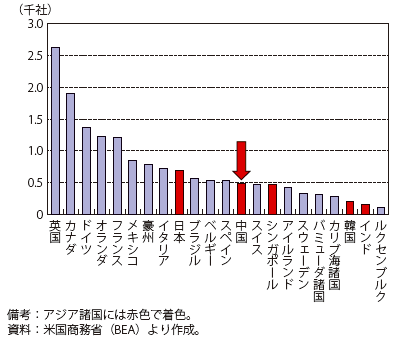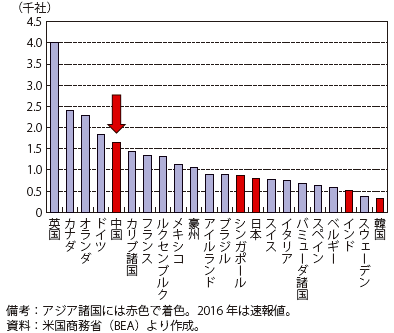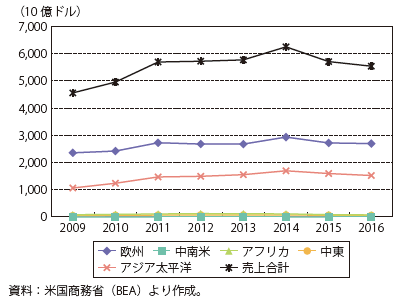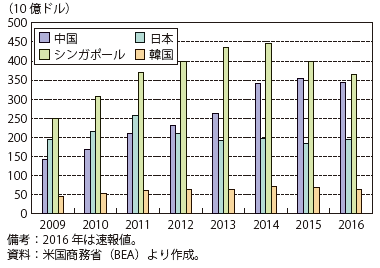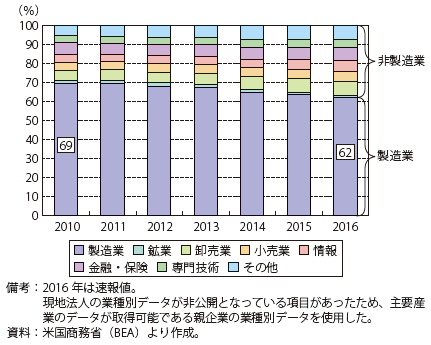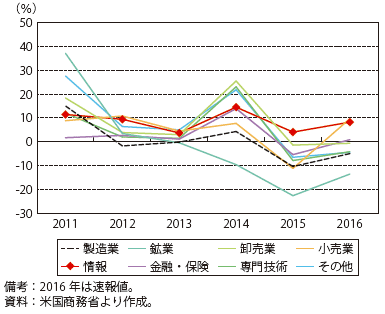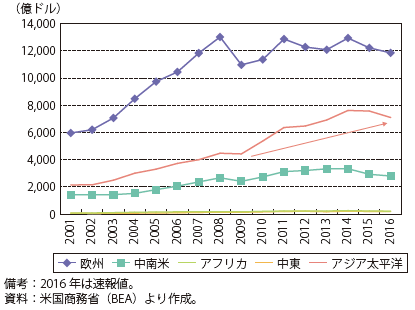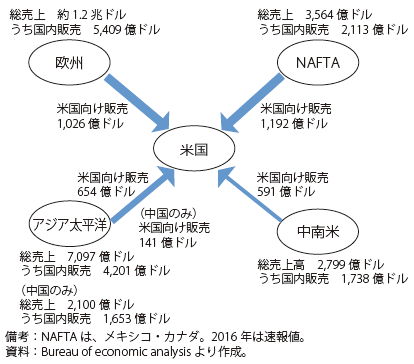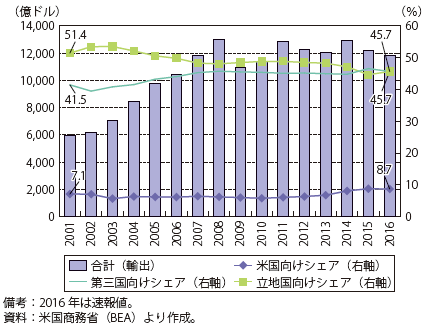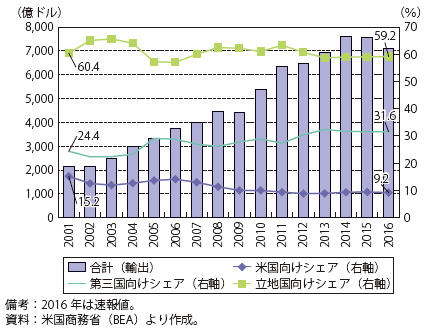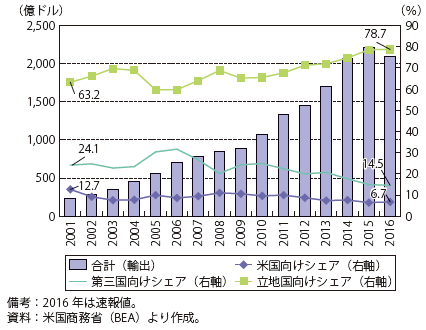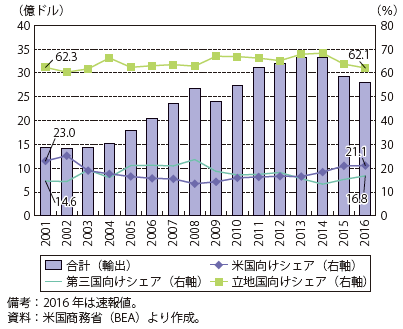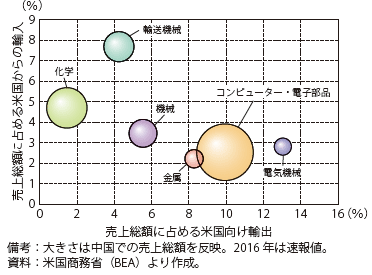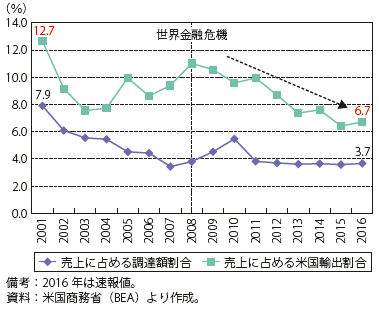- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第3章 第2節 日本を中心としたグローバル・バリュー・チェーンの実態
第2節 日本を中心としたグローバル・バリュー・チェーンの実態
前節では日本の貿易投資動向を概観したが、その背景には、日本の国内企業と海外に展開する現地法人等を結ぶ財の流れ(GVC)がある。日本の貿易の中にはGVCと関わりのない部分も少なからずあるが、国内製造業の輸出の過半は親会社から海外子会社へのものであり、その動向を把握することは重要である。本節においては、このような日本を中心としたGVCの実態について考察していく。
1.日本企業の海外展開
日本企業は、積極的に海外直接投資を拡大し、海外現地法人の設立を通じて海外展開を行ってきた。経済産業省「海外事業活動基本調査」のデータによれば、日系海外現地法人の企業数は、世界金融危機など経済的ショックで一時的に減少することはあったが、趨勢として堅調に増加し、現在、全世界で、製造業約1万1,000社、非製造業約1万4,000社、合計約2万5,000社が操業している(第Ⅱ-3-2-1図)。業種別には、世界金融危機後、製造業が企業数で50%を下回り、非製造業が緩やかにシェアを伸ばしている243。
第Ⅱ-3-2-1図 日系海外現地法人の企業数の推移
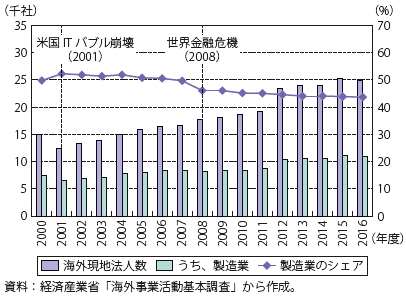
ここでは、まず世界に展開する日系海外現地法人の企業数、売上高、経常利益の推移を見たうえで、次に海外のどこに立地しているのか、地域ごとの特色を概観する。
海外現地法人の売上高は、世界金融危機時などの一時的減少を除けば堅調に増加している(第Ⅱ-3-2-2図)。業種別に見ると、製造業が売上高の50%弱の水準で推移している。一方、経常利益については売上高に比べて変動が激しい(第Ⅱ-3-2-3図)。世界金融危機までは順調に拡大してきたが、その後は減少、回復を繰り返し、伸び悩みが見られる。業種別には、世界金融危機までは、製造業シェアが低下して非製造業が伸びてきたが、金融危機後は製造業のシェアが上昇する動きも見られる。
第Ⅱ-3-2-2図 日系海外現地法人の売上高の推移
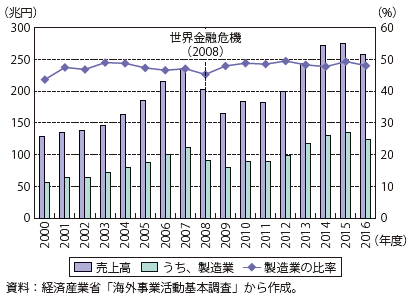
第Ⅱ-3-2-3図 日系海外現地法人の経常利益額の推移
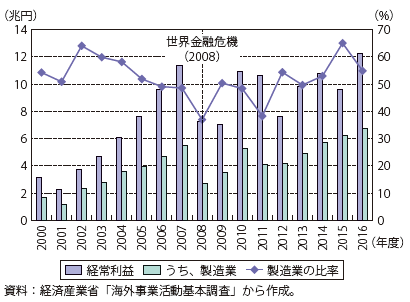
このような中で日本の製造業の海外生産比率は、上昇基調で推移しており、海外の重要性は高まっている(第Ⅱ-3-2-4図)。直近で海外生産比率は23.8%と、世界における日系製造業の全生産の4分の1は海外で行われており、海外に現地法人を有する企業だけで見れば全生産の4割近くが海外生産となる244。業種別には、輸送機械、はん用機械、情報通信機械等が積極的に海外展開をしており、海外生産比率が高い(第Ⅱ-3-2-5図)。
第Ⅱ-3-2-4図 日系製造業の海外生産比率
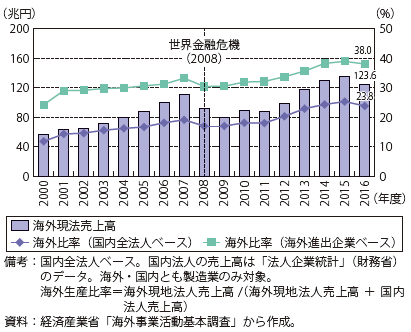
第Ⅱ-3-2-5図 日系製造業の海外生産比率(業種別 / 2016年度)
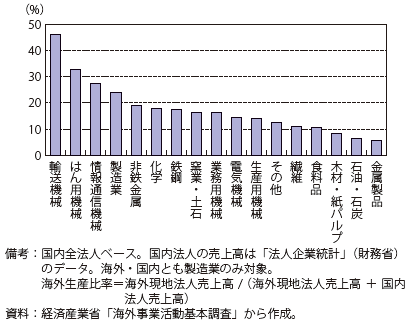
その海外展開先としてアジアの存在感が高まっている。地域別の立地企業数の推移を見ると、製造業においては、米国、欧州の立地企業数がほぼ変わらない中で、アジアへの立地が増加している(第Ⅱ-3-2-6図)。アジアの中では中国の急増が目立ち、ASEAN諸国も緩やかに増加している245。
第Ⅱ-3-2-6図 日系海外現地法人の立地地域別の企業数の推移
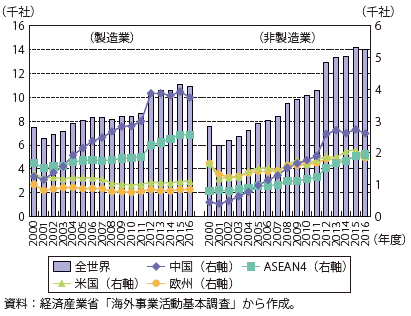
直近(2016年度)時点で見ると、アジアには世界の日系製造業の8割近い約8,300社が立地しており、特に中国、ASEANへの立地が多い(第Ⅱ-3-2-7表、第Ⅱ-3-2-8図)。業種別には、輸送機械、情報通信機械などの機械製造業で半分を占め、鉄鋼、化学などが続いている。また、後で見るように、アジアには最終財の生産を主とする企業とともに、多くの中間財の生産を主とする企業も進出しており、日本からの調達とともに現地国内でも中間財をやりとりする産業集積が形成されていることが示唆される。欧米に比べて相対的に規模が小さい企業が多いのもアジアの特色と言える。アジアでは非製造業も約8,200社が立地しているが、世界の日系非製造業の6割弱と製造業に比べれば世界シェアは低い。非製造業の中では、卸売業が半数以上を占め、サービス業、運輸業が次いでいる(第Ⅱ- 3-2-9図)。アジアでは製造業中心に進出し、それをサポートする商業、サービス、物流、ロジスティクス関係が多く展開していると見ることができるかもしれない。
第Ⅱ-3-2-7表 日系海外現地法人の企業数(2016年度)
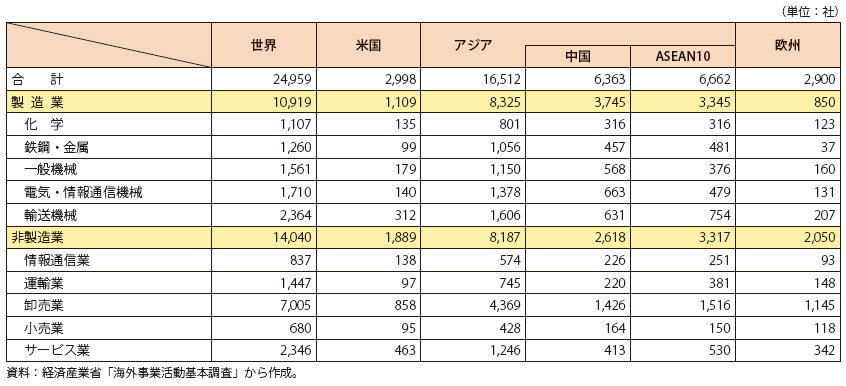
第Ⅱ-3-2-8図 日系海外現地法人の地域分布(2016年度)
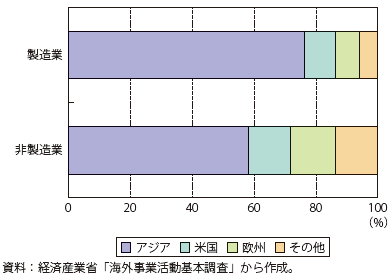
第Ⅱ-3-2-9図 日系海外現地法人の非製造業における業種分布(2016年度)
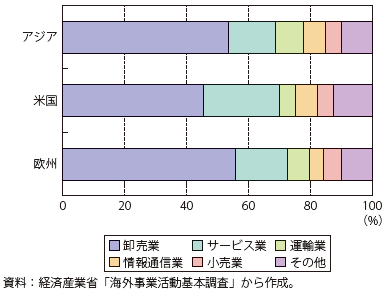
米国、欧州では、アジアと異なり、むしろ非製造業中心の立地となっている。非製造業の中では、卸売業が多いのはアジアと同様であるが、米国ではサービス業シェアが大きい。
海外現地法人の売上高について見ると、製造業ではアジア、特に中国の売上が拡大している(第Ⅱ-3-2-10図、第Ⅱ-3-2-11表)。ただし、米国の売上高は中国、ASEANに匹敵しており、規模の大きな企業が多いことが推測される。非製造業においては米国が突出して拡大しており、アジアにおける売上は必ずしも大きくない。
第Ⅱ-3-2-10図 日系海外現地法人の立地地域別売上高の推移
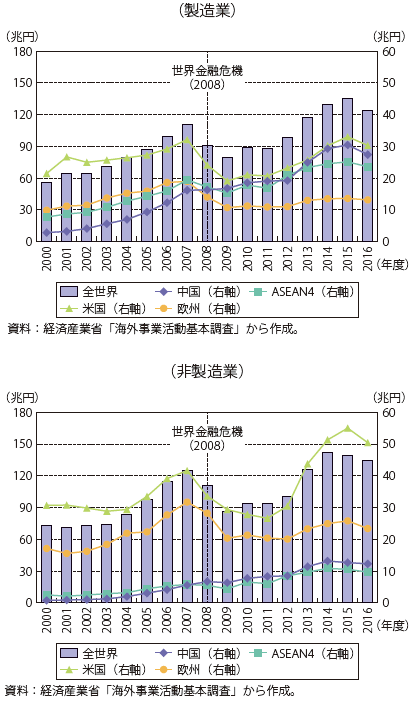
第Ⅱ-3-2-11表 日系海外現地法人の売上高(2016年度)
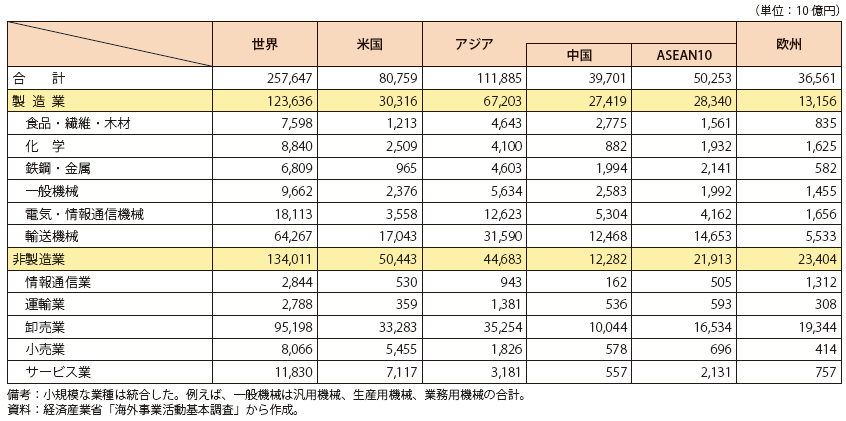
経常利益については年ごとの変動が大きいものの、売上と同様で、製造業はアジアで利益を拡大しており、非製造業は米国が大きい(第Ⅱ-3-2-12図、第Ⅱ-3-2-13表)。ただし、特に非製造業において世界金融危機後、アジア、欧州においては利益が伸び悩んでいる。
第Ⅱ-3-2-12図 日系海外現地法人の立地地域別経常利益
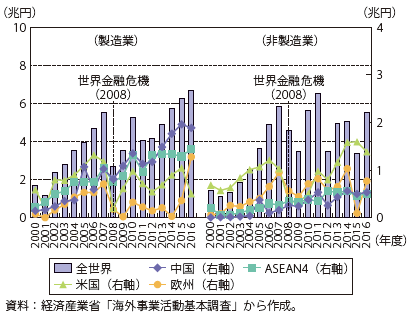
第Ⅱ-3-2-13表 日系海外現地法人の主要業種・立地地域別経常利益(2016年度)
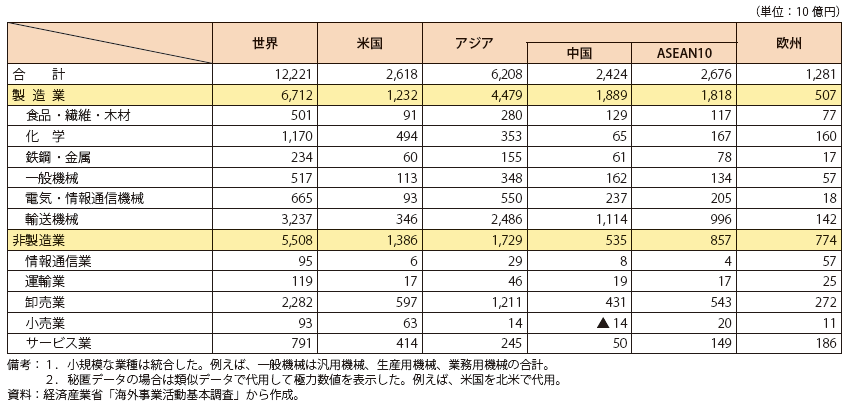
さらに地域から国別におりて見ると、企業数では中国が突出して多く、タイ、インドネシア、ベトナム等のアジア諸国が続いている(第Ⅱ-3-2-14図)。実に、上位10か国のうち9か国がアジアとなっている。併せて売上額も表示したが、首位の米国、第2位の中国の二か国が突出しており、第三位のタイ以下を大きく引き離している。また、売上額上位10か国を見ると、アジア諸国のほか、メキシコ(第5位)、カナダ(第7位)が挙げられ、米国を中心としたGVCの存在が示唆される。欧州諸国の中では英国(第9位)が上位に入っている。
第Ⅱ-3-2-14図 日系製造業現地法人の国別展開(2016年度)
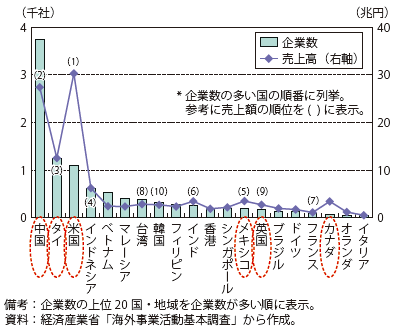
日系海外現地法人の利益率を見ておく。2016年度を見ると、アジアの経常利益率は、米国、欧州を上回る水準にある(第Ⅱ-3-2-15図)。業種別には、地域横断的に製造業の方が利益率が高い。
第Ⅱ-3-2-15図 日系海外現地法人の経常利益率(2016年度)
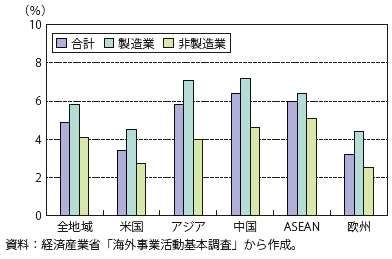
243 第Ⅱ-3-2-1図で2012年度、企業数、売上高が急増しているように見えるのは、調査実施に当たって補足率が上がったためである。
244 製造業に属する法人企業の2016年度売上高から計算。国内に立地する製造業企業の売上高約396兆円(法人企業統計)及び海外製造業現地法人売上高約124兆円の合計約519兆円に対する海外製造業現地法人売上高124兆円の比率。
245 本節において「中国」は特にことわらない限り本土のみで香港は含まない。
2.アジアを中心にしたGVCの展開
日系海外現地法人が、製造業を中心にアジアにおいて、企業数でも、売上高でも拡大してきていることを見た。ここからは、アジアの日系製造業に焦点を置いて分析していく。
最初に、アジアに展開する日系製造業現地法人の特徴(部品供給業者なのか組立業者なのか、企業規模、企業内取引比率等)を欧米に立地する現地法人と比較しながら見ていく。
その上で、アジアを中心としたGVCについて二つの視点から考察する。一つ目は、日系海外現地法人の視点から、日本からの調達、製品の販売先などを考える。二つ目は日本から輸出される付加価値の視点から最終需要地や日本の付加価値の流れを概観する。
まず、日系製造業現地法人の視点から売上高及び日本からの調達額(日本の輸出)を立地地域別に見てみる。当初は米国に立地する日系現地法人の売上高が大きかったが世界金融危機を契機に大きく落ち込み、アジア諸国、特に中国が追いついてきている様子がうかがえる(第Ⅱ-3-2-16図)。アジアにおける現地法人の売上高の増加とともに、総じて日本からの調達額も拡大している246。
第Ⅱ-3-2-16図 日系海外製造業現地法人の売上高及び日本からの調達額の推移
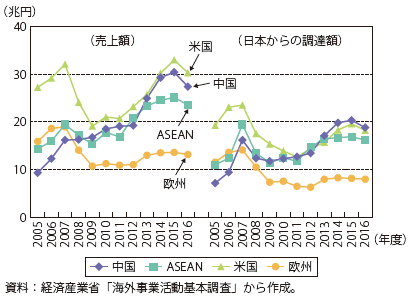
次に、日系海外現地法人を機械製造業に焦点を当てて主要製品の性格(最終財か中間財か)で分けてみる。アジアでは、最終製品の製造を主として行う企業(典型的には組立業者)とともに、中間財の製造を主として行う企業(部品供給業者)も多く進出している(第Ⅱ-3-2-17図)247。これは必要な中間財は日本から輸入するとともに、現地でも供給できるようなサプライ・チェーンの存在を示唆している。先の分析で、アジア諸国は売上額に対して立地企業数が多かったが、これはアジアでは組立業者とともに、多数の中小の部品供給業者(特に情報通信機械、輸送機械)が進出しているためと思われる。
第Ⅱ-3-2-17図 日系海外現地法人(機械製造業)の主要製品別の企業数(2016年度)
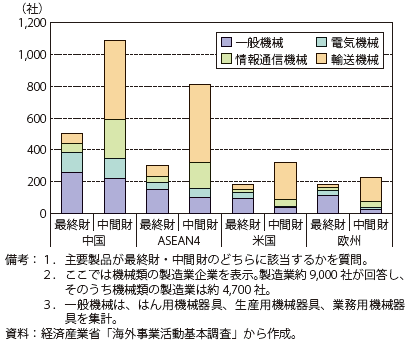
実際に海外現地法人(製造業)の企業規模を立地地域別に比較したのが第Ⅱ-3-2-18図である。アジアに立地する企業は欧米に比べて資本金規模の小さな企業のシェアが高いことが見て取れる。
第Ⅱ-3-2-18図 日系海外現地法人の企業規模分布(2016年度)
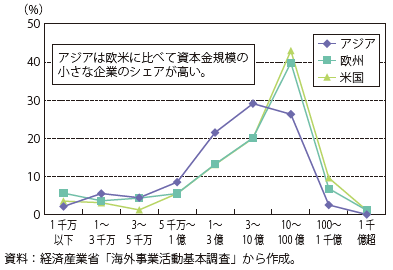
さらに日本国内の親会社の立場から考えてみよう。日系海外製造業現地法人の日本からの調達は、親会社の側から見れば、海外現地法人に対する基幹部品などの中間財輸出に当たる。国内製造業の輸出のうち、総じて資本関係を有する関係会社向け輸出(企業内取引)のシェアが高い248。「経済産業省企業活動基本調査」によれば、2016年度の国内製造業の輸出額のうち、56%までが関係会社向けとなっている(第Ⅱ-3-2-19図)。
第Ⅱ-3-2-19図 日本国内の製造業企業の輸出(関係・非関係会社向け)
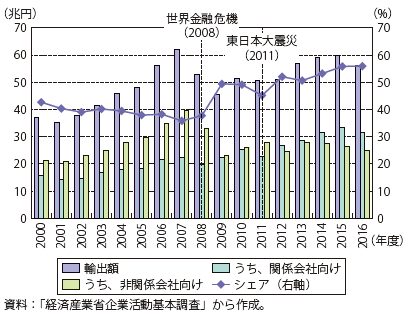
時系列で見ると、2000年代、世界金融危機まで、非関係会社向け輸出がより早いペースで伸びたため、関係会社向け輸出シェアは緩やかに低下。しかし、世界金融危機後は、非関係会社向けが伸び悩む中で、関係会社向けは堅調に増加。結果として、関係会社向け輸出(企業内取引)シェアが上昇している。
関係企業向けシェアを相手地域別に見ると、北米向けが最も関係会社向けシェアが高く、欧州が次ぐ。アジア、中国向けは相対的に関係会社向けシェアが低い。2016年はアジアで低下したものの、2011年以降、アジア、北米、欧州とも関係会社向けシェアは上昇基調で推移している(第Ⅱ-3-2-20図)。
第Ⅱ-3-2-20図 国内製造業企業の輸出における関係会社向け比率
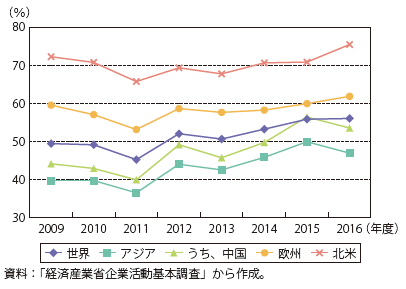
246 詳しく見れば、現地調達の拡大に伴い、日本からの調達額が以前ほど拡大しなくなってきているが、この点については次節で述べる。
247 調査においては、主要製品が最終財と中間財のどちらに該当するかを質問しており、必ずしも回答した財のみを生産しているわけではない。一つの目安として表示した。
248 「経済産業省企業活動基本調査」では、親会社、子会社及び関連会社を「関係会社」としている。ここで、「子会社」とは、ある会社(親会社)が50%超の議決権を所有する当該会社をいう。また、その子会社又はその親会社とその子会社合計で50%超の議決権を所有する当該会社(みなし子会社)及び50%以下であっても経営を実質的に支配している場合も含む。「関連会社」とは、ある会社(親会社)が20%以上50%以下の議決権を所有する当該会社をいう。また、15%以上議決権を所有していること等により、重要な影響を与えることができる会社を含む。なお、日本に立地しているのが外資系企業の場合は、「関係会社」向け輸出の中に、本国に立地する親会社への輸出も含むことになる。
業種別には、電子部品、輸送用機械、電気機械、情報通信機械など、機械関係において関係会社向けシェアが高く、企業内での国際的生産分業が行われている可能性を示唆している。反対に、木材・木製品、金属製品、プラスチック、窯業・土石、非鉄金属、皮革など素材関係は関係会社向けシェアが低い(第Ⅱ-3-2-21図)。
第Ⅱ-3-2-21図 日本国内の製造業企業の関係会社向け輸出(2016年度)
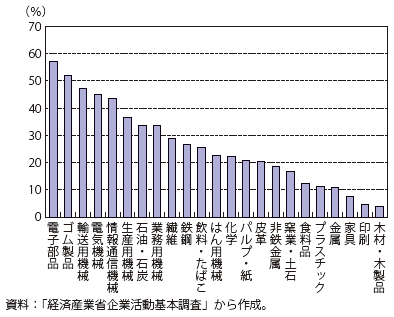
このような日系製造業現地法人のGVCを考えてみよう。日系製造業現地法人の地域別展開、相手地域別の売上額、日本からの調達額等を図示したのが第Ⅱ- 3-2-22図である。既に見たように、日系製造業はアジアに多く展開しており売上規模も大きい。
第Ⅱ-3-2-22図 日系海外現地法人の売上・調達(2016年度)
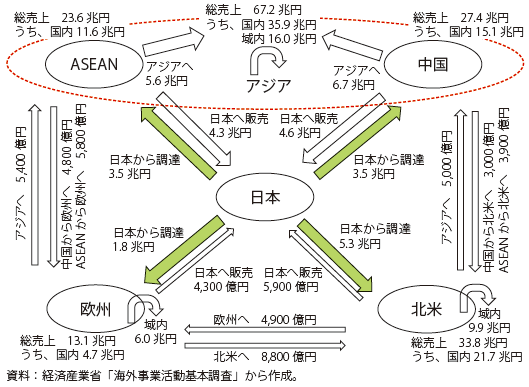
そのGVCの起点といえる日本国内の親会社から海外現地法人へ基幹部品等の中間財を供給していると考えられる。例えば、図では中国に立地する日系製造業現地企業は日本から3.5兆円の調達を行っている。その際に日系現地法人は日本から調達した中間財とともに現地等で調達した中間財も利用している。その生産物は現地で販売されるとともに、同じ地域内や日本、欧米にも輸出される。中国の例であれば、約27兆円の売上があり、そのうち、現地国内で約15兆円、アジア地域へ約7兆円、日本へ約5兆円を販売している。この際に現地の日系現地法人が他の日系現地法人へ中間財を供給することもある。これらの一連の財の流れがGVCにあたる。
まず、日本からの調達を考えてみる。日系海外製造業現地法人は、ほぼ立地地域にかかわりなく、生産活動に必要な資材の2割強を日本から調達している(第Ⅱ-3-2-23図)。その他の調達先としては、現地国内が最も大きなシェアを占め、次が同じ地域の域内(例えばアジアに立地していればアジア域内)からの調達が多い。なお、経済統合が進む欧州では、欧州域内調達が現地国内に匹敵する規模となっている。この日本からの調達のシェアは年とともに次第に低下する傾向にある(その詳細は次節に譲る)。
第Ⅱ-3-2-23図 日系海外製造業現地法人の調達先(2016年度)
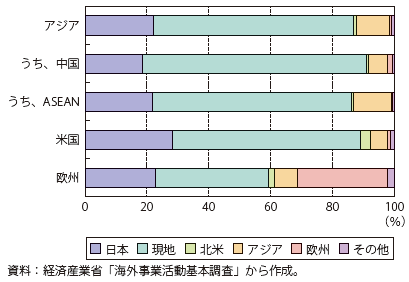
売上相手地域としては、アジア、北米、欧州とも総じて、立地国の国内販売が大きく、同じ地域の域内向け販売が次いでいる。アジアの場合は日本への輸出も大きい。北米、欧州の場合は、日本への輸出は限られている。これには、北米・欧州の現地市場が大きいことや、日本との距離が離れていて輸送費がかかることなどが影響していると考えられる。一方、アジアから北米など地域をまたがる売上は全体の売上規模からすれば意外に小さい。
詳細に見れば売上の相手地域別構成は立地地域によって相違があることが分かる。例えば、米国に立地する日系製造業は、米市場の大きさを反映して圧倒的に国内販売が大きい(第Ⅱ-3-2-24図)。ただし、世界金融危機後は国内販売が金額・シェアとも大きく落ち込んでいる。それでも直近で売上の約7割を国内、約2割を北米(カナダ)が占めている。これに対して、欧州に立地する場合は、国内販売と欧州域内がほぼ拮抗しており、EU内のヒト・モノ・カネの移動自由化の影響が考えられる。さらに2010年代は欧州域内のシェアが緩やかに上昇している。北米、アジア、日本向けも小幅ながらもシェアが上昇している。
第Ⅱ-3-2-24図 主要地域の日系製造業現地法人の相手地域別売上の推移
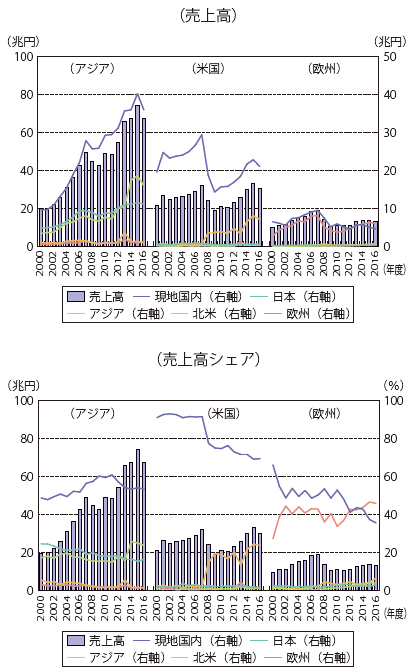
アジアに立地する日系製造業は、欧米に比べて売上の増加基調が鮮明で、特に現地国内販売を中心に売上が増加している。結果として、売上に占めるシェアは、日本、アジア、欧米向けは低下し、国内向けが上昇している。ただし、2012年以降はアジア向けシェアが上昇する傾向も見られる。直近では、現地国内が約5割、アジア域内が約2割強、日本が約2割弱。域外の北米、欧州向けはそれぞれ1~2%と限られている。
米国の中国に対する貿易制限措置によって日系現地法人への影響が懸念されている。ここでは中国に立地する日系企業を製造業に焦点を当てて概観してみる。中国に立地する日系製造業現地法人は約3,700社、売上高は約27.4兆円(2016年度時点)。その売上先を見ると、金額ベースで売上の過半が現地販売であり、輸出は売上額の44.9%(第Ⅱ-3-2-25表)。輸出のうちアジア(日本以外)向けが24.4%、日本向けが16.7%で、北米(米国及びカナダ)向けは1.1%となっている。現地販売の中には、現地の他社に中間財を供給し、その完成品が最終的に輸出に回るなど、サプライチェーンを通じた影響も考えられるので一概にはいえないものの、北米に対して直接輸出される金額は限られている。
第Ⅱ-3-2-25表 在中日系製造業現地法人の売上相手先(2016年度)
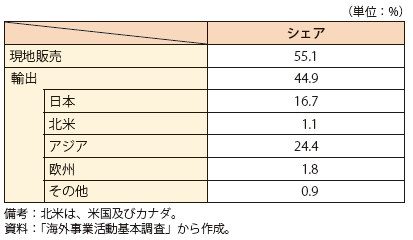
さらに日本からの資材調達、北米向け売上額の規模も含めて、業種別に影響の程度を図示したのが第Ⅱ-3-2-26図である。縦軸は売上額に占める対北米輸出のシェア、横軸は資材調達額に占める日本からの調達シェア、円の大きさは対北米輸出額を反映している。縦軸の上にある業種ほど米国の対中貿易制限の影響を受けやすく、横軸の右にあるほど日本からの調達(日本にとっては対中輸出)に影響が及びやすい。当然、円の大きさが大きいほど影響の規模も大きくなる可能性がある。これを見ると、業種別に対北米輸出額が最も大きいのは輸送機械で、これに情報通信機械、電気機械が次いでいる。この中で北米向け輸出シェアが比較的高いのは電気機械である。日本からの調達(日本にとっては対中輸出)に影響が及びやすいのは情報通信機械で、資材調達の4割以上を日本から輸入している。
第Ⅱ-3-2-26図 在中日系製造業現地法人の主要業種別北米向け輸出(2016年度)
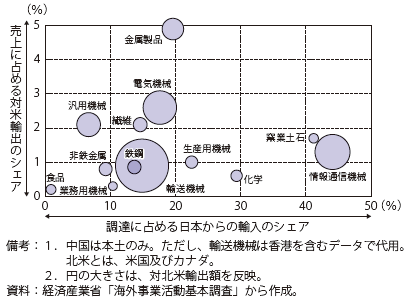
同様に米国に立地する日系製造業企業について見たのが第Ⅱ-3-2-27表である。日系製造業現地法人は約1,100社、売上高は約30.3兆円。売上額の約7割が現地販売で、輸出の多くはカナダ向けで、アジア向け輸出は全体の1.6%となっている。主要業種別には、化学、輸送機械、情報通信機械が大きい(第Ⅱ-3-2-28図)。
第Ⅱ-3-2-27表 在米日系製造業現地法人の売上相手先(2016年度)
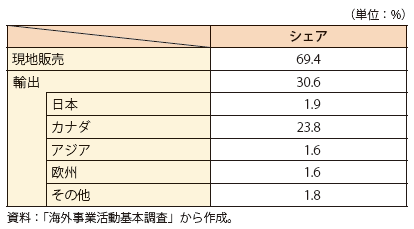
第Ⅱ-3-2-28図 在米日系製造業現地法人の主要業種別アジア向け輸出(2016年度)
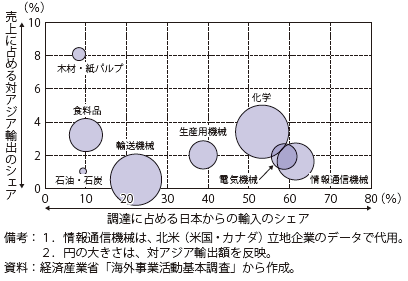
ここからは2つ目の視点である付加価値統計を使って日本のGVCを考えてみる。まず、日本の輸出の最終需要先がどこで、過去からどう変わっているかを見てみよう。2015年時点で、日本の付加価値ベースで最大の最終需要地は米国となる(第Ⅱ-3-2-29図)。従来の輸出統計と比べると、首位の米国・中国の順位が逆転する。中国の場合は輸出額よりも中国を最終需要地とする付加価値額の方が少なく、反対に米国は最終需要地とする付加価値の方が大きい。これは日本の中国向け輸出には、中国国内で加工され再輸出される中間財が多く含まれていること、反対に米国向け輸出には第三国経由で日本の付加価値が届いていることなどを示唆している。アジアの韓国、台湾、タイ等も最終需要地とする付加価値ベースの方が金額が少なく、国際的な生産分業に組み込まれていることを示している。
第Ⅱ-3-2-29図 日本の輸出先(2015年 / 輸出ベース・付加価値ベース)
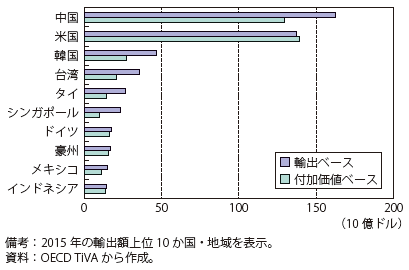
このように最終需要地の観点から付加価値輸出相手国の推移を見てみる249。日本の付加価値ベースでの輸出額は、世界金融危機直後を除いて2011年まで拡大、その後はやや減少している(第Ⅱ-3-2-30図)。主要輸出先は2005年時点では米国が突出した首位であったが、世界金融危機後に大きく減少した。その後ある程度回復するも、世界金融危機前の水準までは戻らないままほぼ横ばいで推移している。一方、中国向けの付加価値輸出は堅調に増加。両国を比べると2005年は米国向けが中国の2倍の規模であったが、中国向けが堅調に増加して世界金融危機直後の2009年にほぼ同水準となり、それ以降は両国が拮抗して推移している。なお、第3位以下は、韓国、台湾、ドイツと続くが上位2か国とは大きく引き離されている。
第Ⅱ-3-2-30図 日本の最終需要地別付加価値輸出の推移
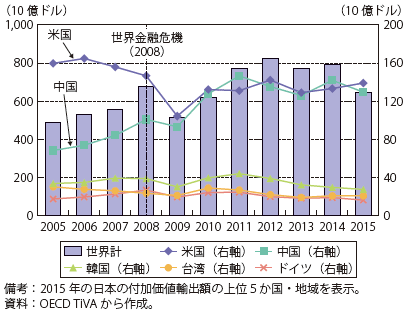
また、日本の輸出に占める各国付加価値や第三国の輸出に占める日本の付加価値の推移を見てみる。日本の付加価値輸出(対世界計)に占める主要国のシェアを見ると、日本のシェアは最も大きいものの、2005年から2015年までの間に緩やかに低下して、中国など外国の付加価値シェアが上昇している(第Ⅱ-3-2-31図)。
第Ⅱ-3-2-31図 日本の付加価値輸出に占める主要国・地域のシェア
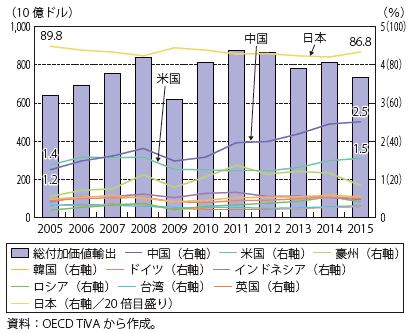
一方、第三国の付加価値輸出に占める日本の付加価値のシェアとして中国の例を見てみる。中国からの付加価値輸出(対世界計)は、中国の付加価値シェアが上昇しており、日本のシェアは低下している(第Ⅱ-3-2-32図)。ただし、シェアの低下は米国を始め他国も同様の動きとなっている。中国の地場企業の成長や主要国現地法人による生産の現地化が進んでいる可能性がある。なお、中国の付加価値の中には日系現地法人が生産した付加価値部分も含む。
第Ⅱ-3-2-32図 中国の付加価値輸出に占める主要国・地域のシェア
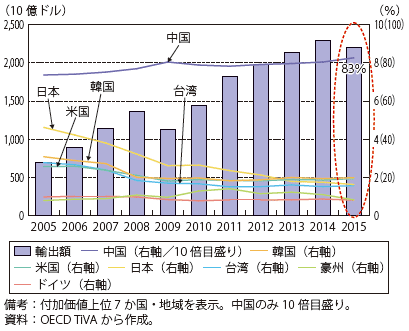
さらに視点を拡大して、世界を巡る日本の付加価値の主要な動きを図示したのが第Ⅱ-3-2-33図である。矢印は各国・地域の輸出に占める日本の付加価値を示している。併せて、日本から輸入される付加価値総額及び、そのうち、その国・地域において、最終消費・固定資産投資として最終需要となる額を表示した。国内で需要されない付加価値は加工・組み立てられた製品に含まれて再び輸出されていると考えられる250。
第Ⅱ-3-2-33図 世界における日本の付加価値のフロー
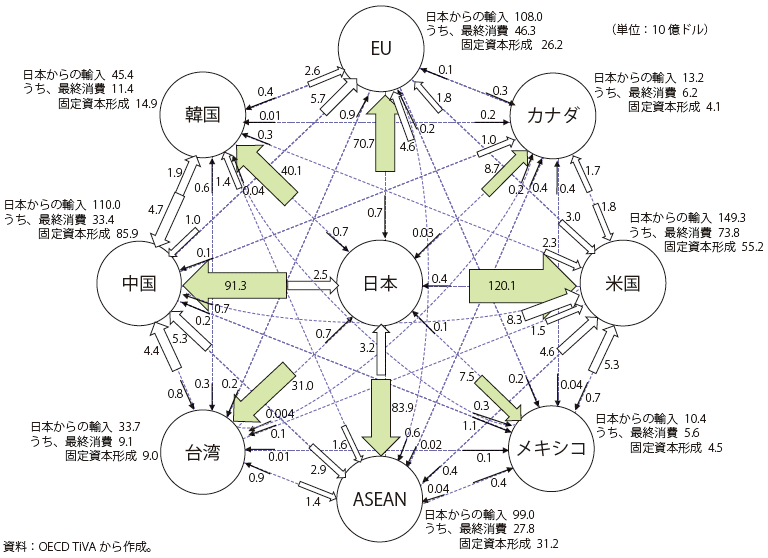
日本の付加価値ベースの輸出先としては、米国、中国が突出して大きく、韓国、台湾、ASEANなど東アジア諸国が次いでいる。東アジアの場合は、総じて日本からの輸入に含まれる付加価値のうち、製品に含まれて再び輸出に回る部分が多く、背景に国際的な生産分業が行われていることを示唆している251。なお、当然のことながら、日本からの輸出には輸出額に対して日本の付加価値のシェアが高く、東アジア諸国から再輸出される分に関しては輸出に対して日本の付加価値シェアは低い。
このように再輸出される日本の付加価値の動きを見ると、第1章第2節で論じたような日本から中国を経由して米国に至るGVCの流れがうかがえる。そのほかにも、日本からASEANやメキシコを経由して米国やEUに至る流れ等も見える。東アジアの中では、日本の付加価値がGVCの関係国の間を動いている。
また、各国の国内で最終消費又は総資本形成として需要される付加価値額も大きい。例えば、日本から中国への輸出を考えると、中国から米国への輸出に含まれる日本の付加価値額以上に中国国内で総資本形成として利用される日本の付加価値額の方が大きい。これは本章第1節で見たように、2019年の日本の中国向け輸出の中で、電子部品の輸出が低下するとともに、半導体製造装置や工作機械の輸出にも影響が出ていることとも符合する。
249 OECD TiVAは、2016年版(対象:1995~2011年)と2018年版(対象:2005~2015年)があるが、両統計は集計に当たっての平仄が異なるため、必ずしも接続できない。ここでは2018年版の2005~2015年を分析の対象とする。
250 一部には、その国・地域における在庫の増減、誤差等も含んでいると見られる。
251 中国については、日本側の対中付加価値輸出(1392億ドル)と中国側の対日付加価値輸入(913億ドル)の数値にずれがある。ここでは、中国の各国からの輸入を表示するため、統一的に中国側の付加価値輸入を使用したが、過小評価となっている可能性がある。