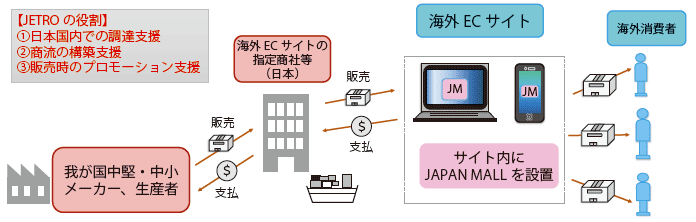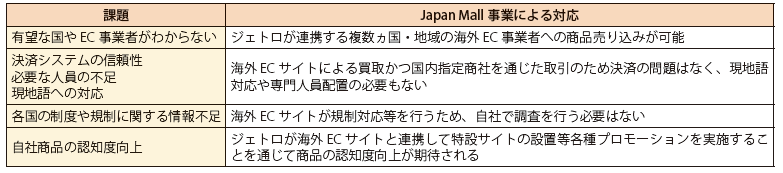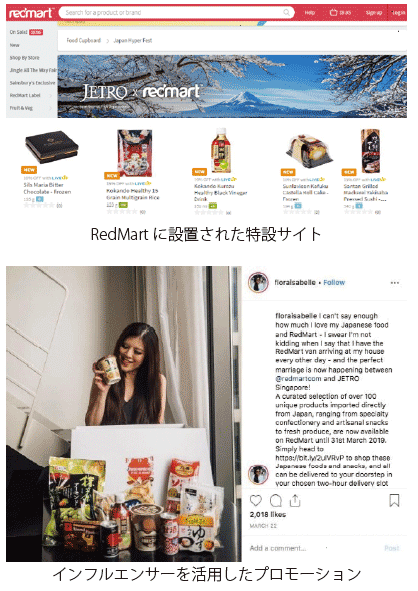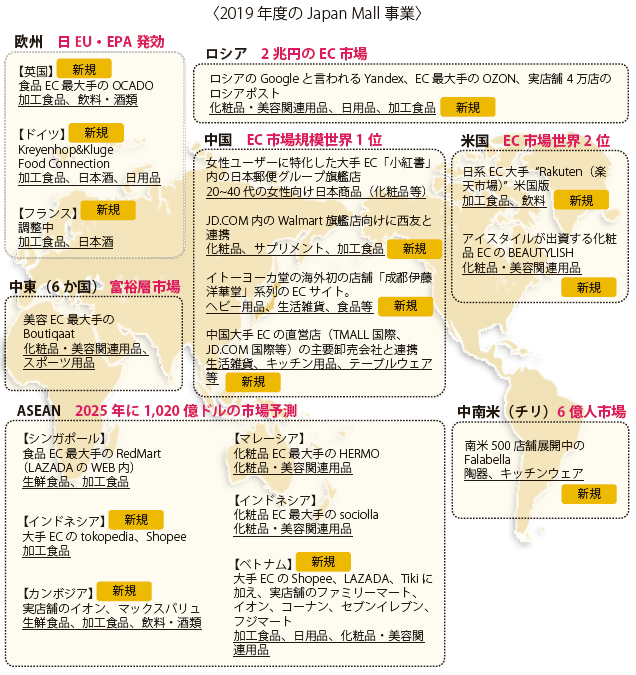- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2019

- 白書2019(HTML版)

- 第2部 第3章 第3節 アジアにおける日本の立ち位置と日本企業・産業が目指すべき方向性
第3節 アジアにおける日本の立ち位置と日本企業・産業が目指すべき方向性
前節では、日本を中心とした世界のGVCの現状を見たが、この節では、日本企業がより深くGVCに組み込まれているアジアにおける日本の存在感や立ち位置を見ることとする。
まず、アジアが先端的な形態255の国際分業が展開する起点となった、日本とASEANの経済関係の現状を検証したい。
255 木村(2018)。国際的生産・流通ネットワーク(Ando and Kimura, 2005)あるいは第2のアンバンドリング(Baldwin, 2011)と呼ばれる生産工程・タスク単位の国際分業の展開は、東アジア諸国以外では、メキシコ、コスタリカ、東欧の数カ国に限られている他、産業集積の形成まで至っている国は東アジア以外ではメキシコにその端緒が見られるにすぎない、としている。
1.日本のASEAN進出を機とした東アジアの工程間分業の進展
アジア、特に東アジアにおいては、1980年代後半以降の日本企業の積極的な直接投資256を発端に、工程間分業が進展し、域内生産ネットワークが発達してきた。
東アジア域内の貿易額は、1984年の約1000億ドルから、2012年の約2兆4000億ドルをピークに、2016年は約2兆2000億ドルとなった。なお、貿易額に占める中間財(部品と加工品)の割合は、1984年の48.4%から、2008年の66.0%をピークに、その後横ばいであるものの、2016年においても65.1%と高水準である(第Ⅱ-3-3-1図)。
第Ⅱ-3-3-1図 東アジア域内貿易額と中間財が占める割合の推移
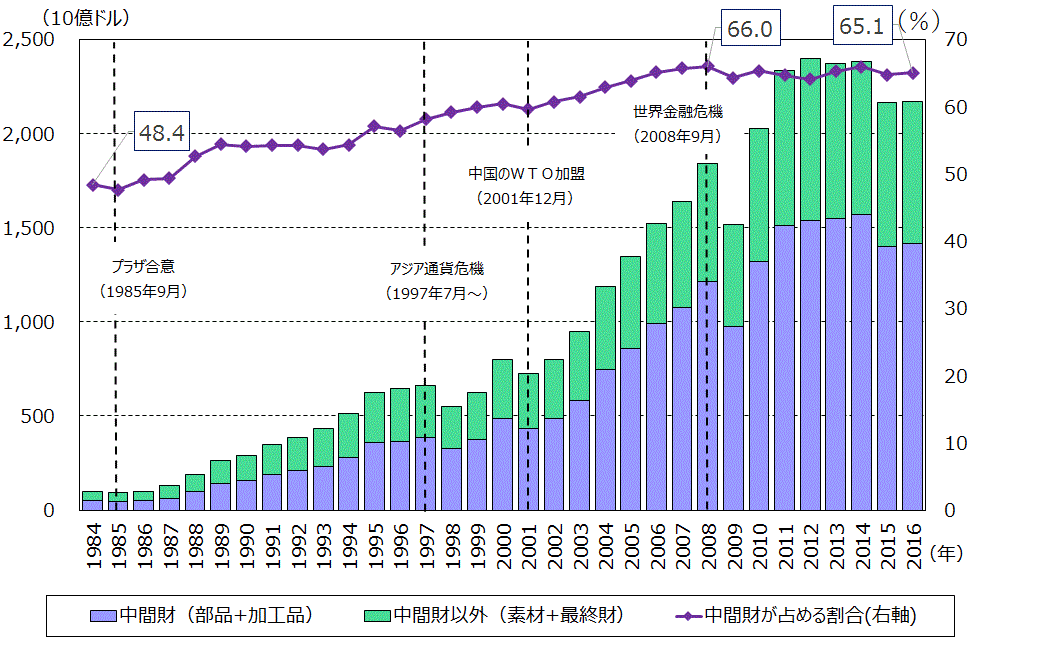
この国際的な工程間分業の発達を背景に、アジアの製造業の実質付加価値額は、世界金融危機前後で大きく拡大し、南北アメリカ、欧州を超え、世界最大の生産拠点となった(第Ⅱ-3-3-2図)。
第Ⅱ-3-3-2図 製造業の実質付加価値額(地域別)の推移
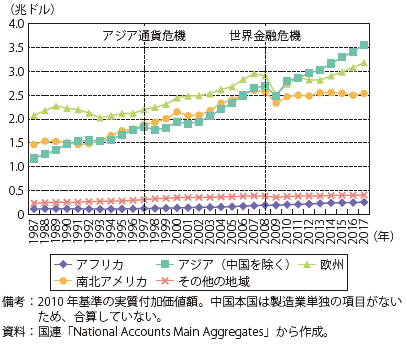
日本の国際的な工程間分業は、アジアの中でも、まずASEANを重要な生産拠点と位置付け展開した。これは、製造業における日本企業の競争力を高めると同時に、ASEANの工業化、産業集積に大きく貢献してきた。その後、中国のWTO加盟を機に、2000年代はASEANから中国へのシフトが見られたが、近年は、中国における賃金上昇等様々な要因を背景に、再びASEANを生産拠点として重視する企業が増加している。
今後も、ASEANと日本の相互補完は互いの成長に不可欠と考えられるが、近年はその関係に変化が生じている。ここでは、その変化がどのようなものであるかを検証し、ASEANにおける日本の存在の現状を把握する。
256 新興国の発展、国内人件費の上昇や、1980年代半ば、1990年代半ば、2010年代初頭頃の円高の方向への推移を背景に、輸出加工型製造業に代表される安価な労働力を活用する目的が中心だった。なお、ASEANの成長を背景にNIEs企業も日本企業の後を追うようにASEANに進出し、1990年代前半までに、日本、NIEs、ASEANの生産ネットワークが構築された。それ以降、産業内貿易(企業内貿易)がアジア域内で急増した。
2.ASEAN貿易における日本の存在感の縮小とその背景
まず、ASEANの世界からの輸入を金額ベースで見ると、1998年の2,783億ドルから2018年の1兆4,229億ドルと、この約20年において約5.1倍に拡大したが、ASEANの日本からの輸入は、約2.4倍に留まった257。一方、同期間、中国は約16.1倍、韓国は約7.6倍、ASEAN域内は約5.1倍と拡大している。割合ベースで見ると、日本は1998年にASEAN域内に次いで第2位の18%を占めていたが、2018年は9%と半減した。一方、同期間、中国は7%から22%と大きく上昇している258(第Ⅱ-3-3-3図)。
第Ⅱ-3-3-3図 ASEANの世界からの輸入
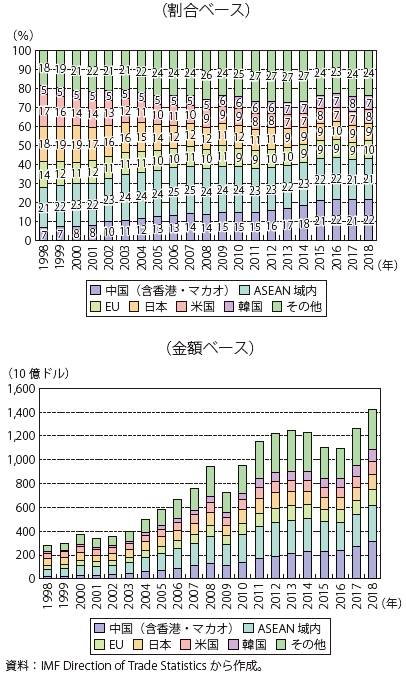
次に、世界からASEANへの直接投資259を見る。
主要な投資国は、ASEAN域内、EU、中国(香港、マカオ、台湾を含む)、日本、米国、韓国である。近年、日本からASEANへの投資額は横ばいとなっている一方、ASEAN域内、EU、中国からの投資額は上昇している(第Ⅱ-3-3-4図)。
第Ⅱ-3-3-4図 ASEANの対内直接投資額(主要国別)の推移
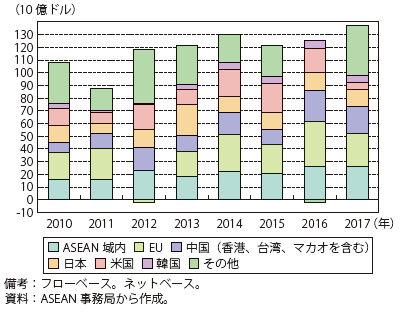
なお、主要な投資業種は、製造業、卸売小売業、金融保険業、不動産業、その他のサービス業である。2017年は、金融保険業が減少する一方、卸売小売業、製造業が増加した(第Ⅱ-3-3-5図)。
第Ⅱ-3-3-5図 ASEANの対内直接投資額
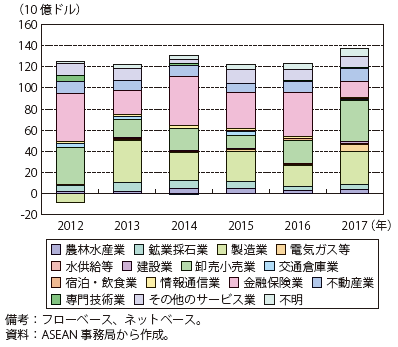
投資面では、ASEAN域内、欧州、中国の好調な推移と比較すると近年見劣りがするものの、底堅く推移しているといえる。
このようにASEANにおける日本の存在感の縮小は、投資面というより貿易面で顕著である。これには以下に挙げるような様々な背景があると考えられる。
257 EUは約3.6倍、米国は約2.3倍の拡大となっている。
258 韓国は1998年から2008年まで約5%を維持し、その後はわずかながら上昇傾向にあり、2018年は約7%となっている。
259 ASEAN事務局の公表値(ネット、フローベース)を利用。2017年値が最新値(2019年4月現在)。
(1)日本企業のASEANへの現地進出
日本企業がASEANにおける現地法人の設立を進めたことにより、従来日本から輸入をしていたものが現地生産に置き換わり、その結果、日本からの輸入が低下したと考えられる。現地進出が進んだ背景には、従来は人件費コストの削減目的が主流であったが、近年はより消費者に近い場所での生産をするための、市場開拓目的の企業も増加している。
日本企業の在ASEAN現地法人(以下、在ASEAN現地法人)数は年々増加傾向にあるものの、近年は伸びが鈍化260している。しかし、世界における日本企業の現地法人数も伸びが鈍化しており、在ASEAN現地法人数が在世界現地法人数に占める割合は、2009年度の約23.0%から、2016年度は26.7%と年々上昇している。日本企業が現地化を進める際、ASEANを嗜好、重視していることが想定される(第Ⅱ-3-3-6図)。
第Ⅱ-3-3-6図 日本企業の現地法人数(在世界・在ASEAN)の推移
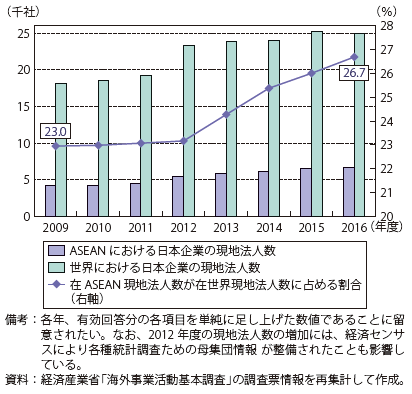
260 国にもよるが、現地進出が飽和(一巡)したことが要因であるという指摘もある。
(2)ASEANにおける現地調達の増加
在ASEAN現地法人の現地調達額は、足下で減少も見られるが、近年は総じて増加傾向にあった。地場企業からの調達の堅調さは、地場企業の成長が反映されていると想定できる。また、低水準とはいえ、2014年度以降、「その他の企業から」、つまり、日系現地法人でも地場企業でもない企業から261の供給も増加しており、調達先の多様化も見てとれる。例えば、外資系企業も調達先の選択肢に加わったことで、結果的に日本からの輸入が低下したと考えられる(第Ⅱ-3-3-7図)。
第Ⅱ-3-3-7図 日本企業の在ASEAN現地法人の現地調達額とその内訳(地場企業・日系企業・その他の企業)の推移
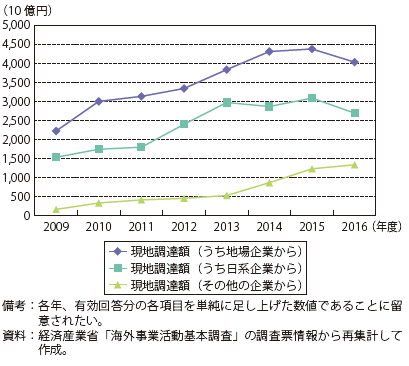
261 海外事業活動基本調査(現地法人調査票)においては、「現地調達額=日系企業から+地場企業から+その他の企業から」という内訳になっている。
(3)ASEANの需要を捉えていない日本企業
6億5千万人という域内人口262、若年層が過半を占める人口構成、所得水準の上昇に伴う中間層の台頭等によりASEAN市場は拡大しているにもかかわらず、在ASEAN現地法人の現地販売額(第Ⅱ-3-3-8図)、その内訳の一つである地場企業向け販売額(第Ⅱ-3-3-9図)は、総じて横ばいまたは低下傾向にある。これはASEANの「新たな」需要分を獲得できていないことや、ASEANが輸入元を日本から他国に置き換えていることが考えられ、在ASEAN現地法人による日本からの調達額の減少にも繋がることによって、結果的に日本からの輸入額が減少したと考えられる。
第Ⅱ-3-3-8図 在ASEAN日本企業現地法人の現地販売額とその内訳(日系企業向け・地場企業向け・その他の企業向け)の推移
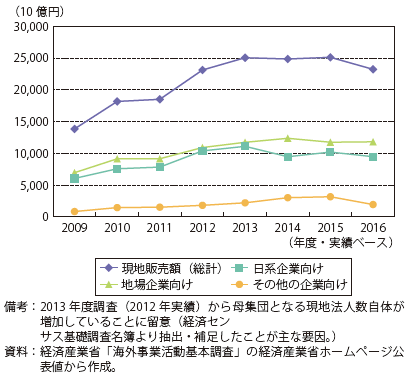
第Ⅱ-3-3-9図 在ASEAN日本企業現地法人の地場企業向け販売額とその内訳(製造業・非製造業)の推移
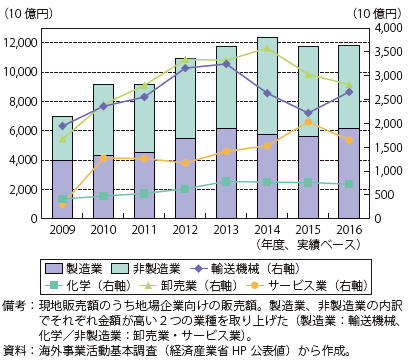
なお、地場企業向け販売額の内訳263をみると、製造業が51.9%、非製造業が48.1%と拮抗している。また、製造業において高い割合を占める上位2業種は、輸送機械(製造業の43.4%)・化学(同11.8%)、非製造業においては、卸売業(非製造業の49.5%)・サービス業(同29.0%)となっている。
日本がASEANの「新たな」需要分を獲得できていないことや、ASEANが輸入元を日本から他国に置き換えている可能性264について言及したが、ここで、生産ネットワークの主要品目でもあり、日本の主要輸出品目である、電気機械、一般機械、輸送機械、精密機械の4品目(それぞれ資本財・部品に分類)に関して、主要プレイヤーである日本・中国・韓国の対ASEAN輸出動向を比較検証する。
その結果、電気機器(部品)は中国と韓国に、同(資本財)は中国に、ASEANの需要を取られている可能性が見てとれる(第Ⅱ-3-3-10図)。なお、韓国については、企業内分業が有名265であるが、電気機器(部品)の輸出に大きく傾斜しているといった特徴がある。
第Ⅱ-3-3-10図 電気機械(資本財・部品)の対ASEAN輸出額の推移(日中韓の比較)
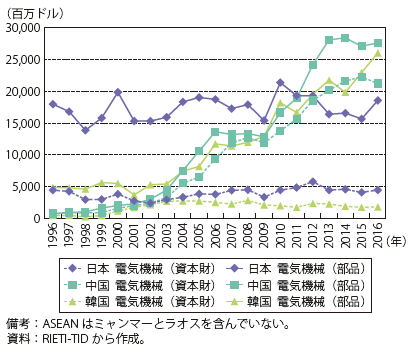
一般機械は、部品・資本財ともに、中国と韓国に需要を取られている可能性があり、特に、一般機械(資本財)における中国の拡大は目立っている(第Ⅱ-3-3-11図)。
第Ⅱ-3-3-11図 一般機械(資本財・部品)の対ASEAN輸出額の推移(日中韓の比較)
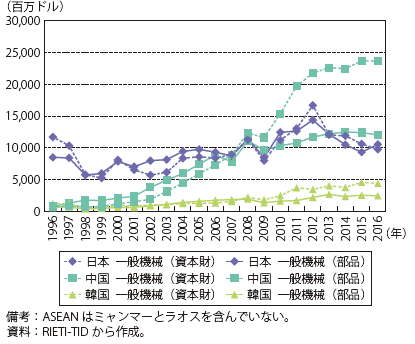
輸送機械については、現地サプライチェーンが他の品目より成熟していると考えられる266ことから、金額の水準が低いことのほか、部品、資本財ともに、日本が他国に比べ優位を維持していることが見てとれる(第Ⅱ-3-3-12図)。
第Ⅱ-3-3-12図 輸送機械(資本財・部品)の対ASEAN輸出額の推移(日中韓の比較)
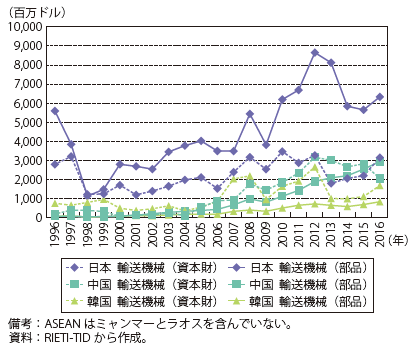
精密機械は、輸送機械よりも更に金額の水準が低いことのほか、部品において、3か国からの輸出金額は足下で拮抗していることが見てとれる(第Ⅱ-3-3-13図)。
第Ⅱ-3-3-13図 精密機械(資本財・部品)の対ASEAN輸出額の推移(日中韓の比較)
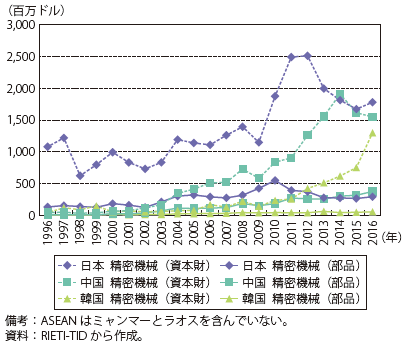
ただし、同じ品目群でも、機能、品質、価格は様々であることには留意すべきである。数量は少ないが高価な商品を供給するか、規模の利益を確保すべく安価な汎用品を大量に供給するか267等、どのような構成をしているかを把握するには、別途詳細な分析が必要である。
262 IMF WEO, April 2019のデータ。ASEAN10か国の総人口(2018年実績値)を合算。なお、2020年には6億6千万人になると推定されている。
263 2016年実績ベースで計算。
264 2019年版ものづくり白書によると、国内製造業は、他国(米国・ドイツ・中国)と比較して、「技術開発力」、「製品の品質」、「現場の課題発見力・問題解決力」については優位性があると認識している一方、「生産自動化・省力化」や「商品企画力・マーケティング力」では劣位と認識している傾向がある。これは、他国に需要をとられている要因を考える上で参考となるだろう。
265 LGやサムソンが具体例としてよく取り上げられる。
266 輸送機器産業は、他の機械産業と比べ重くて大きなものを扱うことが多いことから、輸送コストを考慮し、より産業集積が進んでいる場所を生産拠点に選択することが想定できる。
267 日本企業は、品質に自らの優位性を認識し、高付加価値、高価格帯ゾーンで勝負してきたといえる。それによって日本ブランドへの信頼感を獲得する等成果を上げている一方、若者や中間層が購入できるようなボリュームゾーンにおいては他国に需要を取られているという指摘もされている。
3.日本企業のビジネススタイルの変化~財輸出から配当・ロイヤリティにおける利益重視へのシフト~
ASEANの貿易(特に世界からの輸入)に関し、日本の存在感が縮小していること、それが、日本企業の現地進出、ASEAN地場企業の成長、他国からの供給代替等、様々な背景に起因することは先述した。一方で、従来の部材等の輸出に代わり、現地法人の日本側出資者への支払いである配当・ロイヤリティで利益を確保するという、日本企業のビジネスモデルの変化も見てとれる。
なお、日本側出資者への支払い額を、製造業と非製造業で分類してみると、非製造業よりも製造業の方が大きいことや、非製造業における配当金の額が近年大きくなっていることが見てとれる(第Ⅱ-3-3-14図)。
第Ⅱ-3-3-14図 在ASEAN日本企業現地法人の日本側出資者への支払い(ロイヤリティ・配当金)の推移
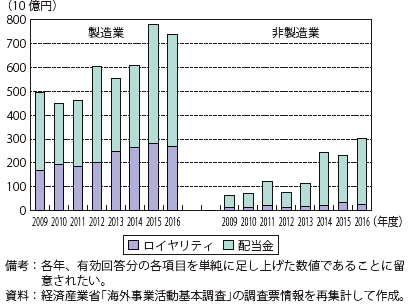
また、在ASEAN現地法人の当期純利益をみると、総じて上昇傾向にある(第Ⅱ-3-3-15図)。参考までに、当期純利益に占める配当の割合を見ると、各年で上下しており明確な特徴は捉えられなかったが、2016年度ベースの当期純利益に対する配当の割合は全産業で49.9%、製造業で45.5%、非製造業で59.5%となっている(第Ⅱ-3-3-16図)。
第Ⅱ-3-3-15図 在ASEAN日系企業現地法人の当期純利益の推移
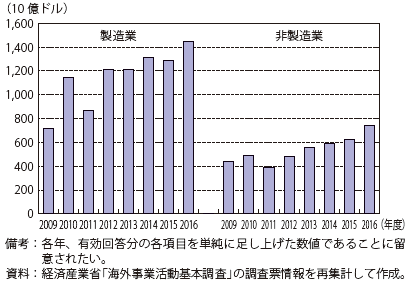
第Ⅱ-3-3-16図 在ASEAN日系企業現地法人の当期純利益と配当金の推移
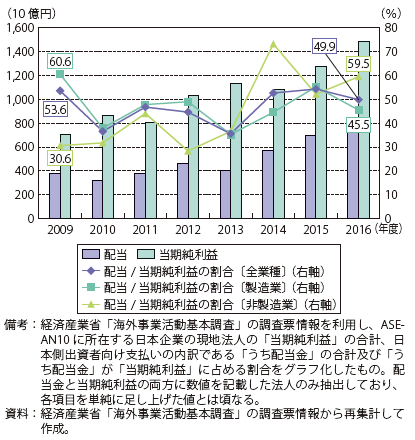
4.日本企業とASEAN企業との資本関係の結びつきの強さ~中国・韓国との比較~
日本企業は、財の輸出のみならず、ロイヤリティや配当で利益を確保する一面が見られることは先述した。これに関連し、ここでは現地法人ではなく、ASEAN企業と日本企業の資本関係がどの程度結びついているか、中国と韓国と比較しながら検証する。
その結果、最終親会社(Global Ultimate Owner)の総合所有比率が100%と登録されている企業のみを抽出268した場合、日本は4,423社、中国は3,613社、韓国は352社であった。このことから、日本企業とASEAN企業の資本関係の結びつきは相対的に強いことが推測できる。
また、出資先企業の国や業種は、各国で特徴がある。
国別では、日本はシンガポールが過半数を占めるものの、タイ、ベトナム、マレーシアなど複数の国に分散し出資している。一方、中国はシンガポールに約94%、韓国はシンガポールの他、ベトナム(45.7%)への出資というように特定の国への出資に傾斜していることが特徴的である269。
なお、業種別270では、3か国とも、製造業より非製造業への出資割合が高く、日本は77%、中国は96.7%、韓国は64.8%となっている(第Ⅱ-3-3-17図)。
第Ⅱ-3-3-17図 ASEAN企業への出資企業数と国・業種別割合(日本・中国・韓国の比較)
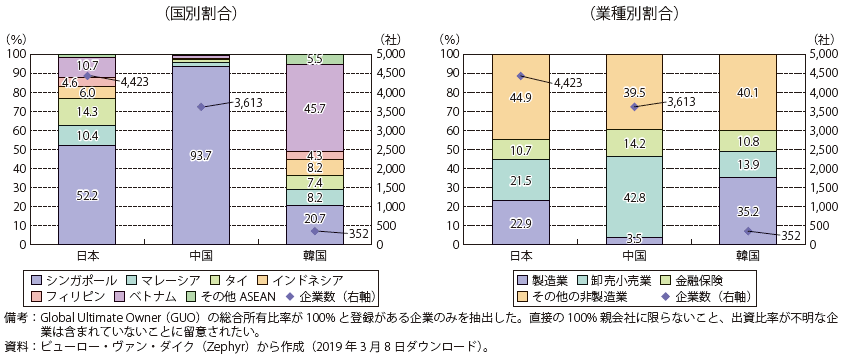
268 ビューロー・ヴァン・ダイクのOrbisデータベースから抽出しており、直接の100%親会社に限らないこと、出資比率が不明な会社は含まれていないこと等留意点がある。
269 3か国の企業がシンガポールを出資先として嗜好しているのは、同国のビジネス環境の良さ、ASEAN地域の統括拠点としての役割等において高い優位性があるからだと思われる。
270 親会社ではなく、子会社であるASEAN企業の業種。
5.ASEAN経済の変化
以上、日本側の視点で日本とASEANの経済関係の現状や変化をみたが、相互関係の変化は、日本企業のビジネスモデルの変化のみならず、ASEAN側の成長、変化に起因するところも大きいと考えられる。以下では、ASEAN自身の変化を挙げてみる。
(1)ASEANの名目GDPの拡大
ASEANの名目GDP額(購買力平価ベース)は2008年に日本を越え、拡大し続けている(第Ⅱ-3-3-18図)。国、地域によって大きな差があることはもちろんであるが、ASEAN全体の生活者の経済水準は日本よりも高い伸びで推移しているといえる。
第Ⅱ-3-3-18図 ASEANの名目GDP (購買力平価)の推移
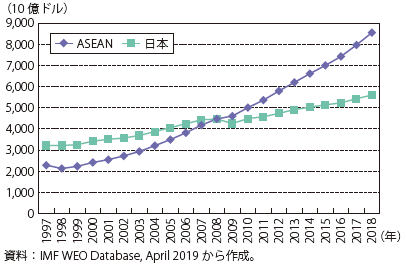
(2)ASEAN域内経済統合の進展
東西、南部、南北等、各経済回廊などのASEAN越境インフラ整備により、ASEAN各国及び周辺諸国との物流・交通が活発化している(第Ⅱ-3-3-19図)。この動きは、2018年1月からほぼ全ての品目について関税が撤廃されたことも相まって、域内経済の連結性を上昇させている(第Ⅱ-3-3-20図)。これらの整備によって、ASEANの貿易・投資が域内外ともに一層拡大し、GVCへの参画がさらに強化されていくと思われる。
第Ⅱ-3-3-19図 ASEANの代表的な経済回廊
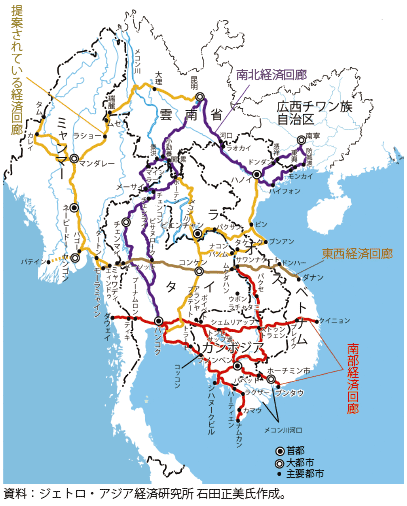
第Ⅱ-3-3-20図 ASEAN域内における関税撤廃の進捗
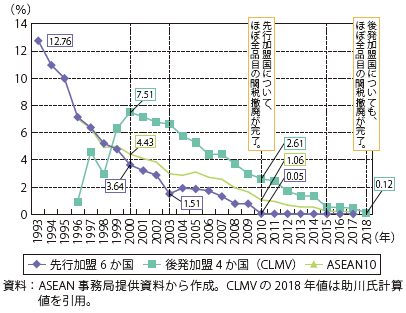
(3)ASEAN企業の対外海外投資の積極化~投資の受け手から出し手へ~
上記(1)(2)で挙げたように、ASEAN経済成長に追い風が吹く環境下で、シンガポール、マレーシアが先行、タイが続き、インドネシア、フィリピン、ベトナムでも、足下で対外直接投資が拡大している。
シンガポールの金額水準が高いことの他、マレーシアに関しては、対外投資が対内投資を超える年も現れたことが注目される(第Ⅱ-3-3-21図)。
第Ⅱ-3-3-21図 ASEAN主要国の海外直接投資(対内・対外)の推移
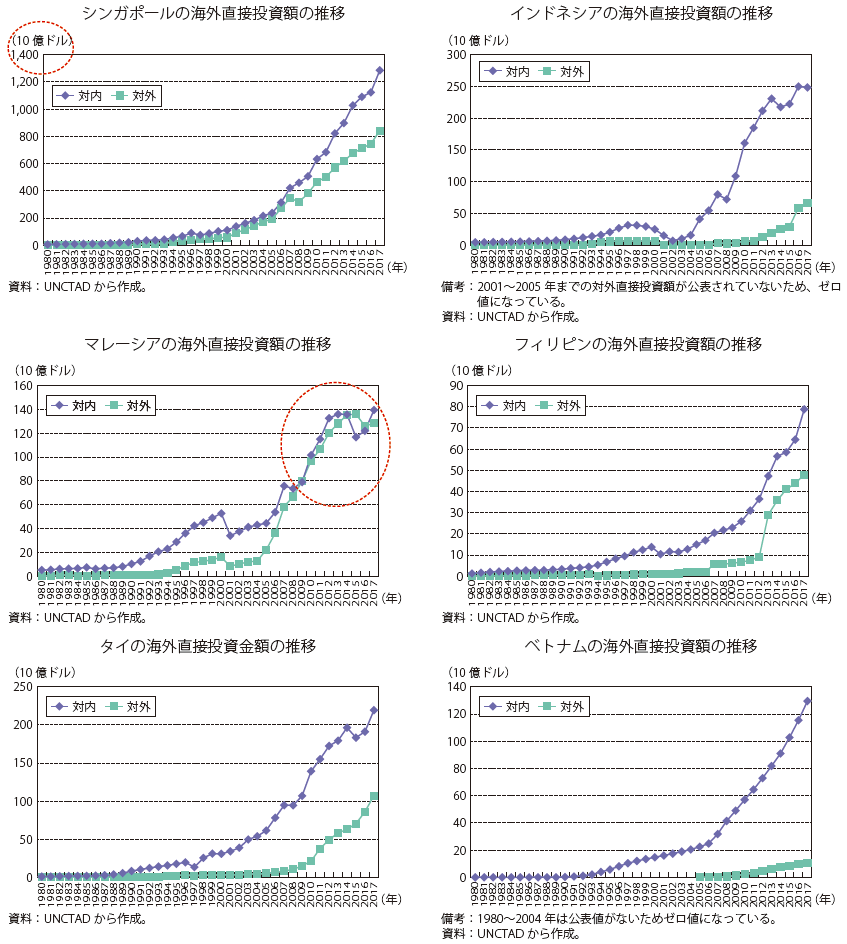
- Excel形式(シンガポールの海外直接投資額の推移)のファイルはこちら

- Excel形式(インドネシアの海外直接投資額の推移)のファイルはこちら

- Excel形式(マレーシアの海外直接投資額の推移)のファイルはこちら

- Excel形式(フィリピンの海外直接投資額の推移)のファイルはこちら

- Excel形式(タイの海外直接投資額の推移)のファイルはこちら

- Excel形式(ベトナムの海外直接投資額の推移)のファイルはこちら

なお、日本企業の親会社に変化があるかを見る271と、2006年は5社だったシンガポールの親会社は2016年に30社と6倍に拡大している(第Ⅱ-3-3-22図)。
第Ⅱ-3-3-22図 日本企業の親会社の国・地域別推移
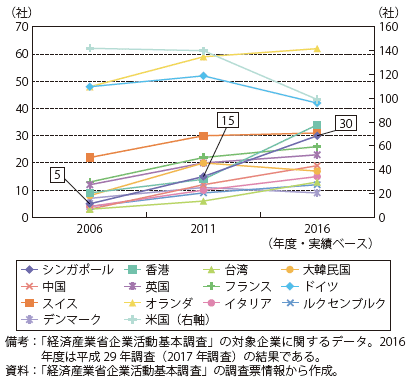
海外からの直接投資により成長してきたASEANの自律的な拡大を反映する一つの指標と思われる。
271 経済産業省企業活動基本調査の調査票情報を再集計したもの。2006年度、2011年度には、調査対象企業の140社超の親会社が米国であったが、2016年度には99社と大きく減少した。ドイツも減少している。一方、中国は6.3倍の19社、香港は3.8倍の34社と増加していることから、日本企業の親会社が欧米からアジアに変化している一面が見てとれる。
(4)平均的雇用者所得の伸び悩み
上記(1)~(3)で挙げた例だけでも、ASEANの成長潜在性の高さが見て取れる。それゆえ、近年、域内外からASEANの中間層増加による消費拡大も期待されている。しかしながら、現時点では、平均的な雇用者の所得は、日本の高付加価値、高価格のものまで購入するまでの水準には達していないことに留意すべきである。例えば、ASEAN先発国中心に賃金動向を分かる範囲でまとめても、日本の賃金水準とは隔たりがあることが分かる(第Ⅱ-3-3-23表)。
第Ⅱ-3-3-23表 日本とASEAN主要国の賃金に関するデータ
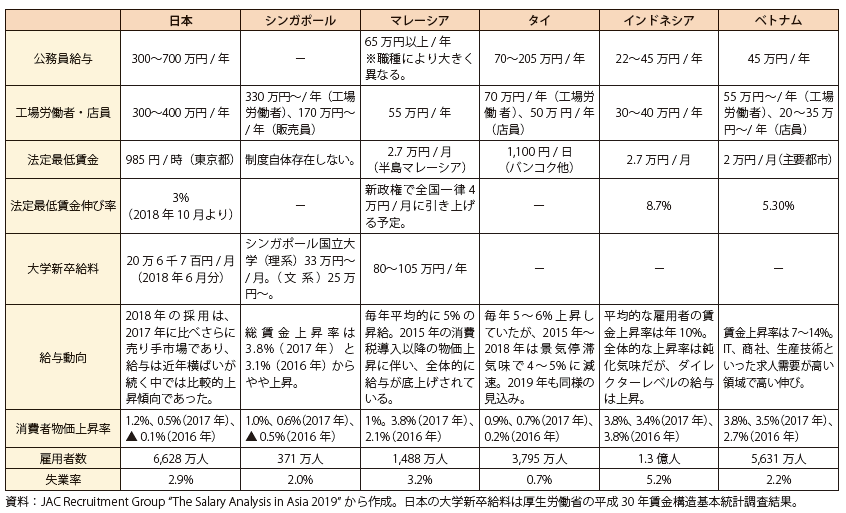
6.共に成長するための日本とASEANの相互協力
上記の通り、変化する環境の中でも、日本とASEANが共に成長するためには、今後も相互に協力し合うことが重要であることは言うまでもない。今後も、日本がASEANの成長に大きく寄与できる一例としては、以下が挙げられよう。
(1)日本の製造業による現地の雇用拡大
ASEANへの対内直接投資額(業種別)を日本、中国、韓国で比較をすると、日本と韓国は製造業に、中国は金融保険業、不動産業に重点をおいていることが分かる。なお、卸売小売業に対する投資が底堅く推移しているのは各国共通といえよう。
製造業は他の業種より、現地の雇用拡大に貢献する。主な投資分野が製造業で、その金額水準も高い日本は、他国に比べ、現地の雇用拡大、ひいては中間層の拡大にも寄与していると想定できる(第Ⅱ-3-3-24図、第Ⅱ-3-3-25図、第Ⅱ-3-3-26図)。
第Ⅱ-3-3-24図 日本からASEANへの直接投資額(業種別)の推移
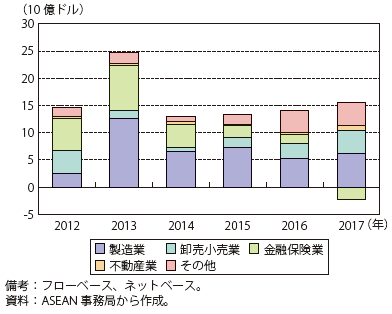
第Ⅱ-3-3-25図 中国からASEANへの直接投資額(業種別)の推移
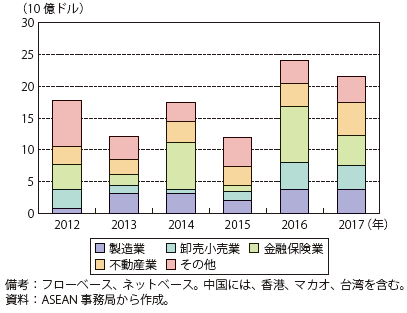
第Ⅱ-3-3-26図 韓国からASEANへの直接投資額(業種別)の推移
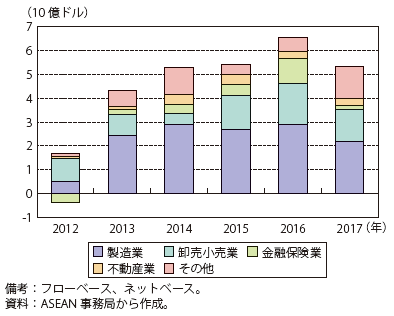
(2)輸出の高度化(技術移転)
ASEANがいわゆる「中所得国の罠」を回避して持続的成長を果たすためには、産業、輸出品目の高度化が必要とされている。Lall教授による技術水準別品目分類(Lall 2000)272に従い、ASEANから主要国(日本、中国、韓国)の輸出動向をみると、日本は早い段階から、ASEANの輸出品目の高度化に貢献してきたことが分かる。また、中国と韓国は日本と同様かそれ以上に、ハイテクとミディアムテク製品のシェアが大きい(第Ⅱ-3-3-27図、第Ⅱ-3-3-28図、第Ⅱ-3-3-29図)。輸出品目の高度化は引き続きASEANから必要とされる役割であろう。
第Ⅱ-3-3-27図 ASEANから日本への輸出構造(Lall分類)の推移
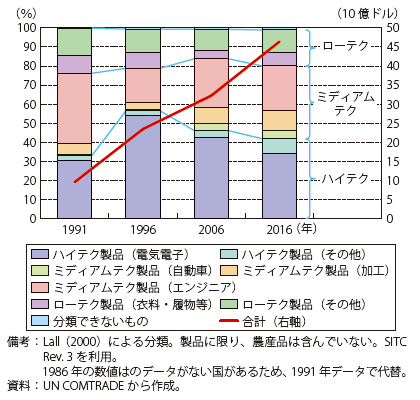
第Ⅱ-3-3-28図 ASEANから中国への輸出構造(Lall分類)の推移
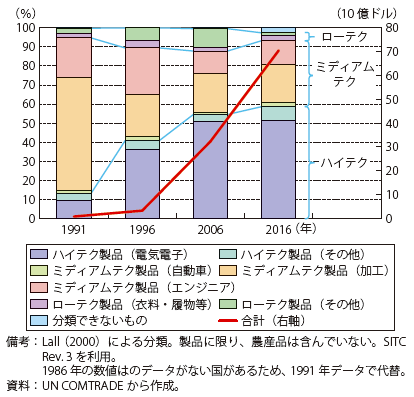
第Ⅱ-3-3-29図 ASEANから韓国への輸出構造(Lall分類)の推移
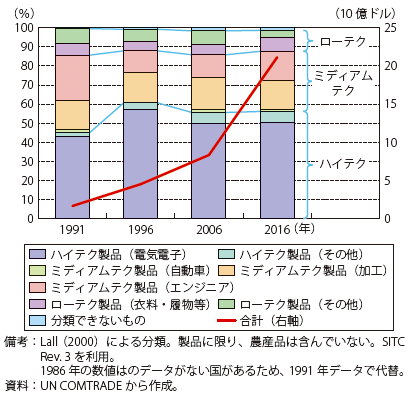
なお、ASEANではNEM(Non-Equity Modes of Operation:貿易でも投資でもない、いわゆる委託生産)という生産形態も多くなっているが、単なるコストセンターとしているだけではなく、一定程度の技術移転としても寄与している。
一方、日本の成長にASEANが大きく寄与できる一例としては、消費市場が拡大すること、インフラ事業を協力して行うことなどが挙げられる。なお、ASEANは地域として一括りにされることが多いが、発展段階、産業構造、人口動態、ビジネス環境等、大きく異なる国々の集まりであることから、消費市場、インフラ市場に参入する際には、その差を見極め、生かすことが必要なのは言うまでもない。
日本とASEANの相互経済関係の深化は、世界の生産市場、世界の消費市場において、今後、より一層存在感を増すものと思われる。
272 ある国の輸出構造がどの程度高度なものであるかを確認するため、STIC3桁分類について、ローテク財、ミディアムテク財、ハイテク財等といった分類する方法。この手法の作成当時から、様々な技術革新を経たことで、現在は、そのカテゴリーが実態に合わなくなっている面もあるものの、輸出高度化の指標として、国際機関等で利用される手法である。なお、Lall教授はハイテク財ほど輸出額の伸びが大きいことから、ハイテク財を輸出することがその国の経済発展に重要であるとしている。
7.今後の日本企業・産業が目指すべき方向性
これまでASEANにおいて日本企業のプレゼンスが低下している現状を見てきたが、ここでは前節で見た日本を中心としたGVCの実態も踏まえ、対象地域も中国を含めたアジアに広げたうえで、今後の日本企業の目指すべき方向性を考えてみる。
(1)日本企業の稼ぎ方の再考
もともと問題意識の出発点は、アジア、特にASEANで日本からの輸入シェアが低下しているという事実に基づいて、日本の存在感そのものも低下しているのではないかということであった。しかし、それは本当に日本の存在感低下につながるのだろうか。むしろ、日本企業の活動を見る時の視点の転換を考えても良い時期にきているのかもしれない。その点に関わるいくつかの問題を再考してみる。
①「日本からの輸出」という視点の転換
日本企業の活動の在り方は変化してきている。当初は、日本企業は国内で最終財の形にまで生産して輸出していたが、既に見てきたように海外現地法人を設立し、日本からは基幹部品など中間財を輸出する国際的な生産分業(GVC)に変わった。そして現在は現地の人材・企業も成長し、一定水準の中間財までは生産できるようになってきている。このような状況下では、むしろ、企業戦略として現地化を進め、資材調達の面ではコストを抑え、現地に精通した人材を活用し、輸出だけでなく現地のニーズにあった製品を生産し、競争力を高めるべく取り組んでいると考えるべきではないだろうか。
そのような視点で見返してみると、前項で指摘した日系海外現地法人の調達の現地化はアジアに限らず、米国や欧州など世界的に見られる傾向であることが分かる(第Ⅱ-3-3-30図)。特に経済統合の進む欧州においては、国内だけでなく欧州域内からの調達も含めた広い意味での「現地化」が進んでいる。
第Ⅱ-3-3-30図 日系製造現地法人の調達相手別シェア
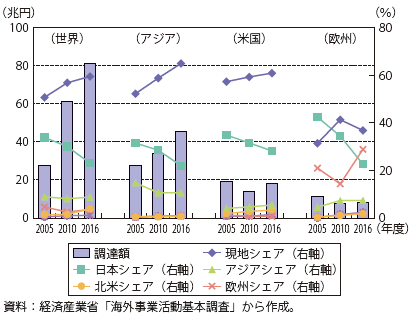
その背景にあるのは生産活動の効率化であり、現地で中間財を含めた産業集積が育ちつつあることを示唆している。その産業集積の中には、技術やスキルを向上させた地場企業とともに、現地に進出した日系部品サプライヤーも含まれている。もし、現地で安価かつ良質な中間財供給が受けられるならば日系組立企業にとっても有益である。日本からは現地では生産できないような、より高度で高付加価値な基幹部品を供給するという役割分担になってきていることが考えられる。
もちろん、そのためには親会社のある日本国内での活発な研究開発やイノベーション活動が重要となろう。また、受入国にとっては日系企業が進出して自由に活動できるように、規制の緩和、知的財産権の保護、海外送金の自由などビジネス環境の整備が前提となってくる。
②日系部品サプライヤーの現地進出
また、現地調達の調達先もかなりの部分まで日系企業が担っている。例えば、アジアの場合、製造業の現地調達のうち約1/4は日系現地法人から調達しており、その規模は日本からの調達額にほぼ匹敵する(第Ⅱ-3-3-31図)。日本からの調達(輸入)と現地日系企業からの調達を合計すれば調達額の約4割は広い意味で日本企業から調達していることになる。それを業種別にプロットしたのが第Ⅱ-3-3-32図である。横軸は日本からの調達シェア、縦軸は現地日系企業からの調達シェア、円の大きさは調達総額を示す。45度線より上にあれば現地日系企業からの調達の方が多く、下にあれば日本からの調達の方が多い。右上に位置するほど広義の日本からの調達比率が高い。
第Ⅱ-3-3-31図 アジアの日系現地法人の調達先内訳(2016年度)
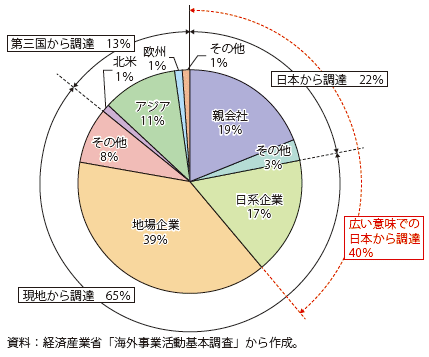
第Ⅱ-3-3-32図 アジアの日系製造業現地法人の広い意味での日本からの調達(2016年度)
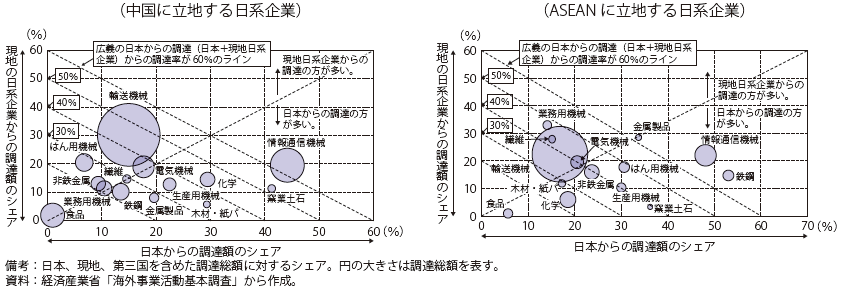
これによれば、日本からの輸入による調達比率は低下しているものの、依然として現地日系企業を含めた「広義の日本からの調達」は情報通信機械で調達額の6割を超え、輸送機械でも4割前後となっている。特に情報通信機械は調達額の4割以上を日本から輸入しており、現地では調達できない基幹部品がかなりあることを示唆している。なお、この図には表示されていないが情報通信機械は日本のほか、アジア域内からの調達も1割程度あるのに対して、輸送機械は圧倒的に現地調達が多くアジア域内からの調達はほとんどない。このような業種特性は、部品の規格化の程度、生産過程におけるすりあわせの必要性、輸送コストの違い、技術水準等が影響していると考えられる。
③企業収益の多様化
日本からの資材調達の低下は、これまでの日本の親会社からの輸出によって利益をあげるモデルから、次第に現地法人の売上によって利益をあげるモデルに重心が移っていく可能性を示唆している。この場合、海外現地法人を有している企業であれば、海外現地法人の収益は連結決算を通じて親会社の利益に組み込まれることになる273。
アジアに立地する日系製造業の日本との取引関係を見ると、世界金融危機後、日本からの調達額は危機前の水準を取り戻せずにいるが、配当金は年による変動はあるものの増加基調で推移している(第Ⅱ-3-3-33図)。さらにロイヤリティは年による変動も少なく安定的に増加している274。現時点では、配当・ロイヤリティとも、調達額に比べて金額的に約1/10の規模ではあるが、2000年代初頭と比べて相対的な比重は高まっている。これは日本の国際収支では財の輸出に代わって、第一次所得収支(配当金収入など)やサービス収支(特許等使用料など)の受取が増えてきていることに符号する。なお、海外現地法人の利益が日本に配当として送金されるためには、EPA戦略や規制制度改革等を通じて再投資先として日本国内市場の魅力を高めることが重要である。
第Ⅱ-3-3-33図 アジアの日系製造業現地法人の日本との取引関係(日本からの調達と親会社への配当・ロイヤリティ)
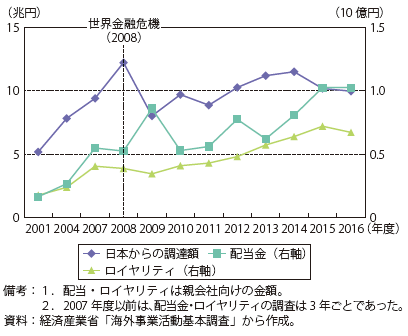
また、アジアは米国や欧州と比べても、配当・ロイヤリティ収入が大きく増加している地域でもある(第Ⅱ-3-3-34図)。
第Ⅱ-3-3-34図 日系海外現地法人の日本出資者への配当・ロイヤリティの推移
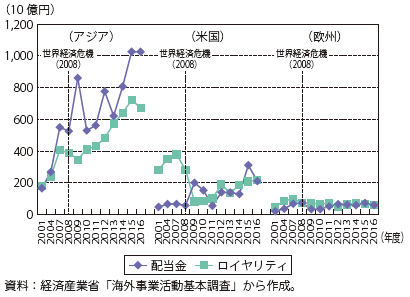
なお、立地地域によって配当・ロイヤリティの支払額を比べると、米国に立地する日系製造業はロイヤリティが配当に比べても顕著に多い(第Ⅱ-3-3-35図)。一方、アジアに立地する企業は配当を中心に親会社に送金している。現地における知的財産権保護の問題などあるものの、ロイヤリティのより一層の活用を検討してもよいかもしれない。
第Ⅱ-3-3-35図 日系海外製造現地法人の親企業への支払い(2016年度)
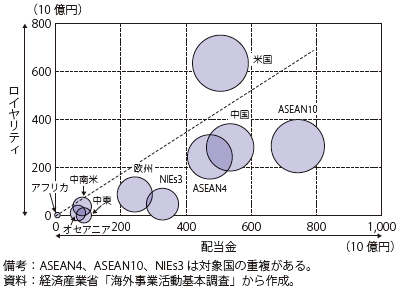
④資本関係のない企業への販売の促進
前節で見たように日本の輸出においては関係会社向け輸出(企業内取引)が大きな割合を占めている。自社の海外現地法人を戦略的に活用していくことは重要なビジネスモデルと考えられるが、一方では、企業の国籍(本社所在国ベース)を超えた取引も活発に行われている。例えば、ある電子機器(スマートフォン)の製造においては様々な国籍の企業が関与している。まず、米国に本社を置く米国企業が企画・設計を行い、次に日本企業、ドイツ企業、韓国企業等が重要部品の提供を行い、その上で台湾企業の現地法人が中国において組立を行い、最初に企画・設計を担当した米国企業が米国に輸入して、販売、メンテナンスを担当する。このような企業の国籍、生産拠点の所在国も超えて高度に発達したグローバル・バリュー・チェーンにおいては、自社の関係会社か否かを問わず積極的に優秀な部材を提供して売上をあげていくことも重要である。試みに日米で輸出における企業内取引の比率を比較してみると、日本企業は米国企業に比べて、企業内取引比率が極めて高いことが分かる(第Ⅱ-3-3-36表)275。
第Ⅱ-3-3-36表 日米企業の輸出における本社から自社の現地法人向け輸出のシェア
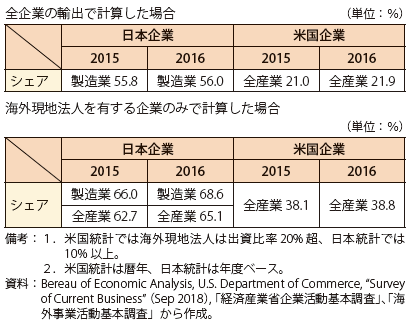
273 なお、海外現地法人を持たず国内からの輸出に従事する企業の場合は、このようなモデルは使えないので、海外進出を検討するのも一案であるし、製品の高度化、差別化など製品の競争力に磨きをかけるという対応になるかもしれない。
274 ロイヤリティは、売上に対して一定の比率を契約することが多いため、利益に大きく左右される配当よりも安定的な推移をしていることが考えられる。
275 日本統計では、総輸出、本社の海外現地法人向け輸出のいずれも「経済産業省企業活動基本調査」で調査対象とする製造業のみの数値。米国統計は、全産業が対象で、総輸出は米国の輸出総額。仮に日本統計の分母を日本の総輸出とした場合は、2015年、2016年の企業内比率はそれぞれ44.1%、45.0%と低下するが、米国より高いことに変わりはない。
(2)現地需要の更なる取り込み/小売・サービス業の展開
日本企業はアジアに積極的に進出し、現地法人の地域別進出先としては圧倒的なシェア(7割程度)を占める(第Ⅱ-3-3-37図)。その一方で、業種別に見ると、製造業・卸売業が過半を占め、小売・サービス業のシェアが他地域と比較し低く、今後まだ拡大余地があると考えられる。第Ⅱ-3-3-38表は、日系海外現地法人の主要業種・地域別売上高を比較したものである。アジアは、米国や世界平均と比べて、小売業、サービス業のシェアが低い。
第Ⅱ-3-3-37図 日系海外現地法人数の地域別シェア(2016年度)
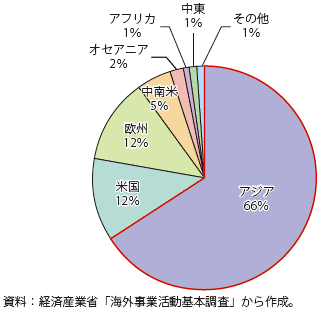
第Ⅱ-3-3-38表 日系海外現地法人の主要業種・地域別売上高(2016年度)
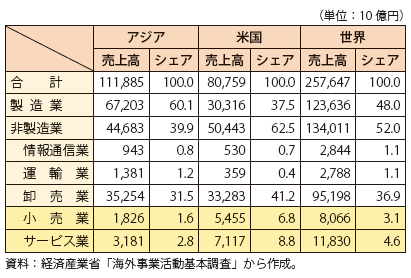
また、アジアにおける主要国の現地法人売上高を比較してみても、日本は製造業のシェアが高い(第Ⅱ- 3-3-39図)276。日本の場合、製造業、卸売業だけで売上の約9割を占め、サービス業、小売業は限られたシェアとなっている。それに対して米国は、サービス業、小売業、運輸業、情報通信業等を含めて多彩な業種が進出している。
第Ⅱ-3-3-39図 アジアにおける主要国現地法人売上の業種構成(2016年)
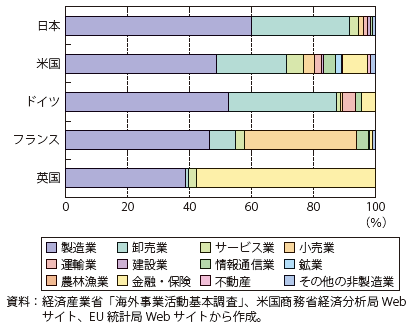
中国を始めアジア諸国は所得向上に伴って、次第にマーケットとしての重要性も高まってきている。日系現地法人は、進出当初は輸出主体の場合もあるが、工夫をこらして現地需要の取り込みを図っていく必要がある。例えば、製造業でもB to C業種(生活用品関連)の拡大の余地があるかもしれない。その際に現地パートナーとの協力関係を築くことは有益との指摘がある。特に、アジアではプラットフォーマーと呼ばれるインターネットを活用した新しいビジネスを開拓する企業が台頭している。
276 各国統計の業種区分等をそろえるなど極力比較可能なようにしたが、必ずしも平仄が同じではない点には注意が必要。例えば、日本の場合、親会社が金融・保険、不動産の場合は調査対象から除外されている。米国の場合はアジアのほか大洋州も含む。欧州の場合、アジアの中でも特定の立地国のデータのみが公表され(中国、香港、インド、インドネシア、タイ、日本、韓国)、業種によってはデータの入手できないこともあるため、確認できるデータだけで集計している。
(3)今後の成長市場への参入
これまでは日系海外現地法人のアジアへの展開に焦点をおいて考察してきた。日系海外現地法人の進出先としては日本の近隣であるアジアが圧倒的に大きなシェアを占め、それに次いで先進国で所得水準も高い米国や欧州への進出が多い。その一方で、その他の地域への進出は限られている。
例えば、アフリカは人口増加により「新たな新興国」として急速に注目を集めるが、主要国と比較して日本企業の関与はいまだ小さい(第Ⅱ-3-3-40図、第Ⅱ-3-3-41図)。中南米についても同様である(第Ⅱ-3-3-42図)。他国に遅れることなく、日本企業も輸出拡大、投資拡大を図っていくべきである。
第Ⅱ-3-3-40図 主要国のアフリカへの輸出額の推移
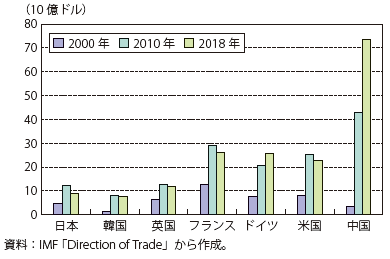
第Ⅱ-3-3-41図 対アフリカ直接投資残高の推移(10億ドル)
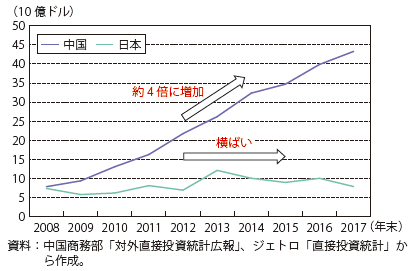
第Ⅱ-3-3-42図 主要国の中南米への輸出額の推移
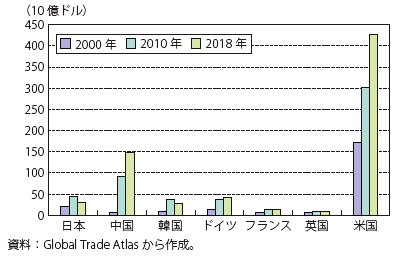
アフリカ、中南米の両地域について、世界のGDPシェアと日系海外現地法人の企業数、売上高シェアを比較したのが第Ⅱ-3-3-43表である。海外現地法人の展開は、立地国の投資環境や日本からの距離などの要因が関係してくるため一概には言えないが、アフリカ、中南米が世界に占める経済規模のシェアを考えれば、日系企業のより積極的な関与が期待される。
第Ⅱ-3-3-43表 世界のGDPシェアと日系海外現地法人の地域別シェア
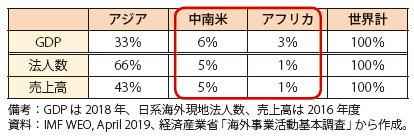
前節及び本節で検討したデータを中心に、欧米企業とも比較しながら、日本企業の目指すべき方向性を考察した。もちろん、目指すべき方向性は、企業により、業種により、対象とする国・マーケット・階層により一様ではない。最も重要なことはそれぞれの事情にあった戦略を考えていくことであろう。