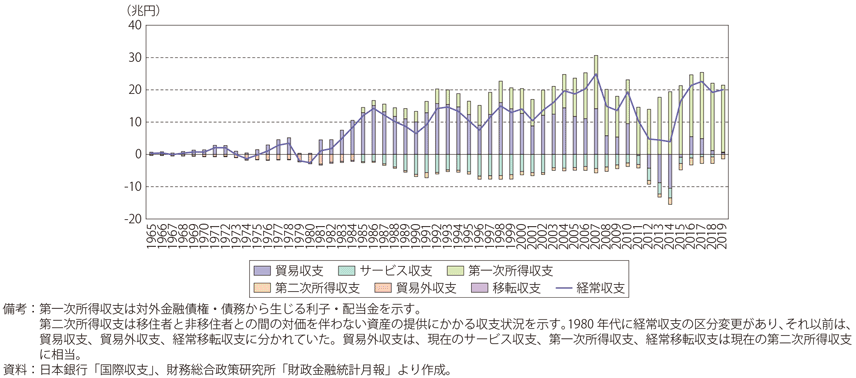- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第2章 第3節 日本のグローバリゼーションの歴史
第3節 日本のグローバリゼーションの歴史
第2次世界大戦以降、20世紀後半にかけて、日本経済は、世界経済とのつながりを深める中で、グローバリゼーションの進展、自由貿易の恩恵を受けながら、急速に成長を遂げた。日本のドル建てのGDP額の推移を見れば、経済成長や1985年のプラザ合意以降、急速に円高方向に推移したこともあり、特に1980年代から伸びが加速し、1993年には世界GDPの約18%を占めた。貿易額は1980年から急速に伸びており、一時減少したものの、再び拡大傾向にあり、日本経済を支えている(第Ⅱ-2-3-1図、第Ⅱ-2-3-2図)。
第Ⅱ-2-3-1図 日本のGDPの推移
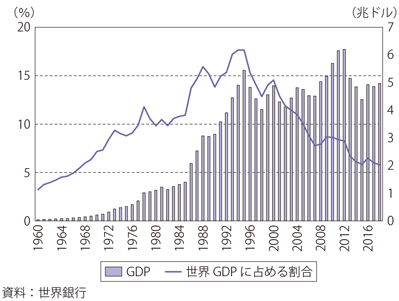
第Ⅱ-2-3-2図 日本の貿易額の推移
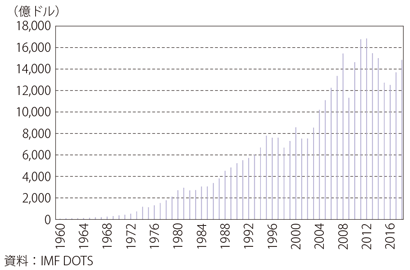
日本の貿易の相手国も変遷してきており、かつては米国が最大の貿易相手国であったが、現在は中国が最大の貿易相手国となっており、また、アジアの国・地域との貿易の拡大も見て取ることができる(第Ⅱ-2-3-3表、第Ⅱ-2-3-4表)。
第Ⅱ-2-3-3表 日本の輸出相手国上位10か国
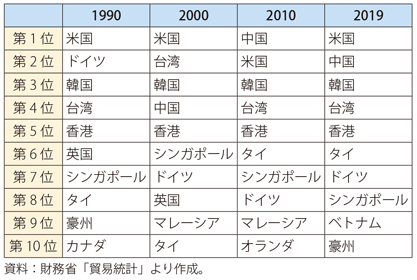
第Ⅱ-2-3-4表 日本の輸入相手国上位10か国
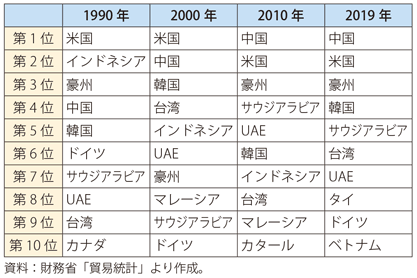
品目別に見ると、貿易としては、一般機械、自動車などの輸送用機器の輸出割合が高く、テレビなどの電気機器の割合は減少傾向にある(第Ⅱ-2-3-5図)。
第Ⅱ-2-3-5図 日本の品目別の輸出割合
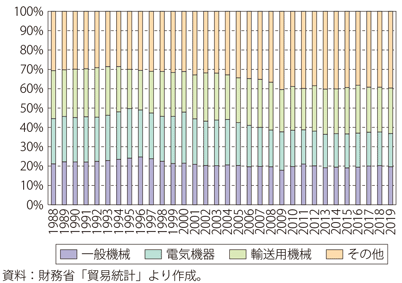
その一方で、サービスの貿易は拡大しており、サービス輸出は2019年に現行の基準では初めて黒字化をした。その要因の一つとして、インバウンドの拡大があり、2019年の旅行収支は2兆円を越える黒字であった(第Ⅱ-2-3-6図)。
第Ⅱ-2-3-6図 サービス貿易の内訳
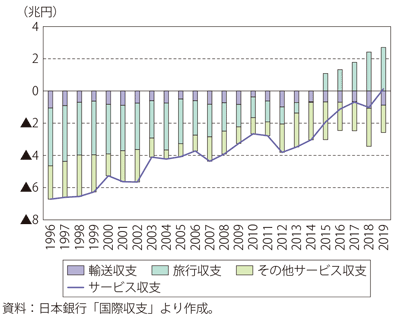
その中で、日本企業は1990年代以降に特に、アジアへ製造業の拠点を移し、生産活動を開始した。第1節において議論した第2アンバンドリングの波はアジアで顕著に見られ、日本とアジアの各国での生産ネットワークが拡大していった。
対外直接投資は拡大を続けており、対外直接投資の残高は過去10年間で2倍強の水準にまで拡大している。対内直接投資残高も拡大傾向にあり、世界とのつながりが資金の面でも増している(第Ⅱ-2-3-7図、第Ⅱ-2-3-8図)。
第Ⅱ-2-3-7図 業種別の対外直接投資残高
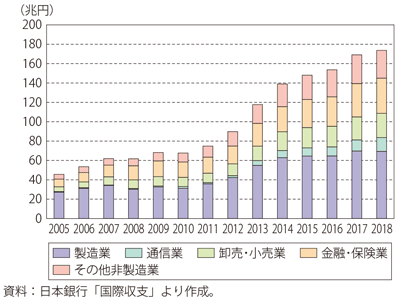
第Ⅱ-2-3-8図 業種別の対内直接投資残高
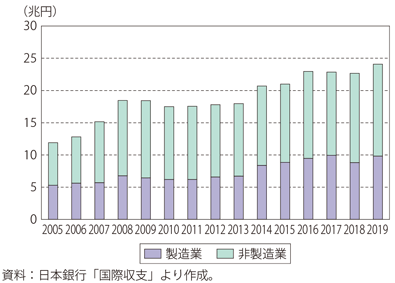
地域別に見ると、欧州、北米、アジアへの対外直接投資残高が大きなものとなっている。特に、近年アジア向けの対外直接投資が拡大しており、これはアジアの高い成長力を日本が取り込んでいることを示唆するものである(第Ⅱ-2-3-9図)。
第Ⅱ-2-3-9図 地域別の対外直接投資残高
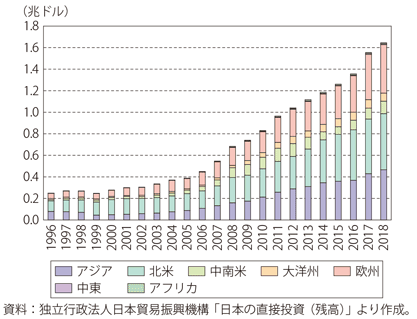
なお、日本のグローバル・バリュー・チェーン参加率をみると、1990年以来、前方・後方への参加ともにその割合が伸びている。前方への参加(Forward Participation)とは、他国の輸出財・サービスの生産に中間投入として使用されている自国の輸出財・サービスの金額が、自国の輸出総額に占める割合を表す。また、後方への参加(Backward Participation)とは、自国の輸出財・サービスの生産に中間投入として使用されている他国からの輸入財・サービスの金額が、自国の輸出総額に占める割合を表す。
長年にわたって、日本の前方への参加度が高いものであったことは、他国に対する中間財やサービスの供給によるものであり、日本企業の技術力やサービスの質の高さを比較優位として、世界で事業展開していたことによる。また、世界経済が活性化することにより生じた需要が、輸出増加を通じて国内に取り込まれるものであった。他方、近年は、後方への参加度の割合が増えており、生産工程の国際的な最適化を通じて、国内生産拠点の生産性向上を図るビジネスモデルへと変換していることが伺われる。
日本の対アジア向けの直接投資残高としては、2010年代以降は特に非製造業の投資額が堅調に伸びていることが分かる。日本企業の対中国・ASEAN4への企業進出数は、製造業・非製造業ともに増加している(第Ⅱ-2-3-10図~第Ⅱ-2-3-13図)。
第Ⅱ-2-3-10図 日本のGVC参加率の推移
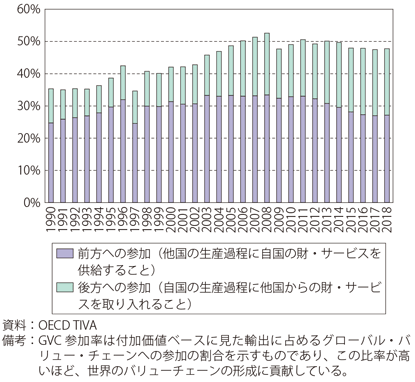
第Ⅱ-2-3-11図 日本のアジア向けの業種別直接投資残高
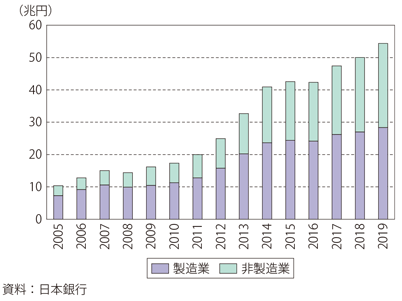
第Ⅱ-2-3-12図 日本企業(製造業)の海外進出企業数推移
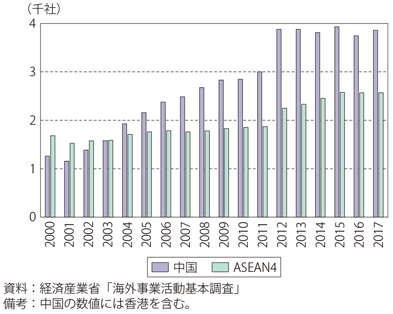
第Ⅱ-2-3-13図 日本企業(非製造業)の海外進出企業数推移
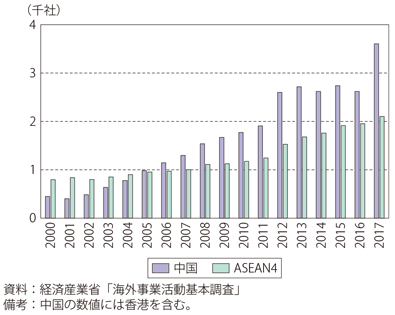
経済のグローバリゼーションの進展に伴い、金融の分野においても大きな変化を遂げた。戦後のブレトンウッズ体制においては、為替レートの安定性を維持すべく、固定相場制が採用され、1ドル360円と固定されていた。1971年のニクソンショックを経て、日本も1973年から変動相場制へと移行した(第Ⅱ-2-3-14図、第Ⅱ-2-3-15図)。国際金融のトリレンマとして知られるように、変動相場制のもとで、自由な資本移動と中央銀行による独立した金融政策を実現する土台となった。
第Ⅱ-2-3-14図 実効為替レートの推移
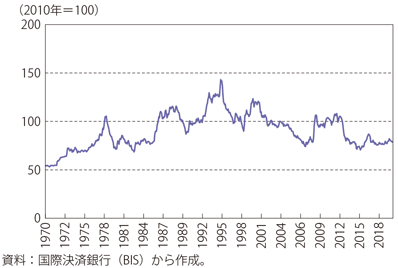
第Ⅱ-2-3-15図 円の対ドル為替レートの推移
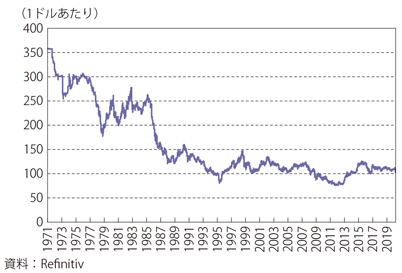
このように、日本の世界とのつながりが増す中で、日本の稼ぎ方についても変化が見られるようになった。第Ⅱ-2-3-16図において、1965年代以降の日本の経常収支を示している。1965年以降から近年まで、貿易収支は黒字基調で推移してきた。また、1980年代以降は経常黒字が定着した。その中で、経常黒字の内容には変遷が見られている。貿易黒字は2000年代後半以降に縮小し、2010年代前半や2010年代後半には貿易赤字となることも見られた。その一方で、第一次所得収支(証券投資収益、配当など)は近年GDP比で4%程度の黒字となり、日本の経常黒字を支えている。これは、アジアを中心とした生産ネットワークの構築、直接投資の拡大を反映したものでもあり、高成長を続けるアジアの成長を日本が取り込み、貿易による経常黒字から投資による経常黒字への変化、つまり、貿易立国から投資立国への変化を示すものである。その過程で複雑なサプライチェーンが形成されており、その動向は第1章において行った分析のとおりである。
第Ⅱ-2-3-16図 経常収支の内訳