

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅱ部 第2章 第5節 世界における第3のアンバンドリングに向けた移行の動き
第5節 世界における第3のアンバンドリングに向けた移行の動き
第3のアンバンドリングにおいては、デジタル技術の活用による国境を越えたバーチャルワーク(遠隔労働)やホワイトカラーロボットの到来「グロボティクス転換(グローバル化+ロボット化)」に直面することとなる。これらのフェイス・トゥ・フェイス・コミュニケーションの代替を可能にする新しいコミュニケーションは、情報通信技術の活用、AI(人工知能)やロボット技術の急速な発展がキーテクノロジーとなっている。これらの活用により、産業面において国境を越えたバーチャルワーク(遠隔労働)やホワイトカラーも含む労働の自動化が起こり、グローバリゼーションのあり方が変容するとボールドウィンは予測している74。
このように第2アンバンドリングの中心であった製造業に留まらず、第3のアンバンドリングにおいてはサービス業も含めて、新しい産業変革の波が起こっている。そのように世界が第2のアンバンドリングから第3のアンバンドリングへの変革を迎える最中に、新型コロナウイルスの感染拡大が発生した。その結果、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを補完する手段として、自動化や遠隔技術に注目が高まっている。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によりコミュニケーションにも変化が生まれてきているが、これは第3のアンバンドリングを加速するものともいえる。
そして、グロボティクス転換に対応するには、十分なICT投資とバーチャルワークが可能な環境の整備、AIやロボットなどの技術革新に対応可能な高度なスキルを持った人材育成が必要である。世界では第3のアンバンドリングの波を捉えた動きが進められているが、新型コロナウイルスの感染拡大という危機を機会として、日本においても産業変革の波を捉えていくことが求められている。
74 リチャード・ボールドウィン、高遠裕子訳(2019)『GLOBOTICS(グロボティクス)グローバル化+ロボット化がもたらす大激変』、日本経済新聞出版。
1.世界における第3のアンバンドリングに向けた移行の動き
第2のアンバンドリングでは主に製造業における国境を越えたサプライチェーンの構築・国際分業が進展してきたが、今後のグローバリゼーションの局面においては、サービス業においても国際分業やAIとの分業という新しい状況に直面することが予想されている。
1970年代以降の製造業からサービス業への転換以来、産業全体に占めるサービス業の割合は堅調に拡大しており、今後もサービス業の比率が高まっていくことが予測されている(日本経済研究センターによる試算、第Ⅱ-2-5-1図)。特に米国、EU、英国、日本を含むOECD諸国におけるサービス業従事者割合は世界平均に比べて約20%も高く、先進国が今回のグロボティクス転換で大きな影響を受けることが予想される(第Ⅱ-2-5-2図)。
第Ⅱ-2-5-1図 製造業・サービス業比率の見通し
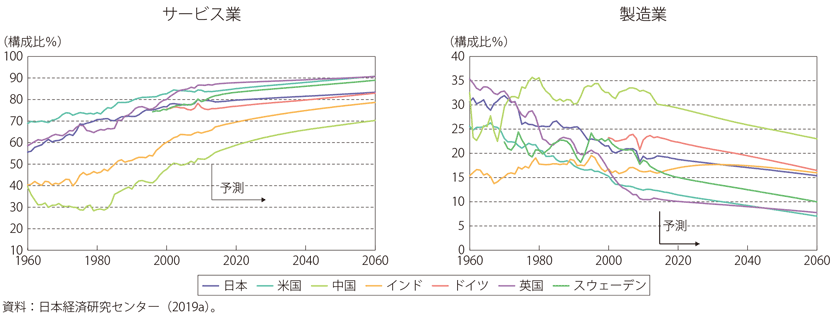
第Ⅱ-2-5-2図 各国・地域のサービス業従事者の割合
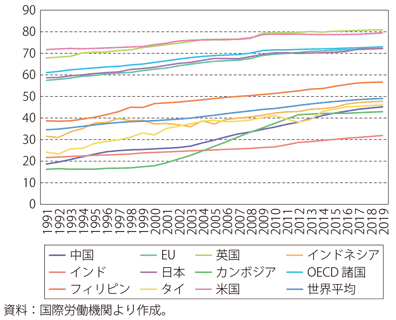
そして、第3のアンバンドリングにおいては、インドや他の途上国の高度なスキルを有するフリーランサーのIT技術者が、米国など先進国のIT企業に母国を離れることなく雇われるという「遠隔移民」が生じ、ボーダレスな働き方が可能になる一方で、それは米国など先進国のホワイトカラーを含む労働者と競争するといった状況が生じることが予測されている。
その中で、著しいデジタル技術の発展を受けて、世界では様々な投資やサービスが提供され始めており、世界各国で国家戦略としてAIや5Gの導入が推進されるなど、産業変革の流れを政府も後押ししている(Box)。
資料:JETRO ビジネス短信、地域・分析レポート、一般財団法人マルチメディア振興センター。
このようなAI技術や今後のデジタル化の基盤となる5Gは、ネットワーク効果を通じた外部性や補完性を有するインフラであり、民間の投資だけでは過小投資になる可能性もあり、世界各国が第3のアンバンドリングに向けた動きを進めるに当たっても、国家の適切な関与や標準化作りを進めることが重要になる。
さらに、新型コロナウイルスの感染拡大は経済・社会のデジタル化を加速させている。ロックダウンや外出自粛が導入される中、デジタルサービスに対するニーズの高まりが見られている。
第1章第6節においてコロナテックの急速な社会実装を見たが、感染拡大を防ぎながらサービスを提供する無人化や遠隔の技術の導入、AI画像認識を使った自動診断、チャットボットを使った健康管理やテレワーク支援プラットフォームなど、コロナ危機を受けて新たなデジタル技術の社会実装が急速に進行している。これらは、第3のアンバンドリングに向けた社会実装の動きと解釈することもできるだろう。そして、国境を越えたバーチャルワークの可能性は、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う人の移動の停滞を補完する側面がある。
その中で、世界ではデジタル化の動きを加速している。
中国政府は3月4日の中国共産党中央政治局常務委員会で「新インフラ建設(新基建)」を再度提唱し、投資規模は年内に1兆元75と予測されている。5Gインフラも「新インフラ建設」の対象3領域に含まれており、5G関連分野では2025年までに累計3.5兆元76の投資が予測されている(Box)。
このように中国では、新型コロナウイルス感染症に対処するため様々なデジタルサービスの社会実装が加速すると同時に、中長期的なイノベーションを促進する動きがみられる。
75 http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/21/c_1125883443.htm![]()
76 http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-03/27/c_1125775213.htm![]()
同様に、インドのモディ首相は5月12日、GDPの約10%に相当する20兆ルピー規模の経済対策パッケージの投入を発表し、現在の危機を乗り切るため、自立したインドとなることが唯一の道であり、自立したインドは、経済、インフラ、テクノロジー主導のシステム、世界最大の民主主義国インドの強みである人口、需要喚起の5つの柱により成り立つと述べた。
シンガポール政府は、中小の金融機関やフィンテック企業を対象として、デジタル化の推進や社員教育に力を入れた企業に補助を行うとしている。具体的には、サイバーセキュリティー、AIの導入などについて補助金を支給することや、社員教育として専門教育を受けた場合、費用負担を行うことを表明した。決済のデジタル化についていえば、小売店や飲食店に加え、屋台や生鮮市場が電子決済を導入する際にも支援することとしている。また、大企業のデジタルプラットフォーマーとの協業に対しても支援するとしているなど、デジタル化を促進させる動きが見られる。
第3のアンバンドリングに向けた産業革新においては制度面も重要である。EUでは、2018年5月に一般データ保護規則(GDPR)が施行された。その中ではデータポータビリティが規定されており、これは、個人が自身のデータを機械可読な形式で受け取ることや、他の事業者に移行することを可能とするものである。これは、個人情報の保護にとどまらず、経済的な意義も有する。これにより、既存企業のデータの囲い込みが難しくなる一方で、個人に対しては利便性を求めてデータを提供するインセンティブを付与するものであり、企業のデータ活用に関する競争を促し、イノベーションを促進することが期待される。
このように、世界では第3のアンバンドリングを加速させるための投資や人材への投資が進められている。さらに、デジタル化の更なる進展という経済実勢を踏まえた制度面での取り組みも見られる。
新興国においても、第3章のアジア・デジタルトランスフォーメーションにおいて見るように、新興国における規制体系の弱さと既存産業の不在により、新たな技術の応用が加速されるケースも見られている。一方、そのデジタルトランスフォーメーションを国全体で進めていくに当たっては、ハード・ソフトのインフラ、政策環境、人的資源などが課題として指摘されることもあり、政府と民間のそれぞれが役割を補完し合うことが重要である。
2.第3のアンバンドリングに向けた日本の課題
この第3のアンバンドリングに向けた世界の流れの中で、日本の現状と課題を確認しよう。
まず、第3のアンバンドリングに向けたインフラの一つであるICT投資の状況である。ICT資本のストック(情報通信機器とコンピューターソフトウェアの合計)の対GDP比を見ると、他国では経済・社会のデジタル化の進展に伴い上昇している中で、日本においては、水準自体は高いものの、その水準が停滞をしている(第Ⅱ-2-5-3図)。
第Ⅱ-2-5-3図 実質ICT投資の各国比較(各国GDP比)
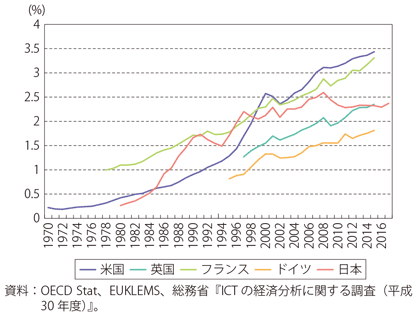
第3のアンバンドリングでは、従来の対面のサービスと異なり、デジタルのサービスにおいて物理的な制約が取り除かれ、遠隔地においても消費活動が行われる。既にいくつかの産業においては物理的な制約を克服しつつあり、デジタル貿易、サービス貿易の拡大が進んでいる。今後、第3のアンバンドリングが加速する中で、サービス分野の貿易は更に拡大することが予想される。
近年のサービス分野の貿易の動向を確認していく。世界的にサービス貿易は拡大傾向にあり、その中でも、テレコミュニケーションやIT、ビジネス・サービスといった分野で近年大きく拡大をしている(第Ⅱ-2-5-4図)。
第Ⅱ-2-5-4図 サービス貿易の拡大
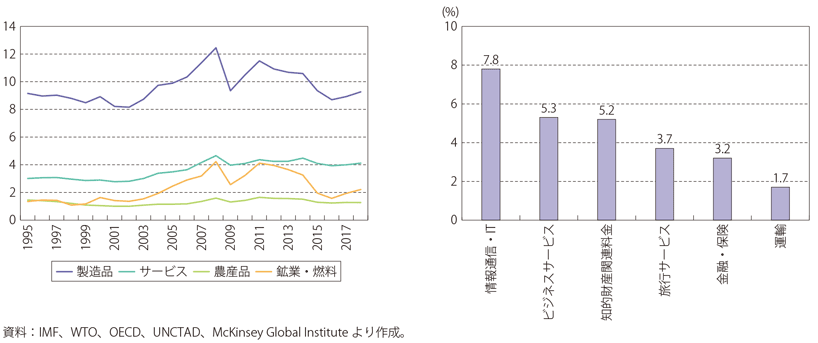
しかし、日本はデジタルも含めたサービス市場での輸出に課題がある。各国の動向を比較すると、ITサービスにおいては、中国や米国、そして、インドの伸びが大きい。インドは、先進国のオフショアリングを低コストで受け入れ、英語で業務を行うという受け皿となってきた。専門サービスにおいては米国が強く、これは、コンサルティングといった分野に強みを有するためでもある。いずれの分野でも日本のサービス輸出については大きな変化がない(日本経済研究センター、第Ⅱ-2-5-5図)。
第Ⅱ-2-5-5図 サービス貿易の分野別・国別伸び額(2000年・2014年)
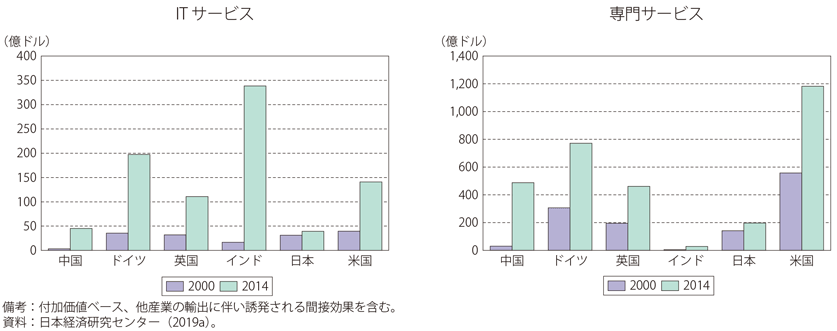
(1)ICTの導入・活用の状況
それでは、日本の第3のアンバンドリングに向けた課題はどのようなものだろうか。まず、デジタル技術の導入の状況を確認していく。
日本企業を対象としたアンケート調査の結果では、企業のICT導入比率は70%と、米国、英国、ドイツと比較して低位にある(第Ⅱ-2-5-6図)。さらに、日本企業によるICT導入・利活用の状況については、大企業で比較的利活用されているものの、中小企業での利活用は低い割合にとどまっている(第Ⅱ-2-5-7図)。
第Ⅱ-2-5-6図 各国企業のICT導入状況
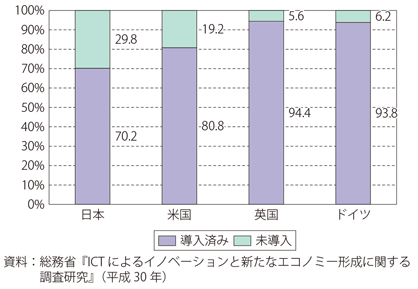
第Ⅱ-2-5-7図 日本企業のICT導入・利活用の状況(社内向けサービスへの活用状況)
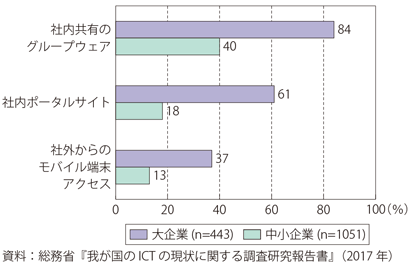
また、第3のアンバンドリングによる産業変革によって、サービス業に従事する労働者を中心に多くの労働者がICTを活用する業務を行う必要が生じることが予想されるが、その変化に対応可能なICTスキルを持った人材育成も重要である。
OECDの国際成人力調査(PIAAC)によると、日本のICTを活用した問題解決能力の平均点の分布は、参加国中1位と高水準であり、ICTを活用できる能力については平均的に見て質が高いといえる(第Ⅱ-2-5-8図)。
第Ⅱ-2-5-8図 ICTを活用した問題解決能力の平均点の分布
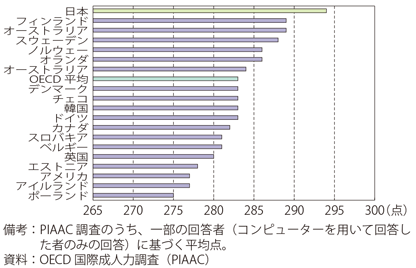
同じくOECDが実施している、初等中等教育段階の児童生徒を対象とした学力調査(生徒の学習到達度調査(PISA))の最新の2018年調査においては、学校の授業においてデジタル機器を利用する時間はOECD平均と比較して大幅に少なくなっており、学校教育におけるICTの導入が進んでいるとはいえない状況にある(第Ⅱ-2-5-9図)。政府は2019年度補正予算において、児童生徒一人につき一台デジタル端末を使うことのできる環境、及びICT化の促進を行うための高速大容量通信ネットワークを整備するための経費を盛り込むなど、教育のICT化に向けた取組を進めている。これらのICT環境を活用し、初等教育段階からの幅広いICT教育が実施されることが今後期待される。
第Ⅱ-2-5-9図 初等中等教育におけるデジタル機器利用状況
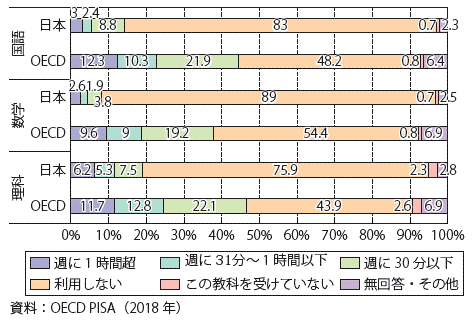
(2)第3のアンバンドリングに向けた日本の課題:無形資産、競争力、ガバナンス、イノベーション
新型コロナウイルスの感染拡大の中で、ITプラットフォーマーへの集中のように、デジタルサービスを活用し、無形資産を有する企業の活動が活発化した。デジタルサービスの拡大する第3のアンバンドリングにおいても同様に、それらの優位性が継続することが想定されるものである。
(1)において示したように、日本はICTの投資や利活用に課題を抱えるが、無形資産の蓄積においても同様の課題が見られる。無形資産とは、コンピューターのソフトウエアやデータ、研究開発による技術や特許、企業や製品のブランドを含むものである。
有形資産への投資と無形資産への投資を比較すると、無形資産への投資が拡大をする傾向は多くの国で見られており、米国においてはその水準が逆転している。その一方で、日本においては、有形資産投資がGDP比で減少傾向であり無形資産投資は増加傾向にあるものの、現在でも有形資産への投資が大きい(第Ⅱ-2-5-10図)。
第Ⅱ-2-5-10図 日米の有形資産投資・無形資産投資(対GDP比)
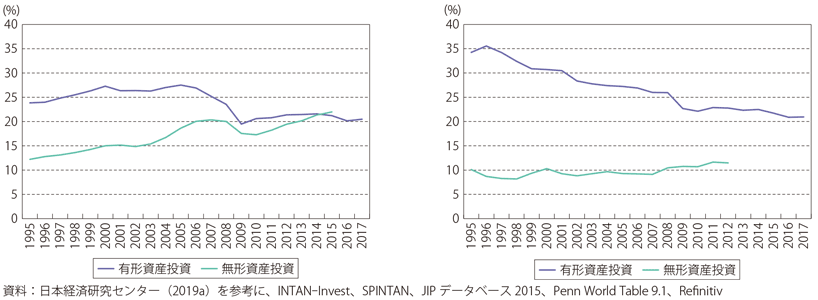
日本の無形資産投資の内訳としては、革新的資産投資が中心であり、ソフトウエアや研究開発にはGDP対比で他の先進国にも遜色のない投資を行っている。革新的資産投資とは、科学・エンジニアリング研究開発、鉱物探査、著作権・ライセンスその他製品開発、デザイン、研究開発である。一方、他国と比べて小さいものは、ブランド、組織構造や社内教育など経済的競争力に関する投資である(第Ⅱ-2-5-11図)。
第Ⅱ-2-5-11図 日本の無形資産投資の内訳
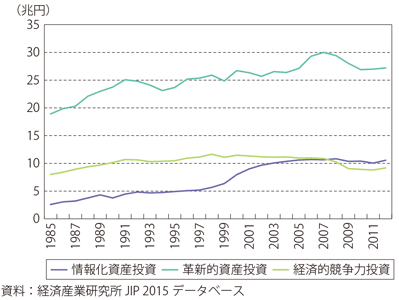
ジョナサン・ハスケルら77は、無形資産をコンピューター化情報、イノベーション財産、経済能力に分ける。これは上記の3分類にも対応するものであるが、導入した新技術を活かし、ブランド化し、経済競争力とする投資に課題がある状況といえるだろう。
第Ⅱ-2-5-12表 無形資産投資の3類型
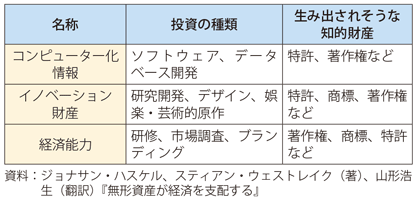
それでは、なぜ日本では無形資産、ICTの活用が十分に進まず、競争力に結びつかないのだろうか。これはITのリテラシーを向上させるための投資や組織・労働の硬直性について課題が存在していることにある。攻めのICTを重視せずコスト削減の手段として活用することや、ICT導入と補完的なものとなる人的資本や無形資産投資への過少投資が存在するといった指摘も存在する78。
つまり、日本企業の迅速な意思決定を阻むような組織構造や、事業環境などには改善余地があるということでもあり、また、人的投資に関しては、日本の企業による社員の教育訓練への支出が減少傾向にある中で、企業の訓練投資にとどまらず、個人に着目し、個人ベースでの学習を促進することも重要になる。
そこで、無形資産の外部性に注目することも重要であろう。ハスケルらによれば、無形資産は他の企業へも恩恵をもたらす波及効果が大きいという性質を持つ。つまり、有形資産の場合には競合性・排除性という性質を持つが、無形資産は同じ資産を同時に使うことができるという非競合性を有するためであり、公共財と同じような性質を有する。また、アイディアは摩耗することはなく、共有することにより波及効果が期待できる。
無形資産の台頭する状況は今後ますます加速するデジタル化という世界の変化に対応した人的・組織的な経済能力を高める重要性を示している。
また、無形資産への投資やその活用を促進するとともに、無形資産の活用を促す制度面での環境整備も重要であろう。EUのGDPRは個人情報のポータビリティに特徴があるが、日本においても2019年6月のG20大阪サミットの際、データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト(DFFT)としてデータ流通の国際ルール作りを進める「大阪トラック」の開始を主導した。このようなルール作りでの協調も、国際的なデータ流通でデジタル技術を生かしながら第3のアンバンドリングに対応し、産業変革の波に対応していくために重要である。
そのDFFTを具現化するため、WTOにおいて、日米欧や中国等84の加盟国・地域が参加して電子商取引に関する交渉を進めている。また、多国間での制度協力の推進も重要である。2019年1月には、日EU間の個人データに係る相互認証枠組みを構築している。
さらに、このようなデジタルの時代に即したガバナンス・イノベーションも重要である79。2019年6月のG20貿易・デジタル経済大臣会合の閣僚声明において、ガバナンス・イノベーションの必要性が謳われたが、近年の技術革新の中で、イノベーションの促進と社会的価値の実現を両立する新たなガバナンスモデルの必要性が高まりを見せている。つまり、サイバー空間を起点として技術やサービスが革新される中で、そのリスクをコントロールするガバナンス自体にも、革新的な方法が導入される必要がある。そして、その実現には、イノベーションの中心的な担い手となる企業や、多様な価値観の担い手である個人による積極的な関与が不可欠であり、国家や政府だけではなく、企業やコミュニティ・個人が協力してガバナンスの担い手となるような抜本的な規制改革、ガバナンス・イノベーションに取り組むことが必要である。さらに、サイバー空間は容易に国境を越えることから、デジタル技術による新たなリスクのコントロールは国際的に共通のアジェンダであり、新たなガバナンスモデルを国内外の様々なステークホルダーと協調しつつ実装に取り組んでいくことが重要である。
このように、新型コロナウイルスの感染拡大は、現在の第3のアンバンドリングという産業革新と平行して、今後の労働のあり方、政府のあり方にも転換の可能性をもたらすものである。
他方で、日本においては、ICT技術やその活用を経済能力に結びつけることの課題、そして、制度整備の重要性が認識される状況にある。デジタルトランスフォーメーションの機会も積極的に活用していくことで、新型コロナウイルスの感染拡大という世界的な危機を、第3のアンバンドリングへ向けた変革を迎えるための機会とすることが日本には求められている。
77 ジョナサン・ハスケル、スティアン ウェストレイク著、山形浩生訳『無形資産が経済を支配する:資本のない資本主義の正体』。2020年。東洋経済新報社。
78 金榮愨(専修大学)「無形資産投資(R&D、ICTなど)」2016年11月25日 財務省財務総合政策研究所「企業の投資戦略に関する研究会」報告。
79 経済産業省「GOVERNANCE INNOVATION: Society5.0の時代における法とアーキテクチャのリ・デザイン」。
