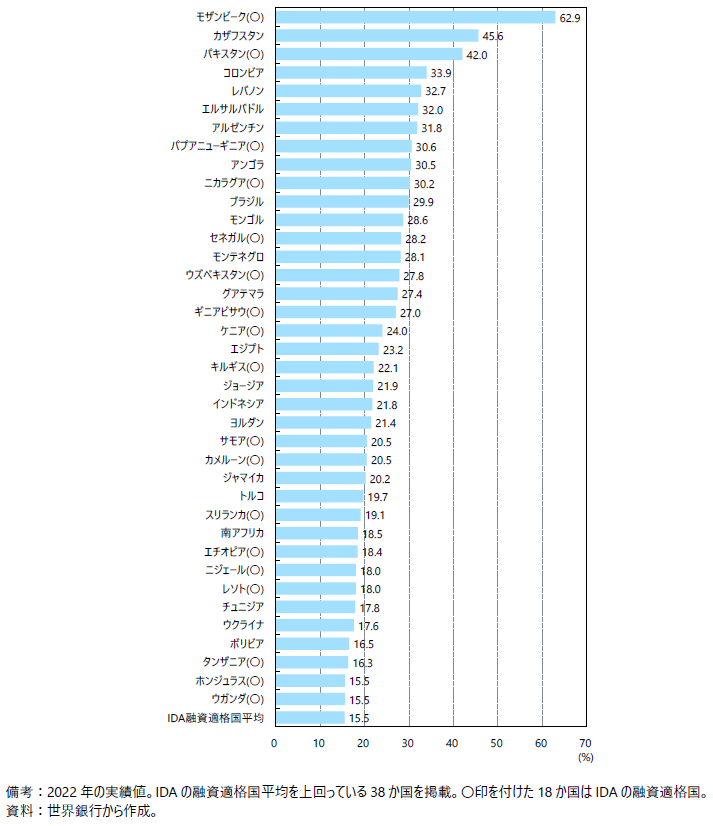第1節 世界経済の現状と見通し
本章では、最近の世界経済の動向及び今後の見通しについて概観するとともに、2022年以降、世界経済に大きな影響を及ぼしたインフレの動向、物価安定のために講じられた金融政策の動向、新興国・発展途上国を中心とした債務の動向について見ていく。
本節では、IMFの「世界経済見通し(WEO)」を中心に、最近の世界経済の動向及び今後の見通しについて概観する。
1.世界経済の現状と見通し
2023年の世界経済は、当初の予想を上回る底堅い成長が見られた。IMF1によると、2022年には新型コロナウイルス感染症拡大からの回復による急成長が、インフレの加速等の要因により減速していたことから、当初は2023年もその影響が持続し、世界的なスタグフレーションや景気後退に陥ることも懸念されていた。しかし、予想よりも早いペースでインフレに落ち着きが見られ、また、予想を上回る労働参加率の上昇を主な要因とする供給サイドの拡大や、個人消費や政府支出といった項目での予想を上回る増加によって需要が下支えされたことから、2023年の世界経済の成長率(実質GDP成長率)は累次にわたって上方修正され、2024年4月の見通しでは、世界全体では3.2%、先進国では1.6%、新興国・発展途上国では4.3%となっている。(第I-1-1-1図)
第Ⅰ-1-1-1図 実質GDP成長率の見通し
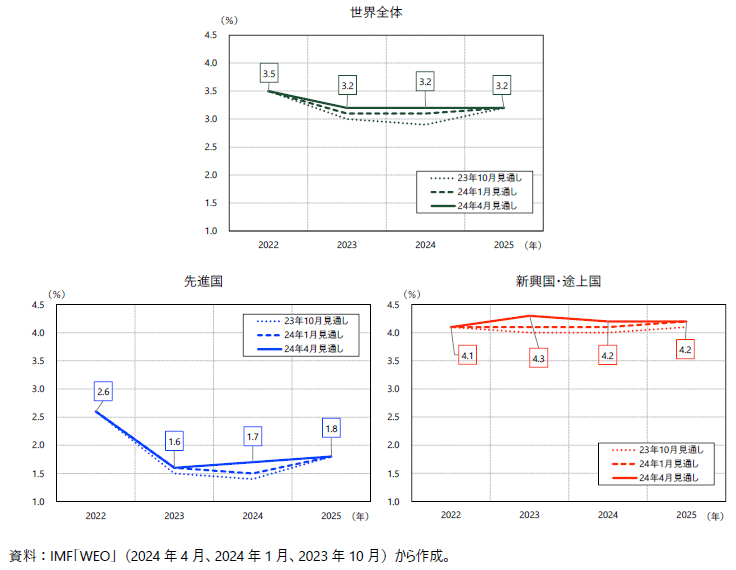
ただし、2023年の経済の回復には、国・地域ごとに差が見られる。IMFによると、先進国では、米国の成長率が最も高く先進国全体の成長率を大きく上回っており、成長に底堅さが見られることから成長率見通しも上方修正されている。また、日本の成長率は、先進国全体の成長率を上回る値となっている。一方で、ユーロ圏や英国は成長率が先進国全体の成長率を大きく下回っており、かつ、ロシアによるウクライナ侵略等の影響も反映され、成長率は下方修正されている。このように、先進国においては、米国と、米国以外の国・地域との間の成長率に差が見られ、また、その差は拡大傾向にあることが見て取れる。
新興国・発展途上国では、インドの成長率が新興国・発展途上国全体の成長率を大きく上回っており、かつ、上方修正が続いている。また、中国やASEAN5の成長率は、新興国・発展途上国全体の成長率と同程度の値となっている。一方で、欧州の新興国・発展途上国やアフリカ、中南米、中東・中央アジアの成長率は、新興国・発展途上国全体の成長率を大きく下回っている。よって、新興国・発展途上国についても同様に、地域ごとに成長率に差が見られることが見て取れる。(第I-1-1-2図)
第Ⅰ-1-1-2図 2023年の国・地域別の実質GDP 成長率
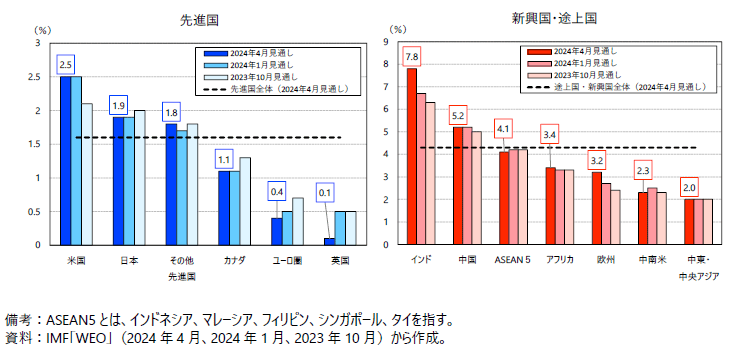
IMFのWEOに基づいたブルームバーグの試算2によると、中国は今後5年間、世界の経済成長に最も寄与する国となり、その貢献度はG7全体を上回ることが示されている。具体的には、2024年から2029年末まで世界経済の成長における中国の貢献度は約21%、G7は同20%となっている。世界経済の成長の75%は20か国に集中し、その半分以上は上位4か国が占める見込みであり、その4か国とは、中国、インド、米国、インドネシアとなっている。
また、今後の世界経済は、当面の間、新型コロナウイルス感染症拡大前(2015年から2019年)の平均の成長率を下回る成長が継続することが予測されている。IMFによると、2023年に予測を上回る底堅い成長が見られ、2024年4月の見通しにおける数年先までの経済成長率の予測値は、世界全体及び新興国・発展途上国では、2023年4月の見通しから上方修正が行われている一方で、2021年4月や2022年4月の時点の見通しと比較すると低い値であり、また、先進国では、2021年4月や2022年4月の時点の見通しを上回る値となっているものの、世界全体、先進国、新興国・発展途上国のいずれにおいても、2024年4月の見通しにおける長期の経済成長率の予測値は、依然として2015年から2019年の平均の成長率を下回る値となっている。IMFによると、こうした当面の間における成長減速の背景としては、各国の金融引締めや財政支援政策の縮小、生産性の低成長の影響があるという。(第I-1-1-3図)
第Ⅰ-1-1-3図 長期的な実質GDP 成長率の見通しとその推移
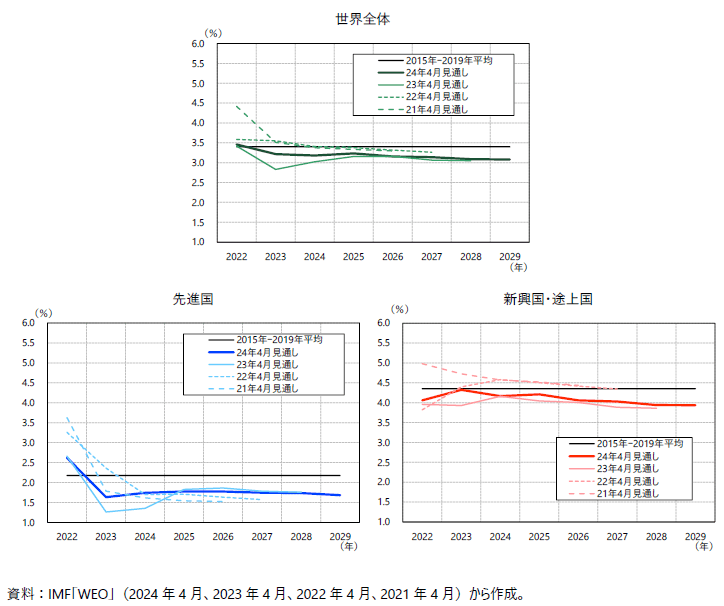
このように、2023年の世界経済は、インフレの鈍化により当初の予測と比較すると底堅い成長が見られたものの、その成長率には国・地域間で差が見られたことを確認するとともに、当面の間は、世界経済は新型コロナウイルス感染症の感染拡大前と比較して低い成長率が継続する見通しとなっていることを見てきた。
1 IMF「WEO」(2024年4月)
2.インフレと金融政策の動向
近年の世界のインフレ動向を振り返ると、新型コロナウイルス感染症拡大からいち早く経済社会活動を再開した欧米諸国で需要が回復した一方、サプライチェーンの混乱や人手不足による供給制約が生じたことにより、2021年から世界的にインフレ基調の動きが見られ始めていたが、ロシアによるウクライナ侵略を背景に更に供給リスクが高まり、2022年以降は世界的なインフレの高進が生じた。
IMFによる分析においても、2022年4月時点と2023年4月時点における見通しでは、段階的にインフレ予測を引き上げていることが見てとれる。しかし、最新の2024年4月時点における見通しでは、先進国については足下のインフレの落ち着きを映じて上方修正を止めており、一部の新興国・発展途上国においてインフレが根強く継続している影響で世界全体のインフレ率では2024年と2025年について上方修正を行っているものの、あくまでも予断は許されないが世界的なインフレは落ち着きが見通される状況となってきている。新興国・発展途上国の地域別の見通しでは、新興国・発展途上国(欧州)についてほかの地域に比べて一段高いインフレ率が見込まれており、ロシアによる天然ガスの供給制限を起因としたエネルギー価格高騰の影響がうかがえる。また、中東・中央アジアについても高いインフレ率が見込まれているが、こちらはロシアによるウクライナ侵略を起因とした食料需給の逼迫の影響がうかがえる(第I-1-1-4図)。インフレ抑制のために概して2022年から引上げの続いていた主要国の政策金利に関しても、足下のインフレの落ち着きを受けて金利据置きの動きが見られている(第I-1-1-5図)。
第Ⅰ-1-1-4図 インフレ率の見通し
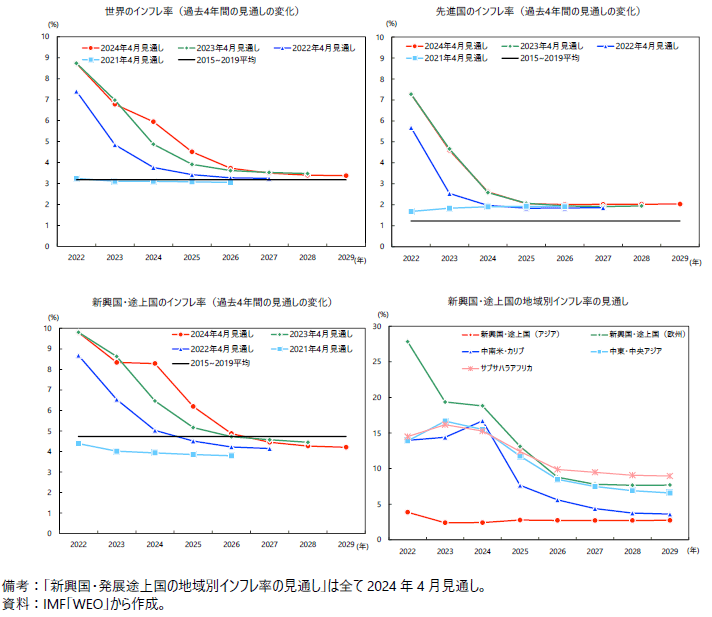
第Ⅰ-1-1-5図 G20 各国・地域の政策金利の推移
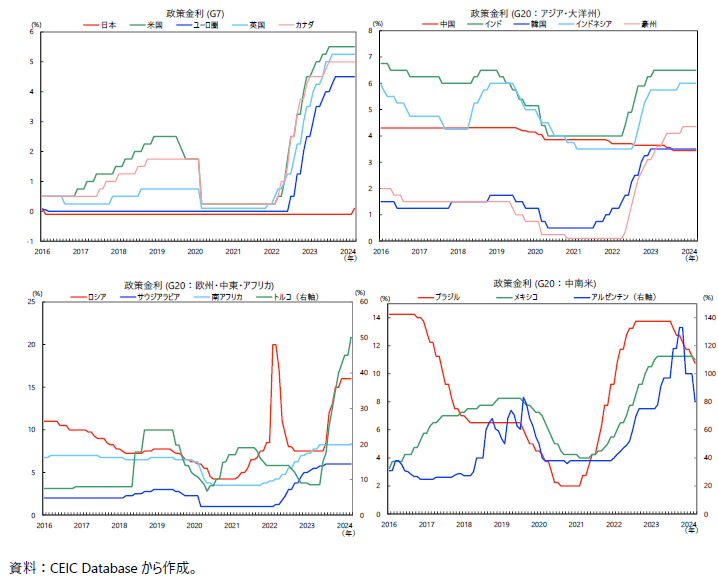
3.新興国・発展途上国の債務の動向
直近の2022年、2023年の2年間は、新型コロナウイルス感染症拡大後の供給回復の遅れやロシアによるウクライナ侵略から生じた供給リスクの高まりにより、世界的にインフレが高進した。足下ではこうしたインフレは落ち着きを見せ始めており、あくまでも予断は許されないものの出口の兆しがうかがえる。一方で、新型コロナウイルス感染症拡大を抑え込むための医療支援や、インフレへの手当ても含めた特に低所得者向けの生活支援などのために追加の財政出動が生じており、各国政府の財政負担は増加した。特に新興国・発展途上国においては、外貨獲得のよすがとなっている先進国市場を中心とした外需が弱い中で、外貨建て対外債務を増やして対応せざるを得ず、債務リスクが上昇している可能性がある。こうした可能性を踏まえて、ここでは幾つかの指標を取り上げて新興国・発展途上国の対外債務の状況を見ていく。
まず、対外債務について外貨建てが大宗を占める新興国・発展途上国において返済が困難となった場合の返済原資とし、また、自国通貨価値の急落時に為替市場へ介入するために用いられる外貨準備高の変動状況について見ていく。実績値を確認できる中で最新の2023年では、対前年比でアジアとサブサハラアフリカにおいて小幅な減少が見られたものの、過去の急落時に比べれば減少幅は小さく、また、2024年以降も大きな減少は見込まれていない(第I-1-1-6図)。
第Ⅰ-1-1-6図 新興・発展途上地域の外貨準備高の変動状況
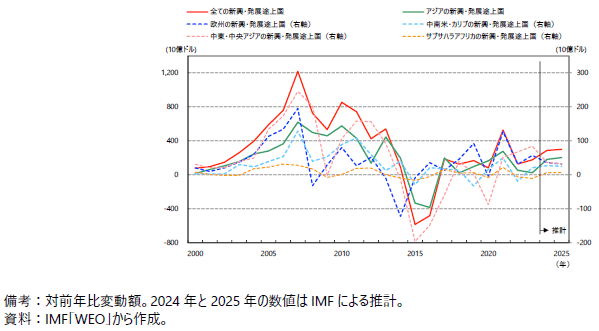
次に、対外債務残高の規模の推移について見ていく。絶対額については、2023年は対前年比で全ての地域において小幅に増加しているが、いずれも安定的に推移しており、また、2024年以降も大きな増加は見込まれていない。絶対額でなく名目GDPに対する割合で見ると、2023年は対前年比でサブサハラアフリカにおいて大きな上昇が認められるものの、全体としては安定的に推移しているといえる(第I-1-1-7図)。同様に対外債務返済額の規模の推移について見ていくと、こちらも返済額そのものは増加も見られるが、名目GDPに対する割合ではサブサハラアフリカを除いて2023年の実績値、2024年以降の推計値共に安定していることが見てとれる。また、サブサハラアフリカについても、2024年以降は従来の水準に戻ることが見通されている(第I-1-1-8図)。令和5年版通商白書において、新興国・発展途上国の対外債務の状況は、インフレの高進への対応・自国通貨価値の安定と経済成長の両立を図る難しいかじ取りが求められる中でも安定した推移を見せていることを確認したが、引き続きその状況が続いていることがうかがえる。
第Ⅰ-1-1-7図 新興・発展途上地域の対外債務残高の規模
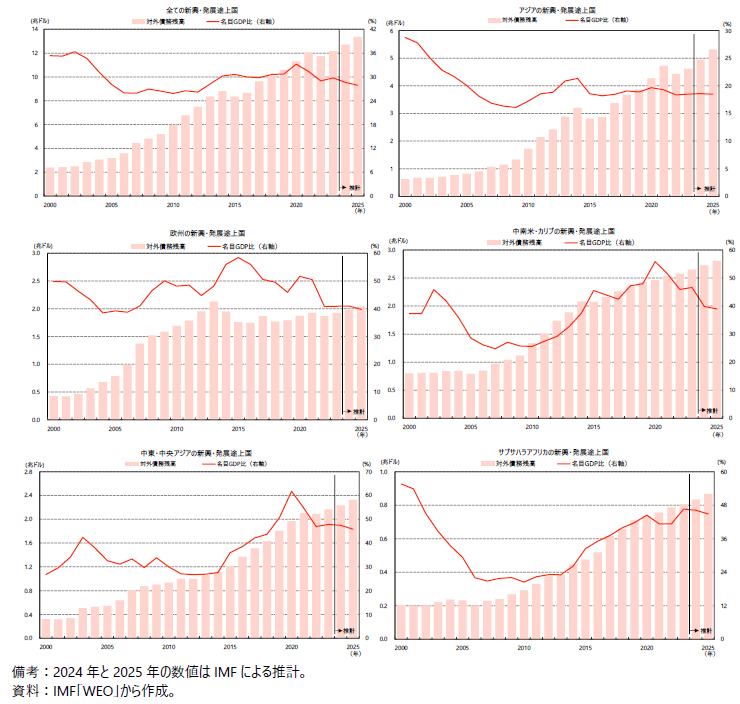
第Ⅰ-1-1-8図 新興・発展途上地域の対外債務返済額の規模
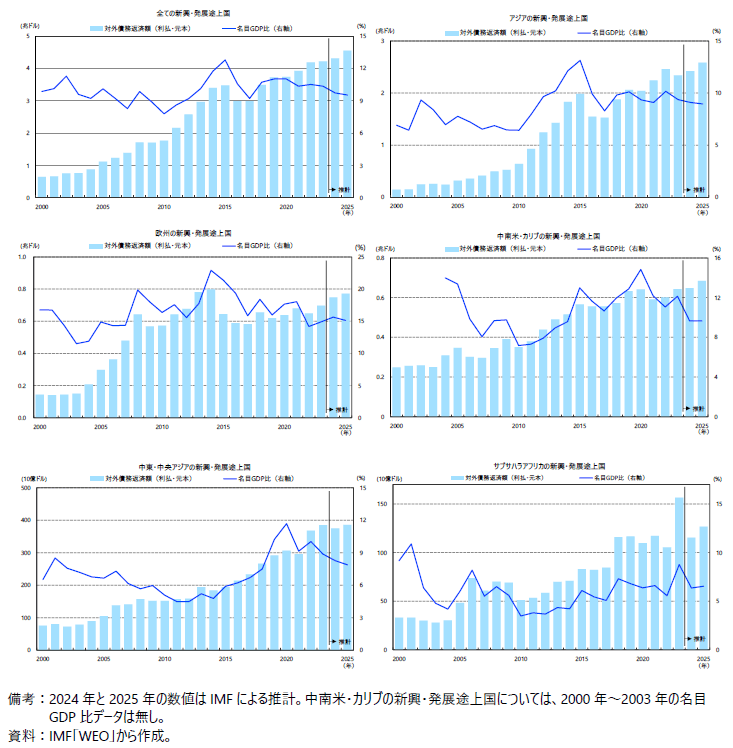
以上、地域別の状況を見てきたが、国別の状況を見ると、一部にはリスクが高まっている国々が存在することにも注意が必要である。国別の対外債務の状況については、世界銀行が中・低所得国に関して「国際債務統計」を作成しモニタリングを行っている。第I-1-1-9図は、その統計から作成したものであり、対外債務の返済可能性を示す指標の一つである、対外債務返済額の輸出・第一次所得に占める割合の大きい順に各国を並べたものである。なお、全ての中・低所得国を並べるのではなく、世界銀行のグループ機関として貧しい国々への融資を行っているIDA(国際開発協会)が融資適格を与えた75か国の平均(15.5%)を上回っている38か国を並べている。これら38か国のうち、〇印を付けた18か国はまさにIDAの融資適格を受けている貧しい国々であるが、残る20か国は貧困度合にかかわらず純粋に対外債務の返済負担が高まっている国々であるといえる。アルゼンチンやエジプトなどIMFの支援が拡大されているところも散見され、こうした国々の債務リスク状況については注意が必要である。
第Ⅰ-1-1-9図 対外債務返済額の輸出・第一次所得比率