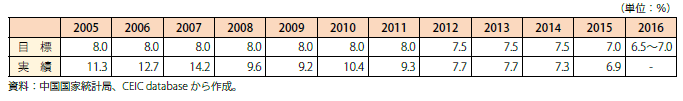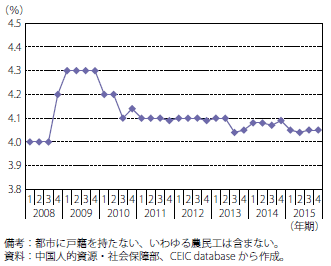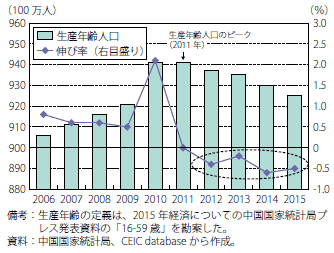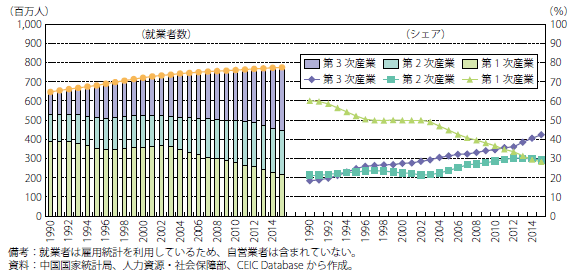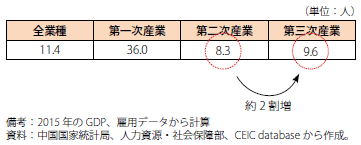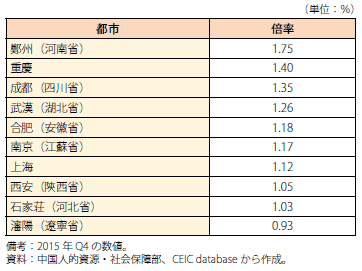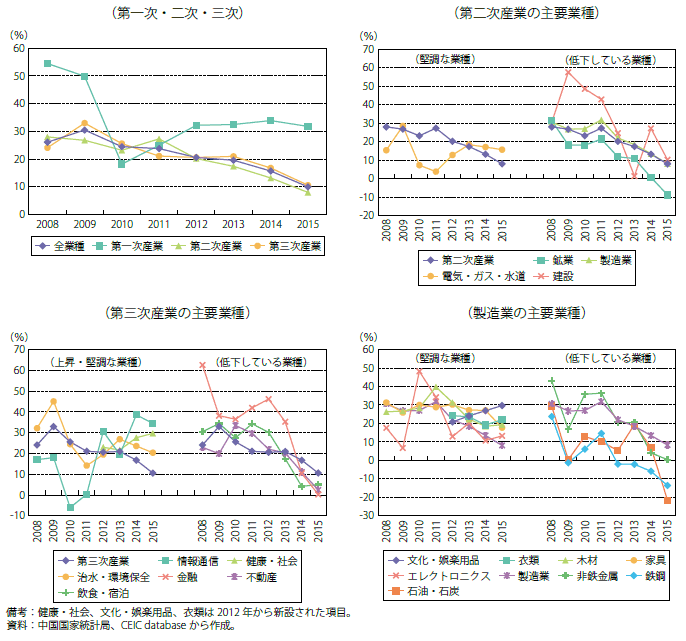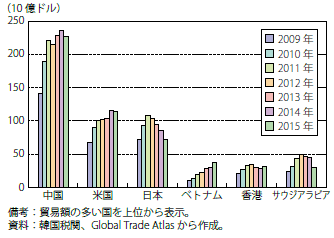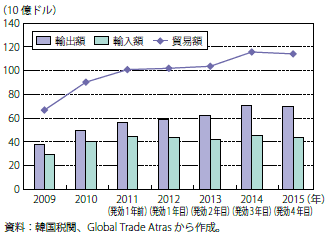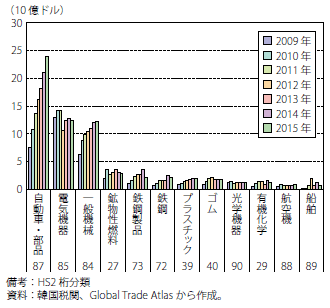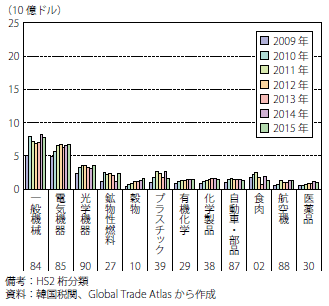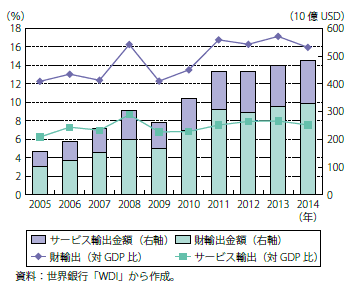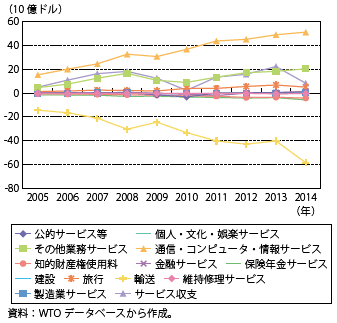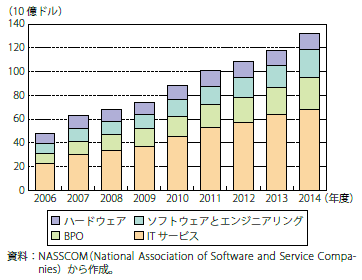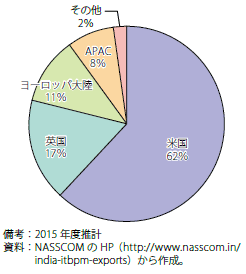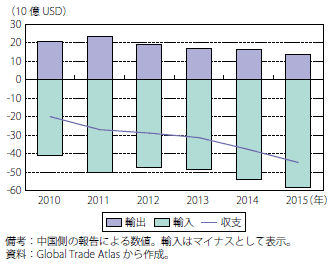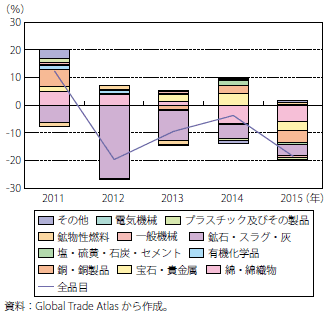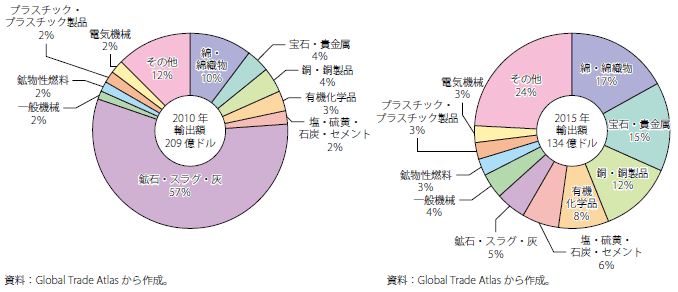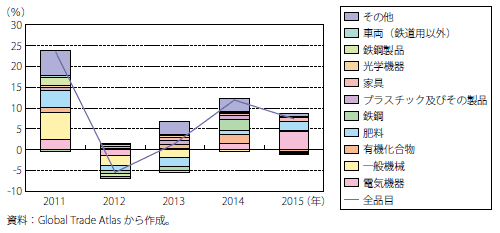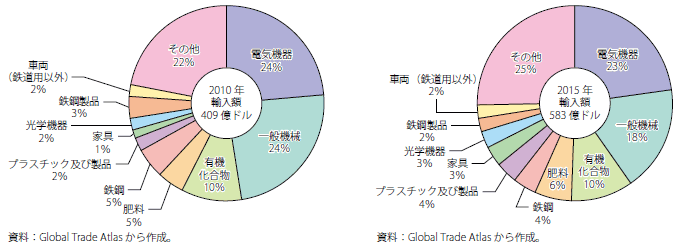第2節 過剰生産能力・過剰債務・資源価格下落と世界経済
1.過剰生産能力と保護主義の兆し
(1)中国経済の減速と過剰生産能力
①中国の経済の基本的構造(新常態への移行)
前節で述べてきたように中国は高い成長を続けてきたが、その成長を支えてきた諸条件は変化している。具体的には、生産年齢人口がピークアウトし、都市部での人手不足から人件費が上昇して、人民元レートの上昇と相まって製造業の輸出競争力に変化が生じている。2008年の世界経済危機後、4兆元の景気対策を始めとする様々な景気対策を講じつつ、一時的に成長を維持しているものの、全体として中国経済は緩やかな減速を続けている。
最近の中国経済の基本的な構造を概観してみよう(第Ⅰ-1-2-1-1図)。中国は、2000年代、インフラや生産設備などの投資活動を積極的に行うとともに、外資企業誘致による輸出拡大を原動力に高い経済成長を遂げた(第Ⅰ-1-2-1-2図)。この結果、国民総生産において、総資本形成及び純輸出(特に輸出)がシェアを拡大するとともに、民間消費のシェアは低下をたどり、外需・投資主導の経済成長の色彩を強めた(第Ⅰ-1-2-1-3図)。2008年に世界経済危機が起こると、米国向けを中心とする外需が急激に縮小したため、純輸出は大幅なマイナスとなり経済への下押し圧力を強めた。これに対して、中国政府は4兆元の景気対策を実施して、総資本形成を大幅に積みますことで成長率の減速を抑えた。しかし、その過程で、国有企業や地方政府は急速に債務を拡大させるとともに、生産能力が大幅に拡大した。その際に拡大した通貨供給量は、金利規制や資本移動規制の影響もあって、国内の限られた投資先を求めて不動産市場や株式市場に流入した。
第Ⅰ-1-2-1-1図 中国の経済の基本的構造
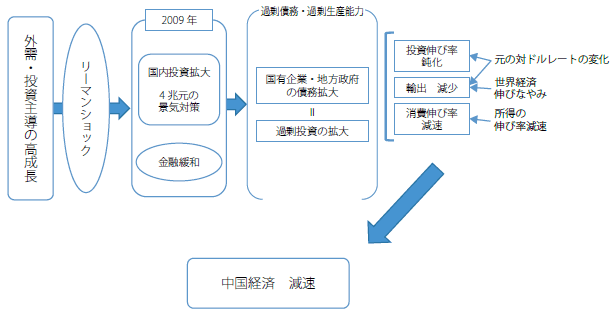
第Ⅰ-1-2-1-2図 中国の実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移
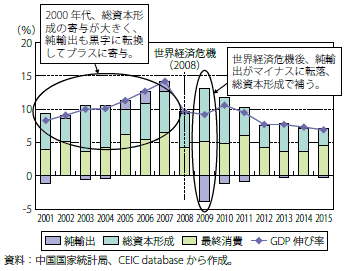
第Ⅰ-1-2-1-3図 中国のGDP構成比の推移
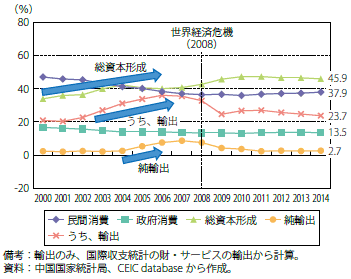
現在の中国は、投資が減速する一方で、所得の伸び率の減速、倹約令の影響、貯蓄率の高止まり等から、消費は比較的緩やかな伸びに留まっている。また、輸出については、世界経済の伸び悩み、人民元レートの上昇、人件費の上昇等から、過去のような大幅な増加基調ではなくなってきており、いわゆる「新常態」に移行しつつある。
こういった中で、人口動態や経済の効率化に影響する規制等に係る構造的な課題も指摘されている。ここからは、今後の中国の成長を考えるための構造的な課題の現状をより詳しく見ていく。
②過剰生産能力の拡大
4兆元の景気対策に当たって、高い経済成長率を前提とした投資も行われたと見られ、幅広い業種にわたって過剰生産能力が課題となっている。具体的な業種としては鉄鋼等が挙げられ、生産能力は拡大する一方で、稼働率は低下しており60~70%台を推移している(第Ⅰ-1-2-1-4図)。その他にも、2013年に中国国務院が、鉄鋼、セメント、アルミ、ガラス、船舶の5業種を過剰投資業種として特に指摘し稼働率を公表しているが、いずれも70%台となっている(第Ⅰ-1-2-1-5表)。中国企業家向けのアンケートによれば、2012年以降、平均稼働率は70%台と低迷しており、足下において更に低下していると見られる(第Ⅰ-1-2-1-6表)。
第Ⅰ-1-2-1-4図 中国における代表的業種の生産能力と稼働率の推移
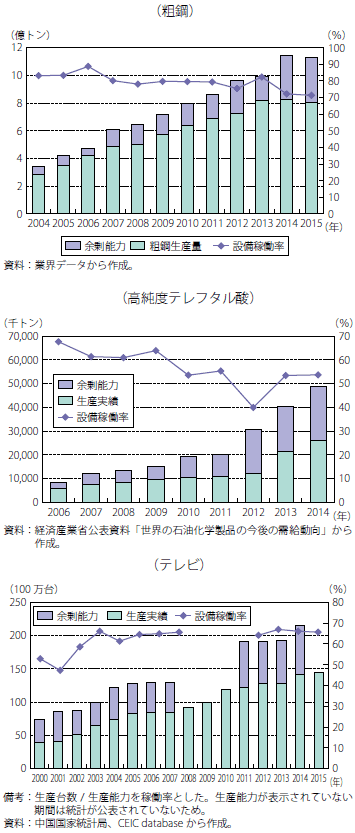
第Ⅰ-1-2-1-5表 中国の過剰生産能力業種と稼働率~国務院「深刻な生産能力過剰解消に関する指導意見」(2013.10)から
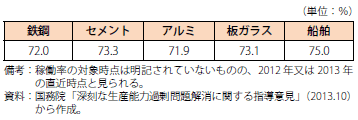
第Ⅰ-1-2-1-6表 中国の平均稼働率
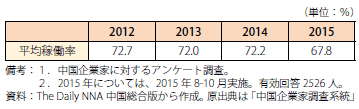
中国政府は、古く生産効率の悪い設備の廃棄を指導するとともに、過剰業種を中心に新規投資の抑制を続けており、固定資産投資の伸び率は低下をたどっている(第Ⅰ-1-2-1-7図)。しかし、設備の廃棄は現地の経済や雇用への影響も大きく、必ずしも迅速に進まない面もあった。このため、過剰生産能力状態が継続し、生産者物価(出荷価格)はほぼ4年にわたって前年比マイナスが続いているが、足下ではやや価格回復の動きも見られる(第Ⅰ-1-2-1-8図)。品目の広がりについても、鉄鋼、石炭を中心に、化学原料、窯業土石から自動車まで幅広い品目に価格低下が広がっている(第Ⅰ-1-2-1-9図)。
第Ⅰ-1-2-1-7図 固定資産投資の伸び率(年初来累計・前年同期比)
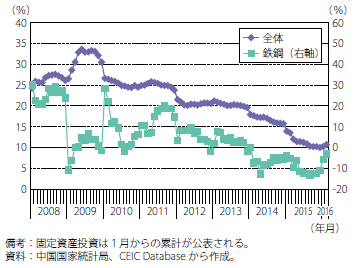
第Ⅰ-1-2-1-8図 生産者物価の伸び率(前年同月比)
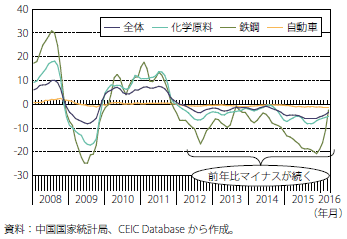
第Ⅰ-1-2-1-9図 中国の主要品目の生産者物価(2016年1~4月 対前年同期比)
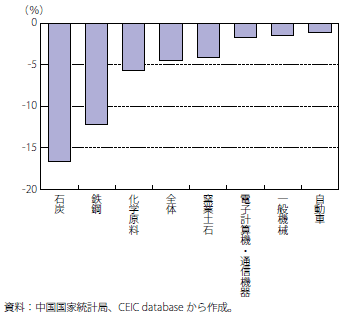
このような中で、後述するように消費は投資を補うほどの力強さに欠け、結果として過剰生産能力業種の多い東北地方を中心に経済は減速している(第Ⅰ-1-2-1-10図)。
第Ⅰ-1-2-1-10図 各地域の実質GDP成長率(2015年)
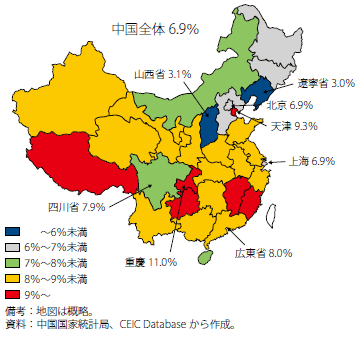
また、中国国内の生産者物価の下落が輸出価格にも影響を及ぼしているとの指摘もある。例えば、中国の鉄鋼輸出の動向を見ると、2014年から数量ベースで急速に拡大しており、一方で輸出単価は低下の一途をたどっていることが確認できる(第Ⅰ-1-2-1-11図)28。
第Ⅰ-1-2-1-11図 中国の鉄鋼(HS72)輸出の推移
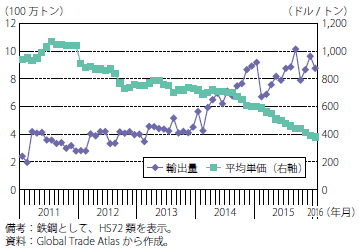
28 ここでは1つの目安としてHSコード72類「鉄鋼」の平均単価を表示した。実際には、鉄鋼の中にも様々な品目があるため、必ずしも個々の品目ごとの動きと一致しない場合もある。また、HSコード73類「鉄鋼製品」は、レール、パイプ、橋げた、窓枠、タンク、ケーブル、ボルト、ナットなど多彩な品目が含まれるため、ここでは平均単価の計算は72類だけで行った。
これまで中国は名目GDP成長率が実質GDP成長率を上回ってきた。しかし、2011年末から2012年にかけて、その差は急速に縮小し、2015年第1四半期には、名目成長率が実質を上回る逆転現象が起こった(第Ⅰ-1-2-1-12図)。これを業種別に見ると、名目・実質成長率の差の縮小は各業種ともほぼ共通に見られるものの、第二次産業においては既に2012年に逆転現象が起こり、むしろその傾向はますます顕著になっている(第Ⅰ-1-2-1-13図)。名目と実質の成長率逆転は、第二次産業においてデフレが進み、物価上昇率がマイナスに転じたことを意味している。その背景として、既に見たように製造業における過剰生産能力のため、生産者物価が鉄鋼等を中心に2011年末から前年比マイナスで推移していることが指摘できる(前出の第Ⅰ-1-2-1-8図)。その結果、名目で見た2015年の第二次産業成長率は0.9%まで低下しており、その中でも鉱業、製造業を含む工業29は0.4%とほぼゼロ成長に近い水準まで低下している(第Ⅰ-1-2-1-14表)。第二次産業に代わって成長率を牽引しているのが第三次産業で、2015年名目成長率で11.7%、実質成長率でも8.8%と相対的に高い伸び率を維持している30。
第Ⅰ-1-2-1-12図 中国の実質GDP成長率と名目成長率の推移
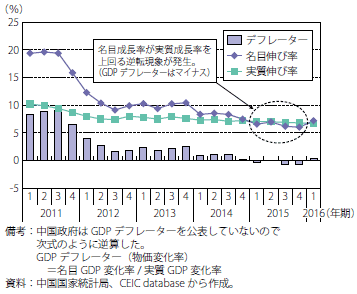
第Ⅰ-1-2-1-13図 中国の業種別GDP成長率の推移
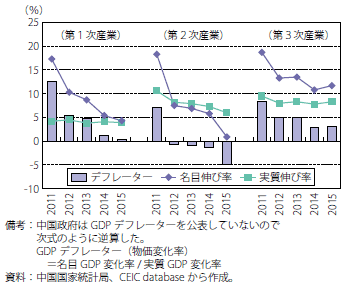
第Ⅰ-1-2-1-14表 中国の業種別GDP成長率詳細
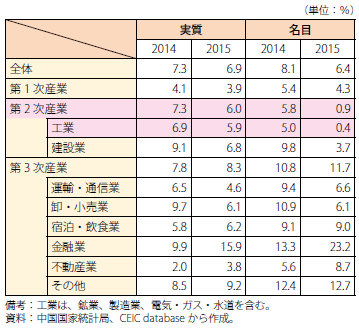
29工業は、鉱業、製造業、電気・ガス・水道を含む。
30ただし、第三次産業の中で特に成長率が高いのは金融業(2015年名目成長率23.2%、実質15.9%)で、2015年半ばまでの株価高騰による手数料等の収入拡大が影響しているのではないかとの指摘もある。
③債務の拡大
世界経済危機以降、民間企業の債務も拡大の一途をたどっている。中国における部門別の債務残高の推移を見ると、景気対策の始まった2009年初頭から非金融企業部門の債務が急拡大していることが分かる(第Ⅰ-1-2-1-15図、第Ⅰ-1-2-1-16図)。このような債務の拡大は、2010年頃、景気対策の終了や景気過熱による物価上昇を抑えるための政策金利引上げとともに一旦はおさまるが、2012年に景気減速から政策金利引下げが実施された前後から再び加速し現在に至っている。
第Ⅰ-1-2-1-15図 中国の債務残高の推移(対GDP比)
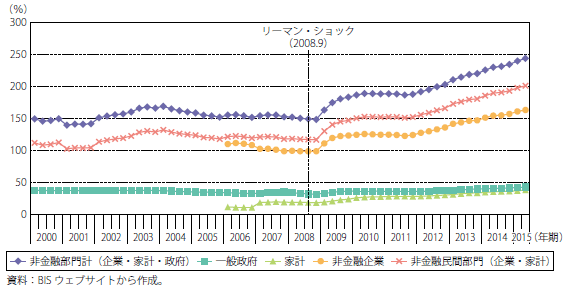
第Ⅰ-1-2-1-16図 日中の債務残高の推移(対GDP比)
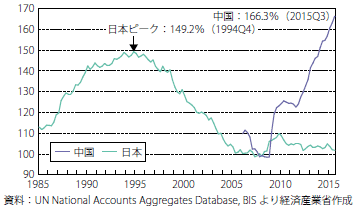
統計上、一般政府債務はあまり拡大していないが、地方政府債務は急速に拡大している。もともと地方政府は、教育、医療など住民生活に直結する公共サービスを提供しており歳入は恒常的に不足していたが、4兆元の景気対策に当たっては、地方政府も負担を迫られたため収支が急速に悪化した。しかし、中国では地方政府の借入れや債権発行が禁止されていたため、投資会社(融資平台)を通じた資金調達が増加した。中国審計署(我が国の会計検査院に相当)が、特別調査を実施して地方政府債務を調べたところ、債務額が拡大している実態が分かった(第Ⅰ-1-2-1-17表)。
第Ⅰ-1-2-1-17表 中国審計署による全国政府性債務の調査結果
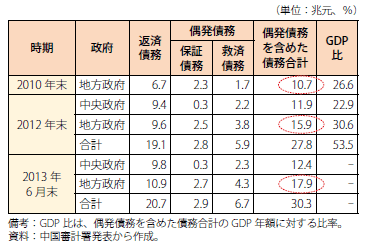
④変動が大きい不動産 / 株式 / 為替市場
中国では対外投資等の規制により、投資先として、余剰資金が国内の不動産・株式等に集まりやすく、価格の変動が大きい。例えば、2013年に上昇基調にあった住宅価格は、政府の価格抑制策等を受けて2014年初頭から価格低下に転じる都市が増え、住宅不況が景気を冷え込ませる一因ともなった(第Ⅰ-1-2-1-18図)。一方、この時に余剰資金が不動産市場から株式市場に流入したと言われ、上海総合指数は2014年中頃から翌年6月までに約2.5倍の水準まで高騰した(第Ⅰ-1-2-1-19図)。
第Ⅰ-1-2-1-18図 全国70都市の新築住宅販売価格の推移
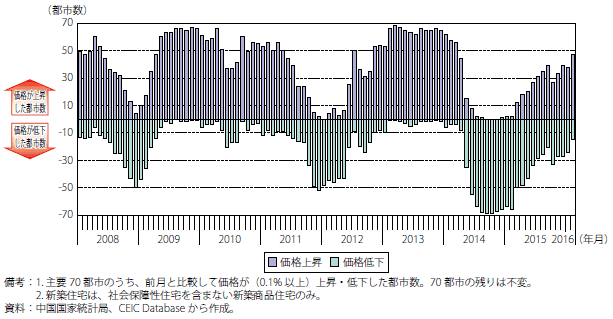
第Ⅰ-1-2-1-19図 上海総合指数の推移
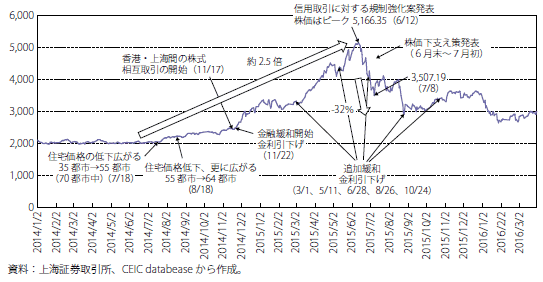
しかし、2015年6月をピークに株価は一転して急速な低下に見舞われ、7月までの1か月間で約3割下落している。この株価下落により、再び資金が株式市場から不動産市場に移動したとされ、2015年半ばからは住宅価格が上昇に向かっている。足下では、地方都市では住宅在庫が解消できず、価格が低調に推移する一方で、沿海部の大都市では高騰が続いている。
住宅や株価などの資産価格は消費に影響を与えるとともに、特に住宅市場は、鉄鋼、セメントなどの建設資材、家電、自動車等の需要を通じて景気に大きな影響を及ぼすため、このような価格の変化は景気への不安定要素となる可能性もある。
また、人民元の為替レートは、管理変動相場制へ移行後、対ドルレート、実質実効レートとも元高方向に推移したことに伴い、中国の輸出競争力に影響を与えた(第Ⅰ-1-2-1-20図、第Ⅰ-1-2-1-21図)。一方で、2015年8月に人民元の為替レート基準値の算出方法が変更され、人民元レートは元安方向へと進んだ。(第Ⅰ-1-2-1-22図、第Ⅰ-1-2-1-23図)。このような中で、中国は為替介入によって人民元レートを維持してきた。政策介入の結果、外貨準備は減少してきたが、足下ではほぼ横ばいで推移している(第Ⅰ-1-2-1-24図)。
第Ⅰ-1-2-1-20図 人民元の為替レートの推移
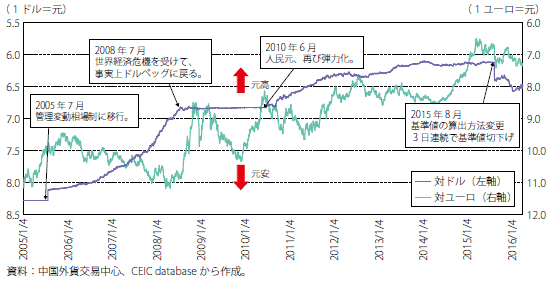
第Ⅰ-1-2-1-21図 実質実効為替レートの推移
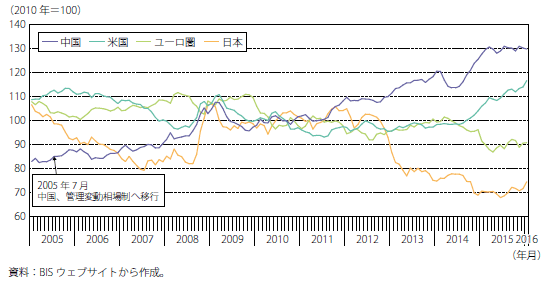
第Ⅰ-1-2-1-22図 中国の国内・国外における人民元の対ドルレート
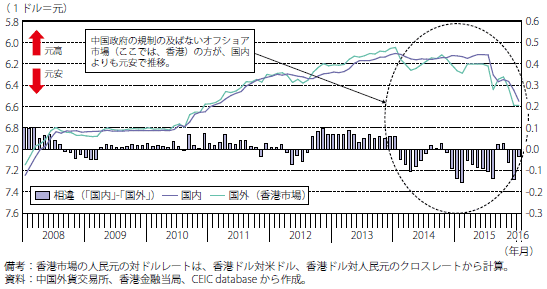
第Ⅰ-1-2-1-23図 人民元の現物価格と先物価格の推移
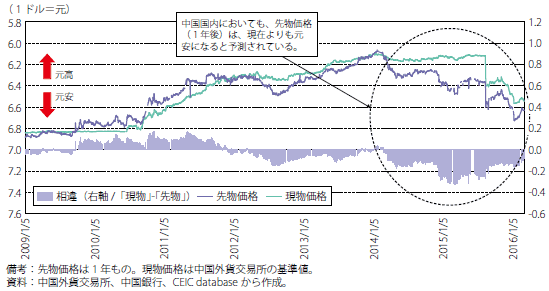
第Ⅰ-1-2-1-24図 中国の外貨準備の推移
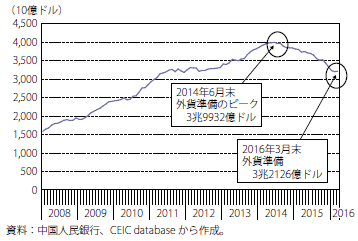
⑤人口ボーナスの喪失と賃金の上昇
すでに見たように生産年齢人口は2011年にピークアウトしており、2012年からは減少に転じている。国連の人口予測によれば、中国は生産年齢人口、その全人口に対するシェアともに低下していくことが見込まれている(第Ⅰ-1-2-1-25図)。
第Ⅰ-1-2-1-25図 中国の人口構成の将来予測(国連推計)
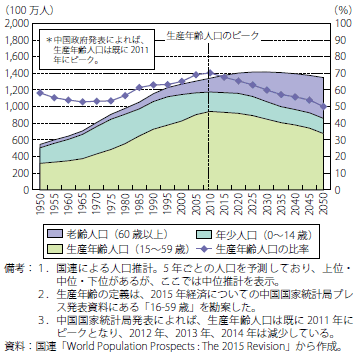
また、労働力の地域別・業種別移動という面からも変化が生じている。かつて豊富に存在した内陸部農村の余剰労働力も減少しているといわれ、都市部の有効求人倍率は1.0を上回って推移している(再掲コラム第1-2図)。その結果、外資企業を引きつけてきた「安価な人件費」は上昇しており、タイ、マレーシアを上回る水準となっている(第Ⅰ-1-2-1-26図)。
(再掲)コラム第1-2図 中国の都市部求人倍率の推移
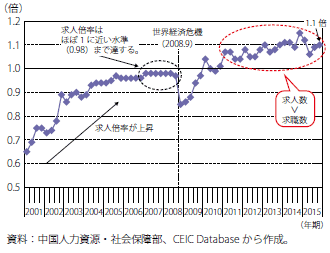
第Ⅰ-1-2-1-26図 日系企業の基本給月給(製造業 / 作業員)
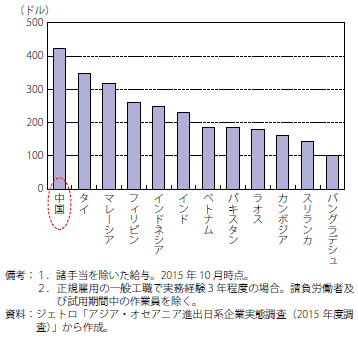
ここまで見てきたように、中国経済は、緩やかに減速する中で、過剰生産能力等の構造的な課題に直面している。一方で、足下では、大都市部の住宅価格の上昇や鉄鋼等の価格回復への兆しが窺われるなど、今後とも中国の経済動向を注視することが必要である。また、構造的な課題に対して、中国政府は、高速成長から中高速成長への移行を「新常態」として、様々な面から構造改革を進める方針を掲げている。例えば、サプライサイドの構造改革として、過剰生産能力の解消、イノベーションや研究開発による生産性の上昇、製造業の高度化、サービス業の拡大に取り組むとともに、需要面からは消費を拡大して、投資主導の経済成長からの転換を図っている。このような中国政府の取組については、本節「3. 新興国等における構造改革の取組」において詳しく見る。
(2)世界経済危機と中国経済等の減速を受けた新興国の経済動向
第1節で概観したとおり、2000年代以降、特に世界経済危機後の先進国の減速を受けて、多くの新興国が中国とのバリューチェーンを深化させ、対中依存を深めていった。その結果、中国経済をはじめとした世界経済が減速するに伴い、当該国の経済も輸出減少により減速圧力が高まった。ここでは、G20の中でも、政治なども含めて転換期にある韓国と世界第4位の人口を持つインドネシアを取り上げ、その影響を見ることとする。
①韓国
(a)韓国経済の動向
韓国の実質GDP成長率は、2011年以降、年率2~3%台と世界経済危機前の実績を下回り推移している。2012年を底に緩やかな回復傾向にあったが、2014年4月に発生した旅客船セウォル号沈没事故により、消費マインドが低下し民間消費の低迷が長引いたことに加え、年後半からは輸出の伸びが失速を始めたことが影響し、2014年の成長率は年率3.3%増となった。
2015年は、5月からの中東呼吸器症候群(MERS)感染拡大により、旅行や外食、レジャー等のサービス消費が落ち込み、外国人観光客数が減少した。年後半になりMERSの収束や政府の消費活性化対策が奏功し、民間消費が回復、住宅建設投資の活発化や補正予算による公共投資の拡大により内需は持ち直しを見せた31。しかし、中国経済減速の影響等による輸出の低迷から、純輸出はマイナス寄与となり、2015年の成長率は政府が当初に目標としていた前年比3%を下回る2.6%増となった。(第Ⅰ-1-2-1-27図)
第Ⅰ-1-2-1-27図 韓国の実質GDP成長率と寄与度の推移(需要項目別)
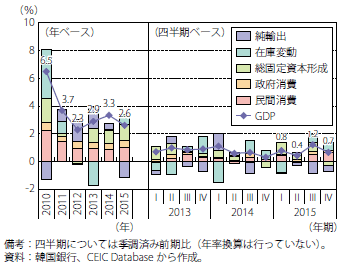
韓国政府は2016年に入り、自動車の個別消費税の引き下げ期間の延長や外国人向け大規模セールの実施等により、引き続き内需の底上げを図る方針を示したが、朝鮮半島の地政学リスクの高まりや世界金融市場の不安定化等に直面している。
韓国政府、韓国銀行及びIMFは、2016年の韓国のGDP成長率について、それぞれ3.1%、2.8%、2.7%と予測している(第Ⅰ-1-2-1-28表)。また、韓国銀行は、2015~2018年の潜在成長率を年間平均3.0~3.2%と推定している32(第Ⅰ-1-2-1-29表)。
第Ⅰ-1-2-1-28表 韓国の実質GDP成長率の見通し(2016年)
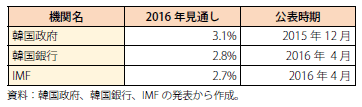
第Ⅰ-1-2-1-29表 韓国の潜在成長率
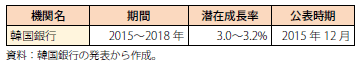
31 2015年7月、韓国政府はMERS被害の克服と国民生活の安定に向け、約12兆ウォン(約1兆3000億円)の補正予算を含む総額22兆ウォンの景気対策発表。翌8月には消費活性化策として、乗用車と大型家電製品に対する個別消費税の引き下げを実施した(15年末までの時限措置)。さらに大規模セール(韓国版ビッグフライデー)を10月1日から2週間実施したほか、韓国銀行は2015年6月、政策金利を過去最低水準の1.50%に引き下げた。
32 韓国銀行は、韓国の潜在成長率について従来3%台半ばとの見方を示していたが、2015年12月、報告書「韓国経済の成長潜在力推定結果」の中で下方修正を行った。低下の要因として、高齢化の進行で社会構造が変化していること、企業の投資不振やサービス業の生産性の停滞等を挙げている。
(b)韓国貿易の動向
国内市場規模が小さく製造業と輸出主導による成長を指向する韓国は、輸出依存度が2014年で40.6%と他の先進国と比べて高い水準となっており(第Ⅰ-1-2-1-30図)、世界経済や他国の景気動向の影響等を受けやすい。
第Ⅰ-1-2-1-30図 各国の輸出依存度の比較(2014年)
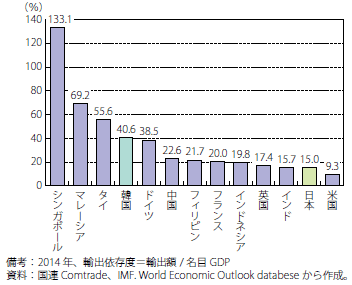
韓国の2015年の貿易について見てみると、中国向け輸出の低迷や原油価格下落の影響により、輸出、輸入ともに減少したが、輸入が輸出以上に減少していることから、貿易収支は過去最高の黒字額を記録した(第Ⅰ-1-2-1-31図)。
第Ⅰ-1-2-1-31図 韓国の貿易収支の推移(対世界)
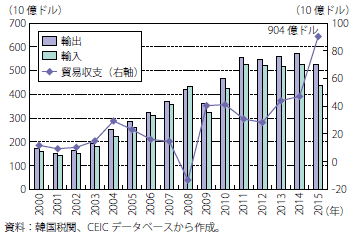
韓国の主な輸出先別に輸出額を見ると、2015年は多くの国や地域において前年比で減少がみられた一方で、ベトナムについては、前年比24.3%増加した。これはベトナムに生産拠点を置く韓国企業向けに携帯電話の生産に関連する部材等の輸出が大きく増加したためとみられている。(第Ⅰ-1-2-1-32表)(第Ⅰ-1-2-1-33図)。 次に主要輸出品目を見てみると、2015年は、集積回路、無線通信機器(携帯電話)等で前年比で増加した以外は、多くの品目で落ち込みがみられた。特に、原油価格の下落を受けて石油製品が急減したほか、自動車と自動車部品については、ロシア、ブラジル等の新興市場における需要低下の影響等から減少したとみられる33(第Ⅰ-1-2-1-34表)(第Ⅰ-1-2-1-35図)。
第Ⅰ-1-2-1-32表 韓国の輸出・輸入額(国・地域別)
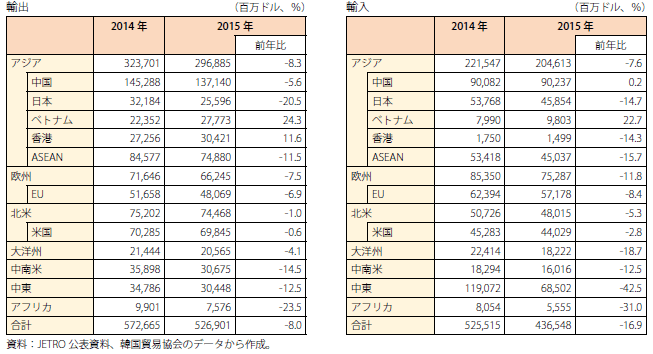
第Ⅰ-1-2-1-33図 韓国の輸出額の伸び率の推移(主要国別)
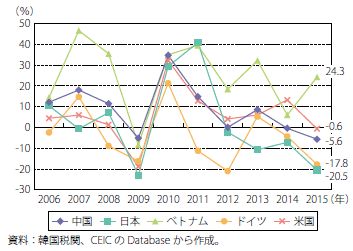
第Ⅰ-1-2-1-34表 韓国の主要品目の輸出額の推移(対世界)
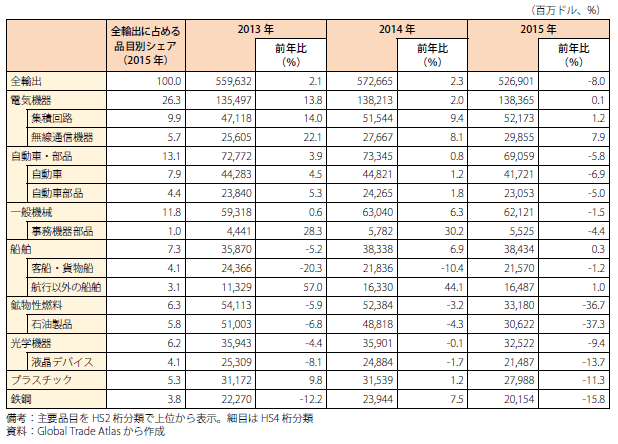
第Ⅰ-1-2-1-35図 韓国の主要品目の輸出額伸び率の推移(対世界)
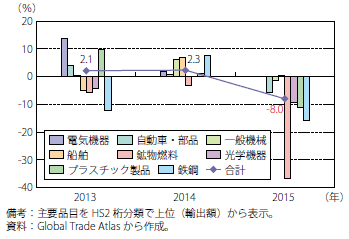
かつて韓国の輸出先は米国、欧州、日本の割合が圧倒的に高く、特に対米輸出はピーク時の1986年には40%まで達していた。しかし、対米国、対欧州、対日本ともに輸出比率は次第に低下し、それに代わり対中国の比率が徐々に高まっていった。特に2002年から2004年にかけて対中輸出は前年比30%を超えて急激に拡大し、2003年には中国が米国を抜き、韓国最大の輸出相手国となり、2015年にはその輸出比率は26.0%と、米国、欧州、日本向けの輸出を合わせた比率にほぼ匹敵する規模となっている。その一方で対日本の比率は4.9%と過去最低水準まで低下している(第Ⅰ-1-2-1-36図)。また、韓国の対中輸入も拡大し、2007年には中国が日本を抜き、輸出入ともに韓国の最大の相手国となった(第Ⅰ-1-2-1-37図)。韓国は、部品や加工品といった中間財の中国向けの輸出割合が高いことから、中国の内需の伸び悩みによる直接的な影響だけでなく、世界経済減速の影響による中国の輸出の減少を通じた間接的な影響も受けやすい構造にあるといえる。
第Ⅰ-1-2-1-36図 韓国の主要輸出先構成比の推移(輸出額ベース)
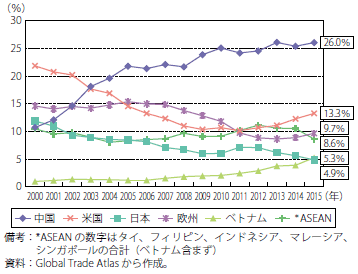
第Ⅰ-1-2-1-37図 韓国の主要輸入先構成比の推移(輸入額ベース)
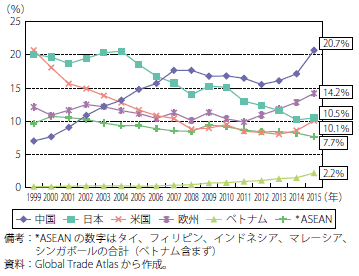
韓国の対中国の貿易の推移を見てみると、貿易収支は黒字を続けており、2015年の貿易黒字額(469億ドル)は、韓国の貿易黒字の合計額(904億ドル)の5割以上を占める規模となっている(第Ⅰ-1-2-1-38表)。
第Ⅰ-1-2-1-38表 日本、韓国、中国の貿易関係(2015年)
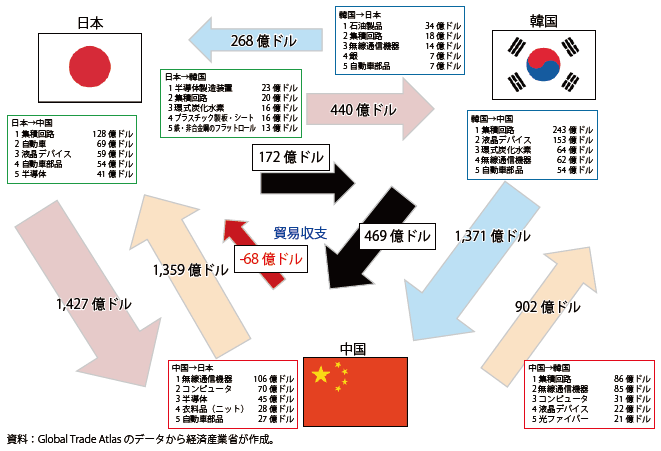
しかし、これまで順調に拡大を続けていた輸出額の伸びが、2014年、2015年と連続してマイナスとなっており、これまで好調を続けていた対中輸出に変化が見られている。(第Ⅰ-1-2-1-39図)。これは、主に中国経済の減速の影響によるものと考えられ、品目別に見ると2015年は電気機器と一般機械を除いた光学機器、有機化学、自動車・部品、プラスチック、鉄鋼といった韓国の主力分野の輸出額が軒並み減少している(第Ⅰ-1-2-1-40表)(第Ⅰ-1-2-1-41図)。
第Ⅰ-1-2-1-39図 韓国の貿易収支の推移(対中国)
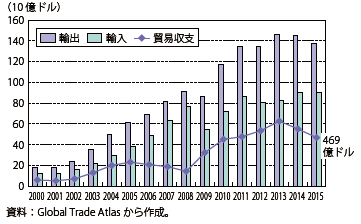
第Ⅰ-1-2-1-40表 韓国の主要品目の輸出額の推移(対中国)
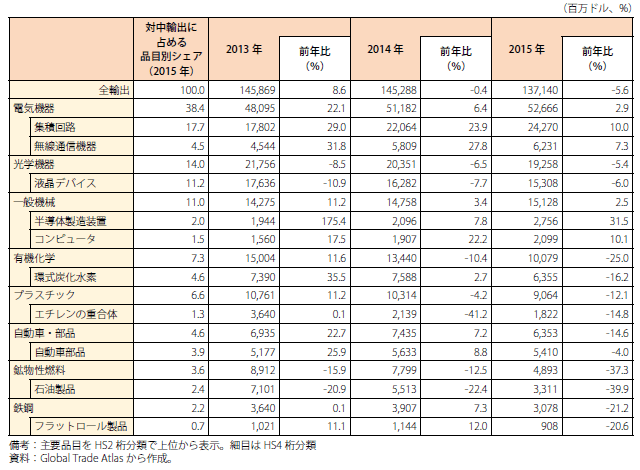
第Ⅰ-1-2-1-41図 韓国の主要品目の輸出額伸び率の推移(対中国)
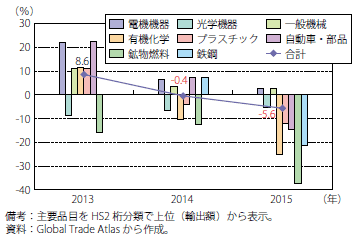
33 JETRO「通商弘報」(2016年2月1日)
(c)韓国の最近の輸出先・投資先の動き
最近韓国では、輸出先や投資先の多様化や生産拠点の分散化を図る動きが見られ、具体的には、ベトナムのプレゼンスが増大している。ベトナム向けの韓国企業からの投資が増加し、現地生産が拡大するのに伴い、韓国からの生産財や資本財の輸出が誘発され、両国の経済関係は活発化している。また韓国の大手電子企業がベトナムをスマートフォンの主力生産基地に位置付けたことにより、関連企業も相次いでベトナムに進出している。そのため、韓国のベトナム向け輸出は堅調に推移しており、2015年にベトナムは、中国、米国、香港に次ぐ韓国の第4位の輸出相手国となったほか、対外直接投資についても、中国向け投資が減少傾向にあるのに対して、ベトナム向けは安定的に推移している(第Ⅰ-1-2-1-42図) (第Ⅰ-1-2-1-43図)。
第Ⅰ-1-2-1-42図 韓国の輸出額の推移(主要国別)
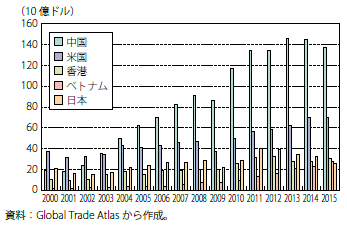
第Ⅰ-1-2-1-43図 韓国の対外直接投資額の推移(主要国別)
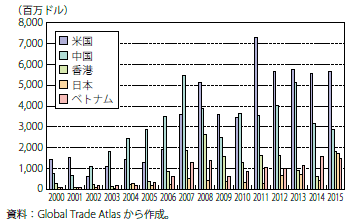
大韓貿易投資振興公社(KOTRA)34の調査によれば、「中国で操業している韓国企業の移転先候補として、ベトナムを挙げる企業が最も多い。ベトナム向け投資が増加した理由は、中国と比較して労働コストが低廉なため生産拠点として魅力があること、一定の人口規模35を有し、市場として魅力があることが指摘できる36」としている。
34 大韓貿易投資振興公社(KOTRA)は韓国知識経済部傘下の政府系機関で、貿易投資促進のために1962年に設立。韓国企業のための海外市場開拓・進出支援、海外市場・海外企業に関する情報収集・発信、外国人投資誘致、貿易・投資に関する専門人材育成、高度外国人材受入れ等を実施。現在のKOTRAの海外拠点は84カ国・122カ所。
35 2014年:約9,250万人(国連人口基金推計)
36 向山英彦「韓国にとって存在感を増すベトナム」(2016年2月)
②インドネシア
(a)世界経済危機後の成長と足下の鈍化
インドネシアは、世界経済危機後、ASEANのどの国より素早い回復をみせ、2010年から3年連続で6%台の成長を維持したことにより、当時のユドヨノ政権の安定性とあいまって、同国の成長性が世界から高く注目された41。世界経済危機後の2008年、新興国を加えて初めて開かれたG20サミットに、ASEANで唯一のメンバーになっていることからも、その期待がうかがえる。しかしながら、2010年以降の成長率は年々鈍化しており、2015年は4.8%となっている(第Ⅰ-1-2-1-44図)。
第Ⅰ-1-2-1-44図 ASEAN各国の実質GDP成長率の推移
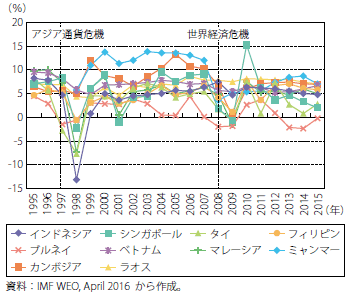
実質GDP成長率が鈍化の一途をたどる、2011年から2015年の直近5年間について、成長率に対する需要項目別寄与度の推移をみると、①常に民間消費の寄与度が高いが、年々低下していること、②2011年、2012年と民間消費と同水準だった総固定資本形成の寄与度が、2013年以降に大きく下降していること42、③輸出、輸入ともに、寄与度が年々低下傾向にあり、2015年においては、輸出も輸入もマイナスに寄与している(輸出の低下を上回る輸入の低下がみられ、純輸出はプラス)こと、が注目できる(第Ⅰ-1-2-1-45図、第Ⅰ-1-2-1-46表)。
第Ⅰ-1-2-1-45図 インドネシアの実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移
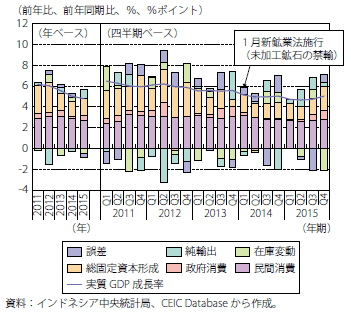
第Ⅰ-1-2-1-46表 インドネシアの実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移(第Ⅰ-1-2-1-45図の数値表)
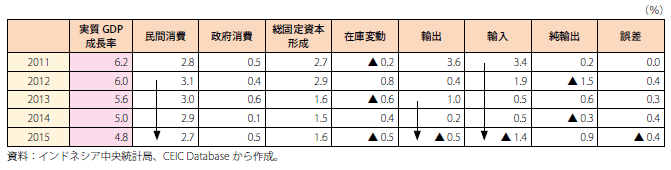
なお、名目GDPの需要項目の割合について、2011~2015年の直近5年間の平均を見ると、個人消費が56%、総固定資本形成が32%、政府消費が9%を占めており、純輸出は0%(輸出:24%、輸入:24%)であることから、主に内需と投資が成長を牽引していることが分かる。
また、同期間の成長率に対する産業別寄与度の推移をみると、①鉱業の寄与度が年々低下し、2015年はマイナスに寄与するまでになっていること、②製造業、卸売・小売・宿泊・飲食業の寄与度が低下していること、その一方で、③農林水産、建設の他、情報通信等の各種サービス業は、安定して成長に寄与していることが分かる(第Ⅰ-1-2-1-47図、第Ⅰ-1-2-1-48表)。
第Ⅰ-1-2-1-47図 インドネシアの実質GDP成長率と産業別寄与度の推移
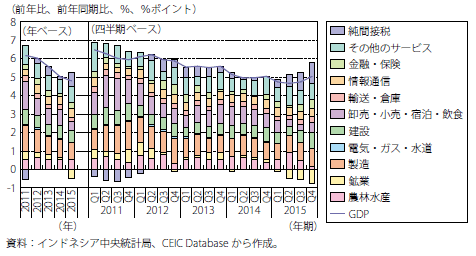
第Ⅰ-1-2-1-48表 インドネシアの実質GDP成長率と産業別寄与度の推移(第Ⅰ-1-2-1-47図の数値表)
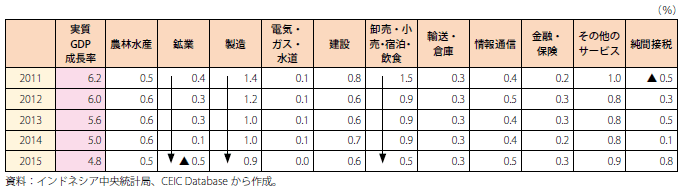
次に、対内直接投資を見ると、2009年以降増加したが、2013年以降2015年まで3か年横ばいになっている43。主な投資国・地域は、シンガポール、日本をはじめとするアジア地域の他、欧州、米州等となっている44(第Ⅰ-1-2-1-49図)。投資分野は、2010年以降2013年まで、第二次産業への投資額は上昇したが、2014年、2015年と下落している。一方で、2013年以降、第三次産業への投資額は上昇し、2015年はほぼ同じ水準となっている。第一次産業への投資額は2008年以降増加したが、他の産業に比べて金額は低い水準であり、2015年は減少している(第Ⅰ-1-2-1-50図)。
第Ⅰ-1-2-1-49図 インドネシアの対内直接投資(投資国・地域)の推移
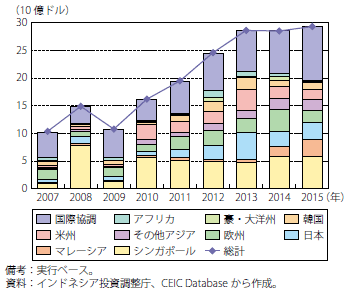
第Ⅰ-1-2-1-50図 インドネシアの対内直接投資(投資分野)の推移
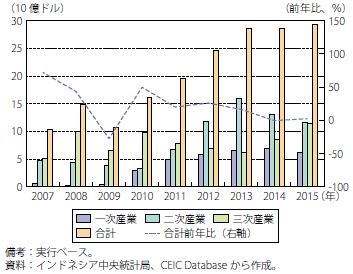
次に、貿易の推移を見る。インドネシアの貿易収支は、アジア通貨危機後、部品、原料等の投入材や資本財の輸入の減少により、黒字幅が拡大した。また、一次産品価格の高騰や資源需要の増加により輸出が拡大したことも、黒字の増加の要因になった。世界経済危機の影響で、一次的に貿易黒字の縮小があったが、その後、いわゆる資源ブームで好転している。しかしながら、2012年頃の世界的な経済後退に伴い、輸出が減少する一方、好調な内需を背景に輸入は増加し、貿易収支は悪化、2012年から2014年の3年連続で、わずかながら貿易赤字になった。直近の2015年は貿易収支が改善し、わずかにプラスになったものの、これは、輸出の減少を上回る輸入の減少がその理由である(第Ⅰ-1-2-1-51図)。
第Ⅰ-1-2-1-51図 インドネシアの貿易収支の推移
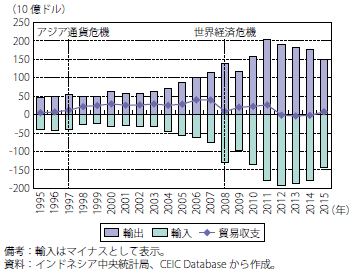
輸出(前年比)について、輸出先上位5ヵ国(寄与度)の推移をみると、2002年以降、世界経済危機時を除き、主に、日本、中国、シンガポール、米国、インドへの輸出が伸びていたが、2012年以降は一転、総じてマイナスの伸びになっており、特に2014年の中国向けの輸出がマイナスに寄与していることがわかる(第Ⅰ- 1-2-1-52図)。
第Ⅰ-1-2-1-52図 インドネシアの輸出の推移(前年比)(上位5ヵ国の寄与度)
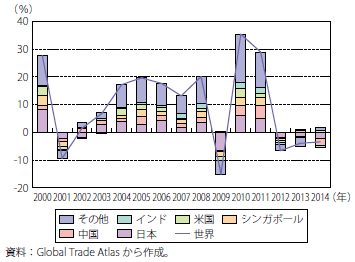
また、輸出上位5品目(寄与度)の推移をみると、2003年以降、世界経済危機時を除き、鉱物性燃料の輸出が伸びていたが、2012年以降は、マイナスに寄与していることが分かる(第Ⅰ-1-2-1-53図)。
第Ⅰ-1-2-1-53図 インドネシアの輸出の推移(前年比)(上位5品目の寄与度)
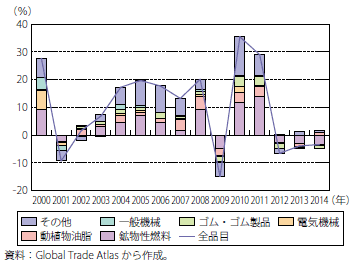
なお、輸出上位2品目である鉱物性燃料と動植物油脂が、全輸出に占める割合の推移をみると、2000年は28.1%しか占めていなかったが、2012年に44.6%まで上昇していることが注目される(第Ⅰ-1-2-1-54図)。
第Ⅰ-1-2-1-54図 インドネシアの輸出の推移(上位5品目と天然資源が占める割合)
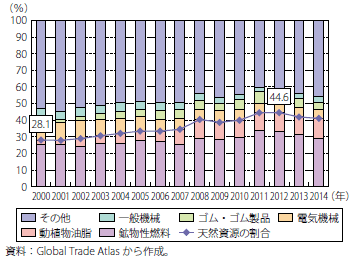
なお、2000年から2014年の15年間における同国の輸出金額と輸出先の変化をみると、全体で2.8倍、中国は6.4倍、インドは10.6倍になっている(第Ⅰ-1-2-1-55表)。
第Ⅰ-1-2-1-55表 インドネシアの輸出額の変化(2000年と2014年の比較)
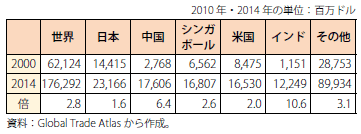
また、輸出総額に占める輸出先の割合の変化をみると、我が国は、23.2%から13.1%に低下している一方で、中国は4.5%から10%、インドは1.9%から6.9%まで上昇していることが分かる(第Ⅰ-1-2-1-56表)。
第Ⅰ-1-2-1-56表 インドネシアの輸出割合の変化(2000年と2014年の比較)
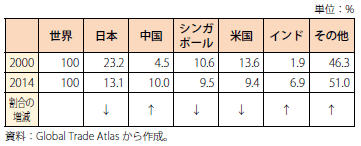
次に輸出依存度45の推移をみる。インドネシアの輸出依存度は、アジア通貨危機直後の1998年に20.5%から42.4%へ上昇した。その後はわずかなアップダウンがあるものの、総じて下降傾向にある(第Ⅰ-1-2-1-57図)。なお、他のASEAN諸国と比較すると、2014年では、インドネシアは20%と最も輸出依存度が低いことが分かる(第Ⅰ-1-2-1-58図)。
第Ⅰ-1-2-1-57図 ASEAN各国の輸出依存度の推移
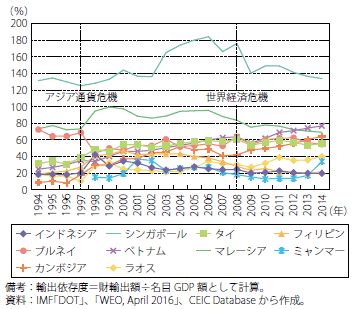
第Ⅰ-1-2-1-58図 ASEAN各国の輸出依存度
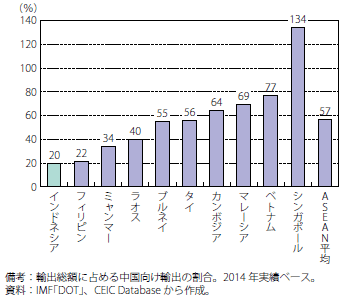
41 2009年、証券市場関係者が、「チャインドネシア」という造語を用いて、新興経済大国として台頭した中国とインドに同国を加えたこの三国の有望性を強調することや、「BRICストーリーにもう一つ“I”を加えるか」というレポートを発信することがあった。
42 2010~2012年にかけては、同国への対内直接投資ブームがあった。また、2015年下期については、新政権下のインフラ投資がうまく予算執行されなかったことが一因だと考えられる。
43 2010~2012年の同国への対内直接投資ブームを主導したのは日本であり、資源分野のみならず、機械工業(自動車・二輪車・部品)、日用消費財、サービス業と多岐にわたった。
44 主な投資国・地域の投資額が全体に占める割合(2015年実績)は、大きい順から、シンガポール(20.2%)、マレーシア(10.5%)、日本(9.8%)、欧州(7.9%)、米州(6.1%)、韓国(4.1%)、香港(3.2%)、中国(2.1%)となっており、アジア地域が全体の約51%を占めている。
45 輸出依存度は、財輸出額を名目GDP額で割ったものとする。
(b)中国経済減速の影響
足下の中国経済の減速がインドネシアに影響を与えているかを見る。まず、中国への輸出依存度について1994年から2014年までの20年間の変化をみると、同国は、中国への輸出依存度が3.0倍になり10.0%を占めるようになった(第Ⅰ-1-2-1-59図)46。なお、他のASEAN諸国と比較すると、2014年では、3番目に低い水準である(第Ⅰ-1-2-1-60図)。そもそも、同国の対世界の輸出依存度は、ASEAN諸国の中では最も低いことから、中国景気の直接的影響は相対的には少ないと思われる。とはいえ、2014年では、ASEAN10か国のうち8か国の中国への輸出依存度が10%を超えており、ASEAN諸国は中国の景気によって経済成長が左右されること47、さらに、近年のASEAN域内の貿易活発化を考えると、同国にとり、中国経済の動向が間接的に及ぼす影響も少なくないと思われる。
第Ⅰ-1-2-1-59図 ASEAN各国の輸出に占める中国向け割合の推移
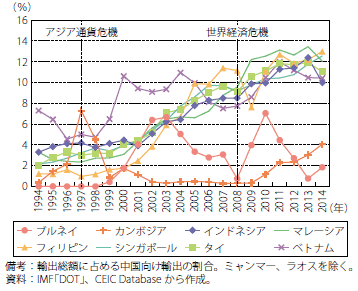
第Ⅰ-1-2-1-60図 ASEAN各国の輸出に占める中国向け割合
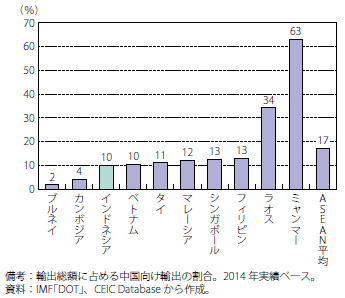
インドネシアと中国との貿易収支は、2012年から赤字拡大傾向にあるが、2015年は2014年と同じ赤字水準に留まっている。世界経済危機直後の2009年を除き、貿易総額が拡大してきたが、2013年から足下では輸出が縮小していることが分かる(第Ⅰ-1-2-1-61図)。
第Ⅰ-1-2-1-61図 インドネシアの貿易収支(対中国)の推移
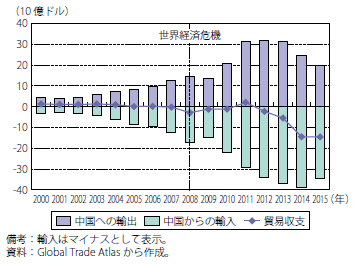
中国への輸出品目(HS4桁ベース)をみると、①世界経済危機後、中国からの需要増加により、石炭、亜炭、パームオイルの輸出が上昇したが、2012年をピークにその後は下落していること、②石炭の輸出が2011年の約64億ドルのピークから、2015年は約16億ドルと4分の1に下落していること、が注目される(第Ⅰ-1-2-1-62図、第Ⅰ-1-2-1-63表)。
第Ⅰ-1-2-1-62図 インドネシアの輸出(対中国)の推移(上位10品目)(HS4桁ベース)
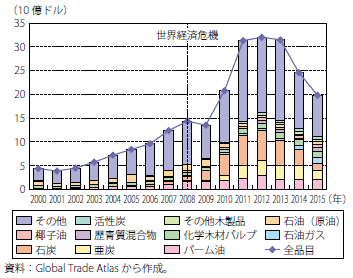
第Ⅰ-1-2-1-63表 インドネシアの輸出(対中国)の推移(上位10品目)(HS4桁ベース)(第Ⅰ-1-2-1-62図の数値表)
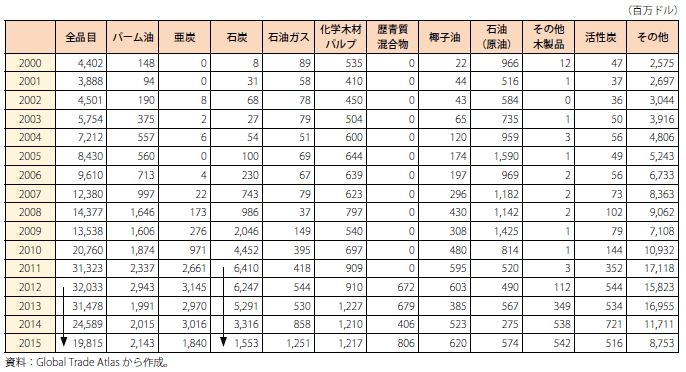
上記から、世界経済危機後の中国への一次産品の輸出拡大が、その間の同国の成長に大きく寄与したものの、足下の急な需要減少が反動として、現在の成長鈍化につながっているものと思われる48。
46 インドネシアの中国への輸出依存度は2013年がピークの12.4%であり、2014年で一転、下降していることも注目点である。
47 ここでは中国本土への輸出のみカウントをしているため、香港を加えると依存度はより高くなる。
48 佐藤(2015)によると、2004年から2011年(世界経済危機の影響を受けている2009年を除く)のインドネシアにおける2桁台の輸出金額の伸びが、一転、2012年以降に下落を見せている大きな理由は、主に、中国からの需要増加に喚起されたコモディティブームの終焉によるもの、としている。
(c)安定成長を維持するための課題
2014年末の政権交代で発足したジョコウィ政権への期待が高まる中、インドネシアの経済成長は足下で鈍化している。同国は、製造業が経済成長を主導するまでには至っておらず、石油純輸入国ではあるものの、資源輸出に依存した経済構造から完全に脱却も達成できていないため、世界経済に左右されることが多いと言える。
そのほか、同国の成長の鈍化は、世界的なリスクマネーの引上げにより、投資・消費の押し上げ効果がなくなったことや、経常収支赤字を危惧するインドネシア中央銀行が、2013年半ば以降、金融政策を引き締めたことも要因と考えられる。
ジョコウィ政権は、任期中の実質GDP成長率の目標値を、平均7%と高く掲げている。今後、高い経済成長を実現し、持続可能なものとするには多くの課題がある。その一つには、輸出構造の高度化がある。同国は天然資源が豊富であるがゆえに、石炭やパーム油といった天然資源への依存度が高く、景気がそれらの価格動向に大きく左右されてしまう。ユドヨノ政権が達成した経済成長は、製造業が主導したものではなく、新興国における需要に応じた、資源輸出に依存したものであったと考えられる(第Ⅰ-1-2-1-64図)。今後増え続ける生産年齢人口の雇用に対応するためにも、国内企業を育成し、高付加価値製品を生産・輸出できる体制をつくることが課題の一つとなっている(第Ⅰ-1-2-1-65図)。そのためには、ジョコウィ政権が目指す経済対策が実行され、ビジネス・投資環境の整備を通じた裾野産業・中小企業の振興や、地方開発、投資・輸出促進の基盤となるインフラ開発が進展するとともに、インドネシアが地域経済統合や経済連携に積極的に関与・主導してゆくことを通じ、更にネットワークを深化させていくことが重要であろう。
第Ⅰ-1-2-1-64図 インドネシアの産業構造の推移
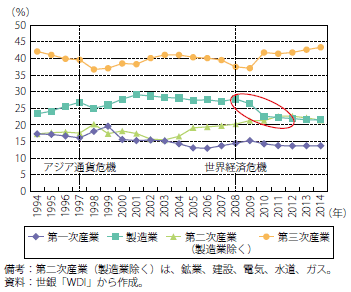
第Ⅰ-1-2-1-65図 インドネシアの人口構成の将来予測(国連推計)
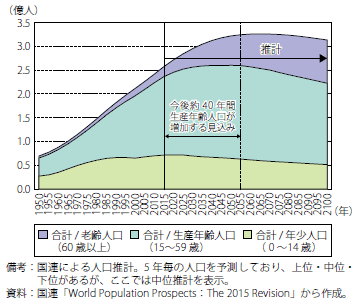
(3)過剰生産能力と世界における貿易制限的措置の増加
世界的な過剰生産能力は、生産国からの輸出量拡大と輸出価額低下により、世界経済の減速と相まって世界各地でアンチダンピング(AD)措置やセーフガード(SG)措置等の貿易救済措置を招く原因となっている。ここではその顕著な例である鉄鋼産業について、過剰生産能力の現状と各国の反応について概観する。
①鉄鋼産業の過剰生産能力の状況
世界の鉄鋼需要は、世界経済危機を受けて2009年に大幅減となったが、2010年以降、中国の景気対策などを受けて回復しつつある。しかし、需要の増加ペースを上回る急激な粗鋼生産能力の増強により、世界の鉄鋼市場では、需給ギャップが拡大し、過剰供給構造となっている。OECDの予測49によると、2015年の全世界の年間粗鋼生産能力が約23億トンであるのに対し、年間見掛消費量50は約16.5億トンに留まっており、約6.5億トンの年間過剰生産能力が発生している。この生産能力と消費量のギャップは年々拡大しており、設備稼働率(粗鋼生産量を同生産能力で除した値)は2005年の84%から、2015年には70 %まで急激に低下している。(第Ⅰ-1-2-1-66図)
第Ⅰ-1-2-1-66図 世界全体の鉄鋼市場における生産能力と生産量のギャップ
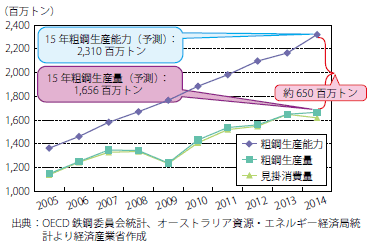
中国では2014年の生産能力が前年比3.4%増加する一方、鋼材見掛消費量が同3.8%減少となった。こうした国内事情も踏まえ、中国からの輸出量は同約1.5倍に急増する一方、鋼材輸出価格については、代表鋼種である熱延コイルの場合2016年2月には前年同月比で約20%低下している。(第Ⅰ-1-2-1-67図)
第Ⅰ-1-2-1-67図 中国からの輸出価格(全鉄鋼平均)の推移
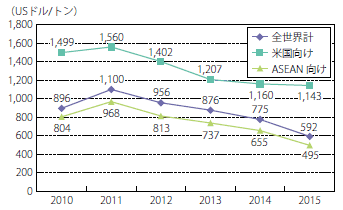
また中国のほか、韓国をはじめ、他のアジア各国でも多くの製鉄所建設・拡張が予定されている。こうした需要の伸びを上回る生産能力拡大の背景としては、需要の減速自体に加え、政府による介入やその他の市場歪曲的な慣行が挙げられる51。理論的には、過剰生産能力状態が長期化すると、生産者は生産能力の縮小に向かうはずであるが、実際にはそうならず、過剰生産能力状態が長期的に継続してしまっている。その理由としては、設備取壊しや雇用調整などの撤退コストが高いこと、市場の将来期待が過度に高いこと、失業者を産みたくない・鉄鋼の自給率を高めたいとの政府の意向52と並んで生産国における市場メカニズムが十分に機能していないことが挙げられる。現実にも、過剰生産能力状態であるにも関わらず、新たな製鉄所建設プロジェクトが進んでおり、今後も、世界の粗鋼生産能力は顕著に上昇することが推測される。(第Ⅰ-1-2-1-68表)
第Ⅰ-1-2-1-68表 アジアで相次ぐ大型製鉄所建設
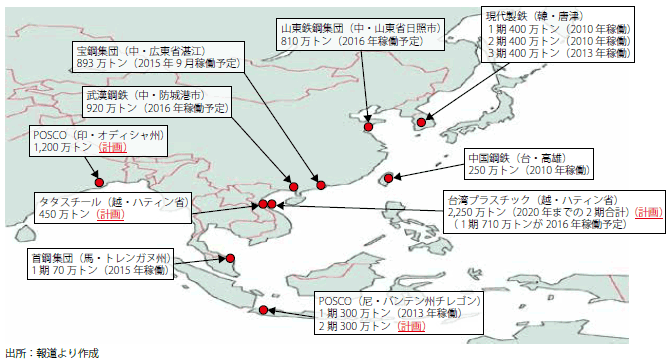
49 OECD Directorate for Science, Technology and Innovation, Steel Committee (2015), Excess Capacity in the Global Steel Industry: The Current Situation and Ways Forward, DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL, March 2015
50 見掛消費量とは、一般的に、当該国・地域の生産量に輸入量を加えたものから、輸出量を差し引いたものをいう。
51 OECD Directorate for Science, Technology and Innovation, Steel Committee (2015)
52 鉄鋼は、多くの産業の基盤となる素材であり、自動車・家電等の製品や、鉄道や高速道路等の交通インフラ、油田・パイプライン等の資源インフラ、そして我々が生活する建物の多くにも使用されている。そのため、各国とも自国における安定供給を志向しており、我が国でも今から100年以上も前の1901年に官営八幡製鐵所が稼働した。
②貿易救済措置の発動増加
需要を超えて生産された鋼材は国内・輸出市場で安価で取引され、結果的に鉄鋼業界全体の収益性低下に繋がっている。加えて、輸入国には安価な鋼材が大量に流入してくることもあり、上述のとおり世界各地で貿易救済措置の発動が増えている。ベースメタル製品を対象としたアンチダンピング(AD)の措置件数は、2011年の21件から2014年には61件に急増しており、セーフガード(SG)の措置件数も増加傾向にある。件数ベースでは、全世界で発動された2014年の貿易救済措置のうち、ADで約39%、SGでは約36%がベースメタル関連であり、2000年代初頭以降減少傾向にあったAD措置件数は、再び増加しつつある。(第Ⅰ-1-2-1-69図、第Ⅰ-1-2-1-70図)
第Ⅰ-1-2-1-69図 世界のセクター別アンチダンピング措置件数の推移
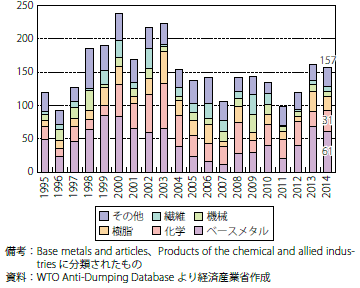
第Ⅰ-1-2-1-70図 世界のセクター別セーフガード措置件数の推移
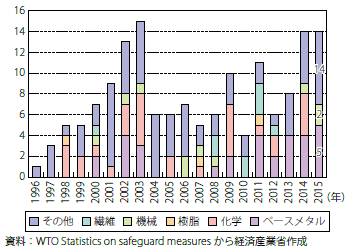
2.資源価格の変動や債務拡大によるボラティリティの拡大
(1) 資源国経済の現状と課題
①資源価格の下落の影響
新興国における資源需要拡大に伴い、資源国経済の成長は加速したが、新興国の景気減速やシェール革命等による供給増加のため生じた資源価格の下落を受け、景気減速した可能性があると考えられる(第Ⅰ-1-2-2-1図)。他方、その影響の大きさは国により異なる。ロシア及びブラジルでは資源価格の下落と軌を一にして実質GDP成長率が減速し、2015年はマイナス成長に陥っている(第Ⅰ-1-2-2-2図、第Ⅰ-1-2-2-3図)。また、為替水準が下落するとともに、国債に係るクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)も上昇している(第Ⅰ-1-2-2-4図)。
第Ⅰ-1-2-2-1図 主要コモディティ価格の推移
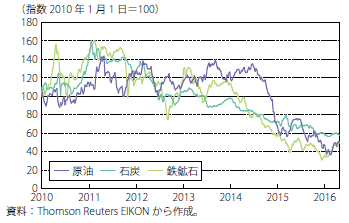
第Ⅰ-1-2-2-2図 資源国の実質GDP成長率と原油価格の推移
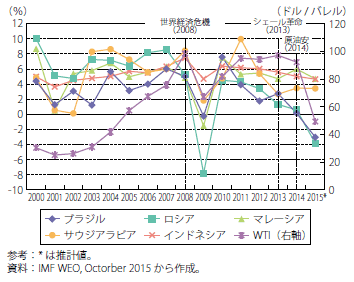
第Ⅰ-1-2-2-3図 ロシア・ブラジルの実質GDP成長率
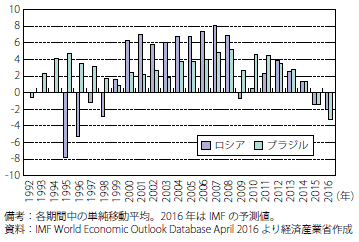
第Ⅰ-1-2-2-4図 主要資源国為替と原油価格WTIの推移
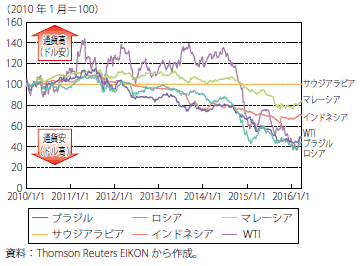
一方、インドネシア及びマレーシアは同じく資源国であるにもかかわらず、これまでのところ、ロシアやブラジルほどの落ち込みは見られない。サウジアラビアについては、対ドル固定相場制の採用により為替レートの変化は見られないが、原油価格が一段と下落した2015年8月末以降、CDSの上昇が見られる(第Ⅰ-1-2-2-5図)。
第Ⅰ-1-2-2-5図 資源国CDS(5年物)スプレッド 推移
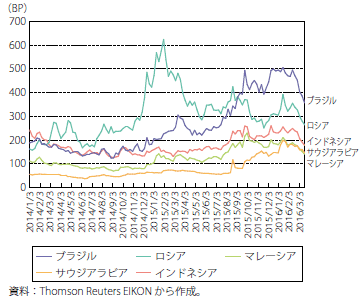
こうした違いには、アジア通貨危機以降の金融面でのリスク耐性向上も影響していると考えられるが、2000年以降のコモディティブーム期に、資源依存を深めたのか、あるいは軽減できたのかも背景にあると考えられる。これら資源国の成長の軌跡を比較しつつ、コモディティブーム期における資源依存の高まりの背景について考察する。
②資源国の課題
主要資源国の財貿易に占める資源依存度は、1980年代以降、インドネシア、マレーシア、メキシコにおいて顕著に低下し、2000年以降、やや増加傾向にあるものの、概ね低い水準で推移している。(第Ⅰ-1-2-2-6図)
第Ⅰ-1-2-2-6図 貿易財に占める資源の割合の推移
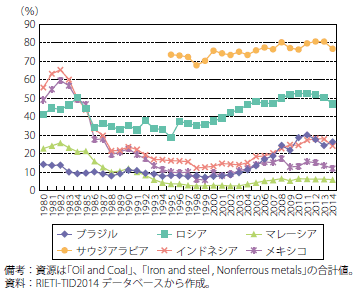
この背景には、第1章で指摘したような製造業を中心としたグローバルバリューチェーンの拡大があると考えられる。すなわち、インドネシアやマレーシアについては、ASEAN統合や産業政策の転換に伴い日系を始めとする外資企業による直接投資が進み、グローバルバリューチェーンへの統合が進んだ。1980年代から1990年代にかけて、財貿易に占める加工品や部品の割合が増加していることは、その現れであると考えられる。(第Ⅰ-1-2-2-7図、第Ⅰ-1-2-2-8図)。
第Ⅰ-1-2-2-7図 マレーシアの財別貿易の推移
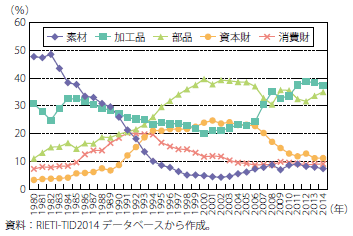
第Ⅰ-1-2-2-8図 インドネシアの財別貿易の推移
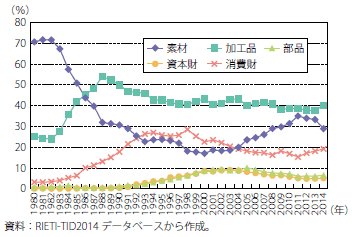
メキシコについても、NAFTAなどの経済統合を背景に、米国企業を中心とする先進国企業の投資が進み、製造業を拡大させた。
一方、サウジアラビアは財輸出に対する資源への依存割合を高い水準で保っており、従来、工業国でもあったブラジルやロシアは逆に資源への依存を深めている。(第Ⅰ-1-2-2-9図、第Ⅰ-1-2-2-10図、第Ⅰ-1-2-2-11図)
第Ⅰ-1-2-2-9図 サウジアラビアの財別貿易の推移
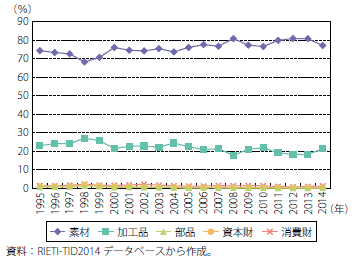
第Ⅰ-1-2-2-10図 ブラジルの財別貿易の推移
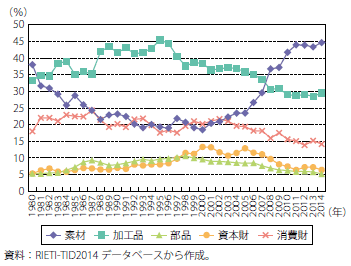
第Ⅰ-1-2-2-11図 ロシアの財別貿易の推移
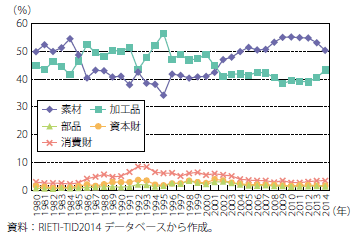
一部の資源国における産業構造の多様化の遅れは、ASEAN等と比較して経済統合が進まず、グローバルバリューチェーンへの組み込みが遅れたことが共通項として挙げられる可能性があるほか、各国固有の課題も存在すると考えられる。
例えばブラジルは、複雑な税制、労働・雇用・社会保障コスト、ロジスティックスコストなどのいわゆる「ブラジル・コスト」の存在が従来から指摘されている。航空等の限られた分野を除き、国際競争力を保つことができていない可能性がある。
産業構造が多様化し、資源依存の経済から脱却するためには、FTAを始めとする経済連携や各国固有の課題に適切に対応していく必要がある。
(2)新興国における債務の拡大
世界経済危機後、多くの新興国において非金融民間企業の債務が拡大を続けている。2008年時点では先進国企業の方がGDPとの比率において新興国企業よりも多くの債務を抱えていたが、2013年に逆転し、2015年第3四半期時点では、新興国非金融民間企業債務の対GDP比は100.7%となり、先進国の85.7%を大幅に上回っている。債務残高自体の増加は中国、トルコ、ロシア、ブラジルにおいて大きいが、家計債務も含めた返済負担を示すデット・サービス・ラシオはブラジル、韓国53、中国において高く、特にブラジル及び中国における伸びが大きい(第Ⅰ-1-2-2-12図、第Ⅰ-1-2-2-13図、第Ⅰ-1-2-2-14図、第Ⅰ-1-2-2-15図)。
第Ⅰ-1-2-2-12図 非金融民間企業部門の債務残高対GDP比(%)
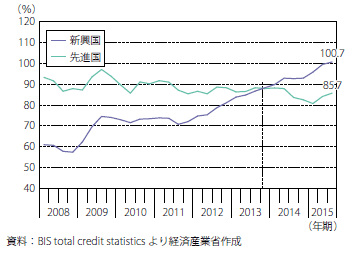
第Ⅰ-1-2-2-13図 主要新興国における債務残高対GDP比の変化 (2008Q3-2015Q3パーセントポイント)
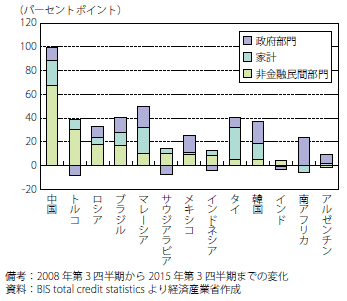
第Ⅰ-1-2-2-14図 主要新興国の非金融民間・家計部門の債務返済負担
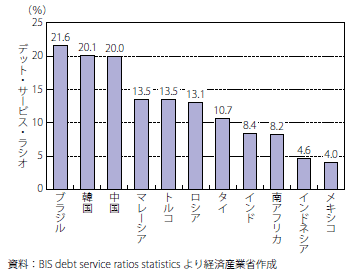
第Ⅰ-1-2-2-15図 ブラジル・韓国・中国の非金融企業・家計部門の債務返済負担
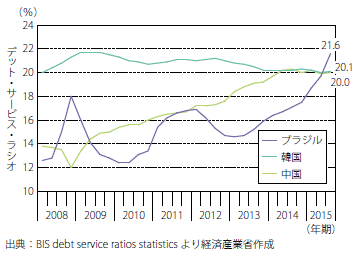
資本と債務の比率を示すレバレッジも拡大しており、国別では中国及び中南米、セクター別では建設や石油・天然ガスでの拡大が著しい。ただし、中国・中南米においてもその他のセクター、建設や石油・天然ガス関連であっても他地域においては顕著な拡大は見られないことが特徴となっている(第Ⅰ-1-2-2-16図、第Ⅰ-1-2-2-17図)。
第Ⅰ-1-2-2-16図 新興国における上場企業のレバレッジ上昇率(2007-2013)
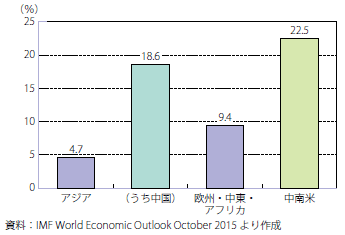
第Ⅰ-1-2-2-17図 主要新興国の上場企業レバレッジ上昇率(2007-2014)
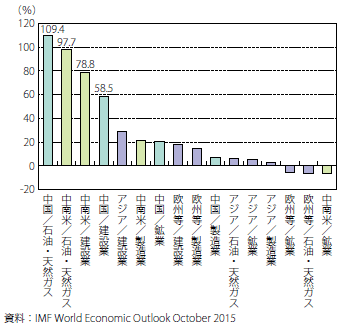
そもそも非金融民間企業のレバレッジは、個別企業レベルの要因、国レベルの要因、グローバルな要因により左右され得るが、IMFの分析によれば、このうち個別企業・国レベルの要因54の重要性が相対的に低下する一方、米国の金利水準や、やや影響は薄まるものの原油価格といったグローバルな要因がより重要性を増しており55、新興国はグローバルな金融環境のタイト化の影響に備える必要があるとされている。例えばブラジルの民間債務は、世界経済危機以降の金利低下局面で大幅に増加しており、世界的な金利水準の低下と関係性がある可能性がある(第Ⅰ-1-2-2-18図)。
第Ⅰ-1-2-2-18図 ブラジル企業による社債発行高・プロジェクトファインストランシェ額(億ドル)
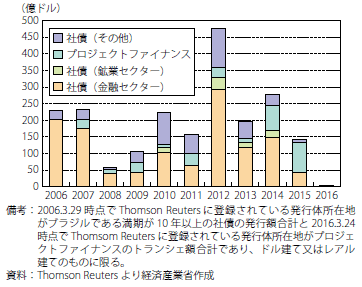
また、並行して中南米を中心に外貨建債務へのエクスポージャーも拡大しており、その点でも注意が必要であるとされている56。ブラジルにおける民間債務のドル建て比率は、鉱業セクターの社債(97.2%)やプロジェクトファイナンス(77.5%)など、一般的にドル建てでのキャッシュフローを期待できるセクターにおいて高いが、金融セクターの社債などにおいても、一定程度の比率があることに留意が必要である(第Ⅰ-1-2-2-19図)。
第Ⅰ-1-2-2-19図 ブラジル民間債務のドル建て比率
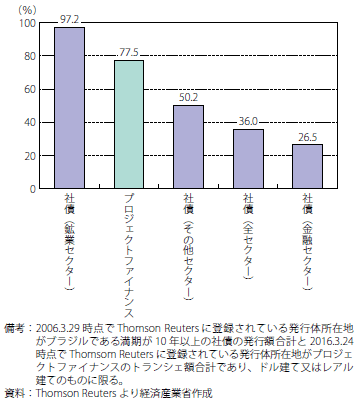
家計債務についてはタイ、マレーシア、シンガポールなど東南アジア諸国を中心に伸びが見られ、先進国並みの水準に至っている57(第Ⅰ-1-2-2-20図、第Ⅰ-1-2-2-21図)。所得向上に伴う消費意欲の拡大に加え、我が国からの支援58等による信用情報に関する制度整備や法制度整備59の進展等が背景にあると考えられる。例えば成人人口に対する信用情報のカバレッジ率はタイが70.8%、マレーシアが70.4%、シンガポールが60.8%と急上昇しており、消費の拡大に貢献している(第Ⅰ-1-2-2-22図)。他方、家計債務の急上昇に対しては金融面での不安定要素とならないよう、個人融資に対する規制を導入する動きも一部において見られる。
第Ⅰ-1-2-2-20図 主要新興国における家計債務の変化(2008Q3-2015Q3パーセントポイント)
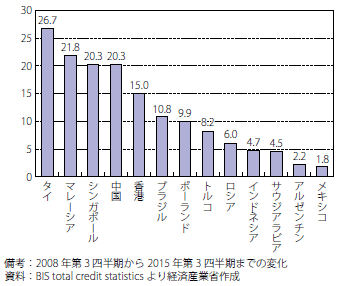
第Ⅰ-1-2-2-21図 ASEAN諸国における家計債務残高対GDP比の推移
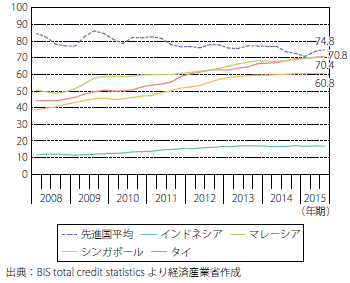
第Ⅰ-1-2-2-22図 成人人口に対する信用情報カバー率
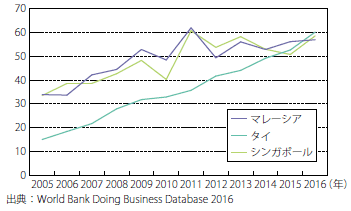
なお、中国や資源国60を除く新興国の多くが経常赤字国であることには留意が必要である。経常収支が赤字である国は、外国から資金を調達しその赤字を賄うことが必要になり、対外純債務が増加する。世界経済危機やユーロ危機を挟み、米国61や南欧諸国が経常赤字を削減した一方、経常赤字国における新興国の比率が高まっている。全世界の経常黒字の総計、すなわちグローバル・インバランスの規模は世界経済危機を境に縮小しているにもかかわらず、引き続き経常黒字が中国やドイツ等に偏り、多くの新興国が経常赤字国に転じている(第Ⅰ-1-2-2-23図、第Ⅰ-1-2-2-24図、第Ⅰ-1-2-2-25表)。
第Ⅰ-1-2-2-23図 グローバル・インバランスの対名目GDP比
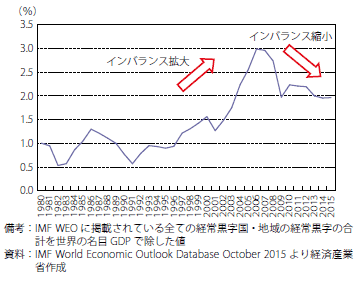
第Ⅰ-1-2-2-24図 世界主要国における経常収支の推移
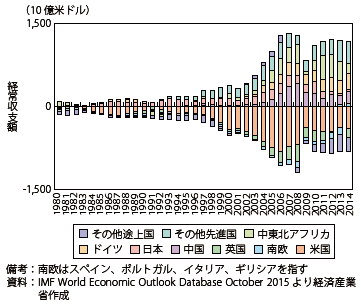
第Ⅰ-1-2-2-25表 グローバル・インバランスの規模の変化
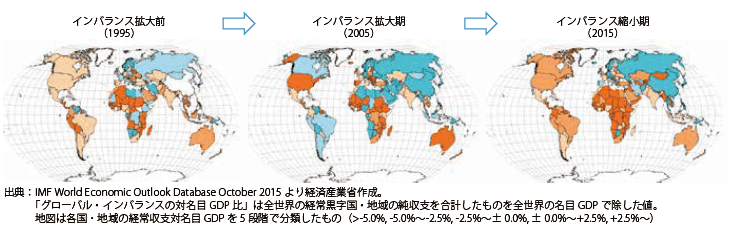
53 韓国の外国資本への依存が高いことは、外国資本が引き上げをする際、韓国内の資金供給を縮小させ、円滑な経済活動に影響を及ぼす恐れがあるとの指摘がある。韓国の対外純資産残高をみると、2014年第3四半期から、統計作成が始まった1994年以来初めて資産が負債を上回り純資産国へと移行した。一方、対外資産・負債残高(2014年末時点)の構成をみてみると、負債については、簡単には撤退が困難な「直接投資」よりも、引揚げが容易な「証券投資」、「その他投資」(融資等)が多くの割合を占めている。また、当該年に支払い期限が来る短期対外債務残高に対する外貨準備高の割合は、ベンチマークである1.0倍を超える水準を保っている。
54 例えば中国の債務拡大は、世界経済危機以降の景気対策や設備投資に依存した経済発展・過剰生産能力と密接に関連していると考えられる。中国の過剰生産能力については、第1部第1章第2節(1)、債務拡大の実態については通商白書2014を参照されたい。
55 Diana Ayala, Milan Nedeljkovic & Christian Saborowski (July 2015) “What Slice of the Pie? The Corporate Bond Market Boom in Emerging Economies (IMF Working Paper WP/15/148)”
56 International Monetary Fund “Global Financial Stability Report October 2015”
57 一般的に先進国は住宅ローン等の家計債務の蓄積に必要な法制度が整備されており、家計債務は新興国と比較して高い水準にある。2015年第3四半期では、先進国における同対GDP比が74.8%であったのに対し、新興国・途上国は32.3%であった(BIS total credit statisticsによる)。
58 例えばAPECにおける構造改革イニシアティブ(EoDB: Ease of Doing Business)の一環として、我が国は資金調達分野においてAPEC参加国・地域の制度支援を実施していた。
59 世界銀行によるビジネス環境評価指標であるDoing Businessにおいては、「資金調達の容易さ」が要素の一つとなっており、信用情報のカバレッジ率や法制度の整備状況などがメルクマールとなっている。
60 IMF World Economic Outlook Database October 2015によれば、資源国の多くは2015年に経常赤字に陥るとの予測がなされている。
61 ドル基軸通貨体制の下、国際取引における決済通貨として米ドルに対する需要が持続的に存在することから、米国は経常収支赤字の拡大や対外純債務の累積を可能とする(小川英治 編著「グローバル・インバランスと国際通貨体制」)が、新興国においてはそのような事情はない。
3.新興国等における構造改革の取組
ここでは新興国の中でも、新常態に移行しつつある中国、世界第二位の人口と高い経済成長率を誇るインド、政治なども含めて転換期にある韓国、足下の資源価格の下落による影響を受けている資源国における構造改革の取組について記述する。
(1)中国における「新常態」への移行
中国は過剰生産能力や投資主導の成長モデルからの脱却など様々な構造的な課題に直面しており、中国政府もそれに見合った政策の方針転換を図りつつある。ここでは2016年の全国人民代表大会(全人代、我が国の国会に相当)で表明された2016年重要政策や第13次五か年計画等を中心に中国政府の取組について概観していく。
①中国政府の基本的な対応方針
中国政府は、2016年3月の全人代に2016年の活動方針を説明するとともに、今後5年間にわたる第13次五か年計画の草案を提示して審議を求めた。
2016年の目標値を見ると、高速成長から中高速成長に移行する「新常態」の中で、GDP、投資、消費等の成長率目標の引下げを行う一方で、雇用関係については2015年と同水準の目標を維持した(第Ⅰ-1-2-3-1表)。景気減速を受けて、財政赤字を拡大しての減税の実施、マネーサプライの伸び率拡大、為替レートの基本的安定など、マクロ経済安定に向けた経済下支えの姿勢も見せている。
第Ⅰ-1-2-3-1表 2016年の主要目標(全人代「政府活動報告」等)
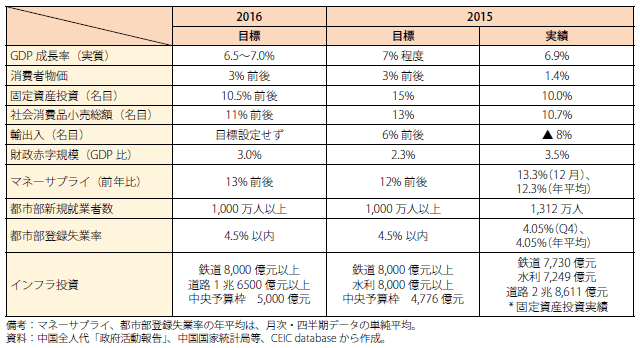
その上で、これまで述べたような構造的な課題に対する方針を見ていくと、サプライサイドの構造改革として、過剰生産能力の解消、国有企業改革、製造業の高度化、近代サービス業の育成等が挙げられている(第Ⅰ-1-2-3-2表)。また、国内需要の拡大と需要構造の改革として、消費の高度化・拡大、インフラや産業高度化に向けた投資の推進、戸籍制度改革も含めた都市化の推進、住宅関連税制による不動産在庫解消などが表明されている。その他に、対外経済関係の推進や環境対策の強化、民生関係では、一人っ子政策の廃止(第二子出産の容認)、高齢化が進む中で医療保険や年金制度の整備等もうたわれている。
第Ⅰ-1-2-3-2表 2016年の重点施策(全人代「政府活動報告」)
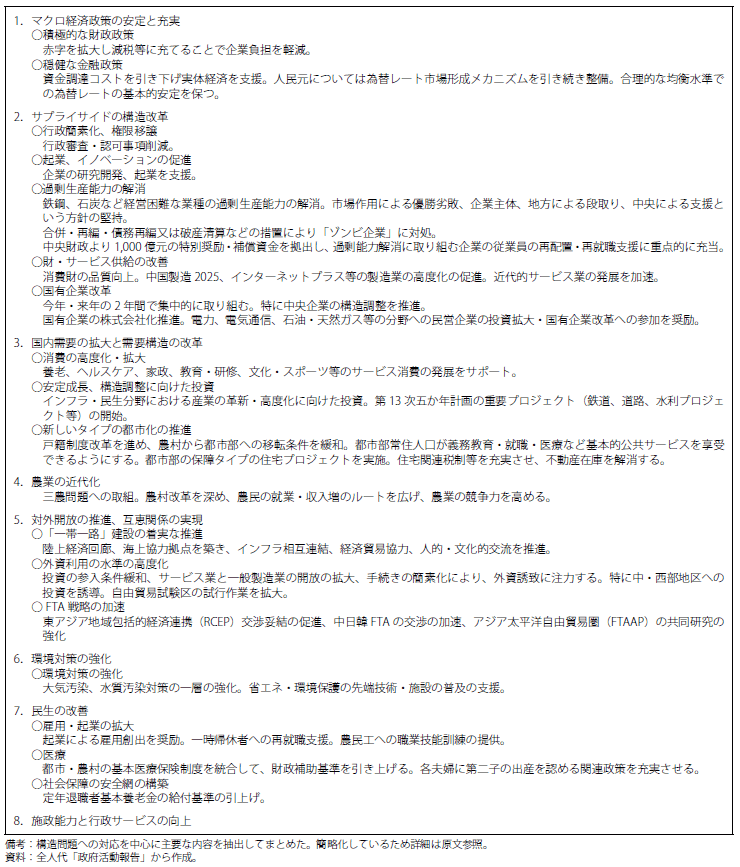
全人代では第13次五か年計画の草案も提出された。経済の中高速成長を維持して、産業の中高次元化を促進するとして、「革新」「調和」「グリーン」「開放」「共有」の5つの理念に則った目標や重点分野を提示している(第Ⅰ-1-2-3-3表、第Ⅰ-1-2-3-4表)。これを見ると、生産年齢人口が減少に転じる中で、イノベーションや産業高度化を進めることで成長を維持していこうとする方針が強く表れている。また、格差や環境問題など成長に伴って生じてきた課題に対して、調和のある発展、環境保全という方向も打ち出している。さらに、改革開放の深化を進めるとともに、このような発展の成果を共有できるように、貧困対策、社会保障、教育制度の整備、所得分配制度の改善などを挙げている。
第Ⅰ-1-2-3-3表 第13次五か年計画の目標
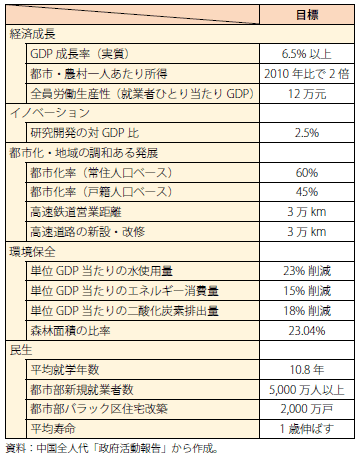
第Ⅰ-1-2-3-4表 第13次五か年計画概要
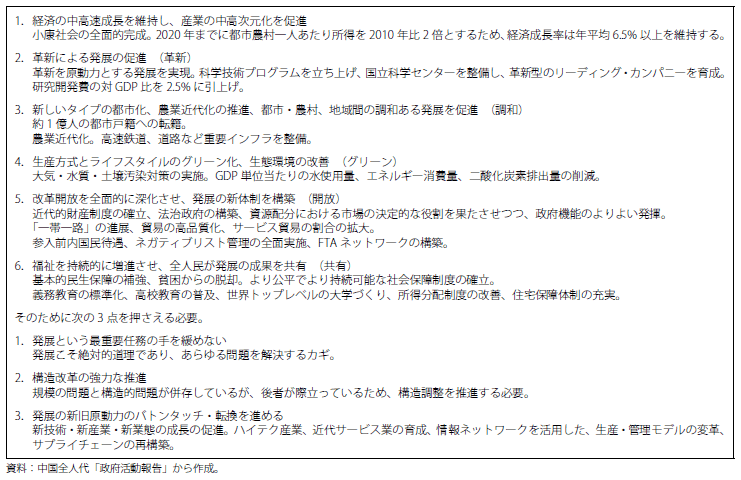
②過剰生産能力・過剰投資
過剰生産能力など特定の課題に焦点を当てて詳しく見ていくと、4兆元の景気対策を契機に、鉄鋼、石炭、セメント等の幅広い業種で過剰投資が行われたと見られ、中国の中央政府は毎年のように対策を公表して、古く生産効率の悪い設備の廃棄を指導するとともに、新規投資の抑制を続けている(第Ⅰ-1-2-3-5表)。
第Ⅰ-1-2-3-5表 中国政府の過剰生産能力の解消に関する取組
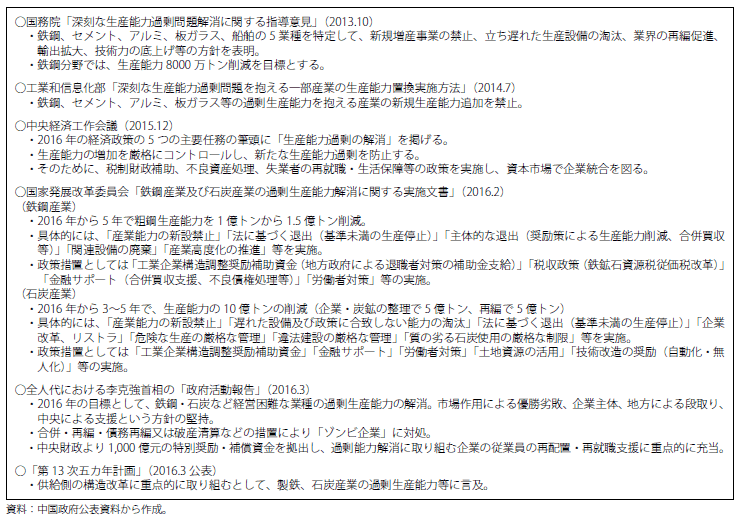
直近では、2016年2月に国家発展改革委員会は、鉄鋼、石炭産業を指定して、産業能力の新設禁止、老朽化・非効率・環境対策など問題のある設備の廃棄を規定するとともに、企業に安全管理や環境対策の厳格な執行を求め、基準に達しない企業には生産停止から退出を促す方針を表明した。具体的削減目標として、鉄鋼は5年間で粗鋼生産能力を1~1.5億トン、石炭は3~5年で、生産能力の10億トンの削減(企業・炭鉱の整理で5億トン、再編で5億トン)を掲げた。そのための政策措置として、補助金(退職者対策)、金融支援(合併買収・不良債権処理)等を実施するとしている。
また、3月の全人代における李克強首相による政府活動報告でも、2016年の方針として、鉄鋼・石炭など経営困難な業種の過剰生産能力の解消を挙げている。市場による優勝劣敗をもとに、企業が主体的に行動して、中央政府は必要な支援を行うという役割分担で、合併・再編等の措置により「ゾンビ企業」に対処するとしている。そのために1000億元の資金を拠出して、従業員の再就職支援等に充当する方針を表明している。
これまで、中央政府から過剰設備削減の方針が出されても、実際の運用に当たって設備廃棄は地元の経済や雇用への影響も大きく、必ずしも迅速に進まない面があった。このような地域経済への影響、特に失業問題の対処は、構造改革の実現に大きく影響すると考えられる。
2016年2月、中国政府は、石炭・鉄鋼産業の過剰生産能力解消の過程で、180万人(石炭産業130万人、鉄鋼産業50万人)の余剰人員が生まれるとの予測を明らかにした。中央政府は、再就職支援等のため、1000億元の資金を拠出することを決定している。これら余剰人員の処遇としては、まず、企業が配置転換を図るべきとし、次に、転職・創業を図る場合は、政府が職業訓練や就職あっせんなどの措置を講じ、また、定年まで5年未満の従業員については合意の下で早期退職という選択肢もあり、さらに再就職が困難な労働者には政府が公益性のある仕事を紹介するとしている62。中国における都市部新規就業者数は2015年までの3年間で毎年約1300万人と発表されており、雇用のミスマッチの解消も含め、今後注視していく必要がある。
62 日経新聞記事(2016.3.1.)、The Daily NNA記事(2016.3.2.)、中国網記事(http://news.china.com.cn/2016-02/29/content_37896781.htm![]() )(2016.2.29.)参照。
)(2016.2.29.)参照。
③経済成長パターンの転換
中国政府は「投資から消費への転換」を図っており、2010年代のGDPに占める投資のシェアは2015年緩やかに低下、民間消費は緩やかに上昇している。消費拡大のための方策として、2016年の全人代で表明された政策方針を見ていくと、まず、住民所得の伸び率を経済成長(6.5%~7.0%)とほぼ同じにすることが目標とされている。また、消費の高度化にあわせて、政策面の障壁を取り除き、消費環境を改善する方針も掲げている。具体的には、養老、ヘルスケア、家政、教育・研修、文化・スポーツ等のサービス消費の発展をサポートし、インターネット情報やファッション消費など新興消費を発展させる。消費者ローンの開発奨励、観光施設の強化などもうたわれている。
また、財政面では財政赤字を拡大(予算ベースで財政赤字のGDP比:2015年2.3%→2016年3.0%)して減税に充て、金融面では通貨供給量を拡大する(M2:2015年前年比12%前後の増加→2016年同13%前後の増加)方針が挙げられている。さらにインフラ投資では第13次五か年計画の重要プロジェクトをスタートさせ、鉄道投資8千億元以上、道路投資1兆6500億元。中央予算枠内の投資を5000億元に増やす(2015年4776億元)などが目標とされている。
④人口政策の変更
生産年齢人口がピークアウトする中で、中国は一人っ子政策の廃止を決定したが、今後の中国の人口動態について出生率などの仮定が公表されている国連人口推計をもとに考えてみる。国連では5つの出生率シナリオのもとに将来の人口推計をしている(第Ⅰ-1-2-3-6図)。まず、中国の出生率を2010-2015年時点で1.55と見ており、一つ目の中位ケースにおいては、出生率が2100年の1.8に向かってゆっくり上昇する。次の高位ケースにおいては出生率が2015-20年に1.8に上昇し、さらに2020-25には2.0を超える。反対に低位ケースにおいては出生率は2020-2025に1.23まで低下する。その他に、現在の出生率が今後も変わらないというケースや総人口が安定するケース(死亡が出生によって直ちに補填されるケース)がある。
第Ⅰ-1-2-3-6図 中国に関する出生率の5シナリオ(国連人口推計)
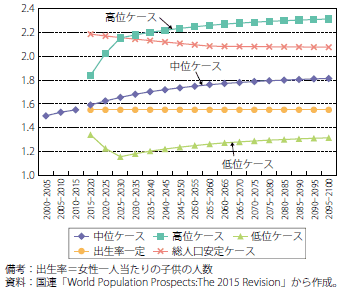
このシナリオに基づいて、今後の中国の生産年齢人口について考えてみる。生産年齢人口については、生まれた子供が15歳に成長するまでの今後15年間は出生率シナリオにかかわらず、予測に差は生じない。その後はシナリオによって生産年齢人口は変化するが、国連の推計では、いずれのケースでも少なくとも今世紀中頃まで生産年齢人口(15-59歳)は下がり続ける見通しとなっている(第Ⅰ-1-2-3-7図)。なお、今世紀後半になれば、高位ケースでは生産年齢人口が増加に転じるが、中位ケース、低位ケースでは減少が続く見込みとなっている。
第Ⅰ-1-2-3-7図 中国の生産齢人口(国連人口推計)
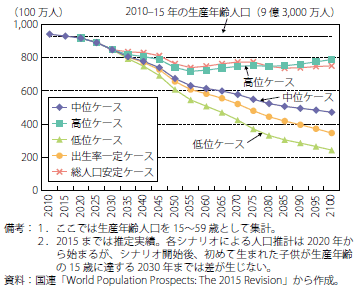
総人口については、高位ケースでは、15億人に向かって緩やかに上昇し、その水準を維持できる見込みだが、中位ケース、低位ケースでは総人口も減少していく見込みとなっている(第Ⅰ-1-2-3-8図)。
第Ⅰ-1-2-3-8図 中国の総人口(国連人口推計)
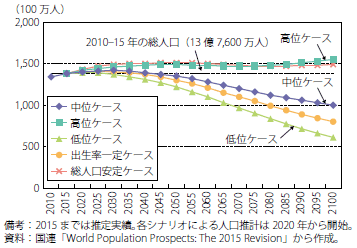
現在、中国は一人っ子政策を廃止して、すべての夫婦に二人目まで子供を認めることとしているが、三人以上認められるわけではない。また、国連推計では、高位ケース(出生率は2を超えて上昇)でさえも、生産年齢人口は現在の9億人強から今世紀半ばには7億人強まで約2億人も減少する見通しとなっており、一人っ子政策の廃止によっても生産年齢人口の大幅な減少は避けられないと見られる。
また、国連以外の人口推計としては、2015年12月に世銀が人口見通しに関する報告書を発表したが、そのデータで見ても中国については2010年から2040年までの30年間に生産年齢人口が10%(約9000万人)減少する見通しとなっている(第Ⅰ-1-2-3-9表)。
第Ⅰ-1-2-3-9表 中国の生産年齢人口の変化(2010→2040)
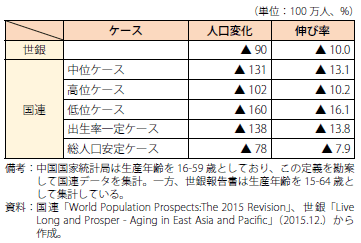
⑤製造業の高度化とイノベーションへの取組み
このように生産年齢人口が減少に転じ、労働力など資源の投入による成長が限界を迎えつつある中で、中国政府は、製造業を始めとした産業の高度化やイノベーションによる生産性の上昇等によって持続的な発展を目指す方針を表明している。
その一つが2015年に公表された「中国製造2025」戦略で、その中では、イノベーションの促進、情報技術と製造業の融合、品質向上、ブランド化の方針を掲げ、建国100年である2049年に中国が世界の製造業トップに立つことを目指している(第Ⅰ-1-2-3-10表)。
第Ⅰ-1-2-3-10表 「中国製造2025」(Made in China 2025)
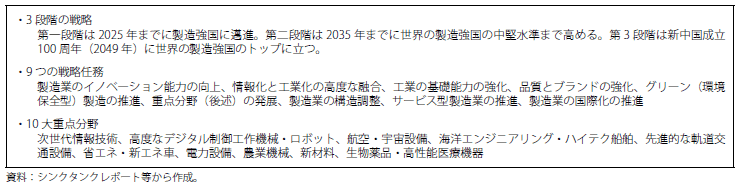
中国政府は、「中国製造2025」の中でも取り上げているように、イノベーションの促進を大きな方針に掲げている。現在の中国のイノベーション水準について、一つの目安として各機関が公表している「国際競争力指数」の中のイノベーション部門のランキングで見ると、約140か国の対象国の中で中国は30位前後であり、日本や米国には及ばないものの、イタリア、ポルトガルといった一部先進国と並ぶ水準と見ることもできる(第Ⅰ-1-2-3-11表)。
第Ⅰ-1-2-3-11表 イノベーションに関する国際ランキング
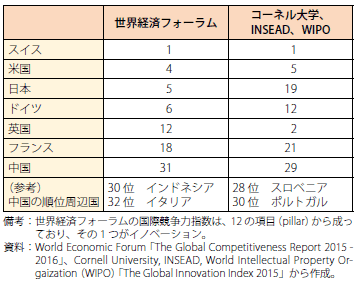
イノベーション活動やその効果について客観的評価は難しいが、中国の研究開発費の対GDP比率は急上昇し、既に英国など一部の先進国を追い越している(第Ⅰ-1-2-3-12図)。第13次五か年計画では、この比率を更に2.5%まで引き上げることを目標に掲げている。
第Ⅰ-1-2-3-12図 中国の研究開発費の推移
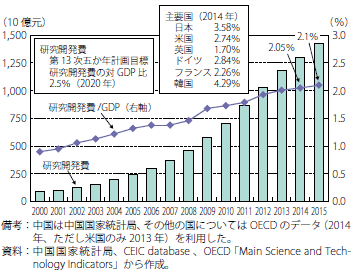
また、特許の国際申請件数では、中国は国ベースでドイツを抜き、米国、日本に次ぐ第3位の地位を占めている(第Ⅰ-1-2-3-13図)。企業ベースで見ても、一部には先進国企業を凌駕するほどの申請を行う中国企業も登場している(第Ⅰ-1-2-3-14表)。
第Ⅰ-1-2-3-13図 特許の国際出願件数上位10か国(2015年)
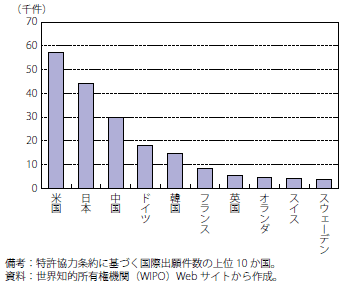
第Ⅰ-1-2-3-14表 特許の国際出願件数上位10社の国籍(2015年)
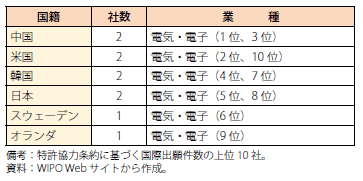
このように中国は依然として知的財産権の保護など課題が指摘されることも多いが、先進国にキャッチアップすべく急速にイノベーションの促進にカジを切ろうとしている。
(2)構造改革への期待が高まるインド
中国の経済成長が鈍化しており、また、資源価格や世界的なマネーの動きに大きく左右され、景気悪化が進行する国々がある一方で、インドは堅調な成長63を維持している(第Ⅰ-1-2-3-15図)。
第Ⅰ-1-2-3-15図 新興国の実質GDP成長率の推移
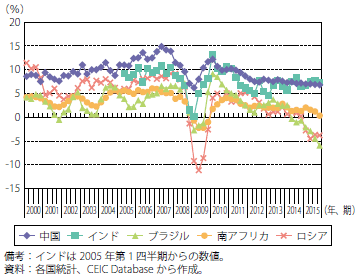
2014年5月、単独の政党としては30年ぶりとなる下院での過半数を獲得したインド人民党(BJP)のモディ政権が始動して約2年が経った。モディ氏個人への高い人気は持続しており、国内外からのインド成長への期待値は高まる一方で、モディ政権の構造改革(いわゆるモディノミクス)は、議会における「ねじれ現象」にも直面している。ここでは、主な経済指標でインド経済の現状を確認するとともに、インド政府の構造改革の取組について概観する。
63 IMFのクリスティーヌ・ラガルド(Christine Lagarde)専務理事は、2015年10月、「世界的な景気減速の中においてもなお、インドは“bright spot”だ」と言及した。
①高成長を維持するインド経済
(a)中国を上回った実質GDP成長率
名目GDPの需要項目別構成(2014年度64実績)を見ると、個人消費が58%、総固定資本形成が31%、政府消費が11%であることから、約6割を占める個人消費が成長の主エンジンになっていることが分かる。
実質GDP成長率(新基準)65を年ベースでみると、2012年度は前年比5.6%、2013年度は同6.6%、2014年度は同7.2%と拡大している。四半期ベースの足下をみると、2015年第1四半期より3四半期連続で7%台を維持しており、大きな伸びとなった。堅調な個人消費が高成長を牽引しているほか、公共投資の拡大も成長の要因になっている(第Ⅰ-1-2-3-16図)。
第Ⅰ-1-2-3-16図 インドの実質GDP成長率及び需要別寄与度の推移
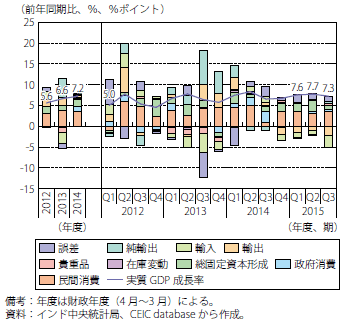
次に、名目GVA (総付加価値)の66産業項目別構成(2014年度実績)を見ると、第一次産業が17%、第二次産業が30%、第三次産業が53%であることから、約5割を占める第三次産業(以下、サービス業)が成長の主エンジンになっていることが分かる。
実質GVAの産業項目別構成(2014年度実績)を年ベースで見ると、2012年度は前年比5.4%、2013年度は同6.3%、2014年度は同7.1%と拡大している。特に、サービス業67の伸びは、2012年度は4.0%、2013年度は3.9%、2014年度は5.3%と大きく成長率に寄与していることが見てとれる(第Ⅰ-1-2-3-17図、第Ⅰ-1-2-3-18図)。
第Ⅰ-1-2-3-17図 インドの実質GVA成長率及び産業別寄与度の推移
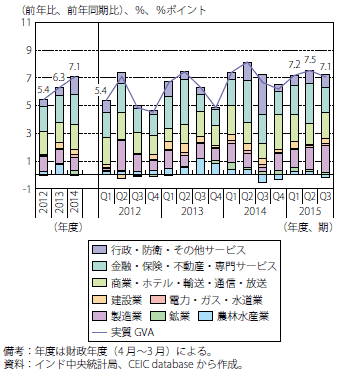
第Ⅰ-1-2-3-18図 インドの産業別の伸び率
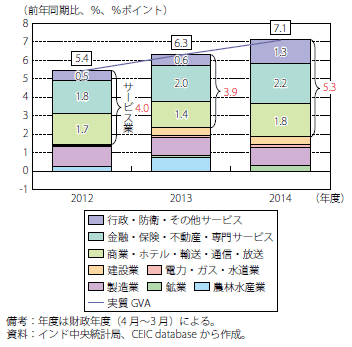
実質GDP成長率は、2015年通年(暦年)で7.3%となり、中国の同6.9%を超える結果となった。上で述べたように、インドが統計作成方法の変更を行ったことに留意が必要ではあるものの、GVAも7%超であることは、インドの成長の勢いを裏付けているといえよう。
他方、名目GDPの伸びは減速しており、実質GDPの伸びが、物価の下落にもたらされた側面もあることに留意が必要である(第Ⅰ-1-2-3-19図)。GDPデフレータは2013年第3四半期以降、低下しており、2015年第2四半期にはマイナスになっている。それゆえ、高い実質GDP成長率を計上しているものの、インド自身は数字ほどの強い成長を実感できてはいないと考えられる(第Ⅰ-1-2-3-20図)。
第Ⅰ-1-2-3-19図 インドの名目GDP成長率
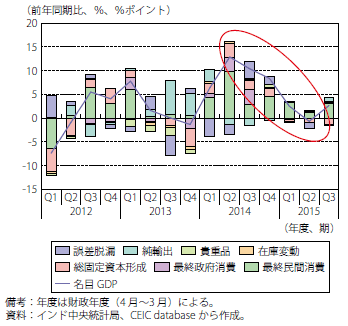
第Ⅰ-1-2-3-20図 インドのGDP(名目成長率・実質成長率・デフレータ)
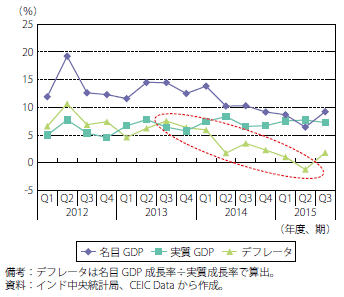
64 インドの財政年度は4月から翌年3月までである。
65 インド中央統計局は、2015年1月、SNA(国民経済計算)の基準年改訂を含む統計作成方法の変更を公表した。これによって、GDPの基準年が2004-05から2011-12に、算出方法が要素費用ベースから市場価格ベースに変更された。新統計の成長率と旧統計の成長率との間では断層が生じており、見かけ上、新統計の成長率が旧統計と比較し高水準になっていることに留意が必要である。
66 生産側から推計された実質総付加価値。GDPはこのGVAに純間接税(NIT:間接税-補助金)を加算したもの。NITの変動に左右されるGDPより月次景気指標に近い動きをする指標として評価され、供給サイドの実質成長率を見る際、よく使われるようになっている。
67 金融・保険・不動産・専門サービス、商業・ホテル・輸送・通信・放送、行政・防衛・その他サービスを指す。
(b)経常収支~赤字が常態であるものの、足下では赤字幅が縮小~
インドの経常収支は、大幅な貿易赤字の影響で、恒常的に赤字である。財の貿易収支と、投資収益等の第一次所得収支が赤字である一方、ソフトウェア等サービス収支、在外インド人(Non Resident Indians:NRI)による本国への送金等の第二次所得収支は恒常的に黒字であるのが特徴である。財の貿易赤字の拡大を背景に、経常赤字は拡大し、2012年度第3四半期の経常赤字は、過去最大の319億ドル(GDP比6.8%)に達していたが、その後、四半期ごとに上下はあるものの、2013年第4四半期は12億ドル(GDP比0.2%)、2014年第4四半期は6億ドル(GDP比0.1%)と、その後は経常赤字の縮小がみてとれる(第Ⅰ-1-2-3-21図)。
第Ⅰ-1-2-3-21図 インドの経常収支の推移
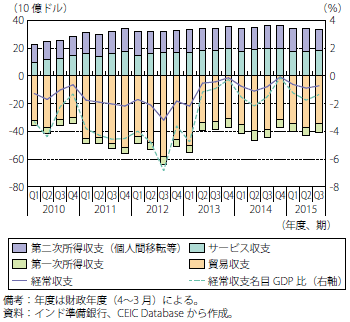
(c)財政収支~赤字が常態。高成長を志向しながらの財政健全化~
2016年2月29日に発表されたインド政府の2016年度予算案によると、高成長の促進とともに、財政健全化を目指す方針を維持しており、2016年度の財政赤字を2015年度(見込み)の名目GDP比3.9%から3.5%に縮小する計画となっている。
今回は、モディ政権発足以降、2度目の予算編成であった。1度目の2015年度予算では、インド独立75周年にあたる2022年に向けて、「TEAM INDIA」と銘打った長期政策ビジョンを公表しており、貧困層、貧困地域をなくすためのインフラ整備等、そのビジョンにそった予算配分がなされたが、今年度もその方向は継続されている。2016年度の政府歳出総額は、2015年度(見込み)から約11%も増加68しており、中でも、インフラ整備には同22%増、農業関連には同84%増と歳出を増加する計画となっている。それらの歳出増に対し、クリーン環境税、インフラ税、たばこや宝石等の各種物品税の増税などで賄う計画になっているが、2015年度予算案において計画されていたGST(財・サービス税)が未だ議会の承認を得られていないことにも留意が必要である(第Ⅰ-1-2-3-22図)(第Ⅰ-1-2-3-23表)。
第Ⅰ-1-2-3-22図 インドの財政収支の推移
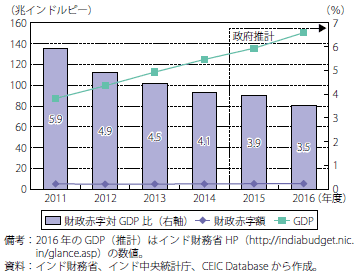
第Ⅰ-1-2-3-23表 TEAM INDIA(2022年に向けての政策ビジョン)
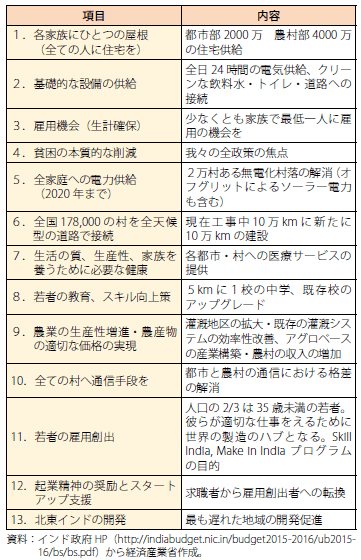
68 2015年度見込みは前年度比約5%増であった。
(d)為替相場・株価~外的要因による影響~
為替相場の推移をみると、2011年半ば以降、通貨安方向になっている。これは、いわゆる欧州債務危機69の影響が理由の一つと考えられる。インドは、欧州債務危機時、経常赤字と財政赤字という「双子の赤字」がギリシャと共通していたことが影響し、通貨安が進む結果となったという指摘もある。その後、同国で米国の量的金融緩和策(QE)の縮小が始まるとの見方が強まり、投資資金が流出する懸念が高まったこと(いわゆるバーナンキショック)で、2013年5月頃から8月まで通貨ルピーがさらに下落した。
インドは他の新興国と同様、経済成長を海外からの投資に依存している一方、経常収支が慢性的な赤字であることから、通貨が下落圧力を受ける傾向がある。政策金利の引上げを行ったこと、経常赤字が縮小したこともあり、一時的には通貨下落は歯止めがかかり、2014年5月まで通貨高方向へ持ち直した。しかし、その後は中国の景気減速、中国株の急落をはじめとする対外的な混乱等がインド市場にも影響し、通貨安傾向が継続している(第Ⅰ-1-2-3-24図)。
第Ⅰ-1-2-3-24図 インドの為替相場の推移
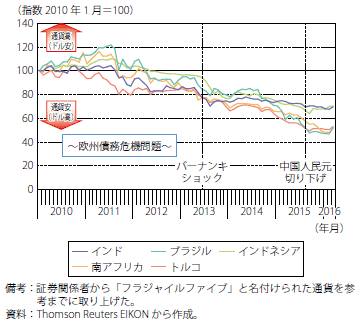
株価の推移については、インドの株式市場を代表するSENSEX株価指数70を見てみる。2012年に入り、株価は上昇傾向にあったが、2014年5月のモディ首相の就任以降、更に加速した。しかしながら、為替と同様、中国景気減速等の外的要因により下落傾向に進んでいるものの、高水準を維持している(第Ⅰ-1-2-3-25図)。
第Ⅰ-1-2-3-25図 インドの株価の推移
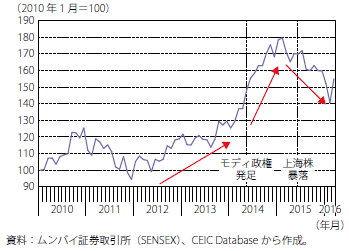
69 2009年10月、ギリシャの財政赤字の粉飾が発覚したことをきっかけに、同国のデフォルト(債務不履行)に対する懸念が広がった。その後、同国のみならず、ユーロ圏、欧州の国々に対しても、ソブリンリスク(国家信用リスク)が意識されたことにより広がった経済危機。
70 ムンバイ証券取引所に上場する30銘柄の浮動株に基づく時価総額加重平均指数
(e)物価~天候要因に大きく左右される物価~
インドでは、消費者物価の5割を占める食品、特に天候要因による野菜、穀物生産の減少がインフレ圧力を高める大きな要因となっている。灌漑設備の導入・改良に注力しているものの、対応が追いついていない。インド準備銀行は、インフレ抑制を最重要課題とし、2015年までにはインフレ率を8%未満、2016年までに6%未満、その後は4%±2%に抑える目標を公表し、物価の引き締め政策を維持している。需給面でコントロール可能な食品以外の物価上昇を金融政策で対処するほか、中長期的には、コールドチェーンといったインフラ整備等による供給力強化を通じて抑えていく政府の取組が期待されている。
2014年前半の消費者物価指数は、2013年後半のインフレ加速から相対的に鈍化したものの、食品価格の高止まりやルピー安による輸入物価の上昇を通じて、前年同月比8%前後の高水準で推移した。2014年後半は、主に食品価格の下落のほか、原油価格の下落による燃料・電気の価格の鈍化により継続して低下し、同年11月は3.3%まで低下した。その後、ガソリン・ディーゼル燃料の価格の引上げ、政府による食品価格の抑制策等でアップダウンがあるものの、その変動幅は以前に比べて小幅であり、消費者物価上昇率は低水準に維持されている。今後は、資源価格の下落によるインフレ押し下げが難しくなることから、物価安定が維持されるか注目される。(第Ⅰ-1-2-3-26図)
第Ⅰ-1-2-3-26図 インドの消費者物価指数の推移
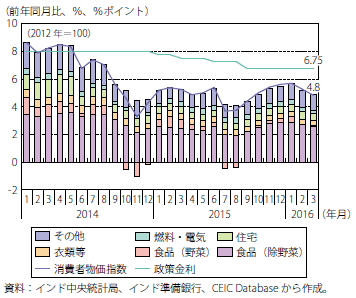
②構造改革の取組と課題
高い経済成長を見せるインドではあるが、上記のとおり、対外的な要因で為替、株価が変動しやすいこと、天候(特にモンスーンの雨量)によって物価が大きく変動してしまうこと等、課題は多く存在する。インド政府は、対外的な要因に大きく左右されない底堅い経済の構築と、経済成長の促進のため、構造改革を進めようとしている。
モディ首相は、製造業振興策“Make in India(インドでつくろう)”キャンペーンとして、海外からの製造業誘致拡大による経済成長を目指すことを明確にした。先に述べたように、近年の同国の成長にはサービス産業の伸びが大きく寄与してきたが、一方で、製造業の国際競争力は弱かったと言える。今後の更なる経済成長と雇用創出の実現のため、製造業強化にも注力し、世界の製造基地になることを目指している。
製造業振興策の対象として、①自動車、②自動車部品、③航空、④バイオテクノロジ-、⑤化学品、⑥建設、⑦防衛、⑧電気機械、⑨電子システム、⑩食品加工、⑪IT・ビジネスプロセスマネジメント(BPM)、⑫皮革、⑬メディア・娯楽、⑭鉱業、⑮原油・ガス、⑯医薬品、⑰港湾、船舶、⑱鉄道、⑲再生可能エネルギー、⑳道路、高速道路、㉑宇宙、㉒織物・衣服、㉓火力発電、㉔観光・おもてなし、㉕健康増進の25分野を示すとともに、投資の専用窓口を設置することを発表した。その他、投資環境の更なる改善、財政再建等のため、以下のような構造改革プランを相次いで発表している。
(a)税制改革
中でも注目されるのは税制改革であり、長年の課題であった物品・サービス税(GST)の導入である。2015年予算の中で、2016年4月1日から実施する、と明記したことで、複雑な間接税体系が簡素化されると対外から注目されていたが、2015年8月の国会審議が棚上げになり、予定通りに実現できなかった。一方で、州レベルでは、ラジャスタン州のように、企業誘致の観点から中央販売税(CST)を減免するなど、先行して税制改革を行う州もあることが注目される。
(b)土地制度改革
GSTの導入とともに大きく注目されているのが、土地制度改革である。2013年に制定された土地収用法に基づき、官民パートナーシップを含め、民間企業が絡む土地収用には、7~8割の地権者の合意、収用対象の土地に関係する住民への社会経済的影響の調査、公聴会の実施が必要とされたが、モディ政権は、手続きの迅速化を目的に、同法の改正等を提出するとともに、同旨の大統領令を発出した。しかし、2015年9月、農村部の有権者を置き去りにすることへの懸念や反対運動を受け、同大統領令を更新しない意向を表明した。また、2016年2月末からの予算国会では、土地収用法に関する審議案は取り下げられ、審議対象となっていない。
(c)外資規制緩和71
政権発足後直ちに、保険、防衛、鉄道インフラ関連の外資規制緩和を実行に移しており、その後も相次いで、分野毎の規制緩和を公表している。
2015年11月には、農業、防衛、放送、建設、小売、銀行等の主要セクターについて、出資比率の上限の引下げや撤廃、手続きの簡素化(例えば、政府承認ルートから自動認可ルートへの変更)を積極的に盛り込んでいる(第Ⅰ-1-2-3-27表)。
第Ⅰ-1-2-3-27表 インドの外資規制緩和
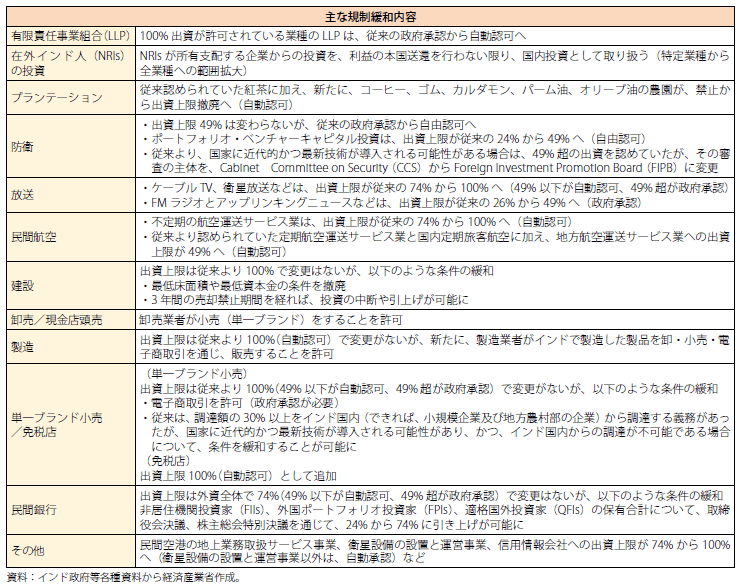
71 対内直接投資の規制は、政府の決定事項であり、議会の承認は不要である。政府が対内直接投資の規制を変更する際は、商工業省の産業政策推進局(The Department of Industrial Policy & Promotion: DIPP)が、報道発表(Press Note)として、変更内容を随時公表している。なお、投資家の便宜を考慮し、規制内容を一つにまとめた「Consolidated FDI Policy」も年に一度公表している(http://dipp.gov.in/English/acts_rules/Press_Notes.aspx![]() )。
)。
(d)金融セクターの改革
公営銀行を中心に、銀行の不良債権が膨らんでいる。政府は、不良債権処理を進めるため、公営銀行に対し公的資金を投入する旨、表明している。その他、Bank Board Bureauに、合併等、公営銀行再編のロードマップを遂行させることや、銀行に対する政府出資比率を50%未満に引き下げる選択肢も表明している。
(e)労働法制改革72
ラジャスタン州における人員整理等に係わる労働規制について、適用除外となる小規模事業者の範囲を拡大した(2014年7月に州政府議会で可決され、中央政府が承認したことで施行に至った)。
72 労働分野の行政は、連邦政府と州政府の共同管轄事項である。連邦法が基本となるが、州法で独自の特別法を決めることができる。ラジャスタン州は企業誘致に積極的であり、他の州に先駆けて、企業経営がし易くなる労働関連法の改正を行った。
(f)補助金の撤廃
財政赤字削減に向け、2014年10月、ディーゼル燃料への補助金を撤廃したほか、同年12月、ガソリンとディーゼル燃料の販売に係る物品税の引上げを行った。
インドの構造改革はモディ政権スタート以前から、連綿として行われてきた。特にインドを大きく飛躍させた構造改革は、1991年の新経済政策である。この新経済政策によって、民間企業に対する許認可制は一部を除き廃止され、その後、例外の対象も減少し、公共セクターの独占も多くの分野で見られなくなった。また、海外投資では、まず、外貨保有率の40%制限が廃止され、51%未満の場合には自動的に海外直接投資の許可がされた。その後、海外投資の自由化もさらに進み、モディ政権になる以前から、多くの分野で100%の海外投資が自動承認されている。貿易では、輸入量規制の廃止、関税の引下げ、輸出規制品目の大幅削減などが実現されている。
このような1990年代の構造改革がインド経済の基礎になり、現在の高い成長率に結びついていることを改めて確認しておきたい。
現在、モディ政権の構造改革73への期待を背景に、企業・家計マインドが改善されているほか、インド準備銀行の金利政策、規制緩和による外国投資の拡大等がインドの成長に拍車をかけていくと思われる。今後約40年は生産年齢人口が増加すると予測されるインドの潜在力は非常に大きく、世界から巨大な生産市場、消費市場としてその動向が注視されることにはゆるぎがないと思われる(第Ⅰ-1-2-3-28図)。
第Ⅰ-1-2-3-28図 インドの人口構成の将来予測(国連推計)
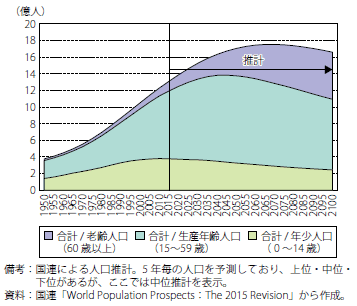
インド経済の今後の成長率については、IMFの見通しによれば、2016年、2017年ともに7.5%の成長が見込まれている。また、世界銀行の見通しによれば、2016年は7.8%、2017年は7.9%を、ADBの見通しによれば、2016年は7.4%、2017年は7.8%といずれも高成長が見込まれている(第Ⅰ-1-2-3-29表)。
第Ⅰ-1-2-3-29表 インドの実質GDP成長率の見通し
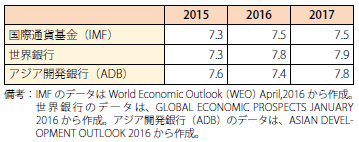
しかしながら、インドのGDP対世界比はまだ2.6%であり、中国(GDP世界比:13.4%)にとってかわって、世界経済の牽引エンジンになることは、短期的には期待できないだろう(第Ⅰ-1-2-3-30図)。
第Ⅰ-1-2-3-30図 インドのGDP対世界比
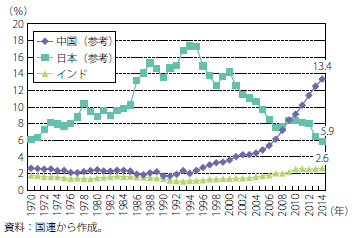
モディ首相が掲げる製造業誘致策(Make in India)を推進するためには、土地取得、インフラ、許認可、税制等、インドに進出する企業にとっての課題を解決していくことが不可欠であり、政府の取組が注目されている。足下では、国内外より、モディ政権の構造改革の進捗が遅いと指摘され、同国の改革のスピードが課題と見られているものの、それは、長期的に持続可能な成長を手にいれるための健全なプロセスともいえる。
今後、政府による財政再建及び経済成長のための構造改革が、スローガンに終わらず、明確な実績を出していけば、長期的に世界経済の牽引役を担うことになると考えられる。
73 モディ政権では、「Make in India」のほか、労働者の技術向上を推進する「Skill India」、手続きの電子行政を推進する「Degital India」、100都市の近代化を推進する「Smart India」等のスローガンを相次いで打ち出している。
(3)韓国における構造改革の取組
韓国は2014年2月に「経済革新3カ年計画」を策定した。韓国の構造的な課題として、公共部門の非効率、競争が制限された環境、生産年齢人口の減少、起業家精神の衰退、生産性向上の遅れ、大企業・中小企業間の格差、サービス業の立ち後れ、輸出に偏った成長等を指摘した上で、①基礎がしっかりした経済(非正常の正常化:公共部門改革、財政・税制改革等)、②力強い革新経済(創造経済:規制緩和とプロジェクトを通じた産業融合、起業支援等)、③内需・輸出均衡経済(内需基盤の拡充:投資促進、消費拡大、雇用促進、中小企業支援等)を計画の3本柱としている。本計画は最終目標を「韓国経済の革新と再跳躍を通じた『国民幸福時代』の実現」とし、3年後の2017年に潜在成長率を4%、雇用率を70%、1人当たり国民所得を4万ドルまで引き上げることを数値目標としている(第Ⅰ-1-2-3-31表)。
第Ⅰ-1-2-3-31表 韓国の経済革新3カ年計画の概要
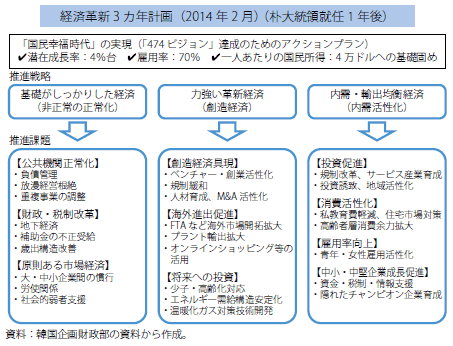
また、具体的には、基礎がしっかりした経済については、負債が膨らんでいる公企業について、統廃合や規制緩和により経営改革を進める。創造経済については、成長が見込まれる産業に財政支援を行い、全国主要17都市に設置する「創造経済革新センター」を拠点として、自治体、大企業、研究機関等の連携の下、ベンチャー企業等の振興を図る。内需・輸出均衡経済については、「保健・医療、教育、観光、金融、ソフトウェア」を重点育成サービス分野に指定し、これまでの輸出型で大企業に依存した経済構造からの脱却を目指すとしている。
中国を始めとする新興国の技術力・生産力の追い上げ等により、韓国の主力分野の国際競争力が低下しており、新たな成長のエンジンとなる産業の育成が望まれている。
政府は、従来の主力輸出品の競争力を維持する一方で、最近の輸出不振の中でも好調な消費財分野として「化粧品、衣類、生活・乳児用品、農水産物、医薬品」の5分野を挙げ、有望輸出分野として重点的に育成を図るとしている。
また、韓国の有望な成長分野として、次世代ディスプレーやバイオ医薬品、化粧品等が挙げられる。次世代ディスプレーについては、液晶に比べ薄型軽量で省電力、画質がより鮮明な点で強みを持つ有機ELパネルについて、韓国企業が世界市場で量産化で先行しており、スマートフォンやテレビ向けに生産、販売されている。バイオ医薬品については、韓国の財閥だけでなく非財閥企業も、海外の製薬大手からの受託生産や、バイオ医薬品の後発薬にあたるバイオシミラー(バイオ後続品)の開発に意欲的に取り組んでいる。また、化粧品についても、ドラマや映画の韓流ブームを追い風に、プレミアム漢方化粧品等が若い女性に人気となっており、主力市場である中国や東南アジアに加え、中東や中南米市場への進出も計画されている。
2014年の韓国のサービス産業(第三次産業)について見てみると、就業者数は全体の約7割であるのに対し、GDPに占める付加価値の割合は約6割と欧米や我が国と比べて低い水準にある。また、OECDの統計によると、韓国のサービス産業の生産性は2014年の製造業を100%とするとその45%程度と、製造業の半分以下に留まり、OECD加盟国平均の90%を大きく下回っている76。これは、高付加価値なサービス産業の育成が進まない一方で、零細な自営業者など、生産性の低いサービス分野に就業者が集中している現状を反映している(第Ⅰ-1-2-3-32図、第Ⅰ-1-2-3-33表)。77
第Ⅰ-1-2-3-32図 韓国の産業別就業者数の割合と付加価値の対名目GDP比(2014年)
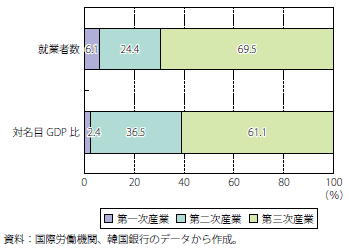
第Ⅰ-1-2-3-33表 主要国のサービス業の付加価値の対名目GDP比の比較(2014年)
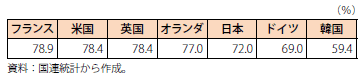
OECDは、このような状況は、韓国の製造業中心の発展により、資本や人材を含む資源の配分が製造業に集中したためと見ており、サービス産業の競争力の低さが、韓国の所得格差や成長率に影響を及ぼしていると指摘した上で、「サービス部門への参入障壁撤廃や、規制改革の推進、貿易や海外投資の自由化等を通じて、サービス部門の競争力が強化されるべき」と述べている78。
朴大統領は、「経済革新3カ年計画」の談話(2014年2月)の中で、「サービス産業に対する投資が拡大し、良質の雇用をつくり出せるように、この間、製造業中心だった財政・R&D・金融支援をサービス産業にも製造業水準に積極拡大し、サービス産業が画期的に発展できる基盤を構築する」と強調している79。
韓国は少子高齢化の進行により、2018年には高齢社会80に移行すると言われており、年金や福祉関連の政策対応に必要な財源確保のため財政支出圧力も強まっていることから、「経済革新3カ年計画」に基づいた構造改革の実現により、持続的な成長に向けた取組みの強化が喫緊の課題となっている。
韓国はイノベーションや新規産業の創出により、厳しい競争下にあるグローバル市場において更なる活路を見いだしていく一方で、これまでの製造業や輸出、大企業主導の成長モデルから、内需主導やサービス産業の振興にも考慮した新たな方向への転換により、国内の雇用や需要の創出を図っていく必要がある。
76 Overview of the OECD Economic Surveys Korea, May 2016
77 算出に用いたデータの出所が異なるため、65図の第3次産業の対名目GDP比と66表のサービス業の対名目GDP比の数値がここでは一致していない。
78 Overview of the OECD Economic Surveys Korea, June 2014
79 百本和弘(2015) 「韓国経済の基礎知識」(2015年10月)、JETROより引用
80 65際以上の老人人口が7%(高齢化社会)から14%(高齢社会)に到達するのに要する年数を「倍加年数」といい、各国の高齢化のスピードを表す指数となる。我が国は世界に類を見ない速さで1970年から1994年の24年間で「高齢化社会から高齢社会に移行」したが、韓国では2000年から2018年の18年間という我が国を上回る速さで移行すると予想されている。
(4)資源国における構造改革の動き
①ロシア/輸入代替の促進とビジネス環境の改善
ロシア経済は、プーチン大統領が就任した2000年以降、2008年の世界経済危機時を除き、一貫して原油価格の上昇によって、経済成長を経験してきた。これを背景にプーチン大統領は2004年に石油・ガス収入の一定割合を積み立てる「安定化基金」81を設置し、歳出補填、年金基金の赤字補填、対外債務の返済、及び国内インフラプロジェクトへの投融資に充てたことにより、安定的な経済成長を後押しした。現在では財政収入の5割、輸出の5割以上を石油ガス産業が占めるなど、ロシアにとって石油ガス産業への依存度は大きい(第Ⅰ-1-2-3-34図)。
第Ⅰ-1-2-3-34図 名目GDPに占める輸出額、資源輸出額の割合の推移
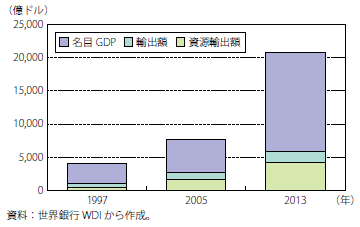
また、2015年12月15日に成立した2016年度予算は、原油価格50ドル/バレル、為替レート63.3ルーブル/ドルを前提として策定され、財政赤字はGDP比3%の2.4兆ルーブルとなっており、財政赤字は主に「準備基金」により補填しているが、原油価格が更に低位推移した場合、更に財政赤字が拡大する可能性がある。
金融政策の主軸はルーブル安に伴うインフレの抑制に置かれているものの、政策金利は2014年末にルーブル安の進行により17%に引き上げられ、その後、段階的に引き下げられたが、11%と高止まっている。現下の経済状況を踏まえれば、政策金利の引き下げが必要な状況ではあるが、インフレの上昇を懸念して、政策金利は高止まりで推移している。
このような状況の中、2015年12月3日に行われたプーチン大統領の年次教書演説において資源依存からの脱却を掲げており82、その具体的対応策として2016年3月1日にロシア政府は、「ロシア連邦の安定的な社会経済発展の確保に向けたロシア連邦政府の行動計画(危機対策計画)」を発表した83。同計画は、連邦予算からの支出総額がおよそ4,700億ルーブルで、最大の支出項目は地方への財政融資に、3,100億ルーブルが振り分けられている(第Ⅰ-1-2-3-35表)。また、経済の多様化と中期的安定化のための環境整備に重点を置き、自動車産業、住宅建設、軽工業や農業といった分野が主な支援の対象となっている84。
第Ⅰ-1-2-3-35表 ロシア2016年の危機対策計画における主要支出項目
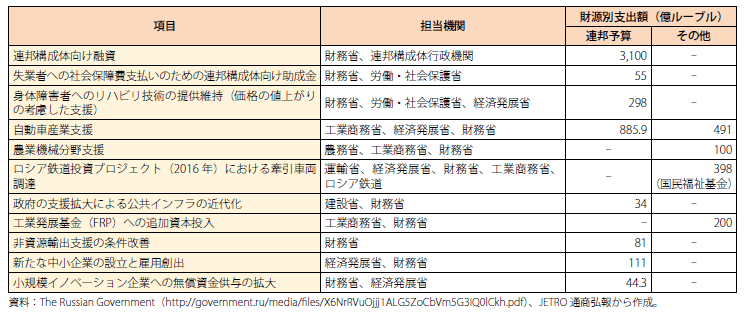
産業に対する支援には、経済構造の多様化に向けた輸入代替の促進及び非資源部門の輸出拡大、ビジネス環境改善・規制緩和などが盛り込まれており、資源依存からの脱却に向けた非資源部門の育成を目指している。
81 2008年に「準備基金」と「国民福祉基金」に分割された。「準備基金」は、歳出補填・対外債務の期限前返済に使用され、「国民福祉基金」は、年金基金の赤字補填、年金の自主積立ての補助に使用されており、2013年11月より、国内インフラ整備プロジェクトへの投融資が可能となった。
82 「競争産業は主として資源採掘部門に集中している。経済構造を変革することによってのみ、我々は安全保障及び社会発展における大きな課題を解決し、現代的な雇用機会を創出し、何百万人もの我が国国民の生活の質とレベルを向上させることが出来る。」
83 The Russian Government(http://government.ru/news/22017/![]() )4月8日時点
)4月8日時点
84 JETRO「通商弘報」(2016年3月30日)
②ブラジル/財政再建と民間債務への対応
ブラジルは総需要が減退し、実質GDPが潜在GDPよりも下回る需要不足の状態にある一方、中南米諸国の中でも財政状況が悪く、財政出動も容易ではない状況にある。こうした状況下において、米州開発銀行は、政府支出の効率化や支出先のターゲティングなどを通じて財政再建を進めるべきであり、その際、健康・教育・トレーニング・貧困対策などの分野における効率性を向上させ、社会的な便益は維持すべきであると提案している。また、民間債務の拡大は金融の不安定化をもたらす可能性があることから対処が必要である一方、資本流出に対処するため金融政策の余地は限られていることから、適切な対処が必要であるとも言及している85(第Ⅰ-1-2-3-36図)。
第Ⅰ-1-2-3-36図 中南米諸国のアウトプットギャップ(横軸)と構造的財政収支(縦軸)
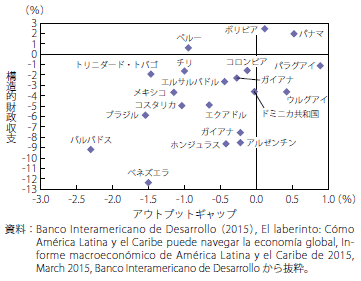
これに関連して、ブラジルでは年金改革に対する取組が進められており、例えば現在は60歳である女性の年金支給開始年齢を男性と同様の65歳に引き上げる意向が示されている86。また、金融取引暫定負担金87(CPMF)の導入や配当金に対する課税などの歳入改革の可能性も示唆されている88。
また、本年5月に大統領代行に就任したテメル副大統領は財政改革などを進める意向を示しており、市場からの期待も高まっているとの指摘もある。
85 Banco Interamericano de Desarrollo (2015), El laberinto: Como America Latina y el Caribe puede navegar la economia global, Informe macroeconomico de America Latina y el Caribe de 2015, March 2015, Banco Interamericano de Desarrollo
86 2015年12月18日のバルボーザ財務大臣発言
87 銀行預金の引出しやクレジットカードの使用等、全ての金融取引に課せられている負担金
88 同バルボーザ財務大臣発言
③アルゼンチン/市場機能重視の改革
アルゼンチンでは、2015年12月にマウリシオ・マクリ新政権89が発足し、経済回復に向けた市場機能重視の改革が始動したところである。
実質GDP成長率については、IMFは2015年(推計値)を1.2%とし、2016年は-1.0%とマイナス成長を見込んでいる(第Ⅰ-1-2-3-37図)90。アルゼンチン政府は、2016年について3.0%の成長を見込んでいるが91、アルゼンチン経済は、景気後退の一方でインフレが高騰するスタグフレーションの危機にも直面しており、今後の動向を注視する必要がある(第Ⅰ-1-2-3-38図)。
第Ⅰ-1-2-3-37図 アルゼンチンの実質GDP成長率の推移
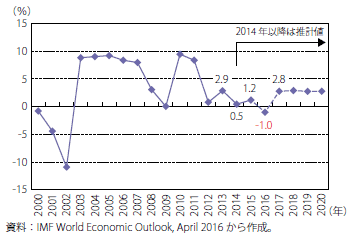
第Ⅰ-1-2-3-38図 アルゼンチンの消費者物価(CPI)上昇率の推移
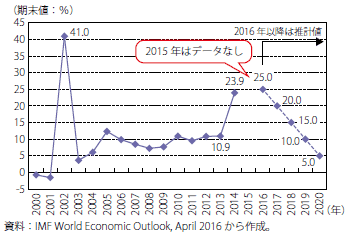
マクリ大統領は公約に基づき、複数ある対ドル為替レートを統一し、実態に近づけるための通貨ペソの切り下げ、及び主要穀物輸出産品に対する輸出税の撤廃、財政赤字の改善、外貨準備高の回復のための施策等を打ち出し、外貨管理規制を撤廃する政策についても順次行うとしている。既に政権発足直後に、変動為替相場制への移行を実施した92ほか、外貨規制の緩和及び主要農産物の輸出税の減免、自動車等の内国税の減免や工業製品の輸出税撤廃、事前輸入宣誓供述制度(DJAI)の廃止93等についても相次いで発表済みである(第Ⅰ-1-2-3-39図、第Ⅰ-1-2-3-40図)。
第Ⅰ-1-2-3-39図 アルゼンチンの国際収支の推移
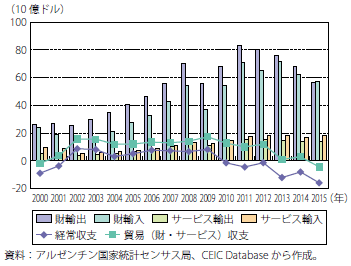
第Ⅰ-1-2-3-40図 アルゼンチンペソの為替レートの推移
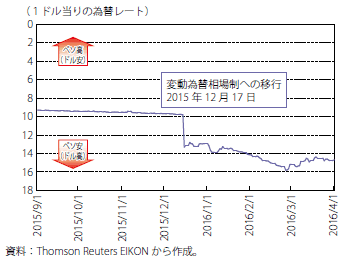
今後は、為替管理緩和による通貨の下落により物価上昇等も懸念され、短期的には景気後退も予想されるが、経済の立直しに必要な改革は痛みを伴うものであり、改革の成果が見え始めれば、電力等のインフラや農業、建設業、エネルギー分野への投資拡大に期待が高まり、外交・通商関係では、EUと南米南部共同市場(メルコスール)間の自由貿易協定(FTA)交渉の進展、太平洋同盟諸国(メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ)への輸出の拡大も期待される94。
89 2015年12月10日マウリシオ・マクリ氏が新大統領に就任し(任期4年)、12年続いた左派政権から中道右派に政権が移行した。外貨や貿易の取引規制を緩めて投資環境を改善し、経済再建に取り組むとしている。
90 ただし、2017年は2.8%とプラス成長に転換すると見通している。
91 2016年国家予算書案より。
92 為替制度の見直しはマクリ政権の最優先課題で、プラットガイ財務相は2015年12月16日、同国の4年にわたる為替規制を廃止すると発表し、翌17日の取引開始から変動相場制に移行した。
93 本制度の廃止と同時に「輸入モニタリングシステム」という新しい名称の輸入管理制度の導入が発表されており、全輸入品目のうち1,400近くの品目(自動車、同部品、情報機器、繊維等)をセンシティブ品目とし、非自動輸入許可の対象として、輸入申請が必要とした。WTOでは新制度の導入により、アルゼンチンが輸入規制に対する是正措置を履行したものとは判断出来ず、申立国(日米欧)で協議が継続中である。
94 JETRO 「通商弘報」(2016年01月06日)
④サウジアラビア/国有企業の民営化
サウジアラビアの経済情勢を規定する主な要因は、GDPの約50%を占める石油分野である。輸出のほぼ全ては石油由来となっており、政府支出の前提となる歳入面も8割を石油に依存している。そのため、サウジアラビアの経済安定性は石油価格と密接に関連しているところ、足下の石油価格の下落により、サウジアラビアの財政状況は悪化しており、サウジアラビアの財政赤字は2015年に同国の経済規模の約15%程度となっている(第Ⅰ-1-2-3-41図)。
第Ⅰ-1-2-3-41図 中東産油国の財政収支対GDP比(%)
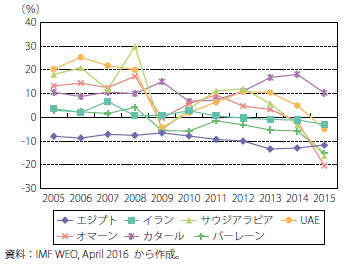
この石油依存から脱却を図るためにサウジアラビア政府は2016年4月25日に、2030年までの今後15年間で達成すべき目標とそのための政策アジェンダをまとめた「サウジアラビア・ビジョン・2030」を発表した。ムハンマド副皇太子は、「2020年までには石油に依存しない経済」にすると発言。本ビジョンは①アラブ・イスラム世界の中心化、②投資大国化、③戦略的立地化が3本柱となっており、その中の経済分野の主な項目としては以下のようなものが挙げられている。
- (1)サウジアラムコの株式(5%未満)を新規株式公開。
- (2)同株式売却等の資金をサウジソブリンウェルスファンド(SWF)に移転し、世界最大のSWFを構築。
- (3)医療・教育分野を中心に、政府機関の民営化・民間資本の参画促進。
- (4)現地での軍事産業の構築(軍事費削減、雇用創出等を視野)。
- (5)再生可能エネルギー開発(9.5GW規模を当初目標)。
サウジアラムコは世界最大の国営石油会社であり、全株式の5%分でも1,250億ドルとなり、大手資源メジャーであるTotalやBPの株式時価総額を上回るとみられている。