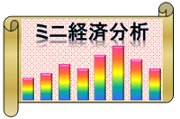第3次産業活動能力・稼働率のウォートンスクール法による試算とその限界
個別ファイルへ飛びます
概要
日本全体の経済状態を判断するうえで、設備や労働などの資源がどの程度活用されているかを示す稼働率の動向を確認することは重要です。製造業については、経済産業省の鉱工業指数で能力・稼働率指数の動向を捉えることができますが、サービス産業(第3次産業)には同様の指標が存在しません。
今回は、サービス産業について、経済産業省の「第3次産業活動指数」に対し、ウォートンスクール法(以下「WS法」という。)を適用することにより、第3次産業活動能力・稼働率を試算してみました。また、試算結果から、第3次産業と製造業の能力・稼働率指数の動向を比較してみました。最後に、WS法による第3次産業の活動能力把握、それに基づく稼働率把握の限界を評価しました。
概要は以下のとおりです。
- 平成27年の第3次産業の稼働率(試算値)は91.1%と試算される。
- 平成27年の第3次産業の活動、能力、稼働率指数は、平成22年と比較して全て上昇しているが、製造業は全て低下している。
- 第3次産業では、活動能力が上昇し続け、稼働率を押し下げる方向に作用しているが、活動量の伸びが活動能力の伸びを上回ることで、稼働率が上昇している。
- 製造業では、生産能力が低下し続け、稼働率を押し上げる方向に作用している。
- WS法による第3次産業活動能力・稼働率指数は年単位指数の推移や製造業との比較といった面では、一定の説得力を持った試算結果になっているとはいえる。
- しかしながら、月次ベースの指数の動きをみると、ほとんど100近辺で変動せず、活動能力の変更が迅速に行われ過ぎているという印象を受けることや、業種指数の動きをみると、稼働状況の実態(実感)を示していないと思われる業種も存在していること等から、今回のWS法による稼働率把握の試みは、試算の域を出なかったと評価している。
詳細な内容につきましては上記スライドショーを御覧いただくか、
こちらの本体資料ダウンロード用ファイル(PDF版)![]() を御覧下さい。
を御覧下さい。
また、今回は補足資料もございますので、
こちらの補足資料ダウンロード用ファイル(PDF版)![]() もあわせて御覧下さい。
もあわせて御覧下さい。