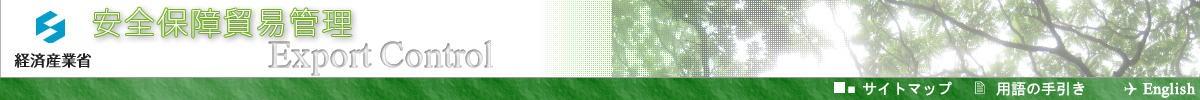ホーム>Q&A>2.素材
(化学品・金属・複合素材・高分子等) (別表第1の2項、3項(1)、4項、5項等)
2.素材 (化学品・金属・複合素材・高分子等) (別表第1の2項、3項(1)、4項、5項等)
|
▼Q1:質問 2013/2/8 ジルコニウム被覆管の製造用材料となる素管形状のジルコニウム(いわゆる「ジルコニウム素管」)は、輸出令別表第1の2の項(2)には該当せず、同2の項(26)に該当すると解釈してよいのですか。 |
|
▲A1:回答 輸出令別表第1の2の項(2)には、その外観及び機質その他の諸要素から、原子炉の部分品として使用されるものであることが客観的に明らかであると認められるものが該当します。 外径、肉厚及び水素化物方向性係数等が被覆管とは異なる「ジルコニウム素管」は、そのまま、ないしはせいぜい若干の手を加えるだけで、原子炉の部分品として使用されるものであることが客観的に明らかであるとは認められないので、同2の項(26)に該当します。 |
|
▼Q2:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の2項(17)に「ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて」とありますが、ガス遠心分離機のロータに用いられなければ(使用されなければ)、該当しないと解釈してよいのですか。 |
|
▲A2:回答 「ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料」の解釈は、「ガス遠心分離機のロータに用いることができる構造材料」を言いますので、当該貨物が実際にガス遠心分離機のロータに用いられなくても(使用されなくても)、貨物等省令第1条第22号に掲げる規定を満たすものであれば該当します。 |
|
▼Q3:質問 2013/2/8 純チタンは輸出令別表第1に該当しますか。 |
|
▲A3:回答 純チタンであれば、少なくとも、輸出令別表第1の1項から15項までには該当しません。 |
|
▼Q4:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の3項(1)に「軍用の化学製剤の原料となる物質又 は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの」とありますが、軍用の化学製剤の製造等に用いられなければ(使用されなければ)、該当しないと解釈してよいのですか。 |
|
▲A4:回答 当該貨物が実際に軍用の化学製剤の製造等に用いられなくても(使用されなくても)、貨物等省令第2条第1項に掲げる規定を満たすものであれば該当します。 |
|
▼Q5:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の3項(1)に該当する貨物で、貨物等省令第2条第1項第1号から第3号の規定に「いずれかの物質の含有量が 全重量の30パーセントを超えるもの」とありますが、これは含有量が全重量のちょうど30パーセントであれば該当しないと解釈してよいのですか。 |
|
▲A5:回答 そのように理解して結構です。 |
|
▼Q6:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の2項、3項(1)又は4項に該当する貨物を外国へ極少量 (例えば10g程度)持ち出そうと考えておりますが、この場合、輸出許可申請は不要と考えてよいのですか。 |
|
▲A6:回答 輸出令別表第1の2項、3項(1)又は4項に該当する貨物につきましては、たとえ極少量であっても、日本から海外へ持ち出す際には輸出許可申請が必要となります。なお、5項から13項又は15項の貨物につきましては、仕向国及び貨物の金額に応じて、少額特例の制度が適用できますので、御確認下さい(輸出令第4条参照)。 |
|
▼Q7:質問 2013/2/8 マイナスイオン効果のある日用品の製造に使用するパウダーを輸出しようとしたところ、 その中にトリウムが含まれていることが分かりました。 分析したところ、非常に微量でしたが、輸出許可は必要ですか。 |
|
▲A7:回答 ウラン、トリウム、プルトニウムやその化合物は、少量であっても輸出許可申請が必要になります。(貨物等省令第1条第1号参照) |
|
▼Q8:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の4の項(25)及び貨物等省令第3条第26号に規定する材料に関する解釈規定に関し、「民生用の電子機器」、「不要な電磁波」、「型抜きしたもの」はそれぞれ具体的にどのようなものを指すのでしょうか。 |
|
▲A8:回答 「民生用の電子機器」とは、携帯電話、パソコン、ゲーム機、音楽プレーヤー、家電製品や、電線、ケーブル等を、「不要な電磁波」とは、いわゆる電磁波ノイズと呼ばれるもので、民生用の電子機器の本来の用途・目的とは無関係に発生し、雑音や誤作動等の原因となるものを、「型抜きしたもの」とは、民生用の電子機器の回路基板や筐体等の形状に合わせて型抜き・切断したもの(円形、楕円形、四角形のような基本的形状を含む)をそれぞれ指します。 |
|
▼Q9:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の5の項の(18)及び貨物等省令第4条第2号に規定する繊維を使用した成型品についての解釈規定により、航空機用のものや船舶用のものについては規制対象が「半製品」に限定されていますが、これはどういったものを指すのでしょうか。 |
|
▲A9:回答 「半製品」は、今後まだ加工される予定や可能性のある貨物を指し示しています(従前より貨物等省令でも用いている用語です。)。今後更に加工を施すことのない「最終製品」は、貨物等省令第4条第2号の規制の対象からは外れています。なお、当該成型品を用いて製造された最終製品については、当該最終製品が、輸出令別表第1の5の項の(18)及び貨物等省令第4条第2号以外に掲げる貨物に該当するか否かについて判定を行う必要があります。 |
|
▼Q10:質問 (化学物質の部分品規定の適用) 2013/2/8 輸出貿易管理令の運用についての部分品規定の改正の背景・意図はどのようなものでしょうか。 |
|
▲A10:回答 輸出貿易管理令の運用についての1-1(7)(イ)の(注1)に記載されているように、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のうち、化学物質であって、他の貨物と混合されている状態のものが、「他の貨物の部分をなしている」に当たるかどうかについて従来の記述では不明確であったため、今回の改正で、化学物質が混合されている状態が、「他の貨物の部分をなしている」に当たることを明示しました。 |
| ▲このページの先頭へ |
|
▼Q11:質問 2013/2/8 潤滑油に酸化防止剤として輸出令別第1の1の項(4)に該当するジフェニルアミンが混合されています。この場合は「他の貨物の部分をなしているもの」として、非該当と扱ってよいのでしょうか。 |
|
▲A11:回答 ジフェニルアミンが、潤滑油の主要な要素となっていない場合、又は潤滑油から分離しがたく、潤滑油がその状態でジフェニルアミンの用途である火薬や爆薬の安定剤等に用いることができない場合は、非該当と扱って構いません。 通常は、酸化防止剤として潤滑油に含有しているジフェニルアミンはごく少量であるため、該当とはならないと推測されます。 <※「他の貨物の部分をなしているもの」の許可要否判断フロー図 |
|
▼Q12:質問 2013/2/8 工作機械の油圧ユニットやシリンダーには作動油、グリース等が混入されています。 作動油を抜き取らずに工作機械を輸出する場合であって、作動油に輸出令別第1の1の項(4)に該当するジフェニルアミンが混合されている場合は、部分品規定は適用できるのでしょうか。 |
|
▲A12:回答 ジフェニルアミンの混合された作動油は、通常は、該当とはならないと推測されます(※前のQ&Aをご参照)が、仮に該当となっている場合には、1-1(7)(イ)の(注1)に記載されているように、その作動油が工作機械の機能の一部を担っており、正当に組み込まれた状態であると判断されるため、部分品規定が適用できます。なお、当然ながら、工作機械自体の該非判定は別途適切に行う必要があります。 |
|
▼Q13:質問 2013/2/8 積層セラミックコンデンサの電極の材料として輸出令別表第1の2の項(9)に該当するニッケルの粉が混合されているペーストがあります。この場合は非該当と扱ってよいのでしょうか。 |
|
▲A13:回答 ニッケル粉がペーストの主要な要素となっていない場合は非該当と扱って構いません。ニッケル粉の価格がペーストの価格の10%を超えるため、主要な要素となっていないとは判断できない場合であっても、ニッケル粉がペーストから分離しがたく、ペーストがその状態で、該当品としての基準を満たす微粒高純度のニッケル粉の用途に用いることができない場合は、非該当と扱って構いません。 通常、ニッケル粉を含むペーストはニッケル粉が40%~50%、他の金属とともに溶媒と混合されており、ペーストからニッケル粉を分離することは困難であり、かつ、ペーストは微粒高純度のニッケル粉の用途であるガス拡散法によるウラン濃縮の隔膜等に用いることができないため、該当とはならないと推測されます。 <※「他の貨物の部分をなしているもの」の許可要否判断フロー図 |
|
▼Q14:質問 2013/2/8 4の項(6)に該当する推進薬又はその原料となる物質については、輸出貿易管理令の運用についての輸出令別表第1の解釈において、「貨物等省令第3条第7号に該当するものが、当該他の貨物に混合されている場合」は、部分品規定の適用はないと判断すべきでしょうか。 |
|
▲A14:回答 そのとおりです。 |
|
▼Q15:質問 2013/2/8 輸出しようとする貨物に当該化学物質がどれだけ含まれているか分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。 |
|
▲A15:回答 該非判定書の確認は、通常の商習慣においてやりとりされる情報(SDSやカタログ等)に基づいて実施していただくことになります。当該貨物に含まれるSDS等に記載のない成分が1の項(3)、(13)、2の項(3)、若しくは4の項(6)のいずれにも該当せず、また、混合先の他の貨物の価格の10%を超えない場合は該当とはなりません。 しかし、この条件に当てはまらないことが懸念される場合は、当該成分について製造者等に問い合わせるなどして、情報を入手してください。なお、当該貨物中に営業上の秘密による非開示成分を含む場合などの、輸出者自身では確認ができない場合は、製造者等へ正しく該非判定が行われているかを聴取し、その情報を元に確認するようにしてください。該非判定書の誤りが原因で違反となった場合は、該非判定書を作成した製造者等にも輸出貿易管理令第十一条の規定に基づき、関係人として説明を求めたり再発防止を求めたりすることがあります。 |
|
▼Q16:質問 2013/2/8 当該化学物質が、非意図的に副生成物や不純物として含まれる場合は、どう判断すればよいのでしょうか。 |
|
▲A16:回答 副生成物や不純物だからということで規制の対象とならないわけではありませんが、1-1(7)(イ)の①に該当しない場合で、混合先の貨物の主要な要素となっていないと判断されるものは非該当と扱って構いません。それ以外のケースについては個別に御相談下さい。 |
|
▼Q17:質問 2013/2/8 当該化学物質が、他の貨物と「分離しがたい」かどうかを、どのように判断するべきでしょうか。 |
|
▲A17:回答 当該化学物質の価額が混合先の他の貨物の価格の10%を超えない場合は、この判断は不要ですが、10%を超え、ご質問に係る規定を利用する場合は、社内の専門家の知見、メーカーから得られる情報や、当該化学物質の製造業界等における一般的な知識・意見等を活用して判断していただくことになります。その際の判断の理由・根拠は、記録、保管しておくことをお薦めします。 |
|
▼Q18:質問 2013/2/8 部分品規定が適用できない場合を規定している1-1(7)(イ)の②で、「当該他の貨物がその状態で当該貨物の用途に用いることができる場合」の判断は、どのように行うのでしょうか。 |
|
▲A18:回答 1-1(7)(イ)の②の趣旨は、当該化学物質が混合された状態のものであっても、輸出令別1に掲げる貨物と同等の機能・性質を発揮する場合には、規制対象貨物として使用することが可能と考えられるため、部分品規定の適用を不可とするものです。 社内の専門家の知見、メーカーから得られる情報や、当該化学物質の製造業界等における一般的な知識・意見等を活用して、「当該貨物の用途に用いることができる」かどうかを判断していただくことになります。 |
|
▼Q19:質問 2013/2/8 炭素繊維(本省受付分)の申請において、最終需要者の事業実態等について問われることがありますが、どのような資料を提出すればよろしいですか。 |
|
▲A19:回答 炭素繊維(本省受付分)については、輸出先における貨物管理の徹底の重要性から、申請内容明細書「6.需要の概要」の別紙として、<申請内容明細書「6.需要の概要」記載事項>を内容とする書類を御提出下さい(「提出書類通達」別記1(ク)を参照ください)。 |
|
▼Q20:質問 2013/2/8 別記2の4.の追加的誓約事項④の人造黒鉛を輸出する場合で、「以下の追加的誓約事項を追加することができます。」とありますが、これは、輸出者の判断で、誓約事項を追加しないことも可能でしょうか。 |
|
▲A20:回答 人造黒鉛の取引は通常、(1)人造黒鉛を部材として使用し完全に消費される場合と、(2)人造黒鉛を例えば放電加工用の部材に加工し、それを再度、新たな最終需要者に販売する場合の2つのケースが考えられます。 (1)のケースでは、追加的誓約事項を追加する必要はありませんが、(2)のケースでは、追加的誓約事項を追加しない場合、加工後の部材がいかなるサイズの場合であっても、再販売又は再輸出を行う際に事前同意を得なければならなくなります。 従って、様式2に追加的誓約事項を付すことにより、再販売又は再輸出の際の事前同意の対象が④に示す大きさに該当する場合のみとなり、非該当サイズ(④に示す追加的誓約事項の大きさ未満のもの)の部材の場合は事前同意が不要となります。 |
|
▼Q21:質問 2013/2/8 海外にジメチルアミンを輸出することになり、ジメチルアミンの輸出許可証を取得しましたが、SDS(安全データシート)を要求されました。SDSを提供することは、外為令別表で規制されている役務(技術)の提供になるでしょうか。 |
|
▲A21:回答 SDS(安全データシート)は、化学製品を取り扱う人にその製品の危険・有害性を知らせて、人の健康・安全を保つために提供されるものです。同シートには、当該化学物質等の成分情報や有害性情報、取扱上注意すべき事項等が記載されていますが、いずれも外為令別表で規定している技術に該当するものではありません。 したがって、ご質問のケースはもちろんのこと、製品安全データシートを単独で提供する場合であっても、役務取引許可を取得する必要はありません。 |
|
▼Q22:質問 2013/2/8 廃水中に含まれるフッ化水素を処理するために、フッ化水素の量に対応した水酸化ナトリウム水溶液で中和し、さらに消石灰で沈殿させますが、その過程でフッ化ナトリウムができます。こうした処理技術を海外へ提供する場合は、役務取引許可を申請することが必要でしょうか。 |
|
▲A22:回答 ご質問の内容にある廃水中のフッ化水素を除去するために、中和反応でフッ化ナトリウムを生成させる方法は、フッ化ナトリウムの製造技術には該当しないので、役務取引許可申請をする必要はありません。 |
|
▼Q23:質問 2013/2/8 物質の使用の技術に関して、以下のような場合にどのように考えればよいでしょうか。 ①径の平均値が2~3μmで純度が99%以上のニッケルの粉(輸出令別表第1の2の項記載の貨物に該当)を使用して、半導体工場の床の塗装用塗料(塗料自身は非規制のもののとき)を作る場合 ②液晶テレビの画面の陰影をはっきりさせるために、液晶材料(非規制のもののとき)に重水素化合物(輸出令別表第1の2の項の貨物に該当)を使用する場合 ③ヒドラジン(輸出令別表第1の4の項記載の貨物に該当)を、医薬品や農薬(これら医薬品・農薬が非規制のもののとき)の製造に使用する場合 ④比弾性率が12,700,000m、比強度が235,000mを超えるアラミド繊維(輸出令別表第1の5の項記載の貨物に該当)を防火服の製造に使用する場合(防火服が非規制のもののとき) ⑤比弾性率が2,540,000mを超え、不活性の環境における融点が1,649度を超えるタングステン繊維(輸出令別表第1の5の項記載の貨物に該当)使用の静電気防止作業服を作る場合(作業服が非規制のもののとき) |
|
▲A23:回答 これらのケースを見ると、どれも規制される物質を、非規制の民生品に使用し分離ができない状態になるもののように考えられます。 その際に、例えば調合率などの情報を提供する場合、これが規制物質の使用の技術なのか、非規制の民生品の設計・製造技術なのかという議論などが生じると考えられますが、この様な問題については、まず、当該調合率が、規制物質からの要求事項なのか、それとも、非規制の民生品の設計・製造側からの要求事項なのかということを考えてみてください。 そして、前者であれば、該当の使用の技術にあたると考えられる(ただし、公知情報(SDSなど)、貨物(一部を除く)の輸出(E/L取得)に付随して提供される必要最小限の使用技術にあたるものは規制されません)、一方、後者であれば、規制物質の使用の技術とは通常は考えられないと判断することが可能と考えられます。 同様に、例えば規制される繊維の織り方について、高い曲率で折り曲げることのないように扱うことが繊維側の特性から来ているときの注意事項や衣服側から要求される編み方、形状、寸法などの要求事項があるかもしれませんが、前者と後者の扱いは調合率の例と同様と考えられるでしょう。 なお、例えば、ヒドラジンが特定のロケット燃料の取り扱い方法として特になんらかの要求事項があるような場合には、ヒドラジンの使用技術として規制対象となりうることがあります。これらは公知の技術かどうか等の観点から確認してください。 |
|
▼Q24:質問 2014/11/28
当社の製品には、潤滑油があります。この製品は、5の項(12)に規制される成分を主成分としていますが、潤滑油の用途のみで設計、製造されたものであり、電子機器の冷媒用に使用されるような実績も確認されておりません。このようなものについては、冷媒用に使用ができないものと解釈して、5の項(12)に非該当と判断してもよろしいものでしょうか。 |
|
▲A24:回答 製造時の仕様及び実際の使用実例などから、当該規制用途に使用することができないと判断される場合は、非該当と判断していただいても構いません。なお、判断の根拠となる情報については、該非判定の際の書類と一緒に書面で保存しておくなど、何らかの形で残しておかれることをお薦めします。 |
|
▼Q25:質問 2021/7/28 輸出令別表第1の3項(1)の申請において、貨物の需要者の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料(様式6)の提出が求められますが、国別の該当貨物の調達数量の欄にはどのように記載すればよいですか。
|
|
▲A25:回答 同項で求める「軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの」は、需要者における貨物管理の徹底の重要性から、様式6の提出を求めています。申請者は、需要者が調達した正しい数量を確認し、様式6に記載して下さい。 また、日本からの調達実績があり、申請者以外からも調達を行っている場合には、申請者と申請者以外の数量をわけて記載して下さい。なお、審査に必要と判断された場合には、調達数量について、申請書の許可数量、実際に出荷した数量、需要者の在庫数量の関係についての詳細を求める場合がありますので、予めこれらの情報を入手しておくよう努めて下さい。 |
|
▼Q26:質問 2021/7/28 (様式6)の備考欄には何を記載するのでしょうか。
|
|
▲A26:回答 Q25で説明しているとおり、当該貨物については、需要者における貨物管理の徹底が求められています。申請者は「該当貨物を使用して製造した最終製品の生産量」、「その際の該当貨物の使用量」が、前年度に比べ大きく増減した場合には、その理由について、詳細に聞き取り、備考欄に記載して下さい。 また、調達実績数に申請者が当該需要者向けに輸出した数量が含まれている場合は、該当年の備考欄には、調達量に紐付く申請者が過去取得した輸出許可番号を記載してください。許可された量と実際の輸出量に齟齬がある場合はその理由も記載してください。 なお、備考欄に書き切れない場合は、用紙の空いた部分や別紙に記載しても構いません。 |
|
▼Q27:質問 2025/4/7 ①中国向けに200kgの化学品の輸出契約を締結しました。この200㎏の化学品を20kgずつ10回に分けて輸出する場合、保有している特別一般包括許可証を使用して輸出することはできますか。
|
|
▲A26:回答 特別一般包括許可を使用可能な20kg以下の化学品の輸出とは、化学品の性能評価のための調達等、元々20㎏以下でのスポット的な契約を想定しています。 このため、20㎏以下に分割して輸出する場合でも元々の契約数量が20㎏超の場合や、20㎏以下の契約であっても継続的に契約が行われる場合は、個別許可申請を行ってください。 |
| ▲このページの先頭へ |