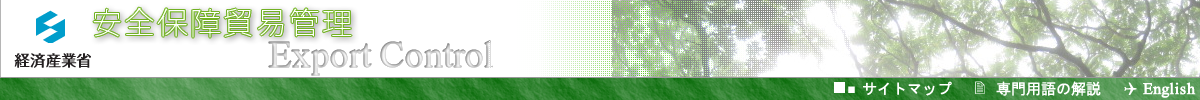
3.工作機械 (別表第1の2項(12)1、6項(2)等(ベアリング含む))
|
▼Q1:質問 2013/2/8 移転先予定の工場敷地内の別の建物や別のラインにおいて、軍用品等を製造している場合、どのようにしたらよいでしょうか。 |
|
▲A1:回答 当省に御相談ください。 |
|
▼Q2:質問 2013/2/8 当社マシニングセンタの中には、輪郭制御をすることができる軸数が5(直線軸3+回転軸2)の仕様の機械があり、それには市販されている数値制御装置を搭載しています。数値制御装置メーカーの仕様としては輪郭制御することができる軸数は最大で同時4軸ですが、この場合の輸出令別表第1の2の項の判定としては、該当となるのでしょうか。 |
|
▲A2:回答 基本的に機械の軸数と制御装置の同時制御軸数とは切り離して考えます。従って、たとえ制御装置として最大同時制御軸数が4であっても、機械として輪郭制御をすることが出来る回転軸数が2以上あるいは軸数が5以上ならば、輸出令別表第1の2の項、貨物等省令第1条第十四号ロ(ニ)あるいは(三)において、該当と判定します。 |
|
▼Q3:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の2項(12)に該当する工作機械の輸出を予定しています。2項(12)では「核兵器の開発又は製造に用いられる~」とありますが、本工作機械は民生用途に使用します。この場合、輸出許可は不要と考えてよいのですか。 |
|
▲A3:回答 貨物等省令第1条第14号の規定に該当する仕様の場合は、貨物の用途を問わず輸出許可が必要となります。 |
|
▼Q4:質問 2013/2/8 該当する工作機械が設置される同一敷地内について、同居企業の有無を確認することとなっていますが、同居企業とはどの範囲までをいうのでしょうか。 |
|
▲A4:回答 一つの事業所の敷地が公道によって複数に分かれている場合であっても、事業として一体で運営されている場合は、同一の敷地とみなします。また、工業地区内で住所表記の細分がない場合においては(例えば、A市○○工業地区(Industrial Zone/Area)としか住所表記がない場合)、工業地区内すべてを同一の敷地とはみなさず、工業地区内にある最終需要者の占有する区画のみを最終需要者の同一の敷地と考えてください。 |
|
▼Q5:質問 2013/2/8 中古の工作機械を輸出したいので位置決め精度を測定し輸出令別表第1の2項(12)と6項(2)に該当するか否かを判定したいのですが、当社では測定できません。位置決め精度の測定を行ってくれる機関等はありますか。 |
|
▲A5:回答 工作機械メーカー等が工作機械の位置決め精度の測定を行っています。 |
|
▼Q6:質問 2013/2/8 2011年7月1日から施行される改正省令では、6項の(1)の軸受において貨物等省令第5条 一のロが、削除されますが、その時軸受の部分品である「玉」は、 同 イで規定されるモネル製又はベリリウム製以外の材料でできた転動体(玉)は、6の項では規制されなくなると解釈してよろしいでしょうか。 |
|
▲A6:回答 モネル製又はベリリウム製以外の材料でできた転動体(玉)は規制されません。 |
|
▼Q7:質問 2013/2/8 ,2025/02/19 貨物等省令第5条 一のイで規定される「モネル製又はベリリウム製」とは、ベリリウム合金など、ピュアな材料でないものも含まれるのでしょうか。 |
|
▲A7:回答 モネルはSpecial Metals Corporationの商標であり、いわゆる同社がモネルとしているものは対象となります。一方、ベリリウム合金は含みません。 |
|
▼Q8:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の2の項(12)に該当する工作機械Aについて、輸出許可を取得し、輸出令別表第3の地域を除く地域にある日系のメーカーXに納品しました。納品から1年後に故障し、修理のため、工作機械Aを日本に戻したのですが、現在も故障の原因が不明のため、急遽、工作機械Aと同一型式で仕様の変更のない工作機械を交換として、メーカーXに輸出しようと思うのですが、この場合、輸出許可は再度、必要でしょうか。 |
|
▲A8:回答 この場合、輸出許可は不要です。輸出令第4条第1項第二号ホに基づく、無償告示第一号1に規定する「修理」には、1対1の交換を含むとされています(運用通達4-1-2(5)(イ)参照。)。故障した工作機械Aと同一型式で、仕様の変更のない工作機械(補正機能を有する工作機械の場合は、同一の補正機能を搭載していること)との交換であれば、輸出令第4条第1項第二号ホの規定により、輸出許可を再度取得する必要はありません。 |
|
▼Q9:質問 2019/10/25 2012年3月31日以前に取得した需要者等誓約書(LETTER OF ASSURANCE (LOA))に基づき管理を行っている貨物の再移転について、どのような場合に事前相談が必要でしょうか。 |
|
▲A9:回答 原許可時において許可条件が付されていない貨物、及び原許可時において許可条件が付されていたものの既に履行済みの貨物については、貨物の再移転によって設置場所の敷地・住所が変更される場合に事前相談が必要です。敷地・住所に変更のない再移転、例えば建屋間や建屋内のフロア間の再移転については事前相談の対象にはなりません。
なお、原許可時において許可条件が付され、現在も条件を履行中の貨物については、同一建屋内におけるフロア内の再移転については事前相談の対象にはなりませんが、建屋やフロアが変更される再移転については事前相談が必要です。 一方、2009年11月20日から2012年3月31日までの間に輸出許可を取得して輸出した貨物であって、許可申請時に以下の2点の資料を提出していた貨物については、同一国内の再移転であれば事前相談を要しません。 ①移設検知装置に係る確認書
②「輸出先の国内における再移転であって所有権・使用権の移転を伴わない再移転の場合に限り、貨物の輸出者又は技術の提供者の事前同意を得る手続を行う対象としない」旨の誓約書
なお、2012年4月1日以降、手続を経てLOAを現行の最終用途誓約書(END-USE
CERTIFICATE (EUC))に変更した貨物については、同一国内の再移転であれば事前相談を要しません。 再移転(所有権・使用権の変更がない、仕向地内での貨物の移転)の事前相談の範囲について(工作機械) |
|
▼Q10:質問 2013/2/8 貨物の表面加工技術は、許可の対象となりますか。 |
|
▲A10:回答 輸出貿易管理令別表第1に示される範囲の貨物の製造に関する技術の提供があれば、許可が必要となることがあります。また、材料加工に関する外為令別表の6の項(1)~(4)などに関する技術についても、許可が必要となる場合があります。 |
|
▼Q11:質問 2013/2/8 輸出する工作機械を操作するためのNCプログラムを輸出しますが、現地ではその工作機械を使ってロボットを製造する計画です。この場合、工作機械の使用技術とロボットの製造技術との2つの役務取引許可が必要となりますか。 |
|
▲A11:回答 外為令別表に該当するNCプログラムであれば、許可が必要です。また、現地でロボットを製造するために、ロボットの製造技術を提供する場合には、役務許可が必要な場合があります。 |
|
▼Q12:質問 <NCプログラムに関する事前同意について>
2013/2/8 工作機械のNCプログラムに関する誓約書の事前同意の扱いはどのようにしたらよいでしょうか。 |
|
▲A12:回答 NCプログラムの再提供の事前同意については、工作機械の誓約書の事前同意と同様の扱いとなりますので、同様の書類を提出ください。 |
|
▼Q13:質問 2015/1/22 ,2015/10/29 輸出令別表第1第2項(12)1に該当する数値制御工作機械について、運用通達に定める「ろ地域」向けに、ストック販売(需要者未定)を実施することは可能でしょうか。 条件等がありましたら、教えてください。 |
|
▲A13:回答 ストック販売を実施することはできます。ただし、以下の条件全てを満たす場合で、かつ、審査を経て許可を得ることが必要となります。 <条件> (1)仕向地は、ろ地域 (ただし、輸出令【別表3の2】、【別表4】を除く)であること。 (2)輸入者(保管者)は、輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者(以下、「CP等保有者」という。)の「子会社等」であること。若しくは、「CP等保有者」または「CP等保有者の子会社等」と「代理店契約」を締結している「代理店」であること。 (3)6ヶ月毎のストック状況報告を履行すること。 (4)再販売、再輸出に関する事前同意申請を履行すること。 (5)適正なストック数量であること。 (6)移設検知装置が設置されており、解除パスワードが製造者により適切に管理・運用されていること。 (7)輸入者(保管者)によりストック機が厳格に管理されること。
ストック機を販売予定会社等に事前に貸出しする場合や、保管者の意図によらず、現地の国内法令等に基づき、強制的にストック機が移転させられる場合等には、保管者の厳格な管理が確保されないことから「再販売」と同等とみなし、事前相談の対象となります。当該事前相談手続きを行わずに設置・保管場所から移転した場合には、許可条件等の違反に該当しますので御注意ください。
なお、委託販売契約※に基づくストック機の取り扱いについては、以下のいずれかの手続きをお願いいたします。
① 委託販売契約の期間満了後は、許可条件に従い、積み戻し期限内に日本に積み戻す。ただし、当該ストック機の設置・保管場所に変更が生じない場合に限り、委託販売契約の期間延長を認めることがあります。
② 委託販売契約の期間満了に伴い、再販売に係る事前相談手続きを行い、貨物の所有権を受託者(保管者)に移転する。 ※委託販売契約とは、ある一定期間、輸出者が貨物の所有権を保有したまま、受託者(保管者)に現地での貨物の販売業務を委託する契約をいう。 |
|
▼Q14:質問 2015/1/22 ストック販売に係る申請において、必要となる資料等について教えてください。 |
|
▲A14:回答 必要となる資料は、通常の申請に係るものに加え、以下に掲げる資料を提出してください。 <ストック販売に係る申請について、特に必要となる資料等> Q13.(2)に係る資料について【輸入者-申請者または、輸出者との関係】 ①「子会社等」においては、「CP等保有者」との資本関係等が分かる資料。 ②「代理店」においては、「CP等保有者」または「CP等保有者の子会社等」のいずれかとストック販売にかかる「代理店契約」を締結していることを証明する書類。 Q13.(5)に係る資料について【適正なストック数量】 ストック数量の妥当性に関する以下の資料。 ①輸入者(保管者)の許可実績の有無、ストック機を既に保有する場合はその数量。 ②ストック機の販売計画書(販売計画、販売先の商圏・対象業種等)。 Q13.(6)に係る資料について【移設検知装置の設置】 製造者による移設検知装置のパスワード管理・運用が適切であることを示す書類(代表権者の記名押印入りの書類)。 Q13.(7)に係る資料について【厳格な管理】 ストック機の設置・保管場所の概要(ショールーム・倉庫等の見取り図・写真等)及び管理体制(施錠状況、警備監視体制等)。 その他、必要に応じて資料を追加する場合があります。 |
|
▼Q15:質問 2019/10/25 輸出令別表第1第2項(12)1に該当する数値制御工作機械(以下、「2項該当工作機械」)について、運用通達に定める「ろ地域」(以下、「ろ地域」)向け展示会に出展するに当たって、輸出許可申請上の留意点を教えてください。 |
|
▲A15:回答
仕向地は、ろ地域(ただし、輸出令別表3の2及び別表4を除く)であること。
展示会は、不特定多数の顧客に対しての、商品展示等する場であることから、これまでも、「需要者が未確定」として申請頂いており、今後も、同様の考え方を原則とした上で、 ①移設検知装置搭載機であること
②(移設検知装置の)パスワード管理・運用が適正であること ③誓約書は、提出書類通達の様式3(需要者未確定) 等の条件を準用して頂くことになります。
なお、ろ地域の展示会への出展後に子会社・孫会社等(のショールーム)でストックする旨の許可をあらかじめ取得していた場合であっても、ストックした子会社・孫会社等から更に再販売等を行う際には、事前同意手続が必要となりますので、留意して下さい。(Q13も参照下さい。) |
|
▼Q16:質問 2014/8/1 「移設検知装置が未搭載の工作機械(以下、移設検知装置未搭載機)」の場合は、2項該当工作機械について、「ろ地域」の展示会に出展出来ないのでしょうか。 |
|
▲A16:回答 移設検知装置未搭載機の場合であっても、展示会出展は可能ですが、その場合、申請者が以下の要件(①~②)に関して確約する旨、書類の提出が必要となります。 <様式自由:但し、社名・申請代表者名を記名の上、押印(代表者印)したものを提出ください。> 要件① 所有権を日本から移転しない。 要件② 展示会終了後、必ず、日本に積み戻す。(日本に積み戻し後、積み戻した旨、経済産業省への報告は別途求めます。) また、出展予定の展示会名、運営主体(主催者)、開催時期、開催場所、出展者等に関する資料を添付してください。ここでいう展示会とは、以下の要件(①~③)全てを同時に満たすものを指します。なお、「内覧会<*>」は展示会に当たりませんので、注意してください。 要件① 展示会運営主体(主催者)が、第三者 (例:業界団体等) 要件② 開催場所が公共施設 (例:コンベンションセンター等) 要件③ 出展者数が、多数 <*>「内覧会」:自社や自社グループなどが主催するもの等 ご不明な場合には、安全保障貿易審査課に、個別にご相談下さい。 |
|
▼Q17:質問 2014/8/1 「移設検知装置未搭載機」の場合、2項該当工作機械について、「ろ地域」の複数の展示会に出展することは可能でしょうか。 |
|
▲A17:回答 原則、一展示会、一申請とします。 但し、移行期間中(下記参照)は出展は可能ですが、輸出許可申請に当たっては、以下に注意してください。 「ろ地域」の複数の展示会それぞれの主催者、開催時期等の説明資料を、必ず申請の際、提出ください。 運用開始から1年間(以下、「移行期間」)は、「一つの申請において、複数の展示会への出展」に係る申請は可能としますが、移行期間終了後は、「展示会毎」の申請のみとします。(移行期間終了後は、複数出展は認めません。) 当該移行期間は、2014年8月1日から2015年7月31日まで。 ご不明な場合には、安全保障貿易審査課に、個別にご相談下さい。 |
|
▼Q18:質問 2014/10/14 輸出令別表第1の4の項(5の2)、貨物等省令第3条第六号の二にて規制対象となっているラジアル玉軸受は、単体(1個)で使用するだけでなく、同一軸受を複数(例えば2個)組み合わせるなど、様々な形態で使用することがあります。そのため単体の軸受と組み合わせた軸受ではその幅寸法が変わりますが、該非判定の際は、製造段階での1個単位の寸法で判断すべきか、または使用時の状態の寸法で判断すべきか、どちらでしょうか。
|
|
▲A18:回答 ここで規制されるラジアル玉軸受は、日本工業規格B1514-1号で定める精度が二級以上のもののうち、貨物等省令第3条第六号の二のイからハに規定されている寸法の全てに該当するものです。該非判定の際は、製造時の単体(1個)の精度の等級及び寸法によってご判断いただければと思います。
|
| ▲このページの先頭へ |