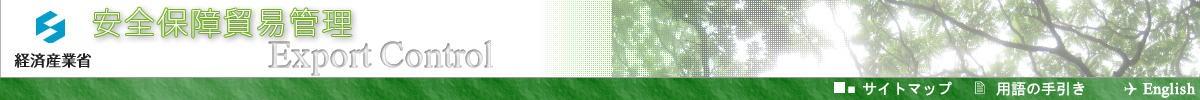
ホーム>Q&A>仲介貿易取引規制について
仲介貿易取引規制について
|
▼Q1:質問 仲介貿易取引規制の対象となる取引とは、何を指しますか。 |
| ▲A1:回答 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引です(外国為替令第17条第3項参照 (e-govリンク))。 |
|
▼Q2:質問 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与に関する取引における「貨物」とは何を指しますか。 |
| ▲A2:回答 輸出貿易管理令別表第1の1の項から16の項までのいずれかに該当するものは、全てこの「貨物」にあたることになります。したがって、仲介貿易取引規制の適用のないものは、食料品や木材などに限定されます。 |
|
▼Q3:質問 売買、貸借又は贈与の当時いまだ製造されていない「貨物」は、対象となりますか。 |
| ▲A3:回答 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与に関する取引である以上、取引客体である貨物が、売買、貸借又は贈与の当時いまだ製造されていないとしても、対象となります。 |
|
▼Q4:質問 外国にある売主、貸主又は贈主以外の他者が所有している「貨物」は、対象となりますか。 |
| ▲A4:回答 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与に関する取引である以上、取引客体である貨物が、外国にある売主、貸主又は贈主の所有に属していない場合においても、対象となります。 |
|
▼Q5:質問 「売買、貸借又は贈与に関する取引」とは、何を指しますか。 |
| ▲A5:回答 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与であって、居住者が貨物の「売り」、「貸し」又は「贈与」契約と「買い」、「借り」又は「受贈」契約の双方の当事者となる場合を指します。 |
|
▼Q6:質問 「売り」、「貸し」又は「贈与」契約とは、何を意味しますか。 |
| ▲A6:回答 居住者が、非居住者に対して貨物を売る契約、貸す契約又は贈与する契約を意味します。 |
|
▼Q7:質問 「買い」、「借り」又は「受贈」契約とは、何を意味しますか。 |
| ▲A7:回答 居住者が、非居住者から貨物を買う契約、借りる契約又は贈与する契約を意味します。 |
|
▼Q8:質問 外国相互間での技術の提供を仲介することは 、仲介貿易取引許可の対象となりますか。 |
| ▲A8:回答 法第25条第1項の技術提供の許可の対象となることがあります。 |
|
▼Q9:質問 外国相互間における貨物の輸送を行うことは、対象となりますか。 |
| ▲A9:回答 物流行為のみに携わる行為は、対象とはなりません。 |
|
▼Q10:質問 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与の予約を行うことは対象となりますか。 |
| ▲A10:回答 売買、貸借又は贈与の予約は対象とはなりません。 |
| ▲このページの先頭へ |
|
▼Q11:質問 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与の取次ぎを行うことは対象となりますか。 |
| ▲A11:回答 対象とはなりません。 |
|
▼Q12:質問 外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借又は贈与に関する取引について、どのような場合に仲介貿易取引規制の対象とされるのですか。 |
| ▲A12:回答 ①輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)に該当する貨物について、②輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項に該当する貨物であって、船積地域と仕向地のいずれもが輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域以外であって、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、仲介貿易取引おそれ省令で定める要件に該当し、または、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合について、仲介貿易取引規制の対象となります。 |
|
▼Q13:質問 船積地域又は、仕向地のいずれかが輸出貿易令別表第3の地域である場合にも、許可を受けなければなりませんか。 |
| ▲A13:回答 輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物については、船積地域又は、仕向地の制限なく許可を受ける必要があります。 一方、輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項に該当する貨物については、許可を受けなければならない場合がありますが、これは船積地域と仕向地のいずれもが、輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域以外である場合であって、核兵器等の 開発等のために用いられるおそれがある場合又は経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合に限定されます。 |
|
▼Q14:質問 規制の対象となる貨物(武器)で、船積地域がオランダ、仕向地がアメリカとなる仲介貿易は許可が必要となりますか。 |
| ▲A14:回答 船積地域及び仕向地が輸出令別表第3の地域であっても、貨物が武器であるため、許可が必要となります。 |
|
▼Q15:質問 規制の対象となる貨物(武器以外)で、船積地域がタイ、仕向地が英国となる仲介貿易は許可が必要となりますか。 |
| ▲A15:回答 船積地域は輸出令別表第3の地域を除く地域ですが、仕向地が輸出令別表第3の地域となるので 、許可を得る必要はありません。 |
|
▼Q16:質問 規制の対象となる貨物(武器以外)で、船積地域がアメリカ、仕向地がオランダとなる仲介貿易は許可が必要となりますか。 |
| ▲A16:回答 船積地域及び仕向地がともに輸出令別表第3の地域となるので 、許可を得る必要はありません。 |
|
▼Q17:質問 規制の対象となる貨物(武器以外)で、船積地域がタイ、仕向地が中国となる仲介貿易は許可が必要となりますか。 |
| ▲A17:回答 船積地域及び仕向地がともに輸出令別表第3の地域を除く地域となるので 、核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合又は経済産業大臣から許可申請をすべき旨通知を受けた場合には、許可が必要です。 |
|
▼Q18:質問 核兵器等の開発等のために用いられるおそれのある場合とは、どのような場合ですか。 |
| ▲A18:回答 当該取引に関して入手した文書等から、当該貨物が、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用若しくは貯蔵若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)別表(以下「別表」という。)に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は居住者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときを指します(「外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(e-govリンク)。 |
|
▼Q19:質問 「取引に関して入手した文書、図画若しくは電磁的記録」は、取引の相手方その他の者から直接入手したものに限られますか。 |
| ▲A19:回答 取引の相手方その他の者から直接入手したものの他、公開情報を含め、当該取引に関して居住者が入手したものすべてを含みます。 |
|
▼Q20:質問 「取引に関して入手した文書、図画若しくは電磁的記録」とは、どの範囲のものを指すのですか。 |
| ▲A20:回答 取引の相手方その他の者から直接入手したものの他、公開情報を含め、当該取引に関して居住者が入手したものすべてを含みます。なお、通常の商習慣の範囲内で入手したものを指しそれ以上に特定の文書等の入手を義務付けるものではありません。 |
| ▲このページの先頭へ |
|
▼Q21:質問 文書等の入手及び取引の相手方等からの連絡は、いつ時点のものを指しますか。 |
| ▲A21:回答 許可を必要とする時点以前のものを指します(「許可を必要とする時点」については、「外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について」1(3) |
|
▼Q22:質問 「外国相互間の移動」とはどういう場合を指しますか。 |
| ▲A22:回答 異なる外国の間の移動を指し、同一国内の移動は含みません。この場合、中華人民共和国、香港、マカオはそれぞれ異なる外国として扱います。 |
|
▼Q23:質問 移動の途中において、本邦で積み替えのみ行うことが予定される場合も「外国相互間」となりますか。 |
| ▲A23:回答 外国相互間の移動として扱います。この場合、積替規制も同時にかかることがあります。 |
|
▼Q24:質問 「船積地域」とはどこを指しますか。 |
| ▲A24:回答 貨物を他の外国に向けて移動させるために船舶、航空機、鉄道、車両その他の輸送手段に積み込む外国を指します。 |
|
▼Q25:質問 当初の出荷をする国から陸送され、他の国の港を経て第三国に移転される場合は、どこが船積地域となりますか。 |
| ▲A25:回答 当初の出荷する国が、船積地域となります。 |
|
▼Q26:質問 リース契約満了後に所有権を移転する場合は「売買」に該当しますか。それとも「貸借」に該当しますか。 |
| ▲A26:回答 契約の内容が、最終的に所有権の移転を予定する場合には「売買」に該当します。したがって、リース契約満了後に所有権移転を予定する契約であった場合には、「売買」に該当することになります。 |
|
▼Q27:質問 「買い」契約を締結する時点において、貨物自体が特定されていない場合にも「売買」に該当しますか。 |
| ▲A27:回答 契約時点で貨物が特定されなくてもその内容が最終的に所有権の移転を予定する場合には 、「売買」に該当します。したがって、この場合も「売買」に該当することになります。 |
|
▼Q28:質問 契約当事者以外の第三者に所有権を移転する場合も「売買」に該当しますか。 |
| ▲A28:回答 契約当事者以外の第三者に所有権を移転する場合も「売買」に該当することになります。 |
|
▼Q29:質問 契約の更改により代物弁済の契約を新たに締結する場合は「売買」、「貸借」又は「贈与」に該当しますか。 |
| ▲A29:回答 既存の契約の履行に代えて、貨物により弁済するという取引を全体的に見て、「売買」、「貸借」又は「贈与」に該当する ことになります。 |
|
▼Q30:質問 契約当事者以外の第三者が代金を支払う場合又は契約当事者以外の第三者に代金の支払いを行う場合は「売買」、「貸借」又は「贈与」に該当しますか。 |
| ▲A30:回答 「売買」、「貸借」又は「贈与」に該当します。 |
|
▼Q31:質問 売買、貸借又は贈与以外の名称の取引は「売買」、「貸借」又は「贈与」に該当しないと考えてよいですか。 |
| ▲A31:回答 実体が売買、貸借又は贈与である取引であれば、売買、貸借又は贈与にあたらないよう装ったものであっても、契約の名称や形式に関わらず、「売買」、「貸借」又は「贈与」として扱われます。 |
|
▼Q32:質問 「売買」、「貸借」又は「贈与」は、売買契約書、貸借契約書又は贈与契約書等一定の要式を備えたものに限られますか。 |
| ▲A32:回答 「売買」、「貸借」又は「贈与」は、売買契約書貸借契約書又は贈与契約書等を作成するかどうかにかかわらず、単に申込みに対して承諾の通知のみによって成立する場合、承諾の通知とともに又は、これに代えて貨物の発送や提供を行う場合等を含みます。 |
|
▼Q33:質問 「売り」契約と「買い」契約、「貸し」契約と「借り」契約若しくは「贈与」契約と「受贈」契約、又は「売り」契約と「受贈」契約、「貸し」契約と「買い若しくは受贈」契約若しくは「贈与」契約と「買い」契約はそれぞれ別個に行われるものに限りますか。 |
| ▲A33:回答 それぞれの契約は、別個のものであることを必要とせず、三者契約によるものについても含まれます。 |
|
▼Q34:質問 「売り」、「貸し」又は「贈与」契約が成立する前に、貨物が移動されていた場合も、「貨物の移動を伴う売買」、貸借又は贈与に該当しますか。 |
| ▲A34:回答 この場合には、当該貨物の移動が、特定の相手方(1社に限定されません。)に向けられた一連のものとして予定されていた場合に限り、「貨物の移動を伴う売買」、賃借又は贈与に該当します。 |
|
▼Q35:質問 「売り」、「貸し」又は「贈与」契約が成立する前に中間地点に移動しておいた貨物について、『移動を伴う貨物の売買』、賃借又は贈与に含まれるケースはどのような場合ですか。 |
| ▲A35:回答 当該貨物の移動が特定の相手方(1社に限定されない)に向ける一連のものとして予定していた場合は「移動を伴う貨物の売買」、賃借又は贈与に含まれます。また、予定されていなかった場合であっても、その後の「売り」、「貸し」又は「贈与」契約 に基づき移動が行われる場合には中間点以降の部分の移動について「移動を伴う貨物の売買」、賃借又は贈与に含まれます。 |
|
▼Q36:質問 貨物の「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」、又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」の個別契約をもつ場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A36:回答 「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」、又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」のうち後に成立する契約より前の時点となります。 |
|
▼Q37:質問 「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」、又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」のうち、一方または双方が申し込みに対して貨物の発送や提供をもって成立するものである場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A37:回答 貨物の発送や提供より前の時点となります。 |
|
▼Q38:質問 三者契約の場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A38:回答 その契約より前の時点となります。 |
|
▼Q39:質問 「売り」、「貸し」又は「贈与」契約の発注に対して成約を待たず貨物を移動する場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A39:回答 その移動させる行為を売買、貸借又は贈与契約の締結に向けた意思表示と認め(売買、貸借又は贈与契約と無関係な貨物移動である場合を除く)、その移動より前の時点となります。 |
| ▲このページの先頭へ |
|
▼Q40:質問 「売り」又は「貸し」契約に関して、売買又は賃借をすることについての合意のみの段階で貨物の移動を行い価格決定は事後に行う場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A40:回答 価格決定の時期に関係なく、売買又は賃借することについての合意より前の時点となります。 |
|
▼Q41:質問 「売り」「貸し」又は「贈与」契約が成立する前に移動しておく場合(一連のものとして予定していた場合)、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A41:回答 移動の前の時点となります。 |
|
▼Q42:質問 複数段階により売買、賃借又は贈与契約が具体化されるものである場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A42:回答 その契約により貨物の移転を行うに必要な行為をすることを具体的に可能とする段階のものをもって、時点の判断基準とします。例えば、基本契約を締結しており個別の出荷は改めて個々の注文にゆだねる場合には、その個別注文の時点がこれにあたります。 |
|
▼Q43:質問 契約中の条項において、居住者側による別途の通知を待った上で実際の出荷を行うものとしている場合、許可が必要となる時点はいつですか。 |
| ▲A43:回答 その別途の通知の時点となります。 |
|
▼Q44:質問 仲介貿易取引の書類等を廃棄した場合はどうなりますか。 |
| ▲A44:回答 その実体が「許可を受けなければならない取引」に該当するものである場合には、たとえ書類等を廃棄していても許可が必要となります。 |
|
▼Q45:質問 2つの売買、賃借又は贈与契約のうち片方の契約の相手方が国内企業であり、その国内企業が外国企業と契約するという関係である場合には、どうなりますか。 |
| ▲A45:回答 両方の契約の相手方がそれぞれ非居住者である場合でなければ、仲介取引規制の適用対象とはなりません。ただし、仲介貿易取引規制の適用対象となる形態を回避するために意図的に片方の契約の相手方を国内企業とした場合は、意図的に片方の契約の相手方を国内企業とした国内企業に許可が必要となります。 |
|
▼Q46:質問 日本企業の海外支店が「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」、又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」の当事者となる場合、許可が必要ですか。 |
| ▲A46:回答 居住者が非居住者である本邦法人の海外支店などの海外事業所と行う仲介貿易取引は、規制の対象となり、許可が必要です。海外支店の職員が行う取引も、個人として行う取引ではなく、海外支店の取引となるので許可が必要となります。 |
|
▼Q47:質問 日本企業の海外現地法人が非居住者と「売り」と「買い」の当事者となる場合、許可が必要ですか。 |
| ▲A47:回答 海外現地法人は、非居住者である日本企業とは別個の独立した法人格であるので、本規制の対象にはなりません。 |
|
▼Q48:質問 許可申請に当たって、該非判定は必要とならないのですか。 |
| ▲A48:回答 輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)については、これに該当していることの確認が必要です。輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項の(中欄に掲げる)貨物については、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合には規制の対象となります。 |
|
▼Q49:質問 仲介貿易取引について、需要者がわかっていて、それが外国ユーザーリストに記載されている企業であった場合はどうなりますか。 |
| ▲A49:回答 仲介貿易取引に係る規制については、輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)である場合には常に許可が必要となります。 また、輸出貿易管理令別表第1の1の項以外の貨物(2の項から16の項の貨物)については、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合、または、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき許可が必要となります。 |
|
▼Q50:質問 仲介貿易取引規制は個別許可ですか。包括許可制度はありますか。 |
| ▲A50:回答 すべて個別許可です。 |
| ▲このページの先頭へ |
|
▼Q51:質問 仲介貿易取引規制に少額特例は適用できますか。 |
| ▲A51:回答 適用できません。 |
|
▼Q52:質問 仲介貿易取引規制に少額特例は適用できますか。 |
| ▲A52:回答 適用できません。 |
|
▼Q53:質問 仲介貿易取引の許可申請は、誰が行うのですか。 |
| ▲A53:回答 仲介貿易取引を行おうとする居住者本人です。一件の移動に関して、複数の居住者が、非居住者との売買の当事者となる場合には、それぞれの居住者が申請者となります。たとえば、 複数の居住者が連名で売買の当事者となって、仲介貿易のみを行う場合には、それらの居住者全てが許可申請をする立場にあります。また、ある貨物がA国からB国へ輸出され、B国で一定の加工をし、それがC国で最終消費されるときに、AB間、BC間をそれぞれ異なった居住者が仲介貿易取引を行う場合等には、それぞれの居住者が申請者となります。 |
|
▼Q54:質問 海外支店が仲介貿易取引に係る行為を行う場合の許可申請は、誰が行うのですか。 |
| ▲A54:回答 本店が申請者となりますが、海外支店がその本店に代わって申請を行うことも出来ます。 |
|
▼Q55:質問 代理人による許可申請はできますか。 |
| ▲A55:回答 仲介貿易取引を行おうとする居住者の代理である旨を記載した書面を添付する場合には、代理人が申請することができます。 |
|
▼Q56:質問 契約後に新たに情報を得た場合には、許可申請が必要となることがありますか。 |
| ▲A56:回答 許可申請の要否は、当該仲介貿易取引に関する2つの契約のうち後に成立する契約より前の時点までに入手した文書等、又はその時点までに取引の相手方となる非居住者等から受けた連絡をもって、判断されます。ただし、契約後に許可が必要となる時点をむかえる場合、例えば契約中の条項において、居住者側による別途の通知を待った上で実際の出荷を行うものとしている契約の場合は、その別途の通知の時点が、許可を必要とする時点となります。したがって、この場合には、当該別途の通知の前に許可申請を必要とする性格の情報を得た場合は、許可申請が必要ということになります。 |
|
▼Q57:質問 自社(本邦法人)の海外支店がその国からの輸出を仲介する場合、つまり、自ら所在しているその国内の業者との間で買い契約、借り契約又は受贈契約を、他国の業者との間で売り契約、貸し契約又は贈与契約をするという場合には、仲介貿易取引規制の適用対象になるということがありますか。 |
| ▲A57:回答 適用対象になります。 それは、海外支店が自ら所在しているその国内の業者との間でする買い契約、借り契約又は受贈契約及び他国の業者との間でする売り契約、貸し契約又は贈与契約の当事者は、いずれも本邦法人である自社であり、その事務手続きを行ったに過ぎない海外支店ではありませんので、この場合は、核兵器等の開発等に関する仲介貿易取引規制の要件である「居住者が貨物の「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」、又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」の双方の当事者となる場合」(「外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について」1(2)① ( また、このことは、その売買、賃借又は贈与に係る業務を行った同一の海外支店が、当該貨物のその国からの輸出を行う場合であっても影響はありません。居住者である本邦法人が、外国相互間の貨物の移動を伴う取引(売買、賃借又は贈与)を行うものと取り扱われるからです。 ※「海外現地法人」の場合は、本邦法人とは別個独立の法人格を有するものであるので、海外現地法人が他国の業者との間で買い契約、借り契約又は受贈契約を、自ら所在しているその国内の業者との間で売り契約、貸し契約又は贈与契約をするという場合には、その契約主体は非居住者である当該海外現地法人であるので、仲介貿易取引規制の対象にはなりません。 |
|
▼Q58:質問 自社(本邦法人)の海外支店がその国への輸入を仲介する場合、つまり、他国の業者との間で買い契約、借り契約又は受贈契約を、自ら所在しているその国内の業者との間で売り契約、貸し契約又は贈与契約をするという場合には、仲介貿易取引規制の対象になるということがありますか。 |
| ▲A58:回答 適用対象になります。 それは、海外支店が他国の業者との間でする買い契約、借り契約又は受贈契約及び自ら所在しているその国内の業者との間でする売り契約、貸し契約又は贈与契約の当事者は、いずれも本邦法人である自社であり、その事務手続きを行ったに過ぎない海外支店ではありませんので、この場合は、核兵器等の開発等に関する仲介貿易取引規制の要件である「居住者が貨物の「売り」と「買い」、「貸し」と「借り」若しくは「贈与」と「受贈」、又は「売り」と「受贈」、「貸し」と「買い若しくは受贈」若しくは「贈与」と「買い」の双方の当事者となる場合」 (「外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について」1(2)① ( また、このことは、その売買、賃借又は贈与に係る業務を行った同一の海外支店が、当該貨物のその国への輸入を行う場合であっても影響はありません。居住者である本邦法人が、外国相互間の貨物の移動を伴う取引(売買、賃借又は贈与)を行うものと取り扱われるからです。 ※「海外現地法人」の場合は、本邦法人とは別個独立の法人格を有するものであるので、海外現地法人が他国の業者との間で買い契約、借り契約又は受贈契約を、自ら所在しているその国内の業者との間で売り契約、貸し契約又は贈与契約をするという場合には、その契約主体は非居住者である当該海外現地法人であるので、仲介貿易取引規制の対象にはなりません。 |
| ▲このページの先頭へ |