サイバー攻撃の被害に遭ってしまったら御活用を! ―中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き―
「情報漏えい」「ウイルス感染」「システム停止」こんなときはまずこの手引きを!
「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」は、「情報漏えいや改ざん」、「ウイルス感染」、「情報システムの機能停止」など、サイバー攻撃による被害が発生した際に、被害を最小限に抑え、早期に復旧するための手順を示したガイドラインです。
この場合、次の3つの対応を行う必要があります。
- ①検知・初動対応
-
●インシデントを検知したら、速やかに情報セキュリティ責任者および経営者に連絡してください。
経営者は、インシデントの発生を確認した場合、速やかに対応方針を指示し、被害を拡大させないための初動対応(ネットワークの遮断、情報や対象機器の隔離、システムやサービスの停止など)を実施してください。
※対象機器の電源を切るなどの不用意な操作は、システム上に残された記録を消さないよう注意が必要です。
- ②報告・公表
-
●被害拡大を防ぐため、二次的な被害が想定される場合は、被害者本人にその事実を報告してください。本人への報告が困難な場合や、インシデントの影響が広く一般に及ぶ場合には、ウェブサイトやメディアを通じて公表することも必要です(※)。 また、必要に応じて問い合わせ窓口も開設してください。
※公表によって被害の拡大を招かないよう、時期、内容、対象などを慎重に考慮する必要があります。
検討の際には、「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(令和5年3月8日 サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会 策定)」も活用ください。●インシデント対応が完了した後は、関係者(被害者や取引先、顧客など)に対して、対応状況や再発防止策について報告する必要があります。また、必要に応じて以下の行政機関にも届け出てください。
●個人情報の漏えいの場合:個人情報保護委員会
●業法などで求められる場合:所管省庁
●犯罪性がある場合:警察
●ウイルス感染や不正アクセスの場合:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- ③復旧・再発防止
-
●復旧にあたっては、原因を調査し、情報(発覚・発生日時、表面化している事象・被害・影響、時系列での対応経過、想定される原因など)を整理してください。
●原因に応じて、必要な対応(修正プログラムの適用、設定変更、機器の入替、データの復元など)を実施してください(※)。
※自社で調査や対応が難しい場合は、外部専門組織(IT製品のメーカー、保守ベンダーなど)や公的機関の相談窓口に支援や助言を依頼してください。●インシデント発生の根本的な原因を分析した上で、再発防止策(新たな技術的対策の導入、ルールの策定、教育の徹底、体制整備、運用の改善など)を実施してください。
万が一、サイバー攻撃の被害に遭ってしまった場合には、ぜひ、こちらのガイドラインを活用し、早期普及に取り組んでいただくようお願いします。
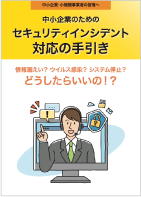
(中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き)
関連リンク
-
- 「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第3.1版 付録8:中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ホームページ
- TOP
-
- サイバーセキュリティ対策を強化したい
-
- サイバーセキュリティ対策を強化したいTOP
- 産業界へのメッセージ
- 産業サイバーセキュリティ研究会
- サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークとその展開
- サイバーセキュリティ経営ガイドラインと支援ツール
- サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(SC3)
- サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ向上のための取引先とのパートナシップの構築に向けて
- 地域SECUNITY(セキュリティ・コミュニティ)
- IPA産業サイバーセキュリティセンター(ICSCoE)
- 情報セキュリティガバナンス
- 暗号技術評価
- 電子署名法制度
- インド太平洋地域向け日米EU産業制御システムサイバーセキュリティウィーク
- ASM導入ガイダンス
- ECサイト構築・運用セキュリティガイドライン
- コラボレーション・プラットフォーム
お問合せ先
商務情報政策局 サイバーセキュリティ課
電話:03-3501-1511(内線)3964
最終更新日:2025年2月19日