

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2017

- 白書2017(HTML版)

- 第1部 第1章 第1節 世界経済の動向とリスク
第1章 世界経済動向
第1節 世界経済の動向とリスク
1.マクロ経済
(1)世界経済の概況と見通し
世界経済は全体として回復基調にあるが、回復のペースは緩慢なものとなっている。2016年の世界の実質GDP成長率は、前年比で+3.1%と緩やかな回復を維持したが、2008年の世界経済危機以降の8年間で2番目に低い伸び率となった(図Ⅰ-1-1-1-1)。
第Ⅰ-1-1-1-1図 世界の実質GDP成長率の推移と見通し
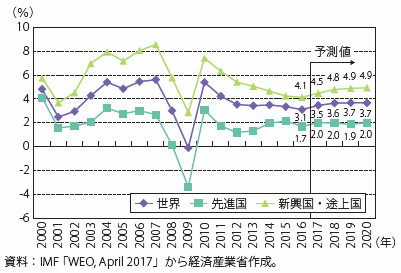
2016年の世界経済は、前半は米国で企業部門の一部に弱めの動きがみられたことや中国経済の減速懸念に加え、6月の英国民投票でのEU離脱派の勝利による金融市場の混乱等により、先行きへの不透明感が高まった。しかし、後半になり、米国経済の雇用情勢の回復や中国経済の各種政策による下支え、主要国中央銀行の英EU離脱ショックへの迅速な対応等により、緩やかに持ち直しが進んだ。
国際通貨基金(IMF)によると、2017年以降の世界経済の見通しのリスクは、上下双方にあるが、中期的には下振れ方向に偏っている。米国や中国等の財政刺激策による景気下支え効果や、OPEC(石油輸出国機構)の原油減産合意に伴う原油価格の安定化、一次産品価格の底打ちによる新興国経済の回復等が期待される一方で、主要国の潜在成長率の低下や世界貿易・投資の停滞、所得格差の拡大等の構造的問題により下振れ圧力も引き続き強い。加えて、保護主義圧力の高まりや、予想より急激な世界金融環境の引締めによる新興国への影響、中東やアジア等の地政学上の緊張等のリスクにも一層の注視が必要となっている。
2017年の世界経済は、2016年後半以降の持ち直しのモメンタムは維持されるものの、世界経済危機以前の水準には達しない、緩やかなペースでの回復が続くと見込まれる。IMFは、世界のGDP成長率を2017年+3.5%、2018年3.6%と予測している(第Ⅰ-1-1-1-2表)。
第Ⅰ-1-1-1-2表 IMFの主要国・地域の実質GDP成長率の見通し
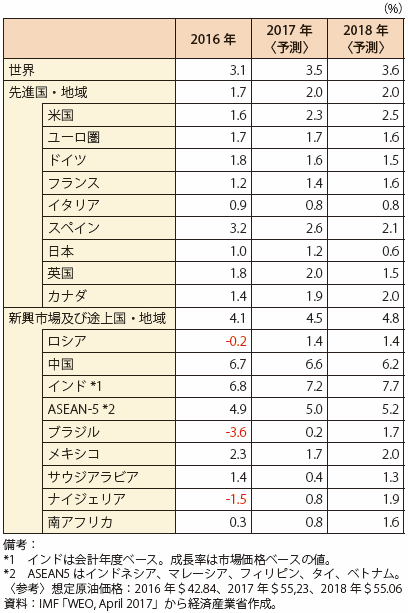
(2)先進国と新興国の経済動向
先進国は、緩やかな回復が続く。2016年前半は、欧州が個人消費主導で緩やかに回復し、米国経済も個人消費の好調に支えられ成長軌道に回復したが、日本は設備投資の減少や熊本地震の影響により伸び悩んだ。後半になり、米国で企業部門の一部でみられていた弱さがはく落し、日本も輸出の回復により緩やかに持ち直した。ユーロ圏は潜在成長率を上回る景気拡大の維持が期待されるが、英国のEU離脱交渉、欧州主要国で予定されている重要な選挙やイタリアの銀行問題の行方等に留意が必要である。
新興国は、国により状況は多様である。2016年前半は資源依存度が高いロシアやブラジルの景気後退が進み、中国経済も過剰生産設備や過剰債務、住宅市場等の調整により成長が減速した。インドが構造改革の進展を背景に好調だった他、年後半からの一次産品価格の底打ちにより、ロシアやブラジルに停滞脱却の兆しが見え始めている。
(3)景況感
景気先行指標である世界の購買担当者指数(PMI)1を見ると、2016年になり、製造業、サービス業ともに業況の改善と悪化の分かれ目となる50の水準を上回り推移している。新興国の伸びのペースは、先進国に比べ緩慢なものとなっている(第Ⅰ-1-1-1-3図)。
第Ⅰ-1-1-1-3図 購買担当者指数(PMI)の推移
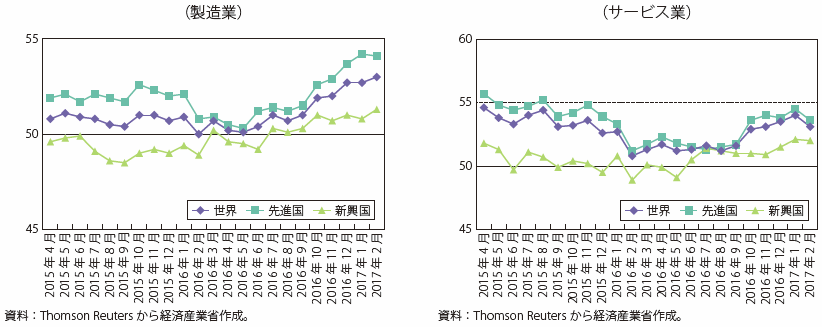
1 購買担当者指数は、各業種の購買担当者に対して生産高や受注状況、雇用等のアンケートを実施し数値化した指数で、50であれば業況は変わらず、50未満ならば悪化、50より大きければ改善していると判断する。
(4)貿易
世界の貿易量は、世界経済危機以前はGDP成長率の2倍近いペースで増加したが、2008年から大幅に落ち込み2009年に底を打った後、2010年には世界経済危機前の水準を超えるまでに回復した。しかし、その後、欧州債務危機の影響等により再び失速して以降、2012年からは貿易量の伸びが、世界経済成長率と比べて伸び悩む「スロー・トレード」の状況が続いており、貿易が世界経済を牽引する力の弱まりが顕著となっている(第Ⅰ-1-1-1-4図)。
第Ⅰ-1-1-1-4図 世界の商品貿易量の伸び率と実質GDP成長率の推移
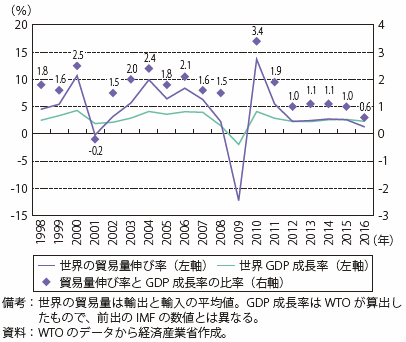
世界貿易機関(WTO)によると、2016年の世界の貿易量(実質商品貿易量)2の伸び率は前年比+1.3%と前年の+2.6%から1.3ポイント低下し、世界経済危機直後の2009年以来の低い伸び率となった。中国を含む新興国の輸入が前年比+0.2%と大幅に鈍化したことが影響した。先進国についても輸出が前年比+1.4%、輸入が同+2.0%と前年から大きく失速した。2017年の世界の貿易量については、前年比+2.4%と予測しているが、世界経済の不確実性が高いことから変動幅を1.8~3.6%としている(第Ⅰ-1-1-1-5表)。 また今後、貿易量を押し下げるリスク要因として、保護主義的な貿易政策の動向、インフレ率上昇に伴う金融引き締め政策や財政引き締め政策による経済成長率の鈍化、英国のEU離脱交渉の行方等を挙げている3。
第Ⅰ-1-1-1-5表 世界の商品貿易量の伸び率(WTOによる)
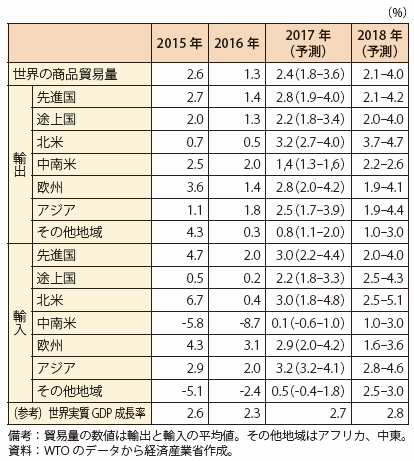
アゼベドWTO事務局長は、「貿易が成長や雇用創出をもたらし、世界経済全体に恩恵を与える重要な役割を果たすことは事実である」が、「一方で職を失ったと懸念を抱く人々を無視することはできない」とし、「製造業の雇用減少の約8割は技術進歩や生産性向上によるもの」であり、「国内レベルで、労働者への支援や訓練等、広範囲にわたる政策ミックスにより対処する必要がある」と述べ、「貿易に対し国境を閉ざすことは、事態を悪化させるだけで、雇用を取り戻せないばかりか、更に失うことになるだろう」と最近の保護主義的な動きに対し懸念を示した4。
また、IMFは、2012年以降の世界の貿易量の伸びのペースの減速は、総需要、特に投資の低調等の「循環的要因」が主な要因であり、それに加えて貿易自由化の停滞や保護主義の高まり、グローバル・バリューチェーン拡大ペースの鈍化等の「構造的要因」も世界貿易の成長を抑制していると指摘し、今後、成長と投資が上向かなければ世界貿易は低迷した状態に留まることから、各国は一層の貿易改革とともに、技術革新やグローバル化といった構造変化により影響を受けた人々に対し、貿易を再び活性化させるための技術やノウハウの伝播を促すような政策を実施する必要があると述べている5。
2 WTOが用いる「貿易量(実質商品貿易量)」は、輸出と輸入の平均値。
3 JETRO通商弘報「2016年の世界商品貿易量は1.3%増の低成長」(2017年4月20日)
4 WTO trade forecasts press conference, remarked by DG Azevêdo (12 April, 2017)
5 IMF World Economic Outlook, October 2016
(5)投資
世界経済が好調だった2000年代半ばは、世界の多くの企業は高成長を続ける中国等の新興国向けに積極的な設備投資を行った。この時期は資源ブームとも相まって、設備投資は貿易を加速させるエンジンとなり、世界の輸入量と投資量の伸び率は、GDP成長率を上回る勢いで推移した(第Ⅰ-1-1-1-6図)。しかし、2011年以降、欧米等の先進国の信用バブル崩壊により、企業の投資活動が慎重になり、更に中国の過剰投資問題等から、投資調整圧力が生じ、設備投資は輸入と共に大きく減速し、2012年以降は、GDP成長率と比べ伸び悩む状況が続いている。IMFは、新興国の投資の減速は、中国経済の減速やリバランスを反映しているが、マクロ経済上の困難に直面する一次産品輸出国(ブラジル、ロシア等)の設備投資や輸入の弱さによるところも大きいと指摘している6。
第Ⅰ-1-1-1-6図 世界の投資量と輸入量の伸び率と実質GDP成長率の推移
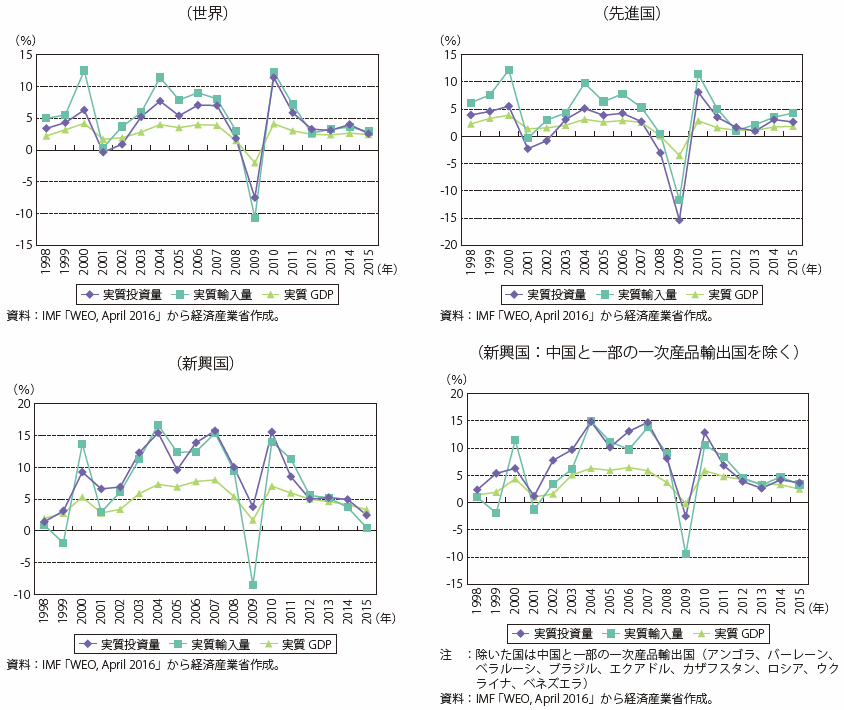
- Excel形式(世界)のファイルはこちら

- Excel形式(先進国)のファイルはこちら

- Excel形式(新興国)のファイルはこちら

- Excel形式(新興国:中国と一部の一次産品輸出国を除く)のファイルはこちら

6 IMF World Economic Outlook, April 2016
(6)消費
主要国の最終消費支出は、世界経済危機及び欧州債務危機の際に落ち込んだ後は回復傾向にあるが、状況はまちまちである(第Ⅰ-1-1-1-7図)。先進国については2014年以降、おおむね回復傾向にあるが、新興国では、インドや中国が堅調である一方、ブラジル、メキシコ、ロシアについては低迷しており、通貨安により輸入物価上昇と、それに伴う消費者物価の上昇、金利引き上げ等が、消費マインドの低下を招いているものと考えられる。
第Ⅰ-1-1-1-7図 最終消費支出の伸び率の推移
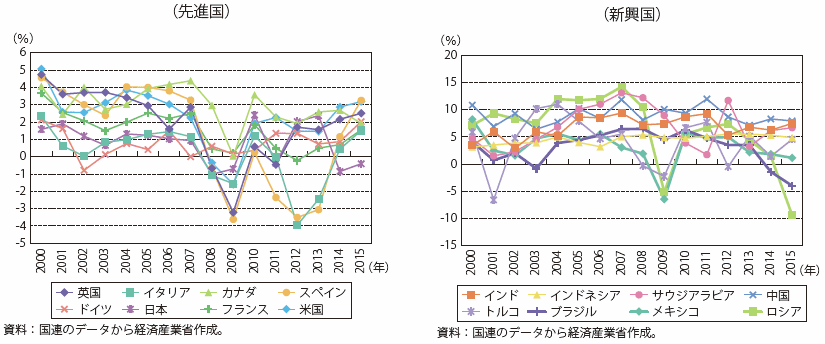
(7)生産
鉱工業生産指数を見ると、新興国は2009年秋に、世界経済危機以前のピークの水準まで回復し、その後も堅調に推移している。アジア新興国が新興国全体を牽引しているのに対し、中南米は低下傾向が続いている。一方、先進国は、世界経済危機を経て2010年12月以降は、ほぼ横ばいで緩やかな回復を続けている。米国は2013年後半に世界経済危機前のピーク値まで回復し、2014年まで上昇した後、横ばいとなっている。ユーロ圏は欧州債務危機の深刻化により、世界経済危機からの回復が腰折れし、長い期間、低迷を続けていたが、最近になり持ち直している。日本は東日本大震災の影響等により、低迷が続いていたが、足下では回復が見られている(第Ⅰ-1-1-1-8図)。
第Ⅰ-1-1-1-8図 鉱工業生産指数の推移
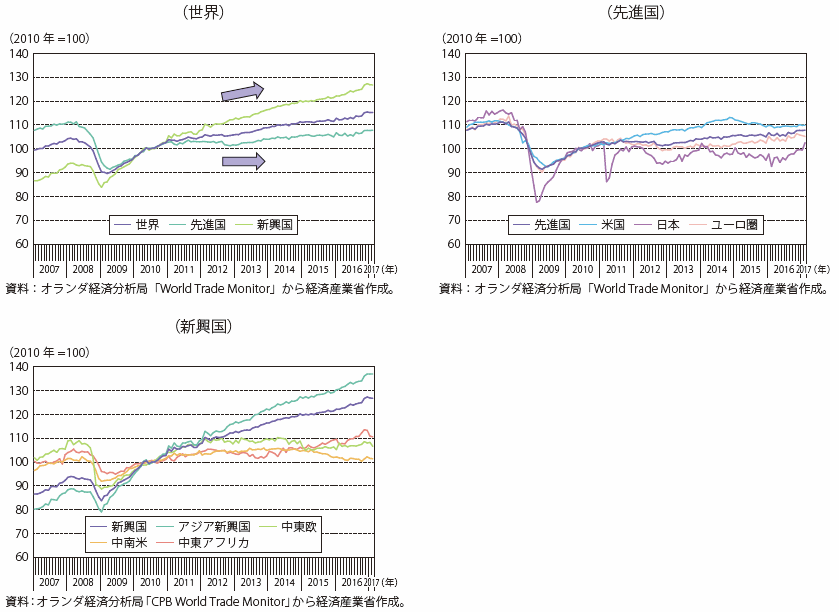
(8)雇用
ILOによると7、2016年の世界の失業者の合計は1億9,800万人と、前年から約320万人増加し、2017年には2億100万人に達すると予測している。また、世界の失業率については、2016年の5.7%から、2017年は5.8%と上昇すると見ている。新興・途上国の労働市場の悪化が深刻で、特に景気低迷の影響を受け、中南米地域(主にブラジル)とサハラ以南アフリカ地域で悪化している。その一方で、先進国では失業者が減少し、失業率も2017年には2016年の6.3%から6.2%に低下する見込みであるが、改善のペースは減速している。また、世界的に若年層の失業が深刻な問題であり、世界の若年失業率はここ数年緩やかに改善していたが、2016年は12.8%、2017年には13.7%に悪化すると予測されている(図Ⅰ-1-1-1-9)(図Ⅰ-1-1-1-10)。
第Ⅰ-1-1-1-9図 主要国の失業率の推移
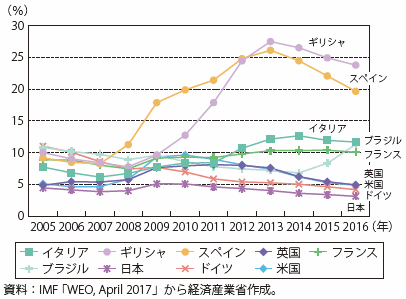
第Ⅰ-1-1-1-10図 若年層の失業率の推移
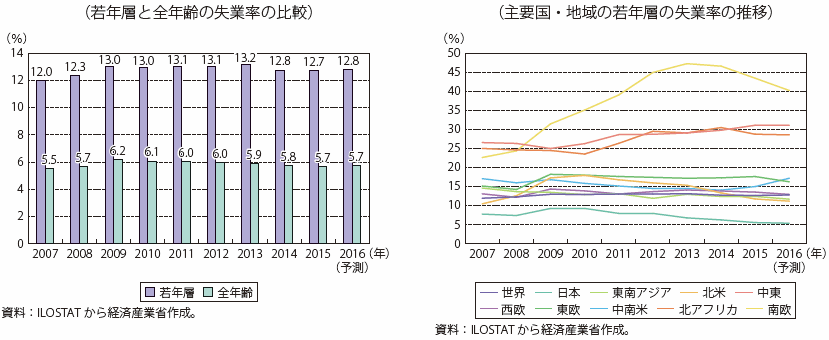
7 ILO World Employment and Social Outlook - Trends 2017
2.金融市場動向
(1)為替
為替については、2016年年初から、米国の利上げ動向、中国経済の減速懸念、欧州銀行部門の健全性に対する懸念、原油価格の下落等を背景として、市場の変動の高まりが見られた。同年11月の米国大統領選挙以降は、トランプ新政権の経済政策への期待を背景として、米金利上昇・ドル高方向への動きが見られた(第Ⅰ-1-1-2-1図)。
第Ⅰ-1-1-2-1図 為替レートの推移
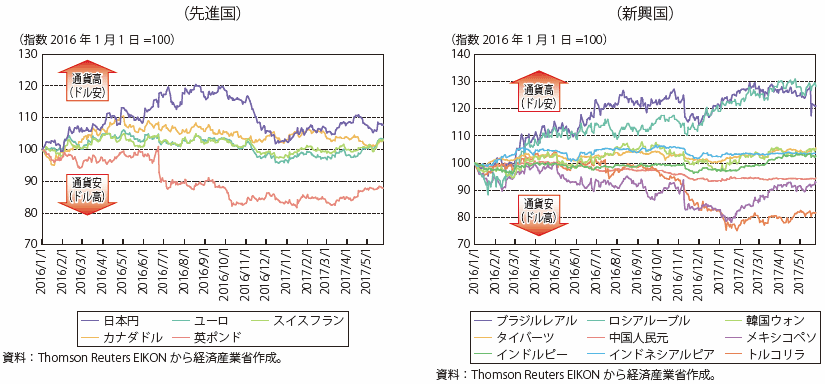
(2)株価
2016年の世界の株価は、予想を下回る米国や中国の経済指標により、2月前半までは下落基調であったが、その後、原油価格持ち直しや米国の利上げ観測の後退により、年初の下げを解消した。6月末の英国EU離脱決定により、欧州経済への先行き懸念から、大きく下振れする場面もあったが、市場の動揺から短期間に回復した。年後半になり、米国の雇用状況の大幅な改善から米国経済への楽観的見方が広がり、夏場からは上昇基調となった。しかし、米国のFRB(連邦準備制度理事会)関係者から利上げに対して積極的な発言と慎重な発言が繰り返され、株価は高値圏でもみ合う展開となった。さらに10月は、米国利上げ観測の高まりや中国の輸出減少に伴う世界経済の不安が再燃し、さらにOPEC (石油輸出国機構)の減産協議の難航に伴う原油下落や、米国大統領選挙を控えての先行き不透明感等を背景に、株価は軟調に推移した。しかし、11月トランプ氏が大統領選挙で勝利すると財政拡張策への期待感が高まり、欧米では株価が上昇した。さらに11月末にOPECが減産で最終合意し原油価格が上昇すると株価も上昇し、12月前半には世界の株価は年初来高値をつけた(第Ⅰ-1-1-2-2図)。
第Ⅰ-1-1-2-2図 株価の推移
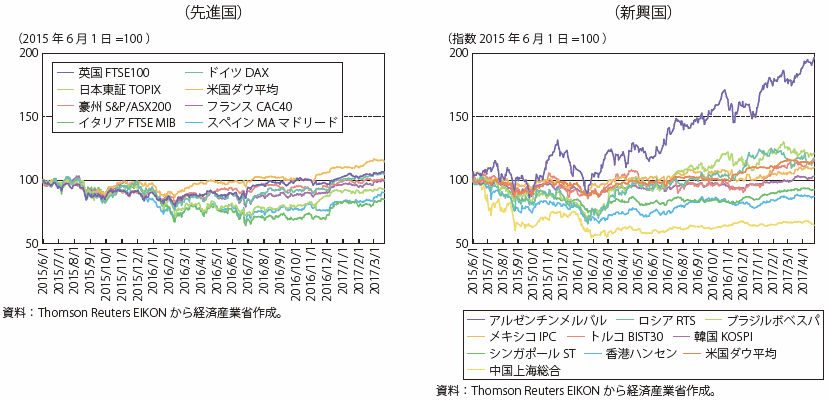
(3)債券市場
2016年前半の主要国の10年国債利回りは、中国や米国経済の減速、原油価格下落、英国のEU離脱等により、危険回避の動きが強まり低下したが、後半になり、米国経済の持ち直しや、財政支出拡大による景気刺激策を唱えるトランプ氏が大統領選挙で勝利したことで、米国債利回りは急上昇した。ブラジル、トルコ、メキシコ等の新興国の10年国債利回りについてもおおむね、年前半は低下傾向だったが、後半になり上昇した。特にトランプ政権の強硬な通商・移民政策の影響を強く受けると見られるメキシコの金利の上昇が目立った。米国の景気刺激的な経済政策に対する期待から、当面、利回りに上昇圧力がかかるが、今後、トランプ政権の政策の実態が明らかになるにつれ、次第に落ち着いた動きになると予想されている(第Ⅰ-1-1-2-3図)。
第Ⅰ-1-1-2-3図 10年国債利回りの推移
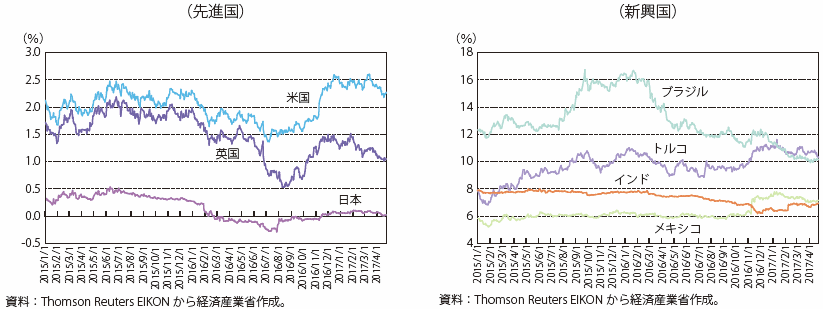
(4)政策金利
世界経済危機の影響を受け世界の経済成長率は急落し、各国でデフレリスクが懸念された。2012年には欧州債務危機も発生し、欧米の中央銀行は、急速に大幅な政策金利の引き下げを実施したが、景気回復にはつながらず、米国、EU、日本の主要先進国の政策金利はゼロ下限に直面し、これらの国々は、低金利政策に加えて、非伝統的金融政策(量的緩和、信用緩和)による緩和的な金融スタンスを導入した。しかし雇用が改善し経済が好調な米国では、2015年12月以来、2016年12月、2017年3月の計3回の利上げが実施され、今後も国内外の経済に与える影響等を考慮しながら、2017年内に追加で2回程度の利上げが実施される見込みである8。日本は2016年にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールを導入し、米国が金融政策の正常化に向かう中で、当面は金融緩和を継続する見通しである。
新興国については、アジアの国の多くは米国の利上げ再開後も追随することなく緩和的な金融政策を継続している。背景として、為替が比較的安定して推移する中、ディスインフレが広がっていること、それに伴い政策金利引き下げの必要性が拡大していること等が挙げられる。インドネシアは2016年初より、インドは同年10月より利下げを実施、通貨安に悩むトルコは、景気低迷の中、同年11月に33か月ぶりに利下げを選択した。メキシコでは通貨安進行とインフレ上昇に対応した利上げを2015年12月以降、継続して実施、一方通貨安の回復とインフレ率低下に伴い、ブラジルでは2016年10月以降利下げを実施した。さらにロシアも通貨の上昇によりインフレが収まり、2017年3月と4月連続で利下げを決定した(第Ⅰ-1-1-2-4図)。
第Ⅰ-1-1-2-4図 政策金利の推移
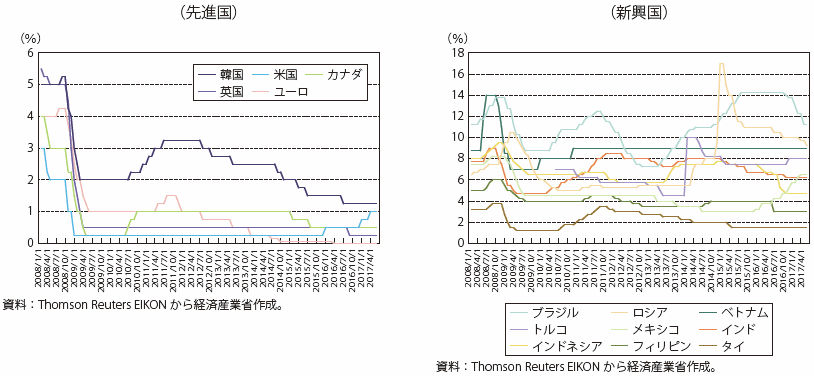
8 米連邦準備理事会(FRB)は2017年3月15日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、2016年12月以来3カ月ぶりの利上げを決定し、同時に公表した政策金利見通しで、2017年中に更に2回の追加利上げを見込んでいる。
3.世界経済成長のリスク要因
IMFによると、堅調な金融市場や製造業や貿易の循環的な回復により、世界的に経済活動の回復が進む中で、生産性の低さや所得格差等の構造的な障害が景気回復の足取りを重くしており、世界経済の成長のリスクは中期的には依然として下振れ方向に傾いている9。下振れリスクは以下に挙げる複数の潜在的な要因から生じ、これらのリスクはそれぞれが無関係でなく、相乗的に影響が強まる場合もあるとしており、注視が必要である。
・貿易や対外投資減少による世界の経済成長の低下に伴う保護主義等の内向きな政策への移行。
・米国の想定を上回るペースでの金利上昇によるドルの急上昇が、世界の金融市場や、特にぜい弱な新興国に与える影響。
・金融規制の大幅な緩和による高リスクな金融取引の増加による将来の金融危機発生の可能性。
・急激な与信拡大による中国金融システムのぜい弱性の深刻化と、他の新興国の継続するバランスシートの弱さによる新興国での金融の引き締め。
・生産能力過剰な先進国での弱い需要、低インフレ、弱いバランスシート、生産性の伸びの鈍さといった要因の負の連鎖の継続。
・地政学上の緊張や国内政治の対立、ガバナンスの弱さや政治腐敗、異常気象、テロ、安全保障問題等。
9 IMF World Economic Outlook, April 2017
