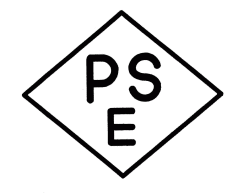リチウムイオン蓄電池の規制対象化に関するFAQ
リチウムイオン蓄電池の規制対象化に関して、皆様から質問をいただいたものの中から主要なものについてQ&A形式にまとめたものを以下のとおり掲載します。
Q1:届出事業者となる者の義務は?
A1:
リチウムイオン蓄電池の製造・輸入行為を行う者が電気用品安全法第3条![]() の届出義務を負う。
の届出義務を負う。
また、電気用品安全法第8条![]() に基づき、技術基準への適合を確認することや、定格電圧・外観について全数検査を行い3年間分の検査記録を保存することが義務付けられる。
に基づき、技術基準への適合を確認することや、定格電圧・外観について全数検査を行い3年間分の検査記録を保存することが義務付けられる。
Q2:機器メーカが修理サービスの一環でリチウムイオン蓄電池を交換する場合は、販売にはあたらないのでPSEマーク表示の確認義務は行う必要はないか。
A2:
販売とは、対価を受け取ることを条件として、電気用品を他に譲り渡すことであることから、修理サービスの一環で消費者に対し電池を供給することは販売に該当するため、PSEマーク表示の確認は必要である。
Q3:リチウムイオン蓄電池の輸入代行者は電安法の輸入事業者となるのか。
A3:
輸入とは、電気用品を国内に移送する行為をいう。通関手続き等の輸入に関する手続きを単に代行するだけの行為は輸入とはならない。ただし、輸入代行であっても、輸入品を国内に供給する事業を行っている場合は、電気用品安全法の輸入事業者となる。
Q4:リチウムイオン蓄電池の電気的加工については完了したが、その後PSEマーク等を貼付する業務を外注する場合、外注先が製造事業者として届出事業者になるのか。
A4:
電気用品の製造とは電気用品を完成させる行為が該当するが、本件のようにPSEマーク等の貼付のみを一部外注するだけの行為は、電池の製造には該当しないことから、電気的加工等の電池を製造した事業者が届出事業者になる。
Q5:リチウムイオン蓄電池を機器と同梱して輸入し、リチウムイオン蓄電池を廃棄する場合、電安法上の手続きは必要か。
A5:
リチウムイオン蓄電池を機器と同梱して輸入する場合は電安法の輸入事業届出が必要となるが、輸入した当該電池を販売せずに廃棄する場合には、前述の届出以外、電安法上の手続きを要しない。
Q6:施行令施行前に輸入したリチウムイオン蓄電池は、施行後に販売することはできるのか。
A6:
本施行令施行前(平成20年11月19日以前)に製造・輸入したリチウムイオン蓄電池は、規制対象外であることから、施行後に販売することはできる。
Q7:電池電極をフィルムで絶縁した(又は電池コネクタを外した)状態で機器にリチウムイオン蓄電池を装着して輸入・販売する場合、装着に該当するか。なお、フィルムの抜き取り、コネクタの装着は消費者が行う。
A7:
装着に該当する。
Q8:リチウムイオン蓄電池を同梱した機器や電池単体をレンタル、リースする場合は、電安法上の責務はあるのか。
A8:
レンタル、リース事業者が、リチウムイオン蓄電池を同梱した機器又は交換用電池を、代金を受け取って販売する(所有権が移転する)場合は、電気用品安全法の販売行為に該当するが、所有権の移転が伴わない場合は、販売行為には該当しない。
Q9:電池単体を中古品として販売する場合、販売事業者にはPSEマークの確認義務があるか。
A9:
電気用品安全法の規制対象であるリチウムイオン蓄電池の中古品を販売する場合にあっても、販売事業者は表示を確認する必要がある。
Q10:海外に電池を輸出し、当該製品が返品された場合、輸入事業の届出は必要か。
A10:
海外からの返品は、輸入の事業とはみなさないことから、輸入事業の届出は必要ない。
Q11:既に生産を終了した機器用の交換用電池としてリチウムイオン蓄電池を供給する場合、技術基準に適合していない電池の販売は行えないのか。
A11:
例外承認の審査基準に該当するものであって、当該承認を受けた場合は、製造(輸入)及び販売することができる。
Q12:汎用性のあるリチウムイオン蓄電池について、電安法対象外の産業用機械器具用と電安法対象の機械器具用に兼用される場合、いずれの用途とも当該電池にPSEマークを付してよいか。
A12:
基本的には、用途に応じて電安法対象の電池にPSEマークを付すこととなるが、現実的に両者を明確に区分して流通させることが困難な場合には、いずれの用途ともPSEマークを付しても構わない。
Q13:販売を目的としない調査用、試験用、解析用、展示用の電池の製造・輸入を行う場合、電安法の規制はどうなるか。
A13:
電気用品安全法第8条![]() 第1項第2号では、試験的に製造又は輸入する場合には、技術基準の適合義務は課せられていない。
第1項第2号では、試験的に製造又は輸入する場合には、技術基準の適合義務は課せられていない。
試験的とは、新製品開発、商品テスト等の場合における社内用等を指している。
新製品の開発のため種々の試作を行うことは技術の進歩を図るため必要なことであり、かつ、その電池は一般の流通には置かれない。
上記例示が、これに該当する場合の電安法の規制は、製造(輸入)事業届出が必要であるが、技術基準の適合は要求されない。
Q14:海外からリチウムイオン蓄電池を輸入し、国内で機器に装着して(あるいは同梱)、さらに当該機器を輸出する場合、電安法上の規制はどうなるか。
A14:
輸出目的でリチウムイオン蓄電池の製造又は輸入事業を行う者には、電気用品安全法第3条![]() の届出義務は適用されるが、電気用品安全法施行令第4条
の届出義務は適用されるが、電気用品安全法施行令第4条![]() に基づき電気用品安全法第8条
に基づき電気用品安全法第8条![]() の基準適合義務は適用されない。
の基準適合義務は適用されない。
また、リチウムイオン蓄電池の製造、輸入又は販売の事業を行う者が、輸出目的でリチウムイオン蓄電池を販売する場合は、電気用品安全法施行令第4条![]() に基づき電気用品安全法第27条
に基づき電気用品安全法第27条![]() 第1項の販売の制限は適用されない。
第1項の販売の制限は適用されない。
Q15:規制対象となるリチウムイオン蓄電池は、単電池の体積エネルギー密度400Wh/L以上としているが、これに加えて、エネルギー量(容量)についての検討は行ったのか。
A15:
エネルギー密度が低い場合には、電池破裂などの場合でも単位体積から放出されるエネルギー量がそれほど大きくならないと考えられるため、エネルギー密度を基準に規制の範囲を定めたものである。
Q16:型式の区分の要素において、単電池の電解質の種類とあるが、電解質とは何か。
A16:
一般的に電池の電解質を表す表現として、「電解質」と「電解液」の双方が用いられているが、リチウムイオン蓄電池の場合にはゲル状のもの(ポリマー電池)があることから、電解液という表現を用いることは適当でない。
このため、本技術基準では「電解質」を用いることとした。
なお、「電解質」には、電解質塩を表す意味もあるが、本技術基準では当該意味を意図して用いてはいない。
Q17:型式の区分において、過充電の保護機能の区分として、「組電池で制御するもの」と「組電池搭載機器又は充電器で制御するもの」があるが、その事例を示すこと。
A17:
過充電の保護機能については、「組電池内の保護回路で、各電池ブロックの電圧を検知して、組電池の回路で充電を制御するもの」にあっては組電池制御、「組電池内、搭載機又は充電器で各電圧ブロックの電圧を検知して、搭載機又は充電器で充電を制御するもの」にあっては搭載機制御に該当する。
Q18:外観検査では何を確認するのか。
A18:
外観検査は、目視などの方法で外観に異常がないこと(例えば、電池容器の変形や破損など)を確認する。
Q19:出力電圧検査の目的及び検査方法を技術基準に規定しなかった理由は何か。
A19:
出力電圧を自主検査項目としたのは、一定の電圧が出力されていれば、短絡、内部配線及び端子などの異常が発生していないことを確認できるためである。
また、出力電圧値については電池製造事業者が定める電圧範囲であること。
なお、出力電圧の検査方法については、特に技術基準で検査方法を定めていないが、単に電圧計を用いて正極端子と負極端子間の電位を測定するという試験方法であることから、技術基準において蓄電池の出力電圧の測定方法を規定しなかった。
Q20:リチウムイオンキャパシタは、電気用品安全法におけるリチウムイオン蓄電池に該当するか。
A20:
リチウムイオン蓄電池とは、正極と負極の両極におけるリチウムの酸化・還元で電気エネルギーを供給する充電式の電池であり、正極ではリチウムが金属酸化物として、負極ではリチウムがイオン状態として蓄電される電池を指している。
リチウムイオンキャパシタは、負極ではリチウムがイオン状態で蓄電され、正極ではマイナスイオンのみ吸・脱着し、正極と負極の両極におけるリチウムの酸化・還元を行うものではないことから、電気用品安全法施行令 別表第二![]() 第12号規定するリチウムイオン蓄電池には該当しない。
第12号規定するリチウムイオン蓄電池には該当しない。